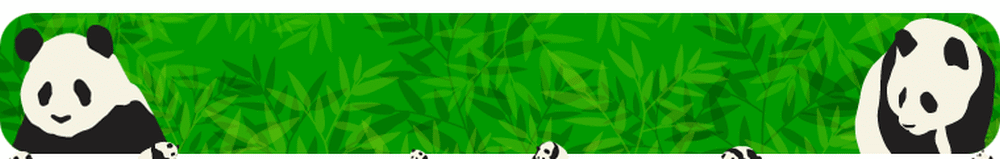PR
X
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(8)及び腰か勇み足な書評
(54)いたづらにむつかしい刑法
(17)ついつい批判的にみてしまう会社法
(18)かなしいけど積読よ
(5)とりあえず買ってみましたが
(10)こわれてく民法
(13)知的財産法だって法律でしょ。
(10)いくら法律じゃないからって、憲法
(2)困ったら裁量で行政法
(2)国際私法は国境を越えない?
(8)法律書への想いをこじらせて
(9)はんぱに裁判員制度
(2)生まれることと終わること
(3)ネットで論文を
(3)手続と実体で倒産法
(1)カテゴリ: 国際私法は国境を越えない?
国際私法に関しては、どれだけ勉強しても「理解」したというレベルに到達した気がしません。
単なる学説の羅列ではなく、山本敬三先生の『 民法講義1総則 第2版 』(有斐閣)『 民法講義4-1契約 』(有斐閣)のように、背後にある原理にまで遡った学説整理をしたものがあればいいんですが。
たいした例を挙げることはできませんが、たとえば、「外国法不明」の場合の処理に関して(以下、網羅的ではありません)。
補充連結によるとする説は、抵触法により準拠法がきまったのに、その準拠法が不明だったのでもう一度抵触法に戻って準拠法選択をやり直すという、法の「選択」レベルでの解決に分類されると。
他方、当該準拠法と内容的に近似している国の法を参考にして当該準拠法の内容を推認するという説は、一旦準拠法が決まった以上はその選択をやり直すということはせず、どうにかして当該準拠法を適用できるようにしようという、法の「適用」レベルでの解決に分類されると。
当該準拠法と最も近似している国の法を代替的に適用する説というのは、理由付け次第で、「選択」レベルでの解決とも「適用」レベルの解決ともどちらともいえそうです。とすると、同じく最近似国法説であっても、その理由付けによって、どのレベルで解決しようとしているのかが違っているわけです(あくまで私の素人考え)。
また、解決のレベルが違うのであれば併用も不可能ではない、ということも分かるわけです。
つっこみ を入れておいたところとも関連する話でもあります。)
・
それから、藤田宙靖先生の『 行政法(1(総論))第4版(改訂版) 』(青林書院)のように、「法律による行政の原理」という近代法上の原理をものさしを用意して、現代法における個々の問題をその原理との距離によって見ていく、というような手法の本もあるといいですね。
国際私法でいえば、「最も密接な関係を有する地の法」の選択を原則とし、個々の問題がそこからどれだけ離れているか、という観点で見ていくことになるんでしょうか。石黒一憲先生の『 国際私法 第2版 』(新世社)は、立場的には「最も密接な関係を有する地の法」の選択を重視するお考えのようですが、意識的にそういう構成にしているわけではありませんし。
というよりも、そもそも、いい教科書ほしいな、という話は、石黒先生の教科書をちゃんと理解できるようになりたいというところから来ています。
単なる学説の羅列ではなく、山本敬三先生の『 民法講義1総則 第2版 』(有斐閣)『 民法講義4-1契約 』(有斐閣)のように、背後にある原理にまで遡った学説整理をしたものがあればいいんですが。
たいした例を挙げることはできませんが、たとえば、「外国法不明」の場合の処理に関して(以下、網羅的ではありません)。
補充連結によるとする説は、抵触法により準拠法がきまったのに、その準拠法が不明だったのでもう一度抵触法に戻って準拠法選択をやり直すという、法の「選択」レベルでの解決に分類されると。
他方、当該準拠法と内容的に近似している国の法を参考にして当該準拠法の内容を推認するという説は、一旦準拠法が決まった以上はその選択をやり直すということはせず、どうにかして当該準拠法を適用できるようにしようという、法の「適用」レベルでの解決に分類されると。
当該準拠法と最も近似している国の法を代替的に適用する説というのは、理由付け次第で、「選択」レベルでの解決とも「適用」レベルの解決ともどちらともいえそうです。とすると、同じく最近似国法説であっても、その理由付けによって、どのレベルで解決しようとしているのかが違っているわけです(あくまで私の素人考え)。
また、解決のレベルが違うのであれば併用も不可能ではない、ということも分かるわけです。
つっこみ を入れておいたところとも関連する話でもあります。)
・
それから、藤田宙靖先生の『 行政法(1(総論))第4版(改訂版) 』(青林書院)のように、「法律による行政の原理」という近代法上の原理をものさしを用意して、現代法における個々の問題をその原理との距離によって見ていく、というような手法の本もあるといいですね。
国際私法でいえば、「最も密接な関係を有する地の法」の選択を原則とし、個々の問題がそこからどれだけ離れているか、という観点で見ていくことになるんでしょうか。石黒一憲先生の『 国際私法 第2版 』(新世社)は、立場的には「最も密接な関係を有する地の法」の選択を重視するお考えのようですが、意識的にそういう構成にしているわけではありませんし。
というよりも、そもそも、いい教科書ほしいな、という話は、石黒先生の教科書をちゃんと理解できるようになりたいというところから来ています。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[国際私法は国境を越えない?] カテゴリの最新記事
-
渉外的親族相盗例? 2007年04月05日
-
国境を越えなくても国際労働法 2007年03月23日
-
刑法における民事的要素と渉外的要素 2007年03月19日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.