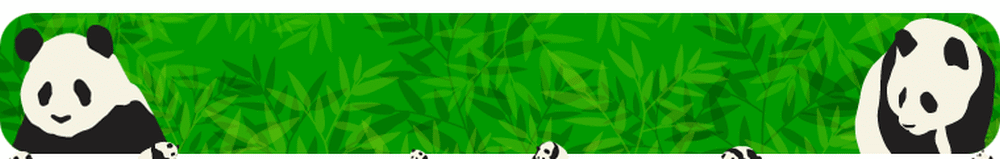全165件 (165件中 1-50件目)
-

佐藤英明『スタンダード所得税法』
弘文堂の本については、『基礎から分かる会社法』で結構なことを書きましたので、バランスをとるために、おすすめできる本もあげておきます。二色刷、重要度に応じてフォントを変える、ケースを多用しているといったことは、今時の教科書と同じ傾向ですが、税法の教科書では極めて珍しいですよね。しかも、ケースというのも、単なる判例を簡略化したものではなく、制度の理解を深めるために、同じようなケースでいろんなパターンを出したりしています。このことが特に活きていると思ったのが、たとえば、租税における垂直的平等とか水平的平等といったものについて、いろんなパターンをあげることで、どうやってバランスをとるべきなのかを具体的に検討しているところなどです。他の本では抽象的に論じられてしまうところも、極めて具体的に考えられるということです。これまた先日あげた『ベーシック税法』では、抽象的な記述にとどまってしまってるところが多いのと比べると、具体的に理解してもらうという配慮が、とても徹底しています。フォントを落とした部分は、確かに本文よりも難しいのですが、ここでもきちんとケースを用いて具体的に解説されていますので、抽象的で何いっているか全く理解できない、ということにはなりません。で、話は最初に戻りますが、なぜこれほどの本が出せる出版社が、会社法のスタンダードの本ではああいう本を出してしまうのかが不思議なわけです。
2009年05月04日
コメント(0)
-

大内伸哉『雇用はなぜ壊れたのか-会社の論理VS.労働者の論理』
会社の論理と労働者・生活者の論理という対立する論理を分析枠組として用いることで、労働問題を解説していく本。例によって、タイトルにあるような「なぜ」雇用が壊れたかに対する回答はありませんし、そもそも雇用が「壊れた」のかどうかも、よくわかりません。労働法は労働者の権利を保護するためだけにあると思っていた人にとっては、それが誤解であることを気づくのに役に立つかもしれませんけど、そうでない人にとっては、まあ普通です。ある程度の知識がある人は読まなくてもいいんじゃないですか。新書といえども、何か光るものがあればいいなと思うのですが、この本にはそういう期待はしないほうがいいみたい。思わせぶりなタイトルに惑わされないように。
2009年05月03日
コメント(0)
-

コリンP.A.ジョーンズ『手ごわい頭脳 アメリカン弁護士の思考法』
例によって、タイトルと中身がいまいち一致しない新書。「手ごわい頭脳」って何でしょう?以下、この本に書いてあることというよりも、この本から連想したことを書きます。・アメリカの弁護士の思考法について書かれた本というより、アメリカ司法の入門書とみたほうがいいかもしれません。というのも、陪審に代表されるアメリカの司法制度の下で、弁護士が最大限の効果をもたらすにはどのように思考すべきか、ということで、その前提となるアメリカの司法制度の説明が分かりやすく書かれているからです(なので、アメリカの法廷ドラマを楽しくみるための基礎知識としても役に立つと思います)。・また、このことからすれば、アメリカの弁護士の思考法というのが、アメリカの司法制度がどういう制度であるかによって既定されているということでもあるわけです。この点、先日紹介した『プロ弁護士の思考術』が、日本の司法制度がこうだから日本の弁護士はこう思考する、という形では論じておらず、普通のビジネス書に書かれていることと内容的にあまり変わらないのとは対照的。日本では、弁護士は、一般的なものの考え方でも十分通用するということなんでしょうか。それは別に日本が劣っているということではなく、日本の司法が一般社会でのお作法とそれほど違っていないということを表していることになるわけですが。逆に、アメリカでは、「弁護士的な考え方」というと、司法向けに特化した思考法だということになるわけです(程度問題でしょうが)。・いわゆる「リーガルマインド」といわれるものや「法の解釈」についても、あくまで印象論ですが、日本では、現行の司法制度べったりではない、抽象的なものとして捉えている気がします。なので、日本のおけるその手の本では、諸外国の学者の、法の解釈に関する見解を、国の違い、時代の違いに応じて相対化しないで、抽象的に引用できるのかもしれません。他方で、この本からすれば、アメリカでは、たとえば陪審制度のもとでは陪審員向けの法解釈というものがあるのであって、宛名のない、抽象的な「法の解釈」というものは、(そういうものが存在するかどうかは別として)考えなくてもいいことになりそうです。そうすると、たとえば「法と経済学」という学問は、日本では最初に、法に対するアプローチとして正しいか否か、という問題の立て方をされることがありますが、アメリカの場合、そういう議論は置いておいて、陪審員向けに考えた場合には難しすぎて役に立たないので使わないが、経済学の素養のある裁判官向けには、正義云々という言葉よりも経済学的手法のほうが理解してもらいやすいので使おう、というように、「正しいか否か」ではなく「役に立つか否か」によって場面ごとに使い分ける、という考え方になるのでしょうか。・「訴訟大国」「訴訟社会」などとして、日本では時に劇画タッチにイメージされることの多いアメリカですが、この本を読むことで、そういったイメージが正確でないことが分かります。・政府に対する不信が基礎となって存在するアメリカの陪審制度が、消費者訴訟、行政訴訟などで大きな成果をもたらしているのを読むにつけ、日本の裁判員制度が、対象事件を殺人事件などの刑事事件に限っていることの不思議さを感じざるをえません。・念のためもう一度いっておきますが、ここに書いたことはあくまで私がこの本を読んで勝手に連想したことがほとんどで、この本自体にこういうことがそのまま書いてあるわけではありません。
2009年05月02日
コメント(0)
-

大竹文雄 『経済学的思考のセンス お金がない人を助けるには』
様々な素材をあげて、経済学的な分析の仕方を解説した本。・素人的には「因果関係」と「インセンティブ」の意味が分かれば十分ってことですね。で、因果関係については、どっちが原因でどっちが結果かということをきちんと分析して見極める必要があるということ、インセンティブについては、あくまで人間を対象とするものだから、金銭的なものだけでなく、非金銭的なものにも配慮しなければならないということが、素材を通して分かります。・「数式」はありませんので、経済学に苦手意識がある人でも、安心して読めると思います。ただ、後半から徐々に素材が固めになっていくので、一読してすぐ理解できないところもあるかもしれません。・こういう経済学の本は、往々にして、わざと常識はずれの結論が導かれる素材を選んで読者をびっくりさせようとすることがありますが、この本は結論的にはそれほどおかしいことは言っていないと思います。これは、おそらく著者が、結論を導くためのプロセスを理解してもらいたいのだと考えているからなんでしょう。まあ、刺激がほしい人には物足りないかもしれませんが。
2009年05月01日
コメント(0)
-

近藤光男他『基礎から学べる会社法』
・第1刷の間違いのすさまじさは、なぜここまでの間違いに気づかないまま出版できたのか、逆に不思議でたまりません。・二色刷で図表も多用しているので、何やら分かりやすそうに思ってしまいますが、内容についてはさっぱり初学者に対する配慮が感じられません。例によって、条文引き写しがほとんど。具体的なイメージなんてさっぱりつかめません。・「計算」のところなんてアリバイ的に一応ひととおりのことは書いておきました程度の内容。わざわざ貸借対照表と損益計算書をそれぞれ丸々1頁つかって載っけていますが、その中身に対する説明もないので、ページの無駄遣いにしかなっていません。「企業会計原則」とか、わざわざ色を変えて太字にしているにもかかわらず、その言葉に対して何の注釈もないので、初学者は、それが何だか分からないでしょう。・ということで、初学者にとって理解しやすい本だとは、とても思えません。かといって、勉強の進んでいる人にとっても、この本を読むくらいなら普通の教科書を読んだ方がいいと思います。なので、この本を読んでもいい人というのは、せいぜい、昔に会社法を勉強したことがあって新会社法を勉強し直したいが、分量の多いのは避けたい、かといって、ビジネス書も避けたい、という人ぐらいじゃないんですかね。
2009年04月30日
コメント(0)
-

三木義一『日本の税金』
・何の味も素っ気もないタイトルですね。さすが岩波新書。でも、中身は非常に充実しています。・単なる制度の羅列ではなく、各種税法の問題点について批判的に検討されています。しかも、こういう新書で税法の批判をするとなると、「納税者の権利が不当に侵害されているから違憲」とか、どうしても、憲法論を振り回した大味な理由付けで終わりになりがちなところですが、この本ではひとつひとつきちんとした検討がなされていて、このボリュームでよくここまでの論点を詰め込めたなあ、って感心します。・そのせいでしょうけども、予備知識のない人にとってはやや説明不足なところもありますので、そういう人は、『よくわかる税法入門』から読んだ方がいいと思います。
2009年04月29日
コメント(0)
-

三木義一『給与明細は謎だらけ』
タイトルをそのまま受け取ると、何やら給与明細自体に謎があるみたいな感じになってますが、そうではなくって、給与明細を受け取っているサラリーマンの皆さんは、給与明細に書かれていることの意味がよく分かってないでしょ、ってことのようです。まあ、今時の新書ならではのタイトルですね。ということで、給与明細に記載されていることについて、その内容をひとつひとつ解説していくというスタイルの本です。サブタイトルが「サラリーマンのための所得税入門」となっていますが、確かに、サラリーマンにとっては、ただ単に税法の解説をされたり、自分と関係のない制度をあれこれ説明されても興味を持ちにくいでしょうから、こういうスタイルはいいんじゃないですかね。スタンスとしては、源泉徴収+年末調整によって税に対する関心から引き離されてしまっているサラリーマンに対して、もっと関心をもったほうがいいよ、という感じで進んでいきます。文章は具体的な数字をあてはめたりして分かりやすいので、非常に読みやすいと思います。
2009年04月28日
コメント(0)
-

矢部正秋『プロ弁護士の思考術』
物事の考え方について、7つのポイントをあげて解説している本。・「プロ弁護士」なんて言葉、どこか違和感がありますが、まあ見栄えをよくするためなんでしょう。・弁護士特有の考え方というよりも、一般的に役に立つものの考え方になっています。なので、応用範囲は広いですが、弁護士特有の考え方を知りたいと思って買った人は、タイトルにだまされたと思うかもしれません。なので、これまで「思考法」とかそういう類の本を読んできた人にとってはそれほど新しいことは書かれていませんので、あえて読まなくてもいいと思います。・思考「術」というほどのものではなく、思考するためのヒント集といった感じ。考える手段を網羅しているわけではありません。自分なりに考えて応用していったらいいと思います。・権威を疑えとか根拠を示せとかって話がでてきますが、にもかかわらず、たとえば他人の意見を引用して、特に根拠も示さずそれに従って記述を進めたりしているのは、読者に対する引っ掛けなんですかね。ちゃんと気づくかな?って感じの。
2009年04月27日
コメント(0)
-

横山雅文『プロ法律家のクレーマー対応術』
弁護士さんの書かれたクレーマーへの対応についての本。法律家の書かれた本なので、どうしても「最終的には弁護士へ相談」となってしまうのですが、どこをポイントにその切り替えをするかということも書かれているので、参考になるとは思います。具体例中心なので分かりやすく読みやすいですが、逆にいうと、抽象論が少なめなので、自分で応用しようと思っても難しいかもしれません。具体例も、お客様相談室とかそういう組織があるような、比較的大きな会社を想定していますし。「対応術」とはいっても、今クレーマーに悩まされている人にとっての特効薬になるようなことが書いてあるわけではありません。あくまで基本的な姿勢みたいなものを知っておく感じ。心理学的な面からのアプローチについては、それなりに記述もありますが、専門ではありませんから、他書で補えばいいと思います。
2009年04月26日
コメント(0)
-

岡村忠生他『ベーシック税法(第4版)』
入門書とされていますが、制度趣旨や具体例もそこそこに制度の解説をしてしまっているところがあったり、会計の知識があることを当然の前提としたような記述もありますので、これを一冊目とするのはふさわしくないと思います。独習向きというのも疑問。実体税法の解説について、所得税・法人税と所得課税のみに絞っているので、税法全体のイメージを掴むにもふさわしくないでしょう。むしろ、記述のレベルが比較的高いので、ある程度勉強してから読む方が使いこなせると思います。
2009年04月25日
コメント(0)
-

三木義一『よくわかる税法入門―税理士・春香のゼミナール (第4版)』
税理士と学生2人の会話+教授による解説という形式で、税法学のポイントをわかりやすく解説しています。税法の入門書は、往々にして各種税法上の制度を淡々とならべるだけの退屈で理解しにくい概説書になってしまうものですが、この本は税法学で問題とされている論点を題材にしているので、興味を持って読めると思います。もちろん、必然的に扱われる範囲は狭くなりますが、どんなことが税法学で議論されているのかを知るにはいいんじゃないかと。この本が出るまでは、税法学ってどこから入ったらいいか分からなかったわけで、まずはこの本から手をつけたらいいと思います。扱われる範囲は狭いものの、基本原則、所得税法、法人税法、消費税法、相続税法、酒税法、地方税法、租税手続法、租税処罰法、租税救済法と、税法学全体から万遍なく拾っているし、題材も比較的身近なものを扱っているのもいいですね。
2009年04月24日
コメント(0)
-

平川宗信『刑事法の基礎』
・基礎からおさらいしてみようと思って読んでみました。平川刑事法学の集大成みたいなものを期待していましたが、どちらかというと、歴史と制度の叙述が多かったです。・ある程度勉強の進んでいる人が、刑事法の歴史や基本原理の説明が手薄な教科書を補うために使う感じでしょうか。「さしあたっての」実益はなさそうですが、徐々に効いてくるといううことになるでしょうか。少なくとも、これを入門書とするのは難しいと思います。・原理原則から説き起こすというのは、非常にいいと思うんですが、それが個々の解釈論にどうつながってくるかを十分に例示してくれていないので、抽象的な理解に止まってしまいます。・「憲法」に基礎をおいた刑事法学ということが書かれています。でも、たとえば、刑事訴訟法において、被害者の人権を被告人の人権よりも強調する立場も、その逆の立場も、それぞれ主観的には憲法に基づいた主張をしているつもりなわけで、憲法を基礎においたとしても、かなり大きな幅があるということです。そもそも、憲法学自体においても、「比較考量論」という判断手法があったりするわけで、憲法を持ち出しても一定の立場が導かれるわけではありません。なので、憲法に基礎をおくというだけでなく、具体的に、憲法を用いるとどういう解釈論が展開されるのかを、例示して欲しかったということです。・テキストという位置づけのせいで、どうしても制度の概説が続いてしまうわけですが、原理原則や歴史の部分、あるいは平川先生自身の見解をもっと深くから論じてくれれば、読み応えのある本になったのに、と残念な気がします。刑事法に限らず法学全体について論じた本ですが、その好例として存在するのが、平川先生の師匠である団藤重光先生の『法学の基礎』なわけです。「の基礎」つながりということで、平川先生のこの本にも同じような期待をしてしまったわけですが、さすがに今の時代、学生のニーズには逆らえないんでしょうか。
2009年04月23日
コメント(0)
-

國貞克則『決算書がスラスラわかる 財務3表一体理解法』
先日、『リーガルクエスト会社法』の「会社の計算」のところの不正確じゃないかと思った記述への指摘をしておきましたが、あとからこの本のことを思い出しました。・この本は、ひとつひとつの取引ごとに、損益計算書(PL)、貸借対照表(BS)、キャッシュ・フロー計算書(CS)のどの数字がどのように変わるか、3表のどことどこがつながっているか、という観点から記述されていて、財務諸表の動き方やそれぞれの役割を理解するにはとても分かりやすい本です。通常の会計のルールでは、財務諸表はある一定期間経過後に作成するものですが、この本ではひとつひとつの取引ごとに、逐一新しい財務諸表を作成しているようなものです。通常のルールのもとでは、「BSはストック、PLはフローを表す」とか言われても、どっちも期末に期中取引をまとめて作成してしまうので、その違いがよく分からないかもしれません。他方で、このやり方だと、PLの数字は増える一方なのに、BSの数字は増えたり減ったりするという違いが分かったり、PLの数字の中でも「利益」だけはBSの数字と同じように増えたり減ったりする、そしてそこがBSとPLがつながってるところだ、とかいったことが分かったりします。つまり、通常の会計のルールとは違う側面から財務諸表を見ることで、より財務諸表の機能に対する理解が深まるということです。・この本では、PLとBSのつながりは、 1 PLの当期純利益とBSの利益剰余金はつながっている。 2 BSの右と左は一致する。というふたつのルールで表現されています(先日の話との関連ということで、CSとのつながりは省きます)。たとえば、事務用品を現金5万円で購入したという例では、 1 PLに事務用品費5万円が計上されるので、当期純利益は-5万円となる。よって、BSの利益剰余金も-5万円となる。 2 BSの右側が5万円減ったので、これとバランスさせるため、左側の現金も5万円減らす。と表現されることになります。通常のルールで勉強されている方であれば、2の記述に違和感を感じるかもしれません。というのも、2の記述は、複式簿記のルールである「取引の二面性」が反映されていない記述だからです。簿記のルールにしたがえば、費用の発生と資産の減少は「同時に」起こっているのであって、BSの右側が減ったからこれにあわせて左側も減らそう、という手順を踏む必要はないはずです。また、BSなりPLの数字を動かすには、あくまで「仕訳」を通さなければならないのが簿記のルールです。ところが2の記述では、BSの右側が減ったから左側もこれにあわせようといっており、なにか仕訳とは別のところで数字を動かそうとしているように読めてしまうわけです(ただし、簿記の世界でも、まさに損益の処理のところで「英米式」とかいって仕訳を通さない処理方法があったりしますが)。なぜ、この本がこういう記述をしているかといえば、「複式簿記」の知識がなくても読めるように、という読者に対する配慮からです。なので、読者に理解しやすくするため、という意味ではよく分かりますが、読者が「おこづかい帳(単式簿記)思考」のままで、2の記述を額面通りに理解しようとすると、変な誤解をしてしまうのではないかとも思います。・ここまで書いてきて、私が何をいいたいのかというと、先日指摘した記述も、「当期純損失が発生したからBSをバランスさせるために資産を減少させよう」と言っているように読めるところが、こういった「おこづかい帳思考」によるものではないかと思ったということです。
2009年04月16日
コメント(0)
-

『リーガルクエスト 会社法』
すぐれた会社法の教科書で、多くの人に勧められると思います。特に、初学者に対する配慮が秀逸。類書では、二色刷・図表を多用しただけで内容は単なる条文引き写しなだけにもかかわらず、入門書と謳っている本がありますが、そういう本はもはやいらないと思います。以下、箇条書きで。・共著者のうち、大杉謙一先生と伊藤靖史先生が、それぞれご自身のブログで、きちんと宣伝をしています。これは以前わたしが書いたところ(こちら)に関係します。おおすぎ Blog【宣伝】 会社法の教科書を書きました 【モード】いとう Diary ~ academic and privateリークエ会社法への道(1)リークエ会社法への道(2)リークエ会社法への道(3)・単なる条文引き写しではなく、簡単であってもその趣旨をきちんと説明している。・わかりにくそうなところは、ケースを用いて説明している。・本文とコラムとできちんとレベル分けがされている。・コラムというと、類書では単なる余談や単なる論点解説にすぎなかったりしますが、この本では初学者に理解しにくい点に対する丁寧な説明だったり、ある程度勉強が進んでいる人でも誤解しやすい点についての説明だったり、あるいは最先端の問題に触れられてたりして、読み応えがあります。・類書と比較して、「計算」の説明が丁寧。たとえば「分配可能額」の説明とか。計算に関する説明が丁寧という点では、名著である龍田節『会社法大要』を彷彿とさせます。ただ、丁寧な説明をしたが故に、ということだと思いますが、若干気になる記述がありました。以下、277頁から引用。(資本の)欠損を説明するくだりです。「仮に、ある会社のある事業年度の損益計算書に当期純損失が計上されたとしよう。これは、その年度の費用と会社が支払う税が、収益を上回ったことを意味する。このような損失が計上される理由はさまざまありうる。それを表示することも、損益計算書の役割である。上記の場合、貸借対照表は次のように影響を受ける。左側の資産の部の合計額は、当期純損失の分だけ、前年度よりも減少する。貸借対照表の左右の数字は一致するものだから、右側の数字も減少しなければならない。右側のうち、負債の部は会社が債務を履行しなければ減少しないし、純資産の部のうち資本金・準備金も、特別の手続をとらなければ減少しない。そのため、剰余金(準備金を除いたもの)が減少することになる。」この記述によると、損益計算書で当期純損失が計上されたことによって貸借対照表の資産の部が減少したかのように読み取れますが、当期純損失と資産(の減少)とはそういう関係にはないですよね。資産が減少するのは、(決算整理事項を除くと)あくまで期中に、資産が減少する取引をしたからであって、損益計算書上で当期純損失が計上されたことの結果ではないはずです。もちろん、・損益計算書で当期純損失が計上されるということは、期中取引で収益の発生よりも費用の発生が多かったからだ。・費用が発生したことが多く計上されているということは、多くの場合、同時に資産の減少も多く計上されているはずだ。・他方で、収益の発生が少ないということは、多くの場合、資産の増加も少ないということだ。・ゆえに、損益計算書で当期純損失が計上されているということは、多くの場合、貸借対照表上の資産は減少しているはずだ。という程度のことはいえますが、論理必然の関係ではないですよね。当期純損失が計上されたとしても資産が減少しない場合、または、当期純損失が計上されていないのに資産が減少する場合というパターンもあるということです。これを論理必然の関係にするには、資産・費用・収益に関する取引として、 資産の増加/収益の発生 費用の発生/資産の減少だけが行われ(逆仕訳含む)、たとえば、 資産の増加/資本の増加 費用の発生/負債の増加といった取引が存在しないという、非現実的な「仮定」を置かなければならなくなります。また、この記述では、当期純損失の分だけ資産の部の合計額が減少するということも言っていますが、これも上の「仮定」が存在する場合に限られます。仮に、こういう非現実的な仮定を想定したとしても、当期に純損失が発生したかということと、当期に資産が減少したかがわかるのは、試算表上において同時に分かるものであって、当期純損失が発生したから資産が減少したという順序があるわけではありません(もちろん、費用が発生したか、資産が減少したか、ということは期中取引においてひとつひとつ把握しているわけですが、ここでは「当期」純損失が発生したかということと、貸借対照表上の資産が前期末より「当期末」において減少したか、という話をしています)。ということで、損益計算書上に多く当期純損失が計上されるような会社には欠損が生じているというのは、それが普通のパターンだという意味で、現象についての記述としては間違いではないのかもしれません。でも、会計的にみればその表現は不正確ではないかと。もちろん、私の拙い会計知識のほうが間違っているのかもしれませんけど。とはいえ、類書では、せいぜい「貸借対照表上の右より左が少ない状態が資本の欠損」という程度の、ただ結果だけを述べただけの記述になっているのがほとんどでしょうから、この本のように、なぜ欠損が生じるのかといった原因を、初学者にも理解しやすいように説明しようとしている姿勢自体は高く評価できるわけです。
2009年04月13日
コメント(2)
-

石田穣『物権法』
最近はロースクール向けの教科書ばかりが出版されていますが、こういった本格的な体系書がもっとでてくれるとうれしいですね。「とりあえず判例・通説で」という近道な勉強法からすれば、冒頭から通説的な物権概念を批判するこの本なんて、とっても遠回りだってことで、敬遠されちゃうんでしょうけど。『担保物権法』が近刊とされていますが、気長に待ちましょう。以下、はしがきから引用。「法解釈学が学問であるならば、論証不能な法命題によって解釈論を展開するのは許されない。われわれ民法の研究者の任務は、論証不能な法命題を論証可能であるかのように説明に技巧を凝らすことではなく、論証不能な法命題であればそれを率直に承認し、論証可能な法命題によって解釈論を展開していくことである。」
2008年07月31日
コメント(0)
-
会社は商人ですよ。
以前も「会社は商人か」ということを問題としましたが(こちら)、これに関連して、最近最高裁判例がでました(最判平成20年2月22日)。 「会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと,すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負うと解するのが相当である。なぜなら,会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は,商行為とされているので(会社法5条),会社は,自己の名をもって商行為をすることを業とする者として,商法上の商人に該当し(商法4条1項),その行為は,その事業のためにするものと推定されるからである(商法503条2項。同項にいう「営業」は,会社については「事業」と同義と解される。)。 前記事実関係によれば,本件貸付けは会社である被上告人がしたものであるから,本件貸付けは被上告人の商行為と推定されるところ,原審の説示するとおり,本件貸付けがAの上告人に対する情宜に基づいてされたものとみる余地があるとしても,それだけでは,1億円の本件貸付けが被上告人の事業と無関係であることの立証がされたということはできず,他にこれをうかがわせるような事情が存しないことは明らかである。 そうすると,本件貸付けに係る債権は,商行為によって生じた債権に当たり,同債権には商法522条の適用があるというべきである。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」 会社の行為が事業とは無関係だと争う側に、その主張立証責任があるという結論自体はいいと思うのですが、「なぜなら」の段落の理由付けが私にはいまいち理解できませんでした。 判例では、 会社法5条 → 商法4条1項 → 商法503条2項と条文を繋ぎあわせることで結論を導き出しています。 後の商法4条1項から商法503条2項への繋がりは条文上明らかですが、前の会社法5条から商法4条1項への繋がりは、どうしてそういえるのかがよく分かりませんでした。 会社法5条は、会社が事業行為(と略します)をすればそれは商行為になるといっているだけで、会社が商行為を事業としているとまでは言っていません(矛盾はしないけどなんか逆なんですよね)。これを繋げるためには「会社がする行為は原則として事業行為だ」という前提を条文外からもってこないといけないような気がします。 会社法5条の中にこの前提が組み込まれているなら、同条は「会社の行為は商行為。但し事業行為でない場合は違う。」と書いてなければおかしいでしょう(会社法は立証責任の分配を意識して作ったというのが条文作成者の自慢のひとつでしょうし)。「会社の事業行為は商行為」と書いてしまったせいで、商法4条1項に直結しなくなっているわけです(商法総則を嫌ってあえてそうしたのかも)。 けどこの前提をもってくると、 1 会社の事業行為は商行為だ(会社法5条)。 2 会社の行為は原則として事業行為だ 3 会社の行為は原則として商行為だ。と会社法5条の文言及び解釈で片づいてしまい、商法4条1項や503条2項をもってくる必要がなくなってしまいます。つまり、503条2項に到達しようとして、会社法5条から商法4条1項を踏み台にして前に進もうとしてもそのままではつながらない、他方で、商法4条1項につなげようとして実質的な理由づけをほかからもってくると、商法4条1項や503条2項がいらなくなってしまうということです。 より厳密にいえば、「会社の行為が事業行為でないことを争う側に立証責任がある」という判例の結論を導くだけなら、上記2の実質的な理由付けだけで十分で、会社法・商法の引用は全くいらない、というか理由付けとしてはただの後付けです。判例の理由付けは、あたかも条文解釈から結論を導き出したようでいて、実は条文自体は何の理由付けにもなっていないのではないでしょうか。 と、ここまでわざと批判的な物言いをしてみましたが、会社法5条と商法4条1項の繋がりについてはおそらく、「会社のやる事業がことごとく商行為になるってことは、翻って会社が商行為を事業にしてるってことになる」ということなんでしょう。なんか循環風だし、もう少し素直に表現したいところですし、最高裁にも、会社法5条と商法4条1項の間にひとつ説明を入れて欲しいところですよね。 ちなみに、以前のブログで問題にしたことは、商法512条のように「商人」であることを前提とする商法の規定を会社の行為に適用するためには、商法4条1項を介在させなければいけないんじゃないかということでした。で、『論点解説新・会社法』では商人性を問題とするまでもなく適用されると書かれているけど、それはおかしいんじゃないかと思ったわけです。 本件判例からすれば、この場合、商法4条1項を介在させることになるんでしょうね。○会社法第5条(商行為) 会社(外国会社を含む。次条第1項、第8条及び第9条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。 ○商法第4条(定義) 1 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。第503条(附属的商行為) 1 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。 2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 第512条(報酬請求権) 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。第522条(商事消滅時効) 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
2008年03月04日
コメント(0)
-

鴨良弼『刑事訴訟における技術と倫理』(日本評論社)
日本評論社から名著がオンデマンド版で復刻されています。オンデマンドにしては比較的良心的な値段だと思うんですけど。私はとりあえず鴨先生の本を買いました。
2008年02月29日
コメント(0)
-

加藤哲夫『破産法 第4版補正版』 その2
以前におかしなところを指摘しましたが(こちら)、訂正表が弘文堂のホームページに載ってました(こちら)。解消されたところもあるんですが、訂正してもやっぱりおかしなままなところがあります。○266頁訂正表にしたがって直すと、以前指摘した記述を含む段落はつぎのとおりになります。(《 》が追加された部分)「この範囲で財団債権とされる範囲以外の租税に関する請求権は破産債権であり(97条かっこ書き)、《破産手続開始前の原因に基づくものについては、》一般の優先権がある債権として優先的破産債権となる(98条1項)。破産財団に関し破産手続に関し破産手続開始後の原因に基づいて生じる租税などの請求権は、破産財団の換価及び配当に関する費用の請求権に該当するものに限り財産債権となるが(148条1項2号)、それ以外のものについては、劣後的破産債権となる(99条1項1号、97条4号)。」 かならずしも間違っているというわけではないけれど、記述が多少追加されても不正確な記述であることはあんまし変わっていません。租税債権について破産法上の区別を整理すると、A 破産開始手続前の原因に基づいて生じた債権 a 開始当時納期限が到来していないもの、または納期限から1年を経過していないもの b 開始当時納期限が到来しており、かつ納期限から1年を経過したものB 破産開始手続後の原因に基づいて生じた債権 c 破産財団の換価及び配当に関する費用 d 破産財団に関して生じたもの e cd以外のものとなっており、それぞれ、Aa 財団債権(148条1項3号で財団債権となる) b 優先的破産債権(2条5項で破産債権とされ、98条1項で優先的となる)Bc 財団債権(97条かっこ書き、148条1項2号で財団債権となる) d 劣後的破産債権(97条4号で破産債権とされ、99条1項1号で劣後的となる) e 破産債権とはならないとして扱われることになります。訂正後の記述にこの記号を代入すると、「a以外の租税に関する債権(bcde)は破産債権であり(97条かっこ書き)、bは、一般の優先権がある債権として優先的破産債権となる(98条1項)。cdのうち、cは財産債権となるが(148条1項2号)、dについては、劣後的破産債権となる(99条1項1号、97条4号)。 この記述の問題は、1 eが破産債権であるように読めてしまうこと2 cが破産債権であるように読めてしまうこと3 bが破産債権となる根拠条文が2条5項であることが明示されていないこと(98条1項は「破産債権」であることを前提にそれが優先的になることを規定するものであって、同項によっていきなり優先的破産債権になるわけではない。ましてや97条かっこ書きはbには無関係。)4 dが破産債権となる根拠条文が97条4号であることが明示されていないこと(一番後ろには書いてあるが、本来は第1文の(97条かっこ書き)と書いてあるところで引用すべき)にあります。おそらく「以外」という言葉を無節操に使っているのが大きな原因なんだと思います。決して間違ってるということをいいたいのではなく、不親切だということ。 だから、もとの記述をできるかぎり尊重するにしても、たとえば、「a以外の租税に関する債権(bcde)のうち、破産開始手続前の原因に基づいて生じた債権でaに該当しないもの(b)及び破産開始手続後の原因に基づいて生じた債権で破産財団に関して生じたもの(cd)は破産債権とされる(2条5項、97条4号)。 そのうち、aは、一般の優先権がある破産債権として優先的破産債権となる(98条1項)。cdのうち、破産財団の換価及び配当に関する費用(c)は財団債権となり(97条かっこ書き、148条1項2号)、それ以外(d)は劣後的破産債権となる(99条1項1号)。」とするか、「破産債権に該当」→「財団・優先/劣後に格上げ/格下げ」という二元的な書き方をやめて、「破産開始手続前の原因に基づいて生じた債権でaに該当しないもの(b)は優先的破産債権となる(2条5項、98条1項)。他方、破産開始手続後の原因に基づいて生じた債権で破産財団に関して生じた債権のうち、破産財団の換価及び配当に関する費用(c)は財団債権となり(97条かっこ書き、148条1項2号)、それ以外のもの(d)は劣後的破産債権となる(97条4号、99条1項1号)。」とすべきでしょう。ちなみに、最後に「なお、破産財団に関しないで破産開始手続後の原因に基づいて生じた債権(e)は、破産債権とはならない。」と付け加えると親切でしょう。法律書は往々にして、条文の裏側を書かないという悪弊がありますので。 なお、266頁7行目で「そのため破産手続開始後1年以内に納期限が到来するもの」に財団債権を限定するとありますが、これは破産手続開始「前」の間違いで、それに伴い「到来した」に変えた方がいいでしょうね。○166頁 延滞税、国税、加算税等が劣後的破産債権とされていることについての記述を、訂正後の記述に書き換えると次の通りとなります。「延滞税などについての破産手続開始後の部分は(1)破産手続開始後の利息などと性質上同じであること(つまり、本税部分に付帯する性質を有する)から、(2)国税などであっても破産手続開始後に破産財団の管理・換価費用として発生するもの以外は劣後的破産債権とされていることとの均衡、また、(3)加算税なども劣後的破産債権とされていることとの均衡に鑑みて、劣後的破産債権とされている。」 ここでも、(2)で「以外」という言葉を無節操につかって、本来はdだけに限定すべき記述がその他の租税債権も劣後的破産債権とされているように読めてしまうのが問題なわけです。また、延滞税、国税、加算税が劣後的破産債権とされていることの説明の後に、延滞税が劣後的破産債権とされている理由だけを書いているのかがよくわかりません。国税や加算税が劣後的破産債権とされている理由はどうしてここに書かないのでしょう。 135頁や266頁とのクロスリファレンスもきちんとしてほしいところです。 また、166頁1行目では「破産手続開始後の」延滞税という限定がないせいで、延滞税全般が劣後的破産債権として扱われているように読めてしまいます。 このように何かおかしな記述のある本ですが、今時の教育的配慮を尽くした教科書を受動的に読むよりも、なんかおかしいんじゃないかという眼で気をつけて読むようになる、という意味では逆に良い本かもしれませんね。ブログのネタにもなってくれるし。
2008年02月22日
コメント(0)
-

新堂幸司『新民事訴訟法』(第三版補正版)
去年の12月に、ショウタロウさんという方からメッセージをいただいていましたが、全く気がつきませんで申し訳ありません。いまさら回答してももはや手遅れでしょうが、一応お答えだけしてみようと思います。メッセージの趣旨は、新堂幸司先生の『新民事訴訟法』の(注)の部分を飛ばして通読しても一定の理解を得ることは出来るのかということでした。どの程度のものを「一定の理解」というかにも違ってきてしまうので何ともいえませんが、注をとばしても読めることは読めます。別にとばしてもいいよなあっていう注もあることはありますし。ただ、私の印象として、難易度については、本文と注とでそれほど厳密な違いがあるようには感じませんでした。本文も注も、難しいところは難しいし。むしろ、注を読むことで本文の理解が進むというところもあるように思います。読んでておもしろいなっていう注もありますし。要するに、注によりけりということですね(それをここで個別的にあげることはさすがに大変だし、最近は目を通してないのでよく覚えていません)。なので、読み方としては、本文と注とで形式的に区別して読むのではなく、本文も注も区別しないで、自分が理解できないところは後回しにして読むという読み方でいいんじゃないかと思います(ただ、限られた時間の中で読まなければならないという現実的な状況にあるならば、本文と注で区別するという形式的な読み方も一つの合理的な方法だと思います)。民事訴訟法は、手続が一通り分かっていないと理解できないところもありますし。これは本文・注の問題とは別の、手続法特有の問題です(その意味では、新堂先生の教科書のような分厚い本をいきなり読むのでは、迷子になるのではないでしょうか)。また、特に未修の方ですと、民法などの実体法の勉強が進んでいないと理解できないところもありますし。新堂先生の教科書の記述について、理解はできないまでも、どこが重要なのかが分かる程度のレベルになってから読んだほうが、スムースに勉強が進むように思います。とりあえず思いついたことを書きましたが、何かあったら追記します
2008年02月21日
コメント(2)
-
慣れないことに手を出して-科学と法学の違い
たとえば、「カラスはすべて黒い」というのは、あくまで仮説であって1匹でも黒くないカラスが見つかったら、覆っちゃう程度のものですよね。 あるいは、飛行機が飛ぶのはどういう原理かっていうのも、今支持されている原理が絶対的に正しいわけじゃなくって、今のところ、その原理を覆す事例(その原理に従っているのに飛ばない、その原理に従っていないのに飛ぶ)が見つかってないってだけですよね。 つまり、科学における学説っていうのは、事例1の場合は飛ぶ、2の場合は飛ばない、3の場合は、・・っていう「事例」(「原因」と「結果」といいかえてもいいと思います)を前にして、それらを整合的に説明できる「理屈」を考え出すってことですよね。そうすると、これまで支持されてきた学説と整合しない事例Xを見つけた場合には「発見」といっていいと思いますけど、「理屈」を考え出すことは、これまでに確認されている事例と矛盾していないものにすぎずそれが真実であるとは限らないから、「発見」とはいいにくいんじゃないですか。 ということで、科学というのは、いくつかの「原因」と「結果」があって、それらに合う「理屈」を考える、そしてその「理屈」に合わない事例が生じた場合にはさらなる「理屈」を考える、そういう営みなんだと思うわけです。 科学なんて自分にとって門外漢なことを偉そうに語ったのは、法学ってもっとひどいんじゃないかと思ったからです。 たとえば、刑法で、「二重抵当の場合に背任罪は成立するか」って論点に関して言うと、二重抵当という「原因(事例)」と刑法247条という「条文」だけではどういう「結果(結論)」(背任罪は成立か不成立か)がでるかが決まらずに、「条文」に論者が思い思いの「理屈」をくっつけた上で、自分の良しとする「結果(結論)」を自由に決められるからです。 科学では、「原因」と「結果」は任意に動かすことはできないから、それに合わない「理屈」はどんどん排除されるわけだけども、法学では、「理屈」の部分を任意に動かすことで「結果」をどちらにも転ばすことができてしまうわけです(科学のレベルでも、観察者によって「原因」と「結果」の見え方が異なるとか、観察したことによって「原因」が動いてしまい「結果」が変わってしまうとか、そういう話は置いておいて)。科学 〔原因〕→ 理屈 →〔結果〕法学 〔原因〕→〔条文〕+理屈 → 結果 (〔 〕は動かせない部分) 私の言葉の使い方が特殊なのかもしれないので、一応整理しておくと、科学における「事例」には、「原因」と「結果」の両方を含めていますが、法学でいう「事例」には、「原因」しか含めておらず「結果」はそこに入れてません。要するに、法学における「結果」はあらかじめ決まっているものではないので、「事例」の中に入れられないということです。科学 「原因+結果」(=事例)法学 「原因」(=事例・要件事実) 「結果」(=結論・効果) もちろん、法解釈にもお作法があるから「理屈」の範囲は全くの無限ではないけども、同じ「条文」から全く逆の「結果」がでてくるような「理屈」が導き出せるなんていうのは、法律家以外の人からみたら、どうかしてるとしか思えないんじゃないですか。 さらにいえば、立法論という形で「条文」自体をかえることもできちゃうので、変わらないのはただ一つ、「原因」だけだということになります。法学 〔原因〕→ 条文+理屈 → 結果(立法論も含めて考えた場合) だからといって、私は、「法学は科学たるべき」などというつもりはなくって、ただ、法学なんてのはこういうものなんだよ、と言いたかっただけです。・ こういう文脈で「自然法思想」なんてのをながめると、「理屈」に対して、単なる法解釈上のお作法以上の限定をかけていくことで、好き勝手な結果を導き出せないようにする考えなんじゃないかと思えるわけです。法学 〔原因〕→〔条文〕+《理屈》 → 結果(《 》は自然法による限定がかけられている) けども、その自然法の中身自体が、科学で言う「原因」と「結果」のように動かせないものではありません。なので、自分の良しとする結果を導くために、あるいは、自分の良しとしない結論を導かないために、自然法の中身を自由に決めることができてしまいます。 その他、法実証主義以外の考えってのは、ほとんどこういうことが当てはまるんじゃないかと思います。 法律には、こういう目に見えない限定ではなくって、「憲法」による限定というのもあります。けども、憲法自体も「条文」によってできているので、憲法による限定の中身も解釈により導き出さなければなりません。 憲法による限定は、憲法の条文がある以上、「自然法」とかとは違って融通無碍ってわけにはいきませんが、それでも、憲法解釈によってある程度自由にコントロールすることができます。しかも、憲法の条文は抽象的な規定が多いから、「法律」の解釈よりも解釈の幅が広いはずです。法学 〔原因〕→〔法律条文〕+法律理屈+〔憲法条文〕+憲法理屈 → 結果・ さらにいえば、法が裁判の場で適用されるということを考慮に入れて、裁判で認定される事実は、裁判官が主観的に認定したものにすぎず、過去に起こった事実をそのまま再現したものではない、などといいだしたら、「原因」さえ不確かなものになってしまいます。 誰が決めるのかという観点でいうと、 原因 実務家。最終的には裁判官 ↓ 条文 立法者 + 理屈 学者、実務家。最終的には裁判官 ↓ 結果は、上の3つが決まれば必然的に決まるはずですがどうでしょうね。 ここまでくるときりがないので、このへんで止めておきます。・追記: 科学の場合も、「原因」と「結果」があらかじめ与えられているのではなく、ある特定の「結果」を導き出すためにどういう「原因」がそろえばよいかを探究する、という営みもあるわけですね。たとえば、生ゴミを有効な資源に変えるためにはどうしたらいいのか、とか。 科学の場合は、任意に「結果」を設定すればいいんでしょうが、法学の場合は、建前上、原因・条文・理屈がそろえば必然的に「結果」が決まることになっているわけですよね。 「効果から要件を考える」という発想というのは、ここでいう科学の場合と似ているわけですが、論者が任意に設定した「結果」の正しさというのは、どこで担保されることになるんでしょうか。 立法論の場合には、任意に「結果」を設定できるだけでなく、その結果を導くための「原因」(要件)も自由に設定できてしまうわけだけども、一応民主主義の手続に乗っ取ってやりました、という言い訳ができると。
2007年08月25日
コメント(0)
-
精神分析する自分を精神分析する-自己言及の難しさ。
例によってタイトルは内容とあんまし関係ないです。 先日の日記に対して応答していただきました。内容からして、無視されてしまうのではないかと思っていたのですが、反応していただいてよかったです。他のブログとの応答ができるなんて、なんか普通のブログになった気分です。ア それは理由ではない-法律書とフィクション イ 不法領得の意思ウ ロボットはパイロット搭乗型よりも遠隔操作型に限る。-学説とのつきあい方 エ リーガルクエストについて・1 論証なしに直接性、不法性を要求している学説は妥当でない2 小林先生は論証なしに直接性、不法性を要求しており妥当でない 私の書いたアに対して、2だと捉えるのはおかしいと批判されたので(イ)、私は1と書いた、と釈明したのですが(ウ)、これに対する応答(エ)を読ませてもらって、あらためていろいろ考えてみると、どうも私は、3 論証なしに直接性、不法性を要求している学説を、何の留保もなしにただ引用している小林先生の引用方法は妥当でないと考えていたような気がします。「妥当でない」が言い過ぎだとすれば「教科書として不親切である」ぐらいになるでしょうか。 小林先生の見解だと捉えて批判しているわけではないが、全くの無罪放免ではなく、小林先生の引用の仕方には問題があると。1のニュアンスを超えているはいるが、2までは及んでおらず3にとどまっているということです。 こういう分かりにくい趣旨が含まれていたため、誤解を招くような文章になってしまったのかもしれません。私自身、エを読ませてもらって、いろいろ考えるうちに、どうやらそうじゃないか、と気づいたくらいですし。・ 個々の論点に対する「重要度」というよりも、ああいう書き方だと、「直接性、不法性」が要求されるのが当然であるかのように読めてしまうのではないか、ということです。そういう書き方の典型としてたまたまこの論点に関する記述を見つけたわけです。だから、論証なしに当然のように書かれている記述であれば、誰が書いたもので、どの論点に関するものでもよかったんです。 たまたま、小林先生自身が書いたものだったので、自己矛盾を指摘しているかのような記述に読めてしまうのかもしれませんが、別の先生が書いたものであっても、同じように小林先生の「一文」をもって指摘していたと思います。 教科書の「外」にでれば必ずしも当然ではないということに気づくのかもしれませんが、私はどうしても「独学者」の視点からみてしまいます。なので、教科書の「中」に、(詳細な検討までは不要ですが)当然ではないことに気づけるような「きっかけ」を組み込んでおいてほしいと思ったわけです。たとえば、ご指摘のように、「疑問の余地もないではない」と一言いれておくとか。 抽象的ないいかたになってしまいますが、教科書の外にでてはじめて教科書の中の問題にはじめて気づくような記述ではなく、教科書の中にいる時点で、外にどういう問題があるかくらいは示唆しておいてほしいということです。「一般には直接性・不法性が必要だって言われてるけど、それほど自明のことじゃないよ」程度の留保は書いておいて欲しいわけです。・ まったくの余談ですが、「独学者」の視点ということでいうと、たとえ専門書であっても、教科書しか読んだことがない独学者でも何とか読めるように、(本文自体はいじらなくていいですが)独学者用の導入部分なり注釈なりを組み込んでもいいんじゃないかと思います。「出版事情の厳しい折」云々とまえがきで述べるくらいなら、そうやって読者層を拡げる努力をしてもいいんじゃないですか。頁数の関係で、とかいうならばネットにのっければいいですし。 裁判員制度がはじまるせいで、刑法学者も、これまでのように専門家だけに通じる言葉で話しているわけにはいかないでしょうし(ただし、難しい言葉を柔らかい言葉に言い換えるなんて皮相的な対応で足りるとは思いません)。まさか、裁判員は非専門家用の刑法規範により判断し、他方で、裁判官はこれまでと同じ専門家用の刑法規範により判断する、なんて判断者ごとに規範を二分するんでしょうか。裁判員が事実認定しやすいように、これまでの刑法規範を簡単にしたものを新たに別建てで用意するということ。 たとえば、窃盗罪(自転車盗)における不法領得の意思(排除意思)を認定するにあたっても(窃盗罪自体は、裁判員制度の対象ではありませんが、これが事後強盗致死に発展する場合もありますし、対象事件と併合して審理される場合もありますので、およそありえないということはないでしょう)、厳密には、窃取の時点でどれだけの時間、どれだけの距離利用する意思があったか、などということを判断しなければならないはずです。しかし、裁判員に当時の内心を認定してもらうのは難しいということで、窃取後に、現実にどれだけの時間・距離利用したか、によって判断してしまうと。もちろん、これだと、行為後の事情によって犯罪の成否が判断されるのはおかしいという理論的な問題や、はじめは(主観的な)不法領得の意思があったのに窃取直後につかまった場合には窃盗罪にならなくなってしまうという実際上の問題がありますが、このデメリットよりも裁判員に判断しやすくするというメリットのほうを優先するという考えもでてくるんじゃないかと思うわけです。 つまり、刑法学説における説の優劣を比べる際に、あらたに、「裁判員にとって判断しやすいか」ということも考慮要素に加わると。今まで言われていたことでいえば「明確性」に含まれるものだと思いますが、誰にとって明確であるか、ということを特定したということです。 ちなみに、これまでの刑法学説が、自分の説が明確であるという場合、誰にとって明確であるといっているのでしょうか。とても一般の人にとって明確だとは思えませんので、まあ、専門家にとって、ということなんでしょう。(にもかかわらず、行為無価値論者が結果無価値論者に対して、おまえの説では行為時に国民に規範を示せていないから不当だ、なんていうのはおかしいと思うわけです。行為無価値論では建前として行為時に規範を示せていることになっていますが、個々の行為者が行為時に行為無価値論者の組み立てた規範を理解した上で行動することができるなんていうのは、フィクションにもほどがあります。行為無価値論が結果無価値論に対して優位なところは、違法性を判断する時点が一つ増えることで、犯罪の成否をコントロールできる道具が一つ多くなるという点です。 国民に対して示す規範としてどっちが分かりやすいのかって点に関しては、もし行為無価値に、法益侵害とは関わりのない何かを含ませるならば、むしろ行為無価値論のほうが分かりにくくなるでしょう。もちろん、ここでいう行為無価値論が、結果無価値と行為無価値が両方そろってはじめて違法だという、名実ともにきちんとした二元論ならばまだ問題は少ないんですが、二元論といいながら、なぜか結果無価値論よりも処罰範囲の広くなっている「偽二元論」だと、その問題点がはっきりとでてきます。中身のはっきりしない行為無価値によって犯罪の成否が左右される場面が多くなるためです。) で、これからは、自説が明確だという人に対して反論するときは、「確かに専門家レベルでは明確といえないこともないが、裁判員が判断するには難しく妥当でない」という反論ができるようになるんでしょうか。 余談が無駄に長くなりましたが、裁判員制度と刑法解釈論との関係については、こちらとこちらにも少し書きました。・ いただいた反応に対する回答として書き始めたつもりが、全体としてなぜか余談のほうが多くなってしまいました(この稿、そのうち書き換える気がします)。
2007年08月10日
コメント(0)
-

ロボットはパイロット搭乗型よりも遠隔操作型に限る。-学説とのつきあい方
以前の日記で、私が『リーガルクエスト刑法各論』の記述に対して指摘した点について、(たぶん)批判しているブログがあるんですが。 ここで(たぶん)と留保して書いたのは、 まず、「とあるブログ」とされてどのブログのことか特定されておらず、リンクも張られていないという形式的な理由からです。 また、そのブログの批判の骨子は、『リーガルクエスト刑法各論』は「法科大学院生向けの教科書・基本書」であるにもかかわらず、「とあるブログ」が、単著・モノグラフィーレベルの詳細・厳密な論証がなされておらず不十分などと批判しているのは妥当でない、というものなんですが、 私の日記では、論証が「不十分」なんて書いたことはなく、論証が「なされていない」と書きました。ましてや、単著・モノグラフィーレベルの詳細・厳密な論証が必要だなどといったこともありません。「論証が0だ」と言ったのであって、「論証が1しかないが10書くべきである」なんて言っていないということです。 また私は、その記述には論証がないと言っただけで、そのブログに書かれているように、その記述が「執筆者の意見・立論であると捉えたうえで」その執筆者を批判する、なんてことはしていません(「樋口範雄先生」に対する身も蓋もない物言いと対比してみてください)。 このように、内容的にみても、私のブログに書いてあることと全然対応していないので、私のブログと似たような別のブログがあって、そっちに対する批判なのかもしれないなあと思ったというのが実質的な理由です。 ただ、「下位基準云々」てところにも触れられているので、さすがにまあ私のブログのことなんだろうなと思うわけです。 ということで、以下は、もし「とあるブログ」が私のブログのことだったら、という「仮定」のもとで書いていきます(なので、私も本文中にリンクを貼るのはやめておきます。とはいっても、そのエントリーにトラックバックを送ってくださっているブログのことなんですが)。○ いくら法科大学院生向けの教科書だからといって、論証が無くてもいいってことにはならないでしょう。判例の結論をそのままなぞるだけの本であれば話は別ですが。 単著・モノグラフィーレベルの詳細・厳密な論証は不要だと批判しながら、じゃあ教科書レベルの論証として何が書いてあるの、ってことには触れられていません。やはり、教科書レベルの論証さえ不要だというつもりでしょうか。 単著・モノグラフィーレベルの詳細・厳密な論証が現に存在するのであれば、教科書では教科書レベルの論証にとどまっていてもいいんですが、私の少ない読書量の範囲では、単著・モノグラフィーで「直接性・不法性」が必要な理由を詳細・厳密に述べたものを見かけたことがありません。あるとしても、せいぜい事例からの「帰納的」な理由付けだけじゃないですか(この辺は私の勉強不足に起因する問題です)。 「不法性」に関して、条文上は「財産上不法『の』利益を得」とされていて「財産上不法『に』利益を得」とはなっていません。 文言解釈からすれば、あくまで財産自体に不法性が備わっていることを要求しているのであって、財産の取得の仕方が不法かどうかは問題としていない、ということになるのでしょう。 なので、不法性が必要なのは「条文に書いてあるから」というのは、正しい解釈論ではないでしょう。文言解釈+αではじめて財産の取得の仕方に不法性が要求されるという結論がでてくるわけです。 教科書レベルでは、文言解釈で押し切ってしまえばいいってことになるんでしょうか。 また、「直接性」に関しては、総論における「因果関係論」と関係があるのか別建ての概念なのかもはっきりしませんが、これも法科大学院生レベルの教科書では、総論と各論を関連づけて書く必要はないってことでしょうか。○ ここからは、なぜ、彼/彼女が、私がブログに書いた<論証がない>を、<記述箇所を執筆者の意見・立論と捉えた上で、これに対し単著・モノグラフィーレベルの詳細・厳密な論証がなされておらず不十分と批判している>などと、曲解してしまったのかを考えてみます(私としては、上に書いた反論のための反論みたいなものより、こういうことを考える方が好みです)。・<教科書であっても、単著・モノグラフィーレベルの詳細・厳密な論証が必要である><執筆者の主張でない記述に対しても、当人が書いた以上執筆者の主張だと捉えて批判してよい>なんて主張は、誰がどう考えてもおかしいですよね。 私がそのような主張をしていないにもかかわらず、なぜ、そのように主張していると曲解した上で批判してしまっているのか、その理由を考えてみたいのですが、 この方の他のエントリーを見る限り、とても私では書けないようなしっかりした論述がなされていますので、決して読解力がないとかそういうわけではなさそうです。 それだけの能力がありながら、私のブログに対しては曲解してしまったのはなぜか。 他のエントリーの雰囲気からも感じられることですが、小林憲太郎先生のことが大変大好きなんでしょう。そうしたところ、大好きな小林先生の著作にケチをつけてる奴がいると。 ここから先が二通りに分かれると思うのですが、1 こいつをどうにか批判してやりたい。「論証がない」に対しては「論証がある」と反論するしかないけども、論証がないのは事実だ。このままでは批判できなくなってしまう。そこで、誰もが明らかに間違いだと分かるような見解に仕立て上げてしまおう、そうすればいくらでも批判できるぞ。直リンを貼らなければ、自分のブログを読んでいる人には実際の主張を見られないで済むし。2 1の思考過程を、意図せず無意識におこなってしまった。 なぜ2のような可能性がありうるかというと、彼/彼女が小林先生のことを大好きだからです。大好きな先生にケチをつけている奴を見ると、正しく言葉を読み込まないまま反射的に批判してしまうと。 私は、別に彼/彼女のことを批判しているのではなくって(他のエントリーを見れば、私よりも断然賢い方であることが分かります)、なぜ曲解しているのかが不思議で、その理由を考えてみたかっただけです。○ もう一つ触れたい記述があって、それは、突然「ポストモダン」なんて単語がでてくるところです。<その人に対する批判はその人の見解に対してすべきである><教科書には単著・モノグラフィーレベルの詳細・厳密な論証は不要である><文脈にあった批判をすべきである>なんて、極めて普通の主張の、どのへんがポストモダンなの?と思わず突っ込みを入れたくなっちゃいます。が、私がいいたいのはそういう普通の突っ込みではありません(ポストモダンの定義とか、私にはどうでもいいことですし)。 この記述がおもしろいと私が感じるところは、記述の大部分が小林先生を擁護するための論述に費やされているにもかかわらず、「このような私の考えは、ポストモダン的すぎるだろうか」なんて、突然自分のことに触れ出すという点です。 このポストモダンに関するくだりは、ごっそり無くなっても何の問題もないですよね。なのに、なぜこんな記述がでてきたのかってことを考えてみたくなるんですが、これには二通りの可能性があるんじゃないかと。1 一つは、「小林先生を守ってあげる」だけではあまりにも自分というものを見失っていると感じたので、自尊心を回復するために「私の考えはポストモダンだ」と言ってみたと。 この場合、自尊心が回復できればいいわけだから、そこに入る言葉は「ポストモダン」じゃなくってもいいことになります(取替え自由であるせいで、逆に、いまいちかみ合ってない「ポストモダン」を持ってきてしまった?)。ただ、彼/彼女にとっては、自分の考えがポストモダンだということが、一番自尊心を回復させやすい言葉だったんでしょう。2 もう一つは、彼/彼女が、小林先生のことをポストモダニストだと捉えていて、単に先生を遠くから援護するだけでなく、「私も先生と同じポストモダニストなんですよ」と近づいていってみたと。 2と考えたほうが、全体の姿勢が一貫していて美しいと感じますがどうでしょう。○ ちなみに、別のエントリーで書いたので読まれていらっしゃらないのかもしれませんが、相続事例で財産の取得に「不法性がない」というあてはめをしているのは間違っている、と指摘したことに対しては、この方は何の反論もしていません。さすがにこれに対してはフォローできなかったんでしょうか。 彼/彼女の言い方からすれば、これも単に誰かの学説の「あてはめ」をただ引用しているだけだということになりますかね。でもさすがに、間違ったことを「ただ」引用しちゃまずいでしょ。 これもまあ、「相続欠格であることがばれずに相続したこと」は刑法上は「不法な」利益移転と評価されない(という見解がある)、だけどそんな細かいことは教科書に書かなくてもよく、不法でないという結論だけ書いておけばいい、なんて「教科書だから」の抗弁を畳み掛けられちゃったら、私はもう何も言えません。○ 以上書いたことは、大部分が私の創作にかかる「物語」に基づいた記述ですので、まあ、的はずれなんでしょう。 ただ、あくまでも「書かれていること」から、その背後にある「書かれていないこと」を推測しているのであって、「書かれていること」に反することを「書かれていること」だと主張する、という誤りは犯していないつもりです。
2007年08月08日
コメント(0)
-
代襲相続の謎と細切れ要件事実論(その2)
(前回の続き)○長い余談(なんちゃって要件事実論) たとえば、事例3に事実を付け加えて、兄弟姉妹E(Aの実子)がいたとして、DがEに対して相続分確認訴訟を起こしたとします(訴えの利益とかそういうのは省略)。 で、Dが自己がBの相続人であることをいうためにはいかなる事実を主張しなければならないのかってことなんですが、 1 B死亡 2 Bの親AがBより前に死亡 3 Bの兄弟姉妹CがBより前に死亡まではいいとして(「Bに子がいない」ってのも請求原因ですか)、Dはさらに、 4 DはCの子てところまで主張すればいいんですか。 で、但書については、Eが抗弁として主張することになると。そして、Eの抗弁は、上記いずれの説を採用するかによって異なると。 5 DはBの直系卑属でない(甲説) 5 抗弁無し(乙説) 5 DはBの傍系卑属でない(丙説) 但書を抗弁にまわしたことで、Eが訴訟で主張しない限りは、DがBの直系卑属(傍系卑属)でないことが裁判所に明らかであっても、裁判所はDが相続人であると認定してもよいと考えるならば、甲説も決して奇妙な見解ではなくなるんじゃないですか。本文と但書の主張立証責任を両当事者に割り振ることにより、889条2項で準用する887条2項は、初めから死んじゃっているのではなく、Eから但書の抗弁が出されて初めてお亡くなりになるということ。 条文作成者が、このような「要件事実的思考」に基づいて、887条2項をそのまま889条2項で準用したというならば、やるなあと思いますけどね。 私としては、上に書いた「Bに子がいない」とかEの抗弁にまわしたことも、すべてDの側で主張すべきじゃないかと思うんですが、特に根拠はありません。 Eの抗弁を請求原因にまわすとすると、・ 甲説では、「DはBの直系卑属である」ことが請求原因となるが、DはBの直系卑属であることを主張できないから、主張自体失当(あるいは、主張はできるが立証できずに請求棄却?)・ 乙説では、但書は空文だから、結論変わらず。・ 丙説では、「DはBの傍系卑属である」ことが請求原因となるが、DはBの傍系卑属であることを主張できないから、主張自体失当(あるいは、主張はできるが立証できずに請求棄却?)となると。 要件事実的思考を極端な形で突き詰めると、たとえば、CがBの相続人であることを主張するという通常の兄弟姉妹の相続の場合でいうと、Cの請求原因は、 1 B死亡 2 CはBの兄弟姉妹だけで足り、これに対して他の兄弟姉妹であるEが、 3 Bには直系尊属Aがいた。と抗弁をだし、これに対してCが 4 Aは死亡したと再抗弁をだすとかいったことになるんですかね。まあ、3は当たり前のことだから主張する必要はなくって、結局、4の再抗弁が請求原因に繰り上がることになりますか。 あるいは、 3 Bには直系尊属AがいるとAが生存していることも抗弁に含めるのかどうか。 これとは別系列の抗弁として、Eは、 3 Bには子Fがいたと抗弁を出し、これに対してCが 4 Fは死亡したと再抗弁を出すってのもありえますか。こっちの3は当たり前とはいえないから、繰り上がるってことはないんでしょう。 ただ、こちらでも 3 Bには子FがいるとFが生存することを抗弁に含めることもありえるんでしょう。 直系尊属の抗弁と子の抗弁が別系統だってのは、質の悪いジョークにしか聞こえないですか。 これは単なる要件事実遊戯なので、この辺の話をあまり真面目に読まないように。全部請求原因に突っ込むってのが、おそらくまともな見解なんだと思いますよ。 ただそうすると、文言解釈による甲説では、889条2項で準用する887条2項但書の生きる道が初めから閉ざされてしまって可哀想なので、要件事実を無理矢理分断して両当事者に主張立証責任を割り振ることで、生きる道を与えてあげてみたかっただけのことです。終わりのほうに書いたことは明らかにやりすぎです。 ただ、たとえば売買契約を締結したことと弁済したことが請求原因/抗弁に分かれるならば、兄弟姉妹であることと子・直系尊属がいることを請求原因/抗弁に分けたっていいんじゃないのか、少なくとも、これらにどれだけ本質的な違いがあるのか、ってことは疑ってもいいんじゃないですか。追記:上であげた例ですが、時列がずれる契約締結と弁済よりも、契約締結と錯誤のほうがいいかもしれません。これは権利根拠事実と権利消滅事実は区別できても、権利根拠事実と権利障害事実の区別は明確でない、という証明責任論の問題に絡んだ話。
2007年08月03日
コメント(0)
-
代襲相続の謎と細切れ要件事実論(その1)
○家族関係 A(父) B(Aの実子) C(Aの養子) D(Cの実子。AC縁組前の出生子) ○事例11 CがDを出産2 AC養子縁組3 C死亡4 A死亡 DはAを相続することができるか?○事例21 AC養子縁組2 CがDを出産3 AC死亡4 B死亡 DはBを相続することができるか?○事例31 CがDを出産2 AC養子縁組3 AC死亡4 B死亡 DはBを相続することができるか?第887条(被相続人の子の相続権・代襲相続権) 1 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 1 左に掲げる者は、第887条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。 第1 直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 第2 兄弟姉妹 2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合にこれを準用する。第901条(代襲相続人の相続分) 1 第887条第2項又は第3項の規定によつて相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであつたものと同じである。但し、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであつた部分について、前条の規定に従つてその相続分を定める。 2 前項の規定は、第889条第2項の規定によつて兄弟姉妹の子が相続人となる場合にこれを準用する。○前提知識1 DはCの子である。2 Dは縁組前の出生子なので、ABとDとの間には親族関係は発生しない。3 Aが死亡した場合、ACの養親子関係は終了するが、CB間の養親族関係は終了しない。○検討1 事例1(子の子の代襲相続の場合) Dは被相続人Aの「直系卑属」でないから(前提知識2)、Dが代襲相続人とならないことは明らかである(887条2項但書)。2 事例2、3(兄弟姉妹の子の代襲相続の場合) 兄弟姉妹の場合にも、887条2項但書が準用されている(889条2項)。ところが、兄弟姉妹の子の代襲相続の場合には、およそ「被相続人の直系卑属」は登場しない。DはCの「直系卑属」ではあっても、被相続人Bとの関係では「直系」でない(事例2)、「直系」でも「卑属」でもない(事例3)。被相続人に直系卑属がいるなら、兄弟姉妹(の子)に相続分がまわってくるはずはないから、被相続人の直系尊属がいることと兄弟姉妹(の子)が代襲相続することとは両立し得ない。 文言通りに読むならば、兄弟姉妹の相続に関してはおよそ代襲相続が発生しないことになる(甲説)。他方、およそ代襲相続が発生しないのはおかしいとするならば、889条2項のうち887条2項但書を準用する部分は空文だと解釈するか(乙説)、限定的に解釈する(丙説)しかない。甲説(代襲相続全面否定説) 但書を文言通りに解釈するなら、兄弟姉妹の子が代襲相続することはおよそありえないという、但書によって本文の効果を完全に打ち消してしまう奇妙な見解に至る。 この説によると、事例2、3とも代襲相続は否定される。乙説(代襲相続全面肯定説) 代襲相続がおよそありえないのはおかしいということで、但書は空文だと解釈するならば、DはBの兄弟姉妹であるCの子でありさえすれば、Bとの親族関係がなくてもBを代襲相続できることになる。 この説によると、事例2、3とも代襲相続は肯定される。丙説(代襲相続部分肯定説) 但書が「直系卑属」としているのは子の子の代襲相続用であり、繋がりの薄い人間に代襲相続されることを防ぐ趣旨であるから(AC間、CD間だけでなく、AD間にも親族関係を必要とする)、兄弟姉妹の子の代襲相続の場合には、「傍系卑属」と読み替えて、BD間にも親族関係を求める、という解釈もありうる。 この説によると、事例2では、DはBの「傍系卑属」なので代襲相続できるが、事例3では、DはBの「傍系卑属」でないから、DはBを相続できないことになる。 甲説 乙説 丙説代襲相続認める 代襲相続認める 代襲相続認める→→→→→→→ →→→→→→→ →→→→→→→認めない 空文 親族以外は認めない←←←←←←← ←←←← さて、DはBを相続できるのでしょうか、という問題なんですが、この辺はもはや原理ではなく、どっちかに決めてください、という問題なんでしょう。 私は、条文をきちんと読むまでは、当然に丙説の結論だと思っていたのですが、この結論にもっていくためには、一定程度の操作が必要なわけです。 (つづく)
2007年08月01日
コメント(0)
-
樋口範雄「人工生殖で生まれた子の親子関係」(法学教室322号)を読んだ印象
以前の日記で書いた代理母がらみの最高裁決定について、樋口範雄先生が法学教室322号で「人工生殖で生まれた子の親子関係」という論文を書かれています。で、これに対して、森田博志先生のブログで詳しく批判的検討がなされています。私も、樋口論文にはどこか違和感を感じているのですが、森田先生ほどの的確な批判ができるわけでもないので、印象論どまりの話をします(にもかかわらず、だいぶ勇み足となります)。・樋口先生自身の結論は、最高裁決定に批判的で、卵子提供者と子との母子関係を認め(たネヴァタ州の判決を承認す)るべきだ、というものです。変なところに括弧をつけたのは、最高裁決定自体は「外国判決の承認」という国際民事訴訟法上の問題であるのに、樋口先生の論述は、「子の福祉のために親子関係を認めるべきか」という実質法レベルの話にとどまっていて何かずれている気がしたからです(気のせいなら幸いです)。・いきなり「結びに代えて」のところからいうと、「法律論の限界に気づかざるをえない」なんていうけども、それは当たり前でしょうと思いました。法律論に限界があるのは当たり前であって、限界がなかったら法律論ではなくなります。憲法上裁判官は法律に拘束されて裁判をしなければならないとされていますが、法律論に限界がなくなれば完全な尻抜けになってしまいます(ここでいう「法律論」が解釈論のことなのか立法論のことなのかはっきりしませんが、さしあたり解釈論だとしてはなしを進めます)。法律論に限界がないならば、法解釈に関するあれやこれやのルールも、もはや不要ですよね。というか、法律の存在そのものがいらないのかもしれません。ここで何か喩えを挙げて「法律が存在していながら法律論に限界がない」という状態を説明しようと思ったのですが、どうにも想像ができませんでした。とんち和尚だって、立て札にちゃんと漢字で『橋』と書かれているにもかかわらず、これを勝手に同音である『端』に読みかえて橋の端を渡ったとしたら、それはとんちでもなんでもなく、単なる無法者にすぎません。幸い立て札をひらがなで書いていてくれたおかげで、同音異義語に読み替えることができたわけです。つまり、いくらとんちとはいえ、ひらがなならまだしも、漢字で書かれているものを同音に読みかえるのはさすがにまずいでしょう、という、とんち解釈の限界があるからに他なりません。問題はどこに「限界」を引くかということだと思います。・法解釈者は、その法律がどこに線を引いているのか、あるいはひくべきかを議論しているわけです。最高裁の線引きに納得がいかないからといって、法律論には限界がある(のはおかしい)などと法の専門家がいうのは自分の仕事を自ら否定しているように聞こえます。法解釈者としては、その線引きがおかしいと正面から批判すればいいことです。実際、(内容はともかく)「結びに代えて」に至るまでの樋口論文の中身ではそうしているのであって、法律論には限界があるなんて誤導的な捨てセリフを残す必要はないでしょう。とんち和尚の事例でも、「ひらがなの場合は同音ならどの意味でとってもよい」というところに線を引くのか、「ひらがなの場合は文脈から可能な範囲に限定する」というところに線を引くのか、という線を引く場所の議論をするわけです。「線なんか引かなくていい」なんていいだしたら法律はその役割を終えることになってしまいます。・ 裁判所自身もこれまで、親子関係につき、文言上認知となっているのを分娩と解釈してみたり、推定規定を(事実上)拡大したり、制限したりして、それなりに工夫してきているわけです。なので「法律論の限界に気づかざるをえない」などと突き放したようなことをいうのではなく、いいところを伸ばしてやればいいわけです。樋口先生が、昭和37年判決を持ち出して血縁重視主義を導こうとするのも(その読み方が正しいかは別として)、そういうことではないんですか。いずれにしても、限界を設けることが法律の役割であることは、変えようがないと思います。・一方当事者側にたって鑑定書を書いたせいで当事者の感情に引っ張られてしまったんでしょうか。法律論には解釈論も立法論もあるのに、これを区別しないで法律論とまとめて言ってしまっていることとか、法律論には限界があるとか言ってしまっているあたりも、自分が納得いかない裁判に対して非法律家の人がいう常套句だし。ちなみに、現政権や前政権を見れば、立法論には限界がないんだなあと実感せざるをえないですよね(極端な例は、手続「法」の内容を緩くすることで硬性「憲法」をやわらかくしちゃうところとか)。・代理母の是非と誰々間に親子関係を認めるかは別問題だと言う点は、私自身もさしあたりそのとおりだとは思っています。けども、卵子提供者との間に親子関係を認めてしまうと、ネヴァタ州に行きさえすれば日本法が認めていない親子関係の設定ができるという事態を正面から認めることになってしまいます。最高裁自身は、お腹を痛めた人が母親だという日本のルールとは違うルールを認めてもよいのかという身分法秩序のことしか触れていませんが、代理母を正面から認めることによって犠牲を被る人も出てくることも考えなければならないはずです。しかも、子の福祉を保護することは、何も卵子提供者との間に「親子関係」というものを認めることによってしか果たせないわけではありません。親がいるからといって必ず幸せになれるわけでもなければ、親がいないからといって必ず幸せになれないわけではありません。だから、 子の福祉 対 身分法秩序という抽象化された図式は正確ではなく、 代理母による親子関係を認めることによる得失 対 認めないことによる得失という事実関係そのままで対比させなければ、正確な議論ができなくなってしまいます。前者の図式では、あたかも代理母否定説が子の福祉を考えていないようなレッテルを張られてしまいますが、必ずしもそうではないということ、また、代理母肯定説が、子の福祉をはかる手段を親子関係の設定しか考えていないことや、代理母による親子関係を認めることによって生ずる犠牲のことを十分考慮していないことも見えにくくなってしまいます。・また、最初に述べたように、樋口論文が、実質法レベルの議論をしているのか国際民事訴訟法レベルの話をしているのか、区別されているようには思えません。最高裁決定の批判をしているというスタイルからすれば、国際民事訴訟法レベルの話をしなければならないはずですが、民事訴訟法118条上の「公序」とは何か、ということについては正面から論じていないように思います。こういう区別が得意なのは、やはり国際私法の学者の側なんでしょうか(ちなみに、道垣内先生は、実質法と抵触法を、蟻と鳩の比喩で対比しています。や、別に他意はありません)。・以上、批判的な物言いになっていますが、「法律論の限界に気づかざるを得ない」という記述に対する批判だったり外在的な批判であって、樋口先生個人の見解そのものに対して批判しているわけではありません。それに、樋口先生が文字通り「法律論の限界に気づかざるを得ない」などと本気で思っているとはどうも考えにくいですし。私が勝手に邪推するに、「最高裁決定の理由は硬直的で結論は不当である」という主張に、どこからか当事者の感情が混入した結果、そういう表現になったんでしょうか。フォローじゃなく本音として、樋口先生の作品はおもしろいと思いますよ。たとえば、「アメリカ信託法ノート(1)」「アメリカ信託法ノート(2)」 内容は非常におもしろいですが、無闇なスペースを減らせばA4判1冊で足りたはず。「フィデュシャリー「信認」の時代」 信認概念について、日本法の解釈論にどう反映させられるのか、いろいろ考えてみたくなります。「アメリカ代理法」 FAのAってエージェント(代理人)のこと、ってところから始まるアメリカの代理のお話。
2007年07月07日
コメント(2)
-

道垣内弘人『信託法入門』
道垣内弘人先生だから、ということで中身を見ないで買いました。最初と終わりは期待を持たせる内容なんですが、それ以外の部分は新しい信託法を条文に即して解説しているだけなので、おもしろさ半減。や、もちろん、新しい信託法の概要を知りたい人にとっては、とてもコンパクトにまとまっているし、具体例も挙げられているので非常に分かりやすいことは間違いないです。でも、そういうことはお役人さんがやればいいことであって、学者である道垣内先生には信託とはなんぞや、ってことを深く掘り下げた本を書いて欲しいわけです。道垣内先生自身も、信託の技術面だけじゃなく本質論にも興味をもってね、みたいなことを書かれていますが、この本の記述は技術面に偏っているので、この本で本質論にまで思い至るとは考えにくいんですけど。名著『信託法理と私法体系』や『刑法と民法の対話』のような内容を日経文庫に期待するのはお門違いですか。けど、たとえ文庫(新書)であっても、最近でいえば、福井健策『著作権とは何か』(集英社新書)のような深みのある本もあるんだし。法律の解説に止めるというのは編集者の意向だったのかもしれませんが、この本で一応義務を果たしたということで、もう一冊『信託とは何か』という本を書いてください。長谷部恭男『憲法とは何か』(岩波新書)みたいな感じで。ちなみに、長谷部先生の本は、私の読み落としがなければ、憲法の条文は引用されていなかった、というか何条に何が書いてあるということさえほとんど書いてなかったはず。これは、現行の日本国憲法の解説ではなく、憲法ってのはそもそも何なんですか、という本質論を展開されているからだと思います。
2007年05月24日
コメント(0)
-
条文解釈のお作法-会社法の読み解き方(423条1項3項、428条1項)(その2)
(前回からのつづき) ここまでは、自己取引の場合でも利益相反取引の場合でもそれ以外の場合でも、423条1項の意味は共通であることを前提に書きましたが、あり得る解釈としては、それぞれの類型ごとに423条1項の意味を使い分けるということも考えられます(以下、二元説一元論に絞って書きます)。 まず、原則論として、423条1項の任務懈怠には任務懈怠(客観)と過失(主観)とが含まれるはずだと。 けども、「自己取引」の場合における423条1項の任務懈怠は、428条1項が任務を怠ることとは区別して帰責事由云々と書いているので、「任務懈怠(客観)」の意味なんだと(それに伴い423条3項で推定されるのも「任務懈怠(客観)」のみとなる)。これは、428条1項によってはじめて任務懈怠(客観)に制限されるのではなく、自己取引における任務懈怠というものが、もともと過失(主観)を含まないものなんだということ(428条1項を確認規定扱いする)。 これに対して、「利益相反取引」における423条1項の任務懈怠は、428条1項のような区別のある規定はないから、原則論のとおりだと(それに伴い423条3項で推定されるのも原則論どおり)。 このことを、任務懈怠の意味に焦点をあわせて整理すると、1 自己取引の場合 428条1項 客観 →423条1項 客観 →423条3項 客観2 利益相反取引の場合 423条1項 客観+主観 →423条3項 客観+主観とそれぞれの類型の中では任務懈怠の意味が整合するわけです。しかし、こういう使い分けが許されるのか、という点が当然問題となりますよね。 考え方の順番としては、本当は上の矢印の順のとおりなんですが、1の場合、428条1項によって423条1項の任務懈怠の意味が制限されるのではなく、423条1項ははじめから「客観」を意味するのだと。なんでわざわざこういうことを言うのかというと、423条1項の任務懈怠を「客観+主観」としてしまうと、(後で制限されるとはいえ)428条1項(「客観」)と一致していなかったことになってしまうからです。 また、上に書いたとおり、423条3項に「主観」も含めてしまうと、同条1項の段階で過失の立証責任がすでに役員側に転換されていることとも整合しなくなってしまうという問題があります。 そうすると、類型ごとに使い分ける、という手法をより強引に推し進め、通常の場合には、423条1項の段階で「立証責任の分配」の一般論により過失(主観)の立証責任を役員側に転換するが、利益相反取引の場合には、423条1項の段階では過失(主観)の立証責任を役員側に転換しないでおいて、423条3項によって、任務懈怠(客観)とともに過失(主観)を役員側に転換される、としてしまうか。3項によってはじめて過失(主観)の立証責任の転換がなされるんだと。任務懈怠の意味及びその立証責任の所在を整理すると、1 自己取引の場合 423条1項 客観(追及側) 423条3項 客観(役員側) 428条1項 客観(主観は不要)2 利益相反取引の場合 423条1項 客観(追及側)+主観(追及側) 423条3項 客観(役員側)+主観(役員側)3 それ以外の場合(通常の場合) 423条1項 客観(追及側)+主観(役員側)ということになり、123それぞれの類型の中では任務懈怠の意味を一致させることができるわけです。 以上、長々と書きましたが、条文解釈のお作法の問題であって、別に実益はありません。だから、教科書の類でも、 423条1項の任務懈怠責任は過失責任 423条3項により利益相反取引の場合は任務懈怠が推定される 428条1項により自己取引の場合は無過失責任となると何ら節操なく並列的に書いてあっても、なんの問題も生じないわけです。任務懈怠の意味が条文ごとに違っている、なんてことは運用上も何ら支障はありませんし。条文作成者としても形式よりも実益を重視したということでしょうか。 何ら関連無く選択された言葉がたまたま一致しているというだけで、無理に意味を合わせる必要はないと思いますが、ここででてくる任務懈怠は意識的に同じ言葉を選択しているはずです。それゆえ、なんとかして意味を一致させようと試みたのですが、それぞれの類型(自己取引、利益相反取引、それ以外)の中で一致させるところまでが限界で、類型間での一致まではできなかった、というところでおしまいです。○会社法第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任) 1 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。3 第356条第1項第2号又は第3号の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則) 1 第356条第1項第2号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。 第356条(競業及び利益相反取引の制限) 1 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2007年05月23日
コメント(0)
-
条文解釈のお作法-会社法の読み解き方(423条1項3項、428条1項編)(その1)
【定期購読1年(12冊)】法学教室以前の日記で「株式会社の役員等の会社に対する損害賠償責任」の条文解釈について書きましたが、これに関して、法学教室6月号(NO.321)で落合誠一先生が論文を書かれているのを読みました。 落合先生の見解を、私なりの言葉を勝手に補って表現すると次のようになります。正確な要約ではないので、以下の解釈は落合先生の見解ではなく、二元説のうちのある一つの解釈モデルということにしておきます。1 423条1項 423条1項の「任務を怠った」には、任務懈怠(客観)と過失(主観)が含まれる。 任務懈怠(客観)の存在は責任を追及する側が、過失の不存在は役員側が、それぞれ立証する責任がある。このことは立証責任の分配に関する一般論から導かれる。2 423条3項 423条3項は、任務懈怠(客観)の存在を推定するもの。過失(主観)は423条1項ですでに役員側にその不存在の立証責任があるから転換する必要なし。3 428条1項 428条1項は、役員側が過失(主観)の不存在を立証しても責任を免れることはできないとするもの(無過失責任)。(落合先生は2に関し、1項と3項の任務懈怠は同義だとされていますので、3項には客観だけでなく主観も含まれると考えているのかもしれません。ただ、こう解すると1の段階で主観はすでに役員の立証責任だとされていることと整合しなくなりますので、解釈モデルとしては、とりあえず、3項は客観のみを推定するものとしておきました(抜け道は後述)) 結論自体はこういうことでいいんだと思いますが、この解釈によると条文にいう「任務懈怠」につき 1 423条1項→客観+主観 2 423条3項→客観 3 428条1項→客観と1と23とで異なる意味に解釈しなければならなくなります(ちなみに、423条1項と同条3項が同義(客観+主観)だとすれば、12と3で異なる意味ということになります)。なお、3が客観であることは文言上動かしがたいでしょう。 形式的にも実質的にも満足できる解釈をするには、やっぱり、423条1項に「ただし、任務を怠ったことが役員等の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」とか入ってないとどうしても難しいよね(これを入れると任務懈怠はすべて「客観」で揃います)。 この但し書きを入れなかった理由を邪推するに、あらゆる事案において常に「任務懈怠(客観)+過失(主観)」と二元説だけで押し切れる(「二元説一元論」と命名します)わけではなく、事案によっては「任務懈怠(客観と主観の総合判断)」と一元説的に判断せざるをえない場合もある(「一元説・二元説二元論」)と考えたんじゃないですかね。 だから、423条1項のような原則規定では、本文(客観)+但書(主観)と明確に区別した書き方をしないでそのへんはぼかしておいて、例外規定の場面で必要な限度で客観と主観を区別した書き方をすると。そうすると、条文間の不整合ははじめから織り込み済みですか。・ もし二元説で割り切れないとすると、やや複雑な状況が発生します。 「自己取引」の場合は、428条1項が明確に二元説の立場に立つことを前提にしていますので、 423条1項 任務懈怠(客観)を追及側が立証 423条3項 任務懈怠(客観)の不存在を役員側に負わせるとなります。 まあ、実際は「任務懈怠(客観)」の中で過失(主観)的なものが考慮されてしまうのかもしれませんが、建前としてはそれは428条1項により禁止されていると。 (自己取引を除いた)「利益相反取引」の場合、上では423条3項は過失(主観)については触れていないと書きましたが、これは「二元説一元論」を前提とした解釈にすぎません。 「一元説・二元説二元論」によれば、423条1項には 1 任務懈怠(客観)+過失(主観) 2 任務懈怠(客観と主観の総合判断)の二つの類型があることになります。 そして、1の場合で立証責任を 任務懈怠(客観)→追及側 過失(主観) →役員側と分配した場合には、423条3項では任務懈怠(客観)だけを転換すればよいわけです。 けど、2の場合には、主観と客観を区別することができないわけだから、 423条1項 任務懈怠(客観主観の総合)を追及側が立証すべき 423条3項 任務懈怠(客観主観の総合)の立証責任を役員側に転換と、3項でも、客観だけを取り出して推定することはできず、主観も含めて推定することにならざるをえないはずです(ただ、総合判断の場合、主観と客観の総合にとどまらず、根拠事実と障害事実をも総合的に判断せざるをえない場合もあるので、立証責任の転換といっても、実際上はそれほどの効果はないのかもしれません。)。 つまり、423条1項に二つの類型が含まれることにあわせて、423条3項でも、客観のみを推定する場合と客観主観をともに推定する場合とがあるということです。 まとめると、1 自己取引の場合(二元説を前提) 423条1項 任務懈怠(客観)を追及側が立証 過失(主観)の不存在を役員側が立証 423条3項 任務懈怠(客観)の不存在の立証を役員側に負わせる 428条1項 過失(主観)の不存在の立証を認めない2 利益相反取引の場合 ア 二元説が相応しい事案 423条1項 任務懈怠(客観)の存在を追及側が立証 過失(主観)の不存在を役員側が立証 423条3項 任務懈怠(客観)の不存在の立証を役員側に負わせる。 イ 一元説が相応しい事案 423条1項 任務懈怠(総合)の存在を追及側が立証 423条3項 任務懈怠(総合)の不存在の立証を役員側に負わせる3 それ以外の場合(通常の場合) ア 二元説が相応しい事案 423条1項 任務懈怠(客観)を追及側が立証 過失(主観)の不存在を役員側が立証 イ 一元説が相応しい事案 423条1項 任務懈怠(総合)の存在を追及側が立証(総合判断の場合の評価根拠事実と評価障害事実の区別は省略) 落合先生が引用されている田中亘先生の見解は、利益相反取引の場合には二元説により理解し、それ以外の場合には一元説により理解する、というもののようですが、ここでわたしが書いていることは、自己取引を二元説のみによって理解し(二元説一元論)、それ以外の場合は一元説及び二元説によって理解する(一元説・二元説二元論)、という考えなわけです(一元論と二元論の二元論)。 わたしの考えの根拠となっているのは条文の書きぶりのみであって、実質的な根拠はとりあえず何も考えていません。ただ、この考えでも、1や2アの場合に任務懈怠の意味が一致しないという問題は解決できていません。 なお、自己取引の場合でも一元説が相応しい事案があるのかもしれませんが(二元論の一元論)、きりがないので考えないことにします。(次回へつづく)○会社法第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任) 1 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。3 第356条第1項第2号又は第3号の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則) 1 第356条第1項第2号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。 第356条(競業及び利益相反取引の制限) 1 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2007年05月22日
コメント(0)
-
これは総論ではないのか。
先日の日記で、強盗罪の財産上の利益の移転に「直接性」「不法性」を要求すべき事例として相続事例というものをあげているという記述をとりあげました。けど、故意に被相続人を殺した場合は「相続欠格」になってしまいますので(民法891条1号)、不法でない移転の例としてあげるのは適切ではないでしょね。相続欠格なのにそれがばれないまま相続できたとすれば、それは「不法な」相続なはずですので。そもそも、刑法学説でいう「不法な」移転というものをどうやって判断するのかは、不法の中身が不明なのでよくわかりません。たとえば、詐欺行為による財産の移転は、民法上は取り消しうるにすぎないし被詐欺者が事後的に承認したとしても、刑法上は詐欺罪が成立する不法な移転と評価されるわけです。また、奪取罪でも、民法上財産の所有権につき取得時効が成立したとしても、刑法上は不法な移転と評価されるわけです。そうすると、相続についても、民法上は問題のないものだったとしても、刑法上は不法な移転だと評価されることもあるんじゃないでしょうか。もちろん、相続事例の場合は「直接性」で制限できるから別にいいってことかもしれませんが、そのほかの例で、単に他の法律上適法と扱われている、という一事だけから、刑法上も不法な移転ではない、と即断するのはおかしいんじゃないか、ということです(ただし、引用元の「リーガルクエスト刑法各論」では直接性ありとなっていますから、相続事例で強盗罪の成立を否定することはできないはず)。というよりも、先日の日記にも書いたとおり、強盗罪が成立するから「不法な」移転と評価されるのであって、財産移転だけを独立に取り出して「不法な」移転かどうかを決めてから強盗罪の成否が判断される、というのはなんか順番が逆なようにも思えます。いずれにしても、ここでいう不法の中身がよく分からないまま、ある事例につき、不法だとか不法じゃないとか言っててもあまり有意義ではないでしょ。「相続欠格」の問題が生ずるのを回避するためには、たとえば、夫Aが、妻BにBの父Cを相続させるため、(Bと共犯関係なく)Cを殺害した、という事例を想定したほうがいいんでしょうね。ただこの場合には、BがCに財産を得させるための行為が強盗罪になるか、という別の論点もでてきますが。そもそも、なぜ相続事例で強盗罪を成立させるべきではないんでしょうか。親殺しが強盗殺人罪になってしまうと、他人を殺すよりも親殺しを重く評価するという尊属殺人罪(刑法旧200条)の復活みたくなるからですか(もちろん、子→親事例だけに限られるわけではありませんが)。もしそうなら、それを理由にすればいいのであって、直接性なんてものでごまかす必要はないでしょう。また、被相続人を殺しても相続欠格があるから(殺人がばれずに)相続人になれるとは限らないし、相続人になれたとしても確実に特定の財産を相続できるわけではない、というのであれば、強盗罪の実行行為性を否定すれば済む話であって(条文的には240条の「強盗」に該当しないということ)、わざわざ直接性、不法性なんてものを持ち出す必要はないでしょう。また、相続人の地位というものが財産上の利益にあたらないのであれば、それを取得することに向けられた殺害行為は「強取」にあたらないことになりますし。もし実行行為性が否定できないのであれば、それにも係わらず強盗殺人罪の成立を否定する理由はどこにあるんでしょうか。場合によっては、殺害した時点では(2項強盗の既遂とするのではなく)1項強盗罪の未遂とし(ただし殺人が既遂なので強盗殺人罪としては既遂)、実際に財産を取得できた段階で、危険が現実化したということで1項強盗罪の既遂となる、という構成でもいいんじゃないですか。この場合は、因果関係の認定の問題がでてきますが(とはいえ法定刑はどっちでもかわらない)。死期をさとった父親が全財産を第三者に寄付しようとしているのを知って、自分の相続する財産が失われるのを防ぐために父親を殺した、というような事案でも、強盗殺人罪を否定していいのかどうか。第三者に対する(もらえるはずという期待権を侵害したことを理由とする)強盗罪でも成立させればいいんですか。なんにしても、相続事例につき一律に強盗罪の成立を否定するのはおかしいんじゃないかと思います。さて、もうひとつの事例である、経営者交代事例の場合はどうなんでしょう。1人株主かつ代表取締役Cを唯一の相続人Bが殺害し、自己を代表取締役に就任させた場合には、株式とともに代表取締役としての地位も取得したといえるのかどうか。相続事例と経営者交代事例が交錯する場合の問題。こういう相続がからまない普通の経営者交代事例の場合には、実行行為性が欠けるとするか因果関係が欠けるとすればいいんでしょうかね。
2007年05月18日
コメント(0)
-
伝わらないこと。
教科書類ではぞんざいな扱いしか受けない普通の清算についてなんですが。一言かけば済むことじゃないですかシリーズ。たとえば、「株主総会+取締役会+監査役」という機関構成の公開会社が清算手続に入った場合、取締役は478条1項1号により清算人になるわけですよね。じゃあ、477条4項で設置が強制されている監査役はどうやって選ぶんでしょうか。結論的には、平常時監査役が自動的に清算時監査役になるみたいなんですが、普通に条文を見ているだけではその結論はでてきません。477条2項からすれば、「清算株式会社」になってはじめて、精算株式会社が定款で清算時監査役を設置できるみたいに読めるし。それに、同条5項では、委員会設置会社の場合は監査委員が監査役になると書かれていますが、それ以外の会社では誰が監査役になるか書かれていませんし。「条文に特段何も書いてない以上、監査役は平常時のままだってことを476条から読み取れ」ってことなんですかね。これとあわせて「480条を見れば、そこでいう定款変更をしてはじめて退任する(んだからそれまでは従前の監査役のまま)ってことぐらいわかるでしょ」ということかもしれません。477条5項は、委員会設置会社に監査役がいないから書いておいただけだと。「国民にわかりやすい」というのは、形式論理的にみて無駄なものは排除するとか、そういうことではないはずなんですけどね。あれとこれを組み合わせれば裏から読み取れる、なんてというのはある種の訓練を積んだ人じゃないと分かりませんし。というか、こういう条文作成法は会社法がはじめてじゃないですか。なんか「新時代の」わかりにくい法律、という感じ。今までのわかりにくい法律とは種類の異なる分かりにくさ。素直な分かりにくさではないわけです。会社法本人は「分かりやすいでしょ」と思っているあたりにたちの悪さを感じます。一言、平常時監査役がそのまま清算時監査役になる旨書いておいてくれれば、わかりやすくなるんですが。例によって、条文引き写し系な教科書には、こういう問題は条文に書かれていないことなので、書いていないわけです。立法担当者によって積極的にいろんな出版物がだされていますが、「内容」の解説本だけでなく、この算数的(?)条文作成技術そのものについても、一冊書いて欲しいですね。あるいは、本当の意味で分かりやすく書くとどういう条文になるか、という本もあればいいですね。○会社法第476条(清算株式会社の能力) 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 第477条1 清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。 2 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。3 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。 4 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。 5 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。 6 第四章第二節の規定は、清算株式会社については、適用しない。 第478条(清算人の就任) 1 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。 一 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。) 二 定款で定める者 三 株主総会の決議によって選任された者 第480条(監査役の退任)1 清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。 一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更 二 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更 2 第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。
2007年05月17日
コメント(0)
-
弘文堂プレップ・シリーズ著者リレーエッセイ
http://recre.boxerblog.com/prep/とても良い企画ですね。
2007年05月16日
コメント(0)
-
常識的犯罪論の断層
1 素人と玄人-裁判員制度が解釈論に与えるインパクト2 それは理由ではない-法律書とフィクション1の抽象的な物言いを2の論点にあてはめると(強盗殺人罪を想定)、財産上の利益の移転が「直接」かどうかは裁判員が常識的に判断すればいい、なんてことになりそうです。裁判員の皆さんに、過去の判例分析なんかしてもらうわけにはいかないだろうし。かといって、裁判官が、「こういう判例がありますよ」なんて分かりやすく解説するっていうのも、なんか誘導になりそうで難しいでしょうね。そうではなく、いかなる事実があれば「直接」といえるかということは裁判官のほうで決めちゃって、裁判員は、裁判官が設定してくれた個々の事実があるかないかだけ判断すればいいんですか。この考えをさらにすすめると、たとえば「殺意」の認定でも、裁判員は、凶器がなんだったかとか部位はどこかといった個々の事実の有無だけを判断し、「殺意」があったかどうかは、裁判官がそこで認定された個々の事実を総合して判断するということになりかねません。間接事実からの「殺意」の認定なんて、裁判員には難しいでしょってことで。「法令の解釈」は裁判官の専権とし、裁判員には「事実の認定」の権限があるわけですが、上の「直接性」の場合、「利益の移転には直接性が要求される」というところまでが法令の解釈であり、どういう事実があれば直接といえるのかは事実の認定の問題なのか、それとも、「利益の移転には○○といった事実があること(直接性)が要求される」と、直接性の中身を決めるところまでが法令の解釈に含まれ、いかなる間接事実があればその直接性の中身たる事実が認定されるのかが事実の認定になる、ということなのか。さらに、そこでいう間接事実として何が必要なのかというところまでもが法令の解釈に含まれてしまうのか。根拠はありませんが、たぶん、1 直接性2 直接性の主要事実は何か。3 2の主要事実を認定するための間接事実は何か。4 3の間接事実は存在するか。12までが法令の解釈にあたり、34が事実の認定ということになるんじゃないですか。殺意の場合は、「直接性」みたいに「そもそも直接性って必要?」って問題はないと思うので、1 殺意の主要事実は何か。2 1の主要事実を認定するための間接事実は何か。3 2の間接事実は存在するか。となり、1が法令の解釈、23が事実の認定と。ただ、2を事実の認定に含めてしまうと、たとえば、「被告人は窃盗の常習犯である」という間接事実から殺意が認定できるという考えの裁判員がいたとしても、裁判官は「その事実を間接事実として使うのは禁止します」とはいえず、あくまでも評議の中で説得するか多数決で押し切るかしかできないってことになりますよね。事実の認定は裁判員の権限だから、裁判官が、「別内容の犯罪をやってるってことを殺意の認定に使ってはいけません」なんて事実認定のルールを押しつけることはできないはずです。使って良いかどうかというルール自体を、国民の常識といわれるものにさらさなきゃいけないということです。もう少し勉強してから書き直します。
2007年05月15日
コメント(0)
-
素人と玄人-裁判員制度が解釈論に与えるインパクト
以前にもどこかで書いたと思いますが、国民に対して何をすれば処罰されるのかを事前に知らせる行為規範性を強調しておきながら、個々の解釈論としては普通の人に理解できないような説をとなえているのは、おかしいんじゃないかと。行為規範性を強調する方向の行く先は、裁判官が裁判で用いる裁判規範は厳密なものとしておき、それとは別に行為者に対する簡単な内容の行為規範を用意しておくか、裁判規範ごと国民に理解しやすい内容にしてしまうか、ですよね。それでも、従来は「行為者」に対する関係(規範を向けられる側)でどうするかってことだけを考えてればよかったんですが、これからは「裁判員」というもう一つのタイプの国民との関係(規範を用いる側)を考えなければならなくなりましたよね。とすると、裁判員制度の導入趣旨から考えて、もはや刑法解釈論なんてものは放棄してしまい、条文だけを手がかりにあとは国民の処罰感情とかいうものだけをストレートに結論に反映させればいいんですか。あるいは、裁判員制度はあくまで「手続問題」だということで、刑法解釈論には影響はない、あるいは影響を及ぼすべきではない、ということになりますか。
2007年05月14日
コメント(0)
-

それは理由ではない-法律書とフィクション
たとえばこういう記述。2項強盗罪に関して、「なお財産上の利益の移転は暴行・脅迫から直接、不法に生じていなければならないとされる。したがって唯一の相続人が相続を目的として被相続人を殺害した場合や被害者の死亡後、経営者会議の議決により経営権を獲得する目的で、被害者を殺害した場合には、強盗殺人罪は成立しない。相続は死亡から直接生じるものの、それ自体は適法な法現象であるし、会議の議決は死亡から直接生じるものでも、また不法なものでもないからである。」(リーガルクエスト刑法各論140頁)ここでは、財産上の利益の移転が暴行・脅迫から「直接、不法」に生じなければならないという「理由」から、そこでかかげる事例において強盗罪を否定するという「結論」が導かれています。じゃあ、「直接、不法」が必要な「理由」はどこからでてくるのかというと、どこにも書いていません。おそらく実際には、そこでかかげる事例において強盗罪を成立させるべきでないという感覚があって、これら事例を強盗罪から除外するために、「直接、不法」という要件を付加した、というところではないかと思います。つまり、表向きはあたかも「演繹」的に答えが導かれたかのように書いてありながら、実は、事例の側から「帰納」的に要件が作り出されたのでは、ということです。それが法解釈として正しいかはともかく、それはそれでひとつの証明方法には違いないのですが、帰納によっていることをきちんと明記してほしいわけです。先日の日記で引用した小林憲太郎先生の一文があてはまるんじゃないかと思うんですが、「共通了解」があるから論証なしでもかまわないってことですか。けど、相続事例や経営者交替事例で強盗罪を否定することには共通了解があるとしても、処罰感情が一致しない事例がでてきたときには、ある人は「直接」だといい、ある人は「直接」でない、といい出すことが予想できます。で、このままでは結局のところ、当該事例を処罰すべきか否かという生の処罰感情でしか、説の優劣を決することができなくなります。また、「不法」かどうか、というのも、もし相続事例で強盗罪が成立するという結論をとるならば、そこでいう相続も「不法」な利益の移転となるわけです。つまり、不法でないから強盗罪が成立しない、あるいは、不法だから強盗罪が成立する、というのは順序が逆であって結論先取りなわけです。このような事態が発生するのは、「直接、不法」がなぜ要求されるのかについての理由が、帰納的にしか根拠づけられていないところにあると思います。規範的な根拠づけがないせいで、「直接、不法」の中身を決めることができないわけです。こういうことはこの本だけに限られるわけではありません。むしろ、この本は最近の本の中では『アクチュアル刑法各論』と並んで優れているほうであって、理由付けなしにあたかも当然のように論述が進んでいくような本は他にもあるわけです。けども、このような優れている本であってもこういう記述があるんですね、ということを言ってみただけです。残念ながら、書かれてあることを正面から読むだけでは法律書を理解できないこともあるわけです。
2007年05月13日
コメント(0)
-
一親多子と一子多親
↑必ずしも正確な物言いではありませんが。 親が子供を複数持つことは、(人口規制政策でも採用されないかぎりは)何ら批判されるものではないわけですよね。 何を当たり前のことを言っているんだ、と思われるかもしれませんが、代理母がらみで、複数の母親らしき人がいる状態は子の福祉にとって望ましくない、という主張に疑問があったからです。一人の母親に複数の子供がいていいことと、一人の子供に複数の母親がいてはいけないということの価値観の違いは何なんでしょうか。つながりの中身が違うから? そりゃあ、母親同士で現実に子供を奪い合ったりすれば子供にとって迷惑なのは間違いないですが、母親らしき人が複数存在しているというただそれだけで、母親らしき人たちの大半が子供の奪い合いを演じ出すというわけではないでしょう。 実際に、奪い合ったとしても、「奪い合うな」といえばいいのであって「産むな」とまでいわなければならない必要性はどこにあるのか。人工生殖で生まれてきた子が社会的に不利に扱われるのだとすれば、それは人工生殖を社会的によろしくないものだと捉えているせいでもあるわけですよね。 現行法上も養子縁組って制度があるんであって、実親/養親と(つながりの中身が異なる)親らしき人を2種類生じさせることもできるわけですよね。普通養子なら実親との関係も切れないわけだし。何か転縁組(重婚みたいなもの)も禁止されていないようだし。 人工生殖を正面切って肯定することには、私も非常に抵抗がありますが、子供の福祉って何だ、ということをもう少し詰めて考えなければならないんでしょうね。で、子供の福祉の観点からは人工生殖それ自体は問題ない(生まれた後のケアの問題)というのであれば、子供の福祉を持ち出して人工生殖を否定するのではなく、それとは別の理由を持ち出す必要があるんでしょう。
2007年05月12日
コメント(0)
-
賃貸借・保証・相続
不可分債務、保証(債権総論)、賃貸借(契約各論)、債務の相続、遺産分割(相続法)とそれぞれの領域にまたがっているせいで、どこを読めばこういうことが書いてあるのか見つかりません。判例があるところは断片的に記述があるんだけども。 以下、未整理かつ何の解決もできていないので、ちょこちょこ書き加えていくと思います。 A賃貸人 B賃借人 C保証人〈事例1〉1 AB間 土地賃貸借契約2 AC間 保証契約3 Bが死亡しDEが相続・ Bの賃借人の地位はDEに相続される。この時点ではDEの賃借人の債務は不可分債務である(判例)。・ DE間で、DがBの地位を相続するとの遺産分割協議が成立した場合、これをAに対抗できるのか?・ B死亡前に未払賃料があった場合、この債務を賃借人の地位の相続とともにDのみに相続させることができるのか、これをAに対抗できるのか? 逆に未払債務は賃借人の地位と切り離してEに相続させることができるのか? どうせAにとっては誰が賃借人になろうが賃料が現実に入ってこなければ債務不履行解除できるんだから差し支えない、といえそうですが、Aが、とにかく出て行ってもらえればそれでいいと考えているんだったらそういうことでいいんでしょうが、未払賃料が相当な額になっていてこれを回収したいと考えている場合は、未払債務を誰が相続するかは非常な関心事ですよね。 共同賃借人の賃料債務が金銭債務なのに不可分債務であることの趣旨を推し進めれば、そして、金銭債務を特定の相続人に相続させるには免責的債務引受の要件が必要となることからすれば、ここでも同様の要件を必要とすべきでしょうか。ただ、通常の金銭債務の相続の場面では「法定相続分による分割債務か特定人への相続か」という選択肢ですが、この場面では分割債務ではなく「不可分債務」にもなりうるので、通常の金銭債務とは違った判断要素が含まれていることになります。 仮に、債務引受の要件を必要とすべきだとして、これは過去の未払賃料債務の相続だけに要求されるのか、債権債務が一体となった賃借人の地位そのものの相続にも要求すべきなのか。 あれこれ書きましたが、こういう問題はすべて、「相続は賃借権の「譲渡」(民法612条)にあたらないから賃貸人の承諾なく自由に行うことが出来る」という解釈だけで割り切ることができますか(もちろん、そもそも不可分債務か否かという問題は612条では解決できませんが、612条により相続が自由ならば、不可分債務だろうが何だろうが相続人側が自由に結論を左右できるということになって、遺産分割されてしまえば不可分債務か否かを問う実益がなくなるというわけです)。 けど、民法612条は「権利」の譲渡とあって「債務」については明記していないし、譲渡の場合に承諾がいるからって非譲渡の場合にはおよそ承諾がいらないという反対解釈が直ちにでてくるわけではないでしょ。 「A(譲渡)ならばB(要承諾)である」が真だからといって「非Aならば非Bである」が真とは限らないわけです。前件からでてくるのは「非Bならば非Aである(承諾がいらないならば譲渡ではない)」が真だということ。だから、反対解釈が文字通り通用するのは、民法612条から、譲渡にあたらない場合には承諾を要求してはいけない、というところまで規制を及ぼしているという趣旨が読み取れる場合に限られるわけです。でも、そこまでのことは読み取れないでしょう。 というわけで、債務については612条は全く規律していないので通常の債務引受に従うとしたり、権利に伴う債務については賃借人の地位の移転に含まれるが過去の未払債務については相続する権利に伴うものではないので、過去の未払債務の相続は通常の債務引受に従う、という解釈もありうるわけです。 909条を援用して、賃貸人は同条にいう「第三者」に該当しないから相続人は遺産分割を賃貸人に対抗できる、っていうのも同じことでしょ。債務の相続だって、その債務の債権者は「第三者」とはいえないけど、免責的債務引受の要件が要求されるわけだし。〈事例2〉1 AB間 土地賃貸借契約2 AC間 保証契約3 Cが死亡しFGが相続・ Cの保証人の地位はFGに相続される。この場合、FGの債務は不可分債務か可分債務か。ア過去の未払債務、イ将来の賃料債務、ウ賃借物返還債務(これに保証が及ぶことは判例)の(保証債務の)どれかによって区別されるか?・ FG間でFがCの地位を相続するとの遺産分割協議が成立した場合、これをAに対抗できるのか?・ C死亡前に未払賃料があった場合、これを保証人の地位の相続とともにFのみに相続させることができるのか、これをAに対抗できるのか?また、未払債務のみはGに相続させることはできるのか。 主債務の賃料債務が不可分債務となる場合に、これに対する保証債務まで不可分債務になるのかどうか。主債務としてのアイが金銭債務なのに不可分債務とされたとしても、これにあわせて保証債務までもが不可分債務となってしまうのか。 特に〈事例2〉では主債務者はB1人のままなので、現状では主債務の不可分債務性は顕在化していないにもかかわらず、保証債務だけが不可分債務となるのか。まあ、〈事例2〉で「4 Bが死亡しDEが相続」した途端、FG保証債務も不可分債務化するというのもおかしな話なので、FG相続の時点で不可分債務か可分債務かどちらかに決めないといけないんでしょう。 主債務が可分債務なのに保証債務が不可分債務というのは保証債務の附従性に反するからありえないんでしょうけど、それ以外でどうなるかはさっぱり分かりません。 共同賃借人の賃料債務は不可分債務であるという判例、賃貸借の保証債務には賃借物返還債務という性質上の不可分債務が含まれるという判例から、判例のない隙間部分を想像力豊かにうめていくと、賃貸借の保証債務はすべて不可分債務になるような気がしますが、何ら法的根拠はありません。通常の金銭債務が連帯債務だった場合でも、複数人に相続された場合は分割債務になるって判例もあることだし。 遺産分割の問題は〈事例1〉と同様
2007年05月11日
コメント(0)
-
うそでまこと-偽証罪における虚偽性の判断方法
裁判所における事実認定が実体的真実に基づかなければならないことは確かにそのとおりなんですが、だからといって、直ちに、証人に対して「実体的真実を証言しろ」と命令しなければならないとまではいえないと思います。 何が真実かってことは、証人の証言も含め数々の証拠から事後的に裁判官が判断することであって、証人が独自に「真実は何か」を判断した上で証言する必要はないと思います。だから、証人が体験時に「BがAを殺すところを見た」と認識したが、事件後の報道や周囲の人の話を聞いていると、どうやらCが犯人だというのが真実に間違いないと確信するにいたった(で、後日裁判官により実体的真実はCが犯人と判断された)としても、証人としては「Bが殺した」と証言すればいいのだと思います。 証人に対して「証言時までの経験に基づいて真実だと考えられることを証言せよ」と命令するのは証人に酷でしょう。「実体的真実を証言しろ」と命令されれば、体験時以降の経験までもを考慮した上で証言しなければならなくなりますが、それは証人にとって過度の負担であって、あくまでも体験時に経験したことだけに基づいて証言すればよい、としておくのが穏当だと思います。 そもそも、実体的真実というもの自体が、その証言も含めた上で判断するものであって、証言の内容により、裁判官が判断する実体的真実も変わってきてしまいます。実体的真実は証言とは独立して存在しているわけではありません。だから、証言が、結果的に裁判官が実体的真実と判断したものと一致していたとしても、本当の真実に合致しているとは限りません。もしかしたら、本当の真実は「Cが犯人」なのに、その証言(「Aが犯人」)の影響で裁判官は「Aが犯人」が実体的真実だと誤って判断しているのかもしれません。 司法作用に対する侵害というのを事後的に判断しようとすると、すでに侵害されていることに気づくことができない場合があるわけです。私も、客観と主観をきちんと区別することが必要だとは思っていますが、体験に反する証言(主観)が裁判の結果(客観)そのものに直接影響を及ぼしてしまうことから、ここではそんなことも言ってられないんじゃないかと思うわけです。 通常の場面では主観が客観に影響を及ぼすことはないとされていますが(例外は主観的違法要素)、偽証罪においては、主観が結果的に客観と一致していたとしても、実は客観のほうが主観に合わせられている可能性もあるわけです。複数の証人が一致団結して記憶に反する証言をして真実を塗りつぶすことに成功すれば適法になるような制度でいいのかどうか。こういう事案のほうが司法作用に対する侵害度が高いんじゃないですか(これは、偽証罪裁判においては当該証言を除外して真実性を判断することにより解決できる問題ですか)。 このことは、偽造罪における「行使の目的」などの一般的な主観的違法要素のように、客観に付け加わることで法益侵害性が高まる、というのともやや性質が異なるわけです。本来あるはずの法益侵害性(客観)が、主観によりなかったことになってしまうことがあるということです。だから、まずは客観から、とみてみたら客観がないってことで偽証罪不成立としてしまうのは早計ではないかと。結果的に客観に一致していれば不可罰とするのは、結果的に死んで無いんだから死ぬ可能性はなかったということで未遂処罰をおよそ否定するかのような印象があります。 ということで、偽証罪の行為規範としては、証人に対して「とにかく自分の認識だけを証言しろ。それが間違いかどうかは裁判所が判断するから余計な気を回すな」という内容にしておくことが望ましいんじゃないでしょうか。裁判における真実性を高めるという目的をそのままの形で証人に押しつけるのではなく、証人は自分の体験したことをそのまま話してくださいとしたほうが、その目的をよりよく実現できるのではないでしょうか。 もちろん、実際の証人尋問は抽象的な聞き方をするわけではないので、個々の尋問との相対的な関係で、何を聞いているかによってその虚偽性が判断されることになるんでしょうけど。(証人が体験したのは「BがAを殺したのを見た」だったとして)質問1 Aをナイフで刺していたのは誰に見えましたか。質問2 その認識は今でも間違いないと確信していますか。 質問1は体験当時の認識、質問2は証言時の認識を聞いているのであるから、証人としては、それぞれの時点の認識と一致した証言をすればいいわけです。 質問1に対して「私が見たのはBに間違いないですが、その後いろいろ話を聞いているうちに、実はCが犯人ではないかと思うようになりました」というのは、余計なことをしゃべりすぎではありますが、これは虚偽ではないでしょう。 他方、質問1に対していきなり「Cに見えました」というのは、(仮に事後的に裁判官が当該訴訟で「Cが犯人」を実体的真実だと判断したとしても)虚偽なんじゃないかと。Bに見えたという当該証人が存在することも含めて、裁判官は何が真実かを判断すればいいのであり、証人に対して「真実を証言しろ」と命令することで、当該証人の体験したことをわざわざねじ曲げさせる必要はないでしょう。 当時の体験という主観を立証することが難しいってのは、主観一般にあてはまることであって、たとえば、故意の立証が難しいからといって主要事実そのものを客観的なものに代替させることは、少なくとも、現行法上は採用されていない立場でしょう(客観的事実はあくまで故意を立証するための間接事実にとどまる)。 客観的な真実とされるものと人の認識との関係とか、哲学チックなことをもう少し勉強する必要がありそう。 たとえば、そもそも、「真実を言え」という命令と「記憶を言え」という命令は、同一人物内において異なった内容となるのかどうか。おなじだとすれば、主観説でも客観説でも(違法性によるか責任によるか理由付けは異なるものの)結論に差がでなくなるはずです。 内容が別だということで主観説と客観説とで対立しているというのは、あくまで特定の立場(人は自己が直接体験したこととは違う事実を真実と認識することができる)を共有した中での対立にすぎないということです。たとえば、人の主観の中で「体験=真実」ならば、体験をそのまま証言したが、客観的には「体験≠真実」であった場合、主観説なら違法性がなく、他方、客観説でも「体験=真実」に反するという認識がないから、故意がなくなるわけです。人の主観の中でも「体験≠真実」という心理状態があり得ると考えて初めて、主観説と客観説とが対立することができるわけです。 林美月子先生の『偽証罪小論』をよく理解できないまま読んでみて思ったことを書いてみました。なお、林先生自身は客観説を採用されています。
2007年05月10日
コメント(2)
-
大学法学部の論文集
CiNiiで無料公開されている大学の論文集のリンクをブックマークにのせてみました。ただ並べてみただけです。
2007年05月09日
コメント(0)
-

山口厚『刑法総論 第2版』
数年前に初版を1、2回読んだきりなので、どこがどう変わったのかは具体的にはいえません。ただ、印象としては、ずいぶん読みやすくなったと感じました。頁数がかなり増えているので、初版より言葉をつくして書いてくれているんだと思います。中身には触れず、形式的なことをいえば、この本、 1 本文 2 括弧内の文 3 注の文と3階層あるんで、理想的には、内容の重要性にあわせて1>2>3となっているのがいいんでしょうが、2や3の中にも、(具体例とか補足にとどまらない)1と同じくらい重みのある文章が紛れているような気がします(たとえば○○頁の記述、とか具体的に指摘できればいいんですけど、一通り読んだ後の印象なのでどこだったか分からなくなってしまいました。以下、その程度の印象論として)。 だから、時間がないときとかに2・3をとばして本文だけ読んでおこう、という読み方がやりにくくなっています。大丈夫、そういうときはこちらの本(『刑法』)を買ってくれればいいから、ということでしょうか。まあ、重要か重要でないかを自分で判断しないといけないというのは、むしろいいことなのかもしれません。 あと、括弧内の文には、おそらく他説からのありうべき批判を先取りして自説の補足をしているところがあるんですが、どういう批判が想定されているのか明示されていなかったりするので、どうしてそういう補足をしているのが十分理解できないものもあります。 もう一度じっくり読むことがあれば、どこがどうなのか具体的に指摘したいと思います。 ちなみに、この本の構成要素としては、(一般的な説明を除いては)「判例、従来の学説、山口説、「若干の」最近の学説(順不同)」という感じなので、最近の学説を教科書レベルで読みたいかたには『アクチュアル刑法総論』のほうをおすすめしておきます。 や、もちろん、最近の学説がそれほど載っていないことが悪いというのではありませんよ。刑法総論の基礎を押さえることがこの本の目的だろうし、山口先生自身『問題探究刑法総論』という本を出してくれているところだし。でも、『問題探究』のほうももっと言葉を尽くして説明してくれると、わたしのような普通人にとってありがたいですけどね。 さらにわがままをいえば、「序章」として刑法解釈の総論というか山口先生が個々の解釈を生み出す前提としてどういうことを考えているのか、みたいなことを書いてくれるとうれしいんですけども。 法益保護主義・責任主義などという原理を共有する人たちの間でも個々の解釈論が分かれるってのは、それら原理と解釈論との間にある何物かが、それぞれの論者によって違うからなんでしょうが(もちろん原理自体の理解の相違にもよるのでしょうが)、その何物かを明示してほしいなってことです。本書全体から読み取りなさい、と言われてしまいますか。山口厚先生の著作刑法総論 第2版刑法各論 補訂版刑法問題探究 刑法総論問題探究 刑法各論新判例から見た刑法判例刑法総論 第4版判例刑法各論 第4版ケース&プロブレム刑法総論ケース&プロブレム刑法各論クローズアップ刑法総論理論刑法学の最前線理論刑法学の最前線2刑法の争点 第3版危険犯の研究
2007年05月08日
コメント(2)
-
会社は商人ですか。
先日、岡口裁判官のブログ(ボツネタ)で、会社が商人かどうか、という点が議論になっていました。(以下、便宜的に「事業(営業)として」とかそういうのを省略して「会社の行為は商行為」みたいに記述します) 私も以前、これにやや関連したことについて疑問に思ったので葉玉先生のブログ(会社法であそぼ。)に質問コメントをして回答をいただいたのですが、移転前のものなので今は閲覧できませんでした。 うろ覚えですが、質問の内容は、『論点解説新・会社法 千問の道標』のQ11(11頁)に、会社には「商人」であることが適用の要件となっている規定が適用されるとあって、この記述が、商法4条を適用するまでもなく、という趣旨なのかどうかが不明だったので、このへんどうなんですか、というものだったと思います。 で、葉玉先生の回答は、葉玉先生自身は商法4条の適用が必要と考えているがグループ内では会社は当然に商人だという意見が有力だったのでそういう回答になった、とのことだったと思います。 そもそも千問のQ11って「会社は、商人か。」って質問なのに、A(回答)には「商人です」とも「商人ではありません」とも明確に書いてなくって、問に答えていない不出来な回答なんですよね。「実益のない質問にはおよそ答えません」というある種の潔癖症なんでしょうか。 まあ、会社法が「第1編 総則」てのをつくって商法「第1編 総則」からの独り立ちをはかったことからすれば、「やっぱ商法4条だけは適用させて」なんて未練がましいことは認めたくないんでしょうね。これもある種の潔癖症みたいな。 でも、たとえば、商法512条みたいに、商行為ではなく商人かどうかで適用を決めている条項を、商法4条を無視して会社に適用するって、法解釈としては不自然だよね。 商法512条を適用するには会社が商人かどうかを決めなければならない、で、会社法の規定をみても、会社法5条には会社の行為は「商行為」だってことは書いてあるけど会社が「商人」かどうかは書いてない、だから会社法上は会社が「商人」かどうかは不明だと、で、商法4条を見てみると、自分の名前で「商行為」をやってれば「商人」だって書いてある、そうすると、会社法5条→商法4条により会社が「商人」だってことが決まり、めでたく商法512条が適用されることになると。条文解釈としては、これが自然な流れだと思うんです。 立法担当者の思惑とすれば、やっぱし、商法第2編以下は会社に適用されるが、同法第1編はおよそ会社には適用されない、て立場なんですかね。で、「会社は商人である」あるいは「会社が商人かどうかは知らないが商法512条とかは当然会社に適用されるぞ」という条理的なものを、会社法5条の行間あるいは俺たちが作った会社法全体の雰囲気から感じ取れってことですか。一心不乱に会社法を熟読玩味するうちに「あ、会社は商人だ」と突然悟ることができますか。 私が会社法から受ける印象は(解釈の余地を残すとかそういうことはしないで)「とにかく書いてしまえ」というものだったんですが(意味の分からないお経よりも、直接教えを書き込んじゃえば効率的じゃねえ的な)、「会社は商人である」と書かなかったのは、何かこれとは逆方向ですよね。 ちなみに、会社法5条と商法503条を並べてみても、「会社は商人である」という回答は、(すくなくとも論理的には)でてきません。 会社法5条 Aの行為は商行為 商法503条 Bの行為は商行為 結論 AはBであるというのは偽でしょ。 会社法の条文はパズルだと形容したのは神田秀樹先生の新書(『会社法入門』)だったかどうか忘れてしまいましたが、この問題(商人規定との接合部分)に関しては、なぜかピースが欠けているわけです。こんなとこ空けておく必要ないだろうに。○会社法第5条(商行為) 会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。○商法第4条(定義) 1 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。 2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 第503条(附属的商行為)1 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。 2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。第512条(報酬請求権) 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
2007年05月07日
コメント(0)
-
『書斎の窓』564号(2007.5月号)
以前の日記で紹介した辰井聡子先生の『因果関係論』について、小林憲太郎先生が書評を書かれています。「名著者=名書評者」といった感じのいい書評。最上級でほめているようで、それと同じくらい、けなしているように読めるのは気のせいですか。内容についてはご自分でお読みくださいとしかいえませんが、まさにその通りと思える一文があったので引用。ただし、これは辰井先生の本だけに向けての物言いではありません。「下位基準と称して論証なしに、共通了解なき新基準をあたかも上位基準から演繹されるかのごとく、提示するのはこの業界のならわしだからである。」「この業界」というのは刑法学者の世界ということでしょう。で、このならわしを「悪習」だとされています。いや、まさにその通りだと思います。小林憲太郎先生の著書刑法的帰責因果関係と客観的帰属アクチュアル刑法各論アクチュアル刑法総論ケース&プロブレム刑法総論リーガルクエスト刑法各論
2007年05月01日
コメント(0)
-
法学教室
【定期購読1年(12冊)】法学教室最近の法学教室はまじめな論文が多くて、おもしろおかしく読めないのが残念。「法学セミナー」との棲み分けですか。最近の遊びの部分としてはせいぜい、4・5月号の2号もつかって、松尾浩也先生の生い立ちから大学入試までを載っけているところぐらいですか。あまりに個人的な内容ですけど。
2007年04月27日
コメント(0)
-
九州大学学術情報リポジトリ
九州大学学術情報リポジトリ九大の論文が読めます。法学関係はこちら。「法政研究」手島孝先生(行政法、憲法)、伊藤昌司先生(民法)、大橋洋一先生(行政法)あたりの論文を読んでみたいと思います。ちなみに、伊藤先生の「実親子法解釈学への疑問」て論文はこの日記(大人たちの利害と子の福祉-代理母の諸問題 )に、「『相続させる』遺言は遺贈と異なる財産処分であるか」て論文は、この日記(夢がかなうと迷惑がかかる人もいる-相続させる遺言の謎 )に、直接は関係ないですが、「法の適用に関する通則法」にいう「関する」ぐらいには関係してそうなので(法の適用に関する通則法・・ )、そのうち読んでみます。
2007年04月19日
コメント(2)
-
大人たちの利害と子の福祉-代理母の諸問題
外国判決の承認という形で代理母問題を扱った最高裁平成19年3月23日決定に絡めて、その辺の問題をあれこれ論じてみたいのですが、さしあたり印象のみ。(以下、「代理母」については依頼女性が卵子を提供するタイプ(依頼女性=卵子提供者)を前提にします)・結論自体は最高裁に同意できますが、身分関係は「身分法秩序の根幹をなす基本原則ないし基本理念にかかわるもの」であるにもかかわらず、親子関係がどういう場合に成立するのか直接明記した規定がないってのはどうかと思います。これは最高裁決定の問題ではなく法律の問題。・「分娩者=母」ルールは、法律に明記されたルールではなく、判例が作り出したルールにすぎないわけですよね。だからこのルール、国民の合意に基づいてできあがったものじゃないわけです。そして、決定ではこのルールの根拠としては一義的に明確な基準だからだとされています。そうだとすると、1親子関係は遺伝子により判定する、2母子関係はわざわざDNA鑑定をしないでも分娩によりこれを推定する、3父子関係は婚姻中に懐胎したらこれを推定する(772条1項)、というルールでも別に不明確じゃないし、現行法にも反しないから、採用可能なルールですよね。にもかかわらず、現行の「分娩者=母」ルールを維持するってのを、単に明確性というだけで理由付けるのは不十分でしょう。これまでのルールを変えたくない、かえるなら立法でお願いします、てことか、あるいは、代理母ビジネスに与えるよろしくない影響を鑑みたか、倫理の問題があるからか、いずれにしても別の理由付けが必要なはずです。しかも、本件ではあくまで外国判決の承認ルートにおける公序要件の問題であって、日本法(というか判例法)のルールを変更せよ、といってるわけじゃないから、単に明確性というだけで、裁判所でつくった「分娩者=母」ルールが日本の公序の根幹をなすことの理由として十分かも疑問です。最高裁は、立法におまかせします的なことを言っていますが、立法で変更できる程度のルールが公序といえるのかどうか。複数のルールを認めるならば、一義的でもなくなりますし。私としては、「分娩者=母」ルールそれ自体を公序の内容とするのではなく、なんら法規制がない状態で代理母を認めてしまうことが日本社会として耐えられるのか、あるいは、子の側からみて分娩者との親子関係を断絶されてしまうことが許されるのか、という観点から公序の内容を構成すべきだと思っています。・親子関係の成否が分娩という事実により決定されるとするならば、認知とか親子関係存在がらみの裁判でDNA鑑定をやってることは何なんでしょう。父子関係は遺伝子、母子関係は分娩による、てことなんでしょうか。捨て子が母子関係存在確認の裁判を起こした場合、子が証明しなければならないのは、分娩という事実であって遺伝的なつながりではないってことでいいんですか。遺伝的なつながりが証明できてもそれだけで親子関係が証明されるのではなく、遺伝的なつながりがあれば通常分娩もしてるだろうという事実上の推定がなされるというだけなのか。これにあわせて父子関係についても、遺伝的なつながりがあるだけでは足りず、自然生殖によるものだとの証明をしなければならないのか。このへんは要件事実が何かという問題でもあります。私には、遺伝子的なつながりが主要事実であり分娩はこれを立証するための間接事実だと思えるのですが、最高裁の立場は分娩自体が主要事実だということのようです。・とにかく実子じゃなきゃいやだっていうのは養子は実子よりも下だということ?・「分娩者=母」ルールを壊して実子を拡げるというやり方と、養子縁組を手続がしやすいように整備しつつ養子を法的にも社会的にも実子と同等にしていくやり方とで、子の福祉に何か違いがあるか。・例の件では、代理母契約の問題で養子縁組できないとのことのようですが、日本じゃ代理母が認められないってことを知ってたなら、契約締結のときに「もし日本で母子関係が認められなかったら養子縁組に協力してね」って条項を入れることもできたはず。それをしないでおいて、母子関係が認められないと子の福祉が害される、っていうのは、子を自ら危険に晒しておいて他人に助けなさいと言ってるようなものでしょ。本当に子供のためを思うなら、事前に養子縁組ルートを確保しておくべきなのに、とにかく実子がいいという大人側の理屈でそれを閉ざしちゃったと。将来の問題解決のために自分の子供を犠牲にするのはあまり褒められたものではないでしょ。ルールは守らなきゃいけないとも言っているようですが、なんでネバダ州のルールを絶対視する一方で日本のルールは守ろうとしないんでしょう。一次的には代理母ルートを望むにしても、それがだめだった場合に、日本のルールの中で最大限子供の福祉を確保できる手段をあらかじめ考えておく必要があったんじゃないですか。将来、子が日本の裁判所で代理母に対して扶養請求をしたとしたら、ネバダ州の裁判は通則法上の公序ルートで排除されて代理母が子の母親とされる可能性が高いから、特別養子縁組を結んであげることのほうが代理母のためになるし(裁判管轄や執行の問題はありますが)。というか、縁組しないことのほうが契約違反となりそうで心配。・代理母を認めるということは、子の側からみると、母となりうる者が複数いるにもかかわらず、子の意思を無視して一方的に分娩者との関係を断ち切ってしまうわけですよね(逆に、「分娩者=母」ルールを維持するということは、分娩者以外の者との関係を断ち切ってしまう)。代理母を認めないことは自分の子供が欲しいという女性の権利を侵害している、といわれますが、逆に、代理母を認めることは自分を産んでくれた人とのつながりを維持したいという子供の権利を侵害しているわけです。分娩者が法的には実親とされていなくても出産してくれたという事実は消えないから何ら子供の権利は侵害していない、なんていうのであれば、卵子提供者が法的には実親とされていなくても遺伝的につながっているという事実は消えないから何ら女性の権利は侵害していない、ということもできますよね。代理母・依頼者間の決めごとを、生まれてきた子供に押しつけてもいいのかどうか。そういう意味で、私は、代理母と子との関係を完全に断ち切ってしまう本件代理母契約は、分娩者と子との関係を保障している日本のルールからは受け入れないと考えています。いずれにしても、大人の事情だけで代理母の是非を論ずるというのは、本当に大切なことを脱落させているということです。・養子縁組というのは、実親/養親と、親と呼ばれる人を2種類作り出す制度なわけです。人工生殖についても、現行の実子ルールに押し込めて、とにかくいずれか一方だけを母親とし他方を全くの他人と決めてしまうのではなく、(両者間に優劣があるとしても)なにがしかの形で両者とも親的なものであるような制度をつくるのもありなんじゃないかと思っています。・実子か養子かなんて、所詮国が作った制度内での人為的な取り決めなんだから、そこまで制度上の実子にこだわる必要があるかは疑問。だけども、まったく同じ理由で「分娩者=母」ルールにこだわる必要があるのかも疑問。・代理母を禁止したいからといって、それによって生まれた子を依頼女性の実子とは認めないという手段によって抑止するのは、非嫡出子の相続分を差別するのと同じ、大人の不始末を子に償わせることになって最悪のやり方ですよね。だから、代理母を認めるかどうかということと実子ルールをどうするかということは、区別して考えるべきでしょう。代理母は社会的に受け入れられないとして依頼者・代理母や実施機関にペナルティを課すとしても、誰を実親とすべきかは、一般的にみて誰との間に親子関係から生ずる権利義務を発生させることがよいか、という観点から決めるべきでしょう。で、どちらかを実親とすると制度決定したとしても、個別具体的な事情により子の福祉にかなわない場合のために、全くの他人を養子縁組する場合とは異なった規律によって養子縁組的な制度を用意すべき、だと考えています。大人の事情と子供の福祉を区別しなきゃいけないというのは「赤ちゃんポスト」問題もおんなしような話で、無責任に子供をつくることを防ぐことで不幸な子供が生まれてくることを減らす一方で、できてしまった子供を救うことで現に不幸な子供を減らさなきゃいけないってことです。一般予防効果を弱めたくないからといって、そのために、現実に生まれてきてしまった子供を犠牲にするわけにはいかないでしょう。どういう立場をとるにしても、大人の側の事情で子供を不幸にするのはやめてほしい。子供は大人のための道具ではありません。
2007年04月16日
コメント(0)
-
夢がかなうと迷惑がかかる人もいる-相続させる遺言の謎
「相続させる」遺言って、特定の相続人に特定の財産をあげたいな、というどこかの誰かが空想したことが現実化しちゃったようなもんですよね。で、法律上存在しない制度なのに、ご都合主義的に生み出されて、なんか後付けでいろんなものがくっついていってる感じ。にもかかわらず、判例では「もともとそういうものですよ」と、なんかはじめから決まっていたかのように押しつけてくるみたいな。東京高裁平成18年6月29日判決ってのがあって、事案を極めて簡略化して言うと、 1甲の遺言 乙に財産Aを相続させる 2乙死亡 3甲死亡という場合、相続させる遺言に代襲相続が適用されて、乙の相続人丙が甲の遺言に基づいて財産Aを相続できるのかって話。判決は、丙は相続できると、で、この帰結は、代襲相続制度の趣旨にも相続人間の衡平にも被相続人の意思にもかなうんだと。ここまで強気で言っておきながら、その後に「念のために」とかいって、この帰結が実際の甲の意思に反しないかを検討しているのはなんかおちゃめではあります。ただ、判決では「特段の事情のない限り」相続できるとか、逃げ道をつくってないのに、実際の意思を確認するってのは無意味ではありますけど。強気な規範を立ち上げて無闇に下級審を拘束しつつ、自分は逃げをうってるってわけじゃあないでしょうが。判決の理由を略述すると、・相続させる遺言は遺産分割方法の指定。これによる相続は法定相続分による相続と同じ。だから相続させる遺言にも代襲相続が適用ないし準用される。・遺贈の場合は、遺贈者・受贈者間の特別な関係を基礎とするから、受贈者が死亡した場合は遺贈の効力を失うとするのが遺贈者(被相続人)の意思にかなう(のでそういう条文がある)。他方、遺産分割方法の指定の場合は、相続だから代襲相続を認めることが代襲相続制度の趣旨にも相続人間の衡平にも被相続人の意思にもかなう。「誰々の意思」ってのは判例上往々にしてフィクションの要素がふくまれているのですが、ここでもその手の違和感を感じます。相続させる遺言→遺産分割方法の指定≒法定相続分による相続(not遺贈)→代襲相続適用・準用という性質論から理由づけをするのは、法解釈の一側面なのでそれ自体はいいのですが、この帰結が相続人間の衡平とか被相続人の意思にかなうっていうのが、どっからでてくるのかが不明なわけです。特に被相続人の意思にかなうとする点は非常に疑問。裁判になってるくらいだからこの問題争いがあったわけで、この判決がでるまではどっちになるか(専門家レベルでも)判断が分かれていたはずです。だから、相続させるってかいてあるだけでは、意思にかなってるかどうか分かるはずないでしょ。にもかかわらず、性質論のみから、被相続人の意思にかなうと結論づけるのはいいすぎでしょう。判決自身が(なぜか知らないけど)検討しているように、個別の被相続人の意思をみてはじめて意思にかなっているかどうかが分かるはずです。で、この判決(あるいは最高裁判決)が一般に広まるようになって、「相続させる遺言には代襲相続が適用される」というルールが確立してはじめて、一般論として、「相続させる」と書いた以上は代襲相続させるつもりだったはず、といえるはずです。この事件、上告受理申立中みたいですが、最高裁がでるまでに遺言を書こうとする人はどうしたらいいんでしょう。たとえば、乙が死んでても丙に遺産をあげたい場合、この判決を信じて「乙に相続させる」とだけ書いとけばいいのか、この判決がひっくりかえる可能性を考えて、「乙に相続させる。ただし相続時に乙死亡の場合は丙に遺贈する」と書いておいたほうがいいのか。後者のように書いておいたら、最高裁でも代襲相続されると判断された場合、代襲相続権と遺贈権はどっちが優先するのか。遺贈を放棄して代襲相続でいけばいいのか。すでに遺言を書いちゃった人も、場合によっては遺言を書き換えないと、裁判所に勝手に代襲相続させることがお前の意思にかなうだろ、と決めつけられちゃいますよ。この問題、どっちが正しいか、というよりも、あらかじめどっちかに決めておいてください、という調整問題にすぎないっぽい。政策的には、遺贈ルールでは効力を失うので、「相続させる」のほうでは代襲相続すると違いを設けた方がいいんでしょうが、遺贈ルールの脱法を裁判所が追認している感じがしてしょうがない。解釈論の限界を超えてますよね。で、最初に書いたとおり、相続させる遺言なんて所詮空想の産物だから、結論はどっちでもいいし、ルールがどっちかに決まってくれればそれにあわせて遺言を書けばいいだけなんですけど、高裁判決の理由付けだけはどうしても納得いきません。代襲相続が被相続人からの直接相続だということと、相続させる遺言に代襲相続が適用・準用されることとがどうつながってんの?とか、短い理由付けの中にいろいろ問題あり。余裕があれば、そのうち判決文を引用して検討してみます。
2007年04月13日
コメント(0)
-
余計なことをしなければ消費者問題は生じない?-出版不況と法律書
最近になってからなのかどうか知りませんが、法律書のまえがきとかあとがきに、「出版事情の厳しいおり」こんな本を出版して頂いてありがとう、的なことが書いてあるのを見かけます。本が売れないのは景気のせいあるいは消費者のせいみたいな書き方なんですが、私としては、常日頃から宣伝不足じゃないのと感じています。以下、法律書にかぎったお話。私は、定期的に法律書を買わないとどうかしてしまうタイプの人間なんですが、そんな私でも、すんなり買えるわけではありません。一部の「著者買い」ができる本を除いては、その本がどういう内容かを知らなければ買いにくいわけです。で、内容を知ろうと思っても、売れない本ほど近くの本屋には置いていないという相関関係がありますので、大きな本屋にいかなければなりません。また、中身をみたところで、電気屋で説明書をみないで展示品の家電をつかってみるごとく、一応分かるには分かるが、ものによっては、その本の本当のよさがその場で中身を読むだけでは分かるとは限りません。で、何某かのガイド的なものがないか出版社のサイトをみてみても、目次とありきたりの紹介文が載っているだけで、それを見て買おうという気にはなれないのがほとんど。ごくごく少数だけの立ち読みコーナーがあったりもしますが、(当然といえば当然ですが)中身がそのまま数頁見られるだけです。デザインとかに気を遣うくらいなら、もっとテキストを充実させてください、と思うものです。書店に本を置かせてもらえない力の弱い出版社ほどサイトを充実させるべきだと思うのですが、全然手が回っていない感じ。新刊がでたときぐらい更新すればいいのに、それさえしてないとか。有斐閣のPR誌「書斎の窓」には、たまに「○○を刊行して」みたいな、著者自身がその本について語る文章が載っていて、これはとてもいいものなんですが、数としては少ないし、書斎の窓自体がお気軽に手に入るものではありません。別に宣伝といっても大金かけてCMをしろとかそういうことを言っているわけではなく、編集者による編集にあたってのあれやこれやの話や著者自身による「○○を刊行して」みたいな文章をサイトにのせるだけでいいわけです。著者も、出版してくれてありがとう、とかいうなら、売れるように努力しなさいよ、と思うのですが、学者的には、一般の人に向けて売っているつもりはない、とでもいうつもりなんですかね。以上、出版事情をしらない一読者の意見でした。出版社には出版社の事情があるのでしょうが、(他の人と比べたらそれなりに法律書出版社の売上に貢献しているはずの)消費者からみるとそう感じました、ということです。自画自賛なだけの宣伝になっても、それはそれで一つの判断材料になるわけだし。
2007年04月06日
コメント(0)
-
渉外的親族相盗例?
刑法244条1項の「配偶者」に該当するかどうかについて、外国人の場合はどうやって判断するんですか。刑法は公法だからという素朴な理由で、抵触法ルートを通らずに独自に判断していいんですか。以前もこの類の話をしましたが、別の例ってことで。以下、私法と民法、国際私法と抵触法を互換的に用います。あと、裁判管轄は日本にあるって前提で。刑法は幸か不幸か属地主義だから、日本で行為したと設定するだけで管轄ありになりますし。・独自に判断できれば抵触法的判断をしなくていいから楽だ、となるのかもしれませんが、独自に判断するにしてもいったい何を手がかりにすればいいんですか。たとえば、ともにA国を本国とする甲男・乙女が、A国での実質的要件を満たした上で、B国でB国上の方式に従った婚姻の届出をし受理された、その後、日本に入国し、甲が乙のお金を盗んだ、という場合に、もし抵触法ルートで判断するならば、日本の国際私法によれば、乙は甲の「配偶者」となり、親族相盗例は適用されるという結論になりそうです。抵触法ルートに忠実に従うなら、どうやって判断したらいいかは明確なわけです。これを刑法独自の判断でやれ、となったらどうすればいいのか。日本の刑法(判例)上、配偶者に「内縁関係」は含まれない、とされていますので、要するに、婚姻の実質的要件と形式的要件の双方を満たしていないといけない、ということなんでしょう(ただし、実質的要件、形式的要件という言葉自体私法上の概念の借用であって、婚姻と内縁を分けるのも刑法独自の考えではない)。この議論、外国人犯罪の場合の配偶者判断はどうすんの、ということなんかはおよそ考えないで、あくまで国内的な事情だけで争われているんでしょうから、そのままここにもってくるわけにはいかないんでしょうが、その点は置いとくと。で、両要件を満たさなきゃいけないとして、外国人の場合は何国法上の実質的要件と形式的要件を満たさなきゃいけないことになるのか。まさかどっちも「日本の」なんてことはないんでしょうが、どうにも雲をつかむような話です。また、何某かの刑法独自の判断をしたとして、日本の抵触法に従えば(成立・方式につき送致される準拠実質法に従い)両要件を満たし婚姻は有効でだったはずなのに、日本の刑法上は婚姻は無効だというように、結論を異にする場合があってもいいのか。私としては、「配偶者」のような明らかに私法上の概念を借用している用語については、あくまでも抵触法ルートで判断しなければならないんだろう、と思います。こうなると「できるだけ日本法で」を望むのが法務省だけでなく、捜査機関もそうなってしまうかも。密接関係地法の原則から離れていく要因として、戸籍実務上の都合だけでなく、刑事実務上の都合が加わるってこと。○ついでにいえば、「民法と刑法」として論じられているものも、私法上の概念を借用している場合には当該私法に従って判断しなければならないと思います。とはいえ、あくまでもそれは「実体法」としての民法にあわせるということであって、仮に民事裁判でも同じ事実が争われていても、刑事裁判では刑事裁判の手続に乗っかって、民法上の要件を検討すればいいということです。また、民法学上、ある論点につきA説・B説と解釈が分かれている場合でも、刑事裁判では裁判官が民法学説上存在しないC説をとったからといって、それが法解釈として成り立つものであれば、何ら責められる理由とはならないはずです。ただ、C説が最高裁判例に反していれば上告理由にはなるってだけです。ちなみに、ここでいう最高裁判例は、民事判例でも刑事判例でもそれ以外でもかまわないはずです。民事事件では民事判例だけに、刑事事件では刑事判例だけに、それぞれ拘束されるなんて変でしょ。事実上、民事事件で刑事判例に違反するってことがあんましないんでしょうけど。・ただ、たとえば、財産罪の保護法益に関する議論(本権説×占有説×その他)なんかは、ここでいったことだけでは解決できないんですよね。私が、「私法上の概念を借用している場合」と控えめに言っているのは、たとえば、刑法235条にいう「財物」みたいに、私法上の概念の借用とはいえないものをどう判断するかが、決めがたいからです。占有説という名付けられた説も、そこでいう「占有」を私法上の概念に完全に一致させる説から刑法上の占有という概念を生み出す説まであるわけです。他方、本権説だって、私法上の本権と完全に一致させる説から刑法上の本権なる概念を生み出す説まであるわけです。図式的に言えば、横軸に占有説と本権説があり、縦軸に刑法独自説と民法従属説があるということ。で、ものによっては「配偶者」のようないかにも借用しました的な用語とは事情が違ってくるんじゃないかと。これをさらに進めてしまうと、「配偶者」概念についても、内縁関係は含まれないなどと、私法上の形式的要件を満たすかどうかという私法上の概念に引っ張られた結論をとるのではなく、刑法独自の観点から判断することで内縁関係も配偶者に含めることができる、という方向にすすむということもありうるでしょう。で、この裏返しで、形式的に結婚していても、偽装だったりとか、あるいは、婚姻関係が破綻している(が離婚届はまだ出していない)場合には、「配偶者」に該当しない、ということにもなるんじゃないかと。というか、ある場面では刑法独自の云々、といっておきながら、244条の「配偶者」には内縁は含まないと私法上の概念に引っ張られた見解をとるのは、一貫しないよね。婚姻届を出すか出さないかで区別することが、刑法独自の観点からみてどういう意味があるのか。「いかにも借用説」で「配偶者」は違う、というしかないですか。極めて頼りないけど。○このへん話は、不作為犯における作為義務の発生根拠についても若干かかわっていそう。つまり、形式的に結婚しているってだけで作為義務が発生するのではなく、当該作為義務を負担させるだけの実質的な夫婦関係がなきゃいけない、逆に、形式的に結婚してなくても、実質的な夫婦関係があればいいと。これによれば、もはや形式的な婚姻というのが作為義務発生にとってほとんど意味をなさないということになるわけです。他にありうる考えとしては、少なくとも形式的な婚姻を必要とした上で、これにプラスして実質的な夫婦関係を必要とするか。244条の「配偶者」を形式的に判断する見解からすれば、こっちの説のほうが整合的でしょうが、たぶん、場面が違うって理由でそういう整合性は無視されるんでしょう。内縁で一切不作為犯が成立しないのはおかしいし。刑法総論上は、単に、作為義務発生の根拠を形式的に判断するか実質的に判断するか、と二者択一で論じられていますが、私法とのつながり重視しつつ刑法独自の不法性をも重視するならば、形式的かつ実質的に判断するという見解もありうるわけです。ここでは、刑法総論上の議論にあわせて、形式的/実質的といいましたが、これは不正確でしょう。つまり、法令や法律行為により作為義務の有無を判断する説を「形式説」と呼びがちですが、民法上も「形式的要件」と「実質的要件」があるのであって、決して形式的要件だけで判断しているわけではありません。ことの中身からすれば「民法だけで判断する説」ということになるんでしょう。他方で、実質的に判断する説のことを「刑法だけで判断する説」、形式的かつ実質的に判断する説を「民法と刑法で判断する説」ということになりますよね。上の例で両方を要求する説(民法だけで判断する説も同じ)が不当な見解となったのは、形式説という名前に惑わされて、婚姻の形式的要件を満たさない内縁では作為義務の根拠とならない、と勘違いしたからです。内縁も、条文に書いてないってだけで、その存在は認められているから、いわゆる形式説であっても、ちゃんと作為義務の根拠となりうるわけです。・このことからすると、244条の「配偶者」につき私法上の概念に従うからといって、当然のごとく内縁関係をここから排除していいとはいえないんじゃないか、となってくるわけです。つまり、私法上の解釈として、一定範囲で内縁者に婚姻者と同じ地位を保障するのであれば、当該場面では内縁者も「配偶者」と呼びうるわけです。だから、私法上の「配偶者」には場合によって内縁者も含む、のであれば、それを借用した244条にも内縁者を含めてもよい場合がある、ということになるのではないかということです。○不作為犯の話になりましたが、ここで抵触法上の議論に戻ると、C国人親子甲乙について、甲が乙を保護しないってことで不保護罪(刑法218条)が問題となった場合、本国法であるA国法が、親は子を育てる義務がおよそなく族長のみがその義務を負う、みたいな法だったらどうするのか。本国法なんか無視しちゃって、日本の刑法独自の判断で甲に作為義務をおわせちゃっていいのか(条文上は「保護する責任のある者」とする)。抵触法ルールに従うとしても、国際私法上の「公序」があるから、結論のまずさはどうにか防げそうですが、公序の中身をどう構成するのか。公法たる刑法上の規律そのものが公序だ、といってしまうのはなんとなく循環論ぽい。それでは結局刑法独自の観点で判断するのと同じことでしょうし。それはそれでいいのかもしれませんが。・244条の話に限りませんが、たとえば、「親族」概念は抵触法ルートを通らずに日本法に従って判断するという見解をとったとして、親族概念について日本とD国でずれがあって、甲は被害者乙が親族だと思って盗んだが、D国法上の概念では親族だが日本法上の概念では親族でない、という場合でも、何のためらいもなく244条不適用って結論でいいんですか。逆に、日本法上の概念では親族だがD国法上の概念では親族でない、という場合には、244条適用って結論でいいんですか。・また、所有者と占有者双方との間に親族関係が必要なわけですが、この「所有者」ってのもどうやって判断するのか。E国法上のゆるーい取得時効で所有権を取得した甲が日本に持ち込んだ物を、甲の親族乙が盗んだ場合、所有者は甲ってことでいいのか。ゆるーい取得時効は日本では正当性をもたないとして所有権は元の持主丙のままだと判断するのか。抵触法ルールに従えば、物権の得喪の準拠法は原因完成地なので、E国で取得時効が完成していれば甲が所有者ってことになると。ゆるさ具合によっては公序が発動することになるんだろうけども、E国で負けてる丙のために公序を発動してあげるのはどうだろう。公序は個人の利益の保護のために発動するのではない、とでもいうんですか。○以上、短い文章にもかかわらず、考えがあっちいったりこっちいったりで、散らかしっぱなしで、なかなか落ち着きません。サイバー犯罪とかそういうハイカラなものよりも、こういう地味な議論をしてほしい。
2007年04月05日
コメント(0)
-

加藤哲夫『破産法 第4版補正版』
改訂直後では、誤植とかそういうのがあること自体は仕方ないとは思うんですが、第4版の間違いがそのまま第4版補正版にも引き継がれているのはどうかと思います。学生さんの教科書として使われているはずだと思いますが、あんまし一生懸命読んでもらっていないんですかね。なお、気になるところを拾い読みしただけなので、他にもあるのかもしれません。○234頁旧法において、賃貸人が破産しても、破産管財人は正当事由のない限り対抗力を備えた不動産賃貸借契約を解除することはできない、と解釈されていたことを述べるくだりで、「対抗力を備えた不動産の賃貸借では、賃借人の側に正当事由(借地借家6条、28条参照)などがない限り、破産管財人は当該賃貸借契約は解除することができないものとして、双方未履行双務契約の一般原則の適用はないものと解されてきた。」とあります。ここでは「破産管財人は当該賃貸借契約『を』解除することができない」でしょ、という日本語の不正確さをいいたいのではなく(そんなこといったら私のブログは壊滅的)、「賃借人の側に正当事由などがないかぎり」破産管財人は解除できないというおかしな記述のことです。これを反対にするとおかしいってことがよく分かるのですが、賃借人の側に正当事由があったら破産管財人は解除できる、ということになってしまいます。これは何がいけないのかというと、正当事由の前についている「賃借人の側に」という文言です。正当事由を備えなければならないのは、賃貸人(破産管財人)が解除することについてなので、賃借人が解除されないことについての正当事由を備える、っていうのはなんか不自然なわけです。引用の借地借家法の条文も、賃貸人が「解除すること」の正当事由であって、賃借人が「解除されないこと」の正当事由ではありません。だから、ここは「解除について正当事由がない限り」(解除できない)としなければならないでしょう(文字数をあわせてみました)。どうしても「賃借人の側に」と言いたくてしょうがないというのであれば、「賃借人の側に背信性のない限り」(解除できない)ということになるのでしょうが、これでは賃貸人の側の事情は考慮されないみたいになってしまいます。あるいは、立証責任のことをおよそ気にしないのならば、「賃借人の側に正当事由などがあるかぎり」(解除できない)となりますが、これでは借地借家法6条、28条の「正当事由」とは真逆の意味になってしまいます。○308頁163条1項で、手形支払いの場合に否認ができないとされているとの説明の後、括弧書きで「(したがって、破産者が租税などの請求権または罰金などの請求権につき、その徴収の権限を有する者に対して担保の供与または債務の消滅に関する行為は、否認の対象となる。163条3項)」とあるのですが、何が「したがって」なんだか分かんないって。結論まるっきり逆だし。そもそも3項の説明が「4 手形支払いと否認の特則(163条)(1)手形支払いの否認」という項目のしかも括弧書きなんかに入っていること自体おかしいし。条文になぞって項目分けするならば、4 手形支払い『等』と否認の特則(163条) (1) 手形支払いの否認 1項の説明 (2) 破産財団への償還 2項の説明 (3) 租税等支払いの否認 3項の説明となるはず。ちなみに、3項の意味は、租税債権に対しては無条件で支払いをしちゃっても否認されないってことでいいですか。一部が劣後的破産債権におっこちた割にはずいぶん優遇されてるなあ。○166頁租税債権の話がでてきたので、ついでに書いておきます。以下は、たぶん私の勉強不足なんでしょうが、疑問だったのでとりあえず。国税徴収法または国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因にもとづいて生ずるもの(97条4号)が劣後的破産債権とされている理由について、「国税などであって破産手続開始後に破産財団固有のものとして発生するものは一般の破産債権とされていることとの均衡からみて」(劣後的破産債権とされている)とあるのですが、A 破産手続開始後に破産財団固有のものとして発生するのが「一般破産債権」B 破産手続開始後に破産財団に関して発生するものが「劣後的破産債権」という理解でいいんですか。というか、違いが分かりません。もし「固有」と「関して」が違うというならば、97条に列挙されてもいないのに、2条5項に反して、破産手続開始後の債権(A)が破産債権になるというのはどういう理屈ですか、という話になりますよね。148条のどこかの号で財団債権になる場合があるのかもしれませんが、ここでは、財団債権ではなく一般の破産債権といってますので。もしかして、固有と関しては同じであって、「国税などであって破産手続開始後に破産財団固有のものとして発生するものは、一般の破産債権との均衡からみて」(劣後的破産債権とされている)の間違いですか。まあ、どういう均衡なんだかこの文では分かりませんが、おそらく、破産手続開始前/後の違いってことになるんでしょう。○266頁さらに、ついでをいえば、148条1項3号で、租税債権が一定の範囲で財団債権となることを説明した後、「この範囲で財団債権とされる範囲以外の租税に関する請求権は破産債権であり(97条かっこ書き)、一般の優先権がある債権として優先的破産債権となる(98条1項)」とあるのですが、優先的破産債権となりうるのは、あくまでも破産手続開始前の原因に基づいて発生したものに限るのであって(2条5項)、説明が不十分。もちろん、その後に開始後の原因に基づいて生じる租税債権の場合について書かれているので、それと対比すれば自ずから分かるだろ、ってことかもしれませんが、不親切であることに変わりはないでしょ。ちなみに、破産財団に関しないで破産手続開始後の原因に基づいて生じた本税債権は、財団債権にも破産債権にもならないみたいですが、破産手続開始後に生じた附帯税債権は、もとになる本税が破産財団に関しないで破産手続開始後に生じたものでも破産債権になるってことでいいんでしょうか。97条3号には、同条4号と違って「破産財団に関して」という限定がないので。附帯税らしくないんだけども。
2007年04月03日
コメント(0)
-
国際私法の教科書-需要者の言いたい放題
国際私法に関しては、どれだけ勉強しても「理解」したというレベルに到達した気がしません。単なる学説の羅列ではなく、山本敬三先生の『民法講義1総則 第2版』(有斐閣)『民法講義4-1契約』(有斐閣)のように、背後にある原理にまで遡った学説整理をしたものがあればいいんですが。たいした例を挙げることはできませんが、たとえば、「外国法不明」の場合の処理に関して(以下、網羅的ではありません)。補充連結によるとする説は、抵触法により準拠法がきまったのに、その準拠法が不明だったのでもう一度抵触法に戻って準拠法選択をやり直すという、法の「選択」レベルでの解決に分類されると。他方、当該準拠法と内容的に近似している国の法を参考にして当該準拠法の内容を推認するという説は、一旦準拠法が決まった以上はその選択をやり直すということはせず、どうにかして当該準拠法を適用できるようにしようという、法の「適用」レベルでの解決に分類されると。当該準拠法と最も近似している国の法を代替的に適用する説というのは、理由付け次第で、「選択」レベルでの解決とも「適用」レベルの解決ともどちらともいえそうです。とすると、同じく最近似国法説であっても、その理由付けによって、どのレベルで解決しようとしているのかが違っているわけです(あくまで私の素人考え)。また、解決のレベルが違うのであれば併用も不可能ではない、ということも分かるわけです。(ちなみに、法の「選択」と「適用」の区別という問題は、「法の適用に関する通則法」というタイトルに関してつっこみを入れておいたところとも関連する話でもあります。)・それから、藤田宙靖先生の『行政法(1(総論))第4版(改訂版)』(青林書院)のように、「法律による行政の原理」という近代法上の原理をものさしを用意して、現代法における個々の問題をその原理との距離によって見ていく、というような手法の本もあるといいですね。国際私法でいえば、「最も密接な関係を有する地の法」の選択を原則とし、個々の問題がそこからどれだけ離れているか、という観点で見ていくことになるんでしょうか。石黒一憲先生の『国際私法 第2版』(新世社)は、立場的には「最も密接な関係を有する地の法」の選択を重視するお考えのようですが、意識的にそういう構成にしているわけではありませんし。というよりも、そもそも、いい教科書ほしいな、という話は、石黒先生の教科書をちゃんと理解できるようになりたいというところから来ています。
2007年04月02日
コメント(0)
-

高木多喜男『担保物権法 第4版』
現代における名著のひとつ、といってもいいんじゃないですか。昭和5年生まれとありますから70代ってことになるようですが、新判例や法改正にあわせてきちんと改訂されているのはいいですね。できの悪い本だと、「新判例・法改正にあわせて改訂!」みたいな謳い文句で売り出しておきながら、従来の記述に取って付けたように判例・新法を付け加えているだけだったりしますが、(たとえば、誰の本だったか忘れましたが、物上代位における差押えの意義について、優先権維持説と特定性維持説の二説を並列的にあげて、私は特定性維持説をとる、と言った後、なお、近時の判例は第三債務者保護説をとるに至った、みたいな第三債務者保護説が全然消化し切れていないものを読んだ覚えがあります)この本では、たとえば、新民法371条や担保不動産収益執行制度ができたことにより、従来の賃料に対する物上代位に関する判例・学説がどのような影響を受けるのか、という点などが論じられていて、法改正が解釈論にもきちんと反映されています(類書でもそれなりに反映してますが、より深く踏み込んでいるということです)。教育的配慮っていうのは、二色刷にしたり図表をたくさん挿入したりすることではないよなあ、と思うのは、何らかのノスタルジーですか。
2007年03月29日
コメント(0)
全165件 (165件中 1-50件目)
-
-

- 本日の1冊
- 読んだ本(浅暮三文)・・その百六十
- (2025-11-19 20:55:43)
-
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- 61 やっぱりタムタムさんはカッコい…
- (2025-11-23 14:06:29)
-
-
-

- 今日読んだマンガは??
- 『その着せ替え人形は恋をする』12…
- (2025-11-24 00:00:05)
-