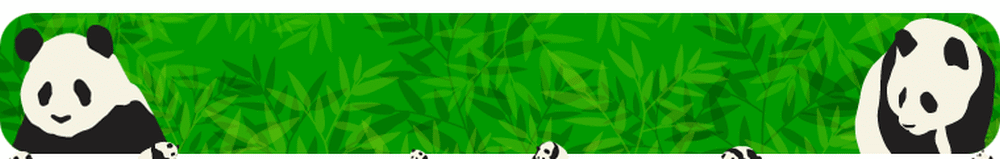PR
X
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(8)及び腰か勇み足な書評
(54)いたづらにむつかしい刑法
(17)ついつい批判的にみてしまう会社法
(18)かなしいけど積読よ
(5)とりあえず買ってみましたが
(10)こわれてく民法
(13)知的財産法だって法律でしょ。
(10)いくら法律じゃないからって、憲法
(2)困ったら裁量で行政法
(2)国際私法は国境を越えない?
(8)法律書への想いをこじらせて
(9)はんぱに裁判員制度
(2)生まれることと終わること
(3)ネットで論文を
(3)手続と実体で倒産法
(1)カテゴリ: 及び腰か勇み足な書評

なお、気になるところを拾い読みしただけなので、他にもあるのかもしれません。
○234頁
旧法において、賃貸人が破産しても、破産管財人は正当事由のない限り対抗力を備えた不動産賃貸借契約を解除することはできない、と解釈されていたことを述べるくだりで、
「対抗力を備えた不動産の賃貸借では、賃借人の側に正当事由(借地借家6条、28条参照)などがない限り、破産管財人は当該賃貸借契約は解除することができないものとして、双方未履行双務契約の一般原則の適用はないものと解されてきた。」とあります。
ここでは「破産管財人は当該賃貸借契約『を』解除することができない」でしょ、という日本語の不正確さをいいたいのではなく(そんなこといったら私のブログは壊滅的)、
「賃借人の側に正当事由などがないかぎり」破産管財人は解除できないというおかしな記述のことです。
これを反対にするとおかしいってことがよく分かるのですが、賃借人の側に正当事由があったら破産管財人は解除できる、ということになってしまいます。
これは何がいけないのかというと、正当事由の前についている「賃借人の側に」という文言です。正当事由を備えなければならないのは、賃貸人(破産管財人)が解除することについてなので、賃借人が解除されないことについての正当事由を備える、っていうのはなんか不自然なわけです。引用の借地借家法の条文も、賃貸人が「解除すること」の正当事由であって、賃借人が「解除されないこと」の正当事由ではありません。
どうしても「賃借人の側に」と言いたくてしょうがないというのであれば、「賃借人の側に背信性のない限り」(解除できない)ということになるのでしょうが、これでは賃貸人の側の事情は考慮されないみたいになってしまいます。
あるいは、立証責任のことをおよそ気にしないのならば、「賃借人の側に正当事由などがあるかぎり」(解除できない)となりますが、これでは借地借家法6条、28条の「正当事由」とは真逆の意味になってしまいます。
○308頁
163条1項で、手形支払いの場合に否認ができないとされているとの説明の後、括弧書きで
「(したがって、破産者が租税などの請求権または罰金などの請求権につき、その徴収の権限を有する者に対して担保の供与または債務の消滅に関する行為は、否認の対象となる。163条3項)」とあるのですが、
何が「したがって」なんだか分かんないって。結論まるっきり逆だし。
そもそも3項の説明が「4 手形支払いと否認の特則(163条)(1)手形支払いの否認」という項目のしかも括弧書きなんかに入っていること自体おかしいし。
条文になぞって項目分けするならば、
4 手形支払い『等』と否認の特則(163条)
(1) 手形支払いの否認 1項の説明
(2) 破産財団への償還 2項の説明
となるはず。
ちなみに、3項の意味は、租税債権に対しては無条件で支払いをしちゃっても否認されないってことでいいですか。一部が劣後的破産債権におっこちた割にはずいぶん優遇されてるなあ。
○166頁
租税債権の話がでてきたので、ついでに書いておきます。以下は、たぶん私の勉強不足なんでしょうが、疑問だったのでとりあえず。
国税徴収法または国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因にもとづいて生ずるもの(97条4号)が劣後的破産債権とされている理由について、
A 破産手続開始後に破産財団固有のものとして発生するのが「一般破産債権」
B 破産手続開始後に破産財団に関して発生するものが「劣後的破産債権」
という理解でいいんですか。というか、違いが分かりません。
もし「固有」と「関して」が違うというならば、97条に列挙されてもいないのに、2条5項に反して、破産手続開始後の債権(A)が破産債権になるというのはどういう理屈ですか、という話になりますよね。148条のどこかの号で財団債権になる場合があるのかもしれませんが、ここでは、財団債権ではなく一般の破産債権といってますので。
もしかして、固有と関しては同じであって、「国税などであって破産手続開始後に破産財団固有のものとして発生するものは、一般の破産債権との均衡からみて」(劣後的破産債権とされている)の間違いですか。まあ、どういう均衡なんだかこの文では分かりませんが、おそらく、破産手続開始前/後の違いってことになるんでしょう。
○266頁
さらに、ついでをいえば、148条1項3号で、租税債権が一定の範囲で財団債権となることを説明した後、
「この範囲で財団債権とされる範囲以外の租税に関する請求権は破産債権であり(97条かっこ書き)、一般の優先権がある債権として優先的破産債権となる(98条1項)」とあるのですが、
優先的破産債権となりうるのは、あくまでも破産手続開始前の原因に基づいて発生したものに限るのであって(2条5項)、説明が不十分。もちろん、その後に開始後の原因に基づいて生じる租税債権の場合について書かれているので、それと対比すれば自ずから分かるだろ、ってことかもしれませんが、不親切であることに変わりはないでしょ。
ちなみに、破産財団に関しないで破産手続開始後の原因に基づいて生じた本税債権は、財団債権にも破産債権にもならないみたいですが、破産手続開始後に生じた附帯税債権は、もとになる本税が破産財団に関しないで破産手続開始後に生じたものでも破産債権になるってことでいいんでしょうか。97条3号には、同条4号と違って「破産財団に関して」という限定がないので。附帯税らしくないんだけども。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年04月03日 10時25分26秒 コメントを書く
[及び腰か勇み足な書評] カテゴリの最新記事
-
佐藤英明『スタンダード所得税法』 2009年05月04日
-
大内伸哉『雇用はなぜ壊れたのか-会社の… 2009年05月03日
-
コリンP.A.ジョーンズ『手ごわい頭脳… 2009年05月02日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.