カテゴリ: 調べてみた
こんにちは。こんばんは。そしておはようございます。
最近、このシリーズばっかりになりつつありますが週末の調べてみた、読んでみた。
今回は堀井憲一郎著 【いますぐ書け、の文章法】(ちくま新書)です。
著者はコラムニスト、フリーライターとあるように書くことの専門家。そして表紙裏にある
『文章はサービスである』という部分に私は興味をもち購入に至りました。
今回も簡単にエッセンスを抜き出せればと思います。それではいってみましょう。
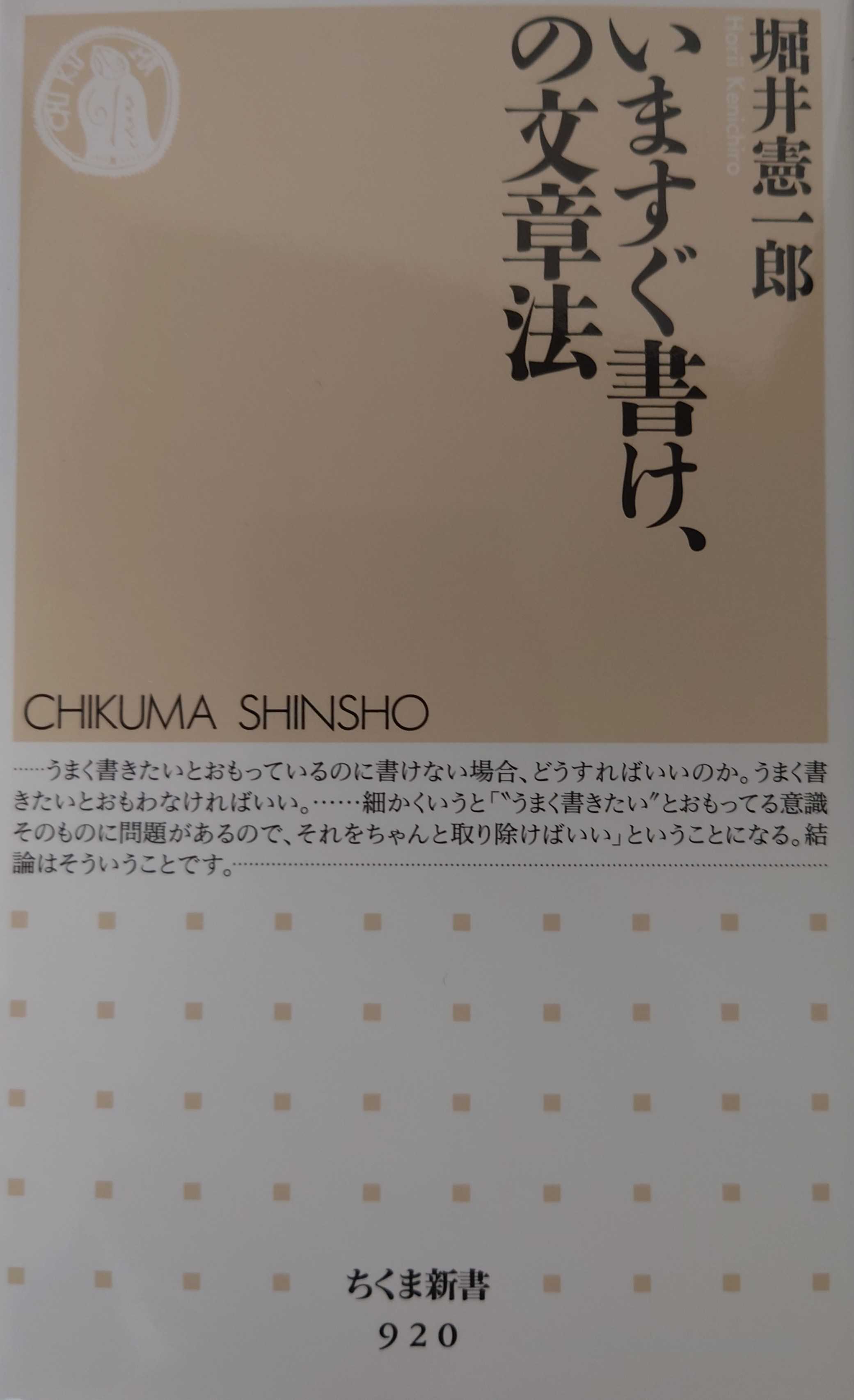
<はじめに>から
”うまく書きたい”とおもってる意識そのものに問題があるので、それをちゃんと取り除けばいい。
<1章 プロとアマチュアの決定的な差>から
プロの物書きは”美しい日本語”を守るために活どうしてるわけではない。ちゃんとした文章は結果
読む人の立場で書け 何ものにも優先して、とにかく読者のことを一番に考えていますか。
読者がどちらの音で読めばいいか迷うような漢字は使うな
自分をさらすことからは逃げられない 読む人のことを考えるというのは、自分を客観的にみること
誰が読む文章なのかが大事 文章が受入れやすいことこれが大事。
<2章 文章は人を変えるために書け>から
過激に言うなら、読者のためなら自分の主張さえも捨てろ
意識は一瞬に変わる、変える 国語力の問題ではない、意識の問題
自分が書いたものをそのまま受け入れて欲しいという気持ちが強い人は、文章を書いても仕方がない
<3章 客観的に書かれた文章は使えない>から
文章は、あくまで個人から発するもの
文章はふつう独断と偏見によって書かれるもの
人に話して楽しいこと、自分が好きなもの、そこから始めるのがよろしい
人は他人の意見なんか聞きたくない。聞きたいのは他人のお話だけである
<4章 直感のみが文章をおもしろくする>から
まず仮説、結論を考える。調べると何とかなるんじゃないか。ぜったいに何ともなりません。
<5章 文章は言い切らないといけない>から
「強く書く」ということを意識しないといけない。書く限りは断定せよ
時系列の誘惑 時間軸に沿って書くな、というのも、最初はなかなかむずかしい
<6章 文章で自己表現はできない>から
文章の精度をあげようとするなら、それは自分で使う言葉を選ぶしかない。
文章の質を上げるには、足すのではなく、削らなくてはいけない。
文章は発表した人のものではない
<7章 事前に考えたことしか書かれてない文章は失敗する>から
書き手であったはずの自分さえも読み手として驚かせること
<8章 文章を書くのは頭ではなく肉体の作業だ>から
とにかく書け、書くとこうなる
頭VS身体の問題 個性は身体にしか宿らない
<9章 踊りながら書け>から
時間的に追いつめられている自分を、精神的に否定的に追いつめないこと
<終章 内なる他者の形成のために>から
いま、自分の持っているものをどう使うか、をきちんと考えるだけ。
まとめの章になっています。詳しくは実物を読まれてください。
読みやすく、かつ厳しく、でも動き出したいと思った本でした。
相変わらず、最初の方にポイントを多く書いてしまう傾向がありますが、それぐらい
最初に大事なことがあったような気がしますので、軽い気持ちでも一度手に取って興味もてたら
ご自身の一冊にしてみてもいいのかな。と感じています。
興味がある方はこちらから↓

いますぐ書け、の文章法 (ちくま新書) [ 堀井憲一郎 ]
最近、このシリーズばっかりになりつつありますが週末の調べてみた、読んでみた。
今回は堀井憲一郎著 【いますぐ書け、の文章法】(ちくま新書)です。
著者はコラムニスト、フリーライターとあるように書くことの専門家。そして表紙裏にある
『文章はサービスである』という部分に私は興味をもち購入に至りました。
今回も簡単にエッセンスを抜き出せればと思います。それではいってみましょう。
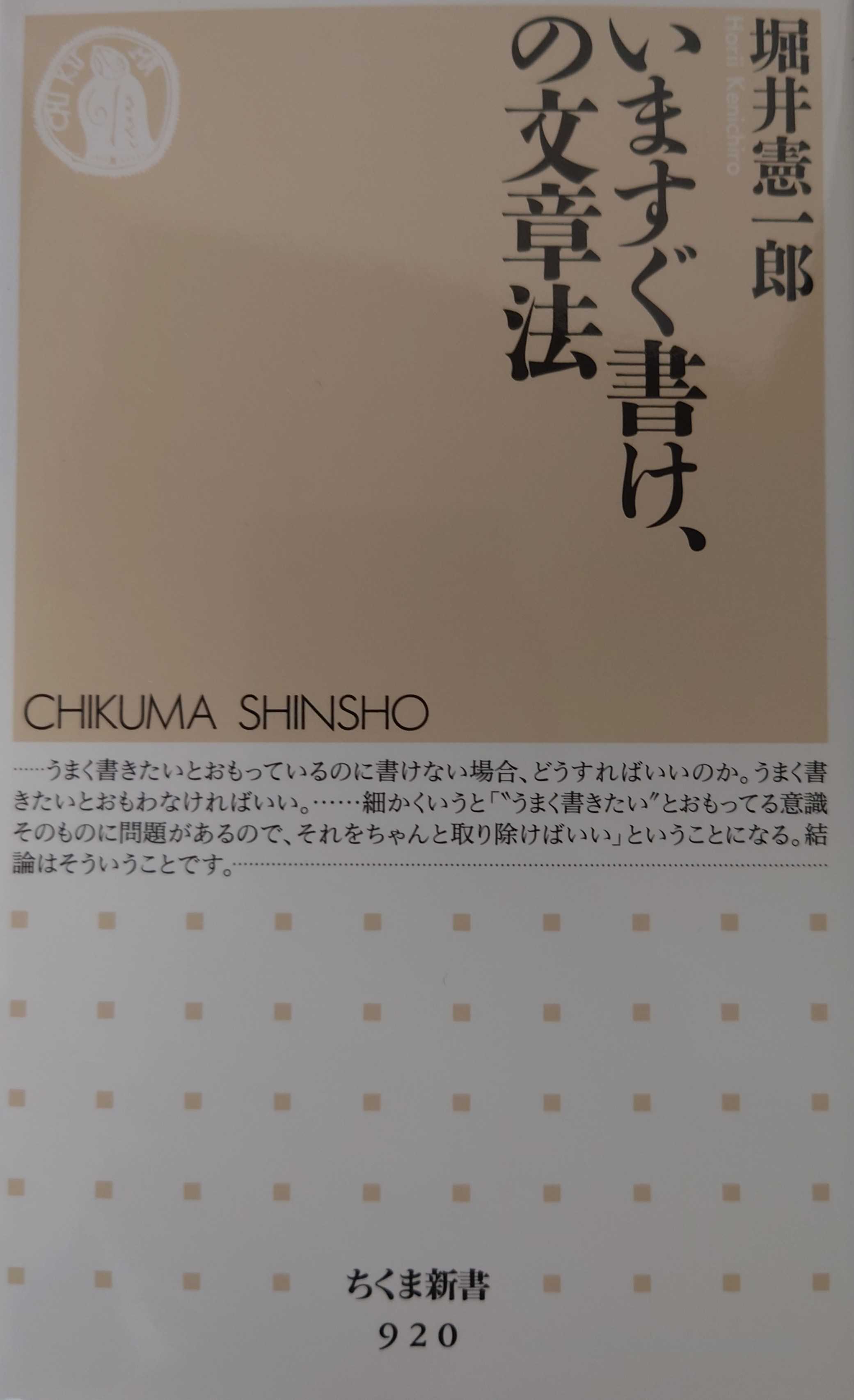
<はじめに>から
”うまく書きたい”とおもってる意識そのものに問題があるので、それをちゃんと取り除けばいい。
<1章 プロとアマチュアの決定的な差>から
プロの物書きは”美しい日本語”を守るために活どうしてるわけではない。ちゃんとした文章は結果
読む人の立場で書け 何ものにも優先して、とにかく読者のことを一番に考えていますか。
読者がどちらの音で読めばいいか迷うような漢字は使うな
自分をさらすことからは逃げられない 読む人のことを考えるというのは、自分を客観的にみること
誰が読む文章なのかが大事 文章が受入れやすいことこれが大事。
<2章 文章は人を変えるために書け>から
過激に言うなら、読者のためなら自分の主張さえも捨てろ
意識は一瞬に変わる、変える 国語力の問題ではない、意識の問題
自分が書いたものをそのまま受け入れて欲しいという気持ちが強い人は、文章を書いても仕方がない
<3章 客観的に書かれた文章は使えない>から
文章は、あくまで個人から発するもの
文章はふつう独断と偏見によって書かれるもの
人に話して楽しいこと、自分が好きなもの、そこから始めるのがよろしい
人は他人の意見なんか聞きたくない。聞きたいのは他人のお話だけである
<4章 直感のみが文章をおもしろくする>から
まず仮説、結論を考える。調べると何とかなるんじゃないか。ぜったいに何ともなりません。
<5章 文章は言い切らないといけない>から
「強く書く」ということを意識しないといけない。書く限りは断定せよ
時系列の誘惑 時間軸に沿って書くな、というのも、最初はなかなかむずかしい
<6章 文章で自己表現はできない>から
文章の精度をあげようとするなら、それは自分で使う言葉を選ぶしかない。
文章の質を上げるには、足すのではなく、削らなくてはいけない。
文章は発表した人のものではない
<7章 事前に考えたことしか書かれてない文章は失敗する>から
書き手であったはずの自分さえも読み手として驚かせること
<8章 文章を書くのは頭ではなく肉体の作業だ>から
とにかく書け、書くとこうなる
頭VS身体の問題 個性は身体にしか宿らない
<9章 踊りながら書け>から
時間的に追いつめられている自分を、精神的に否定的に追いつめないこと
<終章 内なる他者の形成のために>から
いま、自分の持っているものをどう使うか、をきちんと考えるだけ。
まとめの章になっています。詳しくは実物を読まれてください。
読みやすく、かつ厳しく、でも動き出したいと思った本でした。
相変わらず、最初の方にポイントを多く書いてしまう傾向がありますが、それぐらい
最初に大事なことがあったような気がしますので、軽い気持ちでも一度手に取って興味もてたら
ご自身の一冊にしてみてもいいのかな。と感じています。
興味がある方はこちらから↓

いますぐ書け、の文章法 (ちくま新書) [ 堀井憲一郎 ]
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[調べてみた] カテゴリの最新記事
-
【文章の鬼100則】を読んでみた 2021.08.08
-
調べてみた 6月共感の多かったツイート 2021.07.13
-
【要注意】コロナワクチン接種予診票 し… 2021.06.28
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.









