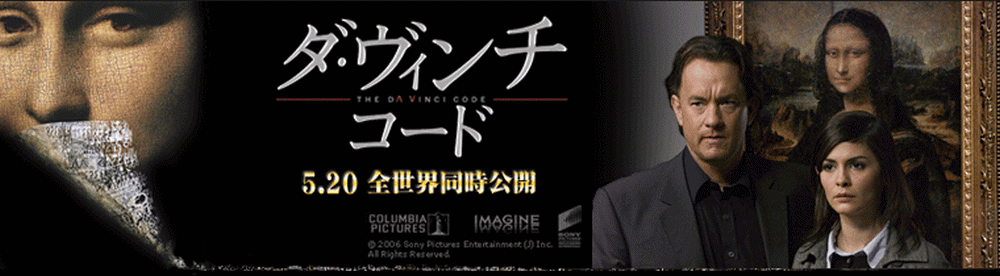PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
🍐 新作「秀吉の野望…
New!
神風スズキさん
みなさんへ、 026… New! はやし浩司さん
今日の天気・・・・… New! ニッチョさん
LIVE SPOT APACHE - … LIVE SPOT APACHEさん
よもだ 悠游さん
バカネコ日記 海獣トドさん
ガンプラの G work-… gontakun122000さん
まみかなの日記(キ… まみかなさん
みなさんへ、 026… New! はやし浩司さん
今日の天気・・・・… New! ニッチョさん
LIVE SPOT APACHE - … LIVE SPOT APACHEさん
よもだ 悠游さん
バカネコ日記 海獣トドさん
ガンプラの G work-… gontakun122000さん
まみかなの日記(キ… まみかなさん
Comments
November , 2025
October , 2025
September , 2025
October , 2025
September , 2025
August , 2025
July , 2025
July , 2025
カテゴリ: カテゴリ未分類
| 形式は文化の基本 3 |
|---|
| (その二)お茶会では自分も鑑賞の対象である。 |
| 何時だったか忘れたが、まだ、お茶を習っていないころだった。友達に誘われるままにお茶会に参加することとなった。お茶の先生のお宅で一席20名ばかりが参加して何回かに分けて茶会が行われるとの事だった。当時、お茶の作法など全く分からなかった私にとって、茶室のあの畏まった雰囲気はそぐわないものであった。ます、正座が苦痛であった。皆、よく座り続けられるものだと思ったものだ。 |
| 亭主の挨拶があり、厳かに道具がそろえられる。茶をたてる一通りの準備が整い、亭主が茶碗の清め茶を点てる準備をする。その間に甘い和菓子が運ばれてきたが、戴き方を知らないので、横目で右隣の友人の所作をまねた。胸が高鳴った。なんだか悪いことをするような感覚であった。前もって「気軽に普通どうりでいいから」と友人に言われていたが、見栄を張って「そうは行くものか」と力んでいたのだ。遠くの主客を見ると、流麗な所作でお菓子を頂いているではないか。隣の友人も心得があるのでお菓子の受け方から戴き方まで作法に則っているように思えた。大げさだが、血が逆流するのではないかと思えるほどだった。と同時に、ろくに作法も知らないでそこに位置を占めた自分の厚かましさとか馬鹿さ加減を恨んだものだ。お茶の世界にいるものは極々常識的であることも、その世界にいないものは、恐怖であり、苦痛であり、窮屈であるように思えた。 |
| ところで、水分補給と言う意味では水を器から飲めば良いだけのことである。少しレベルを高めて、お茶を飲むことは、本来ならば、少し美味なもので喉を潤し、体内の水分補給のための本能的な行為であるから、手に暑さを感じない器で飲めばよいことである。それをどうして難しい約束など創って飲む必要があるのか。このことは、すべて相手との関係を気持ちよく持ちたいというところからきているように思う。水が飲みたいからといって、川でもない限り、相手から差し出された水を、相手に持たせたまま口だけでびちゃびちゃと飲む訳にはいかないだろう。ちゃんと相手からおし頂いて、椀の淵にそっと口をあて飲み干す、そんな相手への感謝のようなものがあっても良い。こんな気持ちの集大成として約束ごとがあるのである。 |
| さて、約束とは、ひとつの仮構である。このような仮構が洗練され固定化していくと、ひとつの文化を創りだす。お茶は、水屋の仕事から道具立て、点茶、戴き方、問答、片付けに至るまで色々な約束ごとがあり、それが利休時代から今日まで続き能などのように日本文化の侘び・さびの世界を作った。 |
| 仮構はまた芸術の基礎でもある。仮構(そのようにする必要は無いが仮に構えるとか無いことをありとするとか虚構)は、本来無秩序のものを秩序立てる働きもする。画家が対象物や自分の思いを、具象化したり抽象化したりする行為である。お茶の文化が約束ごとで成り立ち、その約束ごとが仮構であるとするならば、お茶もひとつの芸術ということが出来よう。それが芸術であるとは、「茶室という空間での道具たちの位置の確かさ、美しさ、一輪の花が与える和み、何にもまして点前やお茶を味わう時の所作の美しさを、そこにいる自分をも含めて表現する」世界である。自分は傍観者=鑑賞者にはなれないのである。閉塞された世界の中に実在するからである。 |
| 自分は傍観者たり得ない。したがって、批評をしても、なおかつその中で踊らされ続ける。このことは、形式としての茶の美意識を受け入れることが出来ないものは、その間口で弾き出されるか自ら見切りをつけて、お茶(文化・制度)から限りなき逃亡を続けるかを選択せねばならないのである。 |
| これって、国の機構によく似てない? 文化や政治が受け入れられないとして国外逃亡したりするのに。 |
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
June 17, 2006 06:00:13 PM
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.