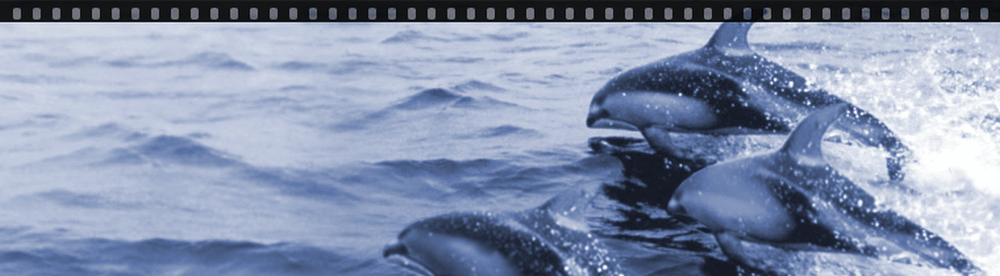PR
X
Calendar
もいっか★フィンラン…
パウエル★Moiさん
ヨーソロー!のひと… ヨーソロー!さん
じょん・どー PhDを… じょん・どーさん
かみぽこぽこ。 かみぽこちゃんさん
CATのアメリカ東… CAT0857さん
レビー小体型認知症… がん評論家@中嶋さん
趣味の部屋 rakuraku88さん
【カラーガード大好… いるまよしやすさん
助産婦じょじょのア… jojo5555さん
故田中角栄の日記 故田中角栄さん
ヨーソロー!のひと… ヨーソロー!さん
じょん・どー PhDを… じょん・どーさん
かみぽこぽこ。 かみぽこちゃんさん
CATのアメリカ東… CAT0857さん
レビー小体型認知症… がん評論家@中嶋さん
趣味の部屋 rakuraku88さん
【カラーガード大好… いるまよしやすさん
助産婦じょじょのア… jojo5555さん
故田中角栄の日記 故田中角栄さん
Comments
Keyword Search
▼キーワード検索
テーマ: 国際関係を語ってみませんか!(221)
カテゴリ: カテゴリ未分類
2日間連続でパウエルさんのトピックをいただきます(苦笑)。
もし「文系人間は帰納法で考える人が多い」という仮定が正しければ、私はどっちなんだろう…。過去の体験から文理どっちとも言えるかなあ、と思いました。
大学では法学部にいたのですが、 最後までこの法律学の思考方法に馴染めなかったんです。なぜって具体例も知らないのに法律の抽象論を話すから。私はチンプンカンプンだったし、同じ理由で法学から脱落する学生は多数います。
一方、法学部の「できる学生」はその抽象論を例えばケーススタディーにどんどん当てはめ、具体的な事例を考えていくことができます。 法律ってどんなことにも対処できるようにした抽象的な文言の塊ですから、演繹型学問の典型でしょう。
でも、 演繹型って限界があります。その典型例だと思うのが憲法9条論議だと思うのです。パウエルさんが「演繹法は大前提という土台がしっかりしていれば、その議論はめっぽう強い」が、「大前提がしばし万能でなかったりする」ということの典型だと思うのです。細かい議論は省きますが、憲法9条の議論は大前提が主張によって全く違います。ですから、 私が昔思ったのは「この主張の違いはどこから起因しているんだろう?」というものです。
どちらかというと個別具体例を多く扱う学問です。また、 理論を演繹的に使うための「大前提」を議論しているところ(そもそも人間って戦争を防止できるのだろうか、など)です。
法学にアジャストできなかった私は帰納法を愛するコテコテ文系で、演繹法を支持する立場を大前提の議論で崩す、かっこ良く言えばそんな感じかなあ。
って、思い付きをわかりづらい抽象論で書いてしまいましたが、わかりました?
さ
もし「文系人間は帰納法で考える人が多い」という仮定が正しければ、私はどっちなんだろう…。過去の体験から文理どっちとも言えるかなあ、と思いました。
大学では法学部にいたのですが、 最後までこの法律学の思考方法に馴染めなかったんです。なぜって具体例も知らないのに法律の抽象論を話すから。私はチンプンカンプンだったし、同じ理由で法学から脱落する学生は多数います。
一方、法学部の「できる学生」はその抽象論を例えばケーススタディーにどんどん当てはめ、具体的な事例を考えていくことができます。 法律ってどんなことにも対処できるようにした抽象的な文言の塊ですから、演繹型学問の典型でしょう。
でも、 演繹型って限界があります。その典型例だと思うのが憲法9条論議だと思うのです。パウエルさんが「演繹法は大前提という土台がしっかりしていれば、その議論はめっぽう強い」が、「大前提がしばし万能でなかったりする」ということの典型だと思うのです。細かい議論は省きますが、憲法9条の議論は大前提が主張によって全く違います。ですから、 私が昔思ったのは「この主張の違いはどこから起因しているんだろう?」というものです。
どちらかというと個別具体例を多く扱う学問です。また、 理論を演繹的に使うための「大前提」を議論しているところ(そもそも人間って戦争を防止できるのだろうか、など)です。
法学にアジャストできなかった私は帰納法を愛するコテコテ文系で、演繹法を支持する立場を大前提の議論で崩す、かっこ良く言えばそんな感じかなあ。
って、思い付きをわかりづらい抽象論で書いてしまいましたが、わかりました?
さ
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
ところで英米法ならどう?
パウエル★Moi
さん
●慣習法→判例を重視する英米法は案外面白いかと思うんです。実際の事例から生み出された叡智というんだろうか、僕には納得できる部分が多いですね。
●フィンランドはドイツ→スウェーデン経由の大陸法です。
●僕も国際政治は帰納法アプローチかな。国際政治ジャーナリズムとどう違うかと聞かれると困るけど。例えば、学者の理論書よりも現場を経た外交官の回顧録とか好きなんですよね。 (2004年12月20日 13時03分57秒)
●フィンランドはドイツ→スウェーデン経由の大陸法です。
●僕も国際政治は帰納法アプローチかな。国際政治ジャーナリズムとどう違うかと聞かれると困るけど。例えば、学者の理論書よりも現場を経た外交官の回顧録とか好きなんですよね。 (2004年12月20日 13時03分57秒)
Re:国際政治ってバリバリ帰納型では(12/19)
まるわ太郎
さん
返事遅れました
kazutaka525
さん
パウエルさん、
英米法ってわかっていないんですよ。判例法が形成されるということは、それだけ司法に大きな権限が与えられているということですかね?
確かに事例から入るほうが法律の勉強になると思うのですが。私は、例えば「土地の二重譲渡」を習ったとき「年間何件この事例が起きて、そのうち何件が裁判沙汰になったのか。どういうときに土地の二重譲渡を使うのか。」ということが気になりました。具体例から入る帰納型ですかね?
まるわ太郎さん
>民法や刑法で言う総則と各論のような違いでしょうか?
法律って各論でも条文と定義から入りますよね?条文と定義って抽象論で、それから判例にあるような個別ケースを扱います。そのように考えると各論でも演繹法です。総論・総則って各論をまた抽象化したものもあるし、各論では扱えない部分を総論としただけのものもあります。個人的にはこの総論・各論というわけ方は好きではありません。 (2004年12月23日 06時22分52秒)
英米法ってわかっていないんですよ。判例法が形成されるということは、それだけ司法に大きな権限が与えられているということですかね?
確かに事例から入るほうが法律の勉強になると思うのですが。私は、例えば「土地の二重譲渡」を習ったとき「年間何件この事例が起きて、そのうち何件が裁判沙汰になったのか。どういうときに土地の二重譲渡を使うのか。」ということが気になりました。具体例から入る帰納型ですかね?
まるわ太郎さん
>民法や刑法で言う総則と各論のような違いでしょうか?
法律って各論でも条文と定義から入りますよね?条文と定義って抽象論で、それから判例にあるような個別ケースを扱います。そのように考えると各論でも演繹法です。総論・総則って各論をまた抽象化したものもあるし、各論では扱えない部分を総論としただけのものもあります。個人的にはこの総論・各論というわけ方は好きではありません。 (2004年12月23日 06時22分52秒)
英米法は面白い
パウエル★Moi
さん
kazutaka525さん
>英米法ってわかっていないんですよ。判例法が形成されるということは、それだけ司法に大きな権限が与えられているということですかね?
●そうです。アメリカの司法は強いです。出した判決が法律になりえるから。連邦最高裁判事は任命ですが、任期は終身ですからね。だから新しく裁判官を任命する際、米国内では大きなニュースになるんです。ブッシュは保守よりの裁判官を任命したがっているようですが。
>確かに事例から入るほうが法律の勉強になると思うのですが。私は、例えば「土地の二重譲渡」を習ったとき「年間何件この事例が起きて、そのうち何件が裁判沙汰になったのか。どういうときに土地の二重譲渡を使うのか。」ということが気になりました。具体例から入る帰納型ですかね?
●日本は大陸法の影響が強いから(でも商法なのかなこれは)、よく分からないのですが、例えば授業で、まず「土地の2重譲渡とは何か」をひたすら定義した後、過去の事例を見る、というのは演繹です。
●アメリカのロースクールは、「ジョンさんが昔、土地取り引きでトラブって訴訟になった」という本当に過去の具体例から入るそうです。それも判例として重要となるケースのみに集中(おそらく年間何件とかの統計ではないかと思います)。そこから土地の2重譲渡とは、こういうことだと決めよう、と定義付ける、これが帰納法です。
●英米の場合、ある訴訟が起こった場合、代理人(弁護士)は、まず過去の似たケースを探し出し、それを応用します。もちろん判例となる事例は全く同じ訳はなく、そこは他の事例で補足する。
●有名な判例は「カリフォルニア州対パウエル」みたいにタイトルを聞いただけで、弁護士の間でどういう事例だったのか即座にわかるくらいです。極端なのに200年ぐらい前の判例をもちだして目下の訴訟に応用する例もありました(確か特許法なんですが)。 (2004年12月23日 23時11分23秒)
>英米法ってわかっていないんですよ。判例法が形成されるということは、それだけ司法に大きな権限が与えられているということですかね?
●そうです。アメリカの司法は強いです。出した判決が法律になりえるから。連邦最高裁判事は任命ですが、任期は終身ですからね。だから新しく裁判官を任命する際、米国内では大きなニュースになるんです。ブッシュは保守よりの裁判官を任命したがっているようですが。
>確かに事例から入るほうが法律の勉強になると思うのですが。私は、例えば「土地の二重譲渡」を習ったとき「年間何件この事例が起きて、そのうち何件が裁判沙汰になったのか。どういうときに土地の二重譲渡を使うのか。」ということが気になりました。具体例から入る帰納型ですかね?
●日本は大陸法の影響が強いから(でも商法なのかなこれは)、よく分からないのですが、例えば授業で、まず「土地の2重譲渡とは何か」をひたすら定義した後、過去の事例を見る、というのは演繹です。
●アメリカのロースクールは、「ジョンさんが昔、土地取り引きでトラブって訴訟になった」という本当に過去の具体例から入るそうです。それも判例として重要となるケースのみに集中(おそらく年間何件とかの統計ではないかと思います)。そこから土地の2重譲渡とは、こういうことだと決めよう、と定義付ける、これが帰納法です。
●英米の場合、ある訴訟が起こった場合、代理人(弁護士)は、まず過去の似たケースを探し出し、それを応用します。もちろん判例となる事例は全く同じ訳はなく、そこは他の事例で補足する。
●有名な判例は「カリフォルニア州対パウエル」みたいにタイトルを聞いただけで、弁護士の間でどういう事例だったのか即座にわかるくらいです。極端なのに200年ぐらい前の判例をもちだして目下の訴訟に応用する例もありました(確か特許法なんですが)。 (2004年12月23日 23時11分23秒)
Re:英米法は面白い(12/19)
kazutaka525
さん
パウエル★Moiさん
イギリス法と三権分立のかかわりについてググってみたのですが、なかなかいい資料はないですね。「英米法とは」という切り口ばかりで、判例法が及ぼす政治的影響力のような切り口はありません。
それから、アメリカとイギリスはかなり法制度が違うはずです。その違いもきちんと抑えたかったのですが、しっかり抑えようとすると修士論文になっちゃいそうです(苦笑)。 (2004年12月24日 08時01分57秒)
イギリス法と三権分立のかかわりについてググってみたのですが、なかなかいい資料はないですね。「英米法とは」という切り口ばかりで、判例法が及ぼす政治的影響力のような切り口はありません。
それから、アメリカとイギリスはかなり法制度が違うはずです。その違いもきちんと抑えたかったのですが、しっかり抑えようとすると修士論文になっちゃいそうです(苦笑)。 (2004年12月24日 08時01分57秒)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.