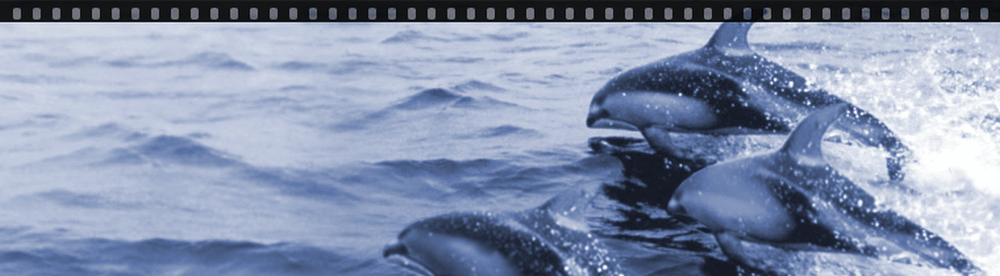PR
X
Calendar
もいっか★フィンラン…
パウエル★Moiさん
ヨーソロー!のひと… ヨーソロー!さん
じょん・どー PhDを… じょん・どーさん
かみぽこぽこ。 かみぽこちゃんさん
CATのアメリカ東… CAT0857さん
レビー小体型認知症… がん評論家@中嶋さん
趣味の部屋 rakuraku88さん
【カラーガード大好… いるまよしやすさん
助産婦じょじょのア… jojo5555さん
故田中角栄の日記 故田中角栄さん
ヨーソロー!のひと… ヨーソロー!さん
じょん・どー PhDを… じょん・どーさん
かみぽこぽこ。 かみぽこちゃんさん
CATのアメリカ東… CAT0857さん
レビー小体型認知症… がん評論家@中嶋さん
趣味の部屋 rakuraku88さん
【カラーガード大好… いるまよしやすさん
助産婦じょじょのア… jojo5555さん
故田中角栄の日記 故田中角栄さん
Comments
Keyword Search
▼キーワード検索
テーマ: 国際関係を語ってみませんか!(221)
カテゴリ: カテゴリ未分類
2日間連続でパウエルさんのトピックをいただきます(苦笑)。
もし「文系人間は帰納法で考える人が多い」という仮定が正しければ、私はどっちなんだろう…。過去の体験から文理どっちとも言えるかなあ、と思いました。
大学では法学部にいたのですが、 最後までこの法律学の思考方法に馴染めなかったんです。なぜって具体例も知らないのに法律の抽象論を話すから。私はチンプンカンプンだったし、同じ理由で法学から脱落する学生は多数います。
一方、法学部の「できる学生」はその抽象論を例えばケーススタディーにどんどん当てはめ、具体的な事例を考えていくことができます。 法律ってどんなことにも対処できるようにした抽象的な文言の塊ですから、演繹型学問の典型でしょう。
でも、 演繹型って限界があります。その典型例だと思うのが憲法9条論議だと思うのです。パウエルさんが「演繹法は大前提という土台がしっかりしていれば、その議論はめっぽう強い」が、「大前提がしばし万能でなかったりする」ということの典型だと思うのです。細かい議論は省きますが、憲法9条の議論は大前提が主張によって全く違います。ですから、 私が昔思ったのは「この主張の違いはどこから起因しているんだろう?」というものです。
どちらかというと個別具体例を多く扱う学問です。また、 理論を演繹的に使うための「大前提」を議論しているところ(そもそも人間って戦争を防止できるのだろうか、など)です。
法学にアジャストできなかった私は帰納法を愛するコテコテ文系で、演繹法を支持する立場を大前提の議論で崩す、かっこ良く言えばそんな感じかなあ。
って、思い付きをわかりづらい抽象論で書いてしまいましたが、わかりました?
さ
もし「文系人間は帰納法で考える人が多い」という仮定が正しければ、私はどっちなんだろう…。過去の体験から文理どっちとも言えるかなあ、と思いました。
大学では法学部にいたのですが、 最後までこの法律学の思考方法に馴染めなかったんです。なぜって具体例も知らないのに法律の抽象論を話すから。私はチンプンカンプンだったし、同じ理由で法学から脱落する学生は多数います。
一方、法学部の「できる学生」はその抽象論を例えばケーススタディーにどんどん当てはめ、具体的な事例を考えていくことができます。 法律ってどんなことにも対処できるようにした抽象的な文言の塊ですから、演繹型学問の典型でしょう。
でも、 演繹型って限界があります。その典型例だと思うのが憲法9条論議だと思うのです。パウエルさんが「演繹法は大前提という土台がしっかりしていれば、その議論はめっぽう強い」が、「大前提がしばし万能でなかったりする」ということの典型だと思うのです。細かい議論は省きますが、憲法9条の議論は大前提が主張によって全く違います。ですから、 私が昔思ったのは「この主張の違いはどこから起因しているんだろう?」というものです。
どちらかというと個別具体例を多く扱う学問です。また、 理論を演繹的に使うための「大前提」を議論しているところ(そもそも人間って戦争を防止できるのだろうか、など)です。
法学にアジャストできなかった私は帰納法を愛するコテコテ文系で、演繹法を支持する立場を大前提の議論で崩す、かっこ良く言えばそんな感じかなあ。
って、思い付きをわかりづらい抽象論で書いてしまいましたが、わかりました?
さ
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.