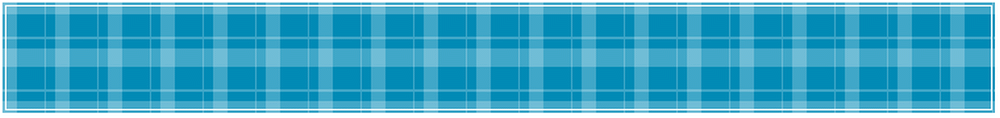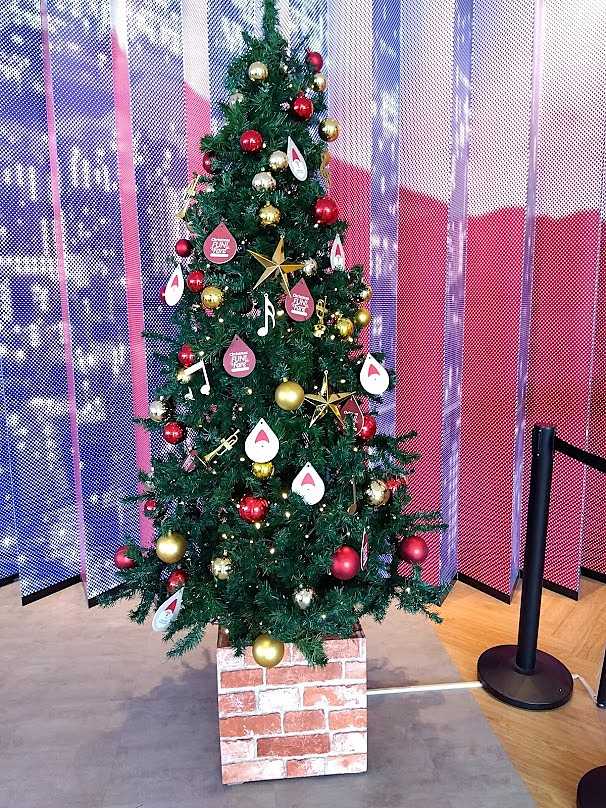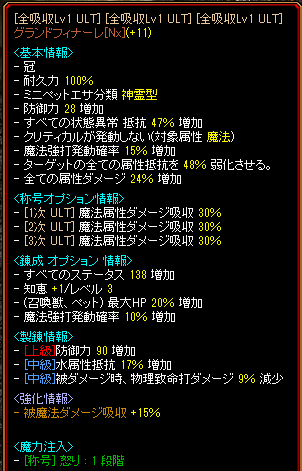2016年01月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

根尾 赤孔雀石・・・
本日 紹介いたします石は、根尾 赤孔雀石「自分的考察により」です。原石は根尾にて採取したものですが、形成時に割れて飛んできそうになるわ、ヒビが入るわで大変でした「瞬間接着剤を垂らしまくりまして どうにか形成し終わりました(^^;;)」研磨は研磨で これまた大変でした、セラミカの番手を上げてくと傷が残る残る! また一つ二つ番手下げて研磨するも取れきれないの連続で、行ったり来たり、心底疲れましたわ、こんなに苦労したのも記憶にないくらいだわo(>_
2016.01.29
コメント(6)
-

part2 津軽岩崎花紋石・・・
前回に引き続き津軽岩崎花紋石を紹介したいと思いますm(_ _)m今回の石は何花紋石なんかなぁ~~青系なんかな赤も部分的に混じってるし、よく判らないので、花紋石だけにしときます、青花紋石・赤花紋石しか今までの知識では知らないのです、まだ色々な色合いの母岩の津軽岩崎花紋石があり、また それの混じったのもあるので、まあ 難しいですわ(^∀^)それと津軽岩崎花紋石の見方としては、母岩の微妙な色合いの変化や模様の変化なども気にかけて頂けたら 面白さが倍増するかも?(? ?)前回のも そうでしたが、珪酸分が多いんでしょうか、艶は気持ちいいくらい出ました、う~~ん満足じゃ(^^;;)
2016.01.24
コメント(6)
-

津軽岩崎花紋石・・・
皆さん急に本格的に寒くなってしまいましたが、如何お過ごしでしょうか?因みに昨日 我が家は名古屋市の西隣になるんですが、雪が約10センチ積もりました(゜_゜i)本日 紹介いたします石は、津軽岩崎花紋石の青花紋石です、母岩の色合いは何色もあり またミックスされたのもありますが、今回のは青系であります。毎回 説明してるんですが、産地は青森県日本海側の山岳地帯のピンポイントで約30メートル?って位の岩盤でのみ産出され掘りに掘られ「超オーバーハングにて崩れたら即死は免れないかも(^^;;)」とても素人には手が出せない状態なんですo(>_
2016.01.21
コメント(6)
-

作台「台座製作」最終章・・・
前回で形成作業は終わり、今回は浸透性樹脂「木固めエース」の塗布&艶消しの工程を紹介いたします。皆さんは何故この工程をするのか疑問をお持ちの人も居られるんではないでしょうか?浸透性樹脂「木固めエース」は普通のニス等とは違い表面にも硬い皮膜を形成いたしますが、材の奥まで浸透して硬く固まり、強度を高めてくれます、ということは 台座の完成後のヒビ・割れ等を防止してくれ台座の表面も硬くしてくれ傷や凹み防止にもなってるので、自分的には殆んどの作台時には使用してます。ただ塗布すれば色合いが幾分濃くなるのとピカピカになるので、自分としては後処理を施してます。「稀に黒檀等 材の色合いや風合いを考え使用しない場合もあります」では画像を含めて紹介いたします。今回 使用する浸透性樹脂「木固めエース」と専用のはけ「刷毛」 刷毛は使用後 シンナーにて洗浄しないと固まり使えなくなるので注意が必要です。浸透性樹脂「木固めエース」塗布後 約1日くらい乾かします。「この画像は撮影時フラッシュを使用してますので、色合いが濃く写ってます。浸透性樹脂「木固めエース」が乾いた状態です、メチャピカピカです、これが好きな人は これで完成ですが・・・スチールウール No.0000 [超極細」にて台座の表面を擦り艶消し状態にし蝋のしみ込んだ布にて表面を磨き整えます。完成した台座です、勿論 着色等はしておりません。秋田県 男鹿青石&専用台座 最終完成形・・・
2016.01.18
コメント(9)
-

作台「台座」の形成作業・・・
今回は作台での使用機材と形成作業を画像を含めて紹介したいと思います。前回作業「底合わせ&切断」の終わった時点での台座裏側に台座の足とサイドの部分をテーパーにするので、鉛筆にて線入れする、台座の足は少しでも出っ張った部分に足を作るとバランスよく見えると思います。「状況により そうでない場合もあるが」木工用超硬カップホィール装着 可変ディスクグラインダー「回転を低速に可変できるディスクグラインダーを使用する」木工用超硬カップホィール装着 可変ディスクグラインダーを使い、サイドの部分を削りテーパーにする「角度を付けて削る」鉛筆にて底の部分を削る為の線入れをする同じく足の部分を削りだす為 軽く歯を入れる木工用超硬カップホィール装着 可変ディスクグラインダーにて足と底の部分を削りだし、荒仕上げは終了木工用ディスクサンダー装着 可変ディスクグラインダー木工用ディスクサンダー装着 可変ディスクグラインダーを使い、全体を整える木工用サンドペーパー装着 コーナードリル♯180木工用サンドペーパー装着 コーナードリルを使い、全体を整える縁取り部分に鉛筆にて線入れをする木工用ディスクサンダー「縁取り専用」装着 可変ディスクグラインダー「ディスクサンダーの先が丸くなっては縁取り作業が繊細で出来ないので、縁取り作業専用です」木工用ディスクサンダー「縁取り専用」装着 可変ディスクグラインダーにて縁取りの部分を削る、この作業が一番 神経を使います、ほんの少しでも削りすぎると修正できない事が多いので・・・♯180と♯400の木工用サンドペーパー装着 コーナードリルを使い、全体を整え 形成作業は終了となります、画像は石を乗っけた状態ですこれにて作台の形成作業は終わり、次回は浸透性樹脂の塗布&艶消しの工程に移ります、完成まで後僅かです!!
2016.01.15
コメント(4)
-

作台作業・・・
今更ですが、作台とは鑑賞石などに専用の台座を作り、飾れるようにすることです。今回は先日 形成・研磨が終わった、秋田県 男鹿青石の作台を使用機材や状況を画像を含めて紹介したいと思います。使用材は東南アジア産 ウリン「アイアンウッド」で名前の如く超硬いと思って作業し始めたら、丁度いい硬さでした、色合いは外周は濃い色合いになってますが、内面は ちょっと濃い色合いの欅「ケヤキ」に似てます。「先ず 石の底面に合わせて罫書き線をエンピツにて書く」「罫書き線の内側に沿ってドリルで連続して穴あけ作業をする」「フォースナビットにて穴あけした内側の部分を均一に削り取る」「回転ヤスリにて石の底部分を現物合わせを何回もしながら、スッポリ納まるように削り合わせる」「台座の外周を鉛筆にて線入れし、電動糸ノコにて切断くり貫く」「くり貫いた部分を石と合わせた所」「これで底合わせ&切断作業は終わり、次回は形成作業を紹介したいと思います」
2016.01.12
コメント(4)
-

男鹿青石の研磨・・・
先日 紹介した幻の秋田県「男鹿青石」の研磨をいたしました。お問い合わせがあったので、使用機材や作業時の石の状態などを画像と文で紹介いたします。あまり硬い石でなく また超軟らかい剥落しそうな部分が多くあり艶々にはならなかったが、まあ こんなもんでしょうf(^_^;)作台作業は近いうちにするのか後日複数に纏めて作業するのか決めてません。研磨に使用する日立工機コーナードリル(D10YB)500~2300rpm研磨の都度 石が水で濡れてる状態では傷の確認ができないので、ドライヤーで乾かし何度も確認します。研磨作業に使うセラミック研磨板で♯300 ♯500 ♯1000 ♯2000 ♯3000を使用します。前回の形成作業が終わった時点の男鹿青石今回の男鹿青石は砂岩の様な柔らかな部分があり瞬間接着剤を その部分に塗布し浸透させ剥落を防止する。セラミック研磨板 ♯300にて研磨した男鹿青石セラミック研磨板 ♯500にて研磨した男鹿青石「ここで研磨終了すると自然風仕上げになる、♯1000まで研磨してしまうと艶が少し出てきて艶消し状態にならないので・・・」セラミック研磨板 ♯1000にて研磨した男鹿青石セラミック研磨板 ♯2000にて研磨した男鹿青石セラミック研磨板 最終 ♯3000にて研磨して研磨作業終了時の男鹿青石
2016.01.08
コメント(4)
-

新春 初形成「男鹿青石」・・・
例年では この時期は寒くて作業小屋とかを持たない自分としては、形成・研磨・作台などはシーズンオフなんですが、今シーズン 異常な天候により、どうにか作業できそうでしたので、年末 岐阜の石友さんより頂いた、幻の男鹿青石「秋田県産」の原石を形成いたしました。作業機材工程等の お問い合わせがありましたので、使用機材や石の状態などを画像と合わせて説明いたします。 「秋田県 男鹿青石の原石」「ダイヤモンドカッター装着 ディスクグラインダー 11,000rpm」この男鹿青石の原石は腐れも多く擦れてないので、かなり削り形成し底切りもしました。「ダイヤモンド蒸着カップホイール装着 ディスクグラインダー 10,000rpm」ダイヤモンドカッターでの大きな形成傷を薄く削り取ります、丁寧に作業します、大きな傷は後で取るのは大変なので。「セラミック研磨板♯100 装着 コーナードリル 3,000rpm」セラミック研磨板♯100使用にて超丁寧に傷を取り除きます、ここで手を抜くと研磨時に痛い目にあいます、これで形成作業は終わり、次回は研磨作業に移ります。※この石は錆びが多く研磨作業に移らず多分廃棄処分にて、平行して形成作業してた以下の2石を研磨の予定です※「形成終了 秋田県 男鹿青石」「形成終了 秋田県 男鹿青石」
2016.01.05
コメント(4)
-

謹賀新年・・・「ブラックオパール」
皆様 新年 あけまして おめでとう御座います、本年も よろしくお願いします30日まで仕事で、31日もドタバタしてて、今日 ようやくノンビリしてましたが、皆様は 如何お過ごしでしょうか?こんなレアなブログですが、訪問して頂ける方が居られるというのは 本当に有りがたいことです、本年も色々なジャンルの内容になると思いますが、ボツボツ更新してきますので、よろしくお願いしますm(_ _)m本日 紹介するのは、オーストラリア ライトニングリッジ産のブラックオパールです、通常ブラックオパールはオパールの中では最上位にランクされてるんです、理由は母岩が黒系だという事です、何故 母岩が黒系だといいのでしょう?遊色が出ている部分は、透明系だったり白系だったり淡い他の色合いだったりして、母岩も同じだったりするので、光が通り抜けたり白系だと遊色の発色が良くないんです。ブラックオパールは母岩が黒系なので、遊色効果が綺麗に現れる場合が多いんです、たとえば最近 よく紹介してるエチオピア産オパールは淡い白系や透明系が殆んどですので、光が通り抜けてしまいますので、黒バックで撮影しないと上手く撮影できないのです。今回も最初 黒バックで撮影に挑みましたが、上手く遊色が撮影出来なかったので、白バックにして撮影し実物とは どうしても まだ同じ感じにはなりませんが、どうにか紹介できるレベルでしたので、撮影終了となりました。何時も思うのですが、オパールの撮影は難しいです(^^;;)
2016.01.01
コメント(4)
全9件 (9件中 1-9件目)
1