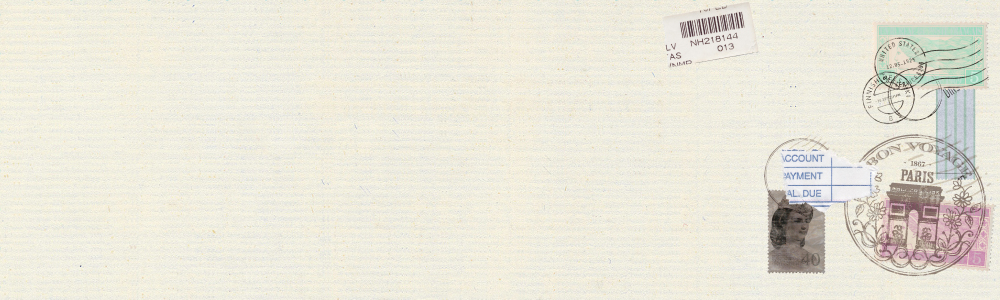PR
X
カレンダー
2025.11
2025.10
2025.09
2025.10
2025.09
2025.08
2025.07
2025.07
カテゴリ
テーマ: ☆留学中☆(2582)
カテゴリ: 留学情報
怒涛の春学期が終わっても休む間もなく2週間後にサマーセッションに突入した。息をつく間もなくとにかく走り続けた2024年だったと思う。サマーセッションは夏の短い間に単位を取得することができるが、その期間の短さがゆえに一回一回の課題の量が非常に多い。私はTask-Based Language TeachingとTESOL Practice Teachingの2つを受講したのだが、TESOL Practiceは10週、TBLTに関してはたった5週間しか授業がなかった。通常学期は15週であることを踏まえるといかにサマーセッションがインテンシブであるかお分かりだろう。
かなり時間が経過してしまったためにうろ覚えの部分があるのだが、濃密な夏の時間をじっくり振り返ることとしたい。
授業1:Task-Based Language Teaching
大学院が複数合格になりシラバスを眺めていた時にこの授業が目にとまり、この大学に行くことになったら必ず受けたいと思っていた授業であった。学部生の頃もTBLTについて学んだことはあったがTBLTに特化した授業は受けたことがなかった。この授業は前述の通りたった5週間しかない。授業は週に2回授業あり、1回の授業は3時間である(途中で昼食休憩が30分ほどある)。
Week 1(1) Course Introduction
課題なし。
自己紹介、コースシラバスの説明、評価の仕方、課題の説明など。TBLTのベースとなる理論やコンセプトのおさらい。Communicative Language TeachingからTBLTとしての地位を築くまでの歴史を辿った。
また、Pecha ku chaという日本で生まれたプレゼン方法を使って簡単なタスクをグループで行った。自己紹介もタスクの要素を加えることで生徒のエンゲージメントを高められることがわかった。どうやらタスクは教師の工夫次第でどんどん教室に取り入れることができるようである。
Week1(2) Conceptual and Theoretical Foundation of TBLT
教科書のチャプターリーディング2章(1章と2章)、その他TBLT関連のチャプターリーディング20ページ。
Willisのタスクサイクルやタスクの概念について学んだ。What is a task?という問いに対して全員で意見を出し合った。様々なタスクの切り口があって面白かった。タスクはTBLTの根底にある概念だが、なかなか定義することが難しい。のちにわかるのだが、学習者のニーズや言語能力に応じてタスクの難しさを逐一調整する必要があることがわかった。つまり、無味乾燥のタスクはTBLTには存在しないらしい。
Week 2(1) Planning Tasks 1
TBLT関連書籍チャプターリーディング2章(3章、4章)。
Willisのタスクサイクルをどのように授業に落とし込むか学んだ。Pre-task, task execution, post-task(share-out)のステージごとで学習者がどのような活動をするのか確認をした。TBLTでは基本的にはタスクサイクルを何度も何度も繰り返し行っていく。
うまく落とし込めれば外国語教育に変革をもたらすゲームチェンジャーであることは間違いないのだが、やはり学習指導要領との相性が悪すぎるように思えた。TBLTは学習者が主体となってタスクを遂行する中でターゲット言語にアプローチをしていく。気付きがあって初めて教師が介入できるのだ(批判を恐れずにざっくり申し上げると、生徒のエラーや気づきをベースに教師がその言語項目に学者の注目を持っていくことをfocus on formと呼ぶ。)。果たしてそのような気づきを教師を指導の前から予見することができるのだろうか。そして、日本のEFL環境では常に30名から40名ほどの学者が一堂に会して学習をしている。各々異なる認知能力を有している学習者が皆同じような気づきをするとは限らない。TBLTを日本の環境で実施するにはあまりにも前提や条件が異なりすぎるような気もする。最近ではTBLTに対して批判的な論文も増えてきている。この辺りを今後さらに調べてみたいと思った。
Week 2(2) Planning Tasks 2
Robinson&Gilabertの論文は短いが、TBLTを認知科学の側面からアプローチしており、タスクをデザインする上で非常に参考になりそうな文献であった。教授が仰っていたのだが、TBLTの研究のほとんどは実験室などのかなりコントロールされた条件下で実施されている場合がほとんどで実際の教室で行われた研究は非常に限られているのだという。特に実際の教室で長期的に行われたTBLT研究は稀有な存在なのではないだろうか。実際にTBLTのELT textbookもあまり見かけない。盛んにtask complexityなどの研究は行われているが教育現場は旧態依然の指導が行われている印象だ。今大学院で学んでいることが机上の空論にならないよう、自分の過去の経験をもとにタスクをデザインしていきたい。
Week 3(1) Instructional Issues in TBLT, Focus on Form and Explicit Instruction
教科書のリーディング(4章、5章、6章)。
タスクの種類やタイプについて学んだ。個人的に面白かったのが、今までタスクといえばペアで行うインフォメーションギャップのようなものを想定していたが、実際にはそれ以外にもopinion, reasoningなどの様々なgapがあることが判明した。そして、TBLTといえばショッピングやマップなど常に実生活を意識しなければならないイメージを持っていた。そして、あまりにも簡易化された地図やロールプレイのような半機械化されたやりとりに辟易している自分もいた。実際にはpedagogical taskという分野もあってアカデミックな内容をタスク化するということも可能だそうだ。
Week 3 (2) Contextual Issues in TBLT II, Proficiency Differences TBLT as a Global Approach
教科書のチャプターリーディング(9章)、論文3本。
学習者の語学運用能力や年齢、認知力に応じてタスクの難易度を調整しなくてはならない。Task complexityはタスクの抽象度、言語材料の提示の有無、背景知識の有無などによって決定される(もっと詳細なカテゴリーがあるのだが、ここでは割愛させていただく)。様々な学習者に対してどのようなアプローチをしていけばいいのかクラスで議論した。改めて、教師と学習者の間で擦り合わせを何度も行わなければTBLTは成立しないことがわかった。そういう意味では教師の調整力がカギを握っているのかもしれない。
Week 4(1) Designing and Analyzing TBLT Unit I
教科書チャプターリーディング(10章、11章)、ビデオ視聴1本。
教科書のチャプターコピーを数部渡され、教科書の内容をアレンジしてどのようにTBLTの要素を加えていくかグループになって議論した。議論をした後にクラス内で発表した。各グループの発表を受けて、改善点がないかクラス内で協議した。同じ内容の教科書であってもアレンジを加えることでエクササイズもタスクになりうることを確認した。繰り返しと暗記が求められるエクササイズもひと工夫をするば立派なタスクになりうることは目から鱗だった。
Week 4(2) Designing and Analyzing TBLT Unit II
教科書チャプターリーディング(12章)。
教授のお子さんが怪我をしてしまったため、急遽対面授業はキャンセルになり、オンライン授業となった。
授業の後に個別ミーティングが開催され、各々が作り上げているカリキュラムプランに対してフィードバックをもらった。
Week 5(1) Lingering Issues(Workshop for Task-Based Unit Plan)
TBLTの理論を学んだ上でTBLTの問題点をクラス内で議論した。やはり一番の多く上がったのはクラスルームベースの研究の蓄積がそれほど多くないことだ。ほとんどのTBLT関連の研究は実験室で行われ、教室で長期間行われた研究があまり出版されていないのが実情である。また、ピュアTBLTは体系的にカリキュラムを構築することが非常に難しい。やはりstudent-centeredなアプローチをすると生徒に委ねないといけない部分が多くなっていき当初計画した通りにいかないことが多々発生してしまう気がする。
Week 5(2) Final Project Presentation
各々がデザインしたTBLTのカリキュラムを発表した。私はEFL環境、学習指導要領の制約を意識しながらレッスンプランを作成してみた。どちらかというとTBLTというよりTask Supported Language Teaching(TSLT)に近くなってしまったような気もするが、日本のような環境ではむしろこちらの方が適しているのかもしれない。
残念ながらコンテストを完全に度外視したレッスンプランも散見され、誰が誰に対して何のために教えるのかよくわからないプレゼンも何本かあったのは事実である。そのようなカリキュラムは大体タスクが「生徒に英語を使いながらやらせる遊び」のようになってしまう。遊びで盛り上がることが必ずしも学びにつながるわけではないと思う。特に学習者の年齢が上がるにつれて学習内容の難易度もそれ相応に上げていかなければらない。タスクの難易度と言語材料の難易度のバランスを取る必要がある。
短期勝負で大変ではあったが、集中して取り組むことができた。短期間で課題を仕上げなければならなかったため、もう少し時間をかけてじっくり推敲したかったというのが唯一の心残りである。TBLTの可能性と今後の課題を大いに学ぶことができた。日本のEFLコンテクストには落とし込むのは非常に難しいのだが、何か打つ手はないのか考えていきたい。
それでは今日も良い1日を。
きたろう
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[留学情報] カテゴリの最新記事
-
米国大学院2年目の学費 2025.06.30
-
アメリカ留学期間中に生活費公開 2025.05.18
-
海外留学を希望されるあなたへ(特に米国) 2025.03.08
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
© Rakuten Group, Inc.