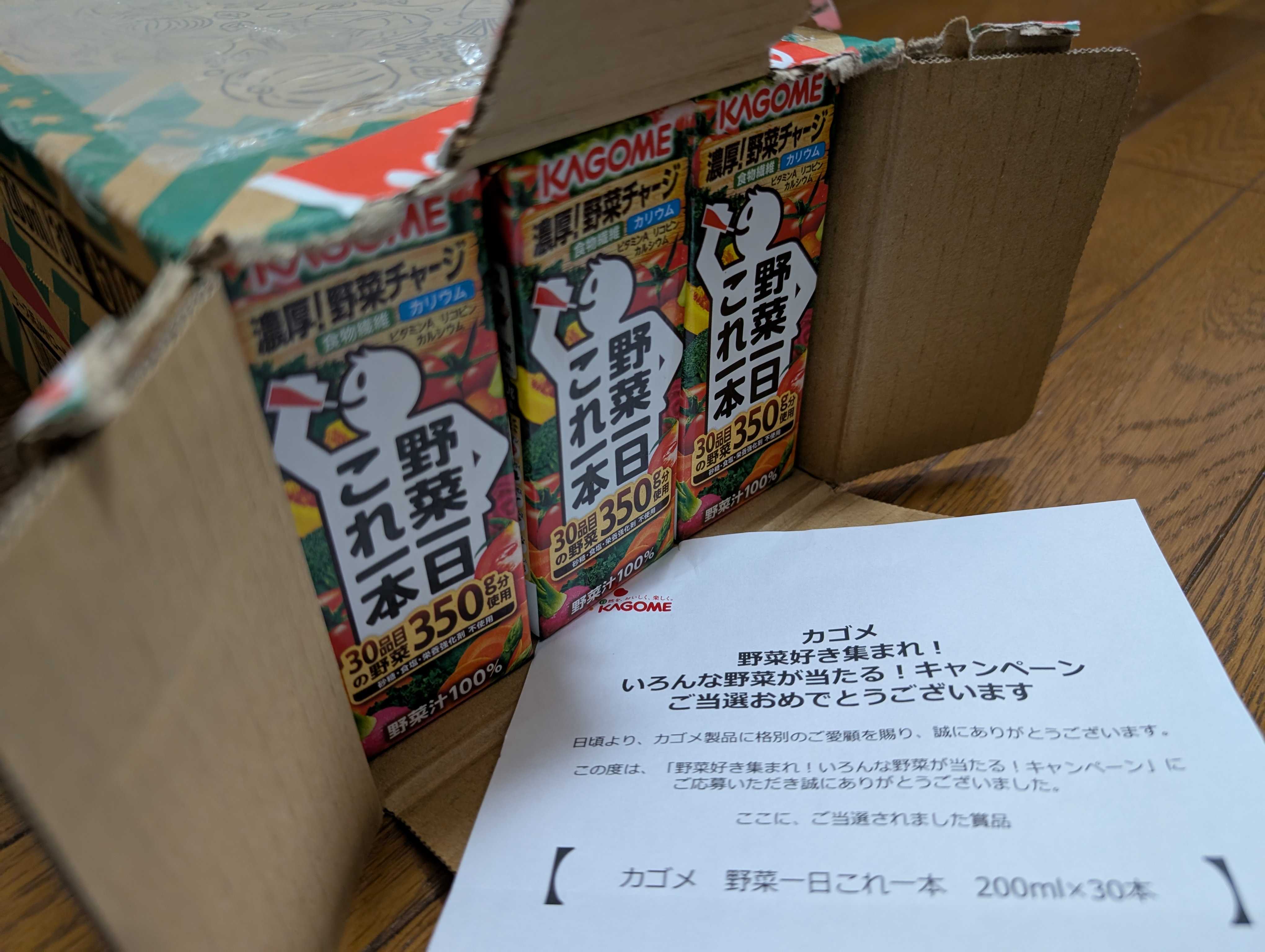7月
8月
9月
10月
11月
12月
2012年01月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
1.17岡野のおやじ
「日本橋の丸善ってとこへ行けば、洋書の専門書がある。そこにプレスの本があるから、それを買って勉強しなさい」「でも洋書なんて、俺は英語も何も読めないんです」「絵と図面を見ていればなんとなくわかるものなんだ。お前も職人だろう。それを見ればいいんだから、とにかく見て覚えなさい」上の文章は痛くない注射針を開発した有名な下町の親父です。その後に、以下の文章が続いております。随所に、キモがあると思いますので、おたどりください。よろしくお願いいたします。そう言われて次の日にすかさずその本屋に行って、一番良さそうなのを買ってきた。ドイツの「プレス便覧」という本だった。今から40年近く前の話だが、値段は忘れもしない。12,500円の本だった。当時、プレス技術はドイツが先進国で、基本的なことがしっかり書かれてあった。なにしろその本がおもしろくて、いつも眺めていた。読むのではなく、図とか写真を眺めるんだ。このドイツ書を20年間ぐらいは、毎日、眺めていた。
2012.01.17
コメント(0)
-
1.16北斎
「北斎の絵なんか、すごいの。あれ、遠近法を知らないからなのね。知らないほうが、発明する。なまじ知っていると、それで間に合わせてしまう」。
2012.01.16
コメント(0)
-
1/15成り下がり
ある創業者の気風のいい語り口から。 前例なんてものは知らなくていい。知れば知るほど、どこか模倣になってしまう。「独創性がなくなる」。困難という泥水を呑まなきゃ、人も組織も成長しない。妥協しなきゃ、世の中渡れないなんて、そんなのは「人生観が弱い人間の考えなんだ」。やめておく理由なんていくつでもあった。けど、そんなものを数えてたら仕事なんて始められない。自分の考えでいいと思ったらやる。「社会の通念とか、常識とか、そんなものはひとまず脇においておけばいい」。成すべき理想があるなら、反対されても、たとえ困難でもやらなきゃいけないんだ。もうカネがあるから安住してやらない、これは実は、もう「成り下がりなんだよ」。
2012.01.15
コメント(0)
-
1・14右脳の判断
「なんとなく仕事相手に対して『受けたくない』と第6感で感じることがあるのです。要するに右脳でキャッチした感覚です。それを左脳が『いや、そんなこと。人のことを悪く思っちゃいけない』と、いい方向で考えようとして、悩むことがあります。でも右脳で『悪い』と思った人は、悪い人だと思えばいいんです。それを『人の長所をみなければ』などと思うと、自分が苦しむんです。でもがんばっても、結局は自分とは合わない人物なんです。別に無理して付き合う必要はない。それが私の最近の結論です。(昔はまったく違いました)」、
2012.01.14
コメント(0)
-
1.13ドラマづくり
「ドラマに‘起承転結’はいらない」猛烈アナーキーなご意見だ。「次に視聴者が見たいシーンは何か。それだけ考えろ。そうすれば起承転結はおのずと生まれる」というのが教えだった。今でも沢山出回っているシナリオの書き方というような本を本屋で手にとってみると、必ず‘起承転結’が大事だと書かれている。以前、あるシナリオ教室を、たまたまちょこっとのぞいてみる機会があったのだが、ドラマは「起→承→転→転→転→転→転→結」くらいがよいと、
2012.01.13
コメント(0)
-
1.12心の中にあること
およそ人間の身の上には、その人の心の中にないことは生じないんだぜ。 みんなこれがわかっていない。思ってもいなかったことが、現実の自分の人生にできあがったといっても、それを自分が無意識に思っていたことに気がつかないで、意識的に思ったこと以外には思ったことじゃないと、こう思ってる。もういっぺん言うよ。自分の身の上には、その人の心の中にないことは生じない。言い換えると、すべての出来事は、心の内部から、自分が知る知らざるとを問わない、心の内部から掲げられた合図によってつくられる。我々人間の生きてる背景には、終始そこに、その人の思い方のとおりに物をつくろうとする力が控えてるよ。現象の背後には必ず実在があり、ということだ。「英語にYou are what you eat(食べたものが自分をつくる)」。こんな言い回しがあるそうで、同様にYou are what you say(話した言葉が自分をつくる)と続けて述べられている。
2012.01.12
コメント(0)
-
1.10お金を貯める
お金を貯めようと思ったら、 「それは使わないことですよ」は当たり前。逆に「使い切る」ことで貯められるという人もいる。それは千円だったら千円分、一万円だったら一万円分をしっかり「使い切る」。まず、お金に対する意識とセンスが身に付くから、無駄使いしないということか。また「使い切る」とは「買った物を大切にする」ことでもあるので、これだったら、自然と使わなくなりお金は貯まる。
2012.01.10
コメント(0)
-
1.10念力とは
「念力とは、気を入れてやることである。気を入れてやっている人の様子は、傍から見ても気持ちが好い。どんな詰まらないような仕事でも、気を入れてやっている人の顔つきは気持ちが好い。あの人の仕事は巧く行くなア、と、そう思えるからである。傍の人がそう思うと、それがまた、その人の気持ちに作用して、巧い上に巧く行くようになる。その人は、自分の気持ちに暗示をかけるようになる訳で、知らず知らず念力になる。人は不断、そうとは気がついてはいないが、殆ど、人からの暗示か、或いは自分自身の暗示によって、ものごとを考えることが多い」、
2012.01.09
コメント(0)
-
1.8イノベーション
シュムペーターの「イノベーション=技術革新」は誤訳で、「イノベーション=新しい結合」だ。 オリジナリティもそうなんだろう。自分らしい「新しい組み合わせ」。
2012.01.08
コメント(0)
-
1.7本田宗一郎の話し方
「役者は、一に口跡、二に容姿」という言い回しがあり、魅力的な演者であるためには、容姿もさることながら、滑口のよい話し方、声の魅力がより大切、らしい。ホンダの創業者・本田宗一郎氏は、実に口が達者で(現場では手も達者で、ずいぶん社員をぶん殴っていた)、その語り口には独特のものがあり、やはり世界のホンダを創業した人ならではだなあ、と誰もが感心していたよう。しかしその話し方、話しぶりは、天性のものではなく、後から勉強して身に付けられたとか。故郷の浜松から東京へ進出する際、これからはいろいろな人に自分の事業のことを話さなくてはならなくなるので、話し方からその準備をされた、というエピソードが残っている。
2012.01.07
コメント(0)
-
1.6y安売りしない
以前から「選択と集中」と言われてたが、まずは「小さなコアコンピタンス」で地盤固め。 儲けてる人はしっかり自分の得意分野を持ち、それを欲しいターゲットだけに売っている。 だから安売りしなくて、いい。相手がどうしても「欲しい」んだから。
2012.01.06
コメント(0)
-
1.5パリのショーウインドー
「パリの、とある街角のブティックのショーウィンドーを覗いていたら、思いがけずしゃれたバッグが飾られていたので、中に入って主人に「いくらか?」と聞きました。すると思いがけず「ノン」といいつつ、ペラペラしゃべりだしました。このバッグは売り物ではなかったのです。ある日、10代の一人の少女が飾られていたこのバッグに目を付け、買いたいと主人に申し出ました。ところが少女の予想した値段よりも、はるかに高価だったと見え、一旦はあきらめたのですが、また次に日に来てどうしても買いたいというので、お金が稼げるまで誰にも売らないでほしいと、半額だけ置いたというのです。主人は快く承諾しました。この少女の熱心さに感動する部分があったのかも知れません。そんな主人に対し、少女はもう一つだけ「願いを聞き入れてくれないか?」と頼んだのです。その願いとは、勤め帰りにこの店先を通るので、バッグをショーウィンドーに飾っておいてほしい、ということでした。このバッグを毎日見ることで「希望が湧くのだ」と彼女はいったというのです。主人は私に「あなたがいま見ているのは、そのバッグだ」というではありませんか。なんだか「おしん」みたいなんですが、「違うもので間に合わせない」。
2012.01.05
コメント(0)
-
1.4美空ひばり曰く
「無私」といえば、もう一つ。美空ひばりから-「家の置物も服も帽子もみんなファンの贈り物なんです。だから何一つ捨てられない。もし、その人が来た時、自分の贈り物があれば嬉しいでしょう。 服も帽子も趣味が悪いといわれても、それを身につけた私がグラビアに映ったのを見たら、きっと贈り主は喜ぶでしょう」。 これを瀬戸内寂聴さんは「私はもう脱帽状態で、何も言えなくなった。この無私奉仕の人こそ、ファンの神様なのだ」と。 そもそも損得はないのである。
2012.01.04
コメント(0)
-
1.3マザーテレサ曰く
「マザー・テレサにとってもっとも重要なのは言うまでもなく行為だ。しかしその行為を支えるものとして、祈りの言葉がある。『考える時間を持ちなさい。 祈る時間を持ちなさい。 笑う時間をもちなさい。それは力の源。それは地球でもっとも偉大な力』。ここに『笑う時間』とあるように、マザー・テレサはよく微笑む人であった。長年彼女の写真をそばで撮り続けて来たカメラマンの写真は、実に見事にマザー・テレさの温かい笑顔をとらえている。近寄りがたい聖人というよりは、ユーモアいっぱいの楽しい話をする人だったという」。
2012.01.03
コメント(0)
-
1.2「コト売り」
有名なラーメンチェーンの創業者も言っていたが、「俺たちはラーメンを売っているのではない。『ありがとう』の声を聞くためにラーメンを売っているのだ」。つまり、「ラーメン」という「モノ」でなく、「ありがとう」と言われる「コト」。お客さんはその店のラーメンを食べて味わえる「ありがたい世界」を体験し来るんだ。極端に言えば枕なんて使い勝手や使い心地の理屈が言えればいい。ラーメンだってなにか一つ特徴があればいい。目的の後ろには背景や前提があり、そこには個人的な関心や趣味とは別に、共通した「人間」と「時代」と「未来」に関することが横たわっているのだ。それらに対する切り方、訴え方こそが、「モノ」を通した「コト」の販売になるのだ。
2012.01.02
コメント(0)
-
1.1小林先生2
あの人にはこういうところがある、そして、こういうところもある。そのように人間を二つに分けて理解してはいけない。人間は一人だ。
2012.01.01
コメント(0)
全16件 (16件中 1-16件目)
1