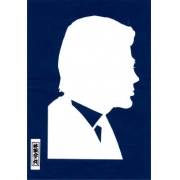カテゴリ: カテゴリ未分類
「爺さんの手記『春愁記』、今回で無事『郷里岡山時代』が完結いたします」
「大変でしたね」
「たまたま岡山県民になったものの、何も知らないのじゃから……調べていくうちに、爺さんとの共感を得た部分もあるぞ」
「はい、それでは、第1部の最終回です」

内山下に医専があった頃、この運動会といえば試験用の動物を連れ出し、吾々が組で引いた連中が走り出すという珍風景なものが人気を呼んでいたことを思い出す。医専は今の二十五銀行のある一帯の地で、病院と並び広大な地域に丸太の柵が並んでおり、学校へ出掛けるには、どちらかもこの柵を回って出掛けねばならぬ退屈な道であった。
当時弟の喬は五つの年下であり、四郎は更に三歳の年下であった。喬の方は中学時代、北側の庭でよく槍をしごいて腕力を鍛えていたということだったが、その様子は見たこともなかった。しかし、幾歳頃のことか、何かの動機で喧嘩をおっ始め、やにわに刀棚に手をかけ、南の庭に飛び降り、杉垣を回って逃げ回るのを追いかけて、縁側に飛び上がったところ、突然現れた老祖父に大声で叱られた上、役所から帰宅した父にも告げられ、無念でたまらなかった。それもこれまで喧嘩はたびたびのことであったが、段々成長し槍術で鍛えた力は自信が出来たためか、弟の方で反抗の力を示したことが無性に気に触れたことが動機らしく思える。次の四郎の方は、体は大きな方であったが、年も違うことであり、あまり喧嘩などした記憶はなく過ごしたことであった。

何にしても、四十年以上以前のことであるが、ここに書き連ねてみると、当時のことどもが次々と頭の中に浮かび出て来るのが、あるいは夢のようでもあり、はたと更に沈思すると、幻のように消え去るようにも思える。この他主立った印象となるものは、蓮正寺で暗い本堂の中を覗いた大曼陀羅や、※1九州北端に建立さるる日蓮上人の模型の見物に、やはり蓮正寺の本堂前で見物したこと、あるいは日清戦争前後だったか、蒙古来襲の大きな絵を幾枚もかかげた公園の※2鶴鳴館に出掛け、生徒一同がその寺に座ったまま※3「四百余州をこぞる……」と唱歌を歌わされたことなどあるが、その前後の時期は判然と分からぬ。

当時の子供といえば、着物など棒縞の手織木綿で紺絣など着る者は余程の上流の者であり、自分など絣の物を着たのは中学に上がった頃、やっと妙な香りのあるまがいものの絣を着せられ、はなはだ得意の気がしたもので、シャツなど棒縞のあるもので白いフランネルなどに仕立てられたものは、これまた上流の子弟で、袖口にふくらんんだ白い物を身につけたことは、相当の年になった頃であったように思える。色々頭に浮かんで来るが、少年時代は比較的無事な歳月を重ねて来たことは事実で、父が引退後、段々年を経るに窮状に陥ったものと見え、家の中も何となく淋しい空気に満たされて来たことであった。
注
 ※1「九州北端に建立さるる日蓮上人の……」
※1「九州北端に建立さるる日蓮上人の……」
熊本出身の湯地丈雄が、明治21(1888)年、熊本県警部を辞職後、愛国精神を鼓舞するため、福岡に「元寇記念碑」を立てようと計画、日蓮宗の佐野前励(日管上人)が共鳴して、北条時宗と日蓮の像を作ろうとしたが、他の宗派の反対で実現せず、亀山上皇の像に変更された。
佐野前励は、湯地と行動を別にし、自分達だけで福岡市東公園に単独の日蓮像を建設した。明治25(1892)年に着工、完成は明治37(1904)年。「日清戦争前後だったか」とあるのが、日清戦争は明治27、8年であるから、筆者5、6歳。多分終戦後、筆者が小学校に入った頃ではあるまいか。
※2「鶴鳴館」
岡山後楽園内の建物。右の写真で、右側の屋根が青く見える建物で、襖を取り外すと百畳の座敷になる。
※3「四百余州をこぞるという唱歌」
上の注1にある湯地丈雄の元寇記念碑運動を支援するために、陸軍軍楽隊の永井建子(けんし)が作った「元寇」という歌。明治25(1892)年に発表された。
国難ここに見る 弘安四年夏の頃
なんぞ恐れんわれに 鎌倉男子あり
正義武断の名 一喝して世に示す
 ※4「郡司大尉が千島同盟を提唱……」
※4「郡司大尉が千島同盟を提唱……」
千島列島を占有することを提唱するが支援がなく、明治26(1893)年3月20日、自分達で用意した5艘の小さな船で東京から海を北上する。南極探検で有名な白瀬中尉も仲間に加わっていた。途中暴風で18人が死亡、郡司大尉も負傷し、通り掛かった軍艦「磐城」に曳かれて函館入り。結局この「磐城」に便乗して8月31日、占守(シュムシュ)島に到着した。一行はここと色丹(しこたん)に別れて越冬するが、色丹の九名は全員死んでしまう。左下の写真は北海道大学付属図書館に所蔵されているその折の写真。本文の絵がその雰囲気をよく伝えていることが分かる。
その年日清戦争となったため、郡司大尉は白瀬中尉に後を頼んで帰り、白瀬中尉はこの年も越冬、病死者が出たが翌年カムチャッカ半島の資料を手に帰国した。白瀬中尉はその後行動を共にすることはなかった。
日清戦争が終わると郡司大尉は運動を再開、明治29(1896)年、同志とその家族を率いて占守島に移住。ラッコなどの猟と家畜を飼い菜園を作った。明治37(1904)年、日露戦争が勃発すると、19名でカムチャッカへ渡り、住民に捕まって殺される。
 北方領土開拓の英雄とされているが、最初の船は長さ13m、幅3mのカッター船3艘と和船2艘、越冬に関しても十分な調査も準備もなかった様子。だが話は上手で学生らの心を鼓舞したらしく、明治26年3月に学習院中学の3年生達が書いた「郡司大尉を送るの序」も残っている。
北方領土開拓の英雄とされているが、最初の船は長さ13m、幅3mのカッター船3艘と和船2艘、越冬に関しても十分な調査も準備もなかった様子。だが話は上手で学生らの心を鼓舞したらしく、明治26年3月に学習院中学の3年生達が書いた「郡司大尉を送るの序」も残っている。
本文に書かれている大尉の遊説は、前にある日蓮像と同じ頃と考えられるので、日清戦争が終結して大尉が移住するまでの間、すなわち明治28(1895)年(筆者6歳)か翌年のことと推察される。
「大変でしたね」
「たまたま岡山県民になったものの、何も知らないのじゃから……調べていくうちに、爺さんとの共感を得た部分もあるぞ」
「はい、それでは、第1部の最終回です」

内山下に医専があった頃、この運動会といえば試験用の動物を連れ出し、吾々が組で引いた連中が走り出すという珍風景なものが人気を呼んでいたことを思い出す。医専は今の二十五銀行のある一帯の地で、病院と並び広大な地域に丸太の柵が並んでおり、学校へ出掛けるには、どちらかもこの柵を回って出掛けねばならぬ退屈な道であった。
当時弟の喬は五つの年下であり、四郎は更に三歳の年下であった。喬の方は中学時代、北側の庭でよく槍をしごいて腕力を鍛えていたということだったが、その様子は見たこともなかった。しかし、幾歳頃のことか、何かの動機で喧嘩をおっ始め、やにわに刀棚に手をかけ、南の庭に飛び降り、杉垣を回って逃げ回るのを追いかけて、縁側に飛び上がったところ、突然現れた老祖父に大声で叱られた上、役所から帰宅した父にも告げられ、無念でたまらなかった。それもこれまで喧嘩はたびたびのことであったが、段々成長し槍術で鍛えた力は自信が出来たためか、弟の方で反抗の力を示したことが無性に気に触れたことが動機らしく思える。次の四郎の方は、体は大きな方であったが、年も違うことであり、あまり喧嘩などした記憶はなく過ごしたことであった。

何にしても、四十年以上以前のことであるが、ここに書き連ねてみると、当時のことどもが次々と頭の中に浮かび出て来るのが、あるいは夢のようでもあり、はたと更に沈思すると、幻のように消え去るようにも思える。この他主立った印象となるものは、蓮正寺で暗い本堂の中を覗いた大曼陀羅や、※1九州北端に建立さるる日蓮上人の模型の見物に、やはり蓮正寺の本堂前で見物したこと、あるいは日清戦争前後だったか、蒙古来襲の大きな絵を幾枚もかかげた公園の※2鶴鳴館に出掛け、生徒一同がその寺に座ったまま※3「四百余州をこぞる……」と唱歌を歌わされたことなどあるが、その前後の時期は判然と分からぬ。

当時の子供といえば、着物など棒縞の手織木綿で紺絣など着る者は余程の上流の者であり、自分など絣の物を着たのは中学に上がった頃、やっと妙な香りのあるまがいものの絣を着せられ、はなはだ得意の気がしたもので、シャツなど棒縞のあるもので白いフランネルなどに仕立てられたものは、これまた上流の子弟で、袖口にふくらんんだ白い物を身につけたことは、相当の年になった頃であったように思える。色々頭に浮かんで来るが、少年時代は比較的無事な歳月を重ねて来たことは事実で、父が引退後、段々年を経るに窮状に陥ったものと見え、家の中も何となく淋しい空気に満たされて来たことであった。
注
 ※1「九州北端に建立さるる日蓮上人の……」
※1「九州北端に建立さるる日蓮上人の……」熊本出身の湯地丈雄が、明治21(1888)年、熊本県警部を辞職後、愛国精神を鼓舞するため、福岡に「元寇記念碑」を立てようと計画、日蓮宗の佐野前励(日管上人)が共鳴して、北条時宗と日蓮の像を作ろうとしたが、他の宗派の反対で実現せず、亀山上皇の像に変更された。
佐野前励は、湯地と行動を別にし、自分達だけで福岡市東公園に単独の日蓮像を建設した。明治25(1892)年に着工、完成は明治37(1904)年。「日清戦争前後だったか」とあるのが、日清戦争は明治27、8年であるから、筆者5、6歳。多分終戦後、筆者が小学校に入った頃ではあるまいか。
※2「鶴鳴館」
岡山後楽園内の建物。右の写真で、右側の屋根が青く見える建物で、襖を取り外すと百畳の座敷になる。
※3「四百余州をこぞるという唱歌」
上の注1にある湯地丈雄の元寇記念碑運動を支援するために、陸軍軍楽隊の永井建子(けんし)が作った「元寇」という歌。明治25(1892)年に発表された。
国難ここに見る 弘安四年夏の頃
なんぞ恐れんわれに 鎌倉男子あり
正義武断の名 一喝して世に示す
 ※4「郡司大尉が千島同盟を提唱……」
※4「郡司大尉が千島同盟を提唱……」千島列島を占有することを提唱するが支援がなく、明治26(1893)年3月20日、自分達で用意した5艘の小さな船で東京から海を北上する。南極探検で有名な白瀬中尉も仲間に加わっていた。途中暴風で18人が死亡、郡司大尉も負傷し、通り掛かった軍艦「磐城」に曳かれて函館入り。結局この「磐城」に便乗して8月31日、占守(シュムシュ)島に到着した。一行はここと色丹(しこたん)に別れて越冬するが、色丹の九名は全員死んでしまう。左下の写真は北海道大学付属図書館に所蔵されているその折の写真。本文の絵がその雰囲気をよく伝えていることが分かる。
その年日清戦争となったため、郡司大尉は白瀬中尉に後を頼んで帰り、白瀬中尉はこの年も越冬、病死者が出たが翌年カムチャッカ半島の資料を手に帰国した。白瀬中尉はその後行動を共にすることはなかった。
日清戦争が終わると郡司大尉は運動を再開、明治29(1896)年、同志とその家族を率いて占守島に移住。ラッコなどの猟と家畜を飼い菜園を作った。明治37(1904)年、日露戦争が勃発すると、19名でカムチャッカへ渡り、住民に捕まって殺される。
 北方領土開拓の英雄とされているが、最初の船は長さ13m、幅3mのカッター船3艘と和船2艘、越冬に関しても十分な調査も準備もなかった様子。だが話は上手で学生らの心を鼓舞したらしく、明治26年3月に学習院中学の3年生達が書いた「郡司大尉を送るの序」も残っている。
北方領土開拓の英雄とされているが、最初の船は長さ13m、幅3mのカッター船3艘と和船2艘、越冬に関しても十分な調査も準備もなかった様子。だが話は上手で学生らの心を鼓舞したらしく、明治26年3月に学習院中学の3年生達が書いた「郡司大尉を送るの序」も残っている。本文に書かれている大尉の遊説は、前にある日蓮像と同じ頃と考えられるので、日清戦争が終結して大尉が移住するまでの間、すなわち明治28(1895)年(筆者6歳)か翌年のことと推察される。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Comments
Freepage List
© Rakuten Group, Inc.