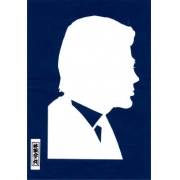【粗筋】
心斎橋でこの道一筋130年、足袋の老舗・布袋屋がイタリア料理店に模様替えするという。親父が引退して息子に継がせるが、自由にやれと言っている。
「何で足袋屋からイタリア料理なんや」
「イタリアに旅(足袋)したんがきっかけらしいわ」
「イタリア料理なら何かメリットあるのか」
「女の子に人気だから……足袋は女の子履かへんもん」
話を聞いている方は、創業230年、呉服の銭亀屋利兵衛の十一代目。番頭が古い人で、今でも男の子は若旦那、女の子はとうはんと呼ぶ。そこへその番頭が飛び込んで来て、十代目の父が倒れたと知らせる。
急いで帰ると、父親は鳴り物入りで物語を始める。五代目は遊び人で店を空け、娘が店番をしているところへ、男が反物を持ち込んで買ってほしいと言う。番頭が追い出そうとして、持っていた反物が散らばってしまう。娘が話を聞くと、病気の母親のために作って売りに出たと言うので、全部買い上げてやる。それから男は反物を作っては買い取ってもらいに通うが、母が亡くなるとやる気を失って反物作りが止まってしまう。半年してようやくやる気を取り戻して品物を売りに来たが、店は五代目が借金を重ねたまま亡くなり、六代目となった娘は無理がたたって寝込んでいた。番頭は、店をたたむので、反物は買えないと言う。今までの反物が売れたのなら、他の店を紹介してもらいたいと言うと、番頭は蔵へ案内した。そこには彼の作った反物が残らず置いてある。親孝行の徳で買ってやったが、とても店に出せる物ではないと言うのだ。
これを聞いた男はおごりを捨て、蔵の反物を小さく切って袋物を作って売るようになった。昼間は小物売り、夜は娘の看病、やがて回復した娘と結ばれて七代目になったのである……十代目はこの暖簾を守ってくれと言い残して息を引き取る。
心斎橋で生まれ育った兄が、妹を連れて来るが、すっかり変わった街並みに時代を感じる。妹の結婚が決まり、老舗の銭亀屋で着物を作ってやろうと思って来たのだが、店がない。この辺りだったが、と探すと、銭亀屋の若旦那とばったり。話を聞くと、今はソウルバーをやっていると言う。
「そんな……先代が亡くなる時、暖簾を守ってくれと言うたと聞いてますが」
「そうや、暖簾は守っとる。これを見とくれ」
店に掛かった暖簾が「ソウルバー銭亀屋」
【成立】
桂文枝(6)の創作落語、第103作目。1997年5月初演。心斎橋の大丸とそごうが心斎橋の文化展を開催し、心斎橋の落語を作ってほしいと依頼された。
【蘊蓄】
私の祖父は横浜の開港記念館(ジャック)を作り、設計士に見込まれて引き抜かれ、東京の松波病院を作るなど、建築家として活動したが、大正時代の第一大戦の景気で物価がどんどん上がるのに公務員給与は据え置き、とうとう大阪へ引っ越す。大丸や十合(そごう)が生まれ、夜の川にネオンサインが映って……という情景を描いている。おかしいのは、翌年公務員給与が見直されて一気に二倍になったそうだ。大阪は建設ラッシュでボーナスに千円(100万円くらいか)が出たと書いている。しかし、仕事は建築現場に来る暴力団まがいのゆすりたかりとの交渉、朝起きると手水鉢の水は真っ黒。空気が悪いと、現在は千葉駅になった場所に引っ越すことになる。戦前に経った千葉県の公立学校は全て祖父の設計、県庁前にある羽衣の松も、祖父のアイディアで作られたことが書かれている。
-
落語「は」の9:羽織(はおり) 2025.11.14
-
落語「は」の8:HOW TO プレイボー… 2025.11.13
-
落語「は」の7:羽団扇(はうちわ) 2025.11.12
PR
Keyword Search
Comments
Freepage List