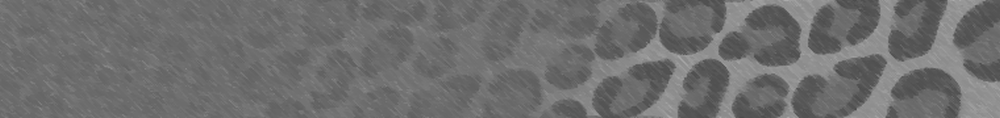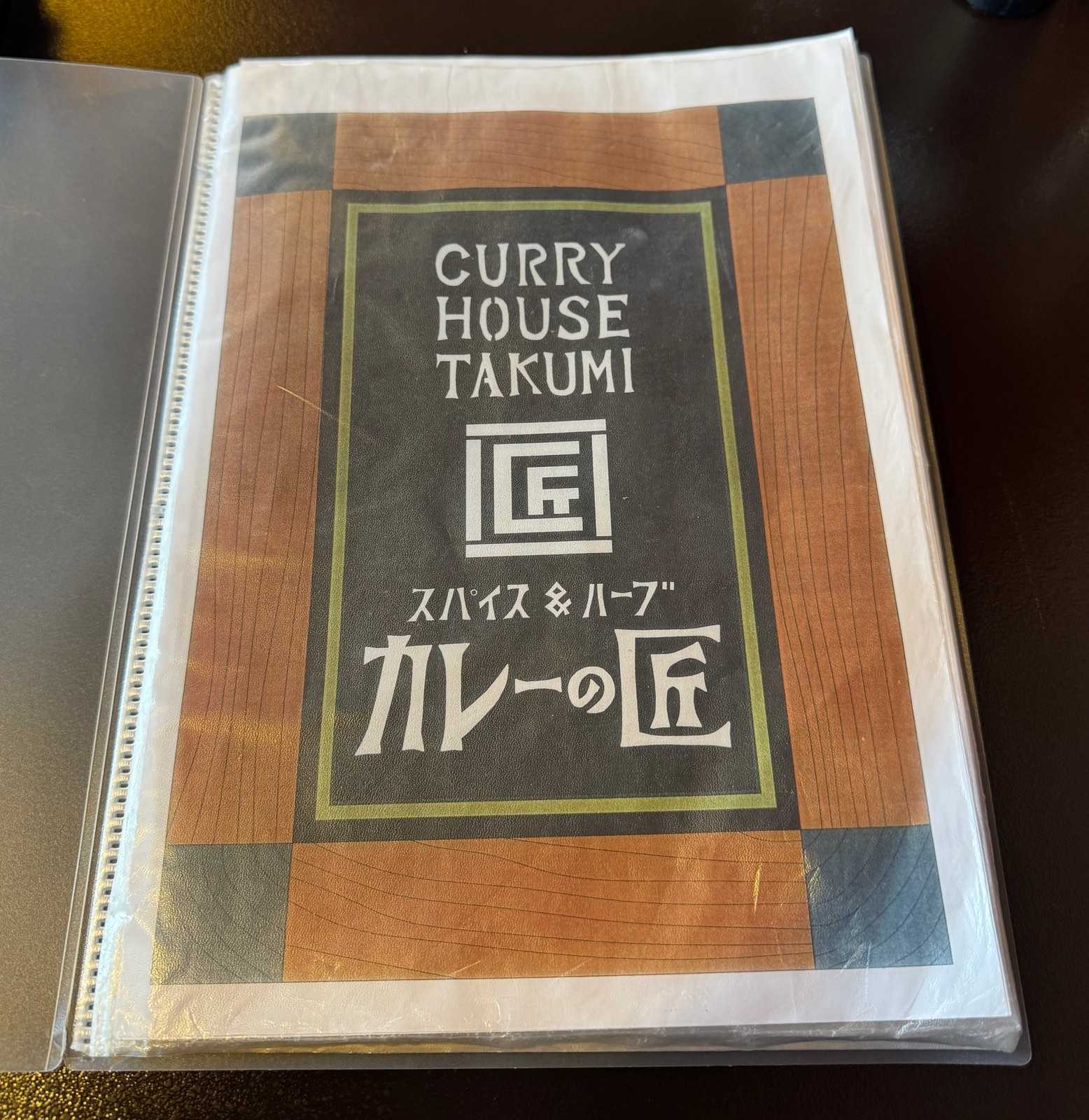2010年10月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
封印。
取り急ぎ。「封印」してみます。ちょっと別の次元に行ってきます。また戻ってくるかもしれませんし、戻ってこないかもしれませんが、取り急ぎこの場所にこの日記があった事は事実ですのでー。では、SEE YA IN THE PIT!
2010.10.09
-

1-3 意外に古いめっきの歴史
めっきとは、日本語であり「塗金」→「滅金」→「鉱金」→「鍍金」→「メッキ」→「めっき」と変化してきたようです。 一般的には「メッキ」と呼ばれたりインターネットで検索をされるようですが、現在のJIS規格では「めっき」が正式名称となります。 めっきの歴史は相当古いです。文献等によりますと、西暦紀元前1500年すずめっきがメソポタミア北部のアッシリアで行われたとの記録があるそうです。日本でもっとも古いめっきと考えられているものは、中国から仏教が伝わったときに仏像や仏具にめっきがしてあったともいわれています。有名なのは、奈良の大仏様をめっきするのに、金アマルガム(水銀と金の合金)を使用したものです。大仏様がピカピカの金めっきをされたものです。現在のわが国の電気めっきは江戸時代末期にオランダから伝来され、薩摩藩の島津斉彬公が電池を用いて金、銀めっきをしたと伝えられております。
2010.10.09
-

1-2 そもそもめっきとは何か?
めっきとは、金属を電気、無電解、置換、化成などの方法を用いて、 素材に析出させる方法、若しくは素材を酸化させる方法をいいます。簡単にいいますと、めっきしたい製品に金属をくっつける、またはめっきしたい製品にそれ以上錆びないような皮膜をくっつける処理のことを指します。 電気めっき:めっき処理液に電気を流し電気分解による析出を利用してめっきしたい製品へ金属皮膜をつける方法。 無電解めっき:めっき処理液に電気を流さず行うめっき方法で化学めっきともいいます。 置換めっき:置換反応(イオン化傾向の大きな金属が解けてイオン化傾向の小さな金属…金や銀などが析出)を利用しためっき方法。 化成めっき:化学的な処理によって金属表面(めっきしたい表面)に酸化膜や無機塩の皮膜を形成し、防錆や塗装の下地処理として利用されるめっき。皮膜の厚さはごく薄いです。
2010.10.08
-

1-1 めっきはこんなところに使われている
めっきは、意外と知られておりませんが、私たちの生活の中では身近に使用されており、パソコン、携帯電話、自動車、二輪車、日用雑貨、家電製品などの部品に利用されております。めっきの種類は多種なため、目的に応じた処理をするのが一般的です。例えば、製品を錆びないようにするめっき、硬さを高くするめっき、滑り性を向上させるめっき、導電性を向上させるめっき、美観性を向上させるめっきなどがございます。 そういう意味では私達の生活の中に溶け込んでいるのが、めっきでございます。めっき技術が存在しないと現在の私達の生活がなりたたないといっても過言ではございません。「めっきが剥がれる」という嘘がばれたときの場合の例えがございますが、めっきはそんなに簡単に剥がれる技術ではございませんので。嘘ではありません。ホンモノなのです。
2010.10.07
全4件 (4件中 1-4件目)
1