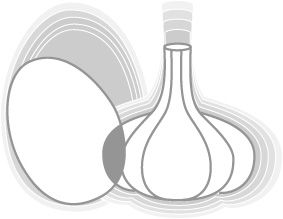PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 食べ物あれこれ(51665)
カテゴリ: 食事
お新香(おしんこ)と言えば漬物の事。ちょっと不思議な響きと思ってしまうのですが、漬物の事を「香の物」と呼ぶ事があるので、そこから派生した言葉という予想はできてしまいます。
漬物は塩や酢、味噌、糠などに野菜などを文字通り漬け込んだ物で、日本の食卓には古くから登場していました。各地に地域性豊かな独自の漬物があり、素材、漬け方にも多くのバリエーションがあります。
漬物は日本の食卓には欠かせない食べ物で、イモ類を除くほとんどの野菜類が漬物の素材として使われています。イモ類が使われなかった理由としては、漬物が生の野菜を素材とする事から、イモ類が含むでんぷんが加熱されないと消化に適した状態にならない事に関係しているのではと考えてしまいます。
野菜は漬物にする事で、野菜が持っていたアクや苦味が抜けて美味しさが増すという一面を持っています。また、野菜の栄養は皮やヘタに偏在している事が多いので、皮やヘタを含めた野菜全体を食べられる状態にする漬物は優れた野菜の食べ方とも言えます。
日本で漬物が作られるようになったのは、野菜の栽培が伝えられてからと言います。そうなると縄文時代まで遡る事となるのですが、当初は野菜の保存方法として伝えられたと考えられます。多量の塩に漬け込んでおけば腐敗菌などの雑菌の発生を抑え、野菜類を長期にわたって保存する事が可能となります。
平安時代に貴族の遊びとして香を焚いてその種類を当てたり、同じ香りがするものを探すという遊びが流行します。長時間、さまざまなにおいを嗅ぐために嗅覚が麻痺してきて、においの違いが判りにくくなってくるので、休憩を兼ねて嗅覚をリセットするために漬物が食べられるようになり、それまでは塩漬けが主流だったものがより香り高い味噌漬けが好まれ、「香の物」と呼べれています。
その後、鎌倉時代から室町時代にかけて茄子や瓜が素材として主流だったものが、さまざまな野菜類が使われるようになり、江戸時代に入ると調味した糠に漬け込む「糠漬け」が登場します。そうした新しい製法の漬物を従来の「香の物」に対し、新しい香の物という事で「お新香」と呼ぶようになり、今日では漬物全体を指す言葉ともなっています。
漬物は塩や酢、味噌、糠などに野菜などを文字通り漬け込んだ物で、日本の食卓には古くから登場していました。各地に地域性豊かな独自の漬物があり、素材、漬け方にも多くのバリエーションがあります。
漬物は日本の食卓には欠かせない食べ物で、イモ類を除くほとんどの野菜類が漬物の素材として使われています。イモ類が使われなかった理由としては、漬物が生の野菜を素材とする事から、イモ類が含むでんぷんが加熱されないと消化に適した状態にならない事に関係しているのではと考えてしまいます。
野菜は漬物にする事で、野菜が持っていたアクや苦味が抜けて美味しさが増すという一面を持っています。また、野菜の栄養は皮やヘタに偏在している事が多いので、皮やヘタを含めた野菜全体を食べられる状態にする漬物は優れた野菜の食べ方とも言えます。
日本で漬物が作られるようになったのは、野菜の栽培が伝えられてからと言います。そうなると縄文時代まで遡る事となるのですが、当初は野菜の保存方法として伝えられたと考えられます。多量の塩に漬け込んでおけば腐敗菌などの雑菌の発生を抑え、野菜類を長期にわたって保存する事が可能となります。
平安時代に貴族の遊びとして香を焚いてその種類を当てたり、同じ香りがするものを探すという遊びが流行します。長時間、さまざまなにおいを嗅ぐために嗅覚が麻痺してきて、においの違いが判りにくくなってくるので、休憩を兼ねて嗅覚をリセットするために漬物が食べられるようになり、それまでは塩漬けが主流だったものがより香り高い味噌漬けが好まれ、「香の物」と呼べれています。
その後、鎌倉時代から室町時代にかけて茄子や瓜が素材として主流だったものが、さまざまな野菜類が使われるようになり、江戸時代に入ると調味した糠に漬け込む「糠漬け」が登場します。そうした新しい製法の漬物を従来の「香の物」に対し、新しい香の物という事で「お新香」と呼ぶようになり、今日では漬物全体を指す言葉ともなっています。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.