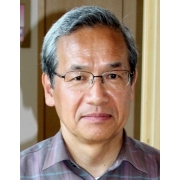PR
X
Category
Calendar
Comments
しろうと自然科学者@ Re[1]:キツネノカミソリの花が咲き始めました。ヒガンバナは、地温が20℃になると花芽が分化して発達し開花するそうですが、キツネノカミソリはどのようにして季節を感じるのでしょうか。7月下旬のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(07/31)
蕗さん8256さんへ コメントありがとうござ…
蕗さん8256
@ Re:キツネノカミソリの花が咲き始めました。ヒガンバナは、地温が20℃になると花芽が分化して発達し開花するそうですが、キツネノカミソリはどのようにして季節を感じるのでしょうか。7月下旬のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(07/31)
猛暑続きですが 狐のカミソリの花が 咲…
しろうと自然科学者@ Re[1]:ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花、たわわに実っているクロガネモチの果実。1月のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(01/30)
蕗さん8256さんへ コメントありがとうござ…
蕗さん8256
@ Re:ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花、たわわに実っているクロガネモチの果実。1月のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(01/30)
日本水仙 ソシンロウバイの花が 奇麗に…
あい変わらず! 花は…
New!
だいちゃん0204さん
季節の花 オオカモ… himekyonさん
himekyonさん
都内公園カワセミ日… ★黒鯛ちゃんさん
★黒鯛ちゃんさん
50日ぶりの小さな庭 hiromomoさん
M.KEIZOの「花のある… M.KEIZOさん
季節の花 オオカモ…
 himekyonさん
himekyonさん都内公園カワセミ日…
 ★黒鯛ちゃんさん
★黒鯛ちゃんさん50日ぶりの小さな庭 hiromomoさん
M.KEIZOの「花のある… M.KEIZOさん
Keyword Search
▼キーワード検索
テーマ: 楽天写真館(354945)
カテゴリ: 山野草と樹木
☆ツタバウンラン。この植物も、図鑑などに載っていないので、名前を調べるのに苦労しました。
☆ツタバウンランは、ヨーロッパ原産で、大正時代に観賞用として渡来したものが野生化したものです。北海道から本州に生えているゴマノハグサ科ツタバウンラン属の帰化植物。
☆花の形は、ゴマノハグサ科のムラサキサギゴケやトキワハゼに似ています。


☆ツタバウンラン(蔦葉海蘭)の名は、蔓性の蔦の葉のようなウンラン(海蘭)から。ウンラン(海蘭)は、北海道から本州・四国の海岸に咲くゴマノハグサ科の植物で、花の形が蘭に似ているので海(海岸)の蘭と名付けられたそうです。
☆スイカズラ。
☆スイカズラは、日本全国に分布し、山野に生える蔓性のスイカズラ科スイカズラ属の植物。つぼみは筒状で(写真左上に4本見える)、花は白・黄色。



☆スイカズラ(吸い葛)の名は、古くに花を口にくわえて甘い蜜を吸っていたことから。
☆ツルニチニチソウ。
☆ツルニチニチソウは、ヨーロッパ原産で、観賞用に栽培されるキョウチクトウ科ツルニチニチソウ属の帰化植物。


☆5月18日・19日に「ムラサキカタバミ」として紹介したのは、正しくは「イモカタバミ」でした。お詫びして訂正します。2種類の似た種があることを、知りませんでした。
☆ウォーキングコースでは、イモカタバミがあちこちで咲いています。ムラサキカタバミは、見かけ次第、紹介することにします。
☆イモカタバミは、南アメリカ原産で、江戸時代末期に観賞用として導入されたカタバミ科カタバミ属の帰化植物。現在では、野生化しています。

☆イモカタバミ(芋片喰)の名は、地下に芋状の塊茎(鱗茎)があるカタバミから。
☆イモカタバミは、花の色が濃く、花弁中央部も同じように色が濃く、雄しべの葯の色は黄色です。いっぽう、ムラサキカタバミは、花の色が薄く、花弁中央部はさらに色が薄く、雄しべの葯の色は白です。2種あることを知っていれば、簡単に区別して確認できます。
☆ツタバウンランは、ヨーロッパ原産で、大正時代に観賞用として渡来したものが野生化したものです。北海道から本州に生えているゴマノハグサ科ツタバウンラン属の帰化植物。
☆花の形は、ゴマノハグサ科のムラサキサギゴケやトキワハゼに似ています。


☆ツタバウンラン(蔦葉海蘭)の名は、蔓性の蔦の葉のようなウンラン(海蘭)から。ウンラン(海蘭)は、北海道から本州・四国の海岸に咲くゴマノハグサ科の植物で、花の形が蘭に似ているので海(海岸)の蘭と名付けられたそうです。
☆スイカズラ。
☆スイカズラは、日本全国に分布し、山野に生える蔓性のスイカズラ科スイカズラ属の植物。つぼみは筒状で(写真左上に4本見える)、花は白・黄色。



☆スイカズラ(吸い葛)の名は、古くに花を口にくわえて甘い蜜を吸っていたことから。
☆ツルニチニチソウ。
☆ツルニチニチソウは、ヨーロッパ原産で、観賞用に栽培されるキョウチクトウ科ツルニチニチソウ属の帰化植物。


☆5月18日・19日に「ムラサキカタバミ」として紹介したのは、正しくは「イモカタバミ」でした。お詫びして訂正します。2種類の似た種があることを、知りませんでした。
☆ウォーキングコースでは、イモカタバミがあちこちで咲いています。ムラサキカタバミは、見かけ次第、紹介することにします。
☆イモカタバミは、南アメリカ原産で、江戸時代末期に観賞用として導入されたカタバミ科カタバミ属の帰化植物。現在では、野生化しています。

☆イモカタバミ(芋片喰)の名は、地下に芋状の塊茎(鱗茎)があるカタバミから。
☆イモカタバミは、花の色が濃く、花弁中央部も同じように色が濃く、雄しべの葯の色は黄色です。いっぽう、ムラサキカタバミは、花の色が薄く、花弁中央部はさらに色が薄く、雄しべの葯の色は白です。2種あることを知っていれば、簡単に区別して確認できます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[山野草と樹木] カテゴリの最新記事
-
ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花… 2023.01.30 コメント(2)
-
ウリノキ、ムヨウラン、ギンリョウソウ、… 2022.06.10 コメント(2)
-
咲き始めたイナモリソウ、ホシザキイナモ… 2022.05.27 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.