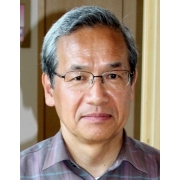PR
X
Category
Calendar
Comments
しろうと自然科学者@ Re[1]:キツネノカミソリの花が咲き始めました。ヒガンバナは、地温が20℃になると花芽が分化して発達し開花するそうですが、キツネノカミソリはどのようにして季節を感じるのでしょうか。7月下旬のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(07/31)
蕗さん8256さんへ コメントありがとうござ…
蕗さん8256
@ Re:キツネノカミソリの花が咲き始めました。ヒガンバナは、地温が20℃になると花芽が分化して発達し開花するそうですが、キツネノカミソリはどのようにして季節を感じるのでしょうか。7月下旬のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(07/31)
猛暑続きですが 狐のカミソリの花が 咲…
しろうと自然科学者@ Re[1]:ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花、たわわに実っているクロガネモチの果実。1月のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(01/30)
蕗さん8256さんへ コメントありがとうござ…
蕗さん8256
@ Re:ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花、たわわに実っているクロガネモチの果実。1月のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(01/30)
日本水仙 ソシンロウバイの花が 奇麗に…
都内公園・カワセミ♂…
 New!
★黒鯛ちゃんさん
New!
★黒鯛ちゃんさん
1泊2日は早いなぁ… New!
だいちゃん0204さん
New!
だいちゃん0204さん
日本の野生蘭 オオ… New!
himekyonさん
New!
himekyonさん
50日ぶりの小さな庭 hiromomoさん
M.KEIZOの「花のある… M.KEIZOさん
 New!
★黒鯛ちゃんさん
New!
★黒鯛ちゃんさん1泊2日は早いなぁ…
 New!
だいちゃん0204さん
New!
だいちゃん0204さん日本の野生蘭 オオ…
 New!
himekyonさん
New!
himekyonさん50日ぶりの小さな庭 hiromomoさん
M.KEIZOの「花のある… M.KEIZOさん
Keyword Search
▼キーワード検索
カテゴリ: 雑感(プロフィール・思い・その他)
☆夕焼けについて一度調べてみたいと思っていました。調べてみると、構造色というもので、光の波長や微細構造による発色現象であることがわかりました。

◎微粒子などによる散乱―夕焼け、青空、白い雲、牛乳
☆夕焼けの色は、太陽光が大気中の窒素分子や酸素分子によって散乱されるために起こるそうです。夕方は大気を通過する距離が日中と比べて長くなり、波長が長い黄・橙・赤などの光線が散乱され、太陽が沈む方向の空が赤く見えることになるそうです。波長が短い青い光線は、障害物に衝突・吸収されるなどの要因で地表に届きにくくなるそうです。

☆青空も同じ現象で、光の波長より小さな粒子による散乱現象は「レイリー散乱」と呼ばれるそうです。日中は、波長が短い青い光線が散乱され、空全体が青く見えるそうです。波長が長い赤い光線などは、大気中を通過してしまい、太陽の大きさの範囲に収まってしまうそうです。

☆雲が白く見えるのは「ミー散乱」によるもので、これは光の波長と同程度の粒子による光の散乱だそうです。

☆牛乳が白く見えるのは、脂肪のコロイドが光を散乱させるためだそうです。

◎多層膜による干渉―甲虫類の金属光沢
☆多層膜による干渉とは、薄い膜を何層も重ねたような構造による光の干渉で、甲虫類の金属光沢のような色はキチン質の層構造によるものだそうです。カナブンは、見る角度によって違った金属光沢に見えます。

☆体に青い金属光沢があるハグロトンボのオスの体色も、同じ原理なのでしょうか。

◎微細な溝・突起などによる干渉―コンパクトディスクの虹色
☆コンパクトディスクでは、アルミ薄幕表面に刻まれた凹凸が光を干渉するので記録面側が虹色に見えるそうです。カワセミの羽の鮮やかな色も、羽の色素によるものではなく、羽毛にある微細な構造によって見えるものだそうです。

☆夕焼けを科学しようとしたのですが、思わぬところに広がってしまいました。本日の日記の内容は、「ウィキペディアフリー百科事典」を参考にさせていただきました。

◎微粒子などによる散乱―夕焼け、青空、白い雲、牛乳
☆夕焼けの色は、太陽光が大気中の窒素分子や酸素分子によって散乱されるために起こるそうです。夕方は大気を通過する距離が日中と比べて長くなり、波長が長い黄・橙・赤などの光線が散乱され、太陽が沈む方向の空が赤く見えることになるそうです。波長が短い青い光線は、障害物に衝突・吸収されるなどの要因で地表に届きにくくなるそうです。

☆青空も同じ現象で、光の波長より小さな粒子による散乱現象は「レイリー散乱」と呼ばれるそうです。日中は、波長が短い青い光線が散乱され、空全体が青く見えるそうです。波長が長い赤い光線などは、大気中を通過してしまい、太陽の大きさの範囲に収まってしまうそうです。

☆雲が白く見えるのは「ミー散乱」によるもので、これは光の波長と同程度の粒子による光の散乱だそうです。

☆牛乳が白く見えるのは、脂肪のコロイドが光を散乱させるためだそうです。

◎多層膜による干渉―甲虫類の金属光沢
☆多層膜による干渉とは、薄い膜を何層も重ねたような構造による光の干渉で、甲虫類の金属光沢のような色はキチン質の層構造によるものだそうです。カナブンは、見る角度によって違った金属光沢に見えます。

☆体に青い金属光沢があるハグロトンボのオスの体色も、同じ原理なのでしょうか。

◎微細な溝・突起などによる干渉―コンパクトディスクの虹色
☆コンパクトディスクでは、アルミ薄幕表面に刻まれた凹凸が光を干渉するので記録面側が虹色に見えるそうです。カワセミの羽の鮮やかな色も、羽の色素によるものではなく、羽毛にある微細な構造によって見えるものだそうです。

☆夕焼けを科学しようとしたのですが、思わぬところに広がってしまいました。本日の日記の内容は、「ウィキペディアフリー百科事典」を参考にさせていただきました。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[雑感(プロフィール・思い・その他)] カテゴリの最新記事
-
東の空にあざやかな朝焼けが広がりました… 2020.11.20 コメント(2)
-
4回にわたる気仙沼大島訪問、そして植物観… 2020.02.23
-
ブログ累計アクセス件数が、7年7か月間で4… 2019.10.14
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.