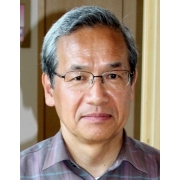PR
X
Category
Calendar
Comments
しろうと自然科学者@ Re[1]:キツネノカミソリの花が咲き始めました。ヒガンバナは、地温が20℃になると花芽が分化して発達し開花するそうですが、キツネノカミソリはどのようにして季節を感じるのでしょうか。7月下旬のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(07/31)
蕗さん8256さんへ コメントありがとうござ…
蕗さん8256
@ Re:キツネノカミソリの花が咲き始めました。ヒガンバナは、地温が20℃になると花芽が分化して発達し開花するそうですが、キツネノカミソリはどのようにして季節を感じるのでしょうか。7月下旬のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(07/31)
猛暑続きですが 狐のカミソリの花が 咲…
しろうと自然科学者@ Re[1]:ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花、たわわに実っているクロガネモチの果実。1月のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(01/30)
蕗さん8256さんへ コメントありがとうござ…
蕗さん8256
@ Re:ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花、たわわに実っているクロガネモチの果実。1月のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(01/30)
日本水仙 ソシンロウバイの花が 奇麗に…
1泊2日は早いなぁ…
 New!
だいちゃん0204さん
New!
だいちゃん0204さん
日本の野生蘭 オオ… New!
himekyonさん
New!
himekyonさん
菜園ニュース:夏実… ★黒鯛ちゃんさん
★黒鯛ちゃんさん
50日ぶりの小さな庭 hiromomoさん
M.KEIZOの「花のある… M.KEIZOさん
 New!
だいちゃん0204さん
New!
だいちゃん0204さん日本の野生蘭 オオ…
 New!
himekyonさん
New!
himekyonさん菜園ニュース:夏実…
 ★黒鯛ちゃんさん
★黒鯛ちゃんさん50日ぶりの小さな庭 hiromomoさん
M.KEIZOの「花のある… M.KEIZOさん
Keyword Search
▼キーワード検索
カテゴリ: 山野草と樹木
☆雌性先熟に続けて、自然観察の中から雄性先熟の植物を調べてみると、20種類もありました。3回に分けて紹介してきました。雄性先熟とは、両性花で雄性が先に熟して現れる植物を雄性先熟といい、自家受粉を避けるための植物の仕組みです。
☆オクトリカブトは、北海道と本州の中部地方以北に生えるキンポウゲ科トリカブト属の多年草です。(2013年9月3日撮影)。

☆オクトリカブトは雄性先熟で、雄しべが外側にしおれており真ん中に薄黄緑色の雌しべが伸びてきているようです。(2013年9月3日撮影)。

☆バラモンギクは、ヨーロッパ原産で、キク科バラモンジン属の帰化植物です。バラモンギクの花(花は全て舌状花)では、キク科植物の特徴である集約雄蕊や雄性先熟を、わかりやすく観察できます。バラモンギクの花の中心部です。舌状花を詳しく見ると、5本の雄しべが集約雄蕊という葯が合着した1本の筒になっており、そこに熟した花粉が詰まっています。写真では、花粉が押し出されてきているのがわかります。(2012年5月20日撮影)。

☆その筒の中から柱頭が閉じたままの雌しべが突き抜けて出て、花柱の先端が2つに開いて他の花の花粉を受粉します。雌しべ柱頭が開くころには、その花の花粉は落ちてしまっており、自家受粉を避ける仕組みです。(2012年5月31日撮影)。

☆ヒマワリは、北アメリカ原産で日本には17世紀に渡来したキク科ヒマワリ属の1年草です。ヒマワリの花は、筒状花が外側から順に咲き、雄性期から雌性期へと移り変わっていきます。内側(左側)は雄性期で花冠から伸びる集約雄蕊が見え、外側(右側)は雌性期になっており先端が2裂する雌しべ花柱が伸びているのが見えます。(2014年7月18日撮影)。

☆ヤツデは、関東以西の海岸近くの森林周辺に自生するウコギ科ヤツデ属の常緑低木です。これは開花前期(雄性期)で小さい5枚の花びらと5本の雄しべがあります。(2014年11月14日撮影)。

☆ヤツデの花びらと雄しべが落ちると、雌しべの柱頭が伸びて開花後期(雌性期)になります。花の中央には、5本の雌しべ柱頭が伸びて広がっているそうですが、本数まではわかりません。(2014年11月14日撮影)。

☆ヤブガラシ(ヤブカラシ)は、北海道西南部以南に分布し、道端、林縁や荒れ地に生えるブドウ科ヤブカラシ(ヤブガラシ)属の多年草です。左側の花にある薄緑色の4枚の花びらと4本の雄しべは開花後半日ほどで散ってしまい、雌しべが中央に立っている橙色やピンク色の花盤(盤状の花托)が残る雌性期になります。(2013年6月24日撮影)。


☆ツタは、ブドウ科ツタ属の蔓性落葉低木です。5枚の花びらと5本の雄しべはヤブガラシと同じように早くに落ちてしまい、雌しべだけの雌性期になります。(2014年7月20日撮影)。

☆雌性先熟とともに、雄性先熟を3回に分けて紹介しました。
☆オクトリカブトは、北海道と本州の中部地方以北に生えるキンポウゲ科トリカブト属の多年草です。(2013年9月3日撮影)。

☆オクトリカブトは雄性先熟で、雄しべが外側にしおれており真ん中に薄黄緑色の雌しべが伸びてきているようです。(2013年9月3日撮影)。

☆バラモンギクは、ヨーロッパ原産で、キク科バラモンジン属の帰化植物です。バラモンギクの花(花は全て舌状花)では、キク科植物の特徴である集約雄蕊や雄性先熟を、わかりやすく観察できます。バラモンギクの花の中心部です。舌状花を詳しく見ると、5本の雄しべが集約雄蕊という葯が合着した1本の筒になっており、そこに熟した花粉が詰まっています。写真では、花粉が押し出されてきているのがわかります。(2012年5月20日撮影)。

☆その筒の中から柱頭が閉じたままの雌しべが突き抜けて出て、花柱の先端が2つに開いて他の花の花粉を受粉します。雌しべ柱頭が開くころには、その花の花粉は落ちてしまっており、自家受粉を避ける仕組みです。(2012年5月31日撮影)。

☆ヒマワリは、北アメリカ原産で日本には17世紀に渡来したキク科ヒマワリ属の1年草です。ヒマワリの花は、筒状花が外側から順に咲き、雄性期から雌性期へと移り変わっていきます。内側(左側)は雄性期で花冠から伸びる集約雄蕊が見え、外側(右側)は雌性期になっており先端が2裂する雌しべ花柱が伸びているのが見えます。(2014年7月18日撮影)。

☆ヤツデは、関東以西の海岸近くの森林周辺に自生するウコギ科ヤツデ属の常緑低木です。これは開花前期(雄性期)で小さい5枚の花びらと5本の雄しべがあります。(2014年11月14日撮影)。

☆ヤツデの花びらと雄しべが落ちると、雌しべの柱頭が伸びて開花後期(雌性期)になります。花の中央には、5本の雌しべ柱頭が伸びて広がっているそうですが、本数まではわかりません。(2014年11月14日撮影)。

☆ヤブガラシ(ヤブカラシ)は、北海道西南部以南に分布し、道端、林縁や荒れ地に生えるブドウ科ヤブカラシ(ヤブガラシ)属の多年草です。左側の花にある薄緑色の4枚の花びらと4本の雄しべは開花後半日ほどで散ってしまい、雌しべが中央に立っている橙色やピンク色の花盤(盤状の花托)が残る雌性期になります。(2013年6月24日撮影)。


☆ツタは、ブドウ科ツタ属の蔓性落葉低木です。5枚の花びらと5本の雄しべはヤブガラシと同じように早くに落ちてしまい、雌しべだけの雌性期になります。(2014年7月20日撮影)。

☆雌性先熟とともに、雄性先熟を3回に分けて紹介しました。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[山野草と樹木] カテゴリの最新記事
-
ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花… 2023.01.30 コメント(2)
-
ウリノキ、ムヨウラン、ギンリョウソウ、… 2022.06.10 コメント(2)
-
咲き始めたイナモリソウ、ホシザキイナモ… 2022.05.27 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.