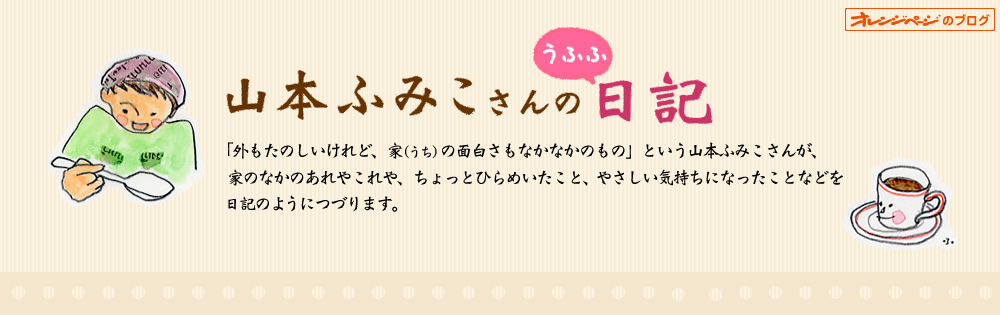サイド自由欄

随筆家。1958年北海道生まれ。つれあいと娘3人との5人暮らし。ふだんの生活をさりげなく描いたエッセイで読者の支持を集める。著書に『片づけたがり』 『おいしい くふう たのしい くふう 』、『こぎれい、こざっぱり』、『人づきあい学習帖』、『親がしてやれることなんて、ほんの少し』(ともにオレンジページ)、『家族のさじかげん』(家の光協会)など。
カレンダー
2025/10
2025/09
2025/07
キーワードサーチ
「こんなもの、捨ててしまいなさいよ、」
「どうして、」
「あんたが持っているには、ふさわしくない、高いの、安いの、というこ
とではありませんよ、僕がいやなんだ、」
「あなたのものでもあるまいし、」
「……そんなことは萬萬ないけれど、もしもだね、あなたの亡いあとに、
誰かが、この道具を見るとしよう……そうすると、あなたの持っている
いい品まで、下る……」
多江は、どきりとしました。
いきなり、引用で気を引こうなどとは、我ながら、狡(こす)いことだ。
これは、「中里恒子」著作の、『時雨の記』(文春文庫)の一節である。
書架のなかの単行本も文庫本も、カヴァの背がいつしか擦れて、「時雨の記」という題名さえ読めないほどの有様は、この小説を好んでくり返し読んだことをあらわしている。
恋、というと、『時雨の記』に登場する壬生と多江のあいだに通う、気を許し合いながらも、ゆるみのない浄らな慕情を連想する。
一昨日、「中里恒子」について調べる必要があって、久しぶりに『時雨の記』をとり出す。そうなることを怖れてはいたが、やはり気がつくと、その場に坐りこみ、読みふけっているのだった。
掲出のくだりまできて、はっとした。
これまで幾度となく、とくに若いころには、大きくうなずきながら読んだ場面だ。ものの持ち方、選び方を、おしえられていたのである。
しかし、いまのわたしに響くのは、壬生の台詞のなかの、「あなたの亡いあとに、」というところ。
いつごろの頃からだろうか。
親しいひとたちの記憶のほかは、自分の持ちものをできるだけ残したくない、と考えるようになっている。
わたしの、母方の祖父母も、ほとんどものを残さなかった。およそ値打ちのあるもの、祖母の着物や装身具、祖父の鎌倉彫りの作品——これらは、わたしがものごころついたときには、すでにたくさんはなかった。
母によると、「差し上げてしまうのよ、どんどん」とのことだった。
(どんどん……)
あれは、祖父母が亡くなって、数か月が過ぎたころのことだ。
とうとう、ふたりの終の栖(すみか)を手放すことが決まる。
わたしは、祖父母の家に忍びこむつもりで、でかけて行った。
忍びこむなどとは、こそ泥のようだが、わたしにとっても拠所だった家が、手の届かぬものになる前に、ただ、もう一度だけ、という気持ちだった。それで、とつ然、訪ねたのだった。行ってみたら、顔見知りの大工のおじさんがいた。
玄関の引き戸に。台所の壁に。カナリアの小屋のあった板の間に。ごはんを食べた居間のあたりに。そして、祖母の着物をはおってひとり遊んだ奥座敷に。
——触れる。
——「さよなら」と「ありがとう」を言う、こっそり。
台所の棚の隅に、新聞紙にくるまれたものをみつける。そっと開くと、祖父母が好んで使っていた、切り子のコップがふたつ出てきた。
(これ、もらっていいかな、わたしが)
誰にも黙って、コップをふたつ、持ち帰る。
わたしには、祖父母と共に過した時間の記憶だけで、じゅうぶんだけど、このコップがあることは、うれしい。
このコップで酌み交わしながら、大事なひとたちに祖父母の話を聞いてもらう。 このコップを眺めるうち、考えるようになっていく。
残すものは、こういうものを少しだけ、と。

祖父母愛用の、切り子のコップです。

切り子といっても、ざっくりしていて、
それが洒落ているように、わたしには見えます。