テーマ: 京都。(6078)
カテゴリ: この本読みました
【 2020年
5月21日(木)】
今日もOFF日。今日はもともとは、昨日に続いての事務所の予定でしたが、OFF日となりました。孫べったりの一日となりました。
それにしてもインターネットは便利です。孫守りにも重宝します。昔ながらの童謡を教えてあげたいとき、歌詞がうろ覚えでも、インターネットで調べればすぐ分かりますし、動画入りで見せることができます。昔なら本を買ったり、レコードを買ったりとかお金もかかりましたが、今はタダ同然。ついでに私の個人的な趣味で「ゼロ戦隼人」の歌詞も調べたりしました。
シャボン玉をしようとしたとき、液がなくなっているのが分かりました。インターネットで調べると「水5:台所洗剤4:のり1の割合でよく混ぜ合わせるだけ!洗濯のりがなければ、砂糖や蜂蜜、シロップでもOK」とのこと。砂糖や蜂蜜を入れるテクニックは知りませんでした。いやいや何でも分かります。
微々資産推移確認は、昨日2019年版のまとめを完了しました。2016年~2019年の推移まとめと、2020年の現在までの入力に取りかかろうと思いましたが。ここで新たな展開。2015年のデータが改良前のフォーマットで作成済みであることを発見しました。2017年の途中から、忙しすぎて毎月の入力ができなくなって3年経過し、2015年分を作成済みであることさえ認識したなかったのです。結局、改良前のフォームで、2015年、2016年の2年間作成していたということです。改良前フォームの2015年版を改良フォームに改変するより、改良フォームに2015年のデータを貼り付けたほうが簡単だと判断し、今日、その作業を開始しました。
1Gルーターの設定は今日もできずでした。
全国が緊急事態宣言対象になって(京都は特別区域)、図書館は完全クローズになりましたが、幸いにもその前に本を借りており、そのときに借りた本を4冊を順次ご近所「1万歩散歩」で二宮金次郎読みしています。緊急事態宣言下(今日、京都は解除されましたが)、6月8日まで借りたままでいいことになっています。
以前角倉了以についての座学研修がガイド会であったときに、最後の質問タイムで「高瀬川と鴨川の交差はどのように船が横切っていたのか。」と質問しました。講師の方はご存知なかったのですが、聴講者の一人が後で調べてくださって、「鴨川に杭を並べて立てて、それを使って船が横切ったそうだ。」と教えてくだいました。その情報の出展が、「老人が子等に語る 伏見風土記」とのことなので、京都市図書館の図書検索で「伏見風土記」で検索したところ、4冊の本が引っ掛かり、4冊とも借りました。そのうち「老人が子等に語る 伏見風土記」、同左「第二集」、同左「総集」は読み終え、紹介を投稿済みです。⇒ こちら こちら と。 こちら 数日前に残りの1冊「高瀬の舟」を読み終えました。すでに読み終えた3冊同様、コロナ禍巣篭り中、ご近所散歩で二宮金次郎して読みました。
著者 :古川隆
発行所 :北斗書房
発行日 :2004年7月(初版)
ページ数:214ページ A5版
価格 :1,492円+税
私の読書期間:~2020年5月14日頃
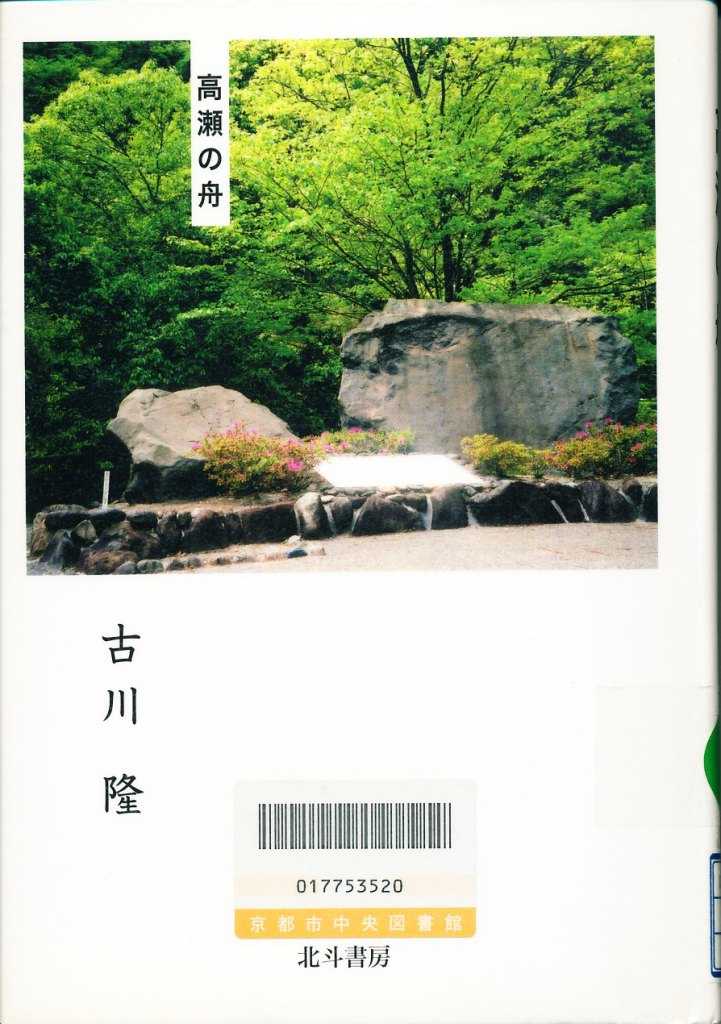
著者は小学校の教諭、最後は校長も務められた方で、アマチュア歴史研究家、あるいは愛好家の方のようで、所謂自費出版のようです。
第1章 高瀬の舟
第2章 伏見・南浜のこと
第3章 西行逍遥
第4章 道元断片
第5章 カタリ
という構成になっています。著者の近く(宇治・伏見)や京都だけではなく、それぞれの表題ゆかりの地を全国や中国にも訪ねた力作です。
第1章は京都の高瀬川から始まって全国の高瀬舟のお話しへと発展します。
京都でのガイドで参考になりそうなことをピックアップします。
・嵐山大堰川沿いの「花のいえ」が最初の角倉屋敷の址であるが、天龍寺の塔頭跡に建てられたものである。
・千光寺には林羅山の「河道主事嵯峨吉田了以翁碑銘」の石碑がある。
・了以の甥、栄可は日蓮宗総本山本圀寺16世の日禛と親交があった。豊臣秀吉は方広寺の落慶で、千僧供養をしたが、日禛は不受不施(法華経の信者以外は布施を受けず、施さず)の宗制を守って出仕に応ぜず。栄可は小倉山の土地を寄進し、日禛は常寂光寺を建てた。日禛に帰依する瀬戸内海賊の旗頭がおり、了以が保津川開削後、備前からの船頭派遣へと繋がった。
・高瀬川にあるH型の堰き止め石は、水量が少ないとき、板を入れて水高を上げるため。板を外すと、水とともに船が進む。
・高瀬川を開削するとき竹田村で耕地がなくなり灌漑用水も減るということで反対が起きたが、了以は損失の場合は弁償するなど誓約書を入れて了解を得た。
・木屋町二条下ルには「綱引き道」が残る。
・大阪冬の陣、夏の陣では、了以の子・素庵が東軍兵站を担当、船をつないだ橋をつくり城を落した。
・維新後、一之舟入や屋敷は織殿(官営織物工場)となり、後刻、二条城内に移築された。東生州の屋敷は山懸有朋の別邸から日銀川田小一郎邸となり、現在はがんこ二条苑。
第4章は道元ゆかりの地
・久我の誕生寺(伝道元誕生地)の西約400mに道元の父・久我通親の墓がある。
・京都国際ホテル(現在、ホテル・ザ・三井京都建設中)は元堀川院の地に建つ。この邸宅をつくったのは藤原基経。堀川院は円融・白河・堀川・鳥羽と4人の天皇の里内裏となった。藤原基経が没すると、堀川院は九条家から久我家へ渡り、久我通親の子通具(もちもと)の邸宅となった。通具は、幼少で父母をなくした道元の養父となった。国際ホテルに道元生誕800年を記念して歌碑が建てられた。
他にもたくさんありますが、このあたりにしておきます。
よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村
今日もOFF日。今日はもともとは、昨日に続いての事務所の予定でしたが、OFF日となりました。孫べったりの一日となりました。
それにしてもインターネットは便利です。孫守りにも重宝します。昔ながらの童謡を教えてあげたいとき、歌詞がうろ覚えでも、インターネットで調べればすぐ分かりますし、動画入りで見せることができます。昔なら本を買ったり、レコードを買ったりとかお金もかかりましたが、今はタダ同然。ついでに私の個人的な趣味で「ゼロ戦隼人」の歌詞も調べたりしました。
シャボン玉をしようとしたとき、液がなくなっているのが分かりました。インターネットで調べると「水5:台所洗剤4:のり1の割合でよく混ぜ合わせるだけ!洗濯のりがなければ、砂糖や蜂蜜、シロップでもOK」とのこと。砂糖や蜂蜜を入れるテクニックは知りませんでした。いやいや何でも分かります。
微々資産推移確認は、昨日2019年版のまとめを完了しました。2016年~2019年の推移まとめと、2020年の現在までの入力に取りかかろうと思いましたが。ここで新たな展開。2015年のデータが改良前のフォーマットで作成済みであることを発見しました。2017年の途中から、忙しすぎて毎月の入力ができなくなって3年経過し、2015年分を作成済みであることさえ認識したなかったのです。結局、改良前のフォームで、2015年、2016年の2年間作成していたということです。改良前フォームの2015年版を改良フォームに改変するより、改良フォームに2015年のデータを貼り付けたほうが簡単だと判断し、今日、その作業を開始しました。
1Gルーターの設定は今日もできずでした。
全国が緊急事態宣言対象になって(京都は特別区域)、図書館は完全クローズになりましたが、幸いにもその前に本を借りており、そのときに借りた本を4冊を順次ご近所「1万歩散歩」で二宮金次郎読みしています。緊急事態宣言下(今日、京都は解除されましたが)、6月8日まで借りたままでいいことになっています。
以前角倉了以についての座学研修がガイド会であったときに、最後の質問タイムで「高瀬川と鴨川の交差はどのように船が横切っていたのか。」と質問しました。講師の方はご存知なかったのですが、聴講者の一人が後で調べてくださって、「鴨川に杭を並べて立てて、それを使って船が横切ったそうだ。」と教えてくだいました。その情報の出展が、「老人が子等に語る 伏見風土記」とのことなので、京都市図書館の図書検索で「伏見風土記」で検索したところ、4冊の本が引っ掛かり、4冊とも借りました。そのうち「老人が子等に語る 伏見風土記」、同左「第二集」、同左「総集」は読み終え、紹介を投稿済みです。⇒ こちら こちら と。 こちら 数日前に残りの1冊「高瀬の舟」を読み終えました。すでに読み終えた3冊同様、コロナ禍巣篭り中、ご近所散歩で二宮金次郎して読みました。
著者 :古川隆
発行所 :北斗書房
発行日 :2004年7月(初版)
ページ数:214ページ A5版
価格 :1,492円+税
私の読書期間:~2020年5月14日頃
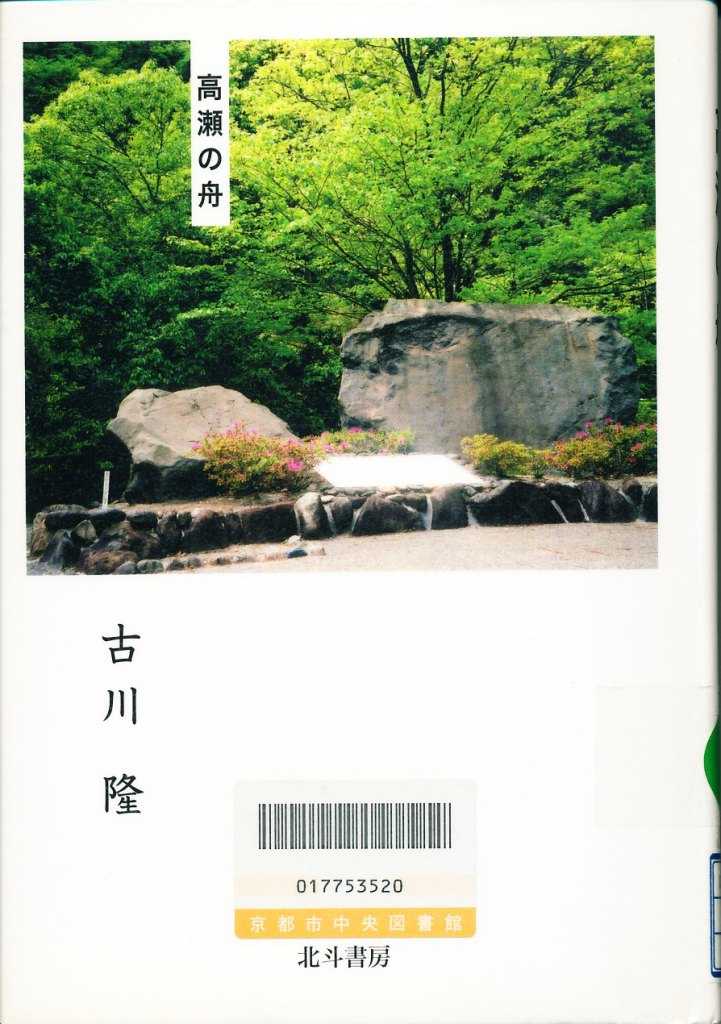
著者は小学校の教諭、最後は校長も務められた方で、アマチュア歴史研究家、あるいは愛好家の方のようで、所謂自費出版のようです。
第1章 高瀬の舟
第2章 伏見・南浜のこと
第3章 西行逍遥
第4章 道元断片
第5章 カタリ
という構成になっています。著者の近く(宇治・伏見)や京都だけではなく、それぞれの表題ゆかりの地を全国や中国にも訪ねた力作です。
第1章は京都の高瀬川から始まって全国の高瀬舟のお話しへと発展します。
京都でのガイドで参考になりそうなことをピックアップします。
・嵐山大堰川沿いの「花のいえ」が最初の角倉屋敷の址であるが、天龍寺の塔頭跡に建てられたものである。
・千光寺には林羅山の「河道主事嵯峨吉田了以翁碑銘」の石碑がある。
・了以の甥、栄可は日蓮宗総本山本圀寺16世の日禛と親交があった。豊臣秀吉は方広寺の落慶で、千僧供養をしたが、日禛は不受不施(法華経の信者以外は布施を受けず、施さず)の宗制を守って出仕に応ぜず。栄可は小倉山の土地を寄進し、日禛は常寂光寺を建てた。日禛に帰依する瀬戸内海賊の旗頭がおり、了以が保津川開削後、備前からの船頭派遣へと繋がった。
・高瀬川にあるH型の堰き止め石は、水量が少ないとき、板を入れて水高を上げるため。板を外すと、水とともに船が進む。
・高瀬川を開削するとき竹田村で耕地がなくなり灌漑用水も減るということで反対が起きたが、了以は損失の場合は弁償するなど誓約書を入れて了解を得た。
・木屋町二条下ルには「綱引き道」が残る。
・大阪冬の陣、夏の陣では、了以の子・素庵が東軍兵站を担当、船をつないだ橋をつくり城を落した。
・維新後、一之舟入や屋敷は織殿(官営織物工場)となり、後刻、二条城内に移築された。東生州の屋敷は山懸有朋の別邸から日銀川田小一郎邸となり、現在はがんこ二条苑。
第4章は道元ゆかりの地
・久我の誕生寺(伝道元誕生地)の西約400mに道元の父・久我通親の墓がある。
・京都国際ホテル(現在、ホテル・ザ・三井京都建設中)は元堀川院の地に建つ。この邸宅をつくったのは藤原基経。堀川院は円融・白河・堀川・鳥羽と4人の天皇の里内裏となった。藤原基経が没すると、堀川院は九条家から久我家へ渡り、久我通親の子通具(もちもと)の邸宅となった。通具は、幼少で父母をなくした道元の養父となった。国際ホテルに道元生誕800年を記念して歌碑が建てられた。
他にもたくさんありますが、このあたりにしておきます。
よろしかったらぽちっとお願いします。
にほんブログ村
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[この本読みました] カテゴリの最新記事
-
【本】朱 第三十五号 2021/01/02
-
【本】平安京講話 (財)京都市生涯学習振… 2020/12/13
-
【本】「稲荷信仰の世界 稲荷祭と神仏習… 2020/12/05
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
カテゴリ未分類
(6)常駐ガイド
(132)同行ガイド
(13)修学旅行ガイド
(51)修学旅行昼食処
(66)研修会
(9)京都ガイド諸活動
(53)私的ガイド
(4)京都研究
(45)京都市内全寺社巡り
(197)京都歩き
(194)美術・博物館
(50)講演会
(21)国内旅行
(6)旧東海道
(65)京都検定1級受検勉強
(239)京都検定1級過去問
(180)京都検定1級問題分析
(9)京都のニュース
(1888)京都のイベント・お祭り案内
(140)京都本
(27)津軽三味線
(31)日本でのゴルフ
(41)懇親会
(61)就職・退職など手続き
(55)吾唯足知~断捨離と必要最低限の買い物
(19)散歩・草花記
(630)健康管理
(24)この本読みました
(35)映画
(33)観劇・観戦
(9)私の十大ニュース
(99)気になったニュース・CM
(317)お天気・気候の話
(12)今日のこと
(170)仕事のこと
(0)癌闘病記
(485)癌治療振り返り
(87)癌治療情報
(593)ドイツの想い出
(209)スイス横断サイクリング
(31)ゴルフとアメリカ生活
(132)アメリカ出張
(36)ワルディ流日米国情比較
(16)母の備忘録
(0)商品レビュー
(3)ブログ記録
(10)食事処、飲み処
(13)京都案内
(218)若冲と応挙
(55)カレンダー
© Rakuten Group, Inc.












