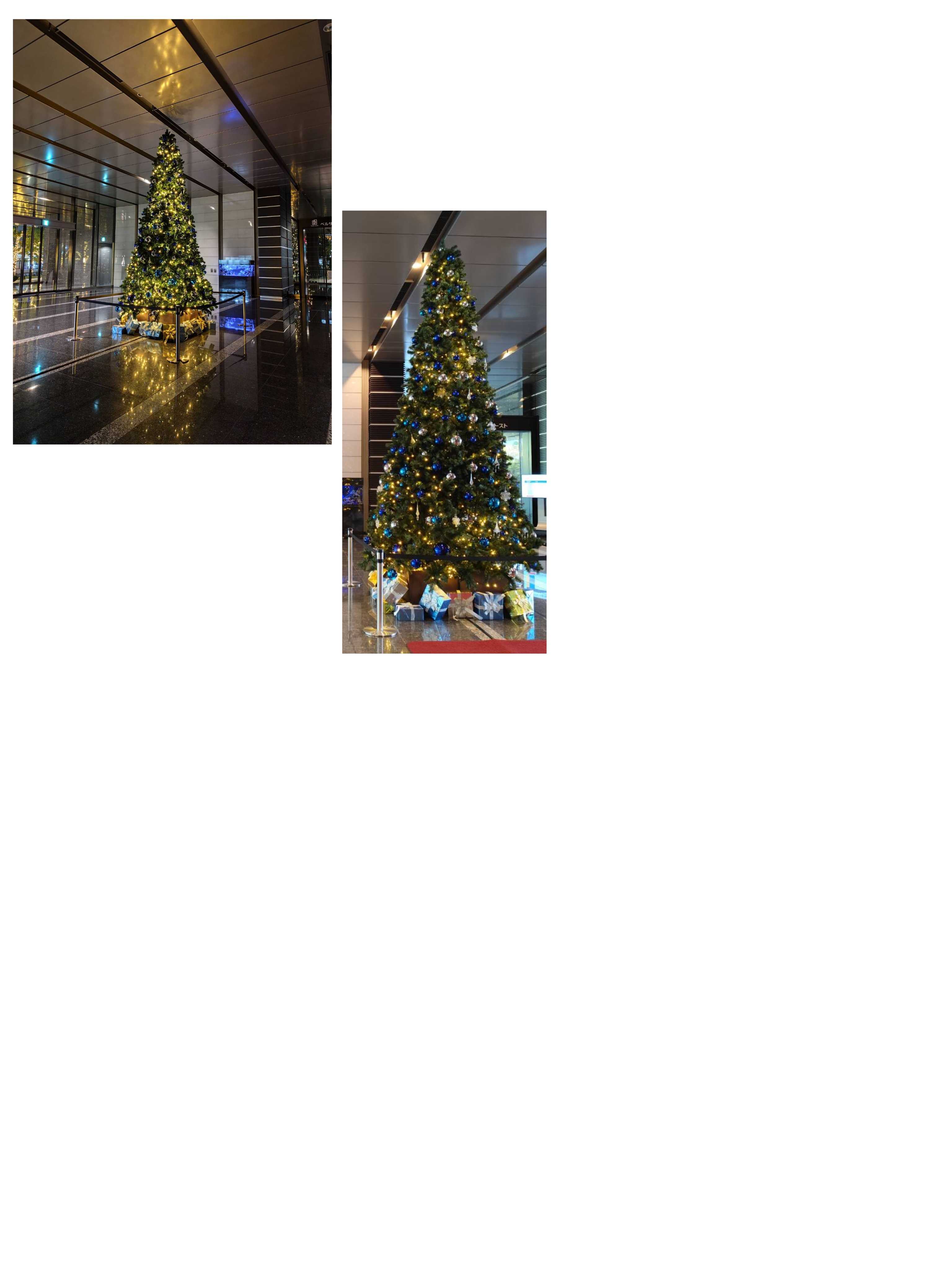全53件 (53件中 1-50件目)
-
倒産→復活
今日は節目の日になった。知る人ぞ知る私は事業失敗経験者だ。その失敗で背負った相手方に対する債務を完済した。10年約定の7年目だった。 今まで機会あるごとに自らの失敗を反省してきた。失敗の原因は色々あるが、つまるところは私の無知(特に法律面)に拠るところが大きい。最後の段階で私が債務を負うことになったのも、私の無知なるが故だ。今ならば大いに対抗する手段を持っているが、そのときは丸腰同然だった。理不尽と思いながらも授業料と思って債務を返済してきた。返済するたびに悔しさを忘れないようにするためでもあった。 実際のところ、一度事業に失敗するとそこからの再起は大変難しい。収入のないところから債務を返済していかなければならないので、その時点をどうやり過ごすかで頭がいっぱいになる。精神的にもおかしくなりそうなものだが、幸い私の周りにはいい人がいっぱいいたことと、両親のおかげで体が丈夫だったことで救われた。 私のように無知が原因で辛い目にあっている人はたくさんいると思う。少しでもそのような人を救えたらと必死に法律を勉強した。元々得意であった会計と経営学がそれに加わり、ようやく武器として使えるようになった。人の無知に付け込んで威張り散らしている大企業の奴らに対抗し、世の中の基盤を支えている大多数の中小企業者の役に立つことが、今の私の生き甲斐になっている。 今日は復活の日になったが、復活といってもマイナスがゼロになっただけのことだ。これから頑張って浮上していかなければならない。もっともっと実力をつけ、中小企業者の役に立つことによって恩返ししていきたい。
2007年02月09日
コメント(0)
-
LLPの会計帳簿
私が所属するLLPは・・・
2007年01月30日
コメント(0)
-
社長の危機意識
社長も人間であるから・・・
2007年01月29日
コメント(0)
-
mixiへ引越し
しばらくの間、ブログはmixiで展開します。
2006年09月01日
コメント(0)
-
最後の一年
今日から30代最後の一年になる。かなり以前から漠然と年代ごとの目標みたいなものがあった。20代は放浪、30代は蓄積、40代は開放、50代は確立、60代は悠々、といったように。20代の放浪は大学を中退したところから始まってそのとおりになった。30代前半で事業の失敗を経験してから、復活を期して知識・能力の蓄積に努めてきた。通過点として行政書士資格を取得したものの、蓄積はまだまだ続く。あと一年で満足な蓄積ができるだろうか。40代で蓄えた力を一気に開放したいので、悔いの無いように蓄積に励みたい。今日は少しショックなこともあった。右手の怪我が一生完治しないと診断された。ただ、これ以上悪化もしないので特に何かを制限されることも言われなかった。自分が我慢できる痛みの範囲内で好きなことをしてもいいのだそうだ。日常生活では多少の不自由があるものの、もともと左手にも不自由さがあるのでバランスがとれたと思っておこう。典型的な田舎のガキであった私は、行動が活発だったためか割と大きな怪我を繰り返してきた。山肌から滑り落ちて頭に穴が開いた。海岸の岩場から転落して膝の皿が浮いてしまった。自己流の練習過多がたたって腰骨が割れてしまい、歩けなくなった。高所から転落して左腕に5ヶ所の骨折を負った。などなど。幸い病気で寝込むようなことはないので、年相応に気をつけることにしよう。
2006年08月30日
コメント(4)
-
廃業ツアー
少々占いじみているが、私にとって市内では鬼門とされる方角(地域)がある。面積的には市内の半分はあろうかという地域なので、ある特定の地区を指しているわけではない。昨日、所用でその方面へ出かけた際、思うことあって地区巡りをしてみた。最初に行った所は、かつて私自身が商売で失敗したところだ。ここにでは他では代え難い多くのことを学んだが、商売としてはあくまでも失敗した。今は違う業種の店舗に変わっていたが、その周辺の他業種はことごとく廃業又は業種転換していた。そこから街道を南下してみると、業種転換もあるものの、やはり廃業が多い。廃業したところはそのまま放ってあるので、荒廃が著しい。しばらく南下したところで西へ向かった。行政書士開業当初、何らかの関わりがあったものの、短期間で付き合いが終わった会社を見に行った。3社訪ねて3社とも無くなっていた。それらの会社がその後どうなったかは全く知らないので、もしかしたら拡張移転したのかもしれないが、当時の状況からはそれをちょっと想像し難い。私の経験上、失敗する経営者に共通する特徴の一つとして「見栄っ張り」がある。経営者個人が身の丈に合わないことをしていたり、周囲にそのような友人等が多くて合わさざるを得ないといったこともある。違った形では、大企業出身者が大企業のやり方をそのまま自らの中小企業に持ち込もうとするものもある。これは開業当初の過大投資となって現れる。悲しい現実だ。廃業の現実を目の当たりにしても落ち込んでいる暇は無い。嬉しい連絡もあった。突然の電話で最近妙に売上が上がって調子がいいという報告だった。この方は破産経験者で、やり直し開業当初は本当に苦労した。生みの苦しみを乗り越えて軌道に乗り始めた頃、徐々に私は関わりを減らしていって、最近は季節ごとの処理を手伝うくらいだ。従って最近の好成績は間違いなく本人の努力の賜物だろう。よかったよかった。
2006年08月26日
コメント(2)
-
営業を客観的に見る
ある二つの会社にそれぞれ別の営業が入ってきたのを、たまたま傍で見る機会があった。一つ目はDMの内容が功を奏し、その後の電話で社長とアポを取り付けたパターン。二つ目は高度な知識を持ちながら社長のニーズと全くマッチせず撃沈したパターンだ。前者についてはたった一枚のDMに現時点の会社のニーズが完全一致した。そのニーズは一般的にはよくあるニーズだが、具体的には会社内部の者しか知り得ないので、DMがその会社を狙い撃ちしたとは思えない。ただし、DM作成者側の意図と受け手の心情が上手く融合したことは間違いない。DMの作り方も上手いし、その後のフォローの仕方も上手いということなのだろう。後者は上場会社の代表取締役が営業担当者を引き連れてやってきた。その方の話はコンサルティング論としては極めて正統であるし、論理に異論を挟む余地は無い。時に上からものを言うような態度も経験豊富な人が若手後輩経営者を諭すようで、これもある意味やむを得ないのかもしれない。ところが、その会社の現状を全く無視して論を進めても経営者の心には響かない。物を売る商売ではないとはいえ、これでは商談がまとまらないのは火を見るより明らかだ。私は営業ノウハウを人に語れるほどの人物ではないが、観察するぐらいのことはできる。人の振り見て我が振り直せとはよく言ったもので、私も心して営業の現場に向き合わなければならない。
2006年08月24日
コメント(2)
-
雨の柱
怪しい空模様ながら、慣らし運転を兼ねて市外の顧問先へバイクで出かけた。国道2号線を西へ向かい、間もなく到着というところで前方に雨の柱が見えた。今いるところは薄明るいのに、前方は不気味な雰囲気を醸し出している。引き返すわけにも行かないので突っ込んでいった。前が見えない。並走していた車も次々と停車していく。私は条件反射的にポケットの携帯電話を鞄にしまった。再び走り出したものの、車が邪魔して前に進めない。足を付くと足首まで水に浸かった。何がなんだか分からないまま、ようやく到着した。社長と従業員は大笑いである。私はバイクで作業場まで入り、すぐさま服を全部脱いだ。全裸で腰にバスタオルを巻いただけの哀れな格好だ。しかし、都合が良いことにそこは車の塗装業だった。塗装を乾燥させるための設備が整っている。靴もパンツもシャツもすべて乾燥設備に放り込んで、とりあえず気晴らしの一服。しかる後に社長との面談が始まった。私は普段からラフな格好で仕事をしているが、会社にいながら全裸バスタオル巻きのビーチサンダルで社長と面談したのは初めてである。そんな格好で売上がどうの、資金繰りがどうのと話をしているのだから、端から見ればまるでコントであったろう。面談を終えて服が半乾きのまま身に付け、事務所に帰った。帰る道中はすっかり天気は回復していた。
2006年08月22日
コメント(671)
-
会社法かんたんセミナー
社会保険労務士の方々を対象に会社法に関するセミナーをした。行政書士として単独で乗り込んでいったため、最初は妙な緊張感があったものの、皆さん熱心でいい人ばかりだったので、気楽に喋ることができた。会社法セミナーといっても法律の解説をしたわけではない。メインテーマは顧問先社長とまともに話することができるようにネタを仕込むことだった。ネタの切り口の一つとして会社法を使おうということだ。中小企業の社長との会話を維持するためには、それほど法律の中身を詳しく知っておく必要もない。ただし、知らなかったでは文字通り話にならないので、実務上どのような場面でどのようなことを話せばよいのかを解説した。社会保険労務士、行政書士に限らず、士業にとって顧問として生きていく方向性は非常に重要であると思われる。そのための一つの能力として情報提供能力は必須であろう。ただし、単なる情報の横流しではなく、そこには提供者の独自性が付加される必要がある。これによって自らの存在価値を示すことができるのだと思う。会社であれば複数の士業が関わっていることも決して珍しくない。その中で一番に社長から声がかかるのは誰か?その地位を獲得した者が本当の意味の顧問であると思う。士業の種類に関係なく、その一番の座を目指して頑張りたい。
2006年08月21日
コメント(2)
-
恐るべしオール電化!
この春引越しした我が家はオール電化の賃貸マンションだ。ガスはない。引越し当初から光熱費が安いとは思っていたが、今月の電気代の請求を見て驚いた。9,000円台である。家族5人の我が家では、夜寝るときはエアコンを付けっぱなしで、合計3台のエアコンが朝まで働いている。梅雨明け以降暑い日が続いているので、フル稼働状態だ。その電気代がこれである。たいしたもんだ。引越しのとき、エアコンを新調したのも功を奏したようだ。最近の電気製品は省エネに力を入れているので、それを使うだけでも前より電気代は下がるはずだ。物は大事にしなければならないが、古い電気製品を使ってエネルギーを浪費するのも考え物である。私は水道代日本一の島で育った。30年前に海底送水管が敷設されるまでは、24時間給水は夢の世界だった。当時の水道代は大阪市の10倍だったと記憶している。日常的に「もったいない」と密着して育ったので、未だに水道光熱費には敏感だ。今日は事務所の電気の検針票が入っていた。動力で動かすエアコンの電気代は前年の52%に過ぎない。これも投資して最新の機器に買い換えたからだが、他にも吹き出し口の方向を上手く調節することによって、設定温度を3℃上げることができた。工夫すればまだまだ節約の余地はありそうだ。
2006年08月19日
コメント(2)
-
新車購入
非常に重要な営業の足であるスクーターを買い換えた。100ccの旧スクーターは4年間で走行距離20,000kmだった。過去1日の最長走行距離は姫路-尼崎の往復だったが、それにしてもよく走ったもんだ。十分元は取れたと思う。今回の新スクーターは125ccだ。高速道路も走れる150ccも候補に挙がったが、その仕様が仕事で使える条件を満たしていなかった。購入を検討したのは少し前だが、買うと決めてからが早かった。昨日の夕方、顧問先の車屋さんルートを通じて車両本体のみを卸値で横流ししてもらい現金で支払う。今日の午前中には自ら登録に走り、昼前にはナンバープレートを取り付けて走れる状態になった。明日の初乗りが楽しみだ。ガソリン価格高騰の昨今、燃費の良いスクーターは本当に助かる。どうしても外回りが多いので、時間とガソリン代節約には大いに威力を発揮する。これまでにも増してフットワーク軽く走り回ろう。
2006年08月18日
コメント(0)
-
ちょっとだけIT化が進展した
今週の日曜日、会社法の基本を講義する。今回初めてパワーポイントでのレジュメ作成に挑戦した。まずはいつものようにワードで作ってみた。その原稿を基に改めてパワーポイントに入力し直した。使い方が全く分からなかったので、他の人が作った別の原稿に上書きしながら作業を進めた。これは結構使えるソフトだ。前々からいいとは思っていたが、触れてみて改めてその良さを実感した。出来上がったレジュメをワード版・パワーポイント版と並べてみるとその違いは一目瞭然だった。内容は全く同じなのに、表現手段でこうも違うのかと驚いた。事務所が進化したような気がして嬉しかった。進化といえば先日、スタッフによる質問票に手書きで回答したものをスキャナでPDF変換してみた。これを共有フォルダに保存しておくと、ノウハウの共有ができる。データでもらった質問票にデータで回答するのは手間がかかるが、PDFにすると走り書きや図まできっちり残るので大変便利だ。アナログとデジタルが上手くミックスできてよかった。道具は道具として便利に使いこなしたいものだ。
2006年08月17日
コメント(2)
-
夏休みと読書
土曜日から始まった事務所の夏休みも今日までだ。私は一足早く今日からレギュラー出勤して色々準備作業をしている。今年の夏は今までとは打って変わって休みを多くとった。7・8月の週末は全て予定が詰まっていたのだから少々遊びすぎか。夏休み前に文庫本を数冊買い込んで島に持ち帰った。子供たちは従兄弟たちと遊びまわっているのでこちらは静かに読書ができる。普段は法律書・実務書が中心だが、この夏休みは少しその世界から離れてみた。ある雑誌の推薦図書コーナーから気に入ったものを取り上げて読むことにした。今回は中国の歴史書を中心にしてみた。「論語」「三国志(1)」「小説十八史略(1)」おまけで「シャーロックホームズの冒険」の4冊だ。シャーロックホームズは娘が気に入ったようで、すぐに取り上げられてしまった。論語は前々から全部読破したいと思っていたのだが、長編なので毎日10編ずづ熟慮しながら読み進めることにした。十八史略から読み始めたが、1巻500ページを一気に読破した。このまま第6巻まで読み進めたいものだが恐らく時間切れだろう。私は幼いころから読書は嫌いではなかったが、学校の宿題で感想文を書かされるのが嫌だった。今はそのような制約がないので楽しく読書できる。それと、親が家で読書していると子供たちが真似するのも不思議な現象だ。我が娘たちは皆本が好きなようだ。先ほど役所から申請完了の連絡があった。役所は盆休みなど関係無いのだろう。今から証書を引き取りに行って、本格的に業務開始だ。
2006年08月16日
コメント(4)
-
明日から海外へ
約10年ぶりに海外旅行へ行く。弟家族と合同で総勢9名だ。今日、現地で使う小遣いを両替し、旅行代金も含めて支払はすべて完了した。我が家は家族5名なので結構な金額になった。コツコツ貯めた500円玉貯金もあっという間に消し飛んだ。平成13年5月に行政書士を開業した当時、家族で海外旅行へ行けるなどとは夢にも思わなかった。自信がなかったというわけではなく、諸事情でどん底に喘いでいた状況から如何に脱出するか、毎日の家族の食い扶持をどう確保するか、将来の夢よりも現実の今をどう生きていくかという考えで頭がいっぱいだった。今日、別のところでまたしても「行政書士は食える資格か?」といった類の質問を見かけた。質問者の気持ちは分からないではないが、そのような質問を発すること自体が将来の道を閉ざしていることにならないか?当然のことながら、食える食えないは資格の問題ではなく、本人の問題だ。少なくとも私は行政書士以外の資格は何も持っていないがきちんと生活している。私は開業以来お金儲けを第一に掲げたことはない。好きなことを優先してやってきた。それを継続できるように今も必死に勉強している。責任が伴わなければただの我儘になるからだ。明日から海外へ行くといっても事務所機能は止まらない。スタッフがきちんと留守番してくれるだろう。5年間でここまで回復できた自分をちょっとは褒めてもいいのかもしれないとふと思った。
2006年07月26日
コメント(2)
-
幸か不幸かよく分からないが・・・
他士業と連携している案件で先方からクレームが入った。その内容は他士業の専管分野なので私には答えることができない。すぐに相方に連絡したが、来週半ばまで動けないという。再びこちらで対応を試みるが、中途半端な対応で火に油を注いでしまった。何とかその状況を乗り切って虚脱感に襲われているところに、その会社の社長から電話が入った。問題再燃かと思いきや、新規顧客を紹介してもらった。その社長がそばにいるということで電話を代わり、アポ取りも完了した。新規商談の約束をしていたので大阪へ向かうことになった。姫路駅から電車に乗るも何かのトラブルでダイヤが乱れていた。本町駅に着いて地上へ出て歩き始めたが、すぐさま道に迷ったことに気が付いた。出足の躓きがここでも響き、40分遅刻して汗だくになって辿りついた。そこから2時間商談は進み、こちらの言い値で顧問契約を締結した。作業が伴わない純粋顧問契約なので、労務負担は少ないものの、責任重大だ。この他にも今日は短時間の間に一瞬で頭にきたり、ちょっと嬉しいことがあったりの繰り返しだった。頭にくる原因を考えていたら、体制的に見直さなければならない点にも気が付いた。今日の出来事は全て良いことだと自分に言い聞かせて今日の仕事は終わりにしよう。
2006年07月21日
コメント(2)
-
会社法と決算
この7月末期限の法人税申告書提出会社から会社法での決算が行われる。今日は税理士と共作した決算書類を携えて決算取締役会に出席した。会社法では計算書類の括りが商法とは変わっており、監査報告と取締役会の順序も入れ替わっている。法律に則った取締役会は無事に終わり、引き続き株主総会に向けて準備に入った。招集通知の作成に当たって改めて関係条文を読み込んでみた。たった一枚の紙切れだが、これが結構奥深い。以前、この書類に関して大失態を犯した経験があり、その時も必死に勉強したつもりだが、改めて条文を眺めてみると新たな発見もあった。やはり実務が関わると同じ条文を見ても気づくことが違ってくる。実践の重要性が改めて浮き彫りになった。招集通知に関する計算規則を調べていると、定款に関する気づきもあった。絶対的記載事項でもないのに、何故定款にそのような規定を置くのかということが理解できた。私は行政書士として定款作成には相当力を入れているつもりだが、そんなことも知らなかったのかと我ながら情けなく思う。他の行政書士、司法書士などは十分理解のうえ定款作成しているのかと思うと、私はまだまだ勉強が足りないと思い知らされる。先程、税理士も税務申告書について何やら難しいことを言っていた。皆それぞれ新しいことに対応するために大変そうだ。取り敢えずは自分の専門分野だけでも情報提供できるようにしていかなければ。
2006年07月18日
コメント(5)
-
縦の知識、横の知恵
仕事を進めていて実感することがある。知識と知恵のコンビネーションだ。知識に関しては自助努力の世界だ。自分でコツコツ勉強して、何本もの柱を立てていかなければならない。これは多いに越したことはないが、そのプロセスは結構大変だ。結果がすぐに反映されないために、挫折の誘惑が次々に待ち構えている。そこを何とか工夫して乗り越えていかなければならない。そうした継続そのものがまた力になっていく。知恵は実践の世界だ。現場では教科書的なことが起こる機会のほうが少ない。目の前で起こる出来事に臨機応変に対応していくためには、知恵が欠かせない。その知恵を身に付けるためには、経験を積んでいくしかない。実務上の経験を積むことによって知識の柱に横糸を架けることができるようになり、そうして知恵が身についていく。試験を突破して実務の世界に入り、まずやるべきことは知識と知恵の習得だ。実践に耐えうる知識を勉強で身に付け、ひたすら仕事をこなすことによって知恵を身に付ける。もっとも有効な方法は圧倒的な仕事量だ。余計なことを考えず、仕事に没頭することこそが王道であると思う。今朝、今月の勉強予定を立てていて、月間の読書量が落ちていることが明確になった。そういえば早朝と夜に少々サボり癖が付いているような気がする。気合を入れ直して知識の習得に努めよう。
2006年07月05日
コメント(2)
-
人+人の相乗効果
この春からある行政書士と文字通り机を並べて仕事をするようになった。先に実務の世界に飛び込んだ者として、その世界のさわりだけでも教えるつもりだった。最近になってよく感じることは、教えているつもりが教わっていることが多いということだ。特に自分が作成した書類をプロの目でチェックしてもらえることは非常にありがたい。同じ部屋で仕事をしていて、その場でチェック・議論ができることは仕事を進めていく上では非常に有利な環境だ。行政書士+行政書士がこれほど相乗効果を発揮できるとを初めて実感できた。一方、行政書士の別の友人はネット集客による価格破壊の影響と、付加価値を提供できる能力不足に悩んでいる。ネットの悪影響は予定通りのことが起こっているだけで特に驚くほどのことではないが、能力向上のための方策には大いに工夫が必要ではないか。例えば、我LLPでは初回問い合わせからの仕事受注率は100%を保っている。商談には通常3名が同席しているが、決して安くはない月額顧問料を獲得できる理由を考えてみることは、大きなヒントになるのではないか。また、我々は5月から週3回の早朝勉強会を継続している。あと1ヶ月でこの勉強会は終わりを迎えるが、自己満足かもしれないものの現在まででも相当の実力が養成できたと思う。これとて一人ではその継続は困難だったかもしれない。スタッフが見せてくれた占いの本によると、冒頭の行政書士はいずれ私のライバルになるらしい。私の能力などたかが知れたものなので、あっという間に追い抜かれるかもしれない。しかし、私も黙って手をこまねいているつもりはない。常に能力向上に努めているし、いつでも勝負を受けて立つ覚悟もある。こうした争いがまた相乗効果を生むのだろう。人+人は不思議な力を生むものだ。
2006年06月20日
コメント(2)
-
決断の前に環境整備を
会社をたたむかもしれないという経営者から緊急の相談を受けた。急なことだったので何ら前準備する暇も無く先方に出向いた。私には手持ちデータが何も無かったので、取り敢えずは経営者の嘆きを聞くことに専念していた。聞くほどに悲惨な状況である。一通り話を聞き終えて、客観的な状況把握をするために数値データの提供を求めた。これがまたビックリだ。年商数億円もある企業のものとはとても思えない杜撰なものだった。税理士さんに数値面をお願いしていて、税金だけはきっちり払っている。しかし、出てくる書類はほとんど手書きで、データとして活用できそうなものは無かった。仕方がないので、資産負債の実情を聞き取り、借入金の返済状況、売上の傾向、営業面の資金繰りの見通しなどを順次明らかにしていった。経営状況の把握が順次進んでいくと、今度は経営者の意識ギャップを埋めていかなければならない。私の感触では今すぐ会社がどうこうという状況ではなかったが、数十年の歴史の中での繁栄期と比べると確かに悪い。しかしそれは当該会社を時系列で捉えた相対的なものであって、現状を切り出して他の会社と比べてみると、絶対的な面ではむしろ良い面がいくつもある。今回私は会社をたたむことも継続することも勧めなかった。それは経営者の決断することだからだ。しかし、その決断の前提となる状況把握はお世辞にも整っているとは言い難い。現状では数パターンのシナリオが描けて、それぞれについて予想に基づく方向性は提示した。その予想とて、現状では実現確率には相当怪しいものがある。重大な決断なのだから、十分な判断材料を用意して臨んで欲しい。そうは言っても経営者の安堵の表情が非常に印象的だった。溜まりに溜まった鬱憤を吐き出せたことが大きかったのだろう。具体的な改善策は提示できなかったが、こういう形で役に立つこともあるのだ。
2006年06月07日
コメント(2)
-
返り討ち
私にとっては超大企業と思われる会社から仕事の依頼を受けた。淡々と前準備を進めていたものの、どうも調子が上がらない。総じて反応が遅い、意思決定者までの距離が遠いなど、大企業としては普通なのだろうが、そういうことに慣れていない私には結構これがつらかったりする。ちょっとしたことがきっかけで、私は今回の仕事を辞退しようと思い、お詫びの訪問をすることにした。訪問ついでにそのちょっとした事件について一言申しあげるつもりでいた。実は社長と面会するのは今日が初めてだった。会社の近くから電話を入れ、社長の在社を確認するも電話口でかなり待たされた。ようやく在社を確認できたので、小走りで会社へ行った。高層ビルの上層階へ昇り、受付で待たされ、小さな部屋で待たされ、やっとのことで社長室へ辿り着いた。部屋には社長一人だけだったが、入った瞬間から何とも言えない雰囲気を感じ取った。社長が最初の一言を喋ったときから完全に押されてしまった。叩き上げの浪速商人のような社長の勢いに抗し切れない。途中何度か反撃を試みるも敢え無く撃沈され、全く相手のペースに取り込まれてしまった。辞退など言い出せる状況ではなく、持って行った書類にその場で追加記入しながら仕事を続行せざるを得なかった。一言物申しあげて立ち去るつもりが、完全に返り討ちに遭ってしまった。やむを得ず仕事を続行することになったが、やるからには抜かりのないように仕上げるつもりだ。それにしても社内でも王様に様な存在であろう社長に対しては、どこかでガツンと意見申しあげたい。どうせ社内で意見するような人はいないのであろうから、特に利害関係の無い私ぐらい何か言ってもいいだろう。それで仕事が切れても困るわけでもないし。私はどちらかというと、そのようなスリリングなことが好きである。
2006年06月01日
コメント(4)
-
姫路市福祉課の人
当地姫路市には「安心コール」という制度がある。仕組みはこうだ。1.独居老人宅に非常用ボタンを設置する。2.何か事故があったとき、独居老人がそのボタンを押す。3.信号が電話回線を通って消防局に伝わる。4.急を要する場合はそのまま救急車が出動。5.そうでない場合は、予め登録してある協力員(今回は私のほか2名)に連絡が入り、その者が駆けつける。今日は私の祖母宅で設置工事があった。ボタンというからボタンそのものを予想していたら、立派な装置だ。拳ほどの大きさの本体ボタン、病院にあるようなコード付ボタン、そして無線型の携帯ボタンのセットだった。今日の工事には姫路市福祉課の人と工事業者の人が来てくれたが、この人たちが素晴らしい。使用方法などを懇切丁寧に説明してくれるのだが、非常に心がこもっていた。その言動からは役所の論理ではなく、老人の権利行使という思想を強く感じた。私の祖母は90歳を超える独居老人だが、非常に遠慮深く、周囲に気を遣うタイプだ。そういう人にとってはボタンを押すこと自体をためらうものだが、そこを優しく説明してくれた。・老人がすることなので、間違って押すこともありえる。その場合はスピーカーに向かって間違えたと言えばよい。・声が出ない状態のときに無理に喋らなくてもよい。声が出ないという状況を判断して消防局が対応する。などといったことを、本人の要らぬ気遣いを取り除くように上手に説明してくれた。当初私が市役所に申込書を提出しに行ったときも丁寧に対応してくれた。そのときの受付の人、今日の二人、いずれもいい顔をしていた。そういういい人だから福祉課にいるのか、福祉課にいるからいい人になるのか、私にはよく分からないが、「いい仕事してますね」と自然に声をかけてしまう人たちだった。
2006年05月29日
コメント(2)
-
優柔不断
ある社長から紹介いただいたコンサルティング案件について、お断りの説明に伺った。紹介先の社長とは3回ほど面談を重ねたが、ただ1点のみの理由で断ることになった。社長が優柔不断なのだ。頭では分かっていても行動が伴わないので、結果を残すことが出来ない。これでは経営改善は到底不可能だ。紹介元の社長との話の中でこの優柔不断ということがひとしきり話題になった。中小企業では会社の命運は99.9%社長にかかっている。その社長がはっきりと進路を示して行動を起こさないと、周りの者が迷惑する。紹介元の社長は社員を10名以上抱えているので、その社員の生活のことを考えると大変なプレッシャーで、迷っている場合ではないと言っていた。同感である。夕方、別の社長から電話があった。超大手企業との契約が成立したとのことだ。この会社は別の大手企業との取引も抱えているが、こちらは仕事がなかなか進まないらしい。社長の息子である専務が優柔不断で何かに付け決断が先延ばしになるらしい。「そんなことでは従業員が付いてこないのでは?」と私が言うと、社長は我が意を得たりとばかりに同感され、その会社の空気を教えてくれた。大も小も関係なく、優柔不断な経営者には困ったものだ。大きな会社ではそのような弱点をカバーしてくれる優秀な人材が周りにいるだろうが、例えば私のような弱小零細企業の経営者ともなると、そのような人材はいない。同業である行政書士でも一人で多くの仕事を抱えながら、スタッフを雇わず、独力で頑張っている人が結構いる。その頑張りには敬意を表するが、事務所経営という観点からはいかがなものか?経営者を相手にしている自分も経営者であるという認識を持てば、行動すべきこともはっきりするのではないか。経営者の優柔不断さが経営にとって致命傷になりかねない。色んなことからそのようなことに考えが巡ってしまった。
2006年05月23日
コメント(10)
-
コンサルタントと経営者
今日はある会社の定例の経営戦略会議に出席した。社長以下取締役4名+私と他のコンサルタントが1名。会議の趣旨は先月の検証と今後の戦略の構成だ。いつものことだが、議論は活発に行われ、私はほとんど静観していた。一通り終わって取締役2名が東京へ帰るため退席してから事件が起こった。私の担当である資本政策に話が移り、結論的には時期尚早ということで作成していた資本政策表の説明を飛ばし、現状と直近の課題について意見を述べたところ、もう一人のコンサルタントが噛み付いてきた。感情むき出しで明らかに喧嘩腰だ。彼は某公的機関所属で然るべき地位の人だ。そういう方が私の言葉尻一つまで捕まえてつっかかってくる。一応反論はしたものの、どうしても議論が噛み合わない。要するに私を蹴落として自己の正当性を主張したいのだ。私が中途半端な返答しかしないので、余計に攻め立ててくる。見かねた社長と取締役が仲裁に入ったが、一向に攻撃の手を緩めない。しかし、私にはまともに議論する気は無かった。一対一なら時間無制限で受けて立つが、経営者を交えた席で会社にとって建設的ではない議論をしても意味がない。コンサル同士が争いをするなど見苦しいだけだ。相手の主張を聞いていてあることに気が付いた。コンサルとしてのポジションの捉え方が全く違うということだ。私は社長の感情や非数値的なことなどアナログ的な部分を重視する。本気になった命懸けの経営者にコンサルがかなうはずがない。コンサルとしては、せいぜい社長が進むための障害を一つでも取り除くことぐらいしかできない。コンサルが経営の先導役を果たすなど到底不可能だ。この考え方は社長の考えを最重視する。社長の考えを肯定するところから仕事が始まるので、周りから見ると「甘い」と写るようだ。他のコンサルが私を攻撃するのはそういう面を見ているからかもしれない。本当はこのような姿勢はコンサルとしては不適格かもしれない。もっと物事をデジタルで考えなければならないかもしれない。しかし私は他のコンサルがどうあろうと、この姿勢が私自身のスタイルだと思っている。私自身はコンサルであると同時に個人事務所の経営者であり、法人の代表取締役でもある。過去には事業で失敗した経験もある。そこで見つけた「経営者力」というものを本気で信じている。感情的に非難されて決して気分よいわけではないが、これが私の信念だ。
2006年05月13日
コメント(4)
-
現場は理屈どおりには行かない
今日から新たな勉強会を始めた。コンサルティング技能の向上のためだ。中小企業診断士の試験問題集を教材に、設問の内容が中小企業の経営現場でどのように現れているのかを検証し、基礎理論にフィードバックしながら理解を深めていくという内容だ。試験合格が目的ではなく、あくまでも実務能力の向上が目的なので、問題と解答・解説を読んで終わりという訳にはいかない。全ての設問を現場の具体的事象に結び付けなければならない私の役目も大変だが、基礎理論の準備不足の参加者はもっと大変だろうと思う。実際、8問こなすのに2時間もかかってしまった。しかし、このペースで進めば間違いなく実務能力は向上すると思う。今日は、新人行政書士が初めて経営者と経営問題について語る場面に立ち会う機会があった。事前準備もほとんどないぶっつけ本番に近かったが、その人の熱意は十分経営者に伝わったと思う。私がその現場から学んだことは、1.業種・業態に関しては自分の思い込みに偏ってはいけない。2.経営者が我々に求める根本的なものを忘れてはいけない。3.問題の本質を見つける探究心の養成を怠ってはいけない。4.経営者にものを教えるのではなく、経営者から学ぶ姿勢を忘れてはいけない。といったところか。現場で起こっていることは、たとえ理屈どおりではないことであっても事実には変わりない。だから現場を重視しなければならない。しかし、だからと言って現場のみに偏っては単に現場経験豊富な人ということで終わってしまう。現場は理屈どおりには行かないものだが、理屈も大切だ。バランスの取れた学習を続けていきたいものだ。
2006年05月09日
コメント(4)
-
信用が保険になった
顧問先に150万円もの追加資金負担が出るミスをしてしまった。原因は極めて単純で、エクセルへのデータ入力ミスだ。作業の最終段階で1桁多く入力していた。昨年12月分のことで今頃になって他の作業をしていて偶然気が付いた。過去最大級のミスだ。早速顧問先へ出向き、先方資料でミスが本当か確認するが、やはり間違いなく私のミスだ。何はさておき社長に謝罪。間髪いれず復旧作業に取り掛かった。何を間違えたのか、何故間違えたのか、間違いがどのような影響を及ぼしているのか、間違えなかったとしたらどうなっているのか、内容が経営数値に関わることだったので、新たな資料も作成し、関係機関への手配も含めてて24時間以内に復旧作業は完了した。改めて謝罪と追加資金負担のお願いに伺うと、社長夫人曰く、「社長は昨日から笑いが止まらない」という。実は私のミスは経営成績が下がる方向へのミスで、そのミスを取り除くと当然ながら経営数値が向上した。間違った金額が大きかったので、本来の正しい数値で計算すると、過去最高の経営数値が出揃ったのだ。社長にしてみれば昨年一年間必死に働いたのに数値面で報われず、何かおかしいと思われていたのだが、これで現場の実感と数値結果が合致したので、万事OKということらしい。追加資金負担は即日決済してくれた。この顧問先は私にとって第一号の顧問先で、付き合いも長い。コツコツと信用を積み重ねる努力を続けてきたおかげで、今は全幅の信頼を置かれている。今回の失敗の件でも私が責められることは一切なかった。それどころか、急いで作成した資料と説明によって私が如何に深く会社の実情を把握しているかが再認識していただけ、新たな仕事まで頂いた。ありがたい限りだ。他の嫌なことも重なって最近気力が減退気味だった。現場ではそういう面を出さず、空元気で乗り切っているつもりだったが、経験豊富な社長には見抜かれていた。翌日、社長夫人から「これでも食べて元気を出しなさい」と手渡されたものがあった。中身は高級霜降り牛肉だった。言葉通り何とかこれで気力を回復させたいものだ。
2006年04月29日
コメント(5)
-
休日前の仕事の棚卸
GWは遊びに行く日以外は全て仕事に当てるつもりだ。心置きなく休むために何を積み残しているのか棚卸してみた。縦に業務内容別に6分野、横に会社名を取って表に仕上げて眺めてみると、色々なことが分かった。1.GWは休めない。2.長期在庫が結構溜まっている。3.自分自身が原因で遅れている業務が多い。4.事務所の収益構造(固定収入と臨時収入のバランス)が一目瞭然。5.業務の難易度の違いが大きい。6.勉強不足で取り損ねている仕事が結構ある。等々・・・やるべきことの全てが分かったので、いざ作業開始と思ったら、次々とトラブルに見舞われる。こうも連続して起こるとさすがに精神的にきつい。今まで経験したこともないような専門分野のミスも見つかり、その原因が極めて単純なケアレスミスだったので、自分の実力も疑わしくなってきた。明日は支部総会だ。役割も与えられているので、ミスの無いように慎重に行動しよう。スタンスを整えて、今こそ踏ん張りどころだ。
2006年04月27日
コメント(2)
-
行政書士は食えないのか?
「ちゃんと行政書士で食っていけてますか?」初対面の行政書士有資格者が私の名刺を見ての第一声だった。哀れみの情感漂う質問だった。「何とか細々と食いつないでいます」私としてはこのように答えるしかなかった。行政書士業界ではよくある光景だ。同業者の集まりなどで黙って座っていると、先輩から同じように問いかけられることもよくある。この場合は先の質問とは意味が少し違って、後輩への気遣いから来る質問だ。いずれにせよ、行政書士は食えないという前提に立っていることには違いない。独立した行政書士は、行政書士であると同時に経営者でもある。食えるか食えないかは経営者としての資質の問題であって、行政書士であることが決定要因にはならない。何らかの経営目的を達成するための土俵が行政書士であるということであって、行政書士の資格そのものに経営上の意味があるわけではない。従って、「行政書士は食えるか?」と問われれば、「人によりけり」という答にしかならないだろう。行政書士に限らず士業の世界では法律で規定された専門業務があり、他士業の専門業務を犯してはならない。これを捉えて○○士は××業務ができないから不利だと考える人がいる。一方で、××士は○○業務ができるからこれを突破口に業務探求していこうと考える人もいる。経営者の資質という点で考えると、どちらが「食える」タイプかは明らかだ。行政書士である私に哀れみの言葉をかけてくれる人は多いが、その気遣いには素直に感謝するものの、これでも結構楽しく毎日を過ごしているのでご心配なく。
2006年04月23日
コメント(9)
-
会社法関連の需要は思った以上にあるかもしれない
今週末、経営者およびその予備軍向のセミナーをする。内容は会社法対策で、あくまでも一般の方が対象だ。今までの自身のセミナー参加や勉強はあくまでも専門家としての目線であったが、今回はできるだけ一般の目線で講義しなければならない。昨日はその打合せがあった。私がタイトル等を考えるとどうしても硬くなりがちなのだが、そこは一般企業の経営者である他のメンバーにほぐしてもらった。タイトルは硬くても内容を砕いていこうとその説明をしていたら、経営者の目線からは好評であった。私の考えの中に「そういえば○○はどうすればいいの?」という点が多々あったようで、意外にニーズを掘り起こせるものだなと感じた。打ち合わせが終わって帰り道、新聞社から電話が入った。会社法の企画モノのネタに困っていたようで、私が先程の打ち合わせ内容を話したら、大変興味が湧いたようだった。セミナーに取材に来るらしい。今日も夜8時を過ぎてから某公的機関から電話が入り、会社法関連の助っ人依頼だった。相談を受けた某機関の担当者も相談者自身も会社法のことがよく分かっていなかったようで、簡単に説明するとあっさり納得してもらった。明日直接お会いして詳細な説明をすることになった。会社法関連では専門家目線のニーズ予想と経営者側の実際のニーズにはズレがあるようだ。事例としては少ないものの、私は肌で感じた。個々の案件に丁寧に対応しながらノウハウを積み上げていくつもりだが、如何せん私の実力では時間がかかり過ぎる。手を広げ過ぎて失敗しないよう、自制心が必要だ。
2006年04月19日
コメント(4)
-
会社法による定款作成
本会での定款研修に参加した。この時期に定款の研修とは時機が遅過ぎるとは思うが、さすがに講師の方はよく勉強されていて、知識の深さを窺い知ることができた。また、色々な方の質問や意見を聞いていると、この業務の奥の深さを実感できる。今までの定款は極論すると雛形丸写しでも何とかなった。しかし、これからの定款は機関設計の多さが象徴しているように、単一の手法では通用しない。定款自治のメリットを享受するために、構想力が求められる。代書屋的発想から抜け出し、無から有を作り上げる気構えが必要ではなかろうか。この分野を業としようとしているものの、準備不足であると思われる人に共通の現象がある。最初からモデル定款を求めようとする姿勢だ。雛形丸写しが通用しない世界である以上、根本知識を習得せずにモデル定款を眺めても意味が理解できないと思う。如何に多くのモデル定款を眺めてみても、全ての事象をカバーできるモデルは提供し得ないからだ。モデル定款に沿って会社の実態を確認するというパターンから、会社の実態を確認してから定款の作成に取り掛かるという姿勢への転換が必要と思われる。これからこの分野に参入しようとしている行政書士はチャンスかもしれない。既に顧客を抱えている行政書士は、それへの対応に追われるからだ。少なくとも私のところでは新規客を獲得している余裕は無い。これから参入してくるであろう行政書士と健全な競争を展開したい。
2006年04月14日
コメント(4)
-
経営計画書の書き方
新規開業予定者から預った経営計画の清書をしている。この方は典型的な技術者タイプで、経営計画書を作るのは初めてだそうだ。しかし、全18ページに及ぶ計画書の中身は非常に素晴らしい。何かを参考に作り上げたという類のものではなく、全体から開業に向けての意気込みが伝わってくる。今回私が清書で手を加える部分は、数値データを表にまとめることと数値計画を作り直すことだ。数値計画には設備投資とそれに伴う資金調達計画、収支計画、資金繰り計画がある。特に会計に疎い一般の方は、収支と資金繰りの整合性をとることに混乱が生じがちだ。今回も案の定これに引っかかっていた。この部分は資金調達計画にも大きな影響を与えるので、慎重にやりたいものだ。経営計画といえば先日、同業者からその作り方を聞かれた。こういった場面で一番多い質問は「何か適当な雛形はないですか?」というものだ。私の答はいつも決まっている。「何でもいいから市販本で十分参考になりますよ」と。経営計画書はその作成目的によって表現方法等が変わってくる。一般の方ならいざ知らず、プロとしてはその度に雛形を参照していては仕事にならない。従って、まずやるべきは経営計画を作るための基本原則を身に付けることだ。その上で雛形を利用するならば全ての書籍が参考になる。雛形を書き写すなどという代書屋的な発想ではプロとして情けない。基本原則は経営に関する基本書を読めば誰でも直ぐ身につく。読む→理解する→実践する。極めて単純なこのプロセスを実行するかしないか、結局はここで差が付くのだろう。
2006年04月08日
コメント(6)
-
専門家に求められるもの
新規開業予定者と面談した。億を越えるお金が動く案件で、私の他1名の専門家を加えて4時間弱にも及んだ。長期間に渡ってコツコツと開業資金を貯めてこられた方で、いざ開業の段になって諸々不安要素が出てきたので、専門家の意見を仰ぎたいということだった。私からは自己資金の有効活用、追加資金調達、設備投資計画、経営戦略などを話し、他の専門家からは税務上の話をした。その翌日、その方からの電話で正式に顧問としてのサポート依頼があり、私たちはLLPとして対応することになった。先方の決断の決め手になったのは、総合力と連携だったそうだ。総合力に関しては、本人が考えていること以上の全体像をつかみ、先手を打って対応できるということだ。これは面談の際、相手の質問に答えるだけでなく、次の事象を想定してこちらから質問を投げ返すということでもある。一般的に行政書士は手続の専門家と言われているが、手続の延長線上だけで考えていると、経営をトータルにサポートするという発想にならない。手続はそれ自体が行政書士の目的にはなっても、経営者の目的になることはありえない。あくまでも一部分だ。連携に関しては、相談者と同世代の我々が、各自の独立専門領域を超えて連携していること自体に価値を感じてくれたようだ。ともすれば一人よがりになりがちな士業の世界で、他士業者が一つにまとまり、共通の目的に向かって走っているLLPという存在に非常に感心いただいた。総合力にしろ連携にしろ、価値を発揮するのは相乗効果だ。一人一人の力を持ち寄って1+1=3以上になるようでなければ意味がない。そのために各自ができることは、自らの専門領域を磨き上げることだ。後は組合せの妙で力を発揮できる。今回は一人では到底なし得ない力を実感することができた。他のLLP組合員に感謝するとともに、独自能力に磨きをかける強力な動機付けになった。
2006年03月28日
コメント(6)
-
LLP制度発展のためには
インブルームLLPとの意見交換会は無事終わった。全28項目からなる質問に答えるという形で議論を進めたが、今回は特に税務・会計に関する分野が中心だった。一言で言ってしまえばこの分野は問題山積だ。しかし、現にLLPの活動は継続しているので、一つずつ問題解決しながら進んでいくしかないだろう。さて、今日のタイトルは我々が受けた質問項目の一つだ。質問者は調査委託者である経済産業省なのだが、こういう質問に関しては役人と我々現場の人間とでは答の方向性が全く違うことが分かる。役人の発想は、制度普及のためにはどんな制度が必要か、という屋上屋を重ねる発想になりがちだ。こうして税金の無駄遣いと事業者を甘やかす制度が次々と出来上がる。私が考える方向性は、一にも二にも実績だ。それぞれのLLPが掲げる目標に関して少しでもそれに近づける実績を挙げ、それをアピールすることだ。LLPは営利を追求する団体であり、ボランティア団体ではない。自らが定めた理念を追求し、顧客満足の対価として利益を得る。そのための手段として例えば設備投資が必要ならば、資金調達に必死になる。その際、国が用意すべきは助成金という甘い汁ではなく、信用補完という後方支援だろう。某LLPの代表者は、多額の資金調達の必要に迫られ、自分の車を売り払ったという。事業者とはこういうものだ。助成金がもらえないからこの事業を止めておこう、税務上の扱いが不利になることがあるからこの手法は止めておこう、○○制度があったらあなたはLLPを作りますか等、質問そのものがバカバカしい。インブルームの方々とは貴重な意見交換ができた。今度会うときは役所の委託事業ではなく、現役LLP組合員同士として制度発展のための本質論を議論してみたい。それが何らかのアクションにつながれば尚いいことだ。
2006年03月25日
コメント(2)
-
有名人がやって来る!
我がLLPアシストが有名人の訪問を受けることになった。著書「さおだけ屋はなぜ潰れないのか?」でお馴染みの山田真哉氏率いるインブルームLLPの方々だ。来訪目的は彼らが経済産業省から受託した調査事業の一環ということだが、理由は何であれ有名な方にはるばるお越しいただけるとは光栄だ。本来目的である調査項目に関しては、事前にその概要を頂いている。その回答についてはメンバーが目下作成中であるが、私としては是非この機会に本質的な議論をしてみたい。私のように片田舎で細々とやっているような人間と、全国区で有名人として仕事をしている人の何が違うのか。また、共に中小企業支援という同じフィールドで仕事をしているものとして、その捉え方、対処法など話題は尽きない。自分で言うのもなんだが、私は本番に強い。形式的な質問などはそこそこに、アドリブと具体策の連発で議論に臨みたいと思っている。
2006年03月20日
コメント(4)
-
セミナーでの失敗
今日は建設業者向原価管理セミナーだった。予定時刻より1時間半ほど早く新大阪のホテル会場に到着。既に先発の公認会計士による新会社法セミナーが始まっていた。控え室で作ったときしか見ていないレジュメを広げて準備をしようと思ったら、主催者の係の人が来て話し込んでしまった。本当にぶっつけ本番だ。主催者側の準備不足で参加者の属性が分からないままスタート。さすがに大阪だけあって人数も多い。建設業の親父タイプばかりかと思っていたら、意外にも若い人と女性も多い。普段はマイクを使わず立ったままセミナーをするが、今日はそういう訳にもいかなかった。持ち時間は1時間。取り敢えずはレジュメに合わせて進行。ところが、付け焼刃で作ったものはすぐにボロが出る。30分でレジュメを消化してしまった。さて困った。残り時間は全てアドリブでいくしかない。原価管理というメインテーマからできるだけ離れないよう、コンサルティングの現場を引き合いに具体的な話をしていった。受講生の表情を観察しながら臨機応変にテーマを変えていったのだが、面白いことに、レジュメに沿った講義より反応が良かった。今まで下を向いていた人も顔を上げて、小ネタにも笑ってくれる。冷や冷やしながらも何とか持ち時間を使い切った。講義の中でITの活用を強く訴えた。電子申請が益々普及してくると、ITアレルギーが命取りになると。そこまで言って私は自己矛盾に気が付いた。開講前に主催者に当然のように勧められた「パソコンはどこに置きましょうか」という質問に、「紙のレジュメですから」と返事した自分を思い出した。そう、会場には極普通にパワーポイントの準備がしてあり、私のパソコンを繋ぐだけになっていたのだが、そんな準備はしていない。いや、そもそも私はパワーポイントを使えない。何とかセミナーは無事に終わったが、失敗はしっかり反省しなければならない。・受講生の属性は予め掴むよう指示しておく。・時間配分を考えてレジュメを作る。・パワーポイントは使えなければならない。等々。反省点も多かったが、収穫もあった。行った時は係の人だけが出迎えてくれたが、帰る時は主催者側の全社員が名刺交換に来られ、玄関まで見送ってくれた。今後のセミナーへの協力依頼を受けたが、こちらはLLPで受託することにした。これは面白そうだ。
2006年03月17日
コメント(8)
-
ハングリー精神
探し物をしていたら、偶然にも20年以上前の高校時代のものが出てきた。懐かしい時代を思い出してしまった。私は中学卒業と同時に家を出て高校は独り暮らしで通った。確か当時の今日3月17日に受験、21日に合格発表だったように思う。その日、友達同士で合格のお祝いをしている最中に電話があり、翌日から野球部の練習に参加せよというキャプテンの一言で全く何の準備もすることなく一人暮らしが始まった。高校3年間はずっと親からの仕送りは月5万円。アパートの部屋にあった電化製品は、冷蔵庫と保温機能の無い炊飯器、洗濯機、15インチのテレビと小型扇風機だけだった。風呂は無し(風呂屋へ)、トイレは共同、電話も無かった。正に貧乏を絵に描いたような生活だったが、私は親にお金をねだったことは一度も無かった。実際、生活費を使い果たしたときには、ご飯に塩をかけて過ごしていたものだ。特につらいと思ったことは無かったが、文字通りハングリー精神は身に付いたように思う。ところで再来週、我が家は新築マンションへ引越しする。妻と娘は電化製品を一新するためにカタログと睨めっこだ。20数年前の一人暮らし開始時とは雲泥の差だ。当時の私は15歳なりに悲壮な覚悟で生活を始めたが、今の家族はこれからの生活が楽しみなようだ。家族のために働いている者としては、これが本望なのだろうが、ここで立ち止まってはいけない。私はまだ38歳。ビジネスの世界ではまだまだ若造だ。立ち止まって小さなことに満足している場合ではない。今日偶然にも懐かしい物を見つけたのは、生活環境が変わろうとしている自分に、ハングリー精神を忘れるなという戒めの意味があったのかもしれない。
2006年03月16日
コメント(8)
-
工事原価管理の重要性
来週、標記のテーマでセミナーをすることになっている。公認会計士の方とダブル講師だ。1ヶ月以上も前から決まっていたことなのに、今日になってようやくレジュメが完成した。作成時間3時間、何とか時間を捻り出して集中して仕上げた。1.損益計算書・完成工事原価報告書一般的な様式と建設業法施行規則の様式は微妙に異なっている。業法上の様式は一般様式を前提にしていると思われる点もある。変更届等においてはソフトで一般様式から業法様式へ簡単に変換されてしまうが、何をどのように変換しているのかは知っておいた方がいいだろう。2.原価とは何か原価について考えることと粗利益について考えることは同じだ。これらの意味・役割を十分理解したうえで、原価管理に入ることが望ましい。特に粗利益が全ての利益の源泉であるということは、当たり前のことだがその意味をよく考える必要がある。3.原価管理の必要性とそのポイントセミナーの核心部分だが、必要性に関しては業界を取り巻く環境変化が大きく影響している。この変化を素直に受け止め、自分は例外という思考に陥ることなく、冷静に判断してもらいたい。また、ポイントとしては稼働率と採算性のバランス、実地棚卸の重要性が挙げられる。このポイントは深く掘り下げてみたい。4.勘定科目別チェックポイント日常の会計処理において、各勘定科目別に注目すべき点を列挙してみた。これについては多くの市販本でも同じような点が指摘されているはずだ。今日レジュメを作ったものの、今の流れから行くと恐らくぶっつけ本番のセミナーになりそうな気がする。レジュメの見直しや書き足しもできそうにないので、スタッフ相手に即興でセミナーをしてみた。彼女たちの反応を参考に本番に臨むつもりだ。
2006年03月09日
コメント(4)
-
効率良く会計作業を進めたい
先週1週間は、様々な時間帯で働くことになってしまった。始業は5時台から、終業は翌朝1時台まで。多いときの1日連続労働時間は20時間にも達した。特に週末の2日間は、スタッフが休みのため自ら会計入力作業をした結果、延べ34カ月分相当の入力作業をした。我ながら感心するやら呆れるやら。最近は自ら入力作業をする機会はめっきり減ってしまったが、たまにやったとしてもその仕上がりスピードでスタッフに負けることはない。手の動きでは私に勝ち目は無いのだが、仕事は完成しなければ意味がない。一つの作業中に二つ三つの内容を盛り込めるかどうかの問題なのだが、会計入力を単純な作業だという前提に立つと、内容を盛り込むという発想にはならない。内容とは何ぞや、というところにノウハウがある。折に触れてスタッフにはそのノウハウを伝授しているものの、部分部分の理解はできても総合的に実践するところが難しいらしい。その度に同じことを繰り返し教えるものの、ここから先は根競べになる。今日は午後から某企業の役員会議に出席した。新年度が始まるのを機に会計システムを一新するそうだ。役員からは様々な要求事項があったが、経営レベルと会計現場レベルの乖離が大きすぎる。私はこの会社の会計を担当するわけではないのだが、このままでは掛け声倒れになることを申し上げ、改善策を提案した。そもそも顧問税理士が提案してきたシステムに、外部の私がケチをつけるのもお互い良い気分はしないのだが、黙っているわけにはいかなかった。会計は広い意味で後に控える「判断」の材料になる。「判断」には正確性を前提としたタイミングというものが非常に重要だ。一つのために二つの作業をするのではなく、二つのために一つの作業で済ませる発想が大事だ。そのためにどこで効率を追求するかが問題である。
2006年03月06日
コメント(2)
-
著作権の勉強の段取りが分かった
ずっと以前から著作権について勉強したいと思っていたのだが、何をどのように勉強したらよいのか分からなかった。実務上、どのような問題が起こり得るのかが分かっていなかったので尚更だ。しかし遂に素晴らしいセミナーに出会うことができ、その概要を掴むことに成功した。セミナー名は、「コンテンツビジネス攻略のための著作権基本スキル徹底習得講座~1日で基礎から学ぶデジタル時代の著作権と権利処理~」第1章コンテンツビジネスと著作権知識第2章著作権に関する基礎知識第3章事例で考える 映像コンテンツの権利処理第4章事例で考える 音楽コンテンツの権利処理第5章コンテンツビジネスの著作権法務戦略著作権を専門とする弁護士が講師で、条文解説型の講義ではなく、豊富な実務経験に裏打ちされた非常に実践的な講義だった。参加者は、NHKを初めとする放送局関係者が多く、他は大企業法務部と思われるような人だった。参加者の顔ぶれからもこの講座の趣旨が窺える。時節柄事務所を丸一日空けることには躊躇したが、思い切って終日勉強に費やしてみてよかった。知識の習得に加え、行政書士とはおよそ関係無いであろう人たちに混ざって勉強できたことは、非常に刺激になった。講義内容を忘れない内に、復習を兼ねて条文解釈の勉強をしておこうと思う。なお、今回の出張では神戸空港を利用した。マスコミからは色々叩かれているようであるが、利用する者にとっては便利であることは間違いない。私のように神戸空港より西に居住する者にとっては尚更だ。テレビ等で偉そうに批判しているパーソナリティのほとんどが大阪府等神戸空港より東の居住者であるところに偏りを感じる。
2006年03月01日
コメント(4)
-
簿記能力向上のために
今日は簿記検定があったらしい。私が初めて3級を受験してから20年が過ぎた。最近のテキストや問題集を見る機会は無いのだが、根幹になるものは変わっていないだろう。私は予備知識ゼロで独学で始めた。匙加減というものが分からなかったので、テキストに書いてあることを忠実に再現していく学習法を取った。それから問題集を繰り返し、検定直前に簿記学校の対策講座に出て合格した。今は仕事の道具として簿記は欠かせないものになっているが、飯の種にする以上はその能力を磨き続けなければならない。経験上その最も良い方法としては反復練習に尽きるだろうと思う。といっても、仕事上のことなのであくまでも実戦用ということになるのだが。実務上の簿記では、会計ソフトと密接な繋がりがある。作業を早く正確に終わらせるためには、会計ソフトの使いこなしが絶対必要になる。使いこなしとは即ち応用のことだ。私などは簿記の教科書には絶対書いていないような方法で使いこなしているが、実践で編み出した方法なので、非常に有用な方法であるし、独自ツールにもなっている。加えてエクセルなどの一般ソフトをどのように組み合せるかも重要だ。会計ソフトはそれ自体が完結型で、非常に高機能なのだが、それでも敢えて周辺ソフトを組み合せるところに仕事の付加価値を生み出す源泉がある。仕事で使える簿記能力向上のためには、簿記の基本原理を習得することが絶対必要条件であり、その上で周辺ソフトを使いこなす術が必要になる。目的と道具を履き違えることなく、付加価値を生み出す意図を持てば十分に飯の種になり得る。後は反復あるのみといったところか。
2006年02月26日
コメント(8)
-
ビジネスプラン発表会にて
この日曜日、某所でビジネスプランコンテストに参加した。私はアドバイザー席での聞き役だったが、メンター席には現役ベンチャー社長が居並び、プランに対して様々な意見が出ていた。演出効果も手伝って中々華やかな場面だった。私自身はといえば、一向に気分が盛り上がらず、腹に一物抱えたまま懇親会へと突入した。酒を飲んでも気分が変わらないので、他のアドバイザーに振ってみた。私:「今日の発表会でキーワードをつけるとしたら?」ア:「マッチング」私:「やっぱりそうか」私の心に引っかかっていたのも「マッチング」だ。最近のビジネスプランの傾向としてこのマッチングがやたらと多いような気がする。道具としてITを駆使するのも共通している。私は決してマッチングを否定している訳ではないのだが、こうも連発されると審査員のセンスを疑いたくもなるし、事業に対する軽薄さが強調されるような気もする。今回は400件以上から選ばれた7件なのでなおさらだ。マッチングが真価を発揮するのは、1+1=3以上になるときだ。いわゆるシナジー効果というものがあってこそ利益の源泉足りうる。ところが最近のプランは、その部分の裏付けが乏しく、結果として安易さや軽薄さを感じてしまう。こういったビジネスを展開すると、初期段階で資金繰り問題が立ちはだかる。それを安易に外部からの出資で賄おうとする傾向があるのだが、資金調達とはそんなに簡単なものではない。日頃地道に商売をしている事業者を相手に仕事をしていると、その安易さがより浮き彫りになる。資金調達といえば出資や借入が代表的だが、根本的には利益を計上しなければ継続性を保てない。その利益とは世の中に価値を提供することの対価だ。大多数の事業者がその価値創造活動を目立たないが地道に続けている。華やかな舞台でプランを発表する者、そのプランに成功者として意見を述べる者、それはそれで結構だが、事業者の本当の姿を知ろうとしなければ、いずれ不幸な場面に遭遇するだろう。
2006年02月21日
コメント(4)
-
入札参加資格申請
この時期、役所への業者登録で行政書士は大変だ。私は基本的にこの種の業務は取り扱っていないが、全く無いわけではなく、ほんの少しだが今日で全て出し終えた。審査の順番待ちをしていると、色々な人を観察することができる。中には記載不備等で泣く泣く帰る羽目になる方も結構いて、役所への書類提出の代理・代行をするという行政書士の典型業務の存在意義に気づかされる。私の地元では3月に合併を控えており、吸収される側の町の業者は新市への新規登録が必要だ。私は新市に事務所を構えているが、出身が吸収される側の小さな町で、予想通りちょっとしたドラマがいくつかあった。何かに付け体制が変わるというのは大変なようだ。今回の季節作業を通じて改めて確認できたこともあった。表面的なニーズ以外にも事業者には何らかの潜在ニーズが絶対あること。各種作業を進めていく上では、その業者のことを良く知っていなければならないこと、の2点だ。前者については当然経営上の問題になるが、業者側からすれば誰に相談したらよいか分からない。行政書士側からは作業だけに目が行っているとニーズに気づかないということで、ミスマッチが起こる。これはお互いにとって不幸なことだ。後者については内容を熟知していれば書類作成がスムーズに進み、付加サービスをつけることもできる。些細なミスが大きな怪我に発展することを防ぐことができるといったことなどか。この時期多くの同種案件を抱えて大変な状況になっている行政書士もたくさんおられるが、私のように少ない案件で色々深く勉強させてもらった奴もいる。どちらにしても得るものは大きい。
2006年02月16日
コメント(2)
-
ビジネスチャンス拡大の原動力は?
私は事務所の壁に今年の経営方針を貼り付けている。A4用紙2枚に渡って書き込んでいるが、その中のアクションプランという項目の一つに「積極的な外部への挑戦」といった類のことを書いている。今年になってこの張り紙が何かと後押ししてくれる場面が多くなった。基本的に講師の仕事は受けない方針にしていたが、某有名ソフト会社から依頼を受けてセミナーをすることになった。大阪の会社から純粋にコンサルティング依頼があった。勉強会のテキスト作成に関して今までに無い大部なものが完成した。とてつもなく大きな案件を受注した。実はこれらはある共通した現象を経ている。どの案件も当初話が舞い込んだ段階では躊躇した。理由は話が大き過ぎたり、知らないことが多かったからだ。ところがその度毎に張り紙に目が行った。「これこそ外部への挑戦ということではないか」。そこで気を取り直し、何でも来い!という気構えで話を進めると、トントン拍子でまとまっていった。難しい仕事を受けたプレッシャーは確かにあるが、それ以上にそのプレッシャーを跳ね除けていく楽しみがある。理念というものの有効性を今さらながら痛感している。ビジネスチャンスは誰にでも数多くあるものと思われる。しかし、それを本当に生かすのは、実際に行動を起こした者であり、その行動の原動力になるものが「理念」ということではないだろうか。
2006年02月10日
コメント(6)
-
行政書士の仕事も色々
朝一番である社長と面談だった。その席上、契約が内定した。報酬総額が法人設立を例に取ると、軽くその100件分以上に相当する。私にとってはとてつもなく大きな仕事だ。他に大勢の優秀な専門家がいるにもかかわらず、私が受けることになった。事務所へ帰る車中で自らの選手生命を賭けて仕事にかかる決意をし、武者震いをしながら緊張感を高めた。事務所に帰って腹ごしらえをしようと思い、ラーメンを作って食べた。私の事務所にはガスコンロも電子レンジもある。外へ出るのが面倒なときは、これらを使って済ませる。昼からは定例の会社法による定款作成勉強会だ。会社法条文、整備法条文、そして旧定款を参照しながら、黙々と提案すべき新定款の作成作業を続けた。まだまだ知らないことが多過ぎるし、あちこち参照するに付け自分のレベルの低さを反省する。そうこうしていると、土曜日には珍しく事務所の電話が鳴る。同郷の人で、人づてに私のことを聞きつけ、業者登録の申請書を書いて欲しいという。私の故郷は合併を控え、新市への再登録が必要だ。いままでは田舎なので適当に済んでいたらしいが、新市への書類はややこしくて書けないと言う。こちらは完全な代書作業だが、同郷の好で快く引き受けた。2月になって集中的に会計の仕事をしているが、今日は脱・会計の日だ。それにしてもコンサルやら代書やら色々仕事の種類はあるものだ。
2006年02月04日
コメント(8)
-
飲食店の計数管理
個人経営の飲食店につき、年間の決算を終えたので、計数管理についてまとめてみたい。数値管理が必要なのはどの業界でも同じだが、飲食店に関しては第一に原価率、第二に月次損益、第三に設備投資計画ということになろうか。これらをどのような形で提供していくかにちょっとしたノウハウが必要になる。1.原価率これは最重要関心事であり、事後報告は許されない。リアルタイムで把握するための仕組みが必要だ。具体的にはエクセル等でレジ(レシート)集計を行い、そこへ納品書を基に食材費を加える。極めて単純な表だが、これによって毎日の原価率の推移をリアルタイムで把握できるようになる。腕のいいオーナーならば、月初の不調を月末までに調整することができる。意識するかどうかが問題なので、リアルタイムには拘らなければならない。2.月次損益通常の会計処理だ。これによって毎月の会計報告をするのは他の業種と何ら変わらない。この延長線上に決算がある。1度でも年間決算を経ると色々発展させることができる。まずは経費率の把握だ。飲食店で注目すべき経費は、人件費と家賃だ。これらを含めて販売管理費率を把握しておくと、先の原価率と合わせて売上だけから容易に最終利益を予測できる。飲食店ではその他一般管理費の変動が少ないからだ。次に季節指数の把握だ。年間の売上変動を把握しておくと、目先の変動に一喜一憂しなくて済む。これらはグラフにして予測値と実績値を絶えず見える形にしておきたい。3.設備投資計画飲食店では、調子が良いとなると多店舗展開がすぐ視野に入る。その際、一番の問題は人材と資金調達だ。人材に関しては個別重要テーマなのでここでは触れないが、資金調達計画は中長期的な対策が必要だ。上記1・2の積み重ねで外部に対するプレゼン能力を高めていくと同時に、すべてにおいて将来を見据えた計画と行動が必要になる。上記は一般論だが、これを個別企業(店舗)に当てはめていくと、当然ながら固有の事情を盛り込まなければならなくなる。そのプロセスで独自のコンサルティングノウハウが蓄積されていく。
2006年01月31日
コメント(3)
-
法律違反のリスクを考慮しているか?
先日来、似たような境遇の2人の若者が建設業許可取得に関して相談に来ている。少年時代に暴れん坊だった奴が中学卒業後仕事につき、奉公してから独立し、同じような境遇の若者を雇い、組織の長として仕事に励んでいる。先日会社を訪問したら、仕事を終えたイカツい兄ちゃんたちが数名くつろいでいたが、威圧感満点で一瞬たじろいでしまった。事業規模がそこそこ大きくなってきたので、元請から許可を取れと勧められているそうだ。そしてその取得方法に関してあの手この手の良からぬことを吹き込まれている。決算申告すらまともにやっていないというのに…。決算申告に関しては税理士に詳細を説明してもらうことにして、私は根本的なことの説明にかかった。今までも説明してきたが、その場は納得しても翌日にはすぐまた誰かに入れ知恵されて振り出しに戻るという繰り返しだったが、そんな状況にもやっと終止符を打てた。私の基本スタンスは正面突破だ。裏道も横道も無い。必要な資格は自ら取得し、他人などあてにさせない。現在から将来にわたるグランドデザインを描き、その中に本人を位置付ける。何時何をすべきか、そうすればどうなるのか、本人が納得するまで説明する。本人が納得しなければ私は受任しない。今回の説得ポイントは三つ。・今の時代は法律違反のリスクは極めて大きい。・きちんとした会計をすればまともな資金調達に困ることはないし、そのルートは私が責任を持って開く。・年商1億円にもなろうとする事業者が恥ずかしい行動をするな。特に業法違反の怖さについては、くどいほど説明した。周りがどうこうではなく、自分自身を規律する問題として捉えるよう説明した。若者のすばらしいところは、納得さえすれば素直なところだ。椅子が壊れるのではないかと思うぐらいゴツイ体をした兄ちゃんが、神妙な面持ちで頷いている姿を見ると、こちらも応援したくなる。先はまだまだ長い。日の当たる場所を堂々と歩んでいってもらいたい。
2006年01月27日
コメント(4)
-
中小企業診断士から学ぶ
某企業に対する中小企業診断士の診断書を見せられた。ベテラン診断士が新人診断士の教育のために、その企業がデータ提供したものの結果だという。戦略診断担当者、財務診断担当者からなるものだったが、後者に対して気になることがあった。1点目:各種分析が丁寧になされ、グラフ等も多用した見栄えの良いものだった。しかし、使われている文言が難しく、その指標が何を意味するものかさえ分からなかった。この人が社長に何を訴えたかったのか分からない(当然、社長本人も分かっていない)。2点目:仕掛品の解釈を間違えていた。この会社は核となるソフトウェア開発が業務の大半を占めている。いわゆる研究開発型企業だ。診断書には仕掛品の削減が最重点項目と書かれていたが、これはおかしい。複数製品を継続的に作っている製造業ならば、仕掛品の削減は重要項目となり得る。しかし、単品のソフトウェア開発においては、途中で仕掛金額が減ることなどあり得ない。完成まで累積的に加算され続け、完成と同時にソフトウェア勘定に振り替って仕掛品はゼロになる。1点目については、出来合いの分析ソフトなどを使ったことが原因だろう。ソフトを使えば正確に計算される。しかし、計算結果を羅列するだけでは、焦点が定まらない。分析ソフトは道具であって、道具というものは何らかの意図があって使うものだ。その意図をはっきりさせないと、相手に伝わるものが無い。2点目については、会社の個別情報を掴んでいないことが原因だろう。コミュニケーション不足というやつだ。仕掛品(在庫)の削減は、経営のスピードアップに繋がり、特に資金の有効活用に結びつく。この流れで言うと、この会社の場合は、資金繰りの苦しさを脱出するために、内部努力で資金効率を上げて外部資金を減らせという結論になる。しかし実態は逆だ。戦略商品が完成間近になっており、会社の命運がこの商品にかかっている以上、外部資金を導入してでも仕掛品に投資しなければならない。つまり、外部資金をもっと増やせという結論になる。会計情報というものは、ある時点の姿を現しており、誰が見ても数字は同じだ。しかし、前後の脈略で解釈すると、示すべき方向性が違ってくることもある。公式を覚えれば、ソフトを使えば、計算は誰にでも出来る。その安易さに溺れないようにしたいものだ。
2006年01月21日
コメント(2)
-
経営セミナーをします!
掲示板にセミナー案内を載せました。LLPアシストとして2回目のセミナーになります。前回の神戸セミナーでは、双方向型セミナーで参加者の課題抽出、解決への方向付けが出来ました。今回も同じような趣旨で地元姫路市で開催します。さて、セミナーといえば先日、地元支部の会社法セミナーに参加した。若手会員による定款についての講義があった。会社法については、それを業務とするためには継続的な自己探求が必要だと思われる。私自身はそのことを肝に銘じて毎日欠かさず勉強している。それでも基本的なセミナーに参加するのは、違った方向から刺激を受けることによって知識の定着を図ることと、自問自答のための課題を発見するためだ。今回のセミナーでも、目論見どおり自問自答すべき課題を2,3発見することが出来た。しかしそれ以上に刺激を受けたのは、講師の姿勢だった。講義内容は極めて基礎的なことであったが、それにしてもあれだけスラスラ話そうと思えば、相当な準備をしたはずだ。講義をする側と受ける側ではこのようにして力の差が付いていく。私も彼に負けないようにしっかり勉強しようと改めて思った。
2006年01月18日
コメント(4)
-
(会計)事務能力を上げるためには
ある会社で事務員さんが交代するということで、社長から依頼されて指導に行った。専務立会いの下、事務員さん2名に次のような説明をした。事務職の種類:一般的に事務職種を大別してみると、1.経理(会計)事務、2.給与計算事務、3.営業事務に分かれる。この内、1と2は業種の影響をあまり受けないが、3については業種によってその内容ががらりと変わる。営業事務:この中心をなすのは請求業務であろうが、請求書を発行するまでの仕組みの構築が重要であり、ここに各社独自のノウハウが盛り込まれたりもする。また、営業内容によって事務の質・量とも大きく違ってくる。経理(会計)事務:手書き帳簿とPC(パソコン)会計の役割分担が非常に重要になる。特にPC会計についてはソフトの習熟が要求されるが、順序としてはオーソドックスに簿記を学習し、然るべき後に簿記に忠実な会計ソフトを使うと後々の作業性が良くなる。手書き帳簿とPC会計の関連:手書き帳簿では帳簿体系が重要になる。また、PC会計では1項目の入力がどこにどのように反映していくのかを押さえる必要がある。ここで簿記の基礎知識が絶対必要になる。入力・計算処理をPC会計で行う前提で手書き帳簿を作ると、何を記帳しておかなければならないか、何が不要であるのかが分かってくる。このようにアナログとデジタルの関連を押さえると、作業性が向上する。事務能力を向上させる順序:事務に限らず能力向上のためには絶対的な量が必要である。その中で効率を追求するなら順序が重要になる。経理(会計)事務ならば簿記(アナログ)→PC会計(デジタル)の順序が正しいと思う。PCはあくまでも道具として捉えるならば、本質である簿記を押さえておかないと応用力が身に付かないからだ。実践あるのみ:簿記3級レベルの習得には、3ヶ月もあれば十分ではないか。その間、実務と勉強の同時進行になるが、然るべき期間が過ぎれば後は実践あるのみだ。適当にコーチを受けながら進むと飛躍的に能力が向上するのだが、それが不可能な場合でも絶対量をこなせば何とかなる。仕事とはそういうものではないか。
2006年01月10日
コメント(4)
-
平成18年事務所経営方針
明日の事務所方針発表会に備えて当事務所の本年経営方針を決定し、スタッフへの説明を終えた。全部をここに書く訳にはいかないが、全体像を掲げてみたいと思う。【経営理念】統合参謀として企業・社会の発展に寄与すること【テーマ】1.(略)2.元気を出して~自分も元気、相手にも元気を与える活動をする。【経営目標】1.(略)年間12件2.(略)年間6件3.(略)年間6件4.(略)【外部環境分析】○機会1.会社法施行に伴う対応ニーズがある。2.(略)3.特に建設業での経営改善ニーズがある。4.(略)○脅威1.本業以外でマイナスエネルギーを受け続ける可能性が大きい。【内部資源分析】○強み1.経営改善に関するノウハウが蓄積されている。2.ネットワークが構築されている。3.事務所新聞を発行し続けている。○弱み1.人材が不足している。2.時間の有効活用に難がある。【アクションプラン】1.企業法務への対応力の向上→(内容略)2.経営コンサルティングの活動フィールドの向上→(内容略)3.許認可業種の統合経営改善に本格進出する→(内容略)4.起業家支援をLLPで展開する→(内容略)5.人材力を強化する→(内容略)6.行政書士の公的活動から撤退する→(内容略)7.時間の有効活用を徹底する→(内容略)
2006年01月07日
コメント(4)
-
謹賀新年と事務所方針
あけましておめでとうございます。皆様にとってすばらしい1年でありますように。毎年正月明け第1週末にML有志による「事務所方針発表会」を行っている。今年は1/8(日)に私の事務所で行う。この発表会では各自が自らの今年1年の方針を立て、皆の前で発表する。狙いは自己暗示だ。他人の方針がどうこうではなく、自分自身に宣言することが重要だ。普段のマネジメント支援現場では、経営理念に基づく経営戦略を説いて回っている。その張本人が方針を持たないようでは話にならない。自らが範を示すことによって言動にも説得力がつく。実際のところ、年頭に方針を発表することに良いことはあっても悪いことはない。時間の経過と共に当初方針とのズレを認識し、良い方向であれば加速し、悪い方向であれば修正の行動をとる。何も無しで事務所経営していくのとは大きく差が出てくるだろう。私個人としてはこの2年ほど、当初方針から大きくずれる傾向にある。予期せぬ拡大傾向に陥っているということだ。積極的に外へ出て色々な人と話をしたり、来る仕事を次々とこなしていく内に、業容が拡大してしまった感がある。この正月休みの間にしっかりと方針をまとめ、発表できるようにしておきたい。
2006年01月01日
コメント(8)
全53件 (53件中 1-50件目)