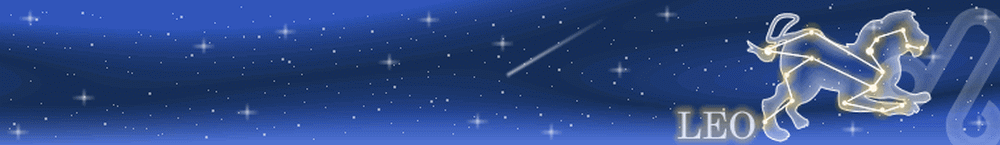テーマ: きれいなブログは好きですか(304)
カテゴリ: 徒然草

随筆という言葉は、近世の伴信友から始まったので、徒然草の時代は、これを日記と言っていた。
吉田兼好は、代々神祇官を務めていた卜部家の三男で、本名はカネヨシといい、出家してケンコウとなった。
姓の吉田は、卜部家が京都の吉田に在り、室町時代に吉田神社の神官になって、吉田姓を名乗るようになったことから、江戸時代になって吉田さんと呼ばれるようになった。
祖父が関東に下り、父は関東生まれだが、後に京へ戻り吉田に住んだ。
母親のことは不明。
幼い頃から知的だった兼好とその父との会話
「仏とはどのようなものでございましょう?」
「仏とは、人が成るものじゃ」
「どのようにして仏になるのですか?」
「仏の教えによって」
「仏は、最初は誰から学んだのでしょう?」
「その前の仏」
「元祖の仏とは?」
「天から降ってきたか、地から現れたのであろう」
父親は、息子に問い詰められて答えられなくなってしまった。
19歳の頃、後二条天皇の蔵人として宮仕えの生活を始めた。
蔵人とは、宮中の機密文書や情報を取り扱う天皇直属の役人。
数年後、左兵衛佐に出世し、左兵衛府で宮門の守備、行幸など天皇家の人々の外出の警備などに従事した。
また、藤原為世という歌道師範に弟子入りして、歌道にも精進し、40歳代になると、二条流の四天王と称されるほどになった。
出家したのは30歳代で、比叡山の横川に籠ったり、神奈川県の称名寺を拠点として、関東を旅して回った。
40歳代で京都に戻り、歌人として政治の中心人物の周囲で暮らした。
仕官、歌人、世捨て人と、様々な立場で時代、人間、事物を観察してきた兼好が、徒然草の執筆を始めたのは、48歳以降と考えられている。
没したのは68歳ぐらいといわれている。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.