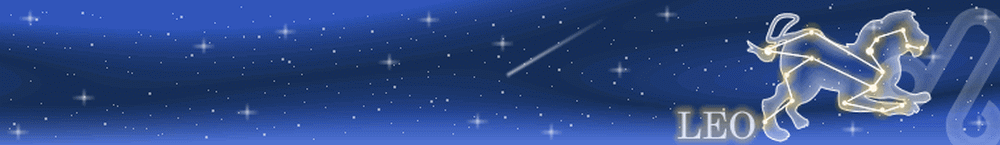全520件 (520件中 1-50件目)
-

ホタルブクロ
百人一首 春の夜の夢ばかりなる手枕に かひなく立たむ名こそ惜しけれ 周防尚侍 (短い春の夜の夢のような儚いたわむれに、手枕を借りたばかりに、立ってしまった浮名が残念です) 周防尚侍(すおうないしのかみ)は、平仲。後冷泉天皇、後三条天皇、白河上皇、堀河天皇に仕え、多くの歌会に参加した。
2010.06.05
コメント(1)
-

アブチロン
法務省赤レンガ棟明治19年、政府は西洋建築による官庁街集中計画に着手した。当初の案では、主要官庁すべてを一ヶ所に集めて、巨大な官庁街にする筈だったが、諸般の事情により縮小された。最終的に、現在は残っていない最高裁判所と、この司法省の庁舎の完成のみにとどまった。 赤レンガ棟は、明治28年に竣工し、計画の壮大さを今に残す唯一の遺構である。堂々たる建物は、ドイツのネオバロック様式で、ドイツ本国の建築にも優るとも劣らない。屋根中央に小さな尖塔を乗せ、左右両翼に張り出したゴシック風の外観は、気品さえ感じさせる。レンガ造りの西洋館には珍しく、なんとなく懐かしさもある。
2010.06.05
コメント(0)
-

徒然草 5
「人は、おのれをつづなやかにし、おごりを退けて、財をもたず世をむさぼらざらんぞ、いみじかるべき。昔より、賢き人の富めるは、まれなり」 訳「人間は生活を簡素に整え、贅沢に走ろうとする気持ちを戒め、必要以上に財産など蓄えず、世間の名声や名誉を求めて奔走せず、あるいは他人に見せびらかすことを慎むことが、見上げた生き方である。昔から、賢い人と尊敬されるような人が、財産家であったためしはない」 むさぼらんぞとは、得られる限りの利益や快楽を掻き取ろうとする浅ましい行いはするな。とはいえ、この日本に暮らしている人々は、そんなことを言い聞かせたところで、聞く耳は持たないだろう。そうした行いがいかに醜く、やがて悪い結果に繋がるとしても、それは自業自得だから、放っておけば良い。贅沢や快楽が身体を損ねるよと言っても、人間はそうなってからでないと気がつかない。言っても理解できない人間には、いくら言っても無駄だ。 「富貴爵禄は、みな人事の無くんばあるべからざる所の者。只当に礼儀を弁ずべし。あに徒に以て外物と為して之を厭うべけんや」富や地位、名誉を欲しないのなら求めなければよろしい。それを罵るのは、世を拗ねた負け惜しみである。人の世には身分があり、(魂の人格もある)隔ても存在し、富貴があり、それによって社会は成立している。富貴爵禄を蔑んだり、罵ったりする人間は、所詮人間社会から遊離し、寂寞の拗ね者になるのが落ちだ。この説は、江戸時代の儒学者、伊藤仁齋の言葉である。
2010.06.05
コメント(0)
-

百人一首
タチアオイ 百人一首 もろともにあはれと思へ山桜 花よりほかに知る人もなし 前大僧正行尊 (私があなたを懐かしく思うように、あなたも私を懐かしく思っておくれ山桜よ、山奥では花以外に私の心を知ってくれる人がいないのだから) 前大僧正行尊(さきのだいそうじょうぎょうそん)は、十二歳で出家し、修験者として名高い。
2010.06.04
コメント(0)
-

猫の母子
2010.06.04
コメント(0)
-

古事記 3
宇宙の初めにあらわれた三柱の天神は、男神のイザナギと、女神のイザナミに言葉を与えた。「地上の有様を見ると、ただ脂のようなものが漂っているだけだ、お前たちはあの地を、人間が住めるように造り上げなさい」こう命令すると、美しい玉飾りを施した天沼矛をイザナギ・イザナミに授けた。国造りという重い責任を負った二神は、天と地の間に架けられた天浮橋に立ち、天沼矛を漂う脂のようなものの中へ突き刺し、ぐるぐると掻き混ぜた。すると、次第に固まっていった。天沼矛を引き上げると、潮が滴り落ちて、積もり積もって島になった。その島をオノゴロ島という。イザナギ・イザナミは天浮橋からオノゴロ島に天降り、立派な柱を立て、巨大な邸を建てた。新婚生活を始めた夫のイザナギが、妻のイザナミに言った。「そなたの身体はどのようにできているのか?」「私の身体は美しく完璧にできていますが、ただ一箇所だけ欠けているところがあります」「私の身体も美しく完璧だが、一箇所だけ余分なところがある、そなたの欠けているところへ、私の余分なところを合わせ、塞いで国を生もうと思う」と話し合った。「そなたは柱の右側から回りなさい、私は左側から回りましょう」と、左右に分かれて回り始めた。出合ったところで、イザナミが、「なんと、見目麗しい男神でしょう」と感嘆し、イザナギも、「なんと、見目麗しい乙女だろう」と感激した。しかし、イザナギは、「女神が先にものを言ったのは、良くない徴だ」と言った。やがて生まれてきた子は骨のない子だったので、葦の舟に入れて流してしまった。次に淡島を生んだが、これも同様だったので、子の数には入らない。
2010.06.04
コメント(0)
-

赤いバラ
百人一首 恨みわびほさぬ袖だにあるものを 恋に朽ちなむ名こそ惜しけれ 相模 (あの人のつれなさを嘆き悲しんで、袖が朽ち落ちてしまうのも口惜しいが、浮名を流して我が名が朽ちることが惜しくてならない) 相模は、相模守大江公資の妻なので相模と呼ばれたが、離婚して一条天皇の娘脩子内親王に仕えた。
2010.06.03
コメント(0)
-

万葉集
モチツツジ 大伴旅人山上憶良とともに「筑紫歌壇」を形成していた。大伴氏は大和朝廷の軍事を担当する有力氏族で、旅人の父安麻呂は壬申の乱で大海人皇子側で戦い、功績をあげた。しかし持統・文武時代の大伴氏には風雅な人が多く、旅人も和歌や漢文学に優れていた。旅人の弟の田主も風流士と呼ばれた人物であり、また妹の坂上郎女にいたっては、女流歌人の第一人者として名を残した。旅人は政治の面でも順調に昇進し、720年には征隼人持節大将軍(せいはやとじせつだいしょうぐん)となり、728年、太宰帥(だざいのそち)として筑紫へ赴任した。その前に、聖武天皇が吉野へ行幸した際の歌。 み吉野の 吉野の宮は山からし 貴くあらし水からし さやけくあらし 天地と長く久しく 万代に 改らずあらむ 幸しの宮(天皇が行く美しい吉野の宮は、山が良く貴い、川が良く清らか、天地は長く久しく万代変わらずこうあってほしいものだ) 昔見し ささの小川を今見れば いよいよさやけく なりにけるかも(昔見た象の小川を再び見ると、ますます冴え冴えと美しくなった) 奈良の都を愛していた旅人にとって、大宰府への赴任は本意ではなかった。太宰帥は名誉ある役職ではあったが、その時旅人は60歳を過ぎていた。その上、大宰府に到着するとすぐ、同行していた妻が亡くなった。故郷から遠く離れた土地での不幸は、老齢の旅人にとって辛過ぎた。 世の中は 空しきものと 知る時し いよよますます 悲しかりけり(この世は空しいものだと知るにつけても、新しい悲しみがこみあげる)
2010.06.03
コメント(0)
-

古事記 2
ザクロ 古事記の著された目的は、第一に、日本の初代天皇が神武天皇で、彼によってこの国の統治権が発動されたこと。第二に、この国の国土は、イザナギ・イザナミの神によって造られ、この神の正統な血を引く者が国土の所有権を持ち、統治権を発動できる、ゆえに天皇が日本を治めるのは正しいことであるという見方が正統とされている。しかしそれは表向きで、その細工された文体、含みを持った叙述、旧約聖書との類似点などから、古事記はそれ以外にもっと重要な意図を持って著されたのではないかと思える。古来より、古事記の謎を解明することは死を意味するなどと言われてきたが、その理由は一体何だろう。古事記は、人類が滅亡する時期を予言しているのではないのか?あるいは、古事記には滅亡を食い止める方法が隠されているのではないか。古事記こそ、人類の未来への手引書なのかもしれない。旧約聖書の天地創造には、「初めに神は天と地を造った。地は形なくむなしく、闇が淵のおもてにあり、神の霊が水のおもてを覆っていた。神が『光あれ』と言うと光があった。その光を見て、神はよしとする。神は光と闇とを分け、光を昼、闇を夜と名付けた。夕となりまた朝になった。第一日目である」と書かれている。一方古事記の国造りには、「宇宙のはじめ、天も地も混沌としていた時、天のいと高いタカマガハラに三柱の神がいた。世界の中心となるアメノミナカヌシ神は宇宙を統一する役目を持った神である。つづくタカミムスビ神とカミムスビ神は宇宙の生成を司る神である。これらの神は配偶者をもたぬ単独神で、姿を見せることはなかった」とある。続いて旧約聖書は、「神は二日目に天と地を分け、三日目には海を、四日目には天体を造った。五日目に空を舞う生物と、水に棲む生物を造り、六日目に地上の動物と最初の人間を造った」と続く。古事記は、「天と地のけじめがなく、形らしい形もない地上は水に脂を浮かべたように漂うばかりで、あたかも海月が水中に流れるような頼りなさであった。しかしそこに水辺の葦が春にいっせいに芽吹くがごとく萌え上がるものがあった。その中から二柱の神があらわれた。うるわしい葦の芽の、天を指し登る勢いを示すウマシアシカビヒコヂ神、ついで永遠無窮の天そのものを神格化した神であるアメノトコタチ神である。この二柱の神も配偶者を持たない単独神で、姿を見せることはなかった」となっている。
2010.06.03
コメント(0)
-

台風
日本は台風の通り道ですが、フィリピンも同じように台風の通り道であるため、昔から大変な目に遭ってきました。フィリピンに台風が襲来するのは、年間20回から30回で、そのうち上陸するのは約9回にもなります。日本の場合は、台風が上陸するのは年間3回前後ですから、多いように感じてもフィリピンに比べれば少ないですね。被害も深刻で、2004年には死者が千人以上、家屋の損壊は13万棟に及びました。フィリピンの気象庁では、台風シーズンには4段階の警報を出し、注意を呼びかけています。警報の第一段階は、小さな木の枝が折れる程度の暴風。第二段階は、ココナツの木が倒れたり、傾いたりする暴風で、一部の学校や会社が休みになる。第三段階は、全てのバナナの木が倒れるほどの暴風で、全ての学校や会社が休みになる。第四段階は、大木が根倒しになるほどの暴風で、この段階になると非難するのも遅すぎるらしい。
2010.06.02
コメント(0)
-

百人一首
百人一首 朝ぼらけ宇治の川霧たえだえに あらはれわたる瀬瀬の網代木 権中納言定頼 (夜がほのぼの明ける頃、宇治の川面に立ち込める霧がとぎれて、その絶え間から川瀬に仕掛けられた網代木が、あちらこちらに見えるようになる) 権中納言定頼(ごんちゅうなごんさだより)は、藤原定頼。和泉式部の娘の小式部をからかって、やりこめられたという逸話がある。
2010.06.02
コメント(0)
-

徒然草 4
徒然草 4或人、法然上人に、「念仏の時、睡にをかされて行をおこたり侍る事、いかがして、この障をやめ侍らん」と申しければ、「目のさめたらんほど、念仏し給へ」と答へられたける、いとたふとかりけり。また「疑ふながらも念仏すれば往生す」とも言われけり。これもまたたふとし。ある人が法然上人に、「念仏を唱えている時、眠くなってしまいますが、どうしたら、仏に対するこのような不始末を解消できるでしょうか?」と訊ねた。すると上人は、「目が覚めたら、その時から続きを唱えれば良いんですよ」と答えた。また、念仏を唱えることにどんな意味があるのかと疑いながらも、念仏さえしていれば、極楽往生できる運命になるのだとも言ったと聞いた。まことに尊いお言葉だ。法然以前の仏教は、戒律重視の宗教だった。法然が登場した平安時代末期から鎌倉時代初期にかけては、貴族文化が衰退し、疫病が流行し、さらに釈迦の教えが形骸化していくという末法思想が広まった。人々は厭世観に捉われていた。そこへ法然が登場し、ただ念仏を唱えなさい、阿弥陀如来は、全ての人間を極楽往生させたいと願っていらっしゃる、如来に帰依しなさい、それだけで良いのだと説いた。これが、法然が始めた浄土宗の教えである。浄土宗のように、念仏を唱えることによって極楽往生できるという宗派を、念仏宗と言います。念仏は「極楽往生させてください」という請願かと思われているが、実はそうではなく、阿弥陀如来の慈悲深さに感謝するお礼の言葉なのである。人々が慈悲深い心を持ちさえすれば、それ以上は何も要求しない。この教えを後に親鸞が、浄土真宗という形に発展させた。吉田兼好が、この法然を取り上げたということは、念仏宗の教えの根本を、兼好は押さえていたのである。
2010.06.02
コメント(0)
-

ブラシノキ
ビン洗いブラシにそっくりな花。英名もビン洗い。日本には明治中期に渡来した。ブラシの毛のように見えるのはオシベで、花びらは極小さくて、開花後すぐに散ってしまう。白花もあるが、まだ見たことがない。
2010.06.01
コメント(0)
-

百人一首
百人一首 今はただ思ひ絶えなむとばかりを 人づてならでいふよしもがな 左京大夫道雅 (今となっては、ひたすらあなたを忘れてしまおうと、それだけを人伝でなく、直接あなたに言える方法があれば良いのに) 左京大夫道雅(さきょうにだいふみちまさ)は、藤原道雅。藤原道長の権勢に押されて、父伊周に死後は没落し、不遇の人生を送った。
2010.06.01
コメント(0)
-

徒然草 3
ニワゼキショオウ 徒然草には、名前を出さず「なにがし」などで表す人の言葉がよく引用されています。これは吉田兼好が、自分の考えをいかにも他人が言ったかのように記したのであろうと、内海月杖(明治の歌人・国文学者)は推測しています。徒然草の内容は、思想、人間観、有職故実、恋愛観、政治批判など多岐にわたり、細やかな感性と観察眼、豊かな知識を持った作者の幅広さをあらわしています。その人間観察の鋭さは、井原西鶴などに多大な影響を与えました。西鶴の作品の多くは、徒然草なくては生まれなかったと言われています。 仏教思想が人々の間に浸透していた中世は、貴族を中心とした華やかな平安時代も末期になると、天然痘などの疫病、日照りによる飢饉、武士の台頭など、混乱期を迎えた。仏教は比叡山の僧兵による三井寺の焼打ちなど、内部抗争が絶えなかった。釈迦入滅後2千年を経ると、教えだけは残るが悟りを得る者はいなくなるという末法思想が流行した。人々は無常観に沈潜し、神仏の助けを懇願した。貴族も庶民も諸魚無情を感じた。兼好も例外ではなかった。それに呼応して現れたのが、鎌倉新仏教で、阿弥陀仏に救いを求める浄土信仰、法然の浄土宗、親鸞の浄土真宗、一遍の時宗が民間に広まった。武士は座禅によって悟りに至る禅宗、栄西の臨済宗、道元の曹洞宗などが受け入れられ、法華経が中心の日蓮宗も発生した。お盆や先祖供養の習慣も、収穫祭と合わさって農民の間にも広まった。仏教が持つ無常観の雰囲気は、文芸にも多大な影響を与え、平家物語などの軍事小説や、出家した世捨て人による隠遁文学が盛んになった。徒然草のほかに、鴨長明の方丈記、西行の山家集などが後世に残った。貴族社会で出世した兼好は、慕っていた貴人が亡くなったのをきっかけに、宮仕えを辞め、世を捨てて出家したと考えられる。兼好のような世捨て人は、出家しても寺には所属せず、僧侶とは区別して、一般には沙味、沙味尼と呼ばれていた。兼好も貴族社会から遠去って、小野の山里、延暦寺の別院修学院の辺りの庵に住んで、一人ひっそり暮らしていたが、歌人としては貴族達との交流を断たなかった。仏教思想の浸透と同時に、兼好のような暮らしを求める人は多く、社会もそれを受け入れていた。そうした立場の人々によって、和歌や文芸、学問の世界で偉大な業績が残った。
2010.06.01
コメント(0)
-

ナツツバキ
椿によく似た白い花を咲かせる。別名シャラノキは、インドの沙羅双樹と間違われたもの。椿の仲間では珍しい落葉樹で、秋には黄葉が見られる。
2010.05.31
コメント(0)
-

百人一首
百人一首 夜をこめて鳥のそら音ははかるとも よに逢坂の関はゆるさじ 清少納言 (夜明け前に、鶏の鳴き真似で騙そうとしても、逢坂の関を通すことは許しませんよ) 清少納言は、清原元輔の娘で、枕草子の作者。中宮貞子の女房として仕えた。
2010.05.31
コメント(0)
-

徒然草 2
吉田兼好の徒然草は、清少納言の枕草子と並ぶ、二大エッセイ(随筆)であり、鴨長明の方丈記を含めると、三大エッセイと言われている。随筆という言葉は、近世の伴信友から始まったので、徒然草の時代は、これを日記と言っていた。吉田兼好は、代々神祇官を務めていた卜部家の三男で、本名はカネヨシといい、出家してケンコウとなった。姓の吉田は、卜部家が京都の吉田に在り、室町時代に吉田神社の神官になって、吉田姓を名乗るようになったことから、江戸時代になって吉田さんと呼ばれるようになった。祖父が関東に下り、父は関東生まれだが、後に京へ戻り吉田に住んだ。母親のことは不明。幼い頃から知的だった兼好とその父との会話「仏とはどのようなものでございましょう?」「仏とは、人が成るものじゃ」「どのようにして仏になるのですか?」「仏の教えによって」「仏は、最初は誰から学んだのでしょう?」「その前の仏」「元祖の仏とは?」「天から降ってきたか、地から現れたのであろう」父親は、息子に問い詰められて答えられなくなってしまった。19歳の頃、後二条天皇の蔵人として宮仕えの生活を始めた。蔵人とは、宮中の機密文書や情報を取り扱う天皇直属の役人。数年後、左兵衛佐に出世し、左兵衛府で宮門の守備、行幸など天皇家の人々の外出の警備などに従事した。また、藤原為世という歌道師範に弟子入りして、歌道にも精進し、40歳代になると、二条流の四天王と称されるほどになった。出家したのは30歳代で、比叡山の横川に籠ったり、神奈川県の称名寺を拠点として、関東を旅して回った。40歳代で京都に戻り、歌人として政治の中心人物の周囲で暮らした。仕官、歌人、世捨て人と、様々な立場で時代、人間、事物を観察してきた兼好が、徒然草の執筆を始めたのは、48歳以降と考えられている。没したのは68歳ぐらいといわれている。
2010.05.31
コメント(0)
-

クレマチス・テキセンシス
クレマチス・テキセンシスは、日本原産のカザグルマや、中国のテッセン、ヨーロッパのピチセラやインテグリフォリアなどの原種や交配種があります。花びらのように見えるのは雄しべが弁化したガク片です。
2010.05.30
コメント(0)
-

百人一首
百人一首 いにしえの奈良の都の八重桜 けふ九重ににほいぬるかな 伊勢大輔(昔、奈良の都で咲いていた八重桜が、今日は九重の宮中で咲いている)伊勢大輔(いせのたいふ)は、大中臣能宣の孫。上東門彰子に仕え、和泉式部や紫式部などと親交があった。
2010.05.30
コメント(0)
-

岡山城
オキシペタルム山陽道沿いにあった主要な城は、幾多の戦火や政治的意図を潜り抜けて生き残っていた。だが、残念なことに、第二次世界大戦の空襲でその多くが焼け落ちてしまった。岡山城の天守閣も、昭和20年に焼失し、現在ある城は復元されたものである。岡山城は別名烏城と呼ばれ、黒々とした外観は重々しい風格がある。この城の軍事、海運上の重要性は、築城から時が経るほど高まっていった。それに目をつけた宇喜多直家は、謀略をめぐらして城主の金光宗高を殺してしまい、戦もしないで城を手に入れてしまった。直家は領地を拡大し、城の改築をして、城下町を整備し、その上山陽道の道筋まで変えてしまった。直家は勢力を広げたが、織田家と毛利家がしのぎを削っている中で、呆気なく病死してしまった。跡継ぎは、僅か9歳の八郎で、策士であった直家を失った家臣たちは、城主の急死を翌年まで隠し続けた。やがて、織田家の家臣羽柴秀吉が城を訪れた時、八郎の母であるお福は、我が子の将来を秀吉に託そうと考え、秀吉を歓待した。八郎は秀吉の側近となり、名前の一字をもらって秀家となった。前田利家の娘、豪姫を娶り、備前から美作、備中東部、播磨西部を領地とし、五十七万四千石の大名になった。秀吉は、天下平定に一息つくと、秀家に城を改修するように勧めた。秀吉の縁者として「相応しい城にしろ」というわけだった。五層六階の威風堂々とした烏城が築かれたが、秀家はこの大事業を楽しむ余裕はなかった。3年後には、関が原の合戦になり、秀家は西軍の副将として戦ったが、敗れて八丈島へ流されてしまった。岡山城には、小早川秀秋が入城した。秀吉の甥で、幼児の頃から秀吉の養子として育てられたが、関が原では東軍に寝返った男だ。秀秋は、城をさらに改築した。しかし、入城して2年ほどで若死してしまった。死因は不明で、色々な説が取り沙汰された。
2010.05.30
コメント(0)
-

百人一首
百人一首 大江山 いく野の道の遠ければ まだふみも見ず天の橋立 小式部内侍(大江山を越えて生野を通る道は遠いので、まだ天橋立に行ったことはありませんし、母からの手紙も見ていません)小式部内侍(こしきぶのないし)は、和泉式部の娘。母とともに上東門院彰子に仕えた。名前は母と区別するため小式部と呼ばれた。
2010.05.29
コメント(0)
-

旧古河邸
イギリス人建築家ジョサイア・コンドル晩年の傑作。建物は大正6年に古河財閥三代当主虎之介の本邸として建築された。外壁は新小松石を積み、屋根はスレート葺き、暗褐色の山荘風で地味な感じがするが、内部はレンガや石で作られた西洋館としては珍しいほど明るく温かい感じで、財閥の本邸とは思えない控えめな上品さがある。内部は残念ながら撮影禁止。家族が日常生活をしていた二階部分は、外からは想像もつかない日本間になっていて、仏間や床の間がある。コンドルが日本建築にも造詣が深かったことが判る。寝室の隣には、八畳ほどの着替え室があり、洋風の浴室にはなんと五右衛門風呂がある。ジョサイア・コンドル明治10年、現在の東京大学工学部の教師として招聘され、優れた日本人建築家を多数育てた。彼は日本文化を深く愛し、この建物の他、多くの作品にその影響が見られる。
2010.05.29
コメント(0)
-

八重咲きドクダミ
民間薬の代表格で、名前は毒を抑える作用があるので、毒溜めから。八重咲きは珍しい。
2010.05.28
コメント(0)
-

百人一首
百人一首 やすらはで 寝なましものを小夜ふけて かたぶくまでの月を見しかな 赤染衛門(あなたが来ないと分かってれば、さっさと寝てしまったのに、来るかと思って待っていたら、夜が更けて西に傾いた月まで見てしまった)赤染衛門(あかぞめえもん)は、藤原道長の妻倫子と、その娘上東門院彰子に仕えた。栄華物語の作者とされている。
2010.05.28
コメント(0)
-

古事記 1
カルミア旧約聖書では、「神は自分の形に似せて人間を創り、これに地上の全てを治めさせた」こうしてできたのが人間、いわゆるアダムである。アダムの誕生から時が経って、イヴが創られた。聖書に関する限り、人類最初の人間はこの二人であるとされている。古事記は、高天原の五柱の神は、地上に成った神とは別扱いで、天神という。この天神に対し、地上にも次々と神が生まれた。1 脂のように漂っていたものの中から成ったのは、地を神格化したクニ ノトコタチの神。2 脂が固まって広々した沼になったことを示す、トヨクモノの神。 この二柱の神も単独神で、姿を現すことはない。3 ウイジニの神(男性神)と、スイジニの神(女性神)は、合わせて 一神とし、脂の固まりから、海と陸に分かれたことを意味している。4 ツニグイの神(男性神)と、イクグイの神(女性神)も、合わせて 一神とし、陸に植物が芽吹き育って行くことを示している。5 オオトノジの神(男性神)とオオトノベの神(女性神)も、合わせ て一神とし、大地が固まったことを示す。6 オモダルの神(男性神)と、アヤカシコネの神(女性神)も、合わ せて一神とし、オモダルは大地の表面が整ったことを示し、女性神は 「あやにかしことし」とあげた悦びの声を神格化している。7 イザナギの神(男性神)と、イザナミの神(女性神)は、互に誘い 合った神という意である。 ここまでを、神代七代という。
2010.05.28
コメント(0)
-

百人一首
百人一首 有馬山 猪名の笹原風吹けば いでそよ人を忘れやはする 大弐の三位(有馬山の近くの、いなの笹原にそよそよと音をたてて風が吹く。どうしてあなたを忘れられましょう、決して忘れはしません)大弐の三位は紫式部の娘。母と同様に中宮彰子に仕えたが、その後、後冷泉天皇の乳母に抜擢された。
2010.05.27
コメント(0)
-

アスチルベ
ユキノシタ科の多年草。別名ショウマ。日本のショウマ類と中国のショウマ類を、ドイツで改良したもので、これらの園芸品種をアスチルベという。
2010.05.27
コメント(0)
-

万葉集 山上憶良
万葉の開花期である第三期には、独特な個性のある歌人が登場し、歌風も多様化した。山上憶良は、ポスト柿本人麻呂の位置にいて、山部赤人や大伴旅人などと同時代を生きた。旅人と共に、大宰府を中心とした文雅の中で多くの秀作を詠んだ。億良の名が最初に史書に登場するのは、遣唐使の書記官に選ばれて渡唐した701年だった。漢文学や仏教、儒教などの素養が深く、帰国後は、後の聖武天皇が皇太子時代の教育係、伯耆の守や、筑前の守などを歴任した。屋良の歌の特徴は、愛別離苦、生老病死、貧困など社会問題や人生を真正面から取り上げた。人生と対峙し、庶民生活の哀歓をみつめて歌にした。また、親子や家族の問題、子を愛する気持ち、家族を思う心などを詠んだ。瓜食めば 子ども思ほゆ 栗食めば まして偲はゆ いづくより 来たりしものぞ まして偲はゆ いづくより 来たりしものぞ まなかひに もとなかかりて 安眠し寝さぬ(瓜を食べれば愛しい子らを思い出すし、栗を食べればいっそう切ない、いったい子どもの面影はどこからやって来るのか、目の前にちらついて眠れないほどだ)この歌の前には、長い漢文の序文があり、釈迦如来の言葉が引用されている。「自分は衆生を我が子のように大切に思っている。子への愛ほど深いものはない」釈迦でさえそう思うのだから、我々凡人はどうして子を愛さずにいられよう。憶良は端的に屈託なく、人間の愛を詠った。
2010.05.27
コメント(0)
-

百人一首
さつき百人一首 めぐりあひて 見しやそれともわかぬ間に 雲がくれにし夜半の月かな 紫式部(久しぶりに逢って、見たのがその人だったかどうか見定める暇もなく、雲間に隠れてしまった月のように、あなたは姿を隠してしまった)紫式部は、源氏物語の作者として有名。父が式部省の学者だったため、藤式部と呼ばれ、後に紫の上にちなんで紫式部になった。幼少時から漢文に親しみ、才女としての逸話が多い。藤原宣孝と結婚し、大弐の三位(娘)を儲けた。夫と死別後、中宮彰子の女房として仕えた。
2010.05.26
コメント(0)
-

アカツメグサ
赤詰め草は、昔オランダからガラス器が輸入された時、パッキンとしてこの花の干したものが詰められていたので、この名前になった。白いクローバーの花は白詰め草。牧草としても入って来て、それが野生化した。
2010.05.26
コメント(0)
-

店番猫
バラ店先に猫が寝ている光景は実に良いので、無くなってもらいたくない。テレビなどで紹介される例が少なくないということは、そうした光景が少なくなっているからか。魚屋の店番をしている猫というのが居た。最初は子猫が怪我をしていて、その母猫が救いを求めるように店の前へ来たという。魚屋さんは猫の親子を二階に住まわせるようになった。魚といえば猫の好物で、敵対関係のように思えるが、その魚屋さんが猫の親子を飼っている。猫の親子は、大好きな魚が並んでいるショーケースの上に座っている。魚屋さんの夫婦が、猫の後ろでニコニコして商売している姿を想像すると、なんとも平和な気持ちになる。
2010.05.26
コメント(0)
-

タニウツギ
タニウツギ雪の多い日本海側に多く、日本産のウツギではもっとも美しい。
2010.05.25
コメント(0)
-

百人一首
百人一首 あらざらむ この世のほかの思ひ出に 今ひとたびのあふこともがな 和泉式部(私は間もなくこの世を去るでしょう。思い出にせめてもう一度だけ、あなたにお逢いしたいものです) 和泉式部は、橘道貞と結婚し、小式部内侍を生んだ。道貞が和泉守だったため、この名前で呼ばれた。「和泉式部日記」の著者。
2010.05.25
コメント(0)
-

王国の名称
グレートブリテンと北アイルランドの連合王国、これが何のことかおわかりでしょうか。これは英国の正式名です。日本人がイギリスと呼んでいる国は、ブリテン国のイングランド、スコットランド、ウェールズ、そして北アイルランドの4カ国が統合された国なのです。ブリテン島の3カ国のうち、イングランドはアングロ人の国という意味で、アングロサクソンの国。スコットランドとウェールズはケルト人の国でした。ケルト人は、紀元前500年ごろからブリテン島に住んでいました。ダイアナ妃は、プリンセス・オブ・ウェールズと呼ばれていました。ウェールズはケルト系のキムブル族が住んでいたので、その部族にちなんで「カムブリア」という地名でした。5世紀になって、ヨーロッパ大陸からアングロサクソン人がやって来て、その地名をウェリクス(外国人)と呼ぶようになりました。キムブル族が、アングロサクソンとの同化を拒んで、孤立した生活を選んだためと言われています。スコットランドにも先住民のカレドニ族が住んでいて、カレドニアという地名がありました。やがてローマ帝国が衰え始めた頃、アイルランドにいたケルト系のスクイト族がこの地域へ移住して、カレドニ族と混血し、混血後もスクイト族を名乗っていましたが、アングロサクソンが、彼らをスコットと呼んでいたので、スコットランドという地名になりました。では、日本ではどうしてイギリスと呼ぶのでしょう。それは、ポルトガル語のイングレスという呼び方が日本語化したものです。
2010.05.25
コメント(0)
-

百人一首
百人一首 滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほ聞こえけれ (大納言公任)(滝が枯れてから年月が経ったが、この滝の名声は流れ伝わり、今でもその音が聞こえてくる) 大納言公任(だいなごんきんとう)は、漢詩、管弦、和歌に優れ、三舟の才を備えているといわれていた。
2010.05.24
コメント(0)
-

キツネノカミソリ
キツネノカミソリが早くも咲き始めていました。花色が狐の毛色に似ていて、葉がカミソリのようなのでこの名前らしい。花が咲いている時には葉が無く、翌年の早春に細長い葉が出る。葉と花が顔を合わせることはない。
2010.05.24
コメント(0)
-

徒然草 1
クレマチス徒然草 1つれづれなるままに、日暮らし、すずりに向かひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。(することもなく、暇に任せて、すずりに向かって心に浮かんでは消えていくつまらないことを、何となく書き付けていると、妙な気持ちになる)吉田兼好の徒然草は、1330年の夏から、翌年の秋にかけて書かれたと考えられているが、これは推測で、当時の作品は、タイトルをつける習慣がなかったし、作者名すら記されていなかった。成立の経緯は、歌人であり、武将でもあった今川了俊と、兼好の弟子の命松丸が、兼好没後に庵の壁に貼られていた反故(書き散らされた紙)を集めて、二冊の本にまとめたということが、和学者の三条西実枝の「昆玉集」に記されている。しかし、段が整然と並んでいることから、実際には兼好自身がまとめたものと考えられる。当時は印刷などなかったので、すべての書物は手書きの写本で、次々と何人もが書き写し伝わってきた。人から人へと伝わる際には、やはり本のタイトルが必要となり、冒頭の「徒然」と、草稿を謙遜した「言い草」の草を合わせて「徒然草」となったものと考えられている。江戸時代には、徒然草が大流行した。流布本の代表は、烏丸光広という公卿が、1613年に写した本である。
2010.05.24
コメント(0)
-

マツバギク
マツバギクは葉が松葉に似ていて、花は菊に似ているのでマツバギク。元気そうに見える花だが、夜間や曇天の日は咲かない。花ことばは「なまけもの」。
2010.05.23
コメント(0)
-

百人一首
百人一首 忘れじの 行く末まではかたければ 今日をかぎりの命ともがな 儀同三司の母(私を忘れないというあなたの言葉が、いつまでも変わらないとは思わないので、そう言ってくださった今日、このまま死んでしまいたい) 儀同三司(ぎどうさんし)の母は高階貴子。藤原道隆の妻。
2010.05.23
コメント(0)
-

宇都宮城
バラ江戸城北方防御の砦として、かつて宇都宮には勇壮な城郭があった。その城を目指して将軍秀忠の行列は進んでいた。家康の七回忌のために、日光東照宮への旅の途中で、宇都宮城を宿とする予定だった。ところが、早馬の使者が書状を持って、行列をとらえた。書状には、宇都宮城主の本多正純に謀叛の動きがあると書かれていた。城内には、将軍暗殺のために吊り天井が仕掛けられ、その下を通る秀忠は落ちてくる天井の下敷きになって圧死するというので、秀忠は震え上がった。しかも正純は、その秘密を守るために、仕掛けを作った大工や同心百名以上を殺戮したという。秘密が漏れ出したのは、与五郎という若い大工が、一目恋人に会いたいばかりに、警戒の目を掻い潜って抜け出し、恋人に会って、その際吊り天井の秘密を恋人に話していたからだった。与五郎は、何のための仕掛けなのかは知らなかったが、恋人になかなか会いに来られない言い訳に、吊り天井の仕掛けを作るのが大変だからと、一部始終を話したのだった。しかし与五郎は、その日の内に惨殺されてしまった。恋人は、与五郎に聞いた話を遺書に認めて、首をくくって死んでしまった。娘に死なれた父親は、遺書に書いてある恐ろしい秘密を知って、家康の娘である加納殿にそれが伝わるように手配した。加納殿は、将軍の身に一大事じゃと色めきたち、早馬で使者をおくったのだった。ところが、吊り天井の話は正純を失脚させるための作り話だった。将軍職を引退した後の家康は、徳川家最高の権力者で、正純はその家康の子飼いの家臣で絶大な権勢を振るっていた。二代目の秀忠にとって、正純は目の上のたんこぶ的存在だった。江戸に戻った秀忠は、宇都宮城を家宅捜索したが、何も見つからなかった。それでも秀忠は、正純を江戸から遠ざけたい一心で、正純を左遷し、移封してしまった。冤罪を蒙った正純は、必死で反論したが、秀忠に難癖をつけられ、上げ足をとられて、完全に失脚してしまった。宇都宮城は、その後も幕府の要人が城主になり、幕末には戸田氏が治めていた。幕末になって、勤王派についた宇都宮城は、幕府軍の猛攻撃を受け、名城と言われた城郭は跡形もなく崩れ去ってしまった。その砲弾による火災で焼け落ちた城址に、立ちつくしている人影があった。「あれはきっと、正純様の亡霊だろう」城下の人々はそんな噂をし合っていた。
2010.05.23
コメント(0)
-

ハコネウツギ
食物繊維日本の昔の一般家庭の食事は、焼き魚に野菜の煮物、ご飯に味噌汁と漬物といった献立だった。その何気なく食べられていた食材が、現在は健康食として脚光を浴びている。日本の食生活は豊かになったように思われているが、栄養面ではむしろ貧しくなっている。食の欧米化が進んで、栄養バランスは大きく崩れてしまった。肉食が増え、食物繊維の摂取が半減し、脂肪摂取率が5倍になり、成人病の死亡率も倍増した。食物繊維は現在では、5大栄養素に次ぐ第6の栄養素といわれているが、昔は食物繊維は消化されないと考えられていた。最近の研究では、その働きが明らかになり、大注目されるようになった。食物繊維の働きは、腸の働きを活性化することと、腸内の善玉菌の働きを助けること、老廃物や毒素を排出してくれることは良く知られているが、もう一つ期待されている働きがある。それは、脂肪や糖分の消化吸収をゆるやかにする働きだ。食物繊維は、糖が急激に吸収されるのを抑え、コレステロールの吸収をやわらげてくれる。飽食の時代、生活習慣の乱れが気になる現代人にとって、脂肪や糖分の摂り過ぎは健康に関わる大問題だが、食物繊維を摂ることで、我々は健やかさを保つことが出来る。生活習慣の乱れや、誤ったダイエットなど、食生活はカロリーコントロールに偏りがちだが、日本人の総摂取カロリーは、それほど高くない。食事の内容に占める脂質の割合が増え、食物繊維の割合が減っていることが、実は問題なのである。今、食事の内容を見直して、カロリー計算よりも、食物繊維をより多く摂取することを心がけたい。食物繊維が豊富な食材は、ごぼうなどの根菜類や玄米などの全粒穀物など、ゆっくり食べて、ゆっくり排泄される食品。リンゴ、豆類、えび、かに、ココア、カボチャ、キャベツ、こんにゃく、海藻類など。
2010.05.22
コメント(0)
-

ヤマボウシ
ヤマボウシはハナミズキに似た白い清楚な花を咲かせます。ハナミズキは、苞の先端がへこんでいますが、ヤマボウシは先端が尖っています。実が熟すと甘く、果実酒にできます。
2010.05.22
コメント(0)
-

九戸城
ミカンの花豊臣秀吉に謀られた城主、九戸政実は、武将数名を引き連れて門外へ出た。迎えた秀吉配下の浅野長政は、政実を丁重に一人引き離して送り出すと、すかさず攻撃の合図を送った。一気に大軍が城内へなだれ込んだ。九戸城の将兵は、態勢など整える暇もなく退却するばかりだった。秀吉軍は、女子供も容赦しなかった。勝どきの声と、断末魔の叫びが交差した。そして包囲された城には火がかけられた。立ち昇る炎、轟音のなかに逃げ惑う人々の絶叫が渦巻いた。振り返った政実の目に、阿鼻叫喚の地獄絵図が広がった。我が城が燃え落ちる、真っ黒な煙りを背に、政実は成す術がなかった。「おのれ、謀りおったな!」その日のうち、政実は奥州討伐の総大将豊臣秀次の前に引き出され、無慚に斬り殺された。政実の首は京へ送られ、晒された。その形相は凄まじく、見た者は誰もが怨念を感じずにはいられなかった。こうして九戸政実の乱は平定され、九戸城には、南部宗家の座を政実と争って勝った南部信直が入城することとなった。城内は片付けられたが、まだすす臭さや、屍の臭いが残っていた。「さすがは豊臣配下の強者、たった1日で皆殺しだ」などと、笑う配下を信直はギロリと睨みつけ、「済んだことだ、今後一切、政実のことは口にするな!」と命じ、あの斬首を思い出していた。「政実だけではない、小田原では北条氏が自刃させられた、秀吉は無慈悲な人だ、政実の恨みが降りかかるかもしれぬ、ましてこの城で起こったこと、怨念も強いであろう」信直は、政実と勢力争いしていたが、怨霊のことを思うと不気味で、戦国の世が終わり、徳川幕府になって落ち着くと、災厄を恐れて居城を盛岡へ移した。九戸城はうち捨てられ、跡は荒れ放題になった。ある年の秋風が吹き始めた頃、南部藩城下では奇妙な噂が流れていた。青白い炎の中、鎧兜の侍が歩き回って、苦しげに叫んでいるのを、何人もの人が目撃した。見た者は、三日三晩熱に浮かされ、遂には死んでしまった。毎年九月になると、城下はその話で持ちきりだった。政実が首をはねられたのが九月四日で、その日の夜になると、九戸城址に亡霊が出て、地獄絵図が再現されるのだった。炎に包まれて死んでいった将兵や女子供が迷い出て、その傍には政実の晒し首が、凄まじい形相で立ちすくみ、無念の叫びをあげているという。
2010.05.22
コメント(0)
-

百人一首
百人一首 嘆きつつ ひとり寝る夜の明くる間は いかに久しきものとかは知る 右大将道綱の母(嘆きながら一人で寝る夜の長いことを、あなたはご存知でしょうか) 道綱の母は、藤原兼家の第二夫人となり、道綱を生んだ。蜻蛉日記の著者。
2010.05.21
コメント(1)
-

ムラサキツユクサ
ムラサキツユクサは、観葉植物のトラデスカンチャの仲間で、春から秋まで次々と花を咲かせます。紫と白の他にも、ピンクや赤がありますが、見たことはありません。花が終わると、種がたくさんつきます。
2010.05.21
コメント(0)
-

古事記
シャクナゲ本居宣長は、読み下すことが非常に難しい古事記を、美しい日本語で上手に読み下した。宣長は、生涯の師と仰いだ賀茂真淵とは、たった一度しか会わなかったが、真淵に古事記の研究を勧められた。真淵は、古事記を読み解こうという志を持っていたので、先ずいにしえの心を理解しようと考え、万葉集を研究し始めた。そのうち老齢になってしまい、すでに古事記を研究する時間がなくなってしまった。1763年5月25日、伊勢松阪で宣長と真淵はたった一度出会い、古事記研究という大事業を約束した。真淵67歳、宣長34歳であった。後に宣長は、師の悲願であった古事記研究の成果として、「古事記伝」を世に送り出したが、時の学者たちによって厳しい批判を受けてしまった。しかし、宣長の「古事記伝」は、現在も古事記研究の先駆けというべき偉大な業績として認められている。古事記が著されたのは、712年ごろのことで、当時読み書きが出来る人はごく一部の人々に限られていたので、読者が多かったとは考えられない。では何のために難しい歴史書を作ったのだろう?古事記は「日本書紀」以下の正史とは異なり、史記、漢書、後漢書に倣って書かれた本ではなく、大和の碑田阿礼なる人物によって書かれたと言われている。そうであるなら、万葉仮名で書けば良いものを、漢文などを混入して判読し難くしたのは何故か?碑田阿礼なる人物は実在せず、安麻呂が勝手に著したものかもしれない。判読し難くしたのは、何か別に隠された意味があるのかもしれない。万葉仮名と漢文を混用して読みにくくした表向きの理由は、要約できる部分は漢文にしたと言われているが、あまり説得力は無い。何事も、古ければ古いほど謎は多いものであるが、古事記は特に不自然で、存在理由、著された意図が分からない。
2010.05.21
コメント(0)
-

ハゴロモジャスミン
百人一首 明けぬれば 暮るるものとは知りながら なほ恨めしき朝ぼらけかな 藤原道信朝臣(夜が明ければやがて日が暮れ、そうしたらまたあなたに逢えると分かっているが、やはりしばらくでも別れなければならないのが辛い明け方です) 藤原道信は和歌の名手として評判が高く、23歳で没し、人々から惜しまれた。
2010.05.20
コメント(0)
-

カルミア
アメリカシャクナゲ、ハナガサシャクナゲとも呼ばれるカルミアは、人形のドレスのような小さな花が房になって咲いています。つぼみは金平糖のような形で、原産地北アメリカではこの木でスプーンを作っていたので、スプーンの木と呼ばれていました。日本には大正時代に渡来しました。
2010.05.20
コメント(0)
-

万葉集 高橋虫麻呂
柿の花万葉歌人の中には、都から離れた異郷の伝説や習俗に憧れて、郷愁を歌に込めたロマンティックな歌人がいた。高橋虫麻呂は、藤原宇合が常陸守だった頃に知り合い、仕え続けた下級官人だった。常陸国風土記の編纂にもかかわった。虫麻呂は各地へ旅をして、伝説や風俗・行事に触れ、それをテーマに歌を詠んだ。常陸国に赴任中の虫麻呂は、常に眺めていた筑波山を詠った。男神に 雲立ち上り しぐれ降り 濡れ通るとも 我れ帰らめや(男体山に雲が立ち上って時雨が降り、びしょ濡れになっても、この美しい夜の途中で帰ったりはしない)これは歌垣に詠ったもので、歌垣とは春と秋に男女が集まって飲食し、歌を掛け合う神事で、求婚の場でもあった。今なら合コンだね。男体山と女体山の中間でこの神事が催されたのだが、都の洗練された文化を知っている虫麻呂にとって、関東一円から大勢の男女が集まって来る歌垣は、さぞ魅力的で情熱的に映ったのであろう。
2010.05.20
コメント(0)
全520件 (520件中 1-50件目)
-
-

- まち楽ブログ
- ウォーク日和に恵まれいいウォークで…
- (2025-11-17 18:30:52)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-

- 株主優待コレクション
- カワサキ (3045)の優待品が到着しま…
- (2025-11-18 12:22:26)
-