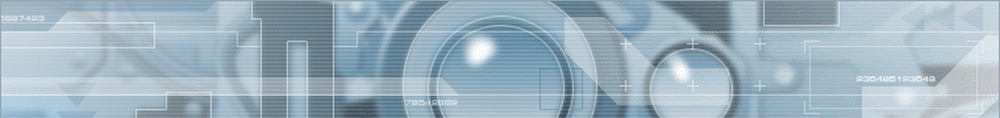前回
の続きです。
6 アダム
A.J.Adam (Mosel) ラシーヌ
Dhroner Hofberg feinherb 2011
7 ヘイマン・ルーヴェンシュタイン
Heymann-Löwenstein (Mosel) ザ・ヴァイン Winninger Uhlen "Laubach" 2007
8 エムリッヒ・シェーンレバー
Emrich-Schönleber (Nahe) 稲葉
Monzinger Frühlingsplätzchen Kabinett 2005
これらのワインについてとのその時に話したことを書いていきます。
ワイン自体の感想はかなり少なく、ファインヘルプの説明ということに重点をおいて書きます。
6のアダムはピースポート村近くのモーゼル川の支流の渓谷ドーロンにある生産量が25,000本の小規模の生産者です。
この造り手の大きな特徴は、名声を博していた100年前のドイツのワイン造りを目指しているということです。そのためにできるだけ化学薬品など人間の手を介入しない自然の力でのワイン造りを行っています(この醸造所に興味のある方は北嶋氏の 過去のブログ
の記事をごらんになってください)。
今回出したファインヘルプもやさしい味わいで心地よい甘みもあり素朴、手造りのワインと言う言葉がぴったりな味わいでした。
人の手を介入しないということでアダムは発酵も天然酵母によるものです。
トロッケンの場合は自然酵母だとアルコール度数が高いところに達する前に発酵が止まってしまいトロッケンの残糖より残ってしまうので人工酵母を使用します(最初から人工酵母のところが一般的ですが、補うために人工酵母を使用するという手法もあります)。自然酵母のみのトロッケンもありますがかなり少ないと思います。
ファインヘルプだと人工酵母を使用しなくても造れます。なので自然な造りという意味合いでは食事に合わせるワインとしてはファインヘルプの範囲が最も適しているのです。
そして発酵をコントロールしない自然酵母の造りの場合には発酵が止まるタイミングが毎年一定にはならないので年によって残糖の残り具合がかわってきたりします。自然にまかせる造り手の場合はそれを良しとしています。畑のテロワールによるぶどうの個性を尊重するからです。僕の大好きなザールの ペーター・ラウアー
(訪問した時のことはこちら、造り手の思想に着いています)はその代表的な造り手です。そしてその味わいの幅広さをカバーできるのがファインヘルプという規定にしばられていないくくりなのです。
また、そういうことによって自然酵母のワイン、ファインヘルプのワインは11か12パーセントのアルコール度数のものが多いので比較的軽く飲みやすいというのもファインヘルプの魅力だと僕は思っています。
それと、アダムは木樽ですが、やわらかいファインヘルプの味わいには木樽がむいていると思っています。僕が好きなファインヘルプは木樽が多いという事なのですが。今回出したワインはほとんどが木樽(大樽)を使用しています。
7のレーベンシュタイン(ドイツ語読みだとルーではなくレーになります)は今までのワインとは少しベクトルが違います。
まず、この造り手はフォルクセンと同様にトロッケンの表記は使っていません(ファインヘルプの明記もありません)。2年前に当主が来日した時に力説していたことがあって( こちら
で書いています)、それは残糖などを数値で区別して分類するのはナンセンス、音楽は数字や理論というのを気にしないで楽しむだろ、ワインもそういうものでなくてはならない、というものです。このことについは後でも少しふれます。
最近の造り手が辛口に関してはシュペートレーゼなどの等級を使わないのと同様にここやフォルクセンも等級のつくPrädikatsweinではなく辛口系は全てQualitätswein(QbA)としてリリースされています。
畑名がついてるこのワインはこの醸造所の最上級のクラスのワインです。トロッケンであればグローセス・ゲヴェックスとしてリリースされるのですが、トロッケンの規定ではないのでGGにはなりません。しかし畑はエアステ・ラーゲErste Lage(ブルゴーニュの畑に対するグランクリュ制度のようなもの)に認定されているのでワインラベルにはそのマークはついています。2012年からVDPの制度が変わってトロッケン以外のエアステ・ラーゲの畑からの最上級ワインにはワインに対してグローセ・ラーゲGrosse Lageという呼称をつけられるようになったのでこれからはこの醸造所の畑名の最上級クラスのは名乗るかもしれません。
レーベンシュタインのトップクラスのはUrlenの区画を土壌の性質ごとに分けられていて何種類かリリースされているのですが、このラウバッハが比較的甘みが残っていてファインヘルプを知るという面では一番面白い教材だと思ったのでこのワインを選びました。
実際に飲むと、6年熟成しているので甘みとしての感覚はほとんどありませんでした。でもふくよかなのは残糖があったからこそだと思います。残糖が熟成して味わいの深みとして表れていました。上品な余韻もあります。
ドイツワインぽくないなーと思ったのですがそれはフルーティーさがないからだと思いました。ドイツの枠を超えてグランクリュのワインだなーという印象をうけました。ドイツ以外でも評価が高いのがよくわかるワインでした。
昨年9月のドイツでの VDPグローセス・ゲヴェックスの試飲会
ではモーゼルだけトロッケン、すなわちGGではないワインも出品されていました。もちろんリースリングです。醸造所のファインヘルプの最上級のものでグローセ・ラーゲに相当するものです。トロッケンではないワインでも最高のものがあるといういことを証明している結果です。
こういう動きがでてきているのは、レーベンシュタインやフォルクセンが残糖数値を気にしないで最高のワインを造り上げるという考えを持ってワイン造りをしてきたからこそなのだと思います。モーゼル、ザールからは残糖を残したファインヘルプの範囲の味わいからも最高級のワインが造られるということが認められてきているのです。
辛口というのはトロッケンのくくりではない、甘みがあったらダメというのではなく、ファインヘルプの範囲でもトロッケンと同じくくりの中で素晴らしいと思えるワインを造ることができる、ということなのです。数値で分類するなと言っているレーヴェンシュタインの思想は、こういったワインができるという自信も影響していると思います。
個人的にはモーゼル、ザールのリースリングはトロッケンよりファインヘルプのほうがおいしいワインを造るのに向いていると思っているのでこの動きは非常に嬉しく思っています。
ラインガウのゲオルク・ブロイヤーも2011年産からシュロスベルクなど一部の畑は残糖を残したトロッケン表記ではないワインにしていますしこれからもどんどん増えていくことでしょう。もちろんファルツなどトロッケンとして素晴らしいワインができる地域、トロッケンが素晴らしい醸造所もたくさんあるということは否定していません。
ファインヘルプには、甘みを残した味わいというのを意図しているファインヘルプと、残糖を気にしないで最高のものを作り上げるためのファインヘルプ、という2つの要素があることがこのレーヴェンシュタインのワインで参加者にはわかっていただけたかと思っています。
前者は比較的安価なワインに多く、後者は高いワインに多いのです。といっても全てがそうといわけではなく、下のクラスでも後者の考えで造られたものもあるし、シュペートレーゼ、アウスレーゼクラスの収獲糖度が高い高品質のぶどうから造られているから価格の高いファインヘルプも存在します。
質(価格)による違い
野生酵母など人の手をなるべく介入させない造り方とファインヘルプの関係性
数値で区別するのはナンセンス、という考え
残糖を気にしないで最高のワインを造りあげようとしている醸造所の意図と志
ここまででこれらのポイントについてはふれられていると思います。
甘口は熟成して甘みが抜けてくるとファインヘルプに近い味わいに。共通点と相違点は?
全ての甘口ワインにいえることではないですが、5年以上経っているカビネット、10年以上経っているシュペートレーゼは甘みが抜けてきます。そういう甘口ワインは若いファインヘルプと感覚としての甘みが似ているので味わいが近いということも話しておきたかったのです。
今回用意したのはナーエの8年経っているもので、産地が今までとは違うし良い例になるか少し不安だったのですが結果的に適している教材となりました。
パッと飲んで感じると似ているなーと思いました。でもやわらかい心地よい甘さと余韻の長さは、熟したぶとうだから、残糖が多く残っていたからこそ、というのが今まで飲んでいった6までのワインと異なっている部分でした(6、7は少ベクトルが違うので省いて考えています)。これはグーツワインクラスのファインヘルプとの比較で、シュペートレーゼ・ファインヘルプと比較するともう少し似た部分もあるのかなーとも思いました。でも熟成したことによる深みというのは大きく違うと感じる部分で、これは好みで使い分けていただければと思います。
僕はたくさん手に入るのなら熟成して甘みの抜けたシュペートレーゼを食中酒としてファインヘルプのような使い方をしたいのですが日本ではなかなかそういうワインを大量買いできないので我慢しています。
注意書きとして付け加えますが、評価の高い畑からの質の良いぶどうと良い造り手により醸造されたワインの場合は、比較的寿命が長くて甘みは長く残っているワインもあります。ということは逆の場合は甘いが抜けるのが早いといえます。またヴィンテージによっても甘みの抜けるカーブは同じ醸造所でも異なります。
これですべてのワインを飲んでもらい僕が話したかったことは一通り話したのでした。
もう一回このセミナーについての記事は書くのでまとめ的なことはその時に書きます。
裏テーマとしてしいたケーキとの相性ということも次回に書きます。
今回出したワインのリンクも次回に貼ります。
-
トリッテンハイマー・アポテーケTrittenhe… 2015.03.14
-
ブロイヤーのトロッケンではないトップキ… 2013.08.18
-
池袋の東武でドイツワインフェアが開催中… 2013.07.26
カテゴリ
カテゴリ未分類
(54)ラーメン
(60)ドイツワイン
(119)東京ドイツワイン協会(ケナー関係含む)
(42)役にたつであろうワインの知識
(17)ドイツワイン 2010年ヨーロッパ旅行編
(29)2010年 ヨーロッパ旅行ドイツワイン以外
(14)ベスト3 ヨーロッパ旅行 土地
(14)ベスト3 ヨーロッパ旅行 体験
(10)ヨーロッパ旅行 08年12月編
(8)ヨーロッパ旅行 08年1月編
(3)ヨーロッパ旅行 実践編
(11)2012ヨーロッパ旅行 ドイツワイン編
(22)2012ヨーロッパ旅行 (ワイン以外)
(6)日本の土地
(28)ベルギービール
(17)その他酒
(10)音楽
(48)プロレス
(18)日本で買えるおすすめドイツワイン
(7)sakae
(3)2013年ヨーロッパ旅 ワイン以外
(3)2013年9月ヨーロッパ ドイツワイン
(4)2014年9月ヨーロッパ
(2)・2025.10
・2025.09
・2025.07
キーワードサーチ
コメント新着
モーゼルだより mosel2002さん
ドイツワインならメ… 店長@ユースケさん
Loving PURORESU hirose-gawaさん
youi's memo youi1019さん