おいらの小説作法
小説作法その1(人は何故小説を読むか)(前編)本日から3回に渡って、関ネットワークス「情報の缶詰」(200年8月号)掲載の「小説作法その1(人は何故小説を読むか)」を連載します。

小説作法その1(人は何故小説を読むか)
関ネットワークス「情報の缶詰」の編集長から、次のような依頼を頂いた。
「次号から連載で『小説作法』なるテーマで執筆をお願いしたいのですが。
今、思いついたことなのでどうかなと思うけど、小説って一つのプロット(主題)を交響曲のように次々と変調しながら展開していくものかなって最近思う。
そして、そのテーマが単純なもので聴くものの心を打つものであれば、主題が何度出てきても聴衆は飽きない。
朝、5時過ぎに起きて小説を読んでいるけど、ごたごたしたものは主題が安定せず、一見、面白そうだが、読むほうが落ち着かない。
そこで、下記のようなテーマを考えてみましたが、
(1)題名の選び方
(2)主題の探し方
(3)主人公
(4)筋の展開の仕方
(5)読み手の心のつかみ方
(6)書き出しとエンデイングなど
(7)芥川賞と直木賞受賞者のその後
(8)小説家志望ということは?
(9)柚木惇さんの執筆作法
などいかがでしょう。
なお、マンネリということについてですが、例えば、ベートーベン第五、ご存知『ジャジャジャジャーン』で始まるものですが、あれを何度も聴くと確かに飽きますが、インターバルを空けて聴くとまた良いものです。
したがって、テーマが良ければマンネリなど心配する必要はないのだと思います。だって、鳥っていつも同じ鳴き声でしょ。しかし、聞く人の心の状態でいろいろに変わって聞こえるものなのだと思います」
小職はメジャー系文学賞の二次予選通過者でしかないが、小職のようなもので良ければということで、この重責をお受けすることにした。
第1回は「人は何故小説を読むか」を中心に書く(この項続く)。
小説作法その1(人は何故小説を読むか)(中編)
1.芸術とは何か
小説作法でありながら、のっけから絵についての質問である。
「貴方は美術館に行かれることがあるだろうか? 美術館で絵を観るとしたら、絵とは何だとお思いになるだろうか?」
一般の人は、こういうことをあまり考えたことがない。

おいらの一番好きな答えは、池田満寿夫の答えである。彼は、「絵を観るとは、人生を観ることだ」とした。つまり、画家はキャンパスの上に人生を描いているのである。そう思って絵を観ると、絵は奥が深い。
実は、小説を読むということもこれと同じである。小説を読む愉しみとは、人生とを何かを捜す愉しみである。絵や小説だけではない、「芸術とは何か」を突き詰めていくと「人生とは何か」にたどり着くのである。
古来より芸術家は、人生とは何かの答えを求めて小説や絵をしたためてきたのである。だから、人は何故小説を読むかと問われれば、人生を知るためなのである。作家は何故書くかと問われれば、人生とは何かを捜し求めて書いているのである。実際、漱石は一生、人生とは何かを書き続けた。
2.小説を読んで人生が分かるか
では、小説を読んで人生とは何かが分かるか。そして、人生が変わるか。考えてみれば、人の一生とは人生とは何かを捜し求めることでもある。小説にその解答があるとするならば、読まない手はない。
おいらは思い出す。学生時代に夜を徹して、人生とは何かを友人と激論したことを。無論、結論が出たわけではないが、それ以来、人は何のために生きるかのという本質的な疑問を持ち続けることになった。ところが、社会人になった直後、一冊の本を読んであっさりとその答えが見付かったのである。
小説の名前は「小説日本銀行」(城山三郎)。
その中で主人公が人生とは何かをあっけなく洩らすのである。
「人生とは、仕事と家庭である」
おいらは拍子抜けになった。何だ、そうだったのかと。そんなに簡単なことだったのかと。おいらは、この言葉で人生が変わったとは思わないが、「生きるということは何か」が少し分かったような気になったのは確かである。
それに対し、永井荷風を読むと、妙に人生を斜に構えてしまうのはおいらだけではないだろう。丸谷才一が云ったと記憶しているが、永井荷風は志を失くしたときに読む小説である(この項続く)。
小説作法その1(人は何故小説を読むか)(後編)
3.テーマ
さて、小説の主題が人生とは何かであったとしても、その切り口をどうするかという問題にテーマがある。

おいらが高校生のときである。クラスの担任の先生は英語教師であったが、文学に造詣が深く、ある日、ふと言葉を洩らした。
「小説のテーマで最後まで残っていたのは、セックスだ。それが、ヘンリー・ミラーによってとうとう書き尽くされてしまった。もう、小説で新たに書くテーマは残されていない」と、この出来物教師が洩らしたのをおいらは聞き逃さなかったのである(どうでも良いことだが、ヘンリー・ミラーのフルネ-ムは、ヘンリー・ヴァレンタイン・ミラーという。晩年の妻は日本人のホキ徳田だ)。
こういうことを高校生に云う教師も教師だが、それにつられてヘンリー・ミラーの北回帰線を読むおいらもおいらである。
考えてみれば、小説だけではなく、絵画の分野でもダビンチやピカソを超える画家がこれから簡単に現れるとは思いにくい。
音楽でもそうだ。モーツアルトやベートーベンを超える音楽家が今後も出てくるという可能性は少ない。
そう考えると、芸術の世界はもう完成し尽くされているのかも知れない。
しかし、今から思えば、このことを高校生で知ったということはおいらにとって大変良かったと思うのである。
小説は書き尽くされているのか。そうか、これから書かれる小説は全て過去の亜流なのか。そうだとすると、古典を読まなければダメだ。それに、もしそうなら前人未到のテーマをおいらが見付けてやろうと思ったのである。
前人未到の分野が見付けられないとしても、作家になるのなら、おいらの書いた小説によって読者の人生が変わるくらいの作品を書く気概が必要だと思ったのである。おいらが高校生のときに思ったことだが、今でもその考え方は変わっていない。
さて、読者はどのようにして小説を読みたいと思うようになるのだろうか。次回は「(5)読み手の心のつかみ方」を中心に述べてみよう(この項終り)。
小説作法その2(どういう小説が文学賞に入賞するか)(前編)
本日から3日間、関ネットワークス「情報の缶詰2010年9月号」に掲載された「小説作法その2(どういう小説が文学賞に入賞するか)」をお送りします。

小説作法その2(どういう小説が文学賞に入賞するか)
おいらの小説作法第2回である。前回予告どおり、「(5)読み手の心のつかみ方」を述べるが、公募小説の場合、読み手は選者となる。だから、趣向を変えて「どういう小説が文学賞に入賞するか」について書く。
1.作家デビューの方法
作家でデビューする方法には色々あるが、一番の近道は、公募の文学賞に応募することである。
作家に資格試験などない。だから、自称すれば誰でも作家になれる。しかし、世間が作家として認めるかどうかはまた別の話しである。
そこで、客観的に作家かどうかの指針として挙げられるのが文学賞への入賞である。
2.どういう小説が文学賞に入賞するか
公募文学賞の代表である「江戸川乱歩賞」に応募するとしよう。おいらは今、同賞に狙いを定め、原稿を書き始めているからである。では、どういう小説が乱歩賞に入賞するのだろうか。
(1)冒頭が命
乱歩賞は、プロの作家も応募するという推理小説界の金字塔である。競争率は一昨年で331倍。しかし、応募される作品のほとんどがプロ裸足(プロがはだしで逃げ出す)の水準であり、難関中の難関と云われる。
だから、一定レベル以上の作品が締め切り直前に数百通も送られて来るので、選者だって困る。畢竟、出だしが平板なものは没原稿にされてしまうのである。
何も皆さんが小説を書く訳ではないのだが、考えてみれば、小説を読んだり、映画を観る場合でも同じである。最初のシーンが月並みであれば、貴重な時間を割こうとは思わない。
それにここが大事なことなのだが、冒頭が面白くなければ、必ず中身も面白くないのである。喜劇役者の演技でもそうである。面接でも同じである。最初の3分間が面白くなければ、ずっと面白くない(この項続く)。
小説作法その2(どういう小説が文学賞に入賞するか)(中編)
(2)冒頭の10枚でジャンルに精通していることをアピール
何事にも云えることだが、素人の書いたものを読む程世の中は暇ではない。何が云いたいかというと、小説を読んでいくうちにその小説が取り上げているジャンルに著者が精通していなければ、小説の内容は薄っぺらなものにならざるを得ない。選者はそれを簡単に見抜いてしまうのである。
読者も同様である。保険のことを書いた小説で、著者が保険について無知であれば、直ちに読むのを止めるだろう。

その逆に、冒頭部分から専門性のある興味深い話しが展開すれば、選者のみならず読者だって読み進むのである。高橋克彦の乱歩賞作品「写楽殺人事件」は、冒頭から蘭画についての蘊蓄が語られていて、あっという間に読み終わってしまう。
(3)エンタ-テイメントとして面白い
ここで勘違いされると困ってしまうのが、専門性に没頭するあまり、オタク小説になってはいけないということである。それでは誰も読んでくれない。あくまでもエンターテイメントとして面白くなければ失格である。
エンターテイメントとして面白いということはどういうことだろう。それは、次のページを捲るのが楽しみだということである。どういう展開になっていくのだろうと選者に思わせる小説のことである。
これに対し、芥川賞などの純文学は違う。後ろの頁に戻ってもう一度内容を確かめてみたいと思う小説である。読者は小説の余韻を愉しむのである。
こうしてみると、頁を進めたいという小説ばかりではなく、頁を元に戻したいという純文学も立派なエンターテイメントである。
(4)これまで見たことのないストーリー
スト-リーは波乱万丈にしなければならない。しかし、波乱万丈だけではダメなのである。世の中には波乱万丈物が五万とある。どんでん返しが二度や三度あっても驚かない。
何が云いたいのか。
これまで見たことのないストーリーにする必要があるのである。言葉を返せば、誰もが驚くストーリーを作れば必ず入賞する。
そんなことが可能かと思われるだろうが、世界の小説の歴史はその繰り返しである(この項続く)。
小説作法その2(どういう小説が文学賞に入賞するか)(後編)
(5)主人公に感情移入(キャラクターが立っている)
小説とは突き詰めれば、主人公への感情移入である。選者が小説の主人公になれるかどうかである。読者も同じである。
そのためには主人公はもとより、登場人物のキャラクターが立っていなければならない。

キャラクターが立つとは、何も特異な人物設定にする必要はない。リアリズムがあるかどうかである。そうしないと小説自体が嘘臭くなるのである。
生身の人間を描く。その人間が自分と同じだと思わせることである。
そうして、初めて、ああ、こういう主人公に自分もなりたいなぁと選者や読者に思わせることである。
(6)スケールがでかい(社会派ミステリー)
松本清張の出現によって、社会派ミステリーという言葉が現れた。それまでの推理小説は探偵小説と呼ばれ、犯人の個人的な動機やトリックを暴くものが中心であったために、革命的な事件であった。
清張が生んだ社会派ミステリーの脈流は、その後、年齢を感じさせない女性作家である、山崎豊子にまで繋がっている。彼女の作品のスケールはでかい。世の中のドロドロを書かせたら天下一品である。そういう作品が待たれているのである。
(7)選考委員を唸らせる
ここまで書けばもう皆さんにもお分かりであろう。要は、選者を唸らせる小説を書くことができれば良いのである。
何だ、そんなに簡単なことだったのかと云われる方も多いと思う。
しかし、そう云う小説なら面白いのが当たり前だし、誰だってそう云う小説を読んでみたい。だが、受賞している作品であっても、そういう作品にはなかなかお目にかかれないものなのである。
さて、いよいよ秋の夜長の九月である。あなたも筆を取られてみたら如何であろうか(続く)(この項終り)。
小説作法その3(小説の醍醐味)(前編)
本日から三日間、関ネットワークス「情報の缶詰」(10年11月号)に掲載されたおいらのエセー「小説作法その3(小説の醍醐味)」を掲載します。

「小説作法その3(小説の醍醐味)」
おいらの小説作法第3回である。
1.「あらすじ派」か、「ペンの赴くまま派」か
本屋に行くと、読みたい小説のあらすじだけをまとめた本が売られていることがある。手に取ってはみるが、誰が買うのだろうとそのまま書棚に戻している。
それで思い出すのが、アメリカに住んでいたときのことである。その手の本が多かったような気がしたのである。知ったかぶりをする必要があるのだろうか?それともアメリカ人はそういう手合いの本で読書を済ませてしまうのだろうか?
さて、この「あらすじ」を今回の冒頭に持ってきたのには理由がある。
小説を書くときに、あらすじを最後まで考えた上で書くのか、それともあらすじを考えないで、ペンの赴くままに書いていくのか。
実は、この問題は小説作法の上で避けて通れない重要な課題である。おいらの好きな吉行淳之介は後者派の代表であり、原稿用紙の上に思い浮かぶ情景から小説を書き始めた。これに対し、三島由紀夫は用意周到に資料を収集し、ストーリーを最後まで完成させてから小説を書いたという前者派であった。
どちらが良いのだろうか。どちらが小説の王道なのだろうか。
プロの世界ではどちらも正解と云える。しかし、素人があらすじを考えないで小説を書くというのは、無謀極まりない。会社で上司に提出するレポートと同じだと考えれば良い。本人に結論が分からないレポートを、上司が最後まで読んでくれるとは思えない。
だから、事前にあらすじを考えないでも名作が書けた吉行淳之介はある種の天才であったのである。新聞小説の連載であっても、最初から最後まで筆にまかせ、それでいて最後はしっかりと締めくくった(この項続く)。
小説作法その3(小説の醍醐味)(中編)
2.あらすじとプロット
ここで、あらすじとプロットの違いについて述べておこう。小説作法の上で重要なことだからだ。

あらすじの例を述べてみよう。
「王様が亡くなった。お妃は嘆き悲しんだ」である。
これに対しプロットは、「王様が亡くなった。後ろ盾の無くなったお妃は嘆き悲しんだ」である。
良い小説とは、あらすじからではなく、プロットから生まれる。
だからプロットが完成すると、それで小説は出来上がったも同然だ。実際、三島由紀夫がそうだったと云われる。
3.神は細部に宿る
しかし、神は細部に宿らなければならない。プロットだけを読むのでは、最初に述べたあらすじ本を読むのと同じである。
プロットに肉付けをして、読者を小説に参加させなければならないのである。この肉付けをさせるコツが、神を細部に宿らせることである。
ハードボイルドの不朽の名作「ロング・グッドバイ」(レイモンド・チャンドラー)の名探偵フィリップ・マーロウから、その方法を学んでみよう(この項続く)。
小説作法その3(小説の醍醐味)(後編)
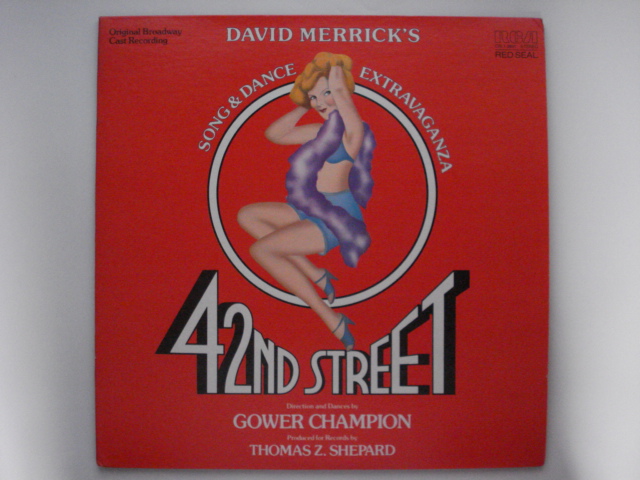
<彼女は振り向いて歩き去ろうとした。私はすかさず言った。
「ミセス・ウエイド、ちょっと待って下さい。用件はまだ終わっていません。けんか腰になるのはよしましょう。我々はみんなそれぞれに真相を究明しようと努めているだけなのです。あなたがチャッツワース貯水池に投げ込んだそのスーツケースですが、それはそれは重かったのでしょうか?」
彼女は振り返って私を見た。「古いものだと申し上げたはずです。そうです、ずいぶん重いものです」
「貯水池のまわりの高い金網のフェンスを、どうやって乗り越えたんですか?」
「何ですって? フェンス?」彼女は言葉に窮したように手振りをした。「いざというときには普段は出ない力が出るものです。何とかやりとげました。必死の思いで」
「あそこにはフェンスはありません」と私は言った。
「フェンスはない?」と彼女は力ない声で言った。筋道を見失ったみたいに。
「そしてロジャーの衣服には血なんてついていなかった。だいたいシルヴィア・レノックスは屋外で殺されたんじゃない。ゲストハウスのベッドの中で殺されたのです。出血はほとんどありませんでした。彼女はもうそのときには死んでいたからです。銃で射殺されたのです。彼女の顔が彫像でむちゃくちゃに潰されたとき、命はとうに失われていました。死体というものはほとんど出血しないのです、ミセス・ウエイド」
彼女は唇を曲げ、侮辱の目で私を見た。「あなたはまるで現場にいらっしゃったようね」と嘲るように言った。
そして我々の前から立ち去った。
(中略)
「金網のフェンスがいったいどうしたんだね?」とスペンサーが取りとめのない声で私に尋ねた。彼は頭を前後に揺すっていた。顔が赤らみ、汗をかいていた。スペンサーはなんとか平静を保ちつつ事態を受け止めようとしていたが、それは容易なことではなかった。
「でまかせですよ」と私は言った。「チャッツワース貯水池には近づいたこともありません。だからそれがどんな様子なのかまったく知らない。金網のフェンスに囲まれているかもしれない。いないかもしれない」
「なるほど」と彼は顔を曇らせて行った。「ポイントは、彼女もそれを知らなかったということだ」
「もちろん知りません。彼女が二人を殺したのです」>
(「ロング・グッドバイ」村上春樹訳、早川書房、2007年)
フィリップ・マーロウ恐るべし。
たった一言でミセス・ウエイドの嘘を見破ったのである。ここで大切なことは、マーロウは読者までも騙したのである。読者を知らないうちに小説に参加させていたのである。
あらすじだけでは小説を読む楽しさは生まれてこない。
人生には、こういう上質の小説を探す愉しみがまだまだある(この項終わり)。
小説作法その4(小説にストーリーは必要か)(前編)
本日から3日間、関ネットワークス「情報の缶詰」(10年12月号)に掲載された「自由人 事始め(その63)『小説作法その4(小説にストーリーは必要か)』」を連載します。

小説作法その4(小説にストーリーは必要か)(前編)
有名な「小説にストーリーは必要か」論争事件である。
1.芥川龍之介対谷崎潤一郎論争事件
芥川龍之介と谷崎潤一郎との間で行なわれた「小説にストーリーは必要か」論争事件である。
この事件は、早い話しが、小説にとってストーリーは本質かという論争である。小説にはストーリーが必要だと主張したのが谷崎であり、なくても良いと主張したのが芥川であった。
芥川対谷崎論争は、「新潮」(昭和2年2月)座談会における芥川の発言に始まる。
この座談会で、芥川は谷崎の作品「日本に於けるクリップン事件」その他を批評して「話の筋というものが芸術的なものかどうか、非常に疑問だ」、「筋の面白さが作品そのものの芸術的価値を強めるということはない」と発言したのである。
自分の作品をけなされた谷崎が面白いはずがない。早速、「改造」誌上に連載していた「饒舌録」の第二回(3月号)に「筋の面白さを除外するのは、小説という形式がもつ特権を捨ててしまふことである」と反論した。
これを受け、芥川は同じ「改造」4月号に、かの有名な「文芸的な、余りに文芸的な--併せて谷崎潤一郎君に答ふ」を掲載、谷崎への再反論とともに芥川自身の文学論を展開したのである。
これ以後、「改造」での論戦は続き、谷崎が再々反論、芥川が再々々反論したが、同年七月、芥川が自殺、「改造」を舞台にした昭和の文壇の注目を集めた両大家の論争は終幕となった(この項続く)。
小説作法その4(小説にストーリーは必要か)(中編)
2.芥川龍之介の主張
芥川は、結論から述べると、芸術性さえあればストーリーのない小説があっても良いと主張した。
芥川は云う。「僕の『話』と云ふ意味は単に『物語』と云ふ意味ではない」「僕等は勿論動物園の麒麟に驚嘆の声を吝(を)しむものではない。が、僕等の家にゐる猫にもやはり愛着(あいぢやく)を感ずるのである」
そして、芥川は「話らしい話のない」「最も純粋な」小説の名手として志賀直哉を挙げる。彼の「焚火」は何か大きな物語が展開される予感がない訳ではないが、実際に大きな出来事が起きる訳ではなく、人々が焚火にあたりながら雑談してそれで終わってしまうという小説である。
芥川は奇抜で低俗なスト-リーだけの小説を嫌い、取りたてて事件の起こらない日常を描いただけの小説であっても芸術作品足り得ると云いたかったのである。

3.谷崎潤一郎の主張
芥川と比較して、谷崎の主張は分かりやすい。
「いったい私は近頃悪い癖がついて、自分が創作するにしても他人のものを読むにしても、嘘のことでないと面白くない。事実をそのまま材料にしたものや、そうでなくても写実的なものは、書く気にもならないし読む気にもならない」
「そこで私は成るべく現代に縁の遠い題材のものを読むことになる。歴史小説か、荒唐無稽な物語か、写実物でも半世紀前の作品か、或いは現代を扱っていても日本の社会とは非常にかけ離れた西洋のものなら、矢張り一種の空想の世界として見る気にもなれる」
「ぜんたい小説に限らず有らゆる芸術に『何でなければならぬ』と云う規則を設けるのは一番悪いことである。芸術は一個の生きものである。(略)予め『どうでなければならぬ』と云う規矩準縄を作ったところで、なかなかそれに当て嵌まるように行くものではない」
「しかしながら現在の日本には自然主義時代の悪い影響がまだ残っていて、安価なる告白小説体のものを高級だとか深刻だとか考える癖が作者の側にも読者の側にもあるように思う。此れは矢張り一種の規矩準縄と見ることが出来る。私はその弊風を打破する為めに特に声を大にして『話』のある小説を主張するものである」
「小説と云うものはもともと民衆に面白い話をして聞かせるのである。源氏物語は宮廷の才女が、『何か面白い話はないか』と云う上東門院の仰せを受けて書いたものだ」
谷崎の主張に付け加えることはない。しかし、その場合でも、おいらは云いたい。
「では、谷崎さん。ストーリーのない小説であっても、貴兄は読者を喜ばせる小説がお書きになれますか」と。
もちろん谷崎は答える。
「当然だ。しかし、ストーリ-があればもっと面白い小説が書ける」(この項続く)
小説作法その4(小説にストーリーは必要か)(後編)
4.さて、軍配はどちらに
しかし、おいらには、同時に芥川の答えも聞こえるのだ。
「ストーリーがある小説よりも、ストーリーがない小説でもっと面白い小説を書いて見せよう」
これをマンガの世界で考えてみれば、ストーリー派の代表が「手塚治虫」(「火の鳥」)で、反対派が「つげ義春」(「ねじ式」)だろう。実際、両者の雌雄は付け難い。
さて、この問題を突き詰めて考えれば、芸術性である。芸術作品としての小説の価値に、ストーリ-が必須かどうかという問題である。
おいらは、この問題を考える場合、いつも思い出すのが、「文藝春秋(芥川賞)」と「オール読物(直木賞)」である。言葉を変えれば、「純文学」と「大衆小説」である。
実は、この論争は大衆小説を巡る論争だったと思われる。最近では、渡辺淳一の小説を石原慎太郎が「何だ、あのエロ小説は」と云ったようなものである。

この問題への谷崎の主張は、小説を杓子定規に考えてはいけない、小説の豊かさというものを損ねてはいけないということである。
だからと云う訳ではないが、海外には純文学とか大衆文学という区別はない。結局、芸術性があればストーリーに目くじらを立てる必要はなく、両者とも正解というのが答えであろう。
5.最後に
一歩も引かず論戦した芥川と谷崎だが、実は仲が悪かった訳ではない。
二人は同人誌「新思潮」の先輩、後輩という間柄であり、論争の最中にも谷崎夫妻、佐藤春夫夫妻と芥川との五人で芝居に出かけるなど親交は厚かったという(この項終り)。
小説作法その5(短編小説の極意)(前編)
本日より3日間、関ネットワークス「情報の缶詰2011年新年号」に掲載された「小説作法その5(短編小説の極意)」をお贈りします。

小説作法その5(短編小説の極意)
おいらの小説作法第5回である。新年だから、とっておきの短編小説の極意をご披露しよう。
1.小説の真髄
人間は誰しも死ぬ。だから、死は万人に対して平等である。しかし、人によっては長命もあり、短命もある。この寿命の長短が人生の価値に影響を与えるのだろうか。
何が云いたいかというと、人生の価値を決めるものがあるとすれば、それは、人生の長さによって変わるものであろうか。
レオナルド・ダ・ビンチはこの質問に対して、「立派に費やされた人生は長い」と明快な答えを出している。
さて、おいらは寿命にかかわらず、人生の価値とは、一瞬によって決まることがあるのではないかと考えるのである。実は、それが小説の真髄でもある。
三島由紀夫が書いた男と女の世界によれば、パーティの席上で妻が良人である夫をなじったとき、公衆の面前であろうとも夫は有無を云わさず妻を平手打ちにしなければならないとしている。そうしないと、一生、その夫は世の中から軽侮されることになるのである。後から女を叱っても意味がない。その男の人生の価値は、その一瞬によって定まるのである。小説家はその一瞬を求めて小説を書くのである。
このことは、政治の世界でも同様である。菅総理の対中国外交や対ロシア外交での失態は目に余る。小説の真髄の話しを出さなくても、今が政治家にとって決断のときだとはっきりと分かるときがある。そのときには何もしないで、事後に講釈をいくら聞かされたとしても、その政治家を信用することはできない。
結局、人生で一番大切なことは「その一瞬」であって、一瞬によって人生そのものが左右されることがあるということである。その一瞬をえぐり出すのが小説である(この項続く)。
小説作法その5(短編小説の極意)(中編)
2.短編小説を読む愉しみ
いよいよ、本題に入る。短編小説を読む愉しみとは何だろう。日頃から小説を読み慣れている人でも、そういうことを考えながら読んでいる人は少ない。

だが、愉しみはちゃんとあるのである。それは、作者が読者に気付かれないように仕掛けている「爆弾」を小説の中から探し出すことである。上質の短編小説ほど、読者には分からないように爆弾が仕掛けられているのである。それを見付けるのが短編小説の極意である。
「爆弾」とは少々乱暴な言葉であるため、表現を変えれば、読者を異次元の世界に連れ込むということである。
具体的に幸田露伴の小説でその爆弾を体験してみよう。短編小説の「観画談」(大正14年。岩波文庫「幻談・観画談 他三篇」所収)である。
「観画談」は、主人公である大器晩成先生が奥州の寒山を訪ねたときの話しである。あらすじを述べてみよう。
大器先生が大雨の降る夜に難儀して一人で山寺に入り、部屋に通される。部屋は暗いので最初は分からなかったが、彼の目が慣れるに及んで、壁に飾ってある大きな絵に見とれる。
春江の景色にあわせて描いた風俗画である。大器先生はこの絵が気に入り、手に持っている灯りを左の方へ移す。岸がなだらかになっており、柳がそよいでいる。雑木林が生い茂っており、柳の枝は風に揺られている。岸辺には春の水が光り、そこに一双の小舟が浮かんでいる。
その側で船頭の老人が今や舟を出そうとしながら、片手を挙げて乗らないかとこちらに向かって叫んでいるように見える。
しかし、その顔だちがハッキリとは分からない。
そこで、大器先生は灯りを船頭の顔に近付けてみた。遠いところから歩み寄って行くように、もうろうとしていた船頭の姿が段々と分って来た。膝も肘もムキ出しになっているハンテンのようなものを着て、小さな笠をかむっている。仰いでいる様子は何ともいえない無邪気なものである。
そのとき、船頭が「おーいっ」とこちらを呼びながら大きな口を開けた。大器先生は莞爾(かんじ)として、思わず「今行くよー」と返事をしようとした。
そのときである。隙間をぬって吹込んで来た冷たい風に灯りがゆらめいたのである。それまで船も船頭も遠くからこちらに近付いていたのだが、その一瞬の間に、船頭は近くから遠くへ去っていったのである。
屋外では雨の音がしている(この項続く)。
小説作法その5(短編小説の極意)(後編)
昨日からの続きである。

この小説では、大器先生が灯りを船頭に近付け、船頭の顔が分って来たところが爆弾を仕掛けたところである。大器先生が思わず「今行くよー」と返事をしようとしたのだが、冷たい風によって灯りがゆらめき船頭が遠くへ去ったときに、その爆弾が破裂したのである。
つまり、露伴は絵の中の船頭の顔が分かった時点で読者を異次元の世界に連れ込んだのである。そして、船頭が実際に声を出した時点では主人公も読者も既に絵の中にいたのである。
だから、主人公は思わず返事をしようとしたのである。無論、読者もそれにつられて返事をしようとするのである。しかし、冷たい風によって主人公は一瞬にして現実に戻される。たった今、目の前で起きたことは現実だったのか、それとも幻想だったのかと思わざるを得ない。人生もまたそれに似たようなものである。
なお、主人公がそのまま絵の中に入ってしまい、後から部屋を尋ねる寺の坊主がその絵を眺めて驚く(または誰も気付かない)というストーリーも考えられるが、そういう含みもこの小説には残されている。
ただし、読者にそう思わせることが肝要であって、実際にそうしてしまうとSF小説になってしまい、小説の深みに欠けることになる。小説の醍醐味とは、小説を読んだ者に自由に想像させることが大切なのである。
短編小説には、この爆弾が必ず入っている。だから、それを探し出すのが短編小説の極意である。無論、長編小説には数多くの爆弾が仕掛けられているのだが、この爆弾を味わうのは短編小説ならではの愉しみと云えよう。
小説を読む愉しみは尽きない(この項終り)。
小説作法その6(小説と映像との違い)(前編)
本日より3日間、関ネットワークス「情報の缶詰2011年2月号」に掲載された「小説作法その6(小説と映像との違い)」をお贈りします。

小説作法その6(小説と映像との違い)
おいらの小説作法第6回である。今回は、小説が持つ「無限の表現の可能性」について述べてみよう。
1.百聞は一見に如かずか
おいらたちは、子供のころから「百聞は一見に如かず」と教えられてきた。確かに事実を伝えるには、そうであるに違いない。しかし、同じ内容を小説で読むのと映像で見るのでは、どちらが印象深いであろうか。
例えば、明るい月を表現するのに、一枚の月の写真と次の歌とではどちらが印象深いだろうか。
あかあかやあかあかあかやあかあかやあかあかあかやあかあかや月(明恵)
この歌の場合、月の明るさが容易に想像できる。その明るさも、人によっては現実の明るさの何十倍までの明るさとなる。このように文字によって表現される世界は実際の映像よりも無限の可能性を有する。
小説も同じである。刑事が犯人を探しているときに会った人物が胡散臭いと思ったとき、胡散臭いという感じを映像で表すのは簡単ではない。
映画でそのニュアンスを出すとなると、ワンシーンでは難しかろう。しかし、小説であれば胡散臭いという一言で済む。しかも、映像の場合は、その映像によってイメージが固定されてしまうという欠点までもある。
それに、例えば大河を映像によって表そうとすると、ロケ場所、撮影条件、天候などの条件があり、これらの問題がクリアされたとしても現実に撮影された大河がイメージに合うかどうかは分からない。
しかし、これを文章で表すと次の俳句で充分である。
さみだれや大河を前に家二軒(蕪村)
わずか17字で大河が表現できる。しかも、各人各様に大きな河を想像することが可能になる。まことに文章の持つ力は無限である(この項続く)。
小説作法その6(小説と映像との違い)(中編)
2.映像を超えるリアリズム
さて、小説で一番大切なことは、リアリズムが出せるかどうかである。読者が小説を読んで嘘くさいと思ったら、その小説は終りである。二度と読まれることはない。
このリアリズムを藤原定家の歌で実感してみよう。

見わたせば花も紅葉もなかりけり浦のとまやの秋の夕暮れ(定家)
この歌にリアリズムがある理由は何であろうか。
それは、何もない浦のとまやの景色であるにもかかわらず、読者に鮮やかな色の花や紅葉を想像させるからである。それも一瞬にしてである。
普通の歌は、何もなければ何も表現しない。しかし、定家は何もない情景に、花も紅葉も映し出すのである。読者の想像力をかき立てるのである。そこがリアリズムである。まことに定家は歌の名手と云われる所以である。
ところで、実際にこの歌を映像によって表すことが可能であろうか。さびれた景色にもかかわらず、鮮やかな花や紅葉を想像させることができるだろうか。
もし、映像でそうさせるとなると、一旦暗い景色を撮影して、その後、コンピュータグラフィックスによって、その映像に色を付けるか、実際に花や紅葉のあるセットを撮影して画面をぼかしながらその色付きの映像を浮かび上がらせる手法以外にはない。
この歌のように優れた文章とは、映像を超えるリアリズムを表現させることである。
つまり、最初から赤や黄色の花や見事な紅葉をカラー映像で見せられたら、文章は映像にはかなわない。それが最初に書いた百聞は一見に如かずである。しかし、定家の歌はそれを逆転させ、映像を超える美を読者に想像させるのである。
おいらは思う。実は、このような表現方法は日本文学独自のものである。これに対し、海外文学の表現方法は直接的である。
読者諸兄も英作文で習ったとおり、日本語を英文に訳すときは、一旦日本語の意味を明確にして(それもあけすけにして)、おもむろに英語に直すのが英作文のコツである。つまり、英語の表現は、まるで映像のように表さなければならないのである。
しかし、日本語はそれ自体が文章の裏にひそむ意味合いを持っているのである。だから、それを愉しむのが日本語の真髄と考えるのである(この項続く)。
小説作法その6(小説と映像との違い)(後編)
3.五感を表す日本語
日本語の持つ強みが海外にはない表現方法であると書いたが、もう一つ、日本語の持つ優れた点に五感の表現がある。

例えば視覚の場合、色を表すのに日本語ほど素晴らしいものはないと考えるのである。
上記の定家の例では、言葉から花や紅葉の色合いが見事に想像できるのである。嗅覚(香り)にしても、聴覚(好きな音楽)にしても、触感(肌触り)にしても日本語で表せないものはない。
最後に、おいらの大好きな歌でしめくくることにしよう。この歌も鮮やかな色を目の前に想像させてくれるのである。
願わくば花のもとにて春死なむそのきさらぎの望月のころ(西行)
淡い桃色をした桜の花が風にそよぎ、桜吹雪の情景が目に浮かぶ。天空には鮮やかな色をした満月も浮かんでいる。
まことに日本語の持つ魅力は尽きない(この項終り)。
おいらの小説作法その7(その小説は誰が語っているのか)前編
本日より3日間、関ネットワークス「情報の缶詰」に掲載した「おいらの小説作法」を連載します。

おいらの小説作法第7回である。今回は、小説の通が泣いて喜ぶ「小説の語り手」について述べてみよう。
1.感情移入
小説にとって一番大切なことは、読者がその小説に感情移入できるかどうかである。読者が主人公になりきれるかどうかによって、作家の力量が試されるのである。
それをミステリー作家である真保祐一氏の「発火点」の書き出しからみてみよう。
「十九歳になろうとする春から、俺は一人暮らしを始めた」
これを
「十九歳になろうとする春から、敦也は一人暮らしを始めた」
と変更した場合、どちらの方が小説に入りやすいだろうか。
これについて、作者である真保氏は「ミステリーの書き方(幻冬舎。日本推理作家協会編著。2010年)」の中で小説の語り手を俺とした理由について次のように述べている。
「読んでもどこにもおかしな点はない。しかし、三人称(筆者注。主人公の名前である敦也にすること)で書くと、単なる説明にしかなっていないように思えてしまう。章の書き出しとしては、あまりにお粗末すぎる印象が残る(以下、略)」
このように真保氏は主人公である俺を小説の語り手(これを一人称方式と呼ぶ)とした理由の一つとして、小説が「説明」にならないためとしている。
2.永遠の課題
実は、この語り手を誰にするかという問題は小説を書く場合の永遠の課題であると云われる(以下、次号)。
おいらの小説作法その7(その小説は誰が語っているのか)中編
2.永遠の課題
実は、この語り手を誰にするかという問題は小説を書く場合の永遠の課題であると云われる(昨日からの続き)。
ただし、読者はこのようなことなど考えたことがない。それは普通、読者が小説を読む立場にいるからであり、小説を書こうとしない限り直面しない問題だからである。

分かりやすく述べてみよう。
私や俺を主人公にした場合(一人称方式)、小説の語り手は私や俺自身となる。この私を語り手とする方式のメリットは、真保氏の解説どおり主人公に感情移入しやすいという点にある。だから、純文学や私小説のほとんどはこのパターンを踏襲している。
しかし、この方式には大きな問題点がある。それは、主人公が語り手となるので、主人公が知らない事まで読者に伝えることができないという欠点である。
例えば、深海に沈みゆく潜水艦のことを想像してみれば良い。誰だってそのシーンを見ることなどできない。主人公が深海に潜って潜水艦を見ていれば別だが、その光景を見ることができるのは神しかいない。つまり、主人公がその潜水艦の側にいなければその際の状況を述べる訳にはいかない。
この場合、私や俺が見えないことを書こうとすると、小説の語り手を主人公から第三者(通常は小説の作者)に変えなければならなくなる。この作業が自然になされないと読者は違和感を覚えることになるのである。
ここで、あなたには素朴な疑問が生じるに違いない。
そういう場合、沈みゆく潜水艦について映画の映像のように客観的に記載すれば良いではないかである。つまり、事実を淡々と記載すればよいと思われるのではないだろうか。
しかし、小説にとって一番重要なことはリアリズムである。小説の途中で客観的な記載が始まったとする。感の良い読者であれば、主人公の知らない事実が出て来ることによって、語り手が変わったことに気付いてしまうのである。
せっかく感情移入した小説であっても、ご都合主義の小説だと思って読むのを止めてしまうことになりかねないのである(以下、次号)。
おいらの小説作法その7(その小説は誰が語っているのか)後編
3.神の視点
この欠点を回避するため、小説の書き出しから語り手を作者とする方式がある。これが神の視点方式(三人称方式)である。私や俺は出て来ず、主人公の名前や彼、彼女を主語とする小説になる。

古典的な例を述べると「昔々、あるところにお爺さんとお婆さんがいました。ある日、お爺さんが山へ芝刈りに、お婆さんが川へ洗濯に行きました」である。
この場合、語り手は三人称を使用しているので、主人公のことのみならず、森羅万象のことを書いても不自然さはない。だから、海外の小説を始めとして、ほとんどの小説がこの方式を採用している。
しかし、この方式では、冒頭述べたように小説が説明になりやすい。しかも、語り手は神の如く万能であるため、何でもありになってしまう。つまり、この方式でもリアリズムに欠けるケースとなる場合がでてくるのである。
また、語り手である作者が専門的な知識や蘊蓄を披露しようとすると、その説明が鼻についてしまい、小説を読んでいるのか、解説書を読まされているのか分からくなると云う欠点も指摘されることがある。
4.司馬遼太郎方式
さて、司馬遼太郎氏は、この問題をどう解決したのだろうか。
彼は、折衷案方式として、一人称であろうと三人称であろうと、必要があれば突如作者として小説の中に現れ、蘊蓄を披露するという恐るべき方式を開発したのである。
しかし、読者は司馬遼太郎氏だからこれを許したのである。そういう芸当ができたのは、司馬遼太郎氏だからだと思われる。
5.文体
以上、小説の語り手をどうするかという、少々玄人っぽい話しに触れてきた。
世界中の作家は、人知れずこの問題に悩みながら小説を書いているということを皆さまにお伝えしたかったのであるが、小説の語り手をどうするかはつまるところ作家の力量に帰属する問題だと思われる。
それを語り手の天才である太宰治で考えてみよう。太宰は以上述べた全ての方式を駆使して、誰が語り手になろうとも瞬時に読者を感情移入させることができた天才であった。太宰治が不世出の語り部と云われる所以である。
読者の中でこの問題に興味のある方は、太宰の小説を今一度読み返して欲しい。そうすれば、なるほど小説にはこういう書き方もあったのかと膝を叩くことができると思うからである(この項終り)。
© Rakuten Group, Inc.






