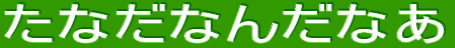全て
| カテゴリ未分類
| 農業・農村
| 森林・林業
| 我が家の田んぼ
| 生き方
| 水俣紹介
| 音楽
| 理想の農業
| 今日の反省
| 読書
| 環境
| 人相を良くする
| 暮らし
| 集落営農組織
カテゴリ: 理想の農業
12月16日付の熊本日日新聞朝刊に、農民作家、山下惣一氏の東京での講演が紹介されています。
山下氏の発言には、しごく共感し納得する部分が多い。
山下氏の講演をうまくまとめて紹介してくださった、熊日記者、渡辺直樹氏に感謝します。
●「儲かる農業」について
「これまで農業が続いてきたのは儲かったからではない。農業が必要だったから」
「『儲け』とは付加価値であり、原料を生産する1次産業にはない。
生産者が得ているものは『対価』。それがあまりに低い。」
生産者が得ているものは『対価』だというのは確かにそうだと思います。
サラリーマンが得ている給料は労働に対する『対価』であって、『儲け』ではないですからね。
それと同じだと思います。
また、それがあまりに低いというのも同感です。林業なんかさらに低いです!
●「大規模化」について
「(棚田が広がる)唐津のような場所は規模拡大が難しい。」
「たとえ集約がうまくいったとしても、農地を提供した農家の次の世代は、
地域を離れる可能性が高まり、地域社会が成り立たない。」
まさに、「久木野まるごと農場」が直面している問題です。
規模拡大をコスト削減につなげることは不可能だと言って過言ではないと環境です。。
対価としての販売額が増えることはあっても、儲けが増えることにはならないのです。
一方、農業経営が成り立つかどうかというよりも、地域社会が成り立つかどうかのほうが重要な課題です。
そういう意味では、「久木野まるごと農場」のような組織の役割は大きいと思っています。
これまでの世代は農業機械への投資に対する抵抗感は少なかったようですが、
若い世代はそうはいきません。農作業を引き受けてくれる組織があることで助かると感じる人は多いはずです。
山下氏が言うように、「次の世代は地域を離れる可能性が高まる」ということとは違う側面があると感じます。
●「競争」について
「農業を続けてきた『ムラ』は運命共同体であり、競争原理とは相いれない。」
「ほかの商売では同業者がつぶれたら儲かるが、農業は違う。
『お前が頑張らないと俺も頑張れない』。そういう関係である。」
横並びですべての農業者が農業を継続していければ理想なのでしょうけど、ある程度は集約されていくと思います。
これまでのように農業者を「農家」と呼び、親から子へ経営を引き継いでしていくシステムは限界に来ています。
「家」で経営を引き継ぐのではない別の仕組みを作る必要があります。
「久木野まるごと農場」を立ち上げたのは、そういう理由からです。
「久木野まるごと農場」は農地を守ろうとしているのではありません。農業者をサポートするのが主たる目的です。
『ムラ』が運命共同体があることに間違いはありませんが、その存続に必要なのが『核』だと考えています。
それは強力なリーダーかもしれません。また、「久木野まるごと農場」のような集落営農組織もそうです。
ある程度の規模拡大も必要ですし、集約も必要だと思います。新たな地域社会の仕組みを考えていかなければなりません。
山下氏の発言には、しごく共感し納得する部分が多い。
山下氏の講演をうまくまとめて紹介してくださった、熊日記者、渡辺直樹氏に感謝します。
●「儲かる農業」について
「これまで農業が続いてきたのは儲かったからではない。農業が必要だったから」
「『儲け』とは付加価値であり、原料を生産する1次産業にはない。
生産者が得ているものは『対価』。それがあまりに低い。」
生産者が得ているものは『対価』だというのは確かにそうだと思います。
サラリーマンが得ている給料は労働に対する『対価』であって、『儲け』ではないですからね。
それと同じだと思います。
また、それがあまりに低いというのも同感です。林業なんかさらに低いです!
●「大規模化」について
「(棚田が広がる)唐津のような場所は規模拡大が難しい。」
「たとえ集約がうまくいったとしても、農地を提供した農家の次の世代は、
地域を離れる可能性が高まり、地域社会が成り立たない。」
まさに、「久木野まるごと農場」が直面している問題です。
規模拡大をコスト削減につなげることは不可能だと言って過言ではないと環境です。。
対価としての販売額が増えることはあっても、儲けが増えることにはならないのです。
一方、農業経営が成り立つかどうかというよりも、地域社会が成り立つかどうかのほうが重要な課題です。
そういう意味では、「久木野まるごと農場」のような組織の役割は大きいと思っています。
これまでの世代は農業機械への投資に対する抵抗感は少なかったようですが、
若い世代はそうはいきません。農作業を引き受けてくれる組織があることで助かると感じる人は多いはずです。
山下氏が言うように、「次の世代は地域を離れる可能性が高まる」ということとは違う側面があると感じます。
●「競争」について
「農業を続けてきた『ムラ』は運命共同体であり、競争原理とは相いれない。」
「ほかの商売では同業者がつぶれたら儲かるが、農業は違う。
『お前が頑張らないと俺も頑張れない』。そういう関係である。」
横並びですべての農業者が農業を継続していければ理想なのでしょうけど、ある程度は集約されていくと思います。
これまでのように農業者を「農家」と呼び、親から子へ経営を引き継いでしていくシステムは限界に来ています。
「家」で経営を引き継ぐのではない別の仕組みを作る必要があります。
「久木野まるごと農場」を立ち上げたのは、そういう理由からです。
「久木野まるごと農場」は農地を守ろうとしているのではありません。農業者をサポートするのが主たる目的です。
『ムラ』が運命共同体があることに間違いはありませんが、その存続に必要なのが『核』だと考えています。
それは強力なリーダーかもしれません。また、「久木野まるごと農場」のような集落営農組織もそうです。
ある程度の規模拡大も必要ですし、集約も必要だと思います。新たな地域社会の仕組みを考えていかなければなりません。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.