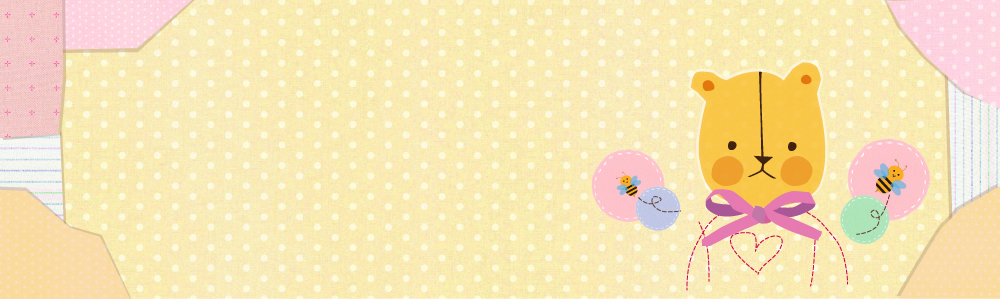下記の記事はダイアモンドオンライン様のホームページからお借りして紹介します。(コピー)です。
大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。 しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、 税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円 でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度 『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』
を出版し、 葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策 と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています(イラスト:伊藤ハムスター)
実体験から得た「3つのチェックポイント」
葬儀社選びは非常に重要です。選ぶべきポイントはたくさんありますが、私が個人的にオススメしたい判断ポイントは、 「①契約後にオプションをつけなくても嫌な顔をしないか、②契約後に担当者が変わらないか、③契約を急かすようなことをしないか」の3点です。
インターネットで検索すると、実にさまざまな葬儀社のホームページが出てきます。どの会社もホームページでは自社の良いところしか載せません。葬儀社の比較サイトもありますが、その多くは、「そのサイト運営者にお金を払っている葬儀社」しか掲載しませんので、情報の信憑性は高いとは言えません。
では、何をチェックするべきか。まず見ていただきたいのは、 Googleの口コミです。目星をつけた会社があれば、その会社の社名をGoogleで検索しましょう。
すると、検索結果にこれまでの利用者の口コミが掲載されています。過去にひどい対応をした会社には容赦なくひどい書き込みがされていますので、電話をする前に一度チェックすることをオススメします。
候補の葬儀社を絞ることができたら電話をしてみましょう。ただ、ここで気をつけていただきたいのが、多くの葬儀社の場合、 最初に電話を取るスタッフと、実際に葬儀を担当するスタッフが異なることです。ここからは私の実体験をお話しします。
大ベテランが担当者。しかし……
私の義父に相続が起きたときの体験談ですが、最初に電話に出たスタッフの対応は非常に感じがよかったので、具体的な見積もりを依頼しました。
その後、葬儀の担当となる方から折り返しの電話がありました。声を聞くと、 恐らく50代後半の男性。自称この道25年の大ベテランとのことでした。
しかし、会話の節々に 「うんうん、そうだね」と敬語ではない言葉を使うのです。「ん?」と思いながらも、こちらも急いでいたので、実際に会って打ち合わせをすることになりました。
最初はとても良い人でした。死亡診断書や火葬許可証など、今後、必要になる書類を代行して取得してくれたり、打ち合わせの場所から自宅まで車で送ってくれたりと。しかし、 正式に契約を交わした後から態度が豹変しました。
葬儀には、正式な契約を交わした後に、決めなければいけないことがたくさんあります。花祭壇に使用する花、遺影、骨壺、おもてなし料理、会葬御礼の品などなど。そして、その1つ1つに値段に応じたグレードが存在します。
担当者の態度が急変! なぜ?
「葬儀にはできるだけお金を使わずに、今後の生活費に充ててほしい」という故人の想いがあったため、私たちはできるだけグレードの低いプランを選択しました。
祭壇に飾る生花について、私の妻が「知り合いに花屋がいるので、そこで価格を抑えて手配したい」という意向を伝えました。すると、その担当者は、 「え? うちで頼まない? そんな話ありますか!」と高圧的な言い方をしてきました。
大事な葬儀を控えている身なので、できるだけ葬儀社さんにも気持ちよく仕事をしてもらいたいという思いもありましたが、 「葬儀にお金をかけないでほしい」という故人の気持ちもあります。
しかし、大切なのはやはり故人の気持ちです。私の妻は、「はい、葬儀にお金はかけるな、というのが父の意向なので」と強く言い切りました。しかし、 それがきっかけで担当者の機嫌を完全に損ねてしまったのです。
斎場での打ち合わせの際に、集合時間よりも早めに到着した私たちに、明らかに聞こえるように 「あー。もうお客さんきちゃったよ」と言うのです。
他にも、頼んだ生花の札に「喪主」という字が抜けていたのをみて 「だから、最初からうちに頼んでいればよかったのに!」と私たちに言ってきたのです!(次の日に葬儀を控えていたので、怒りはぐっと堪えましたが)
これは冠婚葬祭ではよくある話なのかもしれませんが、正式に契約をした後に高額なオプション料金を加算しようとし、それを断ると露骨に嫌な顔をしてくることがあります。
打ち合わせが進んでいくと、「既に関係者に葬儀の連絡をしてしまっているし、今さら葬儀社を変えるわけにもいかない。非常に不快だが、葬儀が終わるまでの辛抱だし我慢するしかないか」という状況に陥ります。
絶対見逃してはいけないチェックポイント
この経験をもとに、みなさまに特に注意していただきたいチェックポイントは、冒頭にあげた3つのうちの「①契約後にオプションをつけなくても嫌な顔をしないか、②契約後に担当者が変わらないか」の2点です。
葬儀社にとって、葬儀は毎日の仕事かもしれません。しかし、 遺族にとっては一生に一回しかない大事な葬儀です。大切な人を亡くし、憔悴しきった中で段取りをしていくことになります。大手の葬儀社だからといって、担当者まで良いかはわかりません。
小さい葬儀社でも担当者は心のこもった仕事をしてくれるかもしれません。電話口だけで判断するのは難しいかもしれませんが、できれば、 実際に担当者となる人とよく話をし、「この人だったら信頼できそう」という直感を頼りに候補を選び、正式な契約の前にオプション内容を確認するといいですね。
また、③の「契約を急かすようなことをしない」も大事な要素です。見積もりの段階で「今すぐ決めてもらえれば割引する」など、契約を急かす葬儀社は、 裏を返すと「他社と比べられたら負けるかもしれない」という気持ちの表れです。
自社のサービスに自信のある葬儀社であれば、「比較していただいても結構です。大切なことなので少し時間をかけて考えてください」と余裕のある対応をするでしょう。
(本原稿は、橘慶太著 『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』 を編集・抜粋したものです)
橘慶太(たちばな・けいた)
税理士・円満相続税理士法人代表
大学在学中に税理士試験に4科目合格。国内最大手の税理士法人山田&パートナーズに入社する。相続専門の部署で6年間、相続税に専念。 これまで手がけた相続税申告(相続手続)は、上場企業の創業家や芸能人を含め、通算500件以上。相続税の相談実績は5000人を超える。 また、全国の銀行や証券会社を中心に通算500回以上の相続税セミナーの講師を務める。
2017年1月に独立開業。モット―は 「最高の相続税対策は、円満な家族関係を構築すること」 。日本経済新聞や朝日新聞など、さまざまなメディアから取材を受けている。2018年にYouTubeを始める。自身が運営する【円満相続ちゃんねる】は、わかりやすさを追求しつつも、伝えるべき相続の勘所をあますところなく伝えていると評判になり、 チャンネル登録者は7万人を超えている。 2020年に刊行した初著書『ぶっちゃけ相続』は4万6000部を突破するベストセラーとなった。
相続手続を甘く見てはいけません
国税庁より、2019年7月~2020年6月における「相続税の調査状況」が公表されました。
税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円
税務署は「不慣れだったため計算を間違えてしまった」という人にも容赦はしません。ミスはミスです。相続に限らず、法律知識は「知っているか・知らないか」で大きな差がつきます。
悲しみに暮れる暇なく、膨大な手続に追われる
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の相続手続が待っています。葬儀であれば、故人が亡くなった4~5日の間に、
●死亡届の提出
●葬儀社の選定
●葬儀の打ち合わせ(場所等)
●親族、会社関係者への連絡
●通夜
●葬儀、告別式
●火葬、納骨
などのことを一気にやらなければなりません。 ひと区切りついたと思いきや、今度は保険証や免許証の返納、銀行の解約手続、準確定申告などが待ちかまえています。
そして、これらの手続には期限があります。中には亡くなった日から7日以内にしなければいけないものもあり、気づいたときには期限が過ぎ、 過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあります。
亡くなった後の全手続をとことん詳しく教えます!
はじめまして。円満相続税理士法人の橘慶太(たちばな・けいた)と申します。この度 『ぶっちゃけ相続「手続大全」相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』
を出版しました。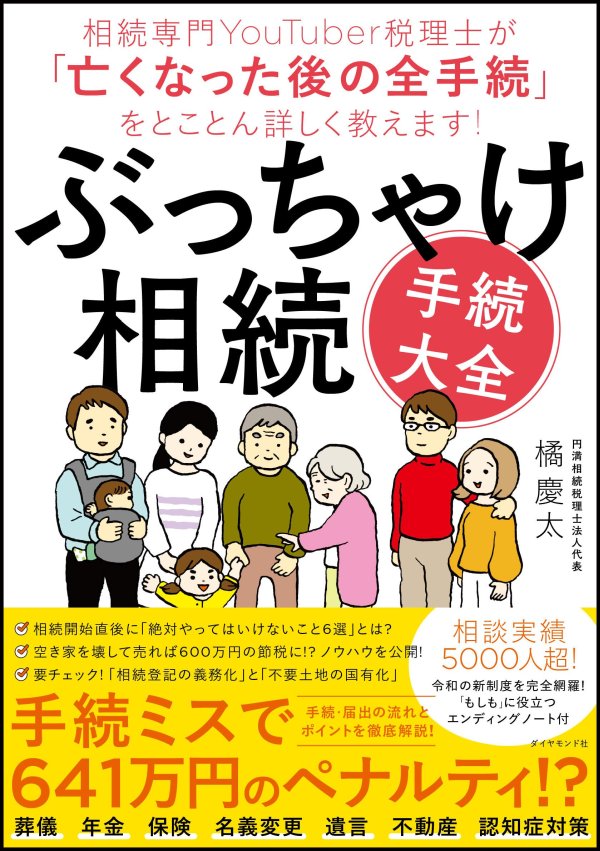
私は相続税専門の税理士として、これまで 5000人以上の方の相続相談に乗り、手続のサポートを行ってきました。これまで日本全国で500回以上、相続セミナーの講師を務めたこともあります。
本書は、 「今まさに身近な人を亡くし、相続に直面している人向けの1冊」として仕上げました。特に、次のような「実際に手続を進める中で出てくる疑問点・注意点」を徹底解説しています。
●やばい葬儀社を見抜く3つのポイント
●相続開始直後に絶対やってはいけないこと
●連絡のつかない相続人への対処法
●遺産分けで揉めないようにするノウハウ
●あらゆる手続に大活躍する「法定相続情報一覧図」の取得方法
●認知症の相続人や障害を持った相続人がいるときの手続
●相続不動産の売却を焦ってはいけない合理的な理由
本書の有効な使い方を紹介しましょう。まず、本書の全体を読み流し、相続手続の全体像や期限、自身に関係する項目を把握します。
そして、実際に各手続に着手する前に、該当ページをしっかり読んでいただければ、スムーズに手続が進められるでしょう。すべてのページを読み込む必要はなく、ご自身に必要なページを読むだけで、すぐ使える内容になっています。
-
お知らせ 2022.02.28
-
「脳トレはほぼ無意味だった」認知症になっ… 2022.02.27
-
大麦、オートミール…全粒穀物の摂取を増や… 2022.02.27
PR