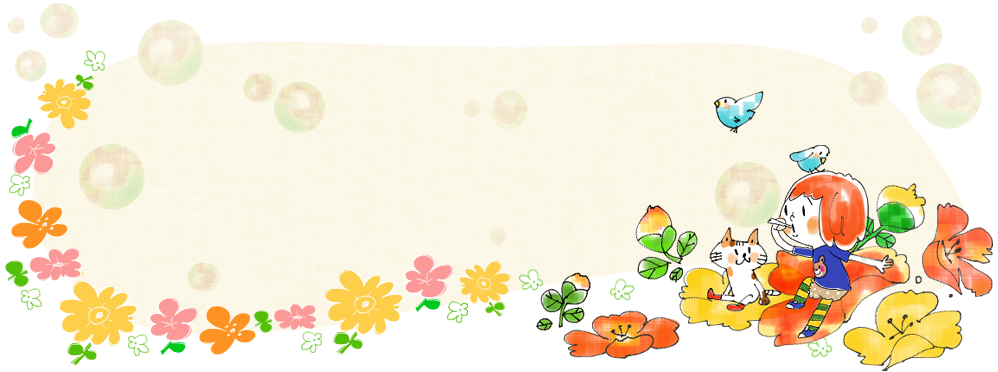カテゴリ: カテゴリ未分類
あの日から二十一年、相変らず自分でできることは何一つない遷延性意識障害者である息子は、五十一歳になった。
「智恵子は東京に空がないという」で始まる、『あどけない話』の中で、ほんとの空が見たいといって、安達太良の山々を忘れることがなかった。
息子はどうかというと、人間界の切符を未だに持っているとはいいきれない。その壊れてしまった脳に、私が投影されている部分が残っているのではないか、とかすかな期待を持っているのだ。
輪禍に遭った二十年前の私と今の私は、悲しいくらい顔つきが変わり耄碌度は進んでいる。それでも息子は「お母さんですよ」と言葉をかけると、時々笑顔を向けてくれ、手を出すとタッチしてくれることもある。笑顔と手の動きは再生したのだ。これは素晴らしいことではないか。
以前、息子は自宅で夫と二人で看ていたのだが、胃ろう部分の器具交換のため短期入院をしていた間に、私は悪性リンパ腫の再発があり、その治療のため息子の看病は出来なくなった。その上頼みの夫の突然の死、そしてコロナ禍。それ以来息子は、家に戻っていない。
面会することもままならない三年間に、笑顔も親しみ込めたタッチも忘れてしまっていないだろうか。
絶望という言葉は、私の禁句である。
私の命の期限は長くはないが、息子が完全に人間界の切符を手にする日を、待ってやらねばという心意気は失せていない。今年五十一歳になる息子だが、私にとって少年のままなのだ。なんとしてでも、「お母さん腹減った」と笑顔で言ってくれる日まで待っていてやりたい。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
© Rakuten Group, Inc.