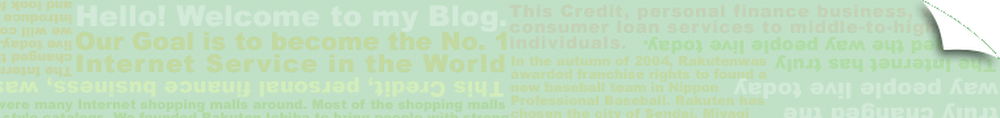2009年01月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-

長谷院境内の石柱
長谷院・境内の石柱長谷院には、まだまだ色々な石柱、石碑、石塔、石仏などがあります。「の~民」は、石柱等には詳しくないのでよく分かりませんが、篤志家が色々な思いを託して建立されたとは思います。「の~民」も村社(地元の神社です)が改修した時や、厄年には神社の囲いの石柱を奉納したことがあります。「の~民」の場合は付き合いですが、篤志家の思いはどんな思いでしょうか?信仰心のない「の~民」の不謹慎戯言ですが、神社仏閣の石塔などは神仏に対する賄賂と、参拝者に対する見栄のような気がしますがどうでしょうか?特に先人の石碑は見栄だと思います。財力も権力もない一般人の「の~民」の戯言です。長谷院・境内の石柱長谷院境内にある開運石です。今でも神社仏閣へ行くと、無病息災や幸運、開運等をお願いしますが、昔、津島上街道を行き来した旅人がここで開運を願ったのでしょう。今の時代開運を願うのは個人のためでしょうが、かって個人の運気上昇は、一族の繁栄に繋がったでしょうからその他の石柱です。「の~民」には掘り込んである文字が読み取れませんので分かりませんが、何らかの願掛け等のものでしょうか? 石塔です。立派なものですが、「の~民」には分かりません。 石塔と名号です。どなたが、何の願掛けで建立されたか分かりませんが、これほどのものを建立されたのは余程の理由があったのでしょう。 名号です。お寺ですから当たり前と言えば当たり前なのですが、昔の人たちの信仰心には感心します。 神社や仏閣によくある清水とそれを守る石仏とです。これほどの寺院の清水なのだからもう少し見栄を張ってもらいたかったです。現在では、ほとんどに神社仏閣では水道水を使用しているとは思いますが、こういうものは形でしょうから石碑です。神社仏閣には先人の石碑が必ずといって良いほどあります。それにしても立派です。
2009年01月22日
コメント(0)
-

長谷院
長谷院 長谷院は、津島上街道に入って始めての寺院で、しかも仁王門まで供えた立派な寺院です。寺院の入口は普通は山門です。津島上街道で仁王門があるのは、この寺院のほかで「の~民」の知っているのは、尾張四観音の甚目寺観音、目の町で有名な明眼院、そして弘法様で有名な蜂須賀の蓮華寺だけです。尾張の殿様が寄進されたものらしいですが、流石御三家筆頭ですね。境内に建立された石柱や石仏をみていると、「の~民」のような不信心者は、『かつての寺院は、現代のテーマパークのようなものかもしれない。』と思ってしまいます。西国三十三観音の1つには『参詣後に津島街道へ通りぬけが出来ます。』との意味をこめた案内がありますし、尾張三十三ヶ所の2番札所だとの看板があります。長谷院 長谷院は、堀江山と号し浄土宗鎮西派の寺院です。 長谷院は、尾張33ヶ所の第2番札所で、冨国二番札所観施世音菩薩の石碑がある 長谷院には、手軽に西国三十三観音巡りが行えるように、仁王門を入って右手の境内には、西国33ヶ寺の本尊をかたちどった石仏が安置されている。西国三十三観音巡りの石仏のうち、三十一番目の観音様である長命寺石仏の舟形光背に、文字が掘り込まれ道標を兼ねている。 尾張藩の第十代藩主徳川斉朝(とくがわなりとも)から寄進された仁王門です。 尾張藩十代藩主徳川斉朝(とくがわなりとも)から寄進を受けた多宝塔です。境内には南無阿弥陀仏の石碑と、堀江山の石碑が建立されている。 長谷院境内の道標です。 長谷院の西側入口には長谷院西方津島街道の入口道標です。長谷院北西角の、堀江山観音道の道標です。
2009年01月20日
コメント(0)
-

横町の石地蔵から長谷院までの津島上街道
横町の石地蔵から長谷院までの津島上街道横町の石地蔵の西側には、プチレストラン ベルという名古屋らしい喫茶店があるが、かつて津島上街道を旅人が旅した時も茶店のようなものがあったのではないだろうか。そこで、団子のようなものをいただき、津島神社へ向かって歩き始めたのではないだろうか?現在この津島上街道の当たる道路は、かつての主要街道の面影は無く、付近の住人の生活道路であるが、甚目寺町から名古屋への抜け道になってしまっている。この付近の地図を見ていると、かつて日本武尊の時代には萱津の地に港があったそうなので、この辺りは海岸線だったのではないかと思うがどうだろうか? 横町の石地蔵から長谷院までの津島上街道 横町の石地蔵のすぐ西にはプチレストラン ベルがある。 プチレストランベルを右手に見ながら、津島上街道を街道沿いに津島方面に進むと、途中に横町公園がある。 横町公園を左手に見ながら、街道沿いに進むと大野せんいの建物が見えてくるが、看板等は見当たらない。(バイブルとした「津島上街道」には看板が見えるとある) 大野せんい前を右折して、すぐに左折する。 しばらく街道を進むと、長谷院の山門が見えてくる。
2009年01月20日
コメント(0)
-

横町の石地蔵
横町の石地蔵新川橋西詰の道標を目印に左折して新川の右岸堤を南進すると、堤防道から別れ右折する道があります。そこには津島上街道の道標が建立されています。右折してすぐにお地蔵様が建立されていますが、これが横町の石地蔵です。この辺りには駕篭などがいたそうなので、さしづめ現代の駅前のようなものだったのでしょう。横町の石地蔵 横町の石地蔵は、百日咳、乳不足、歯痛に霊感あるお地蔵様だそうです。そして子宝に恵まれない人たちにもご利益があるらしく時折新婚家庭に出張される逸話もあるそうです。 毎年8月24日に近い土曜日に地蔵盆が行われ近くの公園にお出ましになるそうです。
2009年01月15日
コメント(0)
-

土器野神明社
土器野神明社津島に向かう前に、新川橋西詰の道標やその少し南にあった津島街道の道標などが、一時移してあった時の神社も訊ねて見るのも良いでしょう。「の~民」も訊ねてみましたが、神社の規模の割りに奥深い感じがする神社でした。この下をクリックしてください地図が表示されます。 <script type='text/javascript' charset='UTF-8' src='http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V1/?lat=35.18907769&lon=136.85415202&sc=2&mode=map&pointer=on&home=on&hlat=35.19696389&hlon=136.85555611&s=123198019948f3a864c82cf60e55d7b08472445f67&width=480&height=360'></script>土器野神明社には、現在新川橋橋詰ポケットパークにある新川橋西詰の道標やポケットパーク南の津島街道道標などが、一時期移されていました。土器野神明社は、清須市土器野町(旧新川町土器野新田)にある神社です。云われによれば、徳川時代の初期に建立されたそうですので、すでに400年以上の歴史のある神社です。 境内は、鬱蒼としていていかにも歴史のありそうな神社です。 境内には、秋葉社、金毘羅社、御岳社、稲荷社が合祀されていました。 土器野神明社には、眼治療で有名な明眼院への馬島道の道標があります。
2009年01月15日
コメント(0)
-

新川橋橋詰ポケットパーク 2
今の新川橋橋詰ポケットパークには、その他のものもありますので津島に出発する前に少し見学をします。新川橋橋詰ポケットパーク新川橋西詰ポケットパークには、津島上街道の道標だけでなく、その他に新川に関する碑や新川の歴史及び津島上街道が分かれた美濃路の歴史のパネルが掲げられている。 津島上街道の道標に並んで、新川橋の親柱が展示してある。 西側の壁面近くには人工川である新川開削頌徳碑及び新川開削のパネル並びに東海豪雨による新川決壊のパネルが展示してある。
2009年01月14日
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-

- 今日のこと★☆
- 今日は、歌舞伎座開業記念日ですよ!…
- (2025-11-21 06:30:05)
-
-
-

- つぶやき
- 楽天ブラックフライデーまず購入した…
- (2025-11-21 06:00:04)
-
-
-

- 株主優待コレクション
- Right-onから株主優待が届きました♪
- (2025-11-21 00:00:24)
-