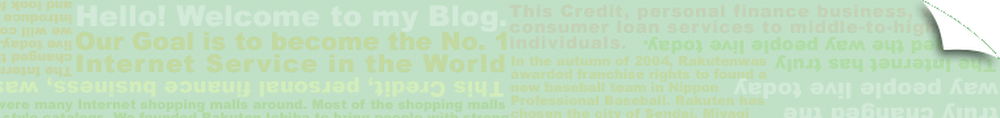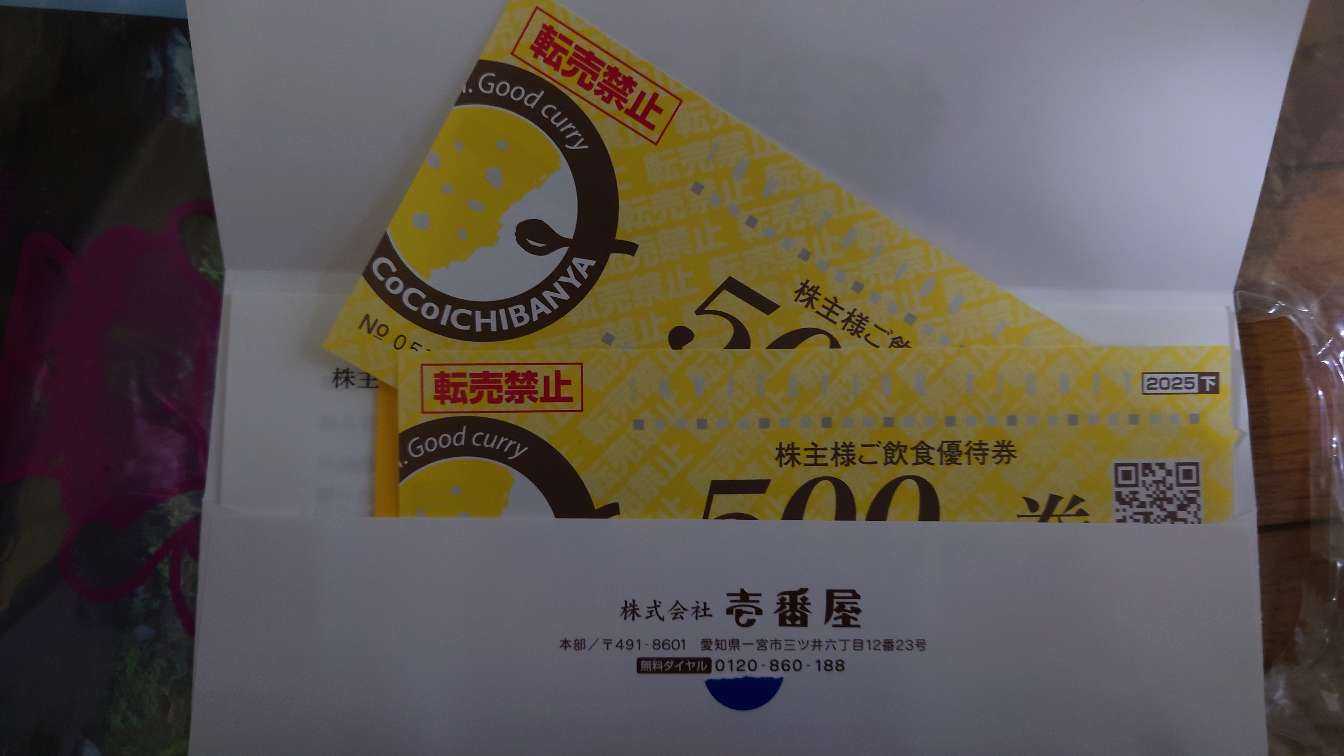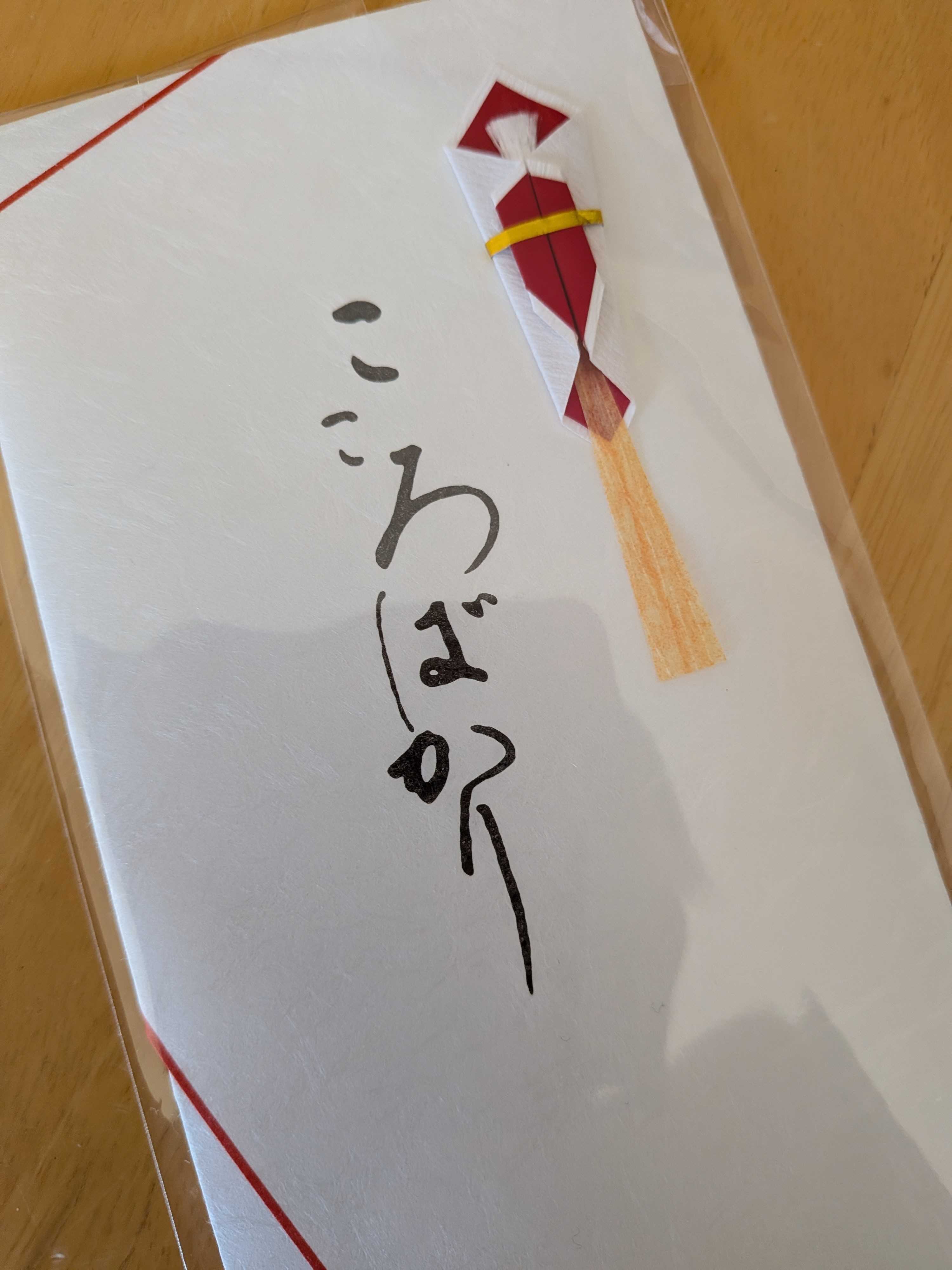2009年02月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

旧津島上街道(五条川右岸堤から薬師寺まで)
旧津島上街道(五条川右岸堤から薬師寺まで) 法界門橋を渡り終え、そのまま津島上街道は津島方面に向かいますが、橋を渡り終えたら左折して10mぐらい南下しますと堤防を降りる坂道があります。 車1台がやっと通れる裏路地のような細道で、現在は法界門橋西信号交差点北進右折車両が信号待ちを嫌って抜け道に利用していますが、かつての津島上街道です。津島上街道は名古屋と津島を結ぶ主要街道ですし、東海道の脇街道として佐屋街道が整備されるまでは主要街道だったはずですがその狭さに驚きます。主要街道は現在で言えば国道、それも国道1号線に代表される一桁番号の国道クラスの主要街道のはずです。「の~民」が、昭和30年代の後半に国道1号線を見たとき、あまりにもの車線広さ(2車線でしたので、交互通行をする必要がなかったからです。)と、通過車両の多さ(車が常に視界の中にある状態の道路でした。)に驚いた記憶があります。その頃の「の~民」の回りの交通事情は、40年代の前半に青年団に入っていた当時、村民運動会で字別(集落別)リレーの練習をするため、郡道(海部郡が設置した道路の意味だと思います)を集落の練習会場にしていたような時代でした。しかし、かつての主要街道(鎌倉時代の主要街道のことです)が、道路幅の基準が一間(約1・8m)だと知って納得しました。考えてみれば「の~民」たち現代人は、現在でこそ車幅1.5~2mぐらいの車で移動していますが、かつて街道を利用していたのは人か馬、若しくは大八車ぐらいしか通らなかったことを考えれば、一間幅の道路で十分ですよね。旧津島街道を抜け県道給父西枇杷島線にでると薬師寺はもうすぐです。
2009年02月23日
コメント(47)
-

仮界からの掛橋・法界門橋
仮界からの掛橋・法界門橋法界門橋は五条川に架かる橋ですが、津島上街道を名古屋方面から来ると、最初にある大きな橋です。この橋は、飯田守著の津島上街道にも、イワクありげな橋と言うことで諸説が述べられています。の~民にとって法界門橋は特別な橋で、輪中地帯で育ったの~民にとっては、堤防の内側こそが世界で、外側は仮界です。法界門橋は、仮界と現実界をつなぐ聖なる橋です。この橋から五条川の下流を見ると水量の少ない時には、川面の杭のようなものが見えます。昭和46年に架け替えられた、かつての旧法界門橋です。法界門橋から津島方面に向かう坂の左側に旧道がありますが、そこにつながっていたことがよく分かります。法界門橋 清須市側から見た 法界門橋です。 現在の津島上街道(法界門橋)です。 五条川の川面です。ところどころに、杭のような橋げた跡が見えます。
2009年02月20日
コメント(4)
-

長谷院を通抜け、法界門橋への津島上街道
長谷院を通抜け法界門橋への津島上街道「平野に坂があれば川がある」の法則があるそうですが、の~民の感覚では、「平野に坂があれば天井川がある」です。津島上街道も新川橋西詰の追分で美濃路と分かれてから始めての坂です。今は人家が建て込んで視界が悪くなったので、桃栄小学校南信号交差点を右折(西に曲がる)して始めて坂に気付きますが、かつての津島上街道は田んぼの中の一本道、常に視界をさえぎる五条川の堤防は見えていたでしょう。堤防といえば、の~民のような0m地帯に住むものにとっては、安心と限界の象徴でしょうね。の~民の住む集落の回りは、巨大な堤防に囲まれています。かつての伊勢湾台風や第二室戸台風では堤防が決壊して洪水となり、たわわに実っていた稲が全滅し、幼いながらに不安にさいなまれた記憶があります。今は河川改修も進み、の~民に限っていえば水害はよそ事になりましたが、それでも台風シーズンの長雨や大雨は不安感をかきたてます。また堤防は、その中に住む住民にとって境界線にもなります。地域を考える時は、堤防の単位で考える癖が付いていますので、幼少の頃は集落を囲む堤防の中だけが世界でした。その後交流が広がるにつれて広がってはきましたが、行政区域に関係なく庄内川の西側はの~民にとっては海部郡ですし、西側木曽川を越えればかかる時間に関係なく旅行感覚になります。同じ津島上街道でも、五条川の法界門橋を超えて、初めて地元の街道になります。長谷院を通抜け法界門橋への津島上街道 長谷院に参拝し、本堂前の長谷院境内の道標にしたがって津島上街道に通り抜ける。「の~民」としては、仏様に彫る「仏像光背形道標」より、こちらの道標のほうが好感が持てる。かつては別の場所に設置されていたのだろう、どうみても道標の面が違っていると思うがどうだろうか? 道標の表示を無視して、西方面に進むと道路に出る。 道路にでる駐車場の角に長谷院西方津島街道の入口道標がある。この道標は、津島方面から来た旅人を長谷院境内に導く道標です。 道路へ出て津島方面へ向かうには右折して北進すると桃栄小学校南信号交差点に出るので、この信号を左折(西向き)する。桃栄小学校南信号交差点の角には食事処の立ち喰い寿司・とんかつの山正がある。ここは寿司ととんかつの食事処であるが、外見と違い気楽な食事処です。 桃栄小学校南信号交差点から西方向(津島方面)見ると坂が右方向(北)に曲がっている。五条川の堤防に沿って曲がっているためですが、成田商店(土建会社のプラント)を右手に見て進みます。昔の津島上街道も、もう少し南のほうから五条川の堤防に沿って、上がり坂の街道が続いていたと思われます。 坂を上がると法界門橋が見えてきます。
2009年02月07日
コメント(0)
-

神明社(長谷院隣接)
神明社(長谷院隣接)長谷院の東隣に神明社があります。ここで「の~民」とっては、珍しいものを見つけました。百度石です。時代劇で、願掛けによく見るものですので、時代劇を作る上で必要なものなので、どこかの有名寺院に在ったものを、いかにも全国どこにでも在るもののように扱っているものだと思っていました。何しろ時代劇では、大名や武家の屋敷の表札や役所の看板をその時代にあったかのように当たり前に映すことを平気でしますので、百度石もその例だと思っていました。神明社が、長谷院隣接しているのは、日本では珍しいことではないので、「の~民」は明治の神仏分離令によって分離された神社だろうと思っていました。ですが飯田氏の津島上街道によると、長谷院の本尊が阿弥陀寺に移転していた時に、長谷院境内に建立されたものだそうですので、仏さまの留守を預かっていた神様ということになるんですね。神様や仏様にこんなことを言っては大変失礼だとは思いますが、神仏が仲良くしていた事例のような気がして、微笑ましいなぁ~と感じてしまいます。神明社で不思議に思ったのは、神社のシンボル狛犬がいないです。いずれ理由を調べたいとは思いますが、逆に考えるとなぜ神社に駒稲がいるのでしょうか?神明社 長谷院の東側に隣接する神明社の入口です。普通の神社ではここに鳥居があるのですが、鳥居が少し中にあるのは理由があるのでしょうか? 神明社の鳥居と社殿です。境内の規模の割りに、鳥居が小さいような気がします。社殿は結構立派なものですね。 百度石です。「の~民」は、江戸時代か明治時代ぐらいに建立されたものかと思っていましたが、反対側に「昭和42年度年行司」と有りましたので、新しく建立されたのを知り驚きました。この後、古い神社や仏閣にあるのに、ヒッソリと建立されているのに気づくようになりました。 神明社の本殿です。奥深い神聖な神社の雰囲気が在りました。 合祀された祠です。秋葉神社をはじめとして3社が合祀されていました。
2009年02月01日
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1