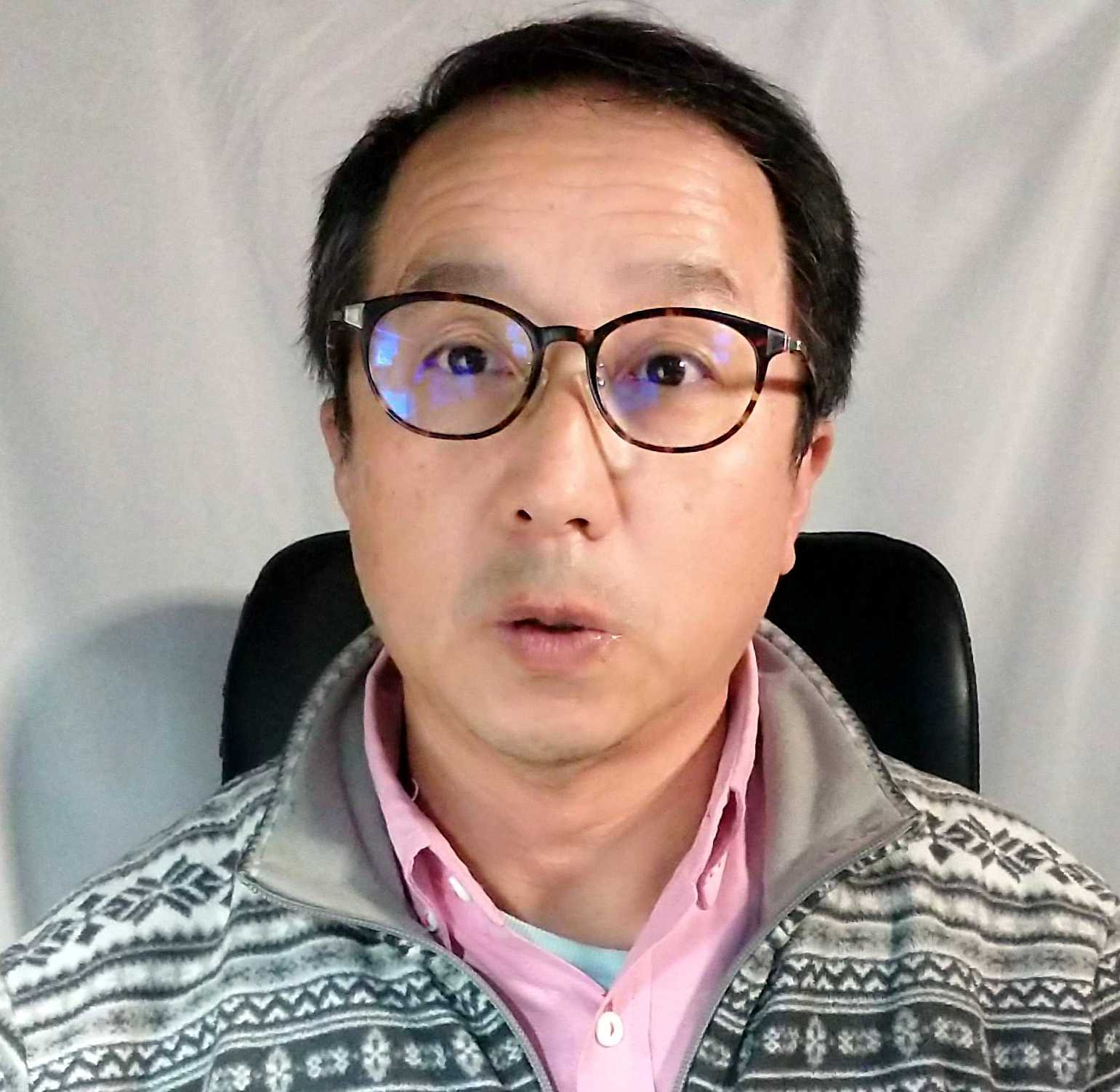PR
Calendar
Category
Comments
Keyword Search
「毎日更新」読レポ第2077
カール・ロジャーズ
~カウセリングの原点~
著:諸富祥彦
発行:㈱KADOKWA
第6章 1955年ロジャーズとジャンドリン
TAE(thinkig (ティンキング:考え)at the edge(エーッジ:角)(4/4)
TEAは、ただそこに立ち戻りだけではなく、自分の暗黙のうちに理解していることを既存の概念ではうまく表現でえきないと感じる時に、妥協することなくそれを表現できるように、「言葉の新鮮な使用法」を開発することを奨励してくれる
。言葉を「暗黙のフェルトセンス」から浮かび上がらせ、「暗黙のフェルトセンス」に照らし合わせてチェックする。
そうすることで、妥協することなく、自分のほんとに言いたいこと、いわんとしていることに真にふさわし言葉をみつけることができるのである
(
https://focusing.org/felt-sense/thinking-ede-tae)。
TEAは、私たちが時折感じる「大切なことにあって、それを自分は知っている。わかっている。けれどもうまく言葉にできない。どう言ったらいいかわからない」時、その暗黙知を「言葉にする」方法である
。
私たちが内側で抱いている暗黙知(ロジャーズ流に言えば、内臓感覚知)を明らかにしていく方法である
。
英語圏ではTAE(thinking(ティンキング:考え) at the edge(エージ:角))「エッジで思考する」と呼ばれているが、ドイツ語圏では、”Wo noch Wore fehlen"「未だ言葉の欠けるところ」ろ名づけられている。後者のほうがダイレクトに中身が伝わりやすいかもしれない。
日本のTAEの普及に尽力している得丸さちと子氏は、次のように説明する。
「自分ではわかっていることなのだけれど、言葉にならない。これを伝えたいというのがあるのだけれど、うまく言えない。”自分のことば”で書きたいけれど、なんだか借り物みたいという経験は、あるませんか?うまく言葉にできないのは、ほんとにわかっていないからだと思ったり、”正しい言葉”の呪文に囚われたりしていませんか?わかっていること、伝えたいこと、いいたいことには、独特の感覚(フェルトセンス)があります。言葉にしたい、”なにか”は、その人だけが知っている、たったひとつのユニークなものです。TAEは、その言いたい「何か」から感じられるフェルトセンス(からだの感じ)に触れながら言葉にしていく、ひつようなら理論にまでしていくことのできる独特の方法です」
と著者は述べています。
TEAは、「自分ではわかっていることなのだけれど、言葉にならない。これを伝えたいというのがあるのだけれど、うまく言えない。”自分のことば”で書きたいけれど、なんだか借り物みたいという経験は、あるませんか?うまく言葉にできないのは、ほんとにわかっていないからだと思ったり、”正しい言葉”の呪文に囚われたりしていませんか?わかっていること、伝えたいこと、いいたいことには、独特の感覚(フェルトセンス)があります。言葉にしたい、”なにか”は、その人だけが知っている」と述べている。
確かに、自分の中の感覚的は、ぼんやりだけどなかなか言葉にならないことがある。そこには、自分の中に”正しい言葉”で言わないとの無意識的なものが、潜んでいるのかも知れない。そんな時は、自分の中の自分に対話して、何を言いたいかを問い、”正しい言葉”を手放して、浮かんだ言葉を書いて、書いて、正しい言葉でなくてOKなので、書いているうちに自分にピッタリのしっくり来る言葉が湧いてくることがある。自分の中に書いて見る事で、書いて見ることを繰り返して行くことで、自分の言いたい表現が見えて来て、ぼんやりしていたことが、少しずつ見えてくる。
この読書レポートも同じように、私の中のぼんやりした言葉にならないことが、書く事でぼんやりしたものが、少しずつ見えてきています。”正しい言葉”を手放していくことで私の中のぼんやりした言葉にならないことが、、少しずつ見えてきています。
-
「毎日更新」読レポ第2105 カール・ロジ… 2024.06.15
-
「毎日更新」読レポ第2104 カール・ロジ… 2024.06.14
-
「毎日更新」読レポ第2103 カール・ロジ… 2024.06.13