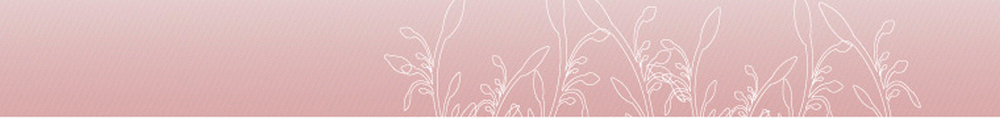2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年01月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
あるある
どの回においてどんなねつ造をしたか、というのは、他の媒体などからの突っ込みで、徐々に明らかになっていくだろう。しかし、「ねつ造のメリット=モチベーションはなんだったのか」という問題が明らかになっていない気がする。(単に報道見てないだけかも)問題となっている制作会社が、通販で納豆や健康食品を売って商売しているわけではないし、研究機関として食っていきたいと考えていたわけでもなさそうだ。ましてや納豆や健食企業の株を買い占めてキャピタルゲインを狙ったわけでもあるまい。だとすると、まずクライアントありきで、扱うべき商材が指定されていて、その商材が健康に役立ちそう、という理由をこじつけることを制作会社に局が課していた、と考えるのが自然かもしれない。(そうでないかもしれない。番組の視聴率アップのためだけにねつ造していたというのもあるかも)コンテンツ内容が広告であること自体は、テレビ局とて公共機関ではないので仕方ないが、これまでどういった団体から、どれくらいの金をテレビ局がもらっていて、どのくらいのプレッシャーを制作会社にかけて作らせていたのかが気になる。しかし、番組制作会社はそのあたりについて何も言わないだろう。番組制作会社は力が弱いから、トカゲの尻尾切りされるだけ、というのはなんともなーと思う。
2007.01.31
コメント(4)
-
警備員の数
東京って、警備員さんの数がやたらめったら多い気がする。街を歩いているとものすごく見かける。普段は景色に溶け込んでいるけど、一度気にし始めると、毎日ものすごい数の警備員とすれ違っていることがわかる。東京都内で、ある一時点を取ってみたときに、何人の警備員が稼動しているんだろう。人口1万人あたりの警備員数の国際都市比較、とかってどっかにデータないかなあ。
2007.01.30
コメント(4)
-
「今使っているOSは旧式。」
という認識をどれだけ植えつけることができるか、が、新OSのマーケティングのキモだ。現時点で、とくにXPや2000で困っていることはない。新機能でアピールするものがないとすると、いかに旧式か、を煽るしかなくなる。
2007.01.29
コメント(1)
-
入力フォームやDBのテーブル数は
コミュニケーション量を増やすには、入力フォームやDBのテーブル数を増やせばいい、と考えている人が多いが、実際には、フォームやテーブル数が増えると、コミュニケーションが発散してしまう。逆にテーブル数や入力フォーム数は減らせるだけ減らしたほうがいい。ユーザーがどうしても欲しい、と感じたときだけ増やす、のが2chの成功要因だ。これが分からないと、(コミュニケーションサービスを設計するのは)難しい。
2007.01.29
コメント(0)
-
他人を変えるのは難しいから自分を変えるしかない?
仕事術系の本なんかで、「他人は変えられない」「だから自分を変えるべき」と書いてある。自分を曲げるより、他人を変える努力をしたほうが、ずっとうまくいくことが多い、と思う。
2007.01.29
コメント(2)
-
自分が入社する前の状況を想像する。会社ができたころを想像する。
新卒であれ中途であれ、「会社に入る」ということは、「途中参加」である。すなわち、「先発」「スタメン」ではなく、「中継ぎ」のメンバーである。そのときに、必要になるのが、「自分が入るちょっと前って、会社がどういう状況だったのか」「その会社ができて大きくなったころ、どういう状況だったのか」その二つを働くなかで想像することだ。これらを感じとることができないと、会社はただの理不尽な存在になってしまうだろう。(それに気づくまで何年もかかってしまいずいぶん悩んだ)G社創業者のT君は、「僕は設立3、4年の会社に入ったが、自分の入る時点までその会社がどういう成長パスをたどったか、とても知りたかった。起業することでそれを追体験できるかも」と言っていた。今思い出しても名言だと思う。
2007.01.25
コメント(0)
-
Google TrendsとAlexaの情報はかなり連動している
ネット業界の人は、割とAlexaのデータを信じていない人が多いように思う。たしかに中堅以下のサイトはそうかもしれないが、ある程度以上の規模のサイトのデータ、ある程度以上のリテラシを対象としてサイトに関して言えば、正しいといわざるをえないと思う。一例として、mixiと2chのキーワードトレンドとAlexaのアクセス推移を見てみよう。Google TrendsとAlexaのグラフがここまで近似している。
2007.01.22
コメント(0)
-
評判なんて一瞬で変わる
なんか今月は、ビジネスの世界において、「世間の評判が一瞬で変わる」というのを目にする月だ。「ウェブ2.0に出遅れて叩かれてた企業がWebAPIを提供開始」「老舗菓子メーカーの不祥事」「超人気の健康番組の効能捏造」「某テレビ局株買い占め後、ずっと損して文句言われてたが、含み益が出た件」世間の評価は手のひらを返したように変わる。だが、変化を作り出すのは人間であり、評判がずっと変わる前に、その原因は作られている。だが、それを見ることはできない。
2007.01.22
コメント(0)
-
開発合宿ポータル
昨年ブレイクした開発合宿。かいはちゅ.comという、開発合宿ポータルができたそうです。
2007.01.22
コメント(0)
-
みんなの楽天市場
楽天市場のウェブサービスが始まったらしい。楽天ウェブサービスセンターデベロッパーIDなんかも簡単に取れて、なかなかいいすね。
2007.01.17
コメント(0)
-
1/10の日記は間違い
ガジェット(ウィジェット)って流行んないだろうなあと思ってたけどに、ウィジェットがモバイル普及とともに流行るかもという内容を書いた。しかし、関連記事を読み、iPhoneにはサードパーティのウィジェットの参入を想定していない、ので、1月10日の日記は間違いでしたorzよく調べてなかった・・・・。まあいずれ開放されるとは思うけど。
2007.01.17
コメント(0)
-
「封鎖できません」
2ch閉鎖騒動で、周りの反応を見ていて思ったのですが、ドメイン(サブドメイン)とサーバーのIPアドレスが、強固に紐づいているものだと思っている人って、世間には相当多い様子。ドメインを差し押さえることができるかどうか、という点に話が行きがちですが、ドメインが万一なくなっても、海外にサーバーがある限り、サービス自体を止めることができないのに。むしろ、今回の件で、もし2chに対してのプロクシーやら、別名のドメイン名を設定する第三者が増えたら、よりサービスの可用性が上がって、2chの閲覧をシステム的に禁止している法人なんかは対応作業に追われそう。
2007.01.17
コメント(0)
-
開発合宿の強みは思考のマッシュアップにある?
1社でやる会議や合宿に比べ、複数社のエンジニアが参加する開発合宿だと、自社内の参加者だけだと見えないものが見えてくるのかもしれない。その事例としてはこういうのがある。人気サイトランキング1社で開発合宿をやっている会社は、外部の合宿参加者を募ってみるといいのかも。リクルーティングや社員教育の意味もありそう。
2007.01.15
コメント(0)
-
年を取ってやばいな、と思うこと
年とともに、誰かに、「教えてください」と言うのがだんだん難しくなってきている。立場的にも、自分の気分的にも。
2007.01.13
コメント(1)
-
今回の騒動で、2chは復活するかも。
2chに限らず、ネットのコミュニティが飽きられつつあり、盛り下がるようになってきているが、2chがこういった騒動で注目を集め、ユーザーが再度注目することになり、より一層アクセスが集まることになって、結果的には2chにとってはウマーな気がします。
2007.01.13
コメント(0)
-
2006年は日本のウェブ業界に逆風だった
2006年の各社のトレンドをAlexaで見てみる。昨年は、サイト(ドメイン数)が爆発的に増えた一方で見ているユーザーはそれほどには増えなかった点、日本の伸びが海外の伸びよりも明らかに鈍化している点、検索エンジンのロジックの変更などの要因により、日本の各社サイトのデータは、おおむね1月と12月で比較すると、2~3割減、というところが普通だ。逆に、その期間、リーチが増えている、というサイトがあれば、そこはかなり実力を持ちつつあるサイトだと言えよう。ちなみに、2007年は、2006年以上に逆風だと思う。
2007.01.12
コメント(1)
-
ガジェット(ウィジェット)って流行んないだろうなあと思ってたけど
グーグル、ヤフー、アップル・・・。各社は、デスクトップやブラウザ上に固有の機能を組み込めるようにウィジェットの機能を提供している。かつてマイクロソフトがやったように、プラットフォームを用意し、サードパーティにツールを作らせる、というビジネスモデルであり、いまさら非オープンでの囲い込みはうまくいかないだろう、と読んでいた。しかし、iPhoneの発表を見て、「ああ、モバイルのガジェットはありだな」と思った。ガジェットをPCでも携帯でも使えるようになれば、もしかすると、PCとモバイルの融合のきっかけになるかもしれない。
2007.01.10
コメント(0)
-
イノベーターやアーリーアダプターは気が短い
コンセプトの発表から、商品発売まで、あまり時間がかかりすぎると、ブレイクする波に乗り損ねる。期待されていたのに出るのが遅れすぎて市場に嫌われてしまった商品。それほどでもないのにリリース後すぐに出荷されうまく話題に乗った商品。
2007.01.10
コメント(0)
-
任天堂はいったん死んだ技術に光を当てる
ブラウン管のテレビがメインだった時代、走査線を利用したガンコントローラーのゲームが一定の市場を占めていた。しかし、テレビの液晶化やプロジェクターの登場により、ガンコントローラータイプのゲームは家庭用ゲームから消えてしまった。PDAで普及していたペン入力は、認識率の問題や携帯電話の普及により、モバイル入力の本命から転がり落ちた。WiiもDSも一度は消えてなくなりそうになったテクノロジーに光を当て、ぽっかりと開いていた市場で一気に勝負した。もしも、PDAが全盛でペン入力UIが今でも普及していたら、ガンコン系の体感ゲームがまだ市場で流通していたら、WiiやDSに今ほどの目新しさを感じなかったかもしれない。
2007.01.09
コメント(1)
-
SNSはブログよりも危険か。
SNSは個人情報と割とひもづいているので、匿名のブログや掲示板では平気で書かれているようなこと(未成年の飲酒とか不倫ネタとか)で容易に炎上する。逆に、知人相手のみにクローズド利用していることで、オープンなブログじゃ書けないことをSNSで書き散らかす、ということもできる。それはそれでアリだ。ただ、どこかでブログとSNSの情報が完全にリンクしちゃうとシャレにならない、という人は今後増えてくるかも。
2007.01.08
コメント(1)
-
CGMか、MGCか。
Consumer Generated Media、通称CGMというのが言われるようになってきた。その一方、企業がコンシューマーに小銭を払ってパブ記事を書かせる、というモデルも出てきている。そんな話を聞くと、くちコミが流行、なんつっても、昔通り、メディアによって消費者を作り出される、「メディア・ジェネレーテッド・コンシューマー」というモデルが大勢なのかな、と思う。
2007.01.05
コメント(0)
-
mottainaiとマクロ分析
「もったいない」がある国とない国でマクロレベルでの経済発展がどう違うか。あとで書く。
2007.01.05
コメント(0)
-
受験メソッド
大学受験だの高校受験が、それほど大変だったのかは覚えていない。ただ言えるのは、仕事の厳しさとはレベルの違う厳しさだということだ。同じ条件のものを学び、同じ問題を同じ制限時間で解く。問題に勝ち、時間との戦いに勝ち、他人に勝つ、そして、多少の努力のうえで、ジンクスに頼ったり合格祈願をしたり。自分は「死ぬほど頑張った」というわけではないが、多少は真剣でやっていたはずだ。だから楽しかった。たったの3科目の話だが。そういえば、「今でも受験時代の夢を見る」という人も多い。それにくらべ、あのあと10数年間、それくらいの努力ができていただろうか。ビジネスの場合は、「人によって前提が違うから」という理由もあって、あまり本気を出し切れないことが多い。受験のときを100とすると、社会人になってからの平均は、年の平均にすると20~40ぐらいかな。受験のときぐらいには頑張ってみる、というときもあってもよい。
2007.01.04
コメント(1)
-
組織は誰に最適化するべきか
組織は、顧客や株主に最適化するべきである、というのは極めて当たり前の話なのだが、では、社内では誰に最適化された設計であるべきであるか。やる気がある人に合わせるべきか、ない人を対象にするか、人数の多い層に合わせるべきか、希少なリソースに合わせるか、マネージャー層に合わせるべきか現場に合わせるべきか、長くその会社にとどまろうとする人に合わせるべきかどうか。そんな風に考えれば、外資系的な、「up or out」という発想がもっとも組織運営に最適化された行動であると感じる。
2007.01.03
コメント(1)
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
-

- Amazonマケプレ
- #PR 2,247円 アサヒ飲料 ウィルキ…
- (2025-04-28 18:18:02)
-
-
-

- パソコンニュース&情報
- プリンタの廃液タンクの中身を交換し…
- (2025-04-28 16:30:23)
-
-
-

- いいもの見つけたよ
- おすすめノートパソコン「富士通 FMV…
- (2025-04-27 09:12:21)
-