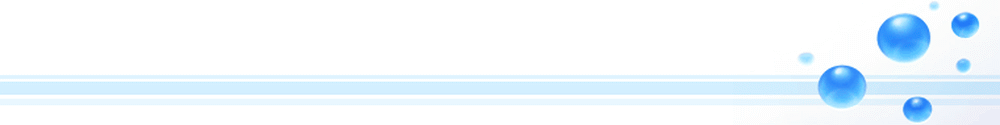第十一幕~第十六幕
本作品は、 「るろうに剣心小説(連載1)設定」 をご覧になってからお読みいただくことをおすすめいたします。面倒とは思いますが、多少オリジナル要素が入りますので、目を通していただきますと話が分かりやすくなります。
『きみの未来』目次
『きみの未来』
第十一幕「鬼とはちみつ」
朝が訪れた。神谷道場も、普段と変わりなく一日が始まる。
五時半。剣心と弥彦は起床。身支度を整え、剣心は朝餉の支度をし弥彦は手伝う。
六時半。朝餉が出来る頃、薫は起きてくる。ここで三人は朝食。
七時から八時近くまで、弥彦は庭掃除と家中の廊下の雑巾がけをする。
ここまでは、普段と同じだった。いつもなら、弥彦はこの後道場で神谷活心流の稽古を受けるか、あるいは出稽古か、または赤べこへ日雇いに出かけたりする。けれど、今日からは違う。
八時から十一時。この三時間は、飛天御剣流の修業時間として決められた絶対的な時間である。八時までに必ず道場へ入っていること、と弥彦は剣心に言われていた。
弥彦はいつもより急いで掃除を終わらせると、道場――倉を剣心が片づけて用意した修業場――へと足を運んだ。木戸の前で、息をする。少し緊張しているのが自分でも分かったが、木戸へ手をかけ薄暗い道場内へ入った。倉に入れられていたものは他の倉へ移動したらしく、中はがらんどうだった。漆喰の壁に囲まれ、両脇の高いところにそれぞれ小さな窓がいくつかあり、そこから少しだけ日の光が差し込まれている。道場の広さは、神谷道場の半分くらいだろうか。
そこで弥彦は待った。あれ程望んでいた飛天御剣流を教えてもらえる日がとうとうやってきたというのに、何故か実感がわかない。弥彦は、初めての今日はなにをするのだろうと想像してみたが、まるで検討がつかなかった。
八時。ちょうどの時間に木戸が開き、剣心が入ってきた。弥彦は振り向かず、床を強く見つめたまま、剣心が弥彦の横を抜け真向かいに立つのを待った。そのとき弥彦が決めていたこと。それは師匠への挨拶。
「――ゃっす!」
薫の時はなぁなぁになっていて、結局最後まで初めの挨拶をしたことがなかった。だから、正直剣心にも躊躇したが、初めに言わないと言えなくなると思い、柄にもないことを精一杯にやってのけたのである。それだけで、弥彦は妙にうろたえてしまったが、修業はこれから始まるのである。気合いを入れて、剣心を見た――が。
弥彦の体は、びくっとした。剣心の目――自分に向けられたそれは、あまりに鋭く厳しかった。普段の穏やかで優しい表情はかけらもない。圧倒的な威圧感に、弥彦は体ががちがちになり、額から汗がにじむ。震えそうになる体を、必死で抑える。
「……刀はどうした」
「……!?」
剣心の低い声に、弥彦は混乱してあわてて考える。稽古と竹刀、二つが固く結びついている弥彦の頭には、刀で修業などということは全く頭になく、当然のように竹刀を背負ってきてしまったのだ。
「さっさと持ってこい」
剣心の絶対的な言葉に、弥彦は条件反射のように道場を飛び出した。全速力で部屋へ戻り、弥月刀をつかんで竹刀を置き、駆け戻る。木戸の前であわてて刀を腰に差し、中へ入って元の位置に戻った。
「抜刀から始める」
激しく息を切らしている弥彦に、剣心は休む間もなく言った。
「よく見ていろ」
剣心は言うが早いが、構えて抜刀した。その動きはあまりにも速く、弥彦には捉えるのにやっとだった。
「やってみろ」
突然の命令に弥彦はとまどったが、ぎくしゃくする体を何とか動かし、剣に手を沿え構える。おととい、剣心と一緒に抜刀したが、一人で抜くのは初めてである。弥彦はおとといの情景を懸命に思い出し、親指で鍔を上げ――剣を振り抜いた。
胸が高鳴った。興奮した。いつも見ているだけだった剣心の抜刀を、自分でやってのけたのだ。
だが――
「振り抜きが甘いっ! もう一度!」
降ってきたのは、褒め言葉ではなく容赦ない怒鳴り声。弥彦は、いつもとあまりにも違いすぎる剣心にただ驚き、見つめていた。
「どうした。言われたらさっさとやれ!」
弥彦はあわてて、再度抜刀した。
「右手に力が入りすぎだ! もう一度!」
弥彦は夢中で抜刀する。
「残心はどうしたっ!」
残心とは、武芸において動作を終えた後も緊張を保つということだが……今の弥彦には一振りするだけで気力がつきそうだった。
こうして何度も抜刀を繰り返した弥彦は、慣れない重い刀を振るう肉体的負担と、それ以上に感じる精神的な苦しさで、息が詰まり意識が遠くなりそうだった。ついには、ガシャン、と刀を落としてしまう。
拾おうとした弥彦の手は、剣心の足に踏みにじられた。そして襟首をつかまれ、頬を思い切り殴られる。
「簡単に刀を落とすなっ!」
弥彦は床に倒れたまま、あまりの痛みにこらえるだけで精一杯だった。
「何してる。さっさと拾え!」
言いながら、剣心は弥彦の腹を容赦なく蹴る。
弥彦はごほっ、ごほっとしながら、激痛に歯を食いしばり震える手で刀に手を伸ばす。そして何度も倒れそうになりながら、必死で立ち上がる。
こうして三時間、抜刀しては怒鳴られての繰り返し。弥彦はぎりぎりの精神力で、ただ立っていることを維持することさえ辛く、けれど無我夢中で剣を振り続けた。
こうして、弥彦にとっては永遠とも思える長い三時間が過ぎ、初めての修業は終わった。
剣心が道場を出ていくと同時に、弥彦はその場に倒れ込んだ。息苦しく、腹がズキズキする。殴られた頬が熱く、腫れ上がっているのを感じる。右手は豆がつぶれ、血がにじんでいる。
弥彦は、天井を見つめていたが、必死で体を起こし道場から外へ出た。
弥彦が道場から一歩外に出ると、すぐ横の壁に剣心が寄りかかって立っていた。弥彦はびくっとしたが、無理に平静をよそおい木戸をしめる。すると剣心は、弥彦の腕をつかみ井戸端へ連れて行った。そして、たらいに水をくむと井戸のへりに置く。
「右手、痛いでござろう? 水に浸して、冷やすでござるよ」
剣心は、弥彦の腕をつかみ、水の中に手を入れてやる。立っていることさえやっとの弥彦の肩を、剣心はもう一方の手で抱きかかえる。弥彦の肩から、かすかな震えが伝わってくる。
「腹も痛むでござるか?」
弥彦は、剣心を見上げた。修業が終わって初めてまともに見た剣心は――優しい表情だった。弥彦は思わず涙が出そうになったが、必死で呑み込んだ。そして問われていることを思い出し、本当は痛くて仕方がなかったが、首を振った。
「そうか」
剣心は、手ぬぐいで弥彦の汗をぬぐってやった。そして弥彦を部屋へ連れて行き、薬を塗り込んだ白い布を弥彦の頬に貼り付けた。
弥彦は、その間押し黙ったままだった。一言でも何か言えば、その拍子にぎりぎりまで来ている涙がこぼれてしまうと思ったからである。だから、ひたすら口を結んで我慢した。
剣心が昼飯の準備に取りかかると、稽古を終えた薫とふらふらやってきた左之助に、弥彦は取り囲まれた。
「どうしたのその体!? 頬腫らして、手の豆つぶれてるじゃない!」
「どうしたって……修業の傷に決まってんだろ」
ぶすっとした弥彦に、薫は興奮状態になってしまった。
「うそ! 絶対うそよ! 剣心がそんな厳しい修業つけるわけないでしょ!」
「明日覗いてみっか」
左之助も、さすがに驚いたらしく、真剣に言う。
「あのなー、道場は立ち入り禁止だ。こないだ剣心にそう言われただろ」
弥彦は、呆れてため息をつく。既に混乱状態の薫をそのままに、左之助は弥彦を覗き込んで聞く。
「で、アイツどんな感じだったんでぇ」
弥彦は、少し考え言った。
「鬼とはちみつ」
「はぁ? なんだそりゃ」
左之助の問いには答えず、弥彦は去っていった。
神谷家の裏で、弥彦はやっと落ち着いて休むことが出来た。ふぅと息を吐く。そして、ようやく修業を振り返る余裕が出来る。
恐かった。それが、一番強く感じたことだった。そして、修業内容は、想像を絶した厳しさだった。けれど、弥彦は思った。どんなに辛くても、絶対に剣心についていこうと。
だが、弥彦はまだ知らない。今日の修業が、どれだけ甘かったかを。これから続く、地獄のような修業の日々を。どれだけ体がぼろぼろになり、精神的に追いつめられ、心に傷を負うかを……。
☆あとがき☆
本編第一回目。話の核となる剣心と弥彦の修業話です。鬼師匠な剣心と、はちみつのように甘い普段の剣心。さて次回からは、弥彦が御剣流の修業に励むという生活の基本を踏まえた上での、数々のエピソードをつづっていきます。そろそろ、斉藤さんや蒼紫様たちが出てきそうです。
第十二幕「夏祭りの夜」
真夏の午後。空からは強烈な日が射してくる。河原の土手、草むらのなかで大の字になって空を仰ぐ少年――弥彦は、まぶたを半分閉じてぼーっとしていた。眠いわけではない。うだるような暑さだが、それにへばる年でもない。飛天御剣流修業二日目。修業は一日目と変わらず厳しかったが、鬼の剣心に早くも慣れた弥彦からは、修業への怖さは消えていた。右手は豆だらけだが、剣心が手当をしてくれているので、特に日常生活に差し支えはない。
けれど、弥彦はひとつため息をついた。
「夏祭り……かぁ……」
弥彦は目を閉じた。弥彦の脳裏に、ごった返す人々と花火が浮かぶ。
再び憂鬱そうに目を開けると、覗き込んでいたのは由太郎だった。
「夏祭りが、なんだって?」
「由太郎! てめぇ何いきなりいるんだよ」
弥彦は、がばっと身を起こして座った。由太郎は、白い布鞄を持って、弥彦を見ていた。
「その手の傷、どーしたんだよ。ん? なんだこれ」
由太郎は、弥彦の横に竹刀と並べて置いてある、白い袋に入れられた細長いものを手に取ろうとした。
「さわんじゃねぇ!」
弥彦はあわててそれを取ると、竹刀を背中に差した。
「俺は今、剣心に飛天御剣流習ってんだ。これは逆刃刀。剣心が、帯刀はダメだけどこうして持ち歩くならいいって言うからさ。あっ、手の傷は修業の傷だ」
「……はぁ!?」
一気に説明された由太郎は、成り行きのあまりの変化にただ驚いていた。
「で、お前は何やってんだよ」
弥彦は、急に由太郎に話題をふってくる。
「何って、学校帰りだよ。いつもこの道通るんだ」
由太郎は、弥彦の隣りに腰を下ろした。
「ふうん。それでお前は、いつフェンシングの稽古してんだ?」
「週一回。日曜日の朝」
「たったそれだけかよ! そんなんで強くなれんのか!?」
弥彦はいきりたった。けれど由太郎は平然としている。
「短期集中が大事。先生がいつもそう言ってる」
由太郎の目は、フェンシングの先生を信頼しきっていた。弥彦もそれを見て、もう何も言わない。
ふと、土手の上を通り過ぎていく人影が、弥彦の目に入った。一瞬弥彦は驚愕した。
「さっ、斉藤!?」
しかしその影はすぐに消えた。弥彦は目をこすり、首を傾げた。
今夜は、夏祭りだった。薫は当然のように行くことを決め、神谷道場の三人は夕方赤べこの前で待ち合わせを決めた。けれど日が沈みかけている今、由太郎と木登りをしていた弥彦は、いまだ下りてこようとはしなかった。
「弥彦早く下りろよ! 祭に遅れるだろ!」
「お前、誰と行くんだ?」
弥彦は枝に腰を下ろして町を見下ろしながら、ぼそりと聞いた。
「誰って、家族に決まってんだろ。特に花火ってのは家族で見るのが当たり前だろ」
「……そーだよな」
弥彦は、夕日の赤さに一瞬心が痛んだが、観念して下へ下りた。
「ったく。剣心さんと薫さん待ってんだろ。行くぞ」
由太郎の言葉に、弥彦は何故か胸が苦しくなったが……由太郎に続いて河原を後にした。
「剣心と薫、先に行ったって!?」
由太郎と別れ、赤べこについた弥彦だったが、一足遅かったようだ。
「花火が始まる時間に小豆茶屋の前で待ってるっていってたさかいに。燕ちゃんも家族と花火見るゆうてたけど、それまで一緒にお祭行ってくれると助かるんやけど……」
「あいつら……わざとだな……」
弥彦はぶつぶつ言っていたが、燕が出てくるとはっとした。紺色に朝顔の浴衣姿。短い髪を結い上げ、かんざしをつけている。
「あ……弥彦くん……」
燕も弥彦も互いに目をそらし、それぞれ頬を赤くした。
「でぇ、なんで俺が女狐と一緒にいるんでぇ」
左之助は恵と並んで夜祭りの町を歩いていた。屋台が並び、金魚すくいやら団子やら砂糖水やらお面やら、延々と店の明かりが続いている。ごった返す人々。
「それはこっちの台詞よ。往診の帰りに、まさかあんたと会うなんてね。それで花火は誰と見るわけ?」
「舎弟のヤツとな。お前は?」
「小国先生と」
左之助は、懐に手を突っ込んだ。
「あんま金ねぇけど、かき氷くらいなら食わせてやるぜ」
「そう? じゃあお言葉に甘えて。でも診療所のつけをちゃらにはしないわよ」
「……女狐め」
きれそうな左之助の表情を見て、恵はくすりといたずらっぽく笑った。
二人は椅子に座り、並んでかき氷を食べた。
「弥彦、今頃燕ちゃんと仲良くやってるかしら」
薫はにこにこして剣心を見つめる。
「どうでござるかな」
剣心は苦笑し、それから薫を見つめる。紺色の生地に桜柄の浴衣。髪は結い上げてかんざしをつけていた。いつもより、大人に見える薫。
「け、剣心……。何?」
薫は見つめられて、心臓が高鳴った。
「浴衣、似合うでござるよ。薫殿」
剣心は、にっこり笑った。薫はかぁぁと赤くなり、頬に手を当てる。その時、ふいに剣心は薫の肩を抱いて自分に引き寄せた。
「剣心……!?」
「ああ、いや済まぬ。酔っぱらいが、薫殿にぶつかりそうだった故……」
そう言いながらも、それから少しの間、剣心は薫の肩を抱いていた。
「ずっと……こうしてたいな……」
薫の小さなささやきは、人々のざわめきにあっという間にかき消された。
「妙から小遣いもらったけど、何買う?」
弥彦はどんどん歩いていく。後ろから、燕が小走りに追いかける。
「ったく、のろまだなお前は。で、何ほしい?」
弥彦は燕が追いつくのを待って聞く。
「弥彦くんは?」
「何か食いもん。けどお前が先に選べよ」
「じゃ、じゃあ、りん……」
いつの間にか燕は、また後方の人並みにもまれていた。
「……しかたねぇな」
弥彦は燕の元へ戻ると、一瞬ためらったが、思い切ってその手を握った。燕は一瞬びくっとする。
「これならはぐれねーだろ。で、なにほしいって?」
「り……りんご飴」
燕が恥ずかしそうに言うと、弥彦はすぐ近くの屋台でりんご飴を買った。
「ほら」
「あ、ありがとう弥彦くん」
燕は、うれしそうにりんご飴をなめた。その仕草に弥彦はなんだか落ち着かない気分になったが……。
「別に。俺の金じゃねぇし」
ぶっきらぼうに答えた。
「でも、ありがとう」
燕が笑うのはめずらしいので、弥彦はもう何も言わず、りんご飴をなめる燕を見ていた。
花火の時間になり、弥彦は燕と別れ、茶屋の前で剣心達と落ち合った。三人は人混みの中、並んで立つ。やがて、夜空に花が咲いた。ぱあん、ぱあん……と、打ち上げられていく花火。剣心を真ん中に、薫と弥彦は花火を見て……いや、弥彦は花火なんか見ていなかった。見ていたのは、まわりの人々。皆、家族で幸せそうに花火を見ている。
弥彦は、心がズキンと痛む。嫌でも思い出す。あの地獄の日々。祭の日は、スリをする弥彦にはもっとも稼ぎ時だった。働きずくめだった母にはとうとう一度も祭に連れて行ってはもらえず、弥彦はスリとして初めて祭の夜を過ごした。こんなに人がいて、家族がいて、皆が幸せそうなのに、自分だけ独りだった。そして独りの自分は、スリをして、皆の幸せをこわさなければ生きていけなかった。一年に一度のそんな夏祭りを、三度経験した。
ぱあんという音に、弥彦は我に返る。大きな花火だった。その光に照らされた、剣心と薫を見上げる。今、ここに立っている自分が、なんだか夢の中のようで……信じられなかった。
また、大きな花火が上がる。
「うわぁ! 剣心! 弥彦! 今のすっごい大きかったわね!」
薫は二人ににっこり笑い、また夜空を見上げた。
「ああ。そうでござるな」
剣心も薫に微笑み、そして弥彦ににっこり笑った……が。
「弥彦?」
剣心は、小さな声でそっとたずねた。
「去年は、スリやってた。一昨年も、その前の年も……」
弥彦は、前を見たまま、ぼそりと言った。
「今年は俺……ここにいても……いいのかなぁ……」
剣心は、返事の代わりにそっと肩を抱いてやった。弥彦は人混みの中で誰にも気付かれずに……ただ剣心がすべて分かってくれたことに気付き……抱かれるまま剣心のお腹に顔をうずめ、ほんの少しだけ泣いた。
少しして、弥彦が剣心から離れ涙をぬぐうと、剣心は弥彦に肩車をしてやった。大きな花火が、一層弥彦に近くなった。
花火は、弥彦の涙をすいこんで、幸せの余韻を残して、静かに終わった。
『花火ってのは家族で見るのが当たり前だろ』
由太郎の言葉を思い出す。弥彦が、剣心と薫を「仲間」ではなく「家族」として意識し始めたのは、この夜が初めてだったのかもしれない。
☆あとがき☆
この話の花火シーンは、管理人のかなり強い妄想です(でもあまり上手く書けませんでした(T_T))弥彦にとって、極道界にいたころのお祭りは最悪の行事だったと思います。家族の中で、孤独をつきつけられ、自分はスリをしなければ生きていけず……。そんな弥彦が剣心、薫と花火を見に行くことが出来るなんて、きっと夢のように幸せなことなんじゃないかなと思いました。三人の家族話は大好きです。
作中三つのCPは、「何となく妄想」です(何それ…)
第十三幕「斉藤の忠告」
「剣心! 弥彦ぉ! 操ちゃんから手紙よ!」
朝餉の支度をしている剣心と弥彦の元へ、薫が飛び込んできた。
「薫殿。今日は早起きでござるな」
「朝っぱらからうるせーやつだな」
薫のはしゃぐ声に、剣心は笑い弥彦はあきれた。そんな二人におかまいなしに、薫は早速手紙を開いて読み始める。
『薫さーん、緋村ぁ、弥彦くん、元気ぃー?』
薫はそこまで読んで、ぷぷっと笑った。
「相変わらず操ちゃんらしいわね」
「ホント相変わらずバカ丸出しだな」
「まぁまぁ弥彦。薫殿、続きを読んでほしいでござるよ」
薫はうなずくと、また手紙に目を通す。
『もうすぐ秋です。秋と言えば紅葉! 紅葉といえば京都!』
操の満面の笑みが、三人の脳裏に浮かぶ。
「紅葉までにはまだ早いと思うぜ」
弥彦に苦笑し、薫はまた先を続ける。
『その頃、是非遊びに来てね! 御庭番衆の新しい仲間も紹介するよ。けどさぁ……』
薫が急にとまどった顔で読むのを止めたので、剣心がのぞきこんだ。
「なんかここから急に字が乱れているでござるな」
薫はうなずいて次を読む。
『最近蒼紫様ってば……そのコに夢中で……!!』
「蒼紫のヤツ、女が出来たって訳か」
ニヤリと笑う弥彦。薫は弥彦を睨むと続きを読む。
『じゃ、じゃあ、秋にねー! あっそうだ! 追伸。十本刀の……』
また驚いて止める薫。だが少しして続けた。
『瀬田宗次郎を見ました。まだアイツ、京都にいるのかも』
「宗次郎が!?」
剣心は驚いたが、ふっと笑った。
「ねぇ、秋にはみんなで京都に行きましょう」
薫はにっこり笑った。
「そうでござるな。それに……」
剣心は弥彦を見て言った。
「師匠にも、一応報告しなければな」
「そーいうもんなのか?」
剣心は、笑ってうなずいた。
「……そういえば、俺もアイツを見たような気がするぜ。斉藤」
弥彦は、ふと昨日のことを思い出した。
「うそっ! あの人火の海に呑み込まれたって……」
「いや……」
剣心は、ふっと笑った。
「さて、ご飯にするでござるか」
ガシャン、と刀を落としてしまった。あっと思ったときには、剣心に襟首をつかまれ頬を殴られる。飛天御剣流、三日目の修業である。
「剣客として刀を落とすのは絶対に許されぬ事。何度言ったら分かるんだ!」
剣心の怒鳴り声を聞きながら、すばやく刀を拾い立ち上がる弥彦。
三日目の今日も、ひたすら抜刀の繰り返し。さすがに手に負担がかかり、頭で分かっていても刀を落としてしまう。けれど、言い訳は一切許されない。それが剣心がつける修業だった。
息が切れ、かすむ目。弥彦は、ひたすら抜刀を続ける。
「ふーん。頬腫らしちゃって。さては悪いことして怒られたんだろ?」
午後の河原。昨日と同じように由太郎にのぞきこまれた弥彦は、あわてて起きあがる。
「うるせーな。修業の傷だって」
弥彦の頬に貼ってある布は、弥彦が出かけるとき、剣心がすれ違いざまにさりげなく貼ってくれた薬だった。
「剣心さんの修業って……そんなに厳しいのか?」
「……まぁ…な」
さすがの弥彦も、認めざるを得なかった。由太郎はどうもピンとこないようで、しばらく想像していたようだった。けれど、やがて違うことを思い出したらしく、肩に背負っていた布袋から鋼の細長い棒のようなものを取り出した。
「じゃーん! これがフェンシングの剣。カッコいいだろ」
「……お前、持ち歩くの、それって思いっきり俺の真似だろ」
弥彦と同じように竹刀まで背負っている由太郎をちらりと見、それから弥彦はフェンシングの剣とやらを受け取った。
「へぇ。先がとんがってねぇんだ。刃も細くて軽いんだな」
「決闘用じゃないからな。スポーツ用だよ」
「すぽーつ?」
「運動用ってこと。さっ、次はお前の番だぜ。逆刃刀見せろよ」
弥彦はとっさに弥月刀を抱えた。
「ダメだ!」
「何だとぉ!? ずるいぞ! 俺は見せたのに……!」
「知らねーよ。剣心が緊急事態の時以外は出すなって……」
取っ組み合っていた二人だったが、弥彦は急に由太郎から手を離すと、土手の上へかけていった。
「おい弥彦!?」
「斉藤!!」
弥彦の言葉に、斉藤は足を止めた。
「神谷のガキか……」
「やっぱ斉藤……と、誰?」
弥彦は、斉藤の隣りに立つ自分と同じ年頃の少年に目を向けた。
「お前こそ誰だよ」
ぼさぼさ頭の少年は、三白眼の目で弥彦をいぶかしげに見た。
「俺は神谷活心流――じゃなくって、飛天……あ、いや……」
弥彦はあわてて言葉をにごした。親しいもの以外、飛天御剣流を習っていることを教えてはならないと、剣心に言われていたのだ。
「とっ、東京府士族明神弥彦!」
久々に決まった名台詞に弥彦はちょっと得意げだったが……。
「やはりヤツに飛天御剣流を習い始めたか」
斉藤のずばりな指摘に、弥彦はうっとなった。
「面倒な仕事を増やしやがって……」
「はぁ? 何のことだよ」
「ガキのお前に説明しても時間の無駄だ。抜刀斎に話しておく。お前はヤツの指示に従え」
そうして斉藤は帰りかけたが……。
「ああ。こいつらと遊んで待ってろ。栄次」
少年を残して、斉藤は去っていった。
☆あとがき☆
操ちゃんと斉藤さんがやっと書けて楽しかったです♪
第十四幕「不穏な動き」
「あーっ? ったく、なんなんだアイツは! 生きてやがったと思ったらいきなり訳分かんねぇこと言いやがって。しかもやっぱり訳分かんねぇ三白眼のガキ残していきやがって」
弥彦はひとりキレていた。
「おいチビ。ガキとはなんだ! 俺はもう十だぜ」
栄次は弥彦を睨み付けて言った。
「なんだ。なら全員同い年じゃん。つーか弥彦、あのさっきの感じ悪そうな警官誰?」
「そっか。お前は斉藤のことも知らなかったんだよな」
弥彦は由太郎に、斉藤について知っている限りを話した。栄次も、初めて聞く話が多かった。それから、栄次は自分のいきさつを二人に話した。故郷の村で両親と兄が殺されたこと。そこで斉藤と会い、今はとりあえず斉藤の家に住んでいるということ。最近斉藤が帰宅したので、たびたび斉藤に連れられて養子先を探しているということ。
「けど、ダメなんだよな。話つけてから行くのに、会ったらみんな断られちまってよ」
栄次はふぅとため息をついた。
「その仏頂面がいけないんじゃねーの? もっとこう形だけでもいい子そうに笑ってさぁ」
「そーいう猫かぶりが出来るのはお前だけだって」
弥彦は由太郎に呆れはてた。
「ははん。さては俺が薫さんに気に入られて由太くんって呼んでもらってるのがうらやましいんだろ」
由太郎はにししと笑った。弥彦はブチンとキレた。
「うるせーてめーなんか……栄次?」
突然立ち上がった栄次に、弥彦はケンカを中断して栄次を見上げた。
「お前らは、家族いるのか?」
突然、栄次はぼそりと聞いた。
「……俺は親父と爺や。それにフェンシングの先生がいるよ」
由太郎は弥彦をちらりと見ながらも、正直に答えた。
「ふぅん。お前は?」
栄次に見つめられた目を、弥彦はなんとなくそらして考える。
「俺は……神谷道場の居候だからな。薫っていう道場主と、剣心っていう俺と同じ居候と、三人で住んでる」
「……ふぅん」
栄次は、その珍しい組み合わせに少し興味を持ったようだった。
「けどよ、お前も大変だよな。一時的とはいえ、あの斉藤と暮らすなんてよ。なんなら、次に当たる家には付き合ってやってもいいぜ。養子話がうまくいくように、なんとかしてやらぁ」
「それがアイツ、もう面倒になったから、自分で勝手に探せってさ」
栄次はまたふぅとため息をついて、腰を下ろした。
「はぁ? なんだそりゃ! 何考えてるんだ斉藤のヤツ!」
弥彦は、ふたたびキレていた。
夕方弥彦は神谷家に戻り夕食を済ませると、剣心は大事な話があるといい弥彦を向かいに座らせた。そばで、薫は針仕事をしている。
「お主に話しておくことがあるでござるよ。薫殿は先程斉藤が来たとき聞いたと思うが……」
薫は軽くうなずくと、静かに針仕事を続ける。
「斉藤のヤツ、もう来たのか?」
「ああ。今日は警官としてな」
「それで?」
弥彦は、真剣に剣心を見つめた。剣心は、一息つくと弥彦に語り始める。
「拙者が抜刀斎であるが故、今まで数々の戦いに巻き込まれてきたでござろう?」
「まぁ、そうだな」
弥彦はうなずいた。
「今までは、敵は拙者が目的だった。けれど、これからはそうはいかないでござる。拙者の跡を継ぐお主をつぶそうと狙ってくる輩も出てくるでござるよ」
「……それで、飛天御剣流や逆刃刀を隠すようにって言ったのか」
剣心はうなずくと、続けた。
「けれどもう既に、情報が漏れているらしい。斉藤は、それを知らせにきたでござるよ。何か不穏な動きを感じると。もし事件が生ずれば仕事が増えるからどうにかしろと言っていたでござる」
「ふぅん」
そこで弥彦も剣心も、ついでに薫も不機嫌な顔になった。思い切り見下した斉藤の顔を剣心と薫は思いだし、弥彦は想像したからである。
剣心は、気を取り直して続けた。
「まだ先の話だとは思っていたが、そうでもないかもしれぬ。いいでござるか弥彦。これからは、薫殿の部屋ではなく、拙者の部屋で寝るでござるよ。布団は弥彦が寝る方がふすま側。そのほうが、寝込みを襲われたとき拙者と敵との間合いが取りやすいでござる」
「……分かった」
守られることを素直に受け入れるのに少し抵抗を感じたが、けれど自分の実力を過信していない弥彦は、しぶしぶ返事をした。
「寝るときには逆刃刀は枕元に置くこと。そうそう、今日から毎日刀の手入れがしっかり出来ているか見るでござるから、後で拙者の部屋に見せに来るでござるよ」
「ああ」
弥月刀を手に入れてから、毎晩手入れをかかしたことがなかった弥彦。大事な刀への手入れには自信があった。
「それと弥彦……」
剣心は、改まって弥彦を見つめた。
「不殺の剣を習うということは、自分をも不殺ということでござる。今までの飛天御剣流とは訳が違う。並大抵の努力では会得は出来ぬでござるよ」
「んなこと分かってるって」
弥彦は当然のごとく答えた。
「分かっているなら、修業はもっと真剣に受けろ。修業中一切の甘えは許さぬ」
「剣心……俺……」
弥彦は、決まり悪そうに薫をちらりと見る。
「薫殿、済まぬがお茶を頼むでござる」
「うん」
薫は、なにか察したように席を外す。
「俺……甘えてなんか……」
うつむく弥彦に、剣心はそっと弥彦の腫れた頬に手を当てた。
「何故ぶたれたか、分かるか?」
低い、剣心の声。
「刀を、落としたから……。けど、手にガタがきてて、握りづらくて……」
「やはりな……」
剣心の言葉に、弥彦は混乱して剣心を見上げた。
「修業中、お主はなんとかそれを口にせず我慢しているが、実はそんな風に思っている。弥彦。それが甘えだ」
弥彦は、はっとした。
「手の豆がつぶれていても、三日間抜刀しつづけても、まだお主は箸だって握れるはず。剣を落としたのは、手にガタがきているから仕方ないと自分を甘やかしたからでござるよ。お主を殴ったのは、確かに刀を落とし剣客として致命的なことをしたから。けれどそれ以上に、甘えを見せたからでござるよ」
剣心の鋭い目。弥彦は、少し考えて答えた。
「……ごめん」
弥彦は、うつむいたままぼそりとあやまった。剣心はしばらく弥彦の姿を見つめた後、にっこり笑った。
「では、逆刃刀を手入れしてくるでござるよ」
うつむいたままうなずいた弥彦は、部屋へかけていった。
「剣心、大事な弟子へのお説教は終わった?」
薫はいたずらっぽく笑い、剣心の横にお茶を置いた。
「ああ。ありがとうでござるよ。薫殿」
薫はにっこり笑い、開け放たれた縁側から外を眺めた。月明かりが綺麗な夜である。
「秋の、気配がする……」
「ああ。もうすぐ……。秋はいい季節でござるな」
剣心と薫は、晩夏のひとときを二人静かに過ごした。幸せに、けれど少し不安をかかえながら……。
☆あとがき☆
作中の、寝込みを襲われたとき奥の方が間合いがとりやすい、というのは、全くのデタラメです(爆)
作者(管理人)は、原作にはなかった『るろうに剣心』の秋を見たかったので、自分で書きます。原作でも見たかったです。
次回、斉藤の妻、時尾さん登場です。
第十五幕「斉藤家と栄次」
「おはよう栄次さん」
「おはよう……」
朝起きてきた栄次に、つつましやかに笑いかけたのは、斉藤の妻である時尾だった。まだ早い時間だというのに、斉藤宅の居間にはすでに手の込んだ朝食が並んでいる。そのお膳の前に、悠然と座り新聞を読んでいるのは、斉藤であった。栄次は、自分のお膳の前に座ると、斉藤を見る。
「何だ」
「牙突と飛天御剣流ってどっちが強いんだ?」
「……情報源は神谷のガキか」
突然の栄次の質問だったが、斉藤は変わらぬ態度で答える。栄次は、それ以上聞くのをあきらめる。この男が質問にまともに返事を返さないことなど、しょっちゅうあることだからだ。
「何で俺を養子へやらないんだよ」
栄次は質問を変えてみる。
「面倒になっただけだ。なんども言わせるな」
斉藤は、新聞に目を通したまま。
「じゃあ……俺が勝手に身の振りを考えて出ていってもいーんだな」
「……お前がそうしたいなら構わんが、その前に相談しろ。第一、ガキのお前が簡単に決められることじゃないだろう。下手な行動をとられると、かえって迷惑なんでな」
斉藤はやっと新聞から目を離すと、時尾に目を向けた。
「時尾。茶を頼む」
「はい」
時尾は優雅な手つきで急須に茶葉を入れ、湯を注ぎ、湯飲みにしずしずと注いだ。斉藤の前に、静かに置く。斉藤は、一口飲んだ。
「じゃあ……!」
栄次が呼びかけたのと斉藤が立ち上がったのは、同時だった。
「じゃあ俺が……ずっとここにいたら……、どうすんだよ……」
「……構わんさ」
斉藤は背を向けたまま答えると、玄関へ出た。
「いってらっしゃいませ」
時尾は三つ指をついて、見送りの挨拶をした。
「ああ」
斉藤は、時尾の愛妻弁当を持ち出かけていった。
「さあ栄次さん。朝ご飯にしましょう」
時尾はにこやかに笑い、栄次の両肩を優しく包んだ。小さめの体に整った顔。控えめに化粧をした気品のある女性である。
栄次は朝食をとりながら、一緒に膳を囲む時尾に話しかけた。
「なぁ、アイツにああいう風に言われると、俺困るんだけど……」
時尾は、優しく栄次を覗き込んだ。
「あの人はいつもああなのよ。だけど、あなたが来てから、とても会話が増えたわ」
「あれで?」
「ええ。それに……」
時尾はくすりと笑うと、そっと栄次を抱きしめた。
「私も、心の中がとてもあたたかいの。ねえ栄次さん。あなたさえよかったら、ここにずっといてくれないかしら。あの人も賛成してくれているし」
「賛成って、あれで?」
栄次は、さっきの『構わんさ』という一言を思い出した。
「ええそうよ。あの人があそこまで言うなんて、大賛成ってことなのよ。養子に出すのをやめたのも、だからなの」
「アイツがそう言ったの?」
時尾は首を振った。
「いいえ。でも分かるわ。夫婦ですもの……」
時尾は全てを見透かしたように微笑むと、いったん抱きしめていた栄次を離し、その両肩に手を置いた。
「栄次さん。考えてみてくれないかしら。うちの養子になること。つまり……」
時尾は、栄次の目をじっと見つめる。
「私たちの子供になるの。あの人をお父さんって呼んで差し上げて、私をお母さんって」
栄次の胸はとくんとした。が、その後襲ってきた訳が分からない焦燥にかられ、家を飛び出した。
「っくしょう剣心のヤツ……いつまで抜刀の練習させる気なんだよ……」
昼食後、弥彦がぶつぶつ言いながらいつもの日課で河原へ行くと、めずらしく栄次が先に来ていた。栄次と出会って約一週間。由太郎を含めた三人は、毎日なんとなくここで過ごすようになっていたが、大抵一番先に来るのは弥彦だった。
「緋村は抜刀斎なんだろ。抜刀の練習させるのは当たり前じゃねーか。アイツだって馬鹿みてーに牙突ばっかやってるよ、庭で」
栄次は寝っ転がりながら、つまらなそうに言った。
「抜刀の練習は当然! んなこたー百も承知だ!」
「自分で文句言ってたんだろ」
いきり立つ弥彦に、栄次はため息をつく。
「けどお前に言われると、なんか無性に腹立つぜ! ……ってか、斉藤って庭で牙突の稽古してんのか?」
「ああ。夜帰ってくるとな。なんか異様に殺気立ってる感じだぜ」
「……突かれないように気をつけろよお前」
弥彦は、かなり本気で忠告した。栄次は、寝ころんだまま横に座った弥彦の方を向く。
「なあ弥彦。お前から見てアイツってどんな感じだ?」
「斉藤か? すっげぇやなヤツ。それに剣心の敵だしな」
「ふうん……」
それきり、栄次は黙ったまま空を見上げていた。
「なぁ栄次。お前、どーすんだよ。このまま斉藤の家にいると、牙突でやられないまでも性格ひねくれること間違いなしだぜ」
弥彦の言葉に、栄次はなんとなくひっかかるものがあった。
「アイツ、そんなに悪いヤツなのか? 確かに口悪いけど、一応警官だし。緋村なんか、お前んとこの女のヒモだろ」
その瞬間、弥彦は栄次の襟首をつかんだ。
「剣心の悪口言うやつぁ、この俺が許さねぇ! 剣心はちゃんと家事こなしてんぞ!」
「……さっき悪口言いながら登場したくせに」
栄次の言葉に弥彦はうっとなって、手を離した。けれど栄次は、そのまま弥彦を見ていた。
「何だよ……」
不思議そうな弥彦を見ながら栄次は思った。さっき自分が斉藤を馬鹿にされて感じた気持ち。今の弥彦と同じなのではないかと、一瞬思った。
「なぁ弥彦。今日これからお前んちに行ってもいいか? 夕飯も食ってっていいか?」
「え? 別にいいけど……どうしたんだよ急に」
栄次にも、よく分からなかった。けれど何故か、自分が悩んでいた答えがそこにあるような気がしたのだった。
☆あとがき☆
時尾さんのキャラを勝手に決めてしまいましたが(史実無視です…)違う! と思われた方ごめんなさい!
第十六幕「お母さんと父さん」
「お帰りでござる弥彦。おろ? 栄次殿。久しぶりでござるな」
二人が道場へ戻ると、洗濯物を取り込んでいた剣心が優しく出迎えた。
「ああ」
栄次は素っ気なく答えたが、新月村で剣心に慰めてもらったあの一件を思い出し、少し照れた表情を見せた。
「剣心。今日はこいつと家で遊んでもいーだろ」
「ああ」
剣心が笑顔でうなずくと、稽古を終えた薫がやってきた。
「薫。悪ぃけど、こいつ夕飯食ってくって言うから、一食多く作ってくんねーか?」
「いいわよ。弥彦のお友達? 初めまして。私は神谷薫。あなたは?」
「み、三島栄次」
栄次は薫に覗き込まれ、少し顔を赤くした。
「ったく由太郎といい栄次といいどいつもこいつも……」
弥彦は呆れながら栄次をひっぱり、部屋へ連れ込んだ。
「おかわりっ!」
弥彦は勢いよく薫に茶碗を突きだした。
「おかわりはいいけど、もっとゆっくり食べなさい? お腹壊すわよ」
「分かってるって」
薫に茶碗を渡した弥彦は、栄次にそっと耳打ちする。
「お前夕飯食いに来たのは失敗だったな。朝と昼なら上手い剣心の飯が食えんだけど、夕飯だけは薫が作ってんだよ」
その瞬間、薫は弥彦のお膳にガチャンと茶碗を置いた。
「聞こえてんのよ弥彦! 悪かったわねぇ料理が下手で」
「薫の料理にケチ付けたことなんか一回だってねーだろ。ただ剣心の方が上手いって言っただけで……」
「それがケチつけてるって言ってんのよ!」
二人が取っ組み合いになりそうなのを、剣心がまぁまぁとしずめる。
栄次は、その様子をただぼんやり見ていた。
「済まぬな栄次殿。落ち着かなくて。うちは、いつもこんな調子でござるから」
剣心は苦笑した。
夕食後、弥彦と栄次は家の屋根に登り、並んで座った。
「お前んちって、ずいぶん賑やかなんだな……」
星空を見上げながら、栄次はつぶやいた。
「まぁな。お前んところは、なんか陰気そうだな」
弥彦はそう返したものの、何か思い悩む表情の栄次をじっと見つめる。
「……そうでもないぜ。アイツもなんだかんだ言って、話しかければごちゃごちゃ返事返すし……。それにアイツの奥さんすっげぇ優しいぜ。意外だろ」
「ああ意外だ」
弥彦は即答した。栄次は、何故かほっとしたように笑う。けれど、すぐに真顔に戻って、空を見たまま弥彦に言った。
「今日あの人がさ。俺のお母さんになりたいって、そう言ったんだ。そんでもって、アイツもお父さんになることに大賛成なんだって、そう言うんだ」
弥彦は、黙ったまま栄次を見つめていた。
「俺、うれしかったんだ。だって親父もおふくろも兄貴もみんな死んで、さみしかったし……。けどさ、そーしたら親父やおふくろはどー思うのかな? 兄貴も……」
二人は、しばらく黙り込んだ。
「お前にとって、緋村と薫さんは何なんだ?」
栄次の突然の質問に、弥彦はとまどう。けれど少し考え、やがてつぶやく。
「よく、分かんねぇ。けど……」
弥彦は、ここから確信を持って続ける。
「剣心は、父上じゃねぇ。薫は、母上じゃねぇ」
栄次は、弥彦を見つめる。
「俺の父上は、障義隊で散っていった誇り高い父上だけだ。母上は、俺を育てるために病で死んでいった優しい母上だけだ」
屋根の上は、またしんとなる。しばらくして、また弥彦が口を開く。
「けどさ、それは俺の場合だ。俺は俺。お前はお前」
栄次は、弥彦を食い入るように見つめる。
「剣心と薫は父上と母上じゃねぇけど、やっぱ特別だ。上手く言えねぇけど……。こないだの夏祭りみたいに花火でも上がってりゃあ、上手く説明できたかもしれねぇけどさ」
弥彦は、空を見上げる。
「俺がそう思ってても、父上と母上は、きっと怒らないと思うんだ。親ってのは、とにかく子供が幸せなのが一番うれしんだよ。だからさ……」
弥彦は、栄次に向き直り、その肩をポンと叩いた。
「お前がうれしかったんなら、アイツらの養子になれよ。父さん、母さんって呼んでやったっていいんじゃねーか? お前の親父やお袋や兄貴も、きっと誰も怒らねーと思うぜ」
またしばらく沈黙が続いたが……。
「そっか……」
栄次は、それだけ答えた。いや、それだけ答えるのが精一杯だった。両親と兄への思い、斉藤一家、それに弥彦の言葉に胸がいっぱいで……。
その時、弥彦は急に立ち上がった。
「おい! あれ斉藤じゃねーか? 一緒にいる女、あれが時尾?」
栄次は道場の玄関に二人がいるのを確認すると、急いで下りていった。
「済まぬでござるよ時尾殿。家には言ってきているものと思いこんでいて……」
玄関先で、剣心は時尾にペコペコ頭を下げていた。
「おい抜刀斎。俺への謝罪はないのか」
「ないでござるな。お前はたまたまそばを通りかかっただけでござろう」
剣心は、急に真顔でぼそりと答える。
「俺は一応アイツを預かっている身なんだ。勝手なことをされると困るんだよ」
斉藤は、不機嫌そうに剣心を見下した。
「勝手なのはお前のほうだ斉藤。中途半端に栄次に期待を持たせ、いまだ養子に取らずのはあまりに――」
「ほう。流浪人のお前によくそんなことが言えるな」
その様子を影で聞いていた薫、弥彦、栄次だったが、たまらず薫は飛び出していった。
「剣心はもう、どこへも行かないわ!」
薫の目には、涙がたまっていた。それを見た弥彦は、思わず自分も飛び出していく。
「そーだろ。剣心」
睨むように、剣心を見上げ問う弥彦。
「確かに、私たちは誰も血がつながってないし、剣心と私は……でも、でも――」
「家族でござるよ」
剣心は穏やかに、けれどキッパリと言った。
「薫殿も弥彦も、共に暮らす大事な家族でござる。そして、これからも拙者が守っていく。だからもう、どこにも行かぬでござるよ」
「剣心……」
薫は、口に手を当てて、涙を流した。弥彦は、ほっと安堵の息をもらした。
「……俺も、どこにも行かねぇ」
いつの間にか、栄次が玄関先に姿を現していた。
「いーだろ、お…お母さん」
栄次がおどおど言うと、時尾は優しくうなずき栄次を抱きしめた。少しして、栄次は時尾から離れ、斉藤に言った。
「じゃ、そーいうことだから。……父さん」
「構わんと言ったはずだ」
斉藤はいつものように仏頂面だったが……その目に宿す光に少しだけあたたかさが感じられた気が栄次にはした。
そうして、三人は帰っていった。栄次は帰り際、弥彦を振り返り、照れた顔を見せた。
「それにしても、時尾には『お母さん』で、斉藤には『父さん』か。なんか気持ち分かるぜ」
「同感でござる」
「当然の結果よね」
剣心たち三人の夜の話題は、それで持ちきりだった。斉藤は、三回くしゃみをしていた。
☆あとがき☆
斉藤一家編完結です。斉藤さんの息子になると結構大変だよ栄次くん・笑
前ページへ 次ページへ
ご感想、日記のコメント欄か 掲示板 に書き込みしていただきますと、とても励みになります。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-
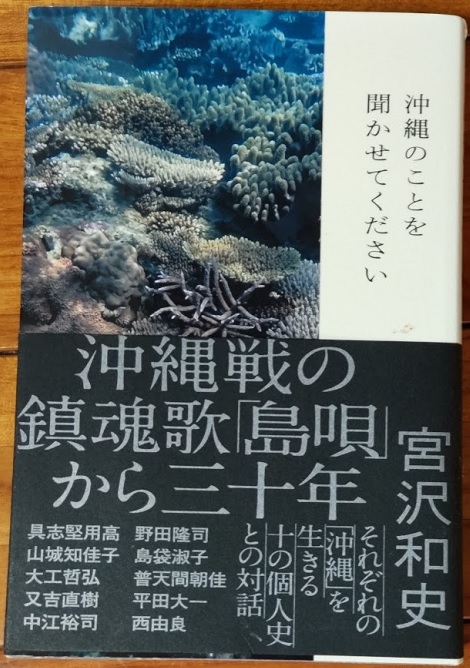
- 最近、読んだ本を教えて!
- 葛藤があったからこそ理解あり
- (2024-11-30 10:46:15)
-
-
-

- この秋読んだイチオシ本・漫画
- 最近読んだオススメ漫画紹介!11/30
- (2024-11-30 08:22:17)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- 悪役聖神官ですが、王太子と子育て恋…
- (2024-10-04 21:52:45)
-
© Rakuten Group, Inc.