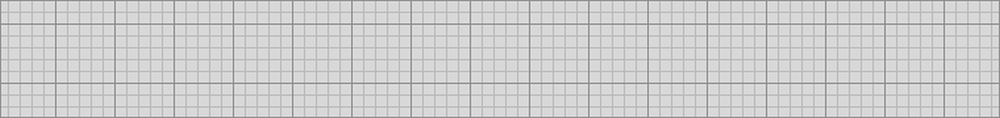全5019件 (5019件中 1-50件目)
-
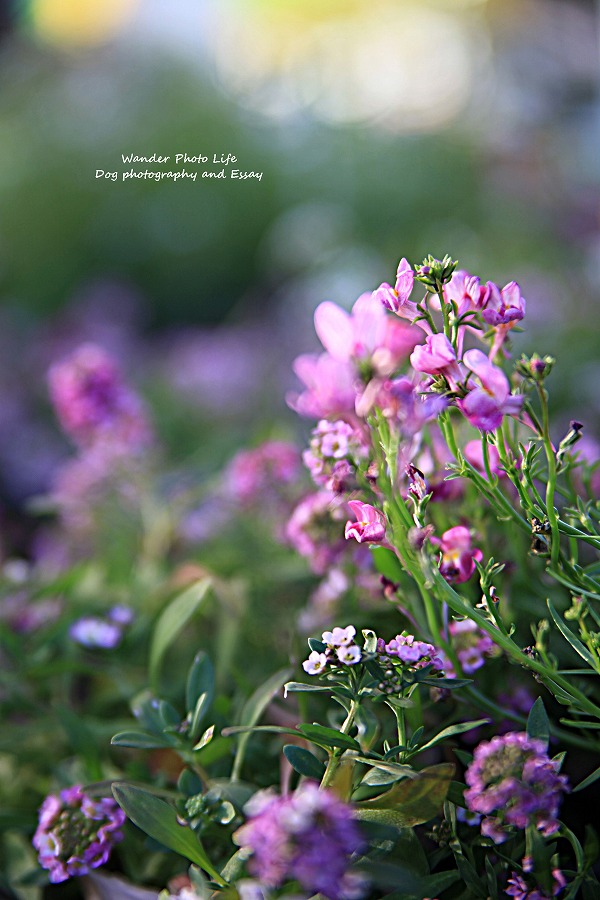
源氏物語〔21帖 乙女 1〕
源氏物語〔21帖 乙女 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語21帖 乙女 (おとめ) の研鑽」を公開してます。春になって女院の一周忌が過ぎ、官人たちが喪服を脱いだ。その流れで四月の更衣の時期になったので、初夏の華やいだ雰囲気が満ちていた。しかし、前斎院は依然として寂しく、退屈な日々を過ごしていた。庭の桂の木の若葉が立てる香りにも、若い女房たちは、宮がまだ斎院であった頃の加茂の祭りのことを懐かしんでいた。そこへ源氏から、「神の御禊の日も今は静かでしょう」と挨拶を伝える使いがやってきた。「今日はこんなことを思いました」 かけきやは川瀬の波もたちかへり君が御禊の藤のやつれを(賀茂の川波がふたたび寄せてきて、あなたが喪服をぬぐみそぎをなさろうとは)紫の紙に正しい立文の形で書かれた手紙が、藤の花の枝に結びつけられていた。斎院は少し感傷的な気分の日だったので、返歌を書いた。 藤衣きしは昨日と思ふまに今日はみそぎの瀬にかはる世を(藤色の喪服を着たのは、昨日のことのように思っていましたのに、今日はもう御禊とは、何と時の移り変わりの早い世でしょう)「儚いものだと思います」それだけが書かれた手紙を、源氏はいつものように熱心に眺めていた。斎院が父宮の喪が明けて服喪を解く際にも、源氏から立派な贈り物が届いた。女王は、「こういうものを受け取るのはよくない」と言っていた。求婚の言葉が添えられているなら断ることもできる。しかし、長い間、公然と贈り物を送り続けてきた源氏の厚意を考えると、返すわけにもいかず、女房たちは困っていた。女五の宮の方にも同じように物資的な援助を続けていたので、宮は源氏を深く愛するようになっていた。「源氏の君というと、いつも美しい少年のイメージだけれど、こんなに大人らしい親切を見せてくれるなんて。顔がきれいなだけじゃなくて、心までも普通の人とは違って立派にできているのね」そう褒めるのを聞いて、若い女房たちは笑っていた。
2025.02.17
コメント(0)
-

源氏物語〔20帖 朝顔 10 完〕
源氏物語〔20帖 朝顔 10 完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語20帖 朝顔 (あさがお) の研鑽」を公開してます。朝顔の君との関係が冷たくなっていく中で、源氏の心には諦めと未練が入り混じっていた。朝顔の君は、源氏の思いを受け入れず、一貫して慎み深く距離を保ち続けた。何度も文を送っても、変わらぬそっけない返事ばかりであった。ある日、源氏はふと、彼女のもとへ訪れてみようと決意する。冬の夜の冷え込みは厳しく、庭の草木は霜に覆われていた。月の光が淡く庭を照らし、静寂の中にかすかな風の音だけが響く。朝顔の君の屋敷に着いた源氏は、門の前でしばらく立ち止まり、これまでのやり取りを思い返していた。彼女の強い意志を知りつつも、諦めきれない心がある。ついに使者を通じて訪問の意を伝えたが、返事は冷ややかだった。「このように何度も訪れられては、世間の噂も気になりますし、私の心の平穏も乱れます。どうかお帰りください」。それでも源氏はしばらく待ち続けた。しかし、夜の深まりとともに、迎え入れられる気配はなく、ただ静寂だけが広がっていた。やがて、帰らねばならぬことを悟った源氏は、思いを込めた和歌をしたため、そっと置いてその場を後にした。帰路につく馬車の中で、彼は物思いに沈み、朝顔の君との縁がついに尽きたことを実感した。二条の院に戻ると、冬の夜の冷たさとは異なる、心の内側からくる寂しさが胸を締めつけた。紫の上のもとに行けば、きっと優しく迎えてくれるだろう。しかし、それだけでは埋められない何かがあった。彼はしばらく庭に佇み、遠くに霞む月を見上げた。凍てつく風が衣の裾を揺らし、思いの深さが胸に迫る。朝顔の君への未練を断ち切ることはできず、しかし、それを追い続けることも許されない。そうして源氏は、静かに夜の闇へと溶け込んでいった。(完)明日より21帖 乙女(おとめ) を公開予定。
2025.02.16
コメント(24)
-

源氏物語〔20帖 朝顔 9〕
源氏物語〔20帖 朝顔 9〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語20帖 朝顔 (あさがお) の研鑽」を公開してます。 かつて解官され、源氏に付き従っていた蔵人も今では旧の地位に戻り、さらに五位の位を得ていた。彼が源氏の太刀を取りに戸口へ来た際、御簾の中に控えている明石を察して挨拶を交わした。彼は、「以前のご厚情を忘れません。しかし、今朝の山風は浦風を思わせ、直接お伝えする機会がなく残念に思っております」と述べた。明石はこれに対し、「山に囲まれたこの地は、海辺の頼りない住まいと変わらぬ寂しさを感じます。松も昔の友ではなくなったと寂しく思っておりましたが、かつての知己がいることに力を得ました」と答えた。源氏の美しさと貫禄が盛りを迎えたこの場面は、彼の気高さを象徴するものであり、彼を取り巻く人々の感嘆の目と明石の深い心情を映し出している。「つまらない隠れ家を見つけられたのは、本当に残念だ」源氏は車の中で繰り返しそう言っていた。「昨夜は月が見事だったから、嵯峨に同行できなかったのが悔やまれる。今朝は霧の濃い中を来た。嵐山の紅葉はまだ早いようだ。秋草はちょうど見ごろだな。ある朝臣はあそこで小鷹狩を始めて、今はいっしょに来られなかったが、どうする?」若い人はそんな話をしていた。「今日はもう一日桂の院で遊ぶことにしよう」源氏がそう言うと、車はその方向へ進んだ。桂の別荘では急いで客をもてなす準備が始まり、鵜飼いも呼ばれた。人夫たちの高い声が聞こえるたびに、源氏は海岸にいたころの漁師の声を思い出していた。大井の野に残った殿上役人が、萩の枝に目印の小鳥をつけて後を追ってきた。杯が何度も巡った後、川辺を散策することを心配されながらも、源氏は桂の院で一日中遊び暮らした。夜になると月が明るく上り、音楽の合奏が始まった。弦楽器は琵琶や和琴だけで、笛の名手たちが伴奏をした曲は秋の風情にぴったりだった。
2025.02.15
コメント(26)
-

源氏物語〔20帖 朝顔 8〕
源氏物語〔20帖 朝顔 8〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語20帖 朝顔 (あさがお) の研鑽」を公開してます。源氏は子供の愛らしい様子に心を動かされ、頭を撫でながら「見ないでいることがこんなにも辛いとは、自分の情愛が浅ましく思えてならない。だが、どうすればいいのだろう。ここは遠い場所だ」と独り言のように言った。乳母はそれを聞き、「遠い田舎で何年も会えないより、たまさかしかお迎えできないことになる方が、皆にとってつらいものでしょう」と返事をした。その時、姫君が小さな手を前に伸ばし、立っている源氏に向かって歩もうとする姿を見て、源氏はその愛らしさに膝を折ってしまった。さらに源氏は、「私には心を休める日がない。たとえ短い時間でも別れるのは耐え難いものだ。奥さんはどこにいるのだろう?なぜここに来て別れを惜しんでくれないのだろうか。そうすれば、せめて少しは心が慰められるかもしれないのに」と嘆いた。これを聞いた乳母は微笑みながら明石の元へ行き、源氏の言葉をそのまま伝えた。しかし、明石は二日間の逢瀬の喜びが尽き、いよいよ訪れた別れの時に心を乱しており、呼ばれてもすぐには出てこようとしなかった。その様子を見て源氏は、彼女が高貴な振る舞いを見せすぎているのではないかと感じた。しかし女房たちに促され、ようやく明石は几帳の陰に控え、顔を隠しつつも優雅に振る舞う。その立ち居振る舞いには気品があふれ、しかも柔和な美しさが感じられ、この人はまるで内親王のように気高く見えた。源氏は几帳の垂れ絹を少し引き、親しげに語りかけた。出発の際、源氏が一度振り返ると、冷静にしていた明石もこの時は顔を見せて彼を見送った。その瞬間、源氏の姿は一段と美しく見え、その気高さに明石をはじめ周囲の人々も感嘆していた。この場面にはまた、源氏と行動を共にする若い役人の姿もあった。
2025.02.14
コメント(22)
-

源氏物語〔20帖 朝顔 7〕
源氏物語〔20帖 朝顔 7〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語20帖 朝顔 (あさがお) の研鑽」を公開してます。「住み慣れた人が帰ってきても、清水だけは昔のままの主人のようだ」と歌を詠むように語る尼君に、源氏は心の中で感銘を受けた。その後、源氏は御堂に赴き、普賢講や念仏三昧の法会、堂の装飾や仏具製作の指図を行い、月明かりの中を川沿いに山荘へ帰った。感傷的な気分に浸る源氏に、明石の君が琴を差し出す。琴は形見として残されていたもので、源氏は懐かしさに駆られ弾き始めた。その音は、昔の夜に戻ったかのように心に響いた。「契りしに変わらぬ琴のしらべにて絶えぬ心のほどは知りきや」そう源氏が詠むと、明石の君は答えた。「変わらじと契りしことを頼みにて松の響に音を添へしかな」明石の君の美しさはかつて以上に輝きを増していた。源氏は彼女を永久に離れがたい存在と感じ、姫君を見つめる目も離せなかった。姫君の愛らしい仕草に、源氏は心を奪われ、こう思った――この子を二条の院で育て、大切に守れば、将来の肩身の狭さを救うことができるだろう、と。しかし、明石の君を引き離すことへの哀れみが口を閉ざし、涙ながらに姫君を見つめるばかりだった。姫君は初め恥ずかしがっていたものの、今では源氏によく懐き、甘えて近寄ってきた。その愛らしい笑顔は、源氏にとって何よりも幸福な光景で、抱かれた姫君の姿は、類い稀な幸運に恵まれた未来を予感させるものだった。三日目には京へ帰ることが予定されていた源氏は、朝遅くに起き、この山荘から直接京に戻るつもりでいた。しかし、その朝、桂の院には高官たちが多く集まり、この山荘にも殿上役人が多数迎えに訪れた。源氏は装束を整えながら、「こんなに大勢の人に見られるとは、決まりが悪いことだ。この家は、あなた方が見て楽しめるような場所ではないのに」と口にしつつ、彼らと共に山荘を出発する準備を進めた。その一方で、源氏はこの地にいる女のことが心に引っかかり、簡単には出発できない様子を見せていた。彼が戸口でためらっていると、乳母が姫君を抱いて現れた。
2025.02.13
コメント(23)
-
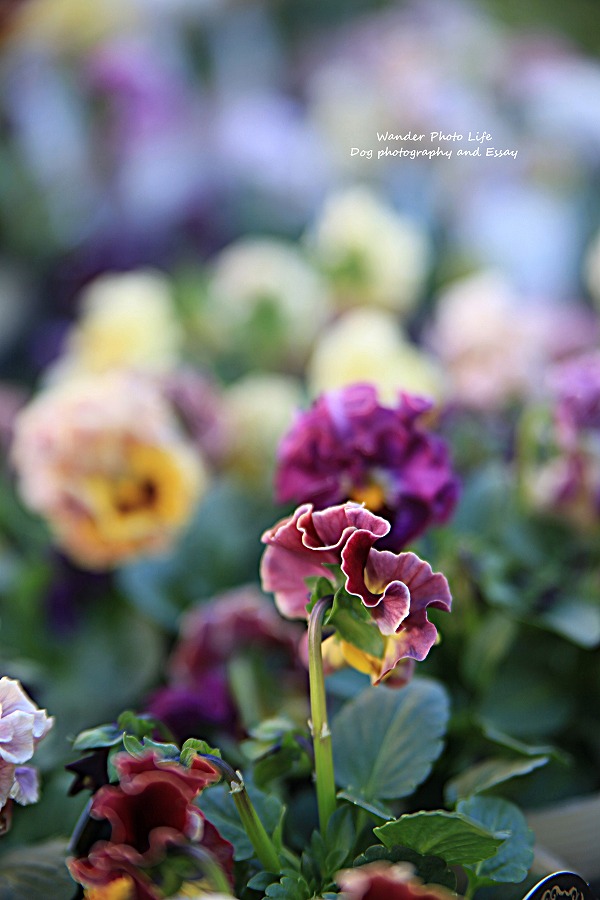
源氏物語〔20帖 朝顔 6〕
源氏物語〔20帖 朝顔 6〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語20帖 朝顔 (あさがお) の研鑽」を公開してます。源氏と尼君、明石の君、姫君、それぞれの立場や想いが繊細に表現されていて、特に源氏の感傷的な心情が巧みに描かれており、琴を弾く場面や、姫君への愛情が溢れる瞬間など、まさに源氏物語の持つ幽玄な美しさが感じられる。「ここに永久に住むわけではありません。いつか立ち去るとき、どれほど名残惜しく、苦しい思いをすることでしょう」と語り、過去の話を振り返っては涙を流したり、笑ったりした。そのような素直で親しみのある姿に、源氏はひときわ美しく見えた。その様子をのぞき見ていた尼君は、老いも物思いも忘れ、微笑んだ。 源氏が東の渡り廊下の下を流れる水の流路を変える指図をしている姿を目にすると、くつろぎながらも優雅なその様子が、尼君には一層うれしく思われた。廊下の縁には仏の閼伽(あか)の具が置かれており、それを見た源氏は尼君の部屋であることに気づいた。「尼君はこちらにいらっしゃいましたか。だらしのない姿をお見せして失礼しました」そう言って直衣を取り寄せ、着替えた源氏は几帳の前に座り、尼君に感謝の意を述べた。「子供が健やかに育ったのは、仏様が尼君の祈りを聞き入れてくださったおかげだと思います。明石で一人お残りになりながら、私たちのことを気遣ってくださったことがどれほどありがたかったか――心から感謝しています」尼君は涙ながらに答えた。「捨てたはずの世に戻ってこのように苦しむ日々を、こうしてご理解いただけるだけでも、生きていてよかったと存じます」また、明石の君の出自を気にしつつも、「二葉の松が頼もしい日を迎えた」と未来への期待を口にするその姿は、品の良さが際立っていた。源氏は山荘の旧主である親王の話を交えながら、昔を懐かしんで語った。新たに整えられた水の流れは、彼らの語らいに調和するかのように高い音を立てていた。
2025.02.12
コメント(23)
-

源氏物語〔20帖 朝顔 5〕
源氏物語〔20帖 朝顔 5〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語20帖 朝顔 (あさがお) の研鑽」を公開してます。順風に恵まれ、一行は予定通り京へ到着。車に乗り換え、人目を避けつつ大井の山荘へ向かった。山荘は風雅に整備され、大井川がかつて眺めた海を思わせるように目の前を流れていたため、環境が変わったとは感じにくかった。しかし、明石の日々がまだ身近に感じられ、時折悲しみが胸をよぎった。新たに増築された廊下や引き込まれた水流は美しく、住まいとしての完成を予感させた。源氏の命を受けた家司が、一行の到着に合わせて饗応を用意したが、源氏自身の訪問は遅れがちであった。明石の君は寂しさを紛らわせようと、源氏から贈られた琴の弦を鳴らしてみた。その音に荒々しい松風が調和するように響き、過ぎた日々の記憶が甦った。数日後、ようやく訪れた源氏は、夕暮れの頃、大井を訪問した。明石の時代以上に美しい直衣姿で現れた彼の姿に、長い間の寂しさが一瞬で慰められた。源氏は明石の君との間に生まれた子供を見て感動し、その美しさに深い愛情を抱いた。無邪気な笑顔を見せる幼子は、源氏にとってこの上なく愛おしい存在であった。「ここではまだ遠すぎる。私が準備した場所へ移られるほうがよい」と源氏は明石に語りかけたが、明石の君は「この田舎者らしさを少しでも改めてから」と控えめに答えた。それを聞いた源氏は彼女の心を思いやり、将来の約束を改めて固く誓った。その夜は語り明かし、源氏は翌朝まで明石を労わり続けた。その後、山荘の修繕箇所について指示を出した源氏は、近隣の領地の人々を集め、庭の草木の手入れなどを進めさせた。彼らの働きによって山荘はより住みよい場所となり、明石での日々の名残が少しずつ薄らいでいくかのようであった。流れの中に立っていた石が皆倒れ、ほかの石と混ざり合ってしまったらしい。この庭は復旧や整備をすれば興趣のあるものになるだろうが、そうした手を加えることが、かえって後に心残りを生むのではないかと源氏はそんなことを思っていた。
2025.02.11
コメント(23)
-

源氏物語〔20帖 朝顔 4〕
源氏物語〔20帖 朝顔 4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語20帖 朝顔 (あさがお) の研鑽」を公開してます。一方で、明石の君は、運命に導かれてこの地を離れることへの寂しさに胸を痛めていた。父である入道を一人残すことも苦しみであり、なぜ自分だけがこのような悲しみを背負わねばならないのかと嘆き、朗らかな運命を持つ人々を羨ましく思っていた。しかし、両親にとっては、娘が源氏に迎えられて上京することが長年の夢であり、それが叶う喜びもあった。しかし同時に、娘との別れが耐えがたく、孤独な未来を思うと涙を禁じ得なかった。入道は仏前で勤行を続けながら、「これからは姫君の顔を見ないで生きることになるのだな」と嘆息していた。尼君もまた、これまでの年月を振り返り、娘の愛人である源氏の心を頼みに京へ戻ることに不安を感じていた。明石の君は父に対し、「行く先の安全を祈ってください」と懇願したが、入道は事情が許さないとしつつも、娘の未来を案じていた。出立の日の朝、涼しい秋風が吹く中、明石の君は海を眺め、父は仏前で祈りを捧げていた。小さな姫君の愛らしさを思うと、祖父としての愛情から離れることが一層辛く、入道は涙ながらに「姫君の高い宿命を信じ、私もあきらめる」と言い残した。そして、「天に帰るような姫君との別れも一つの試練である」と悟りを示したが、それでも祖父としての愛情を断ち切れない様子であった。明石親子の出発は、目立たないよう船を用いることとなった。これもまた、慎重に計画された別れであり、悲しみと希望が交錯する門出であった。午前八時、船が明石の浦を出発した。かつての人々が心を揺さぶられたという明石の浦の朝霧が立ちこめる中、船が次第に岸を離れていくのを見守る入道の心は、仏弟子としての超越した境地を忘れ、呆然と佇んでいた。都への帰還を果たす尼君の心もまた、深い悲しみに包まれていた。「かの岸に心寄りにし海人船のそむきし方に漕ぎ帰るかな」と詠んで涙を流す尼君に続き、明石の君もまた、「いくかへり行きかふ秋を過ごしつつ 浮き木に乗りてわれ帰るらん」と述懐した。
2025.02.10
コメント(25)
-
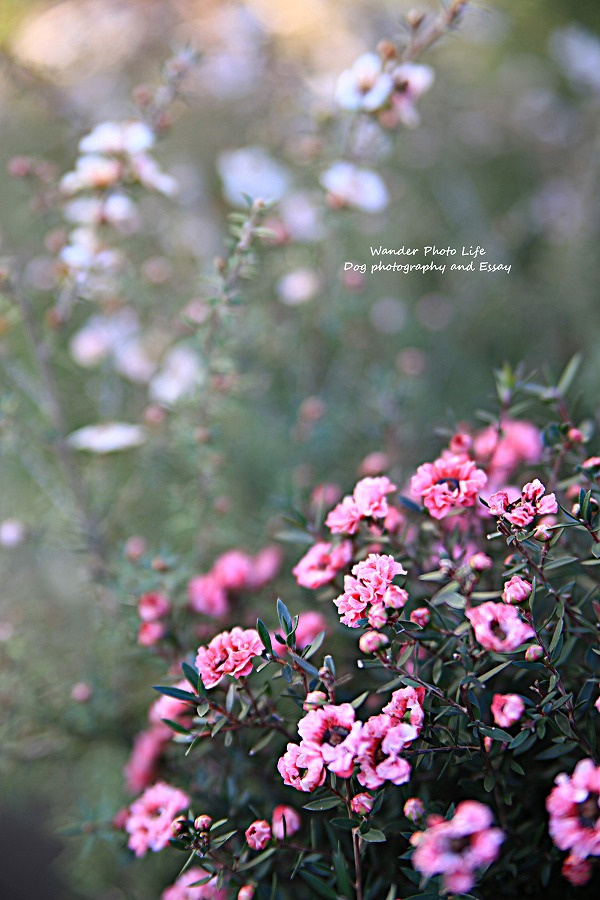
源氏物語〔20帖 朝顔 3〕
源氏物語〔20帖 朝顔 3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語20帖 朝顔 (あさがお) の研鑽」を公開してます。預かり人は「長年所有者が現れなかったため、別荘は大いに荒れています。私は下屋に住みつつ管理してきましたが、近くで内大臣様が御堂を建設し始め、多くの人が訪れるようになっています。そのような賑やかな環境では落ち着いた住居には適さないかもしれません」と答えた。それに対し、入道は「問題ない。内大臣家との関係もあり、あの場所を選んでいるのだ。急いで修繕に取り掛かってほしい」と依頼した。しかし、預かり人は長年自分の財産のように扱っていた田地や建物が回収されることを恐れ、権利を主張し始めた。鼻を赤くして主張するその姿は、いかにも卑屈で憐れなものであった。入道は田地に関して、「私のほうでは田地などいらない。これまでどおりに君は好きなように考えていればいい。別荘その他の証券は私の手元にあるが、もう世を捨てた身なので、財産の権利や義務も忘れてしまった。留守居料も支払っていなかったが、そのうち精算するよ」と言い渡した。この発言に、相手は入道が源氏に関係があることをほのめかしたことで不安を覚え、私欲をこれ以上出すことを躊躇した。その後、入道家からの多額の資金によって、大井の山荘は修繕されていった。こうした動きは、源氏にとっては想定外のことであり、明石が上京を渋る理由を不審に思う一方で、姫君がこのまま田舎で育てられることで後の歴史に不名誉が残るのではないかと憂慮していた。山荘が完成した後、明石から「この山荘を拠点にして上京するつもりだ」との連絡が届いたことで、東の院への居住に同意しなかった理由が初めて明らかとなり、源氏はその慎重な考えを聡明だと感じた。そこで源氏は、惟光に山荘を確認させ、必要な準備を行うよう指示した。惟光は「眺めがよく、海辺のような趣も感じられる場所です」と報告した。それを聞いた源氏は、明石がその地の女主人としてふさわしい品格を備えていると改めて思い、内部の設備に至るまで自ら手配しようと考えた。そして、親しい者たちを密かに迎えに向かわせた。
2025.02.09
コメント(24)
-

源氏物語〔20帖 朝顔 2〕
源氏物語〔20帖 朝顔 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語20帖 朝顔 (あさがお) の研鑽」を公開してます。北の対は特に広く建てられ、多くの仕切りを設けることで、源氏が愛人と見なし、将来的な約束を交わした女性たちが居住できるように工夫されていた。このような背景から、北の対は最も興味深い建物となった。中央に位置する寝殿は誰かの住まいとして使用するのではなく、時折源氏が休息を取ったり、客を招いたりする座敷として用いられることになっていた。一方で、明石の方に対しては頻繁に手紙が送られ、その内容は主に上京を促すものであった。しかし、明石の女性はまだ上京を決断できずにいた。彼女は自身の身分の低さを十分に理解しており、都の貴族の女性たちでさえ、源氏から冷淡ではないものの、それなりの扱いを受けて悩み多き日々を送っているという噂を耳にしていた。そのため、源氏の愛情にどれほどの確信を持てば都へ向かうことができるのか、さらに、娘である姫君の母親として、貧しい出自をさらすことへの不安も重なり、京での生活を思い描くたびに苦悩していた。それでも、姫君を田舎に置いたまま、源氏の子として認知されない境遇に陥らせることもまた耐え難いことであると考えたため、上京を完全に拒否することもできず、明石の女性は煩悶し続けていた。彼女の両親もまた、娘の苦悩を理解しながら歎息するばかりだった。そんな中、入道夫人の祖父である中務卿親王がかつて所有していた嵯峨の大井川近くの別荘を思い出した。その別荘は相続者がいないために長らく荒廃していたが、親王の時代から預かっているという人物を明石へ呼び、相談を持ちかけることとなった。「私は一度田舎に引きこもると決めてから京での生活を再開するつもりはなかった。しかし、娘の将来を考えるとそうもいかない。古い別荘を修繕し、人が住める状態に整えたいのだが、その手配を君にお願いしたい」と入道が言う。
2025.02.08
コメント(20)
-

源氏物語〔20帖 朝顔 1〕
源氏物語〔20帖 朝顔 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語20帖 朝顔 (あさがお) の研鑽」を公開してます。源氏は幼い頃から従姉妹にあたる朝顔の君に強い恋心を抱いていたが、朝顔の君はその思いを受け入れることなく、一貫して拒絶する姿勢を貫いていた。朝顔の君は恋愛感情よりも自身の内面的な清らかさを重んじる性格であり、光源氏の情熱的な求愛にも決して心を動かされることはなかった。物語のこの部分では、光源氏の彼女に対する執着や、進展のない関係への葛藤が描かれる。彼は朝顔の君の拒絶を受けながらも諦めきれず、彼女を思い続ける。しかし、朝顔の君は自分の意志を明確に保ち、光源氏のような魅力的な男性からの求愛であっても自分の生き方を曲げることはない。この姿勢は、朝顔の君が貴族社会における女性としての自立心を持っていることを象徴している。この帖は、光源氏の恋愛感情の複雑さや、彼が多くの女性たちと築いてきた関係の中でも特に困難な場面を描いている。物語全体を通して、静かな情感が漂い、恋愛が成就することのない切なさと、登場人物たちの内面的な葛藤が交錯していく。朝顔の君の毅然とした態度は、物語の他の女性と比較しても非常に個性的であり、その存在は物語において特別な深みを与えている。この帖は、単なる恋愛物語の一部というだけでなく、光源氏という人物の内面をさらに掘り下げる重要な役割を果たしているともいえる。彼の複雑な感情と、それに応じる朝顔の君の毅然とした態度が織りなす微妙な関係性は、物語に深い余韻を残すものとなっている。源氏の東の院が美しく完成したのを機に、「花散里」と呼ばれていた夫人を源氏は新居へ移らせることにした。その住まいは、西の対から渡殿にかけての区域をその居所とし、事務処理のための施設や家司の詰め所も備えられていた。これにより、源氏の夫人の一人としての体面を損なわない立派な住まいが整えられていたのである。また、源氏は東の対には明石の方を住まわせようと以前から考えており、その計画を進めていた。
2025.02.07
コメント(20)
-

源氏物語〔19帖 薄雲 9完〕
源氏物語〔19帖 薄雲 9完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語19帖 薄雲 (うすぐも) の研鑽」を公開してます。最終的に僧都は告白を進めるが、それが帝に与える影響は計り知れないものとなる。僧都の告白を受けて、帝は深い衝撃を受ける。「恥ずかしさ、恐しさ、悲しさ」の入り混じった感情が描写されている。ここでは、帝が自分の出生や運命について新たに知った事実に対してどう向き合うべきか苦悩する様子が表現されている。また、帝が僧都に対して「恨めしい」と告げる場面が印象的だ。幼い頃から僧都を信頼してきたにもかかわらず、これまで秘密にされてきたことへの不満が滲み出ている。この感情は、天皇という絶対的な立場にいる人物の孤独や苦悩を浮き彫りにしている。僧都の告白が引き金となり、帝の中で源氏への思いがより強くなる。源氏は帝の父の子であり、血筋的に特別な存在だが、政治的には臣下として扱われている。この矛盾に帝は苦しみ、源氏に対して特別な愛情や敬意を示すようになる。帝が源氏に天皇の地位を譲ることを考える場面では、自分の地位や責任に耐えられない気持ちや、源氏の人格を深く尊敬している様子が描かれている。しかし、源氏はこれを拒否する。源氏が自分の立場を理解しつつ、過剰な野心を抱かない姿勢を見せることで、彼の高潔さや慎重さが浮かび上がる。この場面は、運命や血筋、政治的な責任、そして人間の感情が複雑に絡み合っている。僧都の告白がすべての中心にあり、それによって帝や源氏が自分たちの立場や未来について考え直すきっかけを得る。また、この物語が描く感情の繊細さが際立つ。帝の苦悩や源氏の葛藤、僧都のためらいや使命感など、すべてが細やかに描写されている。この時代背景を理解するとともに、人物たちの内面に寄り添うことで、この場面の持つ重みや深さが感じられる。この部分は、物語全体の中でも特に劇的で、登場人物たちの心情や立場が大きく変化する重要な場面と言える。(完)明日より18帖 松風(まつかぜ) を公開予定。
2025.02.06
コメント(24)
-

源氏物語〔19帖 薄雲 8〕
源氏物語〔19帖 薄雲 8〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語19帖 薄雲 (うすぐも) の研鑽」を公開してます。かつての恋愛での苦い経験と未練が、彼の内面に大きな影響を与えており、女御への愛情や養父としての責任感と交錯している。これらの感情を背景に、源氏は今後の人生について慎重に考え、心の平穏を求めつつも、家族と国家の未来を見据えて行動する姿勢を示す。物語は、帝と源氏の間の隠された秘密と、それに伴う感情の揺れを描きながら、政治と人間関係が絡み合う複雑な宮廷生活を浮き彫りにする。この背景には、日本の貴族社会の特異性と、そこに生きる人々の葛藤が色濃く反映されている。僧都(僧侶)が帝(天皇)に過去の秘密を告白し、そこから帝や周囲の人々が抱える葛藤や運命が描かれている。僧都が帝に告白する内容は非常にデリケートで、政治や家族関係、宗教的な問題が絡んでいる。この時代、天皇は絶対的な存在であり、家系や血筋、神聖な役割が特別視されていた。その中で、僧都が告げた「秘密」が、帝自身の存在や地位に関わる重大な問題であったことが読み取れる。僧都が最初にためらいながらも「申し上げにくいこと」として切り出した内容は、過去の祈祷に関することだ。この祈祷は、帝の出生やその周囲に関わる不安を鎮めるために行われたもので、特に帝の父である故院(先代天皇)や女院(天皇の母)の間で行われた。しかし、この祈祷には何か隠された意図や背景があり、それが現在の不安定な状況や天災などと結びついているとされている。僧都が語った祈祷の内容は、帝の出生や家族の運命に関するものだった。帝の父や母が極度に心配していたこと、それが僧都に託されていたことが明かされる。この告白により、帝は自分の存在や地位に疑問を抱き、不安や苦悩を深めることになる。帝が「何のことであろう」と僧都に尋ねる場面では、僧都がすぐにすべてを話さずに躊躇する様子が描かれている。これにより、僧都が抱えていた秘密がどれほど重大で、話すことがどれほどのリスクを伴うかが伝わってくる。
2025.02.05
コメント(23)
-

源氏物語〔19帖 薄雲 7〕
源氏物語〔19帖 薄雲 7〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語19帖 薄雲 (うすぐも) の研鑽」を公開してます。すでに七十を超えていた僧都は、源氏から再び宮中での勤めを求められ、辞退する気持ちを抱きながらもこう述べた。「この健康で夜居の勤めを果たす自信はありませんが、女院様への御奉公になることと思い、お引き受けいたします。」こうして僧都は再び帝のそばで夜居の勤めをすることとなった。静かな夜明け、周囲の人々が退出した後、僧都が帝のそばで祈るその時間には、深い静寂とともに過ぎし日の女院への想いが重く流れていた。僧都がかつての祈祷や秘密について語り出した場面から話を始める。僧都は「過去と未来に関わる重大な話であり、これを語ることが天命に背く恐れがある」としながらも、天の意志を恐れて告白を選んだ。この中で、僧都は天皇が幼いころからその存在を支え、祈祷を行っていたこと、その内容が源氏を巡る隠された事実に深く関わっていることを明かす。告白を聞いた帝は驚きと恐怖、悲しみが入り混じった複雑な心境に陥り、源氏が父君でありながら臣下として仕えている事実に胸を痛めた。帝は僧都の言葉から過去に隠されていた事実の重さに直面し、自らの位置を見直さざるを得ない状況となった。源氏への愛情が深まりつつも、それを伝える術を見いだせず苦悩する帝。一方で、源氏もまた、宮廷での振る舞いや自身の立場に関する思索を深める。僧都からの奏上が引き金となり、帝は歴史や書物を通じて同様の例を探し求めるが、日本の中では似たような前例が見つからないことに落胆する。そして、自らの地位を譲ることを考え始める。源氏は帝からの太政大臣への任命やさらなる昇進の申し出を辞退しつつ、慎重に振る舞うことで、帝の意図や内心を探る。命婦を訪ね、僧都が話した内容の背景や女院の意向を確認する場面では、源氏の聡明さと誠実さが際立つ。同時に、故宮や女院への愛惜の念を抱きつつ、現実に向き合う冷静さも見られる。秋の雨の中、源氏は新しい女御を迎える準備を整えながら、過去の恋や人間関係を振り返る。
2025.02.04
コメント(24)
-
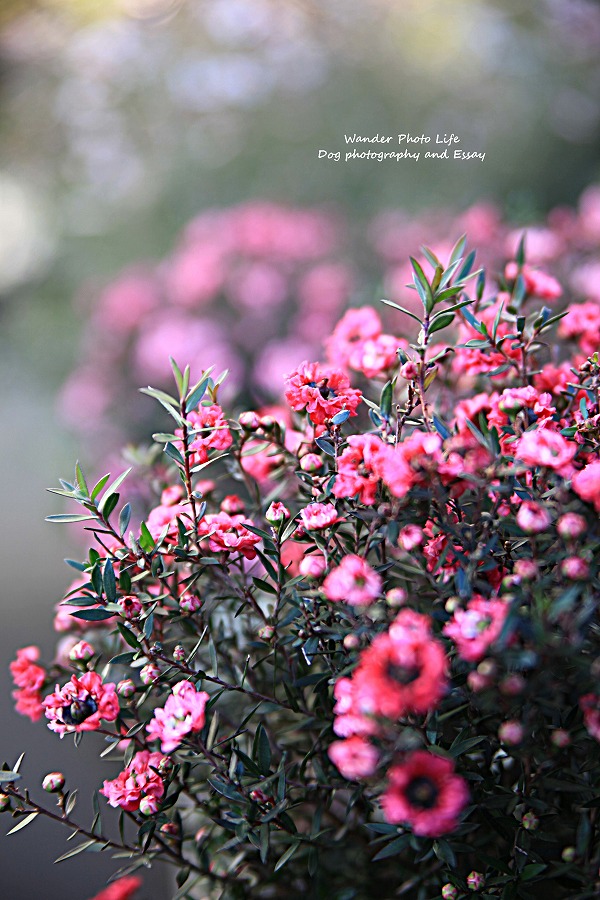
源氏物語〔19帖 薄雲 6〕
源氏物語〔19帖 薄雲 6〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語19帖 薄雲 (うすぐも) の研鑽」を公開してます。その言葉に対し、源氏は返事をすることもできず、ただ涙を流すばかりであった。周囲の女房たちは、源氏の涙に同情しつつも、その激しい感情の表れに驚きを隠せなかった。けれども、源氏にとっては涙を抑えることなど到底できなかった。女院の若かりし頃からの姿が脳裏に浮かび、恋愛感情を超えて彼女の存在そのものが惜しく、最愛の命が失われていくことに人間の無力さを思い知らされ、限りない悲しみに沈んでいたのである。源氏は、太政大臣の薨去という大きな出来事の後に女院が重篤となり、自らも無力さを痛感していたことを振り返り、「陛下の御後見にできる限りの努力をしておりますが、私は長く生きていられないように感じます」と悲しげに語った。その言葉が消えゆく中、まるで灯火が消えるように女院は崩御された。源氏は深い悲しみに沈み、女院の高貴な人格とその生涯を思い返していた。女院は、その権威をもって民衆に愛情深く接し、不公平を避け、過剰な負担を課す政策を拒まれた。宗教面でも華美な仏事や儀式を避け、両親から受け継いだ遺産や官からの支給を実質的な慈善や僧侶への寄付に充てられていた。多くの僧侶や民衆がその恩恵を受けていたため、彼女の崩御を悲しむ声が広がり、世間の人々は皆涙を流した。春の喪服姿の殿上人たちは寂しい雰囲気を漂わせていたが、源氏もまた深い哀しみに打ちひしがれていた。二条の院の庭に咲く桜を見ては、かつての花の宴や故中宮を思い出し、「今年ばかりは」(墨染めに咲け)とつぶやいていた。そして、念誦堂に籠もり、終日涙を流していた。春の夕日に照らされる山の頂や薄雲の流れる景色が目に映る中、源氏の心に浮かんだ歌があった。入り日さす峯にたなびく薄雲は物思ふ袖に色やまがへる。この歌は源氏の誰にも知られることのない心の中の吐露であった。女院の葬儀に関するすべての儀式が終わったころ、帝は一層心細さを感じていた。そんな中、長年女院や朝廷に仕えた高僧がいた。この僧都は、女院の崩御を聞き山から京へ下りてきた人物で、過去には大きな祈願を多く行い女院からも深く信頼されていた。
2025.02.03
コメント(19)
-

源氏物語〔19帖 薄雲 5〕
源氏物語〔19帖 薄雲 5〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語19帖 薄雲 (うすぐも) の研鑽」を公開してます。病気自体はそれほど重いものではございませんでした。それゆえに、死を予感しているような様子を人に見せるのは慎みたいと思い、功徳のための特別な行動も例年以上のことは避けましたと語り、さらに、故院の話を伝えたかったが、病がちで心身の余裕がなく、長く帝にお会いすることができなかったとも述べた。今年37歳になる女院は、実際の年齢よりも若々しく見え、まだ美しい盛りの容姿を保っていた。そのため、帝は彼女の衰えを惜しみ、深い悲しみを抱かれた。女院の病が長引く中で、帝は過去の油断を悔い、もっと早く養生させるべきだったと後悔していた。最近になって急に快癒を願う祈祷を熱心に行わせたが、それまでの対応の遅れを痛感していた。源氏もまた、病を軽んじてしまったことを嘆き、尊貴な女院の命を救うために神仏に祈り続けていた。女院自身は、言葉を発するのも辛そうな様子だったが、心の中では自らの人生を振り返り、高貴な身分に生まれ、人間としての最上の光栄である后の位に就いたことを誇りに感じていた。一方で、帝が源氏との深い関係を知らないことを心残りに思っていた。それは、この世で唯一後悔として残る未解決の心のしこりだった。源氏は一廷臣として、また女院の危篤に深く心を痛める者として、彼女の最期に心を尽くしていた。しかし、それ以上に、長い間胸の内に秘めてきた初恋の想いを告げる機会が永遠に失われることへの悲しみが源氏を苛んでいた。几帳の前で女房たちから女院の御容体を尋ねると、彼女たちは、「女院は病を堪えながら仏事を休むことなく続けていらっしゃいましたが、それが積もり積もってこのようにお悪くなられたのです。このごろでは何一つ口にすることができず、衰弱が進むばかりでございます」と答えた。女院は女房を通じて源氏に言葉を伝えた。「院の御遺言を守り、陛下の御後見をしてくださったことにどれほど感謝してきたか分かりません。いつかあなたにお報いできる時が来ると信じておりましたが、それが叶わぬまま今日を迎えてしまい、本当に残念です」と。
2025.02.02
コメント(29)
-

源氏物語〔19帖 薄雲 4〕
源氏物語〔19帖 薄雲 4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語19帖 薄雲 (うすぐも) の研鑽」を公開してます。源氏は、明石の君との短い逢瀬を惜しみ、離れることを嘆いて「夢のわたりの浮き橋か」と和歌を詠んだ。その後、十三絃を手に取り、明石の君の秋の夜に聴いた琵琶の音を思い出しながら演奏した。源氏は彼女にも弾くよう勧め、明石の君がそれに応じて合わせる姿を見て、彼女の才知と気品に改めて感嘆した。源氏は姫君の近況を明石の君に詳しく語り、二人の間に交わされる会話や時間には深い愛情が込められていた。大井の山荘は源氏にとって愛人の家に過ぎないが、泊まり込む際には簡素な食事を取ることもあり、その一方で定まった食事や行事は桂の院や他の御堂で行う。貴族としての体面を保ちつつも、山荘での生活に溶け込むような寛容さを見せた。こうした態度は、明石の君への特別な愛情によるものだった。明石の君も源氏のこの思いを尊重し、必要以上に出しゃばらず、かといって卑下もしすぎない、絶妙な態度を保っていた。このような彼女の振る舞いは、源氏にとって非常に心地よいものであり、彼女への愛情をさらに深めさせる要因となった。明石の君は、源氏がこれほどまでに親しみを見せる愛人の家はほかにないことを理解しており、その立場を守る術を心得ていた。彼女は、もし東の院など源氏の近くに移れば、その新鮮さが失われ、早々に飽きられてしまうと考えた。自らの地理的な隔たりがかえって源氏の気持ちを繋ぎ止める強みであると自負していた。一方、明石の入道は、今後のすべてを神仏に委ねると語りつつも、娘や孫の扱いに対する関心を絶やさず、使者を頻繁に出して様子を伺った。その知らせを受けて胸が塞がるような思いをすることもあれば、名誉を感じて喜ぶこともあった。こうした複雑な感情を抱えながらも、入道もまた、源氏と娘、そして孫との縁に対して、静かに見守る日々を送っていたのである。女院の御容体が悪化する中で、彼女は弱々しい声で帝に、今年が私の死ぬ年であることは初めから覚悟しておりましたと語りかけた。
2025.02.01
コメント(23)
-

源氏物語〔19帖 薄雲 3〕
源氏物語〔19帖 薄雲 3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語19帖 薄雲 (うすぐも) の研鑽」を公開してます。源氏は彼女にも弾くよう勧め、明石の君がそれに応じて合わせる姿を見て、彼女の才知と気品に改めて感嘆した。源氏は姫君の近況を明石の君に詳しく語り、二人の間に交わされる会話や時間には深い愛情が込められていた。大井の山荘は源氏にとって愛人の家に過ぎないが、泊まり込む際には簡素な食事を取ることもあり、その一方で定まった食事や行事は桂の院や他の御堂で行い、貴族としての体面を保ちつつも、山荘での生活に溶け込むような寛容さを見せた。こうした態度は、明石の君への特別な愛情によるものだった。明石の君も源氏のこの思いを尊重し、必要以上に出しゃばらず、かといって卑下もしすぎない、絶妙な態度を保っていた。このような彼女の振る舞いは、源氏にとって非常に心地よいものであり、彼女への愛情をさらに深めさせる要因となった。明石の君は、源氏がこれほどまでに親しみを見せる愛人の家はほかにないことを理解しており、その立場を守る術を心得ていた。彼女は、もし東の院など源氏の近くに移れば、その新鮮さが失われ、早々に飽きられてしまうと考え、自らの地理的な隔たりがかえって源氏の気持ちを繋ぎ止める強みであると自負していた。一方、明石の入道は、今後のすべてを神仏に委ねると語りつつも、娘や孫の扱いに対する関心を絶やさず、使者を頻繁に出して様子を伺った。その知らせを受けて胸が塞がるような思いをすることもあれば、名誉を感じて喜ぶこともあった。こうした複雑な感情を抱えながらも、入道もまた、源氏と娘、そして孫との縁に対して、静かに見守る日々を送っていたのである。大井の山荘は風流な趣を持ち、建物も独特な雅味を感じさせる造りだった。その住まいは一般的な形式を離れた優雅さを備えており、周囲の自然とも調和していた。明石の君は、源氏が会うたびにその美しさが一層際立っていくように見え、源氏はこの女性を貴族の夫人と比べても劣るところがないと感じていた。彼女の出自を考えれば、本来ならば成し得ない関係と思えるが、偏屈な親の性格がそれを妨げただけであり、家柄自体は決して劣っているわけではないと源氏は考えていた。
2025.01.31
コメント(21)
-

源氏物語〔19帖 薄雲 2〕
源氏物語〔19帖 薄雲 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語19帖 薄雲 (うすぐも) の研鑽」を公開してます。姫君が紫の上のもとで愛情深く育てられる中、明石の君はその愛らしい娘を思い続け、寂しさとともにその決断の正しさを噛み締める日々を送る。こうした物語は、人々の心の葛藤や愛情の形を描き出し、薄雲のように美しくも移ろいやすい人間の感情を鮮やかに表現している。姫君は無邪気に源氏の裾にまとわりつき、御簾の外へ出そうになるほどだった。その様子を愛おしげに見つめた源氏は、立ち止まり姫君をなだめつつ、「明日帰りこん」と口ずさみながら縁側へ向かった。その様子を見た紫の上は、中将という女房を呼び、「遠方人」という言葉を込めた和歌を伝えさせた。源氏は微笑みながらこれに応え、冗談めいた軽妙な和歌を詠んだ。父母のやり取りを知らぬ姫君は、嬉しそうに走り回り、その様子に紫の上の心のわだかまりも和らいでいった。紫の上は「この子が自分の子供であったらどれほど恋しく、愛おしかっただろう」と思いながら、姫君を抱き上げて美しい乳を飲ませる真似をして戯れた。この光景は外から見ても非常に美しいもので、女房たちは、「もしこの子が本当のお子様だったなら、どれほどよかったことでしょう」と囁き合った。その場に満ちる愛情と幸福の空気は、二条の院の人々に春の訪れを告げる象徴的なものであった。大井の山荘は風流な趣を持ち、建物も独特な雅味を感じさせる造りだった。その住まいは一般的な形式を離れた優雅さを備えており、周囲の自然とも調和していた。明石の君は、源氏が会うたびにその美しさが一層際立っていくように見え、源氏はこの女性を貴族の夫人と比べても劣るところがないと感じていた。彼女の出自を考えれば、本来ならば成し得ない関係と思えるが、偏屈な親の性格がそれを妨げただけであり、家柄自体は決して劣っているわけではないと源氏は考えていた。源氏は、明石の君との短い逢瀬を惜しみ、離れることを嘆いて「夢のわたりの浮き橋か」と和歌を詠んだ。その後、十三絃を手に取り、明石の君の秋の夜に聴いた琵琶の音を思い出しながら演奏した。
2025.01.30
コメント(25)
-
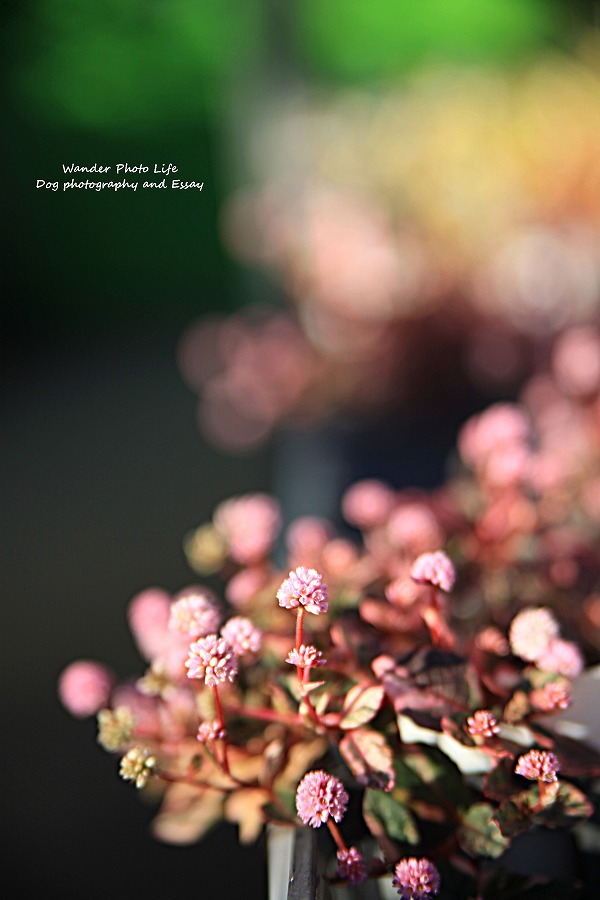
源氏物語〔19帖 薄雲 1〕
源氏物語〔19帖 薄雲 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語19帖 薄雲 (うすぐも) の研鑽」を公開してます。浮舟という女性が登場し、彼女は光源氏の心に深く刻まれた存在である。浮舟は異国から嫁いできた女性であり、源氏の人生の中でかつて愛された人の一人として、彼の心に懐かしさや切なさを呼び起こす役割を担っている。光源氏が空を見上げ、薄い雲を眺める中で、浮舟の姿が過去の記憶と重なり、彼はその雲の中に浮舟がいるような感覚に浸る。薄雲は、源氏が美しいが儚い過去の恋を思い出し、心を揺さぶられる象徴的な存在となっている。冬が訪れる中、川沿いの家で孤独な生活を送る明石の君は、不安に包まれた日々を過ごしていた。明石の君の様子を見た光源氏は、彼女に引っ越しを勧め、近隣の家での生活が状況を改善するだろうと提案するが、彼女はすぐに決断を下すことができずに悩む。歌の中で詠まれる「宿を変えて待つにも見えず」という表現が象徴するように、距離が離れることへの恐れや、源氏の心が冷たくなる可能性が彼女の心を惑わせる。さらに、光源氏は娘である姫君を自身のそばで育てるべきだという意向を示し、紫の上が姫君を非常に大切に思っていることを伝えた上で、正式な儀式を二条院で行うことを提案した。明石の君は、源氏の提案に動揺しつつも、娘が良い環境で育つことの重要性を理解し始める。しかし、姫君を紫の上に預けることが、母親としての自分の立場や過去に影響を及ぼすのではないかという不安を抱え、決断に迷い続ける。明石の君の母である尼君は、姫君の未来を最優先に考えるべきだと諭し、紫の上を信頼して娘を託すことの必要性を説いた。源氏の生い立ちや母親の地位の話を例に挙げ、明石の君の立場では姫君を二条院へ預けるほうが遥かに良い未来を得られることを示唆し、さらに占いや意見を参考にして明石の君の考えを少しずつ変えていった。姫君を手放す苦しみを覚えながらも、明石の君は娘の幸福のために決断を下す。その過程で乳母との別れも重なり、心はさらに引き裂かれるようだったが、それでも姫君の未来を思い、覚悟を決める。源氏は明石の君の心情を思いやりながらも、姫君のために準備を進め、二条院での儀式が華やかに執り行われるよう整える。
2025.01.29
コメント(22)
-

源氏物語〔18帖 松風 9 完〕
源氏物語〔18帖 松風 9 完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語18帖 松風 (まつかぜ) の研鑽」を公開してます。宴が終わりに近づくと、源氏は都への帰途を急ぐ。しかし、その心には明石の君や姫君への思いが残り続けている。宴の華やかさや音楽の美しさとは裏腹に、源氏の内面には、過去と現在の交錯する感情が渦巻いている。源氏と夫人(紫の上)との間に繰り広げられる微妙な感情のやり取りが描かれている。源氏は嵯峨から戻り、二条の院に到着する。桂の院での賑やかな宴の余韻を残しつつ、嵯峨で過ごした時間や道中の美しい景色の話をするが、その言葉の裏には別の思いが隠れている。源氏は、嵯峨での明石の君との再会や、そこで得た心の揺れを紫の上には隠しながらも、その影響が言動ににじみ出る。紫の上は、源氏が何かを隠していることを察し、わずかに不機嫌な様子を見せる。しかし、源氏はその不機嫌さに気づかないふりをし、「自分は自分であるという自信を持てばいい」と諭すように言う。その言葉には、紫の上の嫉妬を軽く受け流す意図があるものの、どこか無神経な響きもある。彼女の不安を理解しつつも、表向きはそれを抑え込もうとする源氏の態度が、二人の間の微妙な緊張感を生んでいる。その後、源氏は大井の山荘に手紙を送るために密かに準備をする。その様子を見ていた女房たちは不満を感じるが、源氏は気にせず行動を続ける。やがて大井からの返事が届いた。それを紫の上の前で隠すことなく読む。手紙の内容に不審な点はなく、紫の上もそれを表面的には気にしないふりをするが、心の奥では複雑な感情が渦巻いていることが伺える。源氏は、明石の君との間に生まれた姫君のことを持ち出し、「この子を紫の上に育ててほしい」と頼む。その提案は、単なる子供の養育を依頼するという以上に、源氏の心の葛藤や罪悪感、そして紫の上への信頼を試すものでもある。紫の上は一瞬ためらいながらも、「小さな姫君のお相手はできる」と応じる。その言葉には、嫉妬や不安を乗り越えようとする健気な気持ちと、母性への強い憧れが滲んでおり、このやり取りの中で、源氏と紫の上の関係の複雑さが浮き彫りになる。源氏は多くの女性との関係を持ちながらも、紫の上を特別な存在として扱っている。しかし、その特別さが彼女にとって必ずしも幸せを意味するわけではなく、他の女性たちとの関係が彼女に不安や孤独をもたらしている。明石の姫君の話を通じて、二人の間に流れる見えない壁と、それを乗り越えようとする努力が描かれている。そして、源氏は大井の山荘に頻繁に通うことができず、月に二度しか訪れることができない。そのため、明石の君にとっては、源氏を待つ十五日間が七夕の伝説のように長く、苦しいものとなる。その切なさが、この場面全体に漂う寂寥感や、人間関係の複雑さを象徴している。(完)明日より19帖 薄雲(うすぐも) を公開予定。
2025.01.28
コメント(20)
-

源氏物語〔18帖 松風 8〕
源氏物語〔18帖 松風 8〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語18帖 松風 (まつかぜ) の研鑽」を公開してます。従者たちの中でも源氏の美しさと気品は際立ち、明石の君との別れを惜しむ姿が、この物語の一瞬の輝きを際立たせている。源氏物語の中でも風情豊かな一幕で、源氏と明石の君、さらにその取り巻きたちとの間の情緒的なやり取りが細やかに描かれている。源氏は明石を去りがたい思いを抱きつつも、都へ戻らねばならない日を迎えている。明石の君は、かつての源氏の厚情を忘れてはいないものの、再会の機会が少ないことへの寂しさを口にする。海辺での孤独な日々を思い出しながら、「山に取り巻かれた今の住まいも、かつての海辺の生活と変わらない」と述べる彼女の言葉には、源氏への深い愛情と切なさが滲んでいる。明石の君は、源氏との別れを前にしながらも、気品と控えめな態度を崩さず、それが逆に彼女の魅力を引き立てている。一方で、源氏は都へ戻るための準備を進める中、桂の院での宴を楽しむことを決める。彼と従者たちは山荘を後にし、桂の院へ向かうが、その途中で自然の美しさや、同行者との会話を通じて、源氏の心には様々な感慨が去来する。特に、海辺の漁師の声を思い出す場面では、過去の明石での生活が鮮やかによみがえり、その記憶と現在の自分との対比に複雑な感情が交錯する。桂の院では、管弦の宴が開かれ、月明かりの中で美しい音楽が奏でられる。秋の夜、琵琶や和琴、笛の音が川風に乗って響き渡り、その場にいる者たちは皆、風雅な世界に浸る。都からの使者も訪れ、宴は一層華やかさを増す。帝の使者は、源氏への期待を込めた歌を伝え、それに応じる形で源氏も歌を詠む。これらの和歌のやり取りは、源氏の立場や人柄、そして彼が抱える孤独や責任感を浮き彫りにする。酒が進むにつれ、人々の感情は高まり、過去を懐かしんで涙を流す者も出てくる。源氏自身も、淡路で見た月を思い出し、過去の恋や出来事に思いを馳せる。和歌を通じた情緒的な交流は、この物語の核心でもあり、人間の愛や別れ、そして時間の流れの切なさを象徴している。
2025.01.27
コメント(23)
-

源氏物語〔18帖 松風 7〕
源氏物語〔18帖 松風 7〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語18帖 松風 (まつかぜ) の研鑽」を公開してます。そして彼は、「契りしに変わらぬ琴のしらべにて…」と和歌を詠み、明石の君もまた応えるように歌を返す。この和歌のやり取りは、二人の間にある深い絆と互いへの変わらぬ思いを象徴している。明石の君は以前にも増して美しさを増しており、源氏の心は彼女に強く引き寄せられている。さらに、姫君の存在も源氏にとって大きな意味を持つ。日陰の存在として育つことに心を痛めつつも、二条の院に引き取ることで将来の不安を取り除こうと考える。しかし、その決意を口に出せば、明石の君を引き離すことになるため、言葉にはせず、ただ姫君を見つめて涙を浮かべるのだった。姫君は初めは恥ずかしがっていたものの、次第に源氏に馴れ、無邪気に笑ったり甘えたりする姿が一層愛らしい。源氏にとって、この幼い姫君はすでに幸運と愛情に包まれた存在に見える。三日目、帰京の準備が整うと、源氏の周りには多くの高官や殿上役人が集まっている。その賑わいの中で源氏は、「この家はあまり人目にふさわしくない」と冗談めかして言うが、その心は明石の君への思いで満ちている。別れ際に姫君を抱いている源氏の姿には、離れ難い愛情が滲み出ており、「遠いじゃないか、ここは」と嘆くように言葉を漏らす。乳母もまた、たまにしか会えない状況を案じていることを伝え、源氏の心情をさらに深く揺さぶる。一方で、明石の君は別れの悲しみに心乱れ、源氏の呼びかけにもすぐに応じようとしない。その慎ましさと気品ある態度が、源氏には少し「貴女ぶる」と感じられるが、やがて彼女は几帳の陰から姿を見せる。その佇まいには柔らかくも気高い美しさがあり、源氏はその姿に深く引き込まれる。別れの時、振り返った源氏の姿を見送る明石の君も、冷静さを装いつつも、その眼差しには切なさが溢れている。源氏の容姿は今が盛りで、以前の痩せた印象から、堂々とした美男子へと変貌している。見送る女房たちもその姿に見惚れ、彼の風格に感嘆する。
2025.01.26
コメント(28)
-
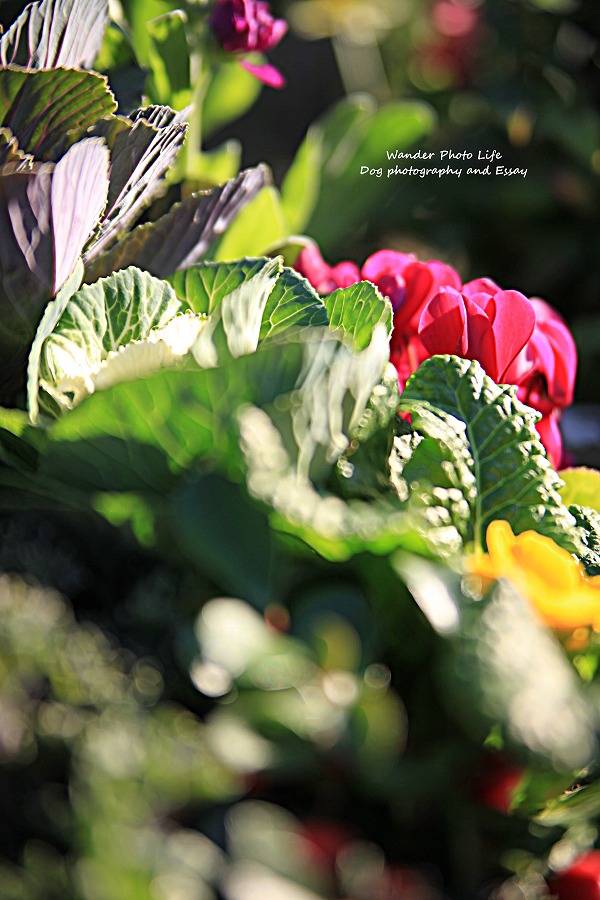
源氏物語〔18帖 松風 6〕
源氏物語〔18帖 松風 6〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語18帖 松風 (まつかぜ) の研鑽」を公開してます。源氏は彼女をいたわり、将来を固く約束することでその夜を過ごす。そして、彼の訪れが桂の院の近くに知られると、多くの人々が集まり、屋敷の修繕や庭の手入れが進められる。源氏はこの庭の改修に関して、「この場所に永遠にいるわけではないから、去るときに未練が残るのは辛い」と過去の思い出を重ね合わせる。こうした感傷的な回想と共に、涙と笑いを交えながら話す源氏の姿には、彼の美しさが一層際立って見える。その様子を陰から見ていた尼君は、老いも忘れたかのように微笑む。源氏は、尼君の部屋に仏具が置かれているのを見て、彼女の生活を思いやり、感謝の意を伝える。尼君も涙を流しながら、源氏と明石の君の娘が健やかに育ったことを喜ぶ。身分の低い母を持つことが障害にならないかと心配する気持ちを吐露する。そこには、娘の未来を案じる母としての深い愛情と不安が滲んでいる。源氏はこの話の流れの中で、昔の山荘の主であった親王のことを思い出し、感慨深く語る。その情景を背景に、庭の流れる水は以前よりも高い音を立て、まるでこの物語に共鳴しているかのようだ。尼君が詠んだ和歌には、長い年月を経て帰ってきた人々への懐かしさと、変わらぬ風景への感謝が込められており、その言葉の端々には、長い苦労を経た者だけが持つ品格が感じられる。最後に、源氏もまた別れの寂しさを和歌に託し、その美しい言葉と振る舞いに尼君は心を動かされる。過去と現在、そして未来が交錯するこの場面には、源氏の優しさと明石の君、尼君の控えめながらも気高い姿が静かに浮かび上がっている。源氏が月例の法会を終えて、明石の山荘へ戻るところから描かれる。法会は、毎月の普賢講や念仏三昧など厳粛な儀式で、源氏はその細部まで僧侶や関係者に指示を出している。そうした責務を果たした後、月明かりの中を川沿いに帰路につく源氏の姿には、静かな余韻が漂う。山荘に戻ると、明石の君が差し出す琴が、源氏の心を過去の思い出へと引き戻す。明石の君との別れの夜を象徴するその琴は、今も音色が変わらず、当時の感情を呼び起こす。源氏は琴を手に取り、その夜の余韻を噛み締めながら一曲奏でる。
2025.01.25
コメント(23)
-

源氏物語〔18帖 松風 5〕
源氏物語〔18帖 松風 5〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語18帖 松風 (まつかぜ) の研鑽」を公開してます。明石の君は悲しみに満ちた日々を過ごしていた。琴を弾く彼女の耳には、松風の音が荒々しく響き、自然がまるで共鳴するかのようだった。その様子を見て、尼君が歌を詠んだ。「山里で一人寂しく過ごす自分に、故郷で聞いた松風と同じ音が吹く」という心情を吐露し、それに続いて明石の君も「故郷での友を恋しく思い、さえずる声を誰が理解できるだろうか」と詠った。二人の心は故郷への未練と孤独感に満ちていた。その後、源氏は明石の君への恋しさが募り、人目を忍んで大井の山荘を訪れることを決意する。夫人にはまだ明石の君が京に上ったことを知らせておらず、他人から聞かれては困ると考え、理由をつけて出発の許しを得ようとした。「桂の院の新築中の指図や、以前から約束していた人を訪ねる必要がある」と説明し、嵯峨野の御堂への参詣も予定していると告げた。しかし夫人は、「長い間待たされることを思えば、まるで仙人の話のように感じる」と皮肉を返す。源氏はその不機嫌を和らげようと、世間でも「自分は昔の自分ではない」と言われていることを持ち出し、夫人の気持ちをなだめようとした。源氏は微行で大井の山荘に向かった。夕方に到着した彼は、直衣姿で一層美しく輝いて見え、明石の君の長い悲しみを一瞬で慰めた。源氏自身も、再び彼女への深い愛情を感じ、二人の間に生まれた娘を見て深く感動した。その美しさは、世間で称えられる左大臣家の子供たちを超えるものだと確信し、無邪気な笑顔の愛嬌に心を奪われた。明石に残っていた乳母も、以前の疲れた様子はなく、美しさを取り戻していた。源氏が明石の君との再会を果たし、彼女のこれまでの苦労に思いを馳せながら、将来を見据えた計画を話す様子が描かれている。明石の君は、かつて塩焼き小屋のある田舎での生活を余儀なくされてきた。その過酷な状況に対し、源氏は深く同情しつつ、彼女をもっと都に近い場所に移そうと提案する。しかし、明石の君は、自分がまだ「田舎者」であることを恥じており、少しでも自分を磨いてから都へ行きたいという慎ましい気持ちを口にする。
2025.01.24
コメント(28)
-

源氏物語〔18帖 松風 4〕
源氏物語〔18帖 松風 4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語18帖 松風 (まつかぜ) の研鑽」を公開してます。明石の君も父に「せめて送ってほしい」と願ったが、それは叶わぬことであり、入道も心配しつつもどうすることもできなかった。別れの悲しみが山荘に満ちる中、出立の準備が静かに進んでいた。明石の入道は、地方官としての仕事が自分に適していないことを悟り、出家を決意した経緯を回想していた。世間的には潔く世を捨てたと見られて満足感もあったが、成長した明石の君を見て、自分の選択が残酷だったのではないかと心が揺れ始めた。特に彼女のような珠玉のような娘を地方に留め置くことへの罪悪感が強く、仏や神に祈りながら、娘が地方に埋もれてしまわないことを願ってきた。その中で源氏の君が婿となったことは喜ばしいものの、身分の違いから常に悲しみが付きまとい、完全には安心できなかった。姫君が生まれたことで多少の自信が持てたものの、彼女は高い宿命を持つ存在であり、こんな田舎で育てるべきではないと覚悟を決めていた。そして自分は僧であり、世の無常を知る者として、祖父と孫の愛を一時味わえたことに感謝し、別れを受け入れようとした。しかし、「姫君を見ずにいられなかった自分が、これからどうするのか」と涙を抑えきれず、「死んでも仏事は不要だ」と言いながらも、姫君への愛情を捨てきれずに祈り続けることを明言した。出立の日、目立たないように船でひそかに明石を離れた。明石の浦の朝霧の中、船が遠ざかるのを見送る入道の心は、仏道に専念する気持ちが揺らぐほど悲しみに満ちていた。尼君もまた「心を寄せた岸を離れ、遠くへ漕ぎ出す」と詠い、涙を流した。明石の君も「浮き木のような運命を経て、都に帰る」と感慨を詠い、悲しみを抱えて旅立った。一行は無事に都に到着し、大井の山荘に入った。そこは明石の風景に似ており、住み慣れた海を思わせる川の流れがあったため、住居が変わった感じがあまりしなかった。しかし、故郷への思いが募り、琴を奏でるなどして物思いにふける日々が続いた。源氏も彼女を訪れる機会を作ろうとしつつもなかなか実現せず、明石の君は都にいながらも孤独感と故郷への恋しさに包まれていた。
2025.01.23
コメント(26)
-
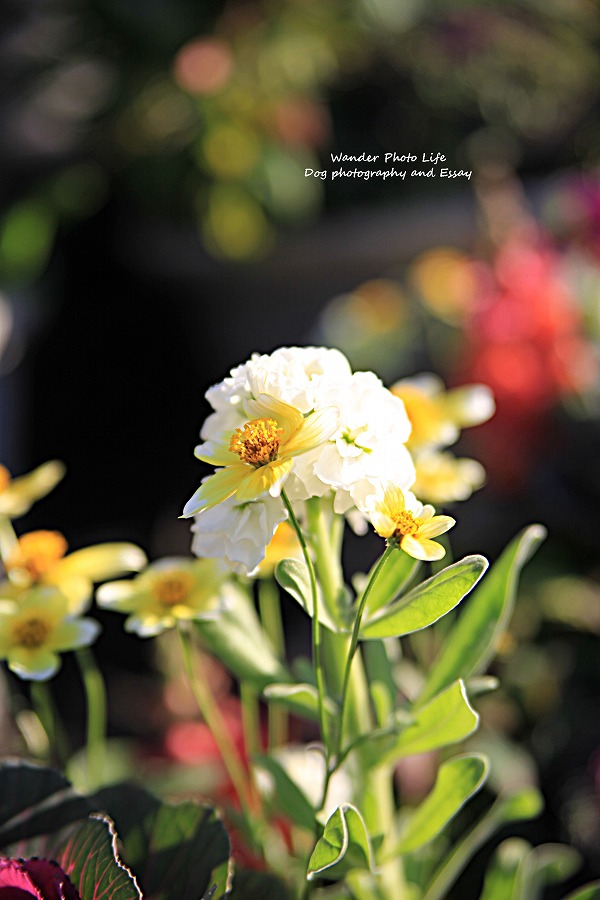
源氏物語〔18帖 松風 3〕
源氏物語〔18帖 松風 3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語18帖 松風 (まつかぜ) の研鑽」を公開してます。惟光が「ながめのよい所で、海岸のような気もする」と報告した大井の山荘は、源氏にとって明石の君にふさわしい風雅な住まいに思えた。源氏が大覚寺の南に建立中の御堂は美術的にも立派なもので、その南側に位置する山荘は川に面して大木の松が立ち並ぶ中に素朴な寝殿が建てられ、寂寥とした趣があった。源氏はこの山荘を明石の君のために整え、内部の設備もすべて自ら手配し、親しい人々をひそかに明石へ迎えに立たせた。明石の君が出京することになったが、明石の浦を離れる時が迫るにつれ、馴染んだ土地との別れが惜しまれた。父である入道を一人残していくことも心苦しく思った。自分だけがなぜこのような悲しみを背負わねばならないのかと、運命を嘆く気持ちが強まった。両親も、娘が源氏に迎えられることは長年の願いであったが、その実現が近づくにつれ、別れの悲しみが募り、入道は夜も昼も物思いに沈んでいた。入道は「姫君の顔を見ずにいることになるのか」と繰り返し嘆くばかりであった。明石の君も、これまで別居の形であったとはいえ、夫婦として過ごした月日を思い、別れることに対して寂しさを感じた。特に父である入道は、頑固でありながらも信頼してきた妻との別れを前に、不安と悲しみが入り混じった感情に揺れていた。若い女房たちの中には、都へ行ける喜びで心が弾む者もいたが、美しい明石の浦を離れることに寂しさを感じないわけではなかった。秋の涼風や虫の音がその寂しさを一層際立たせ、出立の日の朝、明石の君は海を見つめながら感傷に浸っていた。入道は夜通し仏前で勤行をし、娘との別れを思って涙を抑えきれなかった。幼い姫君は美しく、祖父である入道は彼女を溺愛していたため、「片時も顔を見ずにいられなかったのに、これから先どうすればよいのか」と嘆いた。涙を拭い隠しながら、別れの歌を詠んだ入道に、尼君もまた都を離れてきた過去を思い出し、涙を流した。
2025.01.22
コメント(24)
-

源氏物語〔18帖 松風 2〕
源氏物語〔18帖 松風 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語18帖 松風 (まつかぜ) の研鑽」を公開してます。光源氏は東の院を美しく完成させたため、花散里をそこに移すことにした。彼女の住まいは西の対から渡殿にかけての場所に設けられ、事務所や家司の詰め所なども整えられ、夫人としての面目を保つにふさわしい住居になっていた。また、東の対には明石の君を置くことを前々から考えており、北の対は広く建てられて、源氏が愛人と見なしている女性たちを住まわせる予定であった。北の対は特に複数の部屋に仕切られているため、最も面白い建物になった。中央の寝殿は誰の住居にもせず、源氏が時折訪れて休息したり、客を招いたりする座敷として使われることとなった。一方、明石の君には頻繁に手紙が送られていた。源氏は彼女に上京を強く促していたが、彼女はまだ迷いを感じていた。自身の身分の低さを痛感しており、都には源氏が愛する高貴な女性たちが多く、その中に自分が入っても冷遇されるのではないかという不安があった。都での生活が不安である一方、娘を田舎に残し、源氏の子として扱われないことも不憫だと考え、明確に上京を拒否することもできずに煩悶していた。両親もその気持ちを理解し、ため息をつくばかりであった。そんな中、明石の君の祖父である中務卿親王がかつて所有していた嵯峨の大井川の別荘が思い出された。その別荘は長年放置されて荒廃していたが、入道はそれを修復し、京の生活に馴染めない明石の君の住居にしようと考えた。そこで、長く別荘を管理している男を呼び出し、修繕について相談をした。この男は、自分が別荘を私物化しているかのような態度を取り、田地の権利を主張したが、入道は財産には関心がないことを伝え、修繕の準備を進めさせた。その後、修繕が進められ、大井の山荘が整えられていった。源氏は、明石の君がなぜ上京をためらっているのか理解できず、不安に思っていたが、山荘が完成した後、彼女からその場所を新居にするつもりであると知らされ、彼女の聡明さに感心した。そして、惟光に大井の山荘の確認や準備を任せ、明石の君の上京が進められることとなった。
2025.01.21
コメント(26)
-

源氏物語〔18帖 松風 1〕
源氏物語〔18帖 松風 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語18帖 松風 (まつかぜ) の研鑽」を公開してます。源氏物語 第18帖「松風(まつかぜ)」は、光源氏と明石の君の関係が中心に描かれている。明石の君は、もともと須磨で源氏と出会い、彼の庇護を受けて娘をもうけた女性である。現在、明石の君は、都に戻って源氏の二条院の近くに住んでいるが、身分の違いから、彼女は自分の立場をわきまえて、表立って源氏の妻のようには振る舞わないようにしている。この帖では、明石の君が住んでいる場所が描かれ、源氏との間に生まれた娘(後の明石の中宮)が成長しつつあることが明らかになる。源氏は娘を宮中に送り出す計画を立てているため、明石の君もその準備に心を砕いている。彼女は、娘が高貴な身分にふさわしい女性に育つようにと願いながらも、自分が源氏の正妻の藤壺や紫の上と比べて劣っていると感じており、そのため心の中には常に複雑な感情が渦巻いている。一方、源氏は明石の君を大切に思ってはいるものの、彼の関心や情愛は紫の上やその他の女性にも向けられている。源氏は明石の君のもとを訪れるが、その頻度は少なく、明石の君は孤独と寂しさを感じることが多い。彼女は自分の娘が将来栄光を手にすることを期待しつつも、自分の身の上については諦観の念を抱いている。「松風」という帖名は、須磨で源氏と明石の君が共に過ごした日々を象徴している。松の風が吹く音は、明石の君にとっては過去の思い出と結びついており、その音を聞くたびに、かつての愛や孤独が胸に蘇るのである。物語は、そうした明石の君の心情や源氏との微妙な関係を通して、人間の感情の複雑さや貴族社会の現実を描き出している。この帖では、光源氏と明石の君の関係が、ただの恋愛を超えて、親としての責任や社会的立場の葛藤といったテーマにも広がっている。明石の君の心の中には、母としての誇りと女性としての寂しさが交錯しており、彼女の内面の深い苦悩が浮かび上がる。
2025.01.20
コメント(27)
-

源氏物語〔17帖 絵合 8 完〕
源氏物語〔17帖 絵合 8 完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語17帖 絵合 (えあわせ) の研鑽」を公開してます。女院から下賜品が贈られ、さらに親王には帝から御衣が賜られた。その後も人々は絵合わせの話題で持ちきりだった。源氏は「須磨」と「明石」の巻を女院の手元に置いてほしいと申し出た。女院はその前後の巻も見たがったが、源氏は「また改めて」と約束をした。帝がこの絵合わせに満足した様子を見て、源氏は安堵した。絵合わせは二人の女御の対抗心から始まったものだったが、源氏は全力を尽くして梅壺を勝たせたことから、中納言は娘の将来に不安を感じ始めていた。帝が特別に寵愛している女御の父である中納言は、心の中で頼もしさと焦りを感じ、すべては自分の取り越し苦労だと思い込もうと努めていた。源氏は宮中の儀式や催しを、単なる遊戯にとどめず、美術鑑賞の域にまで高めることを目指していた。絵合わせもその一例であり、文化の盛んな時代が現出したことを示していた。しかし源氏は人生の無常を深く感じ、帝がもう少し成長したら出家をしたいと密かに考えていた。若くして高い地位に就いた者は長く幸福でいられないという古例を思い、自分も過分な地位を得たことに危機感を抱いていた。須磨や明石での苦難の日々を経て今に至る運命を振り返り、今後も順風満帆でいることは長命を損なうと考えていたのだ。そこで、郊外に寺院を建て、仏像や経典も準備しつつあった。しかし一方で、子供たちを立派な人物や優れた女性に育てたいという思いも捨てきれず、出家への願望と子供たちへの責任との間で揺れ動いていた。どちらが本当の源氏の心なのか、自分でも分からないままでいた。(完)明日より18帖 松風(まつかぜ) を公開予定。
2025.01.19
コメント(23)
-

源氏物語〔17帖 絵合 7〕
源氏物語〔17帖 絵合 7〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語17帖 絵合 (えあわせ) の研鑽」を公開してます。彼は幼少時から学問に励んでいたが、院は源氏の詩文への傾倒を見て「文学に傾きすぎると、長寿と幸福を兼ね備えた者は少ない。十分な身分があるのだから、名誉を求める必要はない」と忠告したという。それ以来、源氏は幅広く学問を修めたものの、特に秀でた分野はなかったと自省する。しかし絵を描くことだけは心から没頭し、満足するまで描きたいという思いを持ち続けていた。須磨への流謫の際に大自然の美しさに触れ、多くの題材に恵まれたものの、自分の技量では理想を描ききれず、その作品を披露するのは恥ずかしいとも感じていた。今回のような機会に持ち出すことについても、突飛だと思われないかと気がかりだった。これに対して帥の宮は、芸事は頭脳の優秀さも必要だが、師匠に学べば誰でも一定の水準には達すると語る。しかし、字を書くことと囲碁に関しては、特に習わなくても才能を発揮する者が現れることがあるとし、貴族の中でも飛び抜けた才能を持つ者が出ることを指摘する。院は親王や内親王に多くの芸を教えたが、源氏には特に力を入れて指導し、源氏も熱心に学んだため、詩文をはじめとして琴、横笛、琵琶、十三絃に至るまで高い技術を身につけたと賞賛する。絵に関しては単なる趣味だと思っていたが、あまりにも見事な出来栄えに、専門の画家たちが恥じてしまうほどの傑作だと感嘆し、それほどの技術を見せつけるのは、逆に「けしからんことだ」と冗談めかして述べた。宮は最後には冗談を交えたものの、酔いの影響もあってか故院の話を思い出し、次第にしみじみとした表情になった。夜空には二十日過ぎの月が出ていたが、その光はまだ届かず、静かで澄んだ明るさだけが広がっていた。書司に保管されていた楽器が持ち寄られ、中納言が和琴を弾く役を務めた。その腕前は見事で、聴く者を驚かせるほどの名演だった。帥の宮は十三絃を担当し、源氏は琴を奏で、琵琶は少将の命婦に任された。殿上の役人たちの中から音楽に通じた者が拍子を取る役を務め、見事な合奏となった。やがて夜が明け、桜の花や人々の顔がほのかに浮かび上がり、小鳥たちのさえずりも聞こえ始め、美しい朝の情景が広がった。
2025.01.18
コメント(24)
-

源氏物語〔17帖 絵合 6〕
源氏物語〔17帖 絵合 6〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語17帖 絵合 (えあわせ) の研鑽」を公開してます。右側は沈香の木箱に浅香の台、青地の高麗錦を用いた装飾で、侍童は青色の衣に柳色の装束をまとっていた。双方の代表である源氏と権中納言が御前に進み出ると、太宰帥の宮も審判役として招かれた。この宮は芸術、とりわけ絵画に造詣が深く、源氏があらかじめこの話を伝えていた人物であった。彼が審判を任され、多くの精巧な絵巻が披露されたが、その優劣をすぐに決めることは困難だった。四季を題材にした絵も出品され、伝統的な名画に匹敵する現代の作品も少なくなく、それぞれの作品が持つ現代性や新しい魅力について真剣に論じ合われた。女院も襖を開けて朝餉の間に現れ、絵の鑑識に自信を持つ姿が見受けられた。判者が判断に迷うと、女院に意見を求め、短いながらも的確な言葉が下され、その一言一言に深い趣が感じられた。源氏は女院の審美眼を尊敬し、彼女の存在自体をありがたく思っていた。会場全体が絵画と文学への情熱に包まれ、宮廷文化の華やかさと知的な競争の魅力が最高潮に達していた。左右の勝敗が決まらないまま夜が更けていった。最後の番になり、左方から須磨の巻が出されると、中納言の胸中はざわめきだした。右方も最後に備えて素晴らしい絵巻を用意していたが、源氏が清澄な境地で描いた風景画は、他の追随を許さない圧倒的なものだった。判者である親王をはじめ、誰もがその絵を見て涙を流した。想像の中の須磨よりも、絵に描かれた須磨の浦の暮らしはさらに悲哀に満ち、描き手の感情が豊かに表れていた。絵は見る者をその時代に引き戻すような力を持ち、須磨から望む海の景色や、寂しい住まい、沿岸の崎々までが鮮やかに描き出されていた。さらに、草書と仮名混じりの文章がところどころに添えられ、胸に沁みる歌も含まれていた。その美しさと情感に、誰もが他の絵の存在を忘れてしまい、心を奪われた。そして、圧巻はこれであると判断され、左方の勝利が決定した。明け方近く、古い思い出に浸り、心を湿らせていた源氏は杯を手にしながら帥の宮に語り始めた。
2025.01.17
コメント(23)
-

源氏物語〔17帖 絵合 5〕
源氏物語〔17帖 絵合 5〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語17帖 絵合 (えあわせ) の研鑽」を公開してます。最初の議題は『竹取物語』と『俊蔭』であった。左側は、赫耶姫の性格に人間の理想が暗示されていることを強調し、物語の古典的価値を評価した。一方、右側は赫耶姫の天上界が非現実的であり、宮廷描写が欠けていることを批判した。次に『伊勢物語』と他の物語が比較されたが、ここでも意見は分かれた。伊勢物語の深い情緒を擁護する者もいれば、現実の宮廷生活を描いた新しい作品を評価する者もいた。女院は左側の主張に共感を示したものの、議論は白熱し、容易には決着がつかなかった。女房たちは自らの見解を述べ、帝や梅壷の女御の絵が披露される瞬間を待ち望んでいた。源氏もこの場に参内し、双方の熱心な論争を楽しんで聞いていた。宮廷の女性たちがそれぞれの知識と感性を駆使して意見を述べる様子は、まさに宮廷文化の華やかさを象徴しており、彼らの真剣な姿勢が絵画や文学への情熱を物語っていた。絵合わせの最終決戦は、源氏が「御前で勝負を決めよう」と提案したことで、さらに広範な審査を経て行われることになった。源氏は須磨や明石に関する絵を左方の作品群に混ぜており、これに対抗する中納言も新たな傑作を用意するため、自邸で密かに絵を描かせていた。宮廷全体が、絵を制作し収集することに没頭し、それ以外の仕事がないかのような雰囲気に包まれていた。源氏は「新たに作ることよりも、すでに持っている絵の中から優劣を決めるべきだ」と主張していたが、中納言は人知れず新しい絵を次々に完成させていた。院もこの競争を知り、梅壷へ多くの絵を贈った。これらの中には、延喜帝が自ら説明を加えた古い巻物や、自らの時代に行われた華やかな宮廷儀式を描いたものも含まれていた。特に、斎宮発足の日の儀式を描いた絵巻は、公茂画伯に特別に指示して制作された力作であり、沈香の木箱に収められ、精巧な装飾が施されていた。絵合わせ当日、風流な意匠を凝らした包みに収められた左右の絵が会場に持ち込まれた。女官たちの座する控えの間に設けられた臨時の玉座に判者が座し、清涼殿の西側には殿上役人が集まって左右に分かれ、支持する絵を巡って論じ合った。左側は紫檀の箱に収められ、蘇枋の飾り台や紫地の唐錦が敷かれた豪華な装いで、侍童たちも朱色の衣に桜襲の装束をまとい、非常に優美な姿を見せていた。
2025.01.16
コメント(23)
-

源氏物語〔17帖 絵合 4〕
源氏物語〔17帖 絵合 4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語17帖 絵合 (えあわせ) の研鑽」を公開してます。中には長恨歌(中国唐の詩人白居易)や王昭君を題材にしたものもあったが、それらは縁起が良くないと判断し、今回は除外することに決めた。さらに、源氏は過去の旅の途中で日記代わりに描いた絵巻を持ち出し、初めて夫人に見せた。その絵巻は、見る者の感情を揺さぶるほどの力を持つ作品で、源氏と夫人にとっては忘れられない悲しい時代の思い出が詰まっていた。夫人はその絵巻を見ながら、今まで源氏が自分に見せなかったことを恨めしく思い、その気持ちを口にした。源氏自身も、その絵を通じて過去の苦しい記憶を思い起こし、夫人とともに感慨にふけるのだった。宮廷では絵画や文学を巡る競争が熱を帯びていた。源氏と権中納言の間で、互いに美術品を収集し、評価されることに力を注いでいた。特に源氏は、須磨や明石で過ごした時期に関する絵画を大切にしており、彼の思い出と感情がそこに込められていた。夫人は源氏が絵を通じて須磨や明石の記憶を慰めにしていることを理解しつつも、その哀れさに共感していた。源氏は、中宮にも見せるべき絵を選びながら、須磨や明石を描いたものに対して、過去の恋しさを感じずにはいられなかった。その一方で、権中納言も負けじと自宅で画家たちに優れた絵を描かせ、絵巻の装幀にも細部まで凝った作品を作り上げていた。三月の暖かく穏やかな季節で、宮廷では行事も少なく、人々は芸術に集中していた。そのため、絵や文学の傑作を集めて勝負を決めることに強い関心が寄せられた。宮廷には多くの絵巻が集まり、その中でも特に小説を題材にしたものが多かった。これは、見る者が物語の幻想を重ね合わせることで、絵の効果が倍増するためである。梅壷の女御の作品は古典的で価値の高い物語を題材にしており、弘徽殿の作品は新しい話題性のあるものが多く、見た目にも華やかであった。宮廷内では、典侍や命婦たちが絵の価値を巡って激しい議論を繰り広げ、女院もこれを興味深く見守った。絵の鑑賞会は左右に分かれて行われた。梅壷方は左に位置し、平典侍や少将の命婦などが主張を展開した。右側には大弐の典侍や兵衛の命婦が並び、いずれも宮廷内で知識人として認められている女性たちであった。
2025.01.15
コメント(25)
-

源氏物語〔17帖 絵合 3〕
源氏物語〔17帖 絵合 3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語17帖 絵合 (えあわせ) の研鑽」を公開してます。源氏は、この光景を見ながら、もし斎宮の母である御息所が生きていればどれほど喜んだだろうかと思いを巡らせた。聡明で後見役としても優れていた御息所を失ったことは、単なる恋人の喪失以上に、この世の大きな損失であると感じていた。どんなに洗練された女性であっても、あれほどの品格と才知を持つ人は他にいないと、源氏は折に触れて御息所を思い出しては、その存在の大きさを噛み締めていたのである。宮廷にはすでに二人の女御がいる状況だったため、兵部卿の宮は自分の娘である女王を後宮に入れることが難しいと感じ、悶々としていた。しかし、帝が成長して成人すれば、自分の娘を外戚として疎外することはないだろうと希望を捨てずにいた。その一方で、宮廷内では二人の女御が華やかに競い合い、それぞれの魅力を帝に示そうとしていた。帝は特に絵に強い関心を持ち、自身でも絵を描くことを好んでいた。そのため、絵を得意とする斎宮の女御に対する寵愛は自然と深まった。斎宮の女御は美しいだけでなく、雅な絵を描く才能を持っており、帝は彼女とともに絵を描く時間を楽しんだ。特に、女御が寝そべりながら次の筆の動きを考える姿が愛らしく、帝の心を強く惹きつけた。これがきっかけで、帝は頻繁に彼女のもとを訪れるようになり、その寵愛は日に日に増していった。その一方で、権中納言は負けず嫌いな性格から、自宅に有名な画家を抱え込んで絵を描かせていた。彼は「小説を題材にした絵が最も面白い」と考え、文学的な詞書きをつけた絵を帝に献上した。その作品は非常に芸術的価値が高く、帝も関心を示したが、権中納言はその絵を大切にしすぎて、長時間帝の前に出さずにしまい込んでしまうことがあった。帝が斎宮の女御にその絵を見せたがった時も、弘徽殿の女房たちはそれを阻止しようとした。このことを知った源氏は、「権中納言の競争心は今も衰えないようだ」と笑い、「大切な絵を隠して帝を困らせるのはけしからん」と批判した。そして帝に対して、「私の所にも古い絵がたくさんあるので差し上げましょう」と申し出た。そこで源氏は二条の院に保管していた古い絵や新しい絵を整理し、夫人と共にそれらを見分けた。
2025.01.14
コメント(26)
-

源氏物語〔17帖 絵合 2〕
源氏物語〔17帖 絵合 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語17帖 絵合 (えあわせ) の研鑽」を公開してます。前斎宮の入内を巡る状況は、さまざまな人物の思惑や複雑な感情が絡み合って進行していた。女院は、この入内を熱心に推し進めていたものの、細々とした準備や必要な品々を整える役目を担う者がいないことを源氏は気の毒に感じていた。しかし、院に対する遠慮から、二条の院への移動も取りやめ、自身はあくまで傍観者のように振る舞いつつ、実際には事の大半を取り仕切っていた。院はこの状況を残念に思いつつも、敗者は沈黙するべきだと考え、手紙を送ることも控えていた。ところが入内当日、院から豪奢な贈り物が届いた。衣服や香箱、そして数種類の薫香が揃えられた乱れ箱など、どれも精巧で心のこもった品々である。それらは源氏が目にすることを想定して用意されたものであり、女別当がそれらを報告すると、源氏は櫛の箱だけを特に丁寧に見た。その櫛の箱には美しい装飾と共に和歌が添えられており、源氏はその歌に心を打たれた。「別れ路に添えた小櫛を今となっては遠いものと神が戒めるように」と詠まれたその歌に、源氏は自分の過去の苦しい恋を重ね合わせ、院の心情を思いやり、深く胸を痛めた。斎宮として伊勢に下った時に始まった恋が、今になってもなお院の心に残っていることを感じ取ると、その心中を察して苦しさが募った。源氏自身も、なぜ彼女を宮中に入れるという考えを持ったのかと後悔の念に駆られたこともあったが、院の心の優しさや人情深さを思い返し、深いため息をついて考え込んでしまうのだった。一方、斎宮は気分がすぐれず、院からの和歌への返歌をしようとしない。女房たちは「返事をしないのは失礼です」と促すが、彼女は恥ずかしさから筆を取れずにいた。源氏も返歌の必要性を説き、「少しだけでもよいから書くように」と言うが、それすらも斎宮にとっては気が重かった。彼女はかつて帝との別れを惜しんだ日々を思い出し、涙を流す帝の姿や母親のことを懐かしんで悲しんだ。そして、返歌として「別れの際に交わした言葉が今となって悲しい」とだけ書き、控えめに思いを伝えた。宮中の準備は着々と進み、かつて実家に引きこもりがちだった女房たちも次々と戻り、華やかな女御の姿が整いつつあった。
2025.01.13
コメント(24)
-

源氏物語〔17帖 絵合 1〕
源氏物語〔17帖 絵合 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語17帖 絵合 (えあわせ) の研鑽」を公開してます。源氏物語 17帖「絵合(えあわせ)」は、光源氏が須磨・明石での流謫生活を終え、六条院を完成させた後の話で、絵をめぐる宮廷内の競い合いや、人間関係の複雑さが描かれる。六条院には、東西南北の四つの対(棟)があり、それぞれに季節が象徴されている。源氏は、自分の周囲に多くの女性たちを配し、それぞれの棟に住まわせている。そのうちの一人、秋好中宮(あきこのむね)は秋の町に住んでいて、源氏の異母弟である冷泉帝(光源氏の実子)が后に迎えた女性だ。彼女は藤壺の姪にあたるため、源氏にとっては特別な存在。物語の中心は、絵合わせ(絵を比較して優劣を競う遊び)にまつわる物語。六条院に集まった貴族たちが、秋好中宮と源氏の養女である明石の姫君(のちの明石中宮)の間で、所蔵している絵の優劣を競うことになる。秋好中宮の陣営には、彼女を支持する貴族や女性たちが集まり、洗練された美しい絵巻物を揃えた。一方、明石の姫君側には、源氏自身が支援して絵を提供し、その中には須磨・明石での自身の経験を描かせたものも含まれていた。競技は単なる娯楽ではなく、それぞれの女性に対する源氏の感情や社会的地位が反映される象徴的なものだった。秋好中宮の絵は技巧に優れていたものの、明石の姫君の絵には源氏の須磨・明石での苦難や情感が込められており、見る者の心を打った。最終的には、明石の姫君の絵が勝利する。この結果は、源氏が自らの苦難の時期を忘れず、それを乗り越えたことを誇りに思っていること、そして明石の姫君を後ろ盾として大切にしていることを示している。この絵合では、源氏とその周囲の女性たちの微妙な関係や感情が浮き彫りになる。秋好中宮は格式や教養の面で非常に高い評価を受けていたが、源氏にとっては明石の姫君の方が特別な存在であることが暗に示される。また、当時の貴族社会において「絵合」などの文化的競技が、単なる芸術鑑賞を超えて、権力や愛情の力関係を表現する重要な儀式だったこともわかる。「絵合」は一見華やかな競技の場面だが、その裏には、源氏の女性たちへの思い、過去の苦難、そして宮廷内の複雑な力関係が巧みに織り込まれている。
2025.01.12
コメント(26)
-

源氏物語〔15帖 蓬生 13 完〕
源氏物語〔15帖 蓬生 13 完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語15帖 蓬生(よもぎう) の研鑽」を公開してます。源氏の思いやりと力添えによって、末摘花の宮邸は次第に活気を取り戻していく。手入れが行き届き、庭の草木も美しく整えられ、流れには水が通るようになり、かつて荒れ果てていた景色は一変した。家司の中には、源氏の手厚い世話を見て、ぜひ仕えたいと申し出る者も現れ、執事も置かれるようになった。末摘花は二年ほどこの宮邸で暮らし、その後は東の院に迎えられた。ただし、源氏と夫婦として同じ部屋で過ごすことはめったになかった。それでも二条の院から近い場所だったため、源氏が他の用事で訪れた際には立ち寄り、言葉を交わすこともあった。その態度に軽蔑の色は微塵もなく、末摘花に対する配慮が感じられた。大弐の夫人が帰京した際には、末摘花の変わりように驚いたという。侍従もまた、末摘花の幸福を喜びつつ、自分が彼女を見捨てたことを深く後悔した。こうしたエピソードもさらに詳しく書きたいところだが、紫式部は頭痛がしてきたため、また別の機会に思い出して綴ることにしようとある。(完)明日より17帖 絵合(えあわせ) を公開予定。
2025.01.11
コメント(24)
-

源氏物語〔15帖 蓬生 12〕
源氏物語〔15帖 蓬生 12〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語15帖 蓬生(よもぎう) の研鑽」を公開してます。花散里を訪ねた時のことも思い出した。彼女は派手さこそなかったが、静かで美しい女性であった。そのため、今ここにいる末摘花の容姿が劣ると比較することもなく、穏やかな心で向き合えたのだと、源氏はしみじみと思うのであった。賀茂祭りや斎院の御禊の時期になると、その準備のためにと称して、各地からさまざまな品々が源氏のもとに届けられた。源氏はそれをただ受け取るだけでなく、丁寧にあちこちへ分配していた。その中でも特に常陸の宮への贈り物には、源氏自身が細かく気を配り、宮邸に不足しているものを補うよう多くの品を加えて送っていた。さらに親しい家司に命じて下男を派遣し、宮邸の手入れをさせた。庭の蓬を刈り、応急的に板塀を設けるなど、細かなところまで手を尽くしている。しかし、源氏自身が直接訪れることはなかった。彼が末摘花を妻として世間に認められるのは不名誉だと感じていたからだ。それでも手紙は頻繁に送り、細やかな気遣いを欠かさなかった。また、二条の院の近くに建築中の新しい家について、末摘花に知らせていた。「そこにあなたを迎えようと思っている。今のうちに、童女として使うのにふさわしい子供を選び、慣らしておくといい」と手紙に書き添えた。女房たちへの衣服や必要な品々も忘れずに届け、その細やかな配慮に女房たちは感謝し、二条の院に向かって手を合わせるほどだった。源氏は一時的な恋では決して平凡な女性を相手にしないことで知られていた。しかし、何の特長もない末摘花をなぜこれほど大切に扱うのか、不思議に思う者も少なくなかった。それは前世からの因縁に違いない、と人々は噂した。かつて見切りをつけてこの家を去った召使たちも、源氏の援助を知ると再び仕えたいと願い出た。末摘花は善良な性格で、もとに仕えていた女房たちは、地方官の家に移った後の窮屈な暮らしに嫌気がさし、次々と戻ってきた。
2025.01.10
コメント(23)
-

源氏物語〔15帖 蓬生 11〕
源氏物語〔15帖 蓬生 11〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語15帖 蓬生(よもぎう) の研鑽」を公開してます。「こんな草原の中で待っていてくれたあなたの気持ちを思うと、幸せだと感じるよ。そして、私もあなたの最近の気持ちを聞いてはいないけれど、自分の愛を信じて訪ねてきたんだ。どう思ってくれるだろうね。これまであなたを苦しめてきたことも、私が本心からしたことではなく、その時々の世の中の事情がそうさせたのだと思って、どうか許してほしい。これからの私は、誠実さを欠くようなことはしないつもりだ。もしそんなことがあれば、その時は責任をすべて取るからね」と、彼の言葉は情に溢れ、彼女の心を強く揺さぶる。しかし、泊まっていくことはできなかった。荒れ果てた屋敷と今の自分の立場とがあまりにも調和しないと感じ、帰ることを決めた。屋敷の庭に立つ松の木を見上げると、かつて自分が植えたものではないが、年月を経て高く成長しているのが目に入り、その姿に時の流れと自身の境遇を重ね合わせた。思わず口をついて出た歌は、「藤波の打ち過ぎがたく見えつるはまつこそ宿のしるしなりけれ」。時の流れの長さと、その切なさがこみ上げる。「数えてみれば、本当に長い月日が経ったものだね。物哀れになるよ。今度また、悲しかった旅の話でもゆっくり聞かせに来るよ。あなたも、これまでの苦労を私に聞かせてほしい。きっと誰にも話せなかったことがたくさんあるだろうから」と言うと、女王は静かな声で歌を返した。「年を経て待つしるしなきわが宿は花のたよりに過ぎぬばかりか」。その控えめな言葉に、源氏は彼女の深い心情を感じ取り、袖の香りや佇まいも、昔よりもずっと美しく思えた。月の光が西の妻戸から差し込み、廊下はすでに朽ち果てているが、室内が明るく照らし出された。荒れた外観とは裏腹に、室内の飾りは昔のままに保たれ、何とも風流に見えた。古い物語に、親の建てた堂を壊す話があったが、ここではそれとは逆に、親が残したものを大切に守り続ける姿に心を引かれる。彼女の恥じらいの多い性格も、さすがは気高い人だと源氏は改めて感じ、この人を「変わり者の愛人」として忘れていたことを申し訳なく思った。
2025.01.09
コメント(27)
-

源氏物語〔15帖 蓬生 10〕
源氏物語〔15帖 蓬生 10〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語15帖 蓬生(よもぎう) の研鑽」を公開してます。長い間、彼女を放置し自らを責める気持ちになる。そして、こうした機会でもなければ訪れることは難しいと考え、今こそ訪ねるべき時だと思ったが、邸内に足を踏み入れることにはためらいがあった。直接会うよりも先に、歌を詠んで気持ちを伝えたいと考えたが、もし返歌が遅れれば使いが困るだろうと思い、その案は断念する。惟光も、すぐに中に入ることは難しいだろうと感じ、草露を払いながら進むよう提案する。源氏は、その言葉を受けて一首詠んだ後、車を降りる。露に濡れた草を惟光が馬の鞭で払いながら案内し、木の枝からは雫が落ち、まるで秋の時雨のようだった。惟光は冗談めかして、「木の下の露は雨よりもひどいですね」と言うが、源氏の衣服はすでにかなり濡れていた。かつての中門はすっかり姿を消し、屋敷の中へ入ることにも躊躇するほどの荒れようである。一方、女王は源氏が訪ねてきたことを嬉しく思いながらも、その姿を前にして恥じらいを感じる。以前、大弐の夫人から贈られた衣服は気に入らず、放置していたが、女房たちが香を焚き込めたその衣を渋々着替えることになった。そして、煤けた几帳を引き寄せて座り、源氏を迎える。源氏は席に着くと、懐かしさと共に語りかける。「長い間会えなくても、ずっとあなたを思っていた。ただ、あなたから何の便りもなかったので、恨めしく思い、わざと冷淡にしていたのです。でも、この場所を目にしたら、通り過ぎることはできなかった」と、本心を打ち明ける。几帳を少し開くと、女王は恥じらいながら座っており、返事をすぐには返さない。しかし、源氏の思いやりに胸を打たれ、心を奮い立たせるようにして、ようやく口を開くのであった。源氏は、目の前に広がる草原の中でひっそりと待ち続けていた彼女の姿に、深い幸福感を覚えた。彼女が他の希望を持たずに、自分を信じて待っていてくれたことが何よりも嬉しかった。そんな気持ちを胸に、彼は穏やかに語りかける。
2025.01.08
コメント(20)
-

源氏物語〔15帖 蓬生 9〕
源氏物語〔15帖 蓬生 9〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語15帖 蓬生(よもぎう) の研鑽」を公開してます。その余韻に浸りながら雨漏りで濡れた廂(ひさし)の下を拭かせたり、部屋の片付けを指示したりしていた。ふと歌を詠みたくなり、次のような和歌を作っていた。「亡き人を恋ふる袂のほどなきに荒れたる軒の雫さへ添ふ」その頃、源氏の車が門の前に止まった。惟光は邸内に入り、人の気配を探してあちらこちらを見回る。しかし、人の姿や物音はなく、やはり無人のように思えた。ところが月明かりに照らされて、格子が少し開いていることに気づき、そこに人の気配を感じる。恐る恐る近づいて声をかけると、老人らしい咳の後に女性が応答する。「どなたですか?」と問われた惟光は自分の名を名乗り、侍従に会いたい旨を伝える。老女は侍従がすでに別の場所へ行ったことを伝え、代わりに侍従の仲間がいると答えた。その声には聞き覚えがあり、昔よりも老け込んだ印象を受ける。邸内の女性たちは、惟光の姿を見て一瞬狐か何かではないかと疑ったが、彼が丁寧に源氏の意向を伝えると、笑いながら返答する。「変わっているなら、こんな荒れた邸宅には住んでいないはず。私たちは苦しみを経験しながら今日まで待っていたのです」と、無念さと諦めが滲む返事をした。さらに彼女たちはもっと話したそうにしていたが、惟光は迷惑に感じ、「わかりました。そう伝えます」と言い残して邸を後にした。源氏は、長く訪れなかった場所を見渡し、荒れ果てた様子に心を動かされる。昔の面影を探そうとしても、草深く蓬が茂るばかりの景色に、「ここがあの懐かしい場所なのか」と疑うほどである。そんな中で、彼は惟光に報告を求めた。惟光は、ここまでの経緯を語り出し、ようやく一人の老人を見つけたことを説明する。その老人は、かつての侍従の叔母で少将と呼ばれていた人物で、昔と変わらぬ声で語りかけてきたという。惟光はさらに、屋敷内の荒廃した様子を細かく伝えた。源氏はその話を聞きながら、心の中で深い哀れみを感じた。この廃れた屋敷に、どのような思いで女王が暮らしているのだろうか。自分は長い間、彼女を放置していたのだと自らを責める気持ちになる。そして、こうした機会でもなければ訪れることは難しいと考え、今こそ訪ねるべき時だと思った。
2025.01.07
コメント(24)
-

源氏物語〔15帖 蓬生 8〕
源氏物語〔15帖 蓬生 8〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語15帖 蓬生(よもぎう) の研鑽」を公開してます。ほかの場所では雪が解けている時もあるが、末摘花の屋敷では枯れた雑草の陰に深く雪が積もり、その量は増すばかり。まるで越の白山が庭に現れたかのような光景だった。屋敷には今や出入りする下男すらいない。末摘花は、ひっそりと寂しい日々を過ごしていた。以前は侍従と泣き合い、笑い合うこともあったが、彼女が去ってからは夜の帳台の中で、ただ一人寂しく過ごすばかりだった。一方、源氏は念願の紫の上のもとに戻り、満足感に満たされていた。そのため、他の恋人のところへは足が向かず、末摘花のことも時々思い出す程度で、捜し出そうとはしなかった。そうこうしているうちに、その年も暮れていった。四月になり、源氏は花散里を訪ねたくなり、紫の上の了承を得て二条の院を出ることにした。幾日か続いた雨が上がり、残り雨がまだ少し降った後、月が顔を出した。源氏は青春時代の忍び歩きを思い出すような艶やかな月夜に、車の中で昔を回想しながら移動していた。やがて、荒れ果てた邸宅の前にたどり着く。そこには大木が森のように生い茂り、高い松に絡まった藤の花が月明かりに揺れていた。その香りが風に乗って懐かしく漂ってくる。橘の花とは異なるその香りに惹かれ、源氏は車から顔を少し出して周囲を眺めた。そこには、長く垂れた柳が自由に風に乱れ、土塀すらないほど荒れ果てた様子だった。見覚えのある木立に、源氏はここがかつての常陸の宮邸であることに気づく。物哀れな気持ちが胸に込み上げ、車を止めさせることにした。付き添っていたのは惟光で、彼はこのような微行(目立たぬ外出)には慣れている男であり、源氏に常に付き従っていた。源氏は車の中から、荒れ果てた邸宅を見て「ここは常陸の宮だったね」とつぶやく。惟光がそれを肯定すると、源氏は「まだここに住んでいる人がいるかもしれない。機会がある今、訪ねてみよう」と指示を出し、惟光に邸内の様子を探らせた。邸内では末摘花が寂しい日々を送っていた。初夏の物憂い昼間、彼女はうたた寝の夢で亡き父宮を見て目を覚ました。
2025.01.06
コメント(28)
-

源氏物語〔15帖 蓬生 7〕
源氏物語〔15帖 蓬生 7〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語15帖 蓬生(よもぎう) の研鑽」を公開してます。侍従も泣く泣く女王に別れを告げる。「今日は送りだけでもお供します。夫人が言うこともわかりますし、あなたが行きたくないのも理解できます。でも私も辛くてなりません」侍従までもが去ろうとする状況に、末摘花は深く悲しみ、恨めしい思いを抱きながらも引き止めることはできず、ただ涙を流すばかりだった。末摘花は、侍従に形見として何かを贈りたかったが、長い年月のために衣服はすっかり悪くなっていた。そこで、自分の抜け毛を集めて作った九尺ほどの美しい鬘を、雅な箱に入れ、昔の薫香を添えて贈ることにした。その際、涙を浮かべながら歌を詠んだ。「絶ゆまじきすぢを頼みし玉かづら思ひのほかにかけ離れぬる」乳母の遺言もあり、つまらない自分だけれど一生世話をしたいと思っていた。しかし、侍従が去ることに対して恨めしい気持ちを隠せない。末摘花は悲しみに耐えられず、大粒の涙を流しながら訴えた。「私を捨てるのはもっともだけれど、誰があなたの代わりになって私を慰めてくれるのだろう」侍従も涙で言葉が詰まる。「乳母の言葉はもちろん、長い間一緒に苦労してきたのに、遠い地へ行くことになるとは思いもしなかった」さらに、侍従も歌を詠む。「玉かづら絶えてもやまじ行く道のたむけの神もかけて誓はん(姫との縁は決して終わることはなく、これから行く道のたむけの神に願をかけてお誓いします)」命がある限り、誠意を尽くすつもりだと約束する。しかし、大弐の夫人は待ちきれず、侍従に向かって急ぐように小言を言う。侍従は涙を拭い、車に乗り込んでしまう。侍従が去る後ろ姿を見つめながら、末摘花の孤独感はさらに深まる。長年共に過ごしてきた侍従までが去ったことで、女王はますます心細くなった。さらに、老いた女房たちまでもが不満を漏らし始める。「こんな状況ではどうしようもない。私たちだって我慢の限界だ」女房たちは次々と他の雇い先を探し始める様子を見せ、去ることを決意しているらしい。その会話を耳にする度に、末摘花は深く傷つき、絶望的な気持ちに襲われるのだった。十一月に入り、雪や霙(みぞれ)が降る日が多くなった。
2025.01.05
コメント(27)
-

源氏物語〔15帖 蓬生 6〕
源氏物語〔15帖 蓬生 6〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語15帖 蓬生(よもぎう) の研鑽」を公開してます。草ぼうぼうの中を通り、かろうじて見つけた細い道を進んで建物の南向きの縁側に牛車をつけた。末摘花は困惑しながら侍従を応接に出した。侍従は煤けた几帳を押し出し、夫人を迎えた。容貌は以前に比べてかなり衰えていたが、それでもやつれた中に美しさが残っていた。夫人はそんな侍従の姿を見て、「この美しさを女王の顔に代えたいくらいだ」と内心思った。大弐の夫人は、出発を控えていることを伝えつつ、心配している様子を見せながら訪ねてきた。侍従を迎えに来たことを説明し、女王には同行する意思がないことを理解しつつも、せめて侍従だけでも九州へ連れて行きたいと申し出た。表面上は同情的な態度を取っているが、実際のところ、夫人自身は長官夫人としての新たな生活への期待に胸を膨らませている。夫人は過去の関係についても触れた。「宮様がいらした頃、私の結婚相手が悪かったために、こちらとも疎遠になってしまいました。でもその後は、源氏の大将との縁もあって晴れがましく、かえってお邪魔しづらくなっていました。人間、幸せなことばかりではありませんね。私たちのような階級の者は、その点、気楽なのです。遠くに行くことになるので、あなたのことが心配でなりません」女王は静かに答えた。「好意はありがたいですが、私は人並みの人間にもなれないので、このままここで死んでいくのが似合っているでしょう」夫人はさらに続けた。「あなたがそう思うのも無理はありません。でも、こんなひどい暮らしをしている人は他にいないでしょう。大将さんが修繕してくれれば、また立派な屋敷になるでしょうに。近頃はどうしたことでしょうね、兵部卿の宮の姫君以外、みんな遠ざけてしまったようですし。昔はいろんな恋愛関係をお持ちだったのに、それもすっかり清算してしまったとか。あなたのように操を立てて待っていても、今さら受け入れてくれるとは思えないのでは?」この言葉に、末摘花は深く傷つき、涙を流した。しかし九州行きにはどうしても応じようとしない。夫人は侍従だけでも同行させようと促し、日が暮れる中でせきたてた。
2025.01.04
コメント(25)
-

源氏物語〔15帖 蓬生 5〕
源氏物語〔15帖 蓬生 5〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語15帖 蓬生(よもぎう) の研鑽」を公開してます。長い年月が経っても、源氏が自分を思い出さないはずはないと信じていた。堅い誓いを交わしたのだから、心が変わるはずはない。自分の生活が源氏の耳に届けば、きっと救ってくれると信じ続けていた。しかし、世間からは捨てられた女と見られているのだろうとも思っていた。邸は荒廃し、家の中は以前よりもさらに荒れ果てていたが、末摘花はわずかな家財道具を売ることも拒んだ。源氏が戻った時に恥ずかしい思いをするからと、貧困に耐えていたのである。気が滅入って泣くことの多い末摘花の姿は、まるで一つの木の実を大事に抱えている仙人のようであり、その姿には異性を惹きつける魅力は皆無だった。気の毒なほどの状況であるため、これ以上の描写は避けるべきだとさえ思えるほどであった。冬が深まるにつれて、女王の暮らしはますます頼りなくなり、悲しみと物思いに沈む日々が続いた。一方、源氏は故院(亡き父帝)のために盛大な八講を催し、都中がその法要で湧き立っていた。集められた僧たちは並の者ではなく、学問や徳行に優れた者ばかりだった。その中には女王の兄である禅師も含まれており、法要の帰りに妹を訪ねてきた。禅師は源氏の八講について語った。「源大納言の八講は、素晴らしいものだったよ。まるでこの世の浄土のような光景だった。音楽や舞楽も見事で、あの方はまるで仏の化身だと思うほどだ」そう言ってすぐに帰っていった。二人は普通の兄妹のように気軽に話す関係ではなく、末摘花も生活苦を訴えることはできなかった。源氏がそんな盛大な法要を催しながら、自分のような不幸な女を見捨てていることが恨めしく思えた。こうした気持ちから、自分はもう顧みられることはないのだろうと諦めの境地に至りつつあった。そんな時、大弐の夫人が突然訪ねてきた。普段はそれほど親しい間柄ではないが、九州に連れて行くために作った衣装を持参し、立派な車に乗って現れた。門を開ける時から目に入るのは荒れ果てた庭で、門の扉はぐらつき、供の者たちが倒れた扉を立て直す騒ぎになった。
2025.01.03
コメント(26)
-

源氏物語〔15帖 蓬生 4〕
源氏物語〔15帖 蓬生 4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語15帖 蓬生(よもぎう) の研鑽」を公開してます。そんな過去の鬱憤もあって、末摘花を自分の娘たちの女房にしたいと考えていた。彼女は古風ではあるが、頼りになる後見役になるだろうと思ったからだ。「私の家へ来て、琴の音を聞かせてください」と誘うが、末摘花は恥ずかしさから応じようとしなかった。叔母はその態度に不満を募らせ、苛立ちを隠さなかった。その後、叔母の夫が九州の大弐に任命されることとなり、娘たちをそれぞれ嫁がせてから夫婦で赴任する準備を進めていた。出発前にも末摘花を連れて行きたいと申し出たが、末摘花は拒み続けた。そのため、叔母はますます不満を募らせ、「なんて憎らしい。あんな藪の中の人が、偉そうにしている」と悪態をついた。やがて、源氏の宥免が決まり、京に戻ることになった。多くの人々が源氏の復活を喜び、忠誠を尽くした者にはそれなりの報償が与えられた。しかし、末摘花だけは何の恩恵も受けず、誰からも思い出されることはなかった。源氏が追放された時、自分一人の不幸のように嘆き悲しんだ末摘花にとって、その無関心は辛いものだった。周囲の人々が源氏の復権を祝う中、彼女だけは孤立したまま、その不公平さに涙するばかりであった。大弐の夫人は、末摘花に対してますます軽蔑的な態度を取った。彼女は、源氏が末摘花を奥方の一人と認めるはずがないと確信していた。仏でさえ罪の軽い者ほど導くものだと言い、末摘花を手に負えない貧乏女と決めつけていた。貴族であった時のように思い上がっていると嘲笑した。夫人は執拗に九州への同行を勧めた。「世の中が辛くなった時、人は旅に出るものだ。田舎を嫌うかもしれないが、楽しく過ごさせてあげる」と巧みに説得を試みた。これに対し、貧乏生活に疲れていた女房たちは、「それが一番良いのに、どうして意地を張り続けるのか」と、末摘花を非難した。侍従も事情があった。大弐の甥の愛人になってしまい、京に残ることができず、九州行きを決めていた。侍従は何度も末摘花に同行を勧めた。「京に残るのは心配だから、九州へ行きましょう」と説得したが、末摘花は頑なに拒んだ。彼女の心の支えは、忘れ去られた源氏への期待だった。
2025.01.02
コメント(25)
-

源氏物語〔32帖 梅枝〕謹賀新年
源氏物語〔32帖 梅枝〕迎春「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語32帖 梅枝(うめがえ) の正月の風情」を公開してます。正月の宮中では、新年を祝うための盛大な儀式が行われ、桐壺帝の時代の宮廷の華やかさと、紫の上や夕霧などが新年を迎える様子が描かれている。元旦に詠まれる和歌や贈り物の梅の枝が描かれ、平安の文化的な儀式の美しさが表現されている。源氏と紫の上との親密な交流や、元旦の晴れやかな雰囲気を背景にした人物関係の描写も重要で心惹かれる。源氏物語の中で紫式部が「梅枝」の巻で、正月という節を通じて宮廷の洗練された文化と人々の微妙な感情が語られている。元旦は単なる時間の節目ではなく、雅やかな儀式や交流を通じて、人生や人間関係の深まりを描くための重要な舞台として機能している。
2025.01.01
コメント(32)
-

源氏物語〔15帖 蓬生 3〕
源氏物語〔15帖 蓬生 3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語15帖 蓬生(よもぎう) の研鑽」を公開してます。普通なら、古い書物や小説を読み、心を慰めることで、孤独や退屈を紛らわせることもできる。しかし、この女王にはそうした趣味はなかった。他の女性たちのように手紙を書き交わすこともなく、友人も持たなかった。友情を深めることで、自然の美しさや日々の暮らしに慰めを見出すこともできたはずだが、末摘花は父宮が生きていた頃と同じ心持ちのままで、誰とも交際しようとしなかった。親戚であっても、手紙を送ることもなく、関係を深めようとはしない態度が際立っていた。古びた書物棚から取り出すのは、『唐守』や『藐姑射の刀自』、『赫耶姫物語』など、古い物語の絵であった。現代の婦人が好むような新しい物語には目もくれず、湿り気を帯びた古紙や檀紙に書き抜かれた、誰もが知っているような古い歌を眺めては時間を過ごしていた。古歌の優れた作品を選び、作者名を添えて鑑賞することもしない。物思いにふける時に、ただ古い書物を広げるだけであった。現代の女性たちが経を読んだり、仏に勤めたりすることも、この女王には無縁だった。数珠を手にすることもなく、そうした行為を生意気とさえ思っていた節がある。末摘花の生活は、古典的で閉ざされたものであり、父宮を偲ぶ心だけが、この荒れ果てた邸に彼女を縛りつけていた。末摘花の邸には、侍従という乳母の娘が女房の一人として残っていた。この侍従は、かつて斎院に半分ずつ仕えていたが、その斎院が亡くなってからは、やむを得ず別の勤め先を見つけた。侍従の母の妹は、地方官の妻となっていて、身分の違いを気にしない家だったので、侍従も時々そこへ通って仕事をしていた。末摘花は他人との交際を避ける性格で、叔母との関係も冷たかった。叔母は時折、侍従を通じて手紙を送ってきたが、その内容は辛辣で、「姉は私を軽蔑していたから、姫君が孤立しても助けない」というような皮肉を侍従に言わせていた。この叔母はもともと貴族の出でありながら、地方官の妻として生きる運命を受け入れ、卑屈な性格になっていた。
2024.12.31
コメント(27)
-

源氏物語〔15帖 蓬生 2〕
源氏物語〔15帖 蓬生 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語15帖 蓬生(よもぎう) の研鑽」を公開してます。「そんなことをしたら大変なことになる。世間の目もあるし、私が生きている間にこの邸を他人に渡すわけにはいかない。荒れ果てていて怖い場所だとしても、お父様の魂がここに残っていると思うと、心が慰められるのだから」女王は涙を流しながらこう語り、女房たちの進言を頑なに拒絶する。屋敷に残る手道具や骨董品は、価値を知る者たちが手に入れたいと申し出てくることもあった。それらの品々を売ってしまえば、今の窮状を少しは凌ぐことができるかもしれないと、女房たちは説得を試みる。「もう仕方ありませんよ。困れば道具を手放すしかありません。」しかし、末摘花はそれにも断固として反対する。「私のために作られた物を、他の家の飾りにするなんて考えられない。お父様の心を無視することになる。そんなことをすれば、お父様がかわいそう。」彼女には、頼れる人がほとんどいなかった。兄の禅師だけが、たまに山から京へ出てきた時に訪れることがあったが、その兄も古風な性格で、世俗的な生活能力はまるでない。庭の雑草を払うことすら気づかないほど、浮世離れした僧であった。庭は浅茅が生い茂り、蓬は軒先の高さにまで達し、葎が西門や東門を覆い隠してしまった。土塀は崩れ、牛や馬が踏み荒らすようになり、春や夏には牧童たちが無遠慮に放牧にやってくる。邸の荒廃は進み、もはや見る影もない状況であった。八月に強い野分が吹き荒れてから、邸内はさらに荒廃が進んでいた。廊下は倒れたままで、下屋の板葺きの建物は骨組みだけが残り、住む者もなくなった。台所から煙が立つこともなく、人が住んでいることさえ悲しく思われるような邸となっていた。盗賊たちも、この荒れ果てた見た目に魅力を感じず、ここを避けて通るほどであった。そんな荒廃した邸の中でも、寝殿だけは昔の装飾がそのまま残っていた。しかし、掃除をする者もなく、埃が積もり、物は揃っているものの、手入れの行き届かない座敷に末摘花はひっそりと暮らしていた。日々の慰めになるような古歌や物語を楽しむこともなく、物質的な不足を忍ぶような趣味も持っていなかった。
2024.12.30
コメント(24)
全5019件 (5019件中 1-50件目)
-
-

- ◆かわいいペットと泊まれるお宿~◆
- 【オススメお宿】(ペットOK)グラン…
- (2024-08-22 00:41:20)
-
-
-

- 猫のこと ~(=^‥^)
- 保護依頼
- (2025-02-16 22:22:29)
-
-
-

- 猫の里親を求めています。
- *みにゃさんの愛、募集ちぅ-2024年3…
- (2025-01-30 00:32:44)
-