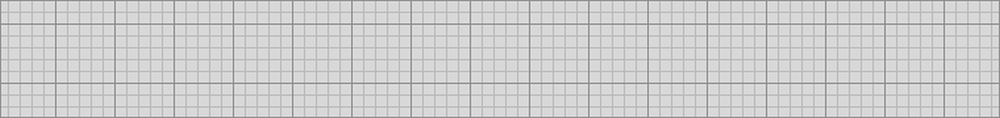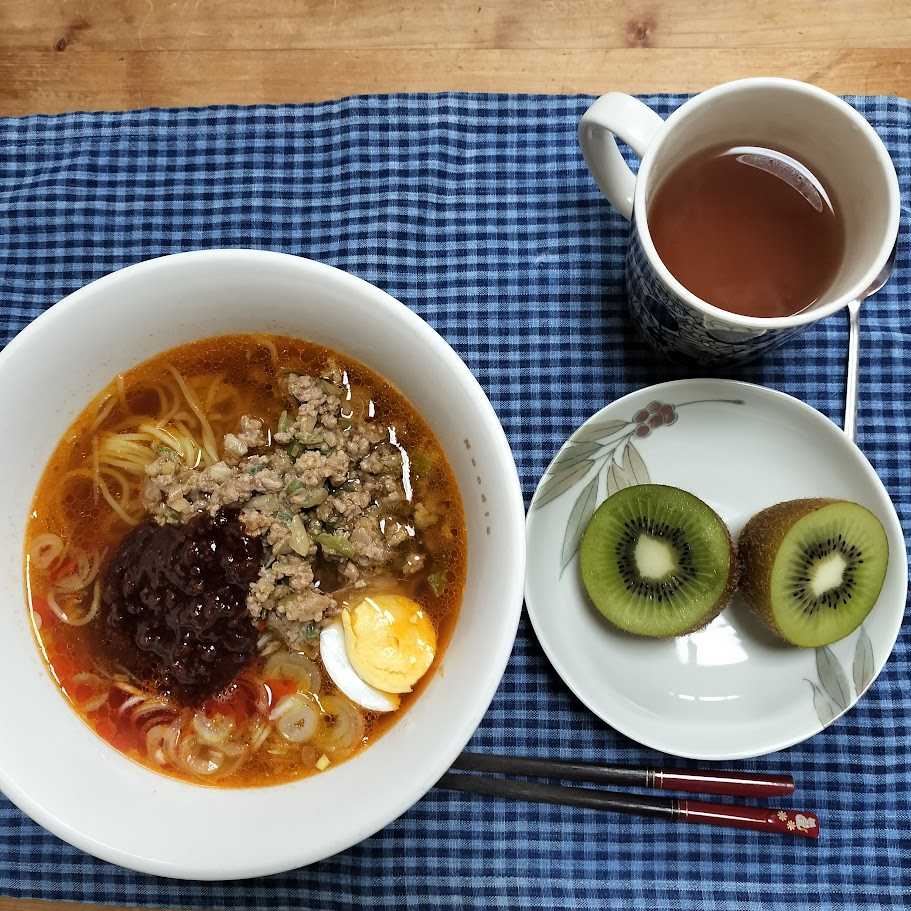全5358件 (5358件中 1-50件目)
-

源氏物語〔34帖 若菜 113〕
源氏物語〔34帖 若菜 113〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。風で外から見えますし、医者のような恰好でそばにいるのは恥ずかしいと軽く注意した。尼君自身は上品に行動しているつもりだが、耳も遠くなり、娘の言葉も「まあいいよと適当にしか聞けない状態だった。尼君は六十五、六歳で、しゃんとした尼姿で上品ではあったが、目は赤く泣きはらしていた。その様子を見て桐壺の方は、昔の源氏の君が明石の浜を去った頃のことを思い出し、はっとした。三月の十日あたり、桐壼の方は無事に男の子を出産した。それまでは安産を願って多くの祈祷が神仏に捧げられていたが、たいした苦しみもなく元気な男児が生まれ、院も安心して喜んだ。もともと出産の間は蔭のような場所で行われており、風流な座敷が並ぶ建物では産養の儀式には不便だったため、南の町に産屋を移す計画が立てられた。紫の女王も出てきて、白い服をまとい母として若宮を抱く姫君はかわいらしく映った。紫夫人は自身に経験がなく、他の女性の出産にも立ち会ったことがなかった。
2026.01.21
コメント(15)
-

源氏物語〔34帖 若菜 112〕
源氏物語〔34帖 若菜 112〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。桐壺の方は自分の身の上が決して欠け目ないものではなかったことを思い返した。養母である夫人の愛に磨かれ、院の娘として尊敬を受ける立場にまでなった自分が、かつて東宮の後宮で他人を劣ったもののように見ていたのは過失だったと反省した。実母が少し低い家の出であることは知っていたが、遠い田舎の家で生まれたとは考えもしなかった。育ち過ぎたために知らなかったことも不思議に思えた。さらに、祖父である入道が仙人のような生活をしている現状も、若い心には悲しいことだった。姫君がいろいろな思いを胸に抱き、寂しげな顔をしているところに明石夫人がやってきた。昼の加持のため、あちらこちらから手伝いの者や僧侶が来て騒がしくしていたが、姫君のそばには尼君だけが得意げに座っていた。明石夫人は、体裁が悪いですよ。短い几帳で体を隠していればいいのにと語った。
2026.01.20
コメント(21)
-

源氏物語〔34帖 若菜 111〕
源氏物語〔34帖 若菜 111〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。明石夫人は桐壼の方が平穏に出産できるかを自身の運命とも信じ、熱心に看護を続けた。老尼である明石入道の尼夫人も、長年姫君に付き添える幸せを感じながら、出産にまつわる昔話を涙まじりに語り、姫君に過去の事情を伝えた。姫君は最初、尼君を無気味な老婆だと思っていた。ただ顔を見つめるだけで距離を置いていた。しかし、実母から「そういう母親もいた」という話を思い出してから、好意を持つようになった。尼君は明石での姫君の誕生や、院が海岸に移ってきた頃の様子を語り、涙を流しながらこのように言った。「京へ戻ったとき、一家の者は縁が切れてしまうと悲しんだが、お姫様が暗い運命から救ってくれたのでありがたい」と。姫君はその話を聞いて泣き、自分がもし尼君の話を聞かなければ、真実を知らずにただ疑いだけで終わっていたかもしれないと思った。
2026.01.19
コメント(23)
-

源氏物語〔34帖 若菜 110〕
源氏物語〔34帖 若菜 110〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。幸運に恵まれていることは、母である夫人と伊勢の御息所双方の誇りと努力が実を結んだ証拠であり、院の大きな愛のもとで二人が立派に育ったことが思い起こされた。大将から院に奉った衣服類は花散里夫人が作り、纏頭の品は三条の若夫人の手によるもので、華やかな催しに参加する者たちに喜びと誇りが分け与えられた。新年になると、六条院では淑景舎の方の出産が近づいたため元日から不断の読経が始められ、諸社寺でも数えきれない祈祷が行われた。院は、かつて葵の上が出産後に亡くなったことから出産の恐ろしさを理解し、少女の身体である桐壼の方が無事に生むことを心配していた。二月になると寝つくほどに苦しむ様子もあり、院も女王も不安を隠せなかった。陰陽師たちの進言により、病室は院外の明石夫人の北の町の対の屋に移され、そこには大きな対の屋二つと廊座敷が幾つもあり、祈祷壇も多数設けられた。評判の良い僧侶たちも集められて祈祷が行われた。
2026.01.18
コメント(24)
-

源氏物語〔34帖 若菜 109〕
源氏物語〔34帖 若菜 109〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。琵琶は兵部卿の宮、院は琴、太政大臣は和琴を奏で、各々の名手が音を響かせた。 六条院では和琴の妙音を久しく聞いていなかった院が、席上で奏でられる和琴の音色に深く感動していた。自らも琴を熱心に弾いていた院は、普段は聞けないような絶妙の音を耳にしてた。昔の話や子息の縁組などで親族関係がさらに深まった二人と酒を重ね、楽しさの頂点に達して酔い泣きするほどだった。贈り物としては、名器の和琴一面と大臣の好む高麗笛、さらに紫檀の箱に唐本や草書の書を入れて、大臣の車に積ませ、馬が受け取ると右馬寮の者が高麗楽を奏した。六衛府の官人には纏頭の品が大将から渡され、質素ながらも自然な華やかさが漂い、宮中や東宮、朱雀院、后宮との関係の深さから六条院はこの際に最も光る家として際立っていた。院は男子が大将ひとりであることに寂しさを覚えたが、その大将が器量よく君主の寵愛を受けた。
2026.01.17
コメント(19)
-

源氏物語〔34帖 若菜 108〕
源氏物語〔34帖 若菜 108〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。聖旨を受けて最高の技術者に製作させ、太政大臣自身も式の場に臨んだ。院はその心遣いに驚きと恐縮を覚えつつ座に着いた。院の席に向かい合う形で太政大臣の座があり、その姿はきれいで堂々と肥え、位人臣の貫禄が感じられる男盛りであった。院はまだ若い源氏の君とともに出席していた。室内の四つの屏風には帝の御筆が貼られており、薄地の支那綾に高雅な下絵が描かれていて、四季の彩色絵よりも立派に見えた。帝の字は光輝くほど美しく、院はその美しさに目を奪われた。室内の置き物や弾き物、吹き物の楽器は蔵人所から供えられた。右大将の勢力も強大であったため、今日の式の華やかさは際立って見えた。左馬寮、右馬寮、六衛府の官人たちにより四十匹の馬が引かれて出され、贈り物の豪華さも目を見張るものであった。夜になり、万歳楽や賀皇恩など形式的な舞が行われたあと、宴の音楽の場が開かれた。太政大臣という音楽の達者も臨場し、誰もがその場の興奮を感じていた。
2026.01.16
コメント(27)
-

源氏物語〔34帖 若菜 107〕
源氏物語〔34帖 若菜 107〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。帝は六条院への好意を表すために予定されていた賀宴を、やむなく中止せざるを得なかった代わりに、そのころ病気で右大将を辞した者の後任として中納言を急に抜擢した。院はその恩に対して礼を述べたが、「突然の御恩命はあまりに過分で、若い彼が職務に耐えられるかどうか疑問です」という謙遜の言葉だった。帝は、右大将を表面的な主催者として、六条院の四十歳の賀の最後の宴を北東の町にある花散里夫人の住居で行わせた。院は派手になることを避けようとしたが、宮中からの内命により行われるこの賀宴は、すべて正式に整えられ、略したところのない立派なものとなった。宴の料理の準備などはいくつか内廷からの手配で行われ、屯食の用意は頭中将の指図で進められた。参列者は親王五人、左右大臣、大納言二人、中納言三人、参議五人、さらに御所の殿上役人、東宮、院の殿上人もほとんどが集まった。院の席やその室に備えられた道具類は、太政大臣が製作させた。
2026.01.15
コメント(19)
-

源氏物語〔34帖 若菜 106〕
源氏物語〔34帖 若菜 106〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。養父の院から深い愛を受けながら、恩返しができなかった自分の思いとともに、前皇太子や母御息所が感謝する志を表そうとしたが、宮中から賀の沙汰を院が辞退された後であったため、大仰なことは避けられた。六条院は、四十の賀は先例から考えると、賀の後長く生きられる人は少ないと語った。今回は内輪のことにして、次回の賀でお志を受けよう」と考え、半公式ながらも派手な賀宴となった。賀宴は六条院の中宮の寝殿で行われ、過去の賀と変わらぬ行き届いた準備がなされていた。高官への纏頭や親王たちへの女装束、非参議の四位・殿上役人への白い細長衣、その他下位の者には巻き絹が下された。院のために整えられた御衣服は華美で見事であり、それに加えて国宝級の石帯や御剣も奉られた。この二品は院の父である前皇太子の遺品であり、院は大いに喜んだ。こうして古い時代の名器や美術品が集まったような賀宴となり、昔の物語で描かれる贈り物の華やかさや善事を思わせる場となった。
2026.01.14
コメント(23)
-

源氏物語〔34帖 若菜 105〕
源氏物語〔34帖 若菜 105〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。席上では音楽が始まり、夜の宴は非常に趣深く面白いものになった。楽器は東宮から差し出され、朱雀院から譲られた琵琶や帝から賜った十三弦の琴などが演奏され、六条院にとって馴染み深い音色が響いた。その音は院に昔の宮廷や懐かしい夢の記憶を呼び起こさせた。もし入道の宮がこの場においでになれば、自分が四十歳の賀を主催して行ったであろうと院は思い返した。しかし今となっては、かつてのように何かを志して見せることは不可能であり、院は深く歎息した。女院を失ったことは、院にとって特別な光を失ったことに等しく、帝もまた寂しく感じていた。帝はせめて六条院だけを最高の地位に置きたいと思われたが、六条院から冗費は国家のため慎むべきとの進言があり、その望みも叶わず、心残りに思われた。十二月二十日過ぎ、中宮が宮中から退出し、六条院の四十歳の残り日を祝う祈祷のため、奈良の七大寺に布四千反を供え、京の四十寺にも絹四百疋を布施した。
2026.01.13
コメント(22)
-

源氏物語〔34帖 若菜 104〕
源氏物語〔34帖 若菜 104〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。日暮れには高麗楽の乱声があり、さらに落蹲の舞も行われた。終盤、権中納言と右衛門督が短い舞を披露したあと、紅葉の中に姿を消すと、観客たちは興味深く見守った。昔の朱雀院の行幸で青海波の舞が絶妙だったことを覚えている人々は、源氏の君や当時の頭中将のように、若い二人の高官が優れた後継者だった。優れた後継者が現れたことに感嘆した。世間からの尊敬も厚く、見た目の美しさや官位の高さも、父たちの世代に勝るとも劣らず、前世からの善果がある家の子息であると祝福された。六条院自身も、そうした光景を見て涙ぐみ、深い追憶に心を動かされた。夜になり、楽人たちが退場すると、紫の上に仕える家職の長が下役たちを率いて現れ、纏頭品の箱から一つずつ取り出して皆に分けた。白い纏頭の服を肩にかけて山ぎわから池の岸へ進む人々の列は、遠目にはまるで鶴の列のように見えた。
2026.01.12
コメント(25)
-

源氏物語〔34帖 若菜 103〕
源氏物語〔34帖 若菜 103〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。宴のために整理され、殿上の役人や五位以上の官人、院に仕える人々の接待所として使われた。寝殿の離れ座敷が式場となり、院用の螺鈿の椅子も設置されていた。西の座敷には衣装の卓が十二卓並べられ、夏冬の服や夜着が積まれており、その上に紫の綾で覆いがされていた。中身が見えないのも趣深かった。椅子の前には置き物の卓が二つあり、支那の羅布の覆いがかけられ、挿頭の台は沈の木に蒔絵で金の鳥が銀の枝に止まる華やかなものだった。これは桐壺の方が手配し、明石の手で仕上げられたため、非常に高雅であった。御座の後ろの四つの屏風は式部卿の宮が担当し、四季の風景が描かれていて、泉や滝の表現に新鮮な趣があった。北側の壁沿いには棚が二つ置かれ、小物が整然と並んでいた。南側の座敷には高官や大臣、式部卿の宮、親王たちが座った。舞台の左右には奏楽者の天幕が設置され、庭の西東には料理の箱詰め八十、纏頭用の唐櫃四十が並んだ。午後二時、楽人たちが登場し、万歳楽や皇じょうの舞が披露された。
2026.01.11
コメント(28)
-

源氏物語〔34帖 若菜 102〕
源氏物語〔34帖 若菜 102〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。十月になると、紫の上は院の四十歳の賀として嵯峨の御堂で薬師仏の供養を行った。本来なら盛大になりすぎるのを院が嫌ったので、派手な準備は控えたが、それでも仏像や経巻、経箱の立派さは極楽を思わせるほどであった。最勝王経、金剛般若経、寿命経といった経典が読まれ、祝福の雰囲気に満ちていた。多くの高官たちが参列し、嵯峨野の秋の景色を眺めるために集まった者も少なくなかった。その日、霜に枯れた原野を行き交う馬や牛車の列は尽きることなく続いた。夫人たちからも誦経の申し込みが多くあり、供養は二十三日まで続いた。そして最終日には、六条院があまりに多くの夫人や子女で溢れて窮屈になっていた。そのため、紫の上が自分の家のように感じている二条院で賀の饗宴を開くことになった。賀の席では、院が着る服や当日の準備に関することはすべて紫の上が取り仕切っていた。しかし花散里や明石の夫人たちも手伝いたいと言い、分担して動いた。二条の院の対の屋は、女房たちの部屋としても使わせていた。
2026.01.10
コメント(16)
-

源氏物語〔34帖 若菜 101〕
源氏物語〔34帖 若菜 101〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。自分は賢くないのでなかなか十分なことはできない、と控えめに答えながら、実の姉が幼い妹に接するような態度で、宮の興味をひきそうな絵の話や、雛遊びは大人になってもやめられないものだというような軽い冗談まで語った。その若々しく柔らかな雰囲気を女三の宮は好ましく感じていた。院が言っていた通り優しい人だと素直に思い、心を開いていった。それ以来、二人の間には手紙のやりとりが始まり、やがて自然に友情が育っていった。書簡の中で遊び心のあるやりとりも交わされるようになった。世間の人々はそうした六条院の内情を面白がって噂した。対の御方(紫の上)は、もう昔ほど院に愛されなくなるに違いない。新しい妻に心を奪われているだろうと言う者もいたが、実際には紫の上への愛情はいっそう深まり、それに加えて宮にも同情を寄せる院の姿が見えたので、結局は紫の上と女三の宮の間も仲睦まじくなり、噂する隙もなくなっていった。
2026.01.09
コメント(27)
-

源氏物語〔34帖 若菜 100〕
源氏物語〔34帖 若菜 100〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。宮の母と自分との血の縁を語ろうとし、中納言の乳母を呼び寄せて話を始めた。紫の上は女三の宮に向かって、自分の父と宮の母は兄妹にあたるので、実は血縁があるのだと語った。だからこそ親しくしてほしいと思っていたのに、これまで機会がなく言い出せなかった。これからは遠慮せずに自分たちの居る方へ遊びに来てくれればうれしいし、もし至らない点があれば注意してほしい、と姉のような優しい気持ちを込めて話した。すると中納言の乳母が口を添えて、女三の宮は母を早くに亡くし、父である帝も出家してしまったから、今は一人きりで心細く暮らしている。だから紫の上のような人に親しく声をかけてもらえることは何よりの喜びだろうし、法皇も宮が紫の上を信頼して頼っていけるよう願っているのだと聞いている、と語った。紫の上は、それを受けて、以前に宮から丁寧な手紙をもらった時からどうにか力になりたいと思っていた。
2026.01.08
コメント(24)
-

源氏物語〔34帖 若菜 99〕
源氏物語〔34帖 若菜 99〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。「水鳥の青羽は色も変わらぬを萩の下こそけしきことなれ」と添え書きをした。紫の上の心にある寂しさや嫉妬は、歌の端々に表れるが、それを表立って訴えることなく抑えている。その健気さに院は感謝の気持ちを抱いた。ちょうどその夜は、どちらの妻のもとにも泊まらなかった。ゆえに、気楽な時であったので、院はふと思い立ち、朧月夜の君がいる二条邸へ密かに出かけていった。いけないことだとわかっていても、抑えきれない衝動があった。一方で、東宮の淑景舎にいる女御(桐壺の女御)は、実の母よりも紫の上を慕っていた。紫の上も、美しく成長した継娘を心から愛し、実の娘と変わらぬ情を注いでいた。久しぶりに語り合ったあと、中の戸を開けて女三の宮の居所に入り、初めて顔を合わせた。まだあどけなく、ただ少女らしく見える女三の宮に紫の上は好感を持ち、年長者らしく保護者めいた言葉をかけた。
2026.01.07
コメント(25)
-

源氏物語〔34帖 若菜 98〕
源氏物語〔34帖 若菜 98〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。院は自室に戻り、女三の宮や桐壺の女御を見た後、それぞれに異なる美しさに目を楽しませていたが、長年見慣れた紫の上には刺激が薄いかもしれない、と一瞬は思われた。しかし改めて向き合った時、やはり第一の美人は紫の上であると強く感じた。気高さと品格に満ち、明るく愛嬌があり、艶やかさの盛りを迎えていた。年を経るごとに、昨日より今日が新鮮に美しく見え、飽くことのない存在であった。どうしてこのように欠点なく生まれた人がいるのだろうと、院は感嘆した。紫の上が書いた手習いの紙を硯の下に隠していたのを、院が見つけ出して読んだ。専門家のように巧みな筆跡ではなかったが、女性らしい美がにじみ出ていた。そこには、「身に近く秋や来ぬらん見るままに青葉の山もうつろひにけり」と記されており、院は目を留めた。
2026.01.06
コメント(22)
-

源氏物語〔34帖 若菜 97〕
源氏物語〔34帖 若菜 97〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。紫の上は、女三の宮があまりにも幼く無邪気で子どもっぽいところを見てしまい、もし自分がそういう姿を知ってしまったことを彼女が気づいたら、さぞ恥ずかしいだろうと感じていた。しかし同時に、夫である院が望むことを止めるのもよくないと思い、受け入れる気持ちになった。紫の上自身は、内親王である夫の新しい妻のところへ伺候する身になった自分を哀れに感じていた。二十年もの間、共に暮らし支えてきたのに、六条院に自分よりも上位に立つ夫人が存在するはずはなかった。しかし、少女の頃から養われてきた自分は軽んじられてよい存在とみなされていた。院は高貴な身分の姫を新妻として迎えたのだろうと思うと、胸が痛んだ。手習いで歌を書くと、自然と棄てられた妻の歌や、夫に冷遇される女の嘆きの歌ばかりが筆にのぼり、自分でも驚くほどそのような思いを抱いていることに気づくのだった。
2026.01.05
コメント(21)
-

源氏物語〔34帖 若菜 96〕
源氏物語〔34帖 若菜 96〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。今回なら自然に見えるでしょうと言うと、院は笑みを浮かべて、よいことです。まだ幼いのですから、いろいろと教えてあげるといいですよと答えた。宮と直接会うより、聡明で世慣れた明石の君に会うことを紫の上は喜びとし、髪を洗い念入りに装いを整えた女王の美しさは、この時にふさわしく際立った。院はさらに宮のもとへ行き、「今日の夕方、対の方にいる人が淑景舎へ伺うついでに、こちらにも立ち寄りたいと言っています。あなたとも親しくなりたいようですから、話をしてごらんなさい。気立てもよく、若々しくて、遊び相手にもなるでしょう」と語った。宮は「恥ずかしいことです。どうお話をすればよいのでしょうとおっとり答える。院は、返事は相手の話に応じて出てくるものです。ただ、好意を持って会うことが大切ですよ」と細やかに教え諭した。院は、自分の妻たちの間が穏やかであるようにと願いながら、二人の縁が自然に開かれていくことを祈っていたのである。
2026.01.04
コメント(22)
-

源氏物語〔34帖 若菜 95〕
源氏物語〔34帖 若菜 95〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。桐壺の女御は東宮に入内してから、退出をなかなか許してもらえなかった。そのため、まだ若く姫君の頃の自由に慣れていた心には、思うように動けない生活が苦しく感じられていた。やがて夏になると体調もすぐれず、ますます帰りたい気持ちが募ったが、それでも東宮は許さない。実は桐壺の女御は妊娠していて、まだ十四、五歳という幼さでの兆候だったから、周囲の人々は危ぶみ、不安を募らせた。ようやく帰ることが認められ、六条院へ戻ることになった。住まいは女三の宮がいる寝殿の東側にある座敷で、一時の仮の住居が整えられた。母である明石の君も共に帰邸した。光る未来のある桐壺の女御に寄り添い、進退をともにできる母は、幸運に恵まれた人と見られた。紫の上は桐壺の女御のもとへ行こうとしながら、院に向かってこう言った。この機会に中の戸を通って女三の宮にも挨拶をしましょう。以前からそう思っていましたけれど、わざわざ伺うのは気がひけていました。
2026.01.03
コメント(23)
-

源氏物語〔34帖 若菜 94〕
源氏物語〔34帖 若菜 94〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。尚侍との情事は決して明かせるものではなかったが、事情をよく知る紫の上には隠し通せず、物越しに逢っただけでは心残りだ、人目をうまくごまかしてもう一度だけ会いたいとほのめかした。紫の上は笑いながら「若返りばかりなさるのね、昔の恋を今に重ねれば私の影は薄くなるばかり」と言った。が、言いつつも涙をにじませ、その姿がいっそう源氏の胸を打った。彼は、あなたがそんなふうに寂しそうだから私の心は苦しくなる、もっときつく当たって懲らしめてくれてもよいのに、どうしてそんな水くさい態度をとるようになったのかと言い、機嫌を取るうちに前夜の真相も打ち明けてしまった。その日は姫宮のもとへ行かずに紫の上をなだめることに終日を費やした。姫宮本人は気にする様子もなかったが、乳母たちは面白くなく思って不満を口にしていた。もし姫宮に嫉妬心があれば源氏はさらに苦しい立場に追い込まれたであろうが、おっとりした少女のような宮であったため、源氏は人形を扱うように気楽に接することができた。
2026.01.02
コメント(23)
-

源氏物語〔34帖 若菜 93〕
源氏物語〔34帖 若菜 93〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。源氏自身も人目を恐れ、昇る朝日に急かされる思いを抱きながら、供の者がひそかに促す声を聞いて庭の藤の花を一枝折らせ、「沈んでも忘れられないのだから、また身を投げてでもこの藤の波に寄り添ってしまいそうだ」と歌い、悩ましげに戸口に寄りかかる源氏の姿を見て中納言は心苦しく思った。尚侍は、再び結ばれた関係を恥じて乱れた心を抱えながらも、やはり抑えきれない恋しさを自覚し、「身を投げる淵が真実の淵でなければ、もう懲りずに波に身を任せることはしません」と応じ、源氏は青年のような振る舞いを自ら恥じながらも、なお女の情熱が冷めていないことに喜びを覚え、次の再会を強く約してその場を去った。自邸に戻った源氏は、女のもとから忍んで帰る自分の姿を妻が気づかぬはずもないと察しつつ、あえて平静を装う夫人の態度にかえって胸を痛め、なぜこうまで冷淡にさせてしまったのかと歎息し、これまで以上の熱情を込めて、変わらぬ愛を尽くして語った。
2026.01.01
コメント(22)
-

源氏物語〔34帖 若菜 92〕
源氏物語〔34帖 若菜 92〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。やがて中納言が妻戸を開けて見送りに出ると、いったん外に出た源氏はまた戻ってきて、「この藤と私には不思議な縁がある気がする。この花がどれほど私の心を惹いているか、あなたは知っていますか。私はここを去ることができない」と小声で語り、なおも藤を眺めて立ち去ろうとしなかった。山から昇った日の光が差し込み、その美しい姿に輝きが重なり、目もくらむほどに映えた。源氏は、昔よりいっそう風采を増して輝く自分の姿を長く眺めることのできなかった朧月夜に、心を動かさずにいられるはずがないと思った。彼女は、過去の過ちのせいで後宮に仕えてはいても表立って后の位に上ることはなかった。運命を背負い、そのために姉の皇太后がどれほど心を砕いてきたか、またあの事件で源氏が永遠に消せない悪名を背負うことになった因縁の人であることを思い出し、複雑な思いに揺れていた。名残尽きぬ一夜をこれきりにはしたくないと願いつつも、今の源氏が軽々しく恋の逢瀬を重ねるはずもないと考えた。
2025.12.31
コメント(24)
-

源氏物語〔34帖 若菜 91〕
源氏物語〔34帖 若菜 91〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。辛い生活を送ることになったのは誰のせいだったか、自分だけが冷たく賢しらな態度で済ませてよいのかと考え、気持ちは揺らぎ始めた。元来、堅さに欠ける性質の朧月夜は、源氏と離れていた年月のあいだ、自分の軽率さを悔やみ、もう清算がついたと思い込んでいたが、いざ昔と同じような夜が目の前に現れる。その年月が一気に縮まり、最初の冷静な態度は保てなくなった。源氏は、相変わらず艶やかで若さを失わない朧月夜の姿を目にして、世間を気にしてため息をつく彼女を、今ようやく得た恋人以上に新鮮に感じ、胸の奥から愛情があふれるのを抑えられなかった。夜が明けるのが惜しく、帰る気持ちにもなれない。明け方のやわらかな光の中で小鳥の声が澄んで聞こえ、花は散り尽くした春の暮れ、浅緑に霞んだ庭の木々を眺めていると、この屋敷で藤の花の宴が開かれたのもこの季節だったと思い出し、昔と今の間に横たわる長い歳月をしみじみ感じ、青春の日々を恋しく思いながら、今この現実が身に沁みた。
2025.12.30
コメント(21)
-

源氏物語〔34帖 若菜 90〕
源氏物語〔34帖 若菜 90〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。源氏は、若者のような扱いを受けているようで落ち着かない、あれからどれだけの年月が過ぎたかを私は一日たりとも忘れたことはないのに、あなたの冷たさが恨めしく思われてならないと切なく訴え、夜は更けていった。池のほとりではしっとりと人けの少ない中、鴛鴦の声がもの悲しく聞こえていた。宮中の空気が身に沁み、かつての栄華を誇った屋敷がすっかり移り変わってしまったことを思うと、人生のはかなさが胸に迫った。源氏は女の心を動かそうとするための見せかけの涙ではなく、自然に真実の涙がこぼれてくる。そして、昔のように焦った若者ではなく、年を重ねて落ち着いたふうを装っていた。恋の思いを切々と語り、このまま何もなく終わってしまうのですかと言って襖を引き寄せた。源氏は歌を詠み、年月を隔て逢うことの難しさを涙したが、朧月夜は、涙をせき止めることもできない清水のように道はもう絶えたと冷たくも突き放すような歌を返したが、心の奥では、昔を思い返し、この人が遠ざかって漂うような辛い生活を送ることになった。
2025.12.29
コメント(23)
-

源氏物語〔34帖 若菜 89〕
源氏物語〔34帖 若菜 89〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。その日は寝殿にも行かず、ただ手紙をやりとりするだけで過ごした。入念に薫物の香を袖に焚き染め、日が暮れるのを待って四、五人の親しい者だけを連れて、昔のようなひそやかな外出に使った網代車で出かけた。六条院が訪れたと聞いて、尚侍はどうして来たのか、自分の返事をどう誤解したのだろうと不機嫌になった。だが、中納言は、適当な理由をつけて帰っていただくのは失礼だと説き、無理やりにでも源氏を座敷へ案内した。源氏はまず見舞いの挨拶を取り次がせた後、近い所まで出てきて物越しにでも話してくれないか、今日はもう昔のような無分別なことをしようと思っているわけではないのだと切実に頼んだ。尚侍はため息をつきながら出てきたので、源氏はやはり軽率な人だと思いつつも満足し、二人にとっては久しぶりの顔合わせとなった。遠い昔の記憶が女の心にもよみがえらないわけではなかった。源氏は東の対の、南東の端の座敷に座り、隣の間にいる尚侍との間は襖が閉ざされていた。
2025.12.28
コメント(20)
-

源氏物語〔34帖 若菜 88〕
源氏物語〔34帖 若菜 88〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。源氏は、すべてを無視して苦しみながらも愛し合った二人の仲なのだから、今さら相手が清らかな顔をしても、かつて世間に立った浮名を取り消すことはできないのだと考え、出家した朱雀院に対しては後ろめたさはあったが、結局は昔の関係を繰り返すだけのことだと心の中で言い聞かせていた。にわかに前和泉守を案内役にして朧月夜の尚侍のいる二条の宮を訪ねる決心を固めた。そこで、妻の女王には、東の院にいる常陸の宮の女王がずっと病気で、その見舞いに取り紛れて行かれなかったのが気の毒だから、昼間は人目があるので夜になってから出かけるつもりだと口実を作った。誰にも知らせず出かけるのだと伝えて、外出の支度を整えた。女王にはそれがただ事ではないように見え、普段はそんな出かけ方をすることもないので不審に思ったが、思い当たる節もないではなくても、女三の宮が来てからは昔のようにすぐ疑いを口にすることを控えていたので、表向きは知らぬ顔をしていた。
2025.12.27
コメント(23)
-

源氏物語〔34帖 若菜 87〕
源氏物語〔34帖 若菜 87〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。彼は昔から親しい中納言を介して二人が会える道を開こうとする手紙を送り続け、さらにその兄である前和泉守を呼んでは若き日のように胸を躍らせた。胸を躍らせながら相談したので、源氏は取り次ぎを通すのではなく、直接顔を合わせなくても物越しに話せばよい、どうしても話さねばならない。そんなことがあるから尚侍の承諾をとってほしい、今の自分は表立ってそんなことができる身分ではないが、それでも会おうとするのだから向こうも秘密を守ってくれるに違いないと語り、それを中納言が伝えると尚侍は、それは必要のない会見であり、自分はもうあの頃のように幼い心で人生を見てはいない。昔から誠のない愛しか与えてくれなかった人の誘いに今さら乗るはずもない。法皇をあのようにお気の毒な暮らしに置いておけない。昔の話を持ち出すなど自分には受け入れられない、たとえ秘密にするとしても自分の心に恥じることになるとため息をつき、そんなことは決して考えられないと断り続けた。
2025.12.26
コメント(19)
-

源氏物語〔34帖 若菜 86〕
源氏物語〔34帖 若菜 86〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。朱雀院は諭し、自分の寺に納める仏像の製作に心を傾けていた。六条院では、源氏がかつて別れざるを得なかった朧月夜の前尚侍を今なお忘れずに思い続け、いつか再び会える機会があれば、その時の胸をえぐられるような苦しみを打ち明けたいと願っていた。しかし、二人の関係は世間の非難を受ける立場にあり、かつて女に大きな傷を負わせる騒動を引き起こしたことを思えば、軽々しく行動することはできず、ただ忍んで過ごしていた。朱雀院とも別れて独り暮らしになっている今の孤独な生活がいっそう彼の心を掻き立て、どうしても会いたくなる。いけないことだと思いながらも友人への手紙の体裁をとっては忘れがたい熱情を伝え、それが幾度も重なったため、前尚侍ももう若い男女のように危うさを気にする年ではないと考えて時折返事をよこし、しかも年齢を重ねてなお美しさと完成の跡を見せる朧月夜の君の筆跡はますます源氏の心を魅了した。
2025.12.25
コメント(27)
-

源氏物語〔34帖 若菜 85〕
源氏物語〔34帖 若菜 85〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。言葉を飾る必要のある手紙ではなかったので、そのまま感じたことを歌にした。「背いた世のうしろめたさは消え難き絆を強いてかければ離れることはありません」そう詠んで返事を書き、女の装束に細長衣を添えてお使いに持たせた。紫の上の筆跡は立派で整っていた。それを見た院は、六条院にはこのようにすべてが整った夫人がいるというのに、幼い姫宮が一人の妻としてここに迎え入れられることを思うと、心苦しい気がした。その後、朱雀院が出家すると、かつて院を慕っていた女御や更衣たちはそれぞれ散り散りに自邸へ帰ることになった。みな哀れな境遇であった。尚侍は亡くなった皇太后が住んでいた二条の宮に移って住むことになった。院は姫宮のことを心配するのと並んで、この尚侍のことも特に気にかけていた。前尚侍は尼になりたいと願っていたが、今その道に入るのは人恋しさからの出家であり、悟りを得た者の行いではない。
2025.12.24
コメント(20)
-

源氏物語〔34帖 若菜 84〕
源氏物語〔34帖 若菜 84〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。さらに歌「背きにしこの世に残る心こそ入る山みちの絆なりけれ」(俗世を捨てて出家しても、娘を残していく心残りが、山へ入る私をこの世につなぎ止める縁である)と詠んで、親としての未練を隠さず述べる。まだ物事を理解することもできぬ幼い娘を、あなたのもとに差し上げる事になた。邪気のない子としてどうかお許しいただき、お世話をお願いします。あなたには縁のないことでもないのですから。背きにしこの世に残る心こそ入る山みちの絆なりけれ」と詠み、親としての心残りを隠そうともしない心情を綴ってあった。こんな手紙を差し上げるのは本来ならためらわれることだ。それほど胸に迫る思いであるという内容だった。院はこれを読んで、同情すべき手紙だから、あなたからも丁寧に返事を書いてさしあげなさい」と紫の上に言い、お使いに来た者には女房を遣わせて酒を勧めた。紫の上は「どう返事を書けばよいのか分かりません。書きにくいとこぼした。
2025.12.23
コメント(23)
-

源氏物語〔34帖 若菜 83〕
源氏物語〔34帖 若菜 83〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。院の心は結局、紫の女王へと傾いていった。なぜこれほどまでに思い詰めるのか、自分自身を疑うほどに、院の愛情は深まっていった。朱雀院はやがて出家して御寺へ移ることになっていたので、このころは六条院へたびたび手紙を送っていた。その文には、姫宮のことを頼む気持ちがこめられていた。自分の気持ちをどう思うかと深く考えず、とにかく娘のことを気にかけて世話してほしい、という願いが書かれていた。そうは言いながらも、まだ幼い姫宮が心配でならない様子が文面にはにじんでいた。紫の上にも手紙が届いた。娘を託す父(朱雀院)と、その婿となる光源氏とのやりとり。場面としては、朱雀院が出家を前にして、まだ幼い娘の女三の宮を源氏に嫁がせることになり、その際に娘を託す気持ちを表した。朱雀院は「まだ物事を理解できない幼い娘をあなたに差し上げることになったが、どうか邪気のない子として許して世話をしてほしい」と源氏に伝える。
2025.12.22
コメント(21)
-

源氏物語〔34帖 若菜 82〕
源氏物語〔34帖 若菜 82〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。芸術的な感性は豊かで優れている人物だった。それなのに、どうして愛娘をここまで凡庸な姫に育ててしまったのだろう、と院は残念に思った。それでも愛情が湧かないわけではなかった。姫宮は院の言葉に従い、素直で、返事も教えられたことをそのまま繰り返すだけで、自分から言葉を生み出すことはない。かつての自分であれば退屈に思い、愛想を尽かしてしまったかもしれない。しかし今の院は、完全なものなど得られないのだと知っていた。欠けた部分は心で補い、平凡な相手に満足すべきだという人生の教訓を積み重ねてきたのだ。だからこそ、この姫宮をも妻の一人として受け入れられる。世間の人はきっと「好ましい結婚相手を得た」と見るだろう。そう思うと、長年ともに過ごした紫の女王の価値があらためて胸に迫り、自分が与えた教育の成果を認めざるをえなかった。ただ一夜離れただけで、翌朝にはその人の恋しさで胸がいっぱいになり、すぐに会えない時間がもどかしくてならない。
2025.12.21
コメント(21)
-

源氏物語〔34帖 若菜 81〕
源氏物語〔34帖 若菜 81〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。「はかなくて上の空にぞ消えぬべき風に漂ふ春のあは雪」宮の文字はやはり稚拙であった。十五にもなればこんなものではないはずだが、と目にとめつつも、女王は見ないふりをした。他の女性の手紙なら、院は辛辣な感想の一つも口にしただろうが、宮の身分を思ってそれは控えた。「安心していてよいのだ」とだけ女王に声をかけた。その日、院は昼間に宮のもとを訪れた。特に念入りに化粧を施した院の美しさに、初めて間近に接した女房は興奮していた。年老いた女房の中には、「どう見ても幸福なのはあちらの奥方だけで、この宮は不快な思いを味わうのではないか」と密かに考える者もいた。姫宮はまだ子どもらしく、小柄で、立派な部屋の調度品と釣り合わぬほどに素朴で無邪気な姿であった。衣に埋もれるように座るその姿は愛らしく、格別に恥ずかしがるわけでもなく、人見知りのない子供のように扱いやすく思われた。朱雀院は学問の奥義には通じていないと人から言われた。
2025.12.20
コメント(23)
-

源氏物語〔34帖 若菜 80〕
源氏物語〔34帖 若菜 80〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。やがて寝殿からの返事が遅いのを気にして、院は居室に戻り、梅の花を手に女王のもとを訪れた。院と女王が梅の花を前に語り合っていた。女王は「花ならこれほどの香りを持っていたいものね。もし桜がこの香りを持っていたら、他の花はみんな忘れ去られてしまうでしょうね」と言う。夫人は「今は梅が唯一の花だからこそ良いと思えるのですよ。春に百花が咲きそろったとき、他の花と比べてどう思えるかしら」と答えた。そんなやりとりの最中に、宮からの返事が届いた。紅い薄紙に包まれた手紙が目を引き、院は思わずどきりとした。幼い宮の書きぶりは当分女王には見せたくない。隔てなく心を向けているとはいえ、あまりに拙い文字を見せれば、宮の身分にかえって傷をつけることになりかねないと院は思った。しかし隠してしまうのも女王には不快だろうと考え、結局は半ば見せるようにして手紙を広げた。女王は横になったまま横目でそれを見た。
2025.12.19
コメント(22)
-

源氏物語〔34帖 若菜 79〕
源氏物語〔34帖 若菜 79〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。乳母に伝えさせたが、返事は「そのとおりにお伝えしました」というだけだった。朱雀院がこれをどう思うだろうかと気がかりで、しばらくは朱雀院を立てるように振る舞わねばと考える一方、それを実行する苦しさに耐えきれず、悲しみに沈んだ。女王もまた同じだった。あちらに思いやりが欠けているのではないかと感じ、自分の立場に苦しんでいた。次の日も院は自室で目を覚まし、宮へ手紙を書いた。晴れやかな気持ちを抱く相手ではなかったが、白い紙を選び筆をとって、「中道を隔つほどはなけれども心乱るる今朝のあは雪」と詠み、梅の枝に添えて侍に持たせ、「西の渡殿から参上せよ」と命じた。院は縁に近い座敷に座り、庭を眺めながら梅の枝の残りを手に弄んだ。白い衣をまとい、雪の残る庭を前に、紅梅の梢で鳴く鶯の声を耳にして「袖こそ匂へ」と古歌を口ずさみ、梅の花を持った手を袖に引き入れながら外を眺める姿は、院という高い身分の人とは思えないほど若々しかった。
2025.12.18
コメント(21)
-

源氏物語〔34帖 若菜 78〕
源氏物語〔34帖 若菜 78〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。しばらく寝たふりをしたのちにようやく格子を上げた。院は、「外で長く待たされて身体が冷え切ったのは、私があなたを恐れて気がねした心のせいで、女房たちに罪はなかったのだろう」と言いながら女王の夜着をそっと引き寄せてみると、下に着ている単衣の袖が涙で少し濡れていた。それを隠そうとする仕草が美しく、院の心に深く響いた。しかし女王の心にはどこか打ち解けきれないところがある。それがかえって上品で艶やかな趣を漂わせてもいた。院は、完璧に整わぬところを残したこの女性の姿を前に、新妻の宮と紫の上の二人を思い浮かべ、心の中で比べていた。そして、二人がたどってきたこれまでの道を振り返るように話しかけ、恨みを捨てきれない女王をなだめて、その日は一日中そばを離れずに過ごした。夜になっても宮のもとへは行かず、手紙だけを届けさせた。今朝の雪で身体の具合が悪く、しばらく気楽なところで養生しようと思いますという文だ。
2025.12.17
コメント(25)
-

源氏物語〔34帖 若菜 77〕
源氏物語〔34帖 若菜 77〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。女王はただ恨みだけに心を傾けていたわけではなかったが、彼女の苦しむ思いが通じたのか、院は夢の中で女王の姿を見て目を覚まし、不安に胸騒ぎを覚えた。鶏の鳴き声を聞きながらじっとしていたが、声が止むとすぐに宮殿を出て女王のもとへ向かった。だが、まだ若い宮であるため、そばには乳母たちが控えており、院が妻戸を開けて外に出るのを見送った。夜明け前で、しばし暗さが増すころ、雪の光に照らされて院の姿がぼんやり浮かび上がった。衣からただよう香りが濃く残っているのに気づいた乳母たちは、「春の夜の闇はあやなし梅の花」と古い歌を思わず口にした。院は庭に積もる雪の白さを砂子の散りばめられた模様と見分けがつかないほどだと眺めながら、女王のいる対へ向かい、口の中で「残れる雪」とつぶやいた。格子を叩いて入ろうとしたが、夜明け近くに訪れることなど久しくなかったので、女王に仕える女房たちは腹立たしく思い、すぐには応じなかった。
2025.12.16
コメント(23)
-

源氏物語〔34帖 若菜 76〕
源氏物語〔34帖 若菜 76〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。確かに自分は孤独なのだ」と思い、噛みしめているものは苦さだけで他の味わいではないと実感する。同時に彼女の心には、須磨に源氏が流された頃の記憶も蘇り、あの時も深い孤独の中で、遠く離れていても源氏が生きていることだけを心の支えにして過ごした。そして、あの時の悲しみで、もし源氏や自分が死んでしまっていたなら、それから後の幸福は味わえなかったのだとも思い直し、今ある境遇の中で自分を慰めようとする。夜は風が吹き、冷え込みも厳しかったので、女王はなかなか眠ることができなかった。近くに仕えている女房が自分の寝返りの気配を感じ取って心配するのではないかと思うと、それもまた気がかりで、寝床の中でじっとしていることさえ苦しく思われた。やがて一番鶏の声が響くと、その声は胸に沁み入るようで、女王の孤独やつらさをいっそう際立たせるものになった。
2025.12.15
コメント(17)
-

源氏物語〔34帖 若菜 75〕
源氏物語〔34帖 若菜 75〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。そばで聞いていた女房の中将や中務は、互いに目を見交わしながら「女王様は思いやりがありすぎる」とひそかに言う。彼女たちはかつて源氏の愛人だった。須磨に流された時期から紫の上に仕えるようになり、深く彼女を慕っている。そのため、紫の上の無理な自己抑制を痛ましく感じている。さらに他の女房の中には、「私たちは最初から愛されないことを覚悟しているから平気だけれど、誰よりも愛されてきたあなたが今の状況をどう思っているのだろう」と慰めの言葉をかける者もいた。しかし紫の上にとってそうした同情はむしろ辛く、自分の痛みを改めて意識させられるものとなる。彼女は「この無常の世で、夫婦愛にそれほど執着しているわけではない」と思おうとするが、それでも心の底から寂しさが湧いてくる。夜更けになり、眠らずに過ごしている自分の姿を周囲が不自然に思うのも嫌で、紫の上は帳台に入る。女房が夜着を掛けてくれて、ようやく人から哀れまれているように思えた。
2025.12.14
コメント(26)
-

源氏物語〔34帖 若菜 74〕
源氏物語〔34帖 若菜 74〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。自ら前向きな言葉をかける。院にはこれまでも多くの女性がいたけれど、理想的な配偶者と胸を張って言えるほどの人はなかった。だから物足りなさを感じておいでになったのだろう。けれども宮様を迎えられて、これでようやくすべてが整い、完全になったのだと。紫の上は、自分がまだ大人として達観できていない部分を自覚していて、まだ子供っぽい気持ちが抜けきらず、源氏とただ楽しく一緒に過ごしていたいと思うのに、周囲の人が私の気持ちを思い量り、かえって関係を難しくしてしまう。普通なら、同じ身分か自分より下の女性が愛されれば嫉妬や不愉快な気持ちになるものだ。相手の女三の宮は高貴な出自であり、また不遇な事情で源氏の妻として六条院に迎えられたのだから、紫の上としては「せめて自分がその人に悪く思われてはいけない」と努めている。彼女は自分の感情に流されまいと気を配り、相手への思いやりを第一にしようとしているのである。
2025.12.13
コメント(24)
-

源氏物語〔34帖 若菜 73〕
源氏物語〔34帖 若菜 73〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。彼女は「この世には永遠に変わらないものなどなく、これから先どんな運命に出会うかもわからないのだ」と考えるようになり、心の底に不安を抱える。だが、紫の上はその動揺を表に出さず、いつも通り穏やかにふるまっている。けれども女房たちは不安を隠せずにささやき合う。これまで他の女性がいても、あなたと競い合えると思う人はいなかったから安心だったのに、今度ばかりは紫の上をも眼中に置かないほど高貴な宮様がいらしたのではどうなるのだろう。これほどの方に劣ってしまうことは耐えられないはずだし、また宮様の側からすれば紫の上が気に病んでいるように見えた。大げさな事と軽く扱われるかもしれないが、そうなれば必ず争いや心労が生じ、奥方はつらい思いをなさるに違いない」と。そのような周囲の心配や嘆きにも紫の上は顔色を変えず、にこやかに皆と語らいながら夜更けまで座敷に出ていた。女房たちの不安が外に漏れて、源氏に不快に思われるのを避けるためだった。
2025.12.12
コメント(20)
-

源氏物語〔34帖 若菜 72〕
源氏物語〔34帖 若菜 72〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。源氏はそれを手に取り、彼女の気持ちに胸を打たれ、憐れみを感じる。そして自らも和歌を返す。「命が尽きても絶えることはないだろう、定めなき世の常とは違う、特別な私たちの契りは」と書き、彼女への誠意を示すが、実際にはそのまま出かけることをやめようとはしない。やがて紫の上が「遅くなっては体裁が悪いでしょう」と促すと、源氏は直衣を改め、香を焚きしめた衣に着替えて出かけていく。その姿を見送る紫の上の心は、とても平静ではいられなかった。これまで源氏は、時に新たな妻を迎え入れようとする素振りを見せることはあった。しかし、そのたびに思い直し、実際には行動に移さずにきた。そのため紫の上は「これからも平穏に幸せが続いていく」と信じて疑わなかった。ところが今回はついに女三の宮が正妻として六条院に迎え入れられ、紫の上のこれまでの安定した立場が揺らぐことになった。
2025.12.11
コメント(23)
-

源氏物語〔34帖 若菜 71〕
源氏物語〔34帖 若菜 71〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。源氏は「本来なら自分は妻を二人持つべきではなかったのに、このことだけは断り切れず、心の弱さから受け入れてしまったために、紫の上にこんなつらい思いをさせてしまった」と深く悔やみ、自分自身を恨む気持ちで涙ぐむ。彼は紫の上に、あと一晩だけは世間並みの義理を果たすために女三の宮のもとへ行かせてほしいと。その後もあちらばかりに通うようなことをするなら、自分自身を軽蔑することになるだろう。しかし、紫の上はどう思うだろうかと苦しげに語る。その姿は痛々しいが、紫の上は少し微笑んで「ほらご覧なさい、ご自身の心だって定まらないのですもの。道理のある方が強いとはいっても、それを貫けないと答える。これは諦念と皮肉が入り混じった言葉であり、源氏は恥ずかしさを覚えて頬杖をつき、うっとりと横になる。紫の上は硯を引き寄せて和歌を書きつける。「目の前に見えるものですら移り変わるこの世に、行く末までも頼りにしてしまったのだなあ」と記し、さらに同じ趣旨の古歌も書き添える。
2025.12.10
コメント(21)
-

源氏物語〔34帖 若菜 70〕
源氏物語〔34帖 若菜 70〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。健気で可憐な態度に六条院も深く感激していた。一方、女三の宮はというと、あまりにも幼く、子どもっぽさしかない存在であった。六条院はかつて若き日の紫の上を二条院に迎えた時のことを思い出し、比較してみる。紫の上はその年頃でも才気が見え、話していて楽しい少女であった。女三の宮にはそうした生き生きとした魅力がなく、ただ子供らしいばかりだった。六条院は「これならば、あまりに出過ぎたことをせず、慎み深いだろう」と自分に言い聞かせて好意的に見ようとするが、それでもどこか張り合いのない新婦だと感じ、内心で落胆していた。その三日の間、六条院は新妻のもとに通うが、紫の上にとってはこれまで経験したことのない孤独な時間であった。心の底から寂しさが湧いてきて、どうしようもない。六条院が女三の宮のもとへ向かうための装束に薫香を焚かせながら、物思いに沈む紫の上の姿は、憂いを帯びてひときわ美しく映っていた。
2025.12.09
コメント(24)
-

源氏物語〔34帖 若菜 69〕
源氏物語〔34帖 若菜 69〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。特別な性格を持った婚礼の場であった。この出来事には、六条院の立場の特異さ、また彼の人生の円熟と新しい局面が示されている。婚礼の三日間は、婿側である六条院からも、舅である朱雀院からも華やかなおもてなしが行われ、邸内は大勢の人々で賑わい、祝いの雰囲気に包まれていた。だが、そんな華やかさの中で紫の上はひとり寂しさを覚えていた。彼女自身は、六条院との夫婦関係がこれによって不安定になるとは思ってないし、これまで誰よりも愛される妻として確固とした地位を保ってきた自信もあるが、まだ幼いとはいえ内親王という高貴な身分の女性である。新しい妻として迎えられたことを考えると、どうしても自分が退いていくような気がし、心の奥で羞恥や寂しさが湧き上がってしまう。それでも紫の上はその気持ちを押さえ、むしろ大らかに、女三の宮が移ってくる前の支度を六条院と共に進めるという健気で可憐な態度をとった。
2025.12.08
コメント(21)
-

源氏物語〔34帖 若菜 68〕
源氏物語〔34帖 若菜 68〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。六条院はその態度をどこか物足りなく感じていたが、ここには、親子や養父子という関係を超えた、複雑な絆と距離感が描かれている。やがて二月十余日、朱雀院の娘である女三の宮が六条院に入る日がやってくる。六条院の邸宅でもその準備が整えられていた。先日の若菜の賀で使われた寝殿の西の対に帳台が立てられ、さらにその周辺の部屋や渡殿も女房たちの居所として割り当てられ、華やかな婚礼の場が整った。形式は入内に準じるもので、朱雀院からも婚礼道具が運び込まれ、列の行列はきらびやかで、随行する者の中には高官も多く混じっていた。その中には、かつて姫宮を正妻にと望みながら叶わなかった大納言の姿もあり、彼は心の中で涙を飲みながら従っていた。そして行列が六条院に到着すると、六条院自らが出迎え、姫宮を車から抱き下ろすという前例のない行動をとる。これは天皇の入内の儀式でもなく、また親王夫人の婚礼とも異なる、
2025.12.07
コメント(22)
-

源氏物語〔34帖 若菜 67〕
源氏物語〔34帖 若菜 65〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。まず六条院は、自分がもう世の中の表舞台から退き、好き勝手な隠居のような生活をしているので、月日の流れを意識することも少なくなっていたと語る。ところが、周囲の人々が四十歳という年齢を祝い、年を数えてくれることで、改めて老いが自分の身に迫っていると実感し、急に心細さを感じたのだと述べる。そして、気軽に訪れて昔と今を比べるように自分を見に来てほしいと頼むが、今の立場では自由に人に会いに行けない不自由さもあり、自分から会いに行くことができずに寂しく思っている、とこぼす。この言葉には、老いを意識しながらも、まだ人との交流や愛情を求める六条院の人間的な思いがにじんでいる。その一方で、玉鬘の側もまた複雑な感情を抱いている。実父である太政大臣への親子としての情はもちろんあるものの、実際に自分を育て導き、今の幸福な境遇を与えてくれたのは六条院であるという感謝の念が強く、年月が経つほどにその思いは深まっていた。しかし、玉鬘が六条院のもとを訪れても、長居せず早く帰ってしまうことがあり、六条院はその態度をどこか物足りなく感じていた。
2025.12.06
コメント(24)
-

源氏物語〔34帖 若菜 66〕
源氏物語〔34帖 若菜 66〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。六条院はその響きに身を沁み入るように聴き入り、兵部卿宮もまた感情を抑えきれず、酔いながら涙を流すほどであった。やがて宮は院の意向を伺い、琴を御前へ移すと、院もその場の気分に抗しきれず、自ら珍しい曲をひとつ弾いた。そのため、決して大規模な演奏ではなかったが、趣のある音楽の夜となった。楽器の演奏が終わると、階段のあたりに集められた声のよい若い殿上人たちが合唱を行い、「青柳」が歌われる頃には、すでにねぐらに帰っていたはずの鶯さえ驚いて鳴き出すかと思われるほど華やかでにぎやかな響きが広がった。宴は形式上は左大将の主催であったが、六条院自身の側からも纏頭の贈り物が用意され、場の盛り上がりをさらに際立たせた。やがて夜が明け、玉鬘の尚侍は自邸へ戻ることとなる。その際、六条院から贈り物が与えられ、祝宴の余韻を残しながらこの一夜の華やかな出来事は締めくくられた。 六条院が四十歳を迎えて賀宴を開いた後の、彼自身の心境の吐露と、その後に続く朱雀院の女三の宮入内の場面が描かれている。
2025.12.05
コメント(24)
-

源氏物語〔34帖 若菜 65〕
源氏物語〔34帖 若菜 65〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。六条院の四十歳の賀宴における音楽のやり取りが詳しく描かれている。まず、二つの和琴が用いられた。父である太政大臣が弾いた琴は、絃をやや緩め、柱も低くして余韻を深く重々しく響かせるように調整されていたため、音は落ち着きと深みを持っていた。それに対して息子の右衛門督が弾いた琴は、華やかに音が立ち上がり、甘美で親しみやすい響きを奏でた。その優れた演奏は人々を驚かせ、親王たちでさえ「ここまで上手だとは思わなかった」と感嘆するほどであった。さらに、兵部卿宮が宮中の名器である琴を手に取った。この琴は、かつて宜陽殿に納められ、代々第一と称されてきたもので、先帝の晩年には御長皇女が愛用し、下賜された由緒ある楽器であった。今回は賀宴のために太政大臣が借り出してきたものであり、その音色は六条院に、父帝の治世や姉宮の思い出を深く呼び起こした。
2025.12.04
コメント(25)
-

源氏物語〔34帖 若菜 64〕
源氏物語〔34帖 若菜 64〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語〔34帖 若菜〕 の研鑽」を公開してます。院の前に並べた。院の席には沈香の木で作られた盆が四つ置かれ、上品な杯台などがささげられた。朱雀院がまだ病から回復していなかったため、専門の楽人は招かれなかったが、音楽の準備は周到であった。玉鬘の実父である太政大臣が担当し、選び抜かれた名器が並べられた。その際、大臣は「この世に六条院の賀宴以上に高雅な集まりはないだろう」と語り、心を尽くして楽器を揃えた。和琴は大臣が秘蔵してきた逸品であり、かつて名手が弾き込んだために扱いにくいと敬遠されていたが、院の強い求めで右衛門督が演奏することになった。若者は父譲りの技を見事に発揮し、予想以上の腕前を披露した。その演奏は人々を驚かせ、父から子へと芸が受け継がれることの稀有さを思わせた。特に和琴は中国から伝来した楽器と違い、清掻きだけで他の楽器を統率する難しいものであるが、右衛門督の爪音は澄んで響き渡り、場を圧倒した。
2025.12.03
コメント(24)
全5358件 (5358件中 1-50件目)