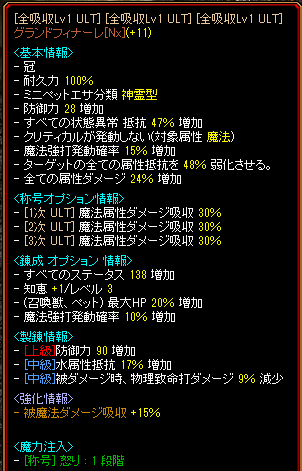第十五章
「中央館」
ルウェンはこの一日で、ある程度の現在のモネルダの有力権力者を把握することができていた。そこから賊と繋がりを持てそうな者をさらに検出し、割り当てることも、その日のうちにある程度見いだす事もできていた。
――ざっと、百人くらいか。さて、どうしたものか。あまり長い事モネルダにいるわけにはいかない。そう時間をかけることができない今、百人全員調べ上げるなんて無理な話だ。
ここは一度帰って、ゆっくり考えてみるとしよう。
一気に疲れが足にたまり、ルウェンはカモフラージュのために用意した商売道具を降ろした。連鎖するように足の先端から首まで、どっと疲れが押し寄せ、彼は中央広場の建物に持たれるように背中を預ける。
アーチェルドの将軍も年をとったものだ。自信の老いを感じながら、ルウェンはため息交じりに笑った。この歳になると、いったん疲れを意識し始めるとそう簡単に抜けない。若い頃は気にすることもなく、仕事に集中していたというのに、今では意識してしまう事のほうがずっと多い。
本来なら、ルウェンは将軍を引退し隠居するつもりであった。しかしそれは、今回のアーチェルドの紛争と、それに乗じての賊の活動の活発化によって先送りとなってしまった。
だが、彼は特にそれが不憫だと感じなかった。どういうことか、今まで以上のやる気を感じた。それがどういうことなのか、まだ彼自身わかっていない。だから、まだ老いには勝てるとも思っていた。
どうやら、この老いという敵は宿敵らしい。長い闘いになりそうだ。ルウェンはそれを克服するのは無理だろうと思った。が、老いに負けてアーチェルドの使命が果たせなくなるのは絶対に避けなければいけない。
誰も見ていないのを確認して、ルウェンは自分の頬を軽く叩いた。張りのない若干鈍い音が響く。彼は荷物を背負い、歩き出した。
不意に、辺りが静かであることに気づく。静かであることは別に珍しくもない。太陽が沈み、月が三日月の形をして顔を出す時間帯だ。昨日の忙しい時だって、この時間はほとんどの者が帰路へ付き、商人は店をたたんでいたのだから。
肝心なのは、本当に人がどこにもいないということだ。建物はどこも明かりがなく、近くの酒場も賑わいがない。
他の商人も見えず、まるでその空間にルウェン一人だけが取り残されたようだった。
今まで全く気がつかなかった。住民はどこへいるのだろう。どこかで祭りがあり、そこへ集まっているのだろうか。だとしたら、なんの祭りだ?
人が誰もいない。本当にそれだけなのだが、ルウェンは気になってしょうがなかった。なんだかそれが、今回のモネルダと賊の関係を見計る決定的な事実に繋がるような気がしてならなかった。
探してみよう。人に聞くのはまずい。自分の力だけで、探してみるのだ。
疲れを意識し始めた老人の体はくたくたであった。もし目の前に清潔なシーツの敷いてあるふかふかのベッドがあれば、倒れ込んでしまいたいという誘惑に勝つ自信がないほどだ。
というのも、ルウェンが歩き回った中央区はモネルダの半分の大きさもあり、人気を探していくにはあまりにも広過ぎたからだ。
モネルダに来るのは初めてではない。だが、これほど長くこの場所を歩き回ったのは初めてだ。そして、こうして苦労して探して数時間。彼はようやく、人が集中するある場所へとたどり着く――
結局、夜が明けてもルウェンは帰ってこなかった。ルセスたちが支度を整え、朝宿屋を出る時になっても、彼は姿を現さなかった。
心配で、不安いっぱいの目でピーターはルセスを見る。その目には涙も浮かんでいた。
「ルウェン様、どうしたんだろう?」
彼の様子だけで、瞳の力を使わなくても彼の心情がはっきり理解できる。気持ちはわかる。もちろん、ルセスだって心配だ。だがピーターは、今後の旅商人に偽るという務めを忘れてしまいそうなくらい取り乱していた。
小さくため息を吐いて、それでも優しい声でルセスは言った。
「わからないけど、きっと大丈夫だよ。だってルウェン様だよ? ぼくたちより、ずっとうまくできているはずだよ」
「じゃあ、じゃあなんで昨日は帰ってこなかったんだよ?」涙ぐむ子供のような口調でピーターは言った。
「もしかしたら、疲れて眠ってるんじゃないかな。ほら、ここって広いでしょ? 昨日はきっと歩き疲れて、宿に帰る前に眠ってしまったんだよ」
そんなことを言うルセスを見て、ピーターはため息をついて諦めたように歩き始めた。子供のルセスに励まされるのがなんだか情けなくなってきたのだろうか。
こんな会話があと何回続くだろう。ルセスは気づかれないくらいの小さなため息を吐いた。
確かに、ルウェンが帰ってこなかったのはおかしい。彼は約束や決めごとを破るような人物ではない。彼の性格からして、非常事態が彼の周りに起きた、という可能性が一番考えられる。
ルセスはそれに気づいている。そして、ピーターもだ。だが彼らはそれを受け止めるほど大人ではなかった。ルセスだって、何事もなければいいと強く願うだけだ。
三日目の商売を開いた。昨日ほどではないにしても、初日よりずっと客足は少なく、まどろだ。せめて初日並の多さと忙しさなら、この不安を一時的に忘れられたかもしれない。
それから夕方にかけての数時間、ピーターとルセスは会話をしなかった。お互い、不安な気持ちでいっぱいだったのだ。
店を畳む時間になり、一人の男性客がルセスとピーターの前に立った。フード付きマントから見える薄汚れたよれよれのブーツを見るところ、旅人のようだ。
男は商品を見るようにしゃがんで、よくわからない模様の描かれた皿を一枚手に取り、口を開いた。
「なにか異常はあったか?」
その声を聞き、途端にピーターが立ちあがる。
「る、ルウェン様!!」
フードを頭の後ろに下げ、男はけげんそうな表情を浮かべた。
「シクエイ親方、いったいどこへ行ってたんですか?」とルセス。
するとピーターは「あっ」と声を出したかと思うと掌で口を覆った。彼がルウェンだということは、誰にも知られてはならないのだ。
「なんの連絡もなしに帰らなくてすまなかったな。調べ物が増えてしまって、戻る暇がなかったのだよ」
「いったいどこに行ってたんです? それに、その格好…」
ルウェンの格好は、最後に別れた時の服装とは違っていた。もっと綺麗だったはずだ。それが今では、何十年と旅をしてきた旅人のような年季の入った服装をしている。
自分の服を見ながら、ルウェンは言った。
「ああ。追手がいてな。連中から逃げるために、これで三回着替えてきたのだ」
「お、追手ですって!?」声を押さえながらもピーターは驚いた声で言った。
それにしても、ルウェンは最後に会った時から十年は歳とったように、別人になっていた。その原因は、極度な疲れがたまっていたからだとルセスは思った。
「うむ。話す事は山ほどあるが、まずは宿へ戻ろう。ここで表立っていい話ではない」
三人は急いで店を畳み、宿屋へ戻っていった。
宿屋に戻り、食事を取った後に、ルウェンは語った。
「君達も思わなかったかね? 祭りか何かがあるとしても、だ。あまりにも人が少なすぎると。私はモネルダの中央区に足を運んだのだが、それでも人がほとんどいなかった。建物のほとんどは明かりが付いておらず、とても人がいるようには見えなかった。
そこで私は中央区を調べ、どこで何が起きているのかを探る事にしたのだ。その時にはもう夜も更けていたのだがな。そして数時間探していると、ある館へ到達した。その周りの建物は珍しく明かりがあり、まるで暗い森の中に村が一つあるような光景だった。
都に住む者はその館へ入っていった。その館というのがかなり大きなものでな。マルチェルダの城ほどとはいかないが、それに近い広さを持っていた。いったいなんの館なのか、私は気になりその館を調査する事にしたのだ。
館へ入っていくのはどれも都の住民だった。それは貴族、平民問わず、あらゆる人々が押し寄せるように入っていたのだ。私も入ろうと考えたが、それはやめておいた。なぜならその館は、都の民以外進入を許可されていないからだ」
「どうして、そんなことがわかったんですか?」とピーター。
「それは、中へ入っていくのが全員、老若問わず女性だけだったからだ」
それを聞いてルセスが首をかしげる。ルウェンの言葉の意味がさっぱりわからなかったのだ。
「女性だけ? …でも、それはどういう意味です? 女性だけだからって、そこの住民だってわかるものなんですか?」
「うむ。なぜならここにいる民のほとんどは、女性だけだからだ」
ピーターとルセスは同時に顔を合わせ、首をかしげる。しばらく虚空の時間が過ぎ、ルウェンが話を再開しようとする刹那、ピーターが思いだしたようにはっとした。
「うむ」ルウェンは頷いた。「話すと長くなるが、ここモネルダは他の四大勢力と比べて、マルチェルダとの親睦が一番深い都なのだ。マルチェルダが援軍の申請を出せば、このモネルダはすぐに対応し、協力してくれた。賊の掃討にだって、快く援軍を出してくれたものだ」
それなら、なおさらモネルダはマルチェルダに取って盟約を結びやすい関係なのではないだろうか。ルセスが疑問を口に出すのを待たず、ルウェンは続けた。
「アーチェルド中の賊が全て統率された今、マルチェルダとモネルダだけでは手に余る。それでも戦わざる得なかった。戦いは激戦となり、ここモネルダからそう遠く離れていない地、〈クセイン地方〉で繰り広げられた。
結果、モネルダはクセインから賊が流れ込むのを避けるため、クセイン地方で行われていた戦いに参戦し、全力で援軍を出した。その結果が……」
なるほど、わかったぞ。ルセスは頷いた。
「つまり、援軍としてこのモネルダの男たちが次々と狩りだされた、ということですね?」
「うむ。マルチェルダはモネルダに頼り過ぎた。そして、モネルダも私たちに甘すぎた。クセイン地方での戦いはモネルダとマルチェルダの勝利に終わるが、戦い事態は終わっていない。モネルダはさらに兵を送り、マルチェルダの支援をしてくれたのだ。それも、二年ほど前の話だ。今では、ここモネルダの住人で男はほとんどいない。残っているのは、女子供だけだ。それでもマルチェルダは、この状況だ、何もしてやれることがなかったのだ。君たちがここで見かける男性は、ほとんどが旅人だ」
確かに今思い返してみれば、男性より女性の方がここではよく見かけた気がする。それに自衛の騎士も都では見た記憶がない。
「旅人は宿や寝床にいる時間。そして都中の建物の明かりのなさから、住民は中央区の館へ集まっていると考えるのが妥当だ。そして中に入っていくのは女ばかり。さて、これでは男性で、さらに旅人である私が入る事はまず不可能だ」
「え、でも、なんで追手から逃げていることになってたんです?」夕方の事を思い出したようにピーターが言った。
「なぜ住民が館に集まるのか、私はどうしても知っておきたかった。だが、なるべく人に聞くのは避けたかった。いくら旅人とはいえ、夜中に唯一人が集まっていた中央区へ入るのは怪しまれると思ったからだ。
だから私は、彼女らの目を忍んでこっそりあの館を覗いてみようと思ったのだ。ここからの話は大分省くが、結果私は彼女たちに見つかり、館の中から出てきた屈強そうな男数名に追われる身となってしまった」
「じゃあ、それからずっとぼくたちの所まで来るのに、逃げてきたんですか?」顔の青ざめたピーターは驚愕の表情を浮かべている。
「ああ。何とか巻く事はできた、と思う」
「屈強な男、と言いましたね。都の住民でしょうか?」ルセスが鋭く問うた。
「いや」ルウェンは首を振る。断定してはいるものの、その目には疑心の光がまぎれていた。「男はすべて、兵に投与されたはずだ。恐らく別の地方から呼んだか、旅人を雇ったのだろう。もしここに男が残っているなら、相当強いコネのある貴族か、歩く事もままならない老人だけだ」
それを聞いたピーターが腕を組んでベッドの上で胡坐をかいた。
「うーん…なんだかわけがわからなくなってきましたね。いろんな気になることができて、どれから調べていくものか…」
「糸が絡まっているなら、一本一本取り除いていけばいいだけだ。時間はかかるが、それが一番適当な手段だ。それに、君達が心配することはない。私が単独でやるのだからな」
「でも、そんなのルウェン様だけに任せるなんて、ぼくは嫌です」
そうルセスがきっぱりと言うもので、ルウェンは一瞬戸惑いの表情を浮かべると思うと、すぐに厳しい表情へ戻った。
「だからといって、君たちに任せるわけにもいかない。マルチェルダから人を呼ぶ事もできるが、呼んでここに来るまでの時間があるなら、もっと徹底的に私が調査に取りかかるべきだ」
「ぼくたちだって、できることならなんでもやりますよ」
つかの間、ルウェンとルセスはお互いを睨むように強い視線を交えていた。その間に立
っていたピーターはおろおろと二人を見て、何か言おうと口を開くが、ぱくぱくするだけであった。
「ふぅ」沈黙を破ったのはルウェンのため息だった。そのため息は、どちらかと言えばルセスではなく疲れが原因で吐き出されたようだ。「こうなることを承知して、君をここへ連れてきたんだ。いまさらあがいたって、私では程度が知れるな」
ルウェンが微笑を浮かべたため、ルセスは緊張を解いて肩を落とした。
「では、ないかお手伝いをさせてもらえるのですね!?」
「あ、ああ。まあ、君たちは子供なのだから、簡単なものをやってもらおうと思うのだが…」
「例えば、どんなものです?」
「うーむ…まっ、それは明日考えよう」
「ぐへぇ」ベッドに倒れてピーターが言った。「ルウェン様も、真剣にやってるんだかなんだかわからないや」
「私は真剣そものさ。真剣だからこそ…」言葉を切り、ルウェンはルセスを見る。そのまなざしには期待に満ちた熱さがあった。「何を与えるべきか、思いつかんのだよ」
ルウェンが調べるべきものはどれも最重要なものばかり。そのうちのどれかを鉄だわさせるとしても、絶対的に慎重に選ぶ必要がある。
それに、今彼は疲れていた。今は休み、疲れのとれた朝に決めた方が、判断力も信頼できるというものだ。
「わかりました。じゃあ、明日また話しあいましょう」
「ああ、助かる。では、今日はもう寝るとしよう。お休み」
「おやすみなさい」
言葉を交わすと、それっきり何も言わずに三人はベッドに埋もれた。
翌朝までルウェンは大きないびきをかいて眠っていた。どれほど大変だったかわからないが、いびきが疲れを表しているのなら、今まで一緒に旅してきた中で一番苦労をしたのだろう。
それにくらべて、今朝は誰よりも早く起床していた。顔色も、昨日より十年は若返ったかのようにすっきりしている。
「さあ、朝だ。ルセス、ピーター、起きろ」
朝の柔らかい日が瞼を越して目に焼きつき、ルセスとピーターは目を覚ました。ピーターの頭は寝癖でひどいささくれができていて、ルセスはつい笑ってしまった。
「それで、ぼくたちの役割は決まったんですか?」ピーターが自分の寝癖を直しながら言った。
「あれからすぐに寝て今起きたんだ。決まっているわけなかろう」とルウェンは笑った。
「えぇっ。じゃあ、何も計画立ててないんじゃないですかぁ」
「だから、今からそれを決めるのだよ」
三人は早い朝食をとり、その日の商売は休業して、宿で話しあうことにした。とはいうものの、実際ルセスやピーター自信何をすべきかわかるはずもなく、ルウェンが悩んで考える様をただ見ているだけ、というのが今の現状だ。
「うむぅ…」
話しあいという名のルウェンの一人悩みが始まって小一時間、痺れを切らしたピーターとルセスは落ち着きなく彼を見ていた。肝心のルウェンは、悩んで悩んで、それでも答えがでないで悩んでいる様子だ。
「あの…」とうとうルセスが不満の交じった声を出した。それを見た隣のピーターがあわあわと焦っている。
「なにかね?」ルウェンはまるで廊下でばったり出会った知り合いに挨拶するような声で言った。
「決まらないのなら、ぼくたちが提案してもいいですか?」
「ほお、それは。なんだね、ルセス?」
「中央区の館について、調査させてください」
「なんと!」
驚くのも無理はないだろう。ピーターは勿論だが、いい加減ルセスの好奇心や大胆さになれてきたと思っていたルウェンですら、信じられないような顔をしているのだから。
「だって、ルウェンさまは変装していたとはいえ、もう顔も割れてるんでしょう? それなら、ぼくたちが一番その場所の調査に適任じゃないですか? ぼくたちは子供だし、顔だって知られてません。それに、ルウェン様はここじゃ有名すぎますよ」
「いやぁ、しかし…うむ、まあ、悪くは…ないか。……いや、やはり危険すぎる」
「き、危険なんですか?」とおどおどしながらピーターが言う。「あ、そういえばルウェン様は昨日ずっと屈強そうな男に追いかけられていたとか…」
青ざめ始めるピーターには目もくれず、ルセスは身を乗り出した。
「でも、他に方法はあります? 一刻も早く調査を進めたいなら、やっぱりぼくたちがあの場所へ行くしか方法はないんですよ。お願いです、ぼくたちに館の調査をさせてください!」
まっすぐ見つめてくるルセスの瞳から目を離さず、ルウェンも真っ直ぐ彼の瞳を見ていた。ルセスの瞳は深い海のような色をしているが、濁りが一切なく純粋だ。時たまに、その純粋さから、自分自身の罪悪感を感じてしまう。
しかし、今はそんなこと考えもしないかった。今そこにあるのは、純粋な気持ちが二つだけだ。
アーチェルドを救いたい気持ち、そしてその気持ちに応えてやりたいと思う気持ち。
ルウェンは半分諦めたような調子でため息を吐いた。
「仕方がない。駄目だと言っても、君はきっと無断で何かをしでかすような気がする。では、君らに値する相当の役目をやらねばならんだろうな」
ルセスとピーターの表情が明るくなった。ルセスはともかく、ピーターも力になれることは嬉しいようだ。が、彼はあまり今回得策できるものではないな、とルウェンは考えた。
「一応、中央区の館を覗いて追われる前、私はあの館についてできるだけ情報を集めていたんだ。あの館では定期的に都の民を集め、集会を開いているのだという。それがどういった内容なのか、都の民以外誰も知らない。もしかしたら、本当にただの集会なのかもしれん。今時期は虫が多く、農作物の被害が甚大だ、とか、旅人があまりに多いが、この時期なのだから出来るだけ都を繁栄させよう、とか、どこでも開かれる集会と同じ内容なのかもしれん。
あの屈強そうな男たちだって、今はほとんど女しかいないこの都を守るために雇われた者たちだったかもしれん。まあ、これは多分そうなのだろう。嫌な方へ考えるのが難しい条件だ。それなら、ルセス。君でも調査はできそうだな」
「え、あの、ぼくは…」ピーターが肩を吊り上げて言った。
「ピーターは私といてもらおう。中央区の館については私に考えがあってな。ルセスにしかできないことなのだ」
不安そうにルセスが眉をしかめる。
「身体が小さいから、屋根から中へ入らせるとか、ですか?」
「ハハハ…さすがに私も鬼ではない。子供である君にそこまでさせるはずないではないか。私がやってきたことに比べれば、ずっと楽だ。まあ、君の適切な判断が要求されるかもしれんが……後は、君に任せよう」
不安に曇っていたルセスの表情が少し晴れた。どうやら彼は、任せられた事に関して喜んでいるようだ。
「さあ、では準備に取り掛かろう。集会は今日もあるらしい。時間帯は昨日より早い夕方からだ」
鬼だ。ルセスは素直にそう思った。
「………この案は納得できません」
様子を見ていたピーターが抱擁するような苦笑を浮かべている。それがルセスは気に入らなくなってきた。
同じように、寛大な――どこかいやらしさを感じる――笑みを浮かべるルウェンが微笑を浮かべて言った。
「ハッハッハ、なかなか似合っているぞ。これなら、まず……」
ルセスが睨み、ルウェンは息を止めるように言葉を切った。今自分がどんな顔をしているのだろう。とにかく、ルウェンを黙らせるのに申し分ない眼をしたのだろう。
「はぁ…」ルセスはため息を吐いて、鏡に映る自分の姿を見た。
足首まである長いスカート。可愛らしいフリルの目立つ上着。小物屋でもよく見かける、花の髪飾り。
そして今までうなじで止めていた長い髪を全部降ろすと、まるで――
「かわいい女の子だね」
ルセスが思おうとしたことをピーターが言った為、ますますルセスは不満に思った。今は自分を見る全てが、気に入らなくなってくる。
「…他に案はないんですか? なんでぼくが、こんな恰好を…」
「いやいや、あの館はどういうわけか女性しか入れないようなのだよ。男子は中に入れず、館のすぐ近くの建物に預けられていたんだ。となると、だ。あそこへ入るには、女性が必要になるんだ」
「ぼくは男です!」
「だが、子供でもある。君くらいの年なら、女装したってわかるまい。ピーターではきびしいところもあるしな」
とはいうものの、さすがにこれはないとルセスは肩を落とした。彼は昔から、女の子みたいだと思われるのが一番嫌だった。確かに目も大きいし、肌も白く金色の長い髪がなびくところ、そう見えなくもないかもしれない。だが、それが原因でこんな恰好にさせられるのなら、いっそ髪の毛を短くして肌も日焼けしてもいいとルセスは考えた。
「それに、こんなんでうまくいくんでしょうか?」
「だから、それを君の判断に任せるんだよ。もし都の娘でないことがばれて、中へ入れないようだったら、もう引き返してもらって構わない。別の方法を考えればいいのだからな。だが中へ入る事ができれば、君の行動範囲内で君の出来る事をやってもらおう」
まあ、確かにルウェンの言うとおり、館へ入るにはこの方法くらいしかなさそうだ。だけど、やっぱり腑に落ちない。特に二人が必死で笑いを押さえているところを見ると。
「……二人とも、楽しんでいません?」
「でも、本当に似合ってるんだよ?」と嘘偽りない声でピーターが言った。
「うむ。声を少し高くできれば、どこからどう見ても女の子だ。これなら怪しまれないだろうな。あとは、言葉に気をつければ完璧だ」
なんだか反論する気が起きなくなってきた。すでにこんな恰好までしてしまったのだし、自分も同罪な気がしてきた。
「…とにかく、これっきりですからね?」
「おお! では受けてくれるのだな?」
「……これも、アーチェルドのためになるというのなら、行きますよ。夕方からでしたね?」
もうこうなったらやけだ。そう決めてみると、なんだか吹っ切れた気分になってきた。
「あ、ああ。では館まで案内しよう。君をそこまで送った後は、君の帰りを待って大人しく目立たないよう宿にでもいよう」
「それは、やめたほうがいいんじゃないですか?」
「どうして?」
「だって、ルウェン様は彼らに追われる身ですよ? 一緒にいたら、ぼくまで怪しまれるじゃないですか」
それに、これ以上自分を知っている人間にこの姿を見られたくなかった。親友のピーターでも、憧れのルウェンでさえも、だ。
ルウェンはルセスの主張に同意し、ピーターと宿に残る事にした。ピーターは不安そうにルセスを見送り、それでも冗談半分のようなセリフをルセスに残した。
「女の子らしく、だよ?」
ここに、師のランスロットがいなくて本当によかったと思う。初めて出会い、彼の瞳から情報を一瞬読んでしまったとき、彼は自分の第一印象を『女の子みたいだ』と思っていたのだから。こんな姿、絶対に見せるわけにはいかない。
これが終わったら、ルウェンとピーターにも口止めをしておかなければならないな。中央区の大きな館を目の前に、ルセスはそう思い、笑みをこぼした。
© Rakuten Group, Inc.