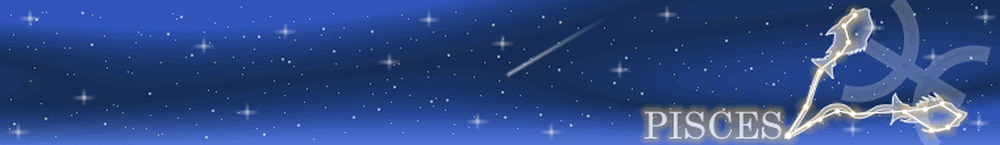小品「布袋(ホテイ)」
京造りは間口が狭い上に奥行が長いので、奥の土間は暗かった。おしめ等を洗っていた咲代は、ふと、その手を止めた。店先でことりと音がしたからである。
「あんた?---お客はんらしいえ。」
「うん」
生返事だけで、出て行きそうにもない。夫の居るだろう見当に顔を向けて、
「あんた!お客はんと違うかて言うてますのに・・・?」
「うん、今行く」
言葉数は増えても調子は同じであった。ほんに仕様のない人という素振りで、前掛けで手を拭き拭き、咲代は店に出て行った。が、直ぐに戻って来た。
「確か、ことっと音がしたのに、誰も居やはらへんわ。もう、今日で三辺目え。けど、あんなもん盗みに来る人もあれへんやろな。」
と言われて、
「何言うねん!店に出したアるもんには、一つ拾万円からするもんかてあるのんや。商売もんに何ということ言うのや、ほんまに、えらい女房もろたもんや。」
「へえ、えらい女房で悪おしたね。あたしが居いひんかったら、この子の世話、あんた、して呉れはりますのんか?」
どうですと言わんばかりの目を夫に向けてから、咲代は背中の末子の寝顔を見ようと、体ごと首を捩じった。首に力が入るから、口がへの字になる。それが清六の癪に障った。
「お前が居いひんかったら、この子も出来へんかった筈や。ほんまによう産む女や。」
「あたしに産ました人は、あんたどすやろ?・・・ほれほれ、ひどいお父さんやなア、かわいそうに、かわいそうに。」
そんな言葉を残して、咲代はまた洗濯にかかった。この末子で七人目であった。もうこれ以上はーーーという意味で、末子と名付けたのである。清六は、元来、のんき症で、父から土地等の不動産を譲り受けていることは、一層、彼を暢気にした。
それに清六は古いものが好きで、惚れ込んで貰った咲代が、年々古女房になっていくのに、内心安らぎを感じているのであった。また、古道具屋という商売も、いわば彼の趣味に近かった。毎朝古めかしい品物に、一つ一つ叩きをかけることが、彼の生き甲斐であった。
ここ二、三日は知人から借りた戦記ものの古本を、奥の部屋で読み耽っていて、店番もルーズになっていた。しかし、今はとっさの直感から、彼は店先に飛び出た。
棚の一番手前にあるべき布袋の置物が無くなっていた。今朝、いつになく荒っぽく叩きをかけて、その出っ腹から音がしたので、よく覚えている。清六は、やられたと思った。盗んだ者も憎かったが、気の緩んでいた自分に腹が立った。
仏像だの、甲冑だの、鏡台だの、櫛だの、等身大の人形だの、骨董ものでゴタゴタした店先であるだけに、ぽっかり空いてしまった棚の隅の空間が、淋しかった。
・・・・清六の肩が落ちた。咲代が後ろに来て、じっと見守っているのも知らなかった。盗まれた布袋の銅像は、値打ちものではなかった。たゞ、その腹の丸みが、他の布袋のものより秀でていた。黒艶のある豊かな腹の丸みに、清六は一家の安泰を託していたことに、この時、初めて気付いたのであった。
それから、そばに妻の居ることに気付いた。淋しげで虚ろな彼の目と、それを慰める咲代の目がしばし無言の語らいをした。
そこへ、老紳士が入って来た。咲代は奥へひっ込んだ。老紳士客は、やヽ大きな武者人形に目を付けたようであった。色褪せているにも拘わらず、その人形を見つけてくれた老紳士を、清六は有り難く感じて、揉み手をしながら、したり顔で上客に接した。盗まれた布袋のあった場所は、やはりぽかんと空いた侭で淋しかった。・・・<昭和44年6月20日作>
最終更新日 2005年01月10日 13時33分51秒
© Rakuten Group, Inc.