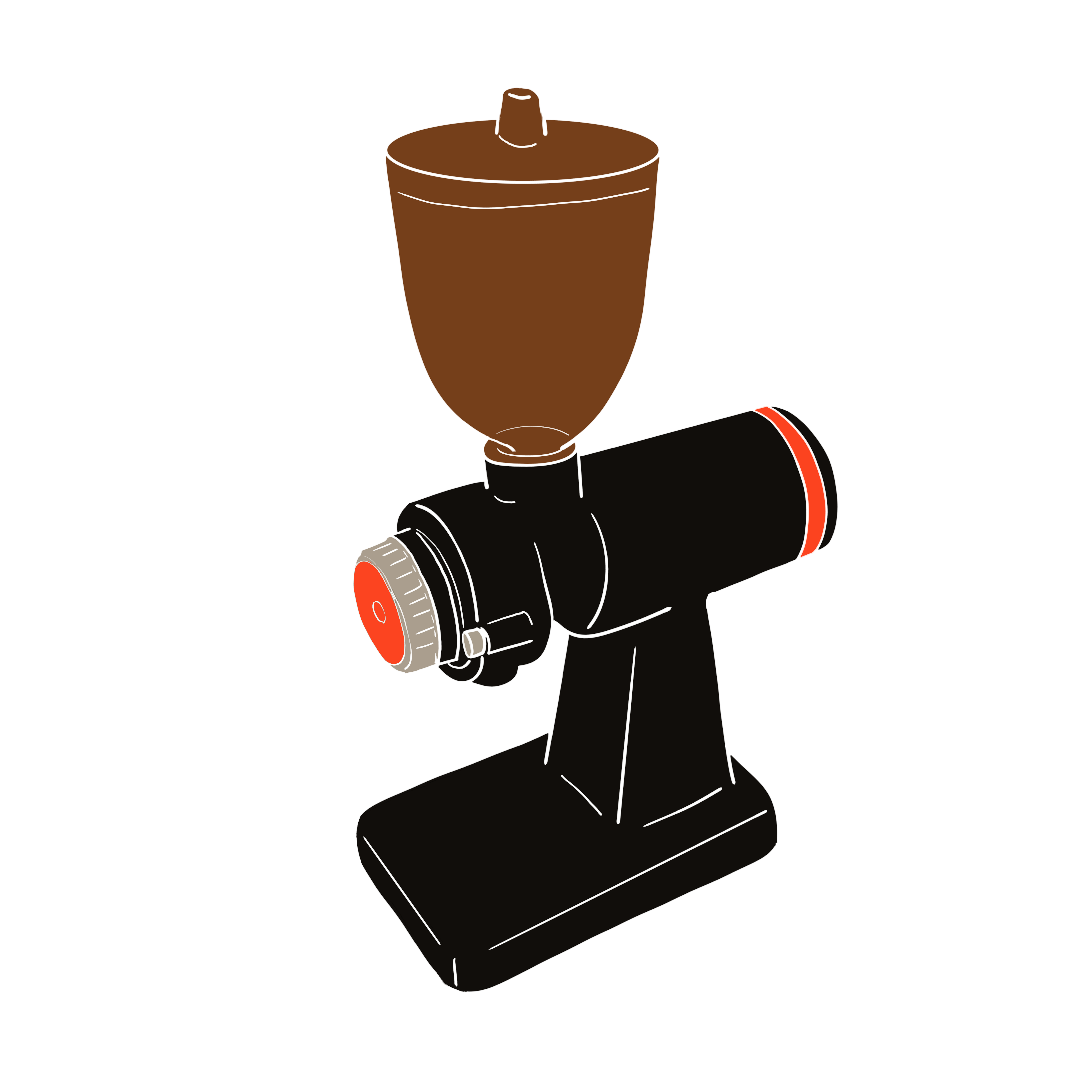カテゴリ: カテゴリ未分類
私、ノートつけるの好きみたい(笑)

謎に英語なのは、ついでに英語への抵抗感を減らすためです。これは結構昔からやっていること。あと、問題は継続すること。できるといいな。
焙煎を始めた頃は、そんなに考えていなかったのでノートなんてつけるつもりもなかったのですが、色々進めていくうちに焙煎によって全然違うことを体感してしまったので・・・記録することにしました。
しかし問題は手網焙煎ということ。機械だったら客観的に色々評価できるけど、私の武器は手網とタイマーと目視だけ。
でもその中でも何かできるのではないかと思いました。
まず、豆の情報は私でもゲットできるので、それは書く。産地はもちろん、標高や製法も大事。とはいえまだ理解しきれてはいませんが。
観察の情報としては、豆の色大きさや均一感、欠点豆の多さなど見た目ももちろん。
ひとまずの客観的な情報として10粒分の重さも記録することにしました。
品種によって大きさが違うので比較は出来ません。しかし、おそらくだんだん分かってくるはずです。ぼんやりとでも。そしてこの重さの情報は水分量に関係するところなので、それも焙煎のヒントにします。
これらの豆の情報から、焙煎前に決めることは
①スタートから豆全体を温める”弱火”時間を何分にするか?
②そこから1ハゼまでを何分に設定するか?
というところが大きな決定ポイントになります。
例えば大粒で、不揃いで、水分量が少なそうなら①の時間を長めにします。①を疎かにすると半焼けになってしまうので。
②の時間は酸味・甘味・粘性に関係しそうなので、豆の特製と自分が目指すゴールによって決めます。例えば甘味を出したいときは②の時間を短めにします。
そして、肝心なところは実際にやってみたときに、想像と違う場合にどうするか、というところまで考えておくところ。何せ、客観的評価がほぼないので、予想より色の代わりが早い!なんてこともあるし、逆もまた然り。それによって若干火加減を変えます。
もうひとつ重要なポイントは、火加減をなるべく客観的にするために、コンロの火力は常に最大にし、距離で火の強弱を変えます。これもできるだけ条件が同じになるように、火から5cmおきにテープで目印をつけます。これまではテキトーにやっていたけどテープを貼るだけでかなり統一的にできていると思います。
と、ここまで書いていますが
ちなみに参考にしたHPはこちら
https://donatecoffee.hatenablog.com/entry/2018/07/12/201344
英語も読んでみましたが専門用語が多く、ありがたいことに日本語訳してくれているので読みやすいです。
やはり豆の特性を最大限に美味しく焙煎できるようになりたいのよね。
何回かノートをつけながらやってみましたが、結構いい感じです。
具体的に戦略を考え、こうすればよかったかな?といった反省もできるし、実際に飲んでみて考察できるから。
今日はとても感動的な焙煎ができましたが、それはまた今度書きます。

謎に英語なのは、ついでに英語への抵抗感を減らすためです。これは結構昔からやっていること。あと、問題は継続すること。できるといいな。
焙煎を始めた頃は、そんなに考えていなかったのでノートなんてつけるつもりもなかったのですが、色々進めていくうちに焙煎によって全然違うことを体感してしまったので・・・記録することにしました。
しかし問題は手網焙煎ということ。機械だったら客観的に色々評価できるけど、私の武器は手網とタイマーと目視だけ。
でもその中でも何かできるのではないかと思いました。
まず、豆の情報は私でもゲットできるので、それは書く。産地はもちろん、標高や製法も大事。とはいえまだ理解しきれてはいませんが。
観察の情報としては、豆の色大きさや均一感、欠点豆の多さなど見た目ももちろん。
ひとまずの客観的な情報として10粒分の重さも記録することにしました。
品種によって大きさが違うので比較は出来ません。しかし、おそらくだんだん分かってくるはずです。ぼんやりとでも。そしてこの重さの情報は水分量に関係するところなので、それも焙煎のヒントにします。
これらの豆の情報から、焙煎前に決めることは
①スタートから豆全体を温める”弱火”時間を何分にするか?
②そこから1ハゼまでを何分に設定するか?
というところが大きな決定ポイントになります。
例えば大粒で、不揃いで、水分量が少なそうなら①の時間を長めにします。①を疎かにすると半焼けになってしまうので。
②の時間は酸味・甘味・粘性に関係しそうなので、豆の特製と自分が目指すゴールによって決めます。例えば甘味を出したいときは②の時間を短めにします。
そして、肝心なところは実際にやってみたときに、想像と違う場合にどうするか、というところまで考えておくところ。何せ、客観的評価がほぼないので、予想より色の代わりが早い!なんてこともあるし、逆もまた然り。それによって若干火加減を変えます。
もうひとつ重要なポイントは、火加減をなるべく客観的にするために、コンロの火力は常に最大にし、距離で火の強弱を変えます。これもできるだけ条件が同じになるように、火から5cmおきにテープで目印をつけます。これまではテキトーにやっていたけどテープを貼るだけでかなり統一的にできていると思います。
と、ここまで書いていますが
ちなみに参考にしたHPはこちら
https://donatecoffee.hatenablog.com/entry/2018/07/12/201344
英語も読んでみましたが専門用語が多く、ありがたいことに日本語訳してくれているので読みやすいです。
やはり豆の特性を最大限に美味しく焙煎できるようになりたいのよね。
何回かノートをつけながらやってみましたが、結構いい感じです。
具体的に戦略を考え、こうすればよかったかな?といった反省もできるし、実際に飲んでみて考察できるから。
今日はとても感動的な焙煎ができましたが、それはまた今度書きます。
送料無料!! 生豆 スペシャルティ・プレミアムコーヒーお試し焙煎飲み比べセット 300g×5銘柄 1.5Kg|お試しセット アサヒコーヒー 自家焙煎 旭コーヒー スペシャルティコーヒ− プレミアムコーヒー
価格:5724円(税込、送料別)
(2022/10/30時点)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2ca300bd.50472551.2ca300be.741ba4c6/?me_id=1374079&item_id=10000083&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fasahicoffee%2Fcabinet%2Fspblend%2Fnamamameota%2Fnamamamea001.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)