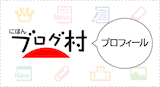PR
Keyword Search
Calendar
今回それなりに長文です、お時間の無い方と読むの面倒な方はスルーでお願いします。
いきなり余命3トン宣告でマグロ遊漁者一時パニック。

広域漁業調整委員会で決定
先日広域漁業調整委員会が開かれましたね。
7月29日に開かれた太平洋広域漁業調整委員会では太平洋海域で クロマグロの大型魚を狙う遊漁者に対し、期間を定めて採捕を禁止できる追加処置を設けました。
これはTACに支障を及ぼす量に達したと認められた場合、委員会の会長が公示できものなんだとか。
ちなみにこの目安となる数字が、 全国の合計で20トン程度を超える時 とのことです。
今年6月から大型魚を採捕した場合、報告を義務付けて、その結果、2週間程度で10.8トンに到達しました。
それが6月末で14.7トン、7月28日時点で16.8トンとなったようです。
私なりにこの問題について、いくつかの疑問や何でこうなったんだ?と色々思うところがあったので少し整理してみました。
●いつから何で遊漁を対象とする採捕の数量が20トン程度となったのか?
●委員会の指示で遊漁を対象とする指示ってのはどうなのか?
●全国で20トン程度だと不平等すぎる。
●恨みやっかみで嘘の報告があるのではないか?
●委員会が遊漁を対象に指示をするのであれば、委員会のメンバーの中に遊漁者代表を複数名入れるべき。
●正確な遊漁の採捕量がわからなくなった。
●そもそも遊漁に規制は必要なのか?
などです。
それでは個別に書いていきましょう。
私が感じた率直な問題点と感想
まず、
●いつから何で遊漁を対象とする採捕の数量が20トン程度となったのか?
についてですが、んー。これ多くのアングラーにとっては結構突然でしたね。
もしかしたら関係者の間では知っていたことなのかもしれませんが、この20トンの根拠と言うのが2021年漁期の大型魚留保枠は81.7トンらしいのですが、50トン程度が漁業による突発的な積み上がりへの備え。
10トン程度が試験研究など。
そして、その 差し引き21.7トンが遊漁による採捕の限度 とのこと。
これ、サラっと新聞に書いてたんですけどね、そもそも何で
遊漁の枠が 留保枠 なんでしょ?
まず、そこが疑問。
しかも、留保枠の中の余った部分しか割り当てられていないって、疑問に思いません?(笑)
また、 20トン程度って枠ですが、少なすぎるんです。
日本にはマグロを対象とした遊漁船が1100隻いるそうなんですね。その内、クロマグロを対象としている数はわかりませんが、仮に、20トンを1100隻で分け合うと 一隻あたり約18キロしかキープできない ことになるんですね。
こんなことってありえますか? この10倍ぐらいあっても良い気しませんか?
さらにプレジャーボートを入れたら一隻あたり年間10キロぐらいしかキープできないんじゃないのか?って思いますよ。
それ後出しじゃんけん過ぎる と思ったんです。
もっと早くから今年度の採捕量を遊漁者に伝えていれば、こんな時期にこんな採捕量にならなかった。
と思うんですね。(これからモンスターサイズが期待できるのに・・・・)
シーズンが始まる前に、そして多くの人にわかるように今年は20トンと言えない理由があったんでしょうか?
これが一つの不信感としてあります。
そもそも遊漁の枠自体も必要なんでしょうか?そんな素朴な疑問もあります。
そして、
●委員会の指示で遊漁を対象とする指示ってのはどうなのか?
についてですが、これもサラっと言ったな~と思ったんですけど、 遊漁者を対象って何ぞや?? ってことなんです。
大体この手の指示って、都道府県の規則とごっちゃになりやすいんですけど、今年の千走川のマスの指示であったように、「○○海域でいつからいつまで採捕を禁止、ただし、承認を得た〇〇は可能~」とか「こうなったら~~の操業を禁止」とか「〇〇業を営もうとする者は承認を受けろ」って感じが多いような気がするんです。
これは、漁業者も含めてですよね。
しかし、今回なんと!!! 遊漁者による って前置きがついてるんですよ(笑)
ターゲットは遊漁者のみです。
日本海・九州西広域漁業調整委員会会長は、日本海・九州西海域における遊漁者によるくろまぐろ(大型魚)の採捕が、漁獲可能量制度に基づくくろまぐろの資源管理の枠組みに支障を来すおそれがあると認めるときは、期間を定め、日本海・九州西海域において遊漁者によるくろまぐろ (大型魚) の採捕を禁止する旨、公示する。
引用:水産庁HP 日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第67号(案)
ちなみに、 広域漁業調整委員会って言うのは 、 我が国周辺水域における水産資源の管理を的確に行うために、都道府県の区域を越えて広域的に分布回遊し、かつ、それを漁獲する漁業種類が大臣管理漁業と複数の知事管理漁業にまたがる水産資源の管理に係る漁業調整を行うことを目的に、平成13年の漁業法の改正により 国の常設機関として設置されている ようで、
うーむ。漁業調整ですか。
で、その機能は
広域的に分布回遊する資源を対象とした資源管理に関する事項(当面は国が作成する資源回復計画に関する事項が中心)について協議調整を行います。
1.複数都道府県にまたがる海域を回遊する魚種の資源管理についての検討
2.資源回復計画の作成に係る審議
3.資源管理措置の適切な実施を担保するための「委員会指示」の発動
4.1に関連する漁業調整
引用:水産庁HP
とのことですが、資源管理をする上で、規制をするのはわかるものの、 追加で遊漁者のみを対象をするはいかなものか? と思います。今までも十分な規制は遊漁者にあったはずです。
釣り人目線をお話をさせていただくと、巻き網自体は問題のない漁かと思うのですが、時期を考えることも資源回復計画に入れていただきたいところです。(色々理由があるはわかりますけど)
北海道のアングラーの私としては 川に上がったサケを網でせき止めて全て丸ごと捕まえている、そして「資源回復しねー。」って言ってると同じ感覚 なんですけど(;´∀`)
それも、大した脂の乗っていない、しかもこれから産卵する前の魚です。そりゃ、単価も安く大量に獲らないと儲からないし、資源も回復しませんよ(笑)
それなら 遊漁者のみを対象とするのではなく、同じく漁業者も対象にすべきです。
その方が圧倒的に効率は良いのですから。
確かに、 委員会が漁業法の枠組みの中の機関であるとすれば 、 漁業法自体は 漁場の総合的な利用による漁業の発展を目的とする法律 で、漁業権、漁業の許可、漁業調整委員会等について規定しているので 可能 かもしれませんけど、ちょっと・・・ 自分達ファースト であんまりだなって感じです。
ただ、水産庁のHPに書かれているとおり、これ漁業法の第120条1項が基になっていると私は思うのですが、 漁業調整委員会は水産動植物の繁殖保護など漁業調整のために 遊漁者を含む関係者に対して 、水産動植物の採捕等に関する指示をすることがでるそうなんです。
具体的な例として、漁具・漁業の制限、禁止区域、体長の制限等の指示と書いていたのですが、今回のケースは特殊なんでしょうか?
ちなみにこの法律がよくわかっていなかったので、参考程度に漁業法をザーっと調べてみました。
120条1項にはこう書かれています。
海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権(第六十条第一項に規定する漁業権をいう。以下同じ。)又は入漁権(同条第七項に規定する入漁権をいう。次条第一項において同じ。)の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。
関係者と書いていますが、特に遊漁とは書いてはいません・・・遊漁も関係者なの?
んー。
この辺詳しくないのでこの辺で。
続いて、
●全国で20トン程度だと不平等すぎる。
についてですが、これもサラっと言われてますけど、微妙すぎません?
マグロシーズン、仮に山形、新潟、秋田、和歌山、九州付近でシーズンインしたとして、これ、この地方で20トンを我先に獲ったら青森、北海道に来る前にシーズン終了です。
上手に何らかの方法で配分しないと同じ遊漁でも エリアによる不平等は今後出てくるでしょう。
この辺、遊漁者同士、あとは調整がんばってー!!って感じなんですけど、ん~~~。
誰がどうやってするの?って感じです。
●恨みやっかみで嘘の報告があるのではないか?
そうそう。この報告。誰でも簡単にできます。
この報告が100%全て事実なら良いのですが、遊漁業界に恨みのある方、マグロアングラーへのやっかみがあり、困らせたいがために嘘の報告をバンバンする人。
いずれ出てくるんじゃないのかと思います。
果たして、 この報告に信ぴょう性はあるのでしょうか?
正直、いちいち報告者が実在する人物なのか?報告が事実など調べるわけないと思うんですがね。
んーー。
こんな闇を感じると こんな報告自体あまり意味の内容
に感じてしまいました。
また、太平洋広調委の委員らはすべての釣り人が遊漁団体の傘下に収まっていない点について、 「実際にどれだけの遊漁者がマグロを釣っているのか。漁業同様の努力量が出せない限り、枠を分け合う事はできない」
など言及したそうです。
お互いの信頼関係もないのも原因かと思いますが、なんか、なおさら報告がいらないような気がしてきました・・・・。
ってか遊漁の枠?そんなのいつ、だれが、どこで決めたの?
初めて聞いたけど。
しかも何でこんな規制入ってるの?釣り人が釣りまくったから??
違いますよね。
で、今釣り人にしわ寄せが来てるの?
絶対におかしいと思います。
自分達が蒔いた種なのに?
その始末を釣り人にさせるのもどうかと・・・。
次。
●委員会が遊漁を対象に指示をするのであれば、委員会のメンバーの中に遊漁者代表を複数名入れるべき。
についてですが、残念ながら広域漁業調整委員会に遊漁者はいません。
それでも今年遊漁に関する3団体の代表が参考人として意見を述べる機会をいただきました。
(日々、多くの釣り人のために努力していただいた団体のみなさんありがとう!)
しかし、意見を述べる機会をいただけただけです。
遊漁者を対象とする指示を出すのであれば、委員の中に遊漁者の代表も入れるべき
だと思います。
そうでなければ、今後理不尽な指示を我々遊漁者に一方的に出される可能性があります。
可能性があると書きましたが、今回出されましたね・・・。
私の意見としては、 資源管理に遊漁者を対象とする指示を出したという事は、遊漁による資源管理をすれば、 一定の資源は回復・そして管理をできる
と、今回委員会に言われたと同じこと
です。
なので、広域漁業調整委員会が「我が国周辺水域における水産資源の管理を的確に行うため」の委員会であると言うのであれば、 遊漁者も委員会の委員として入れるべきである
と考えます。(マグロ漁だけでないのはわかりますけど)
この辺、各委員会の例規集などあるのか調べてみましたがネットではうまく見つけることはできませんでした。
特に委員会の構成に規定がないのであれば、場合によっては遊漁者代表も入れて欲しい
と思います。
●正確な遊漁の採捕量がわからなくなった。
資源を管理する上で重要なことは何か?
それはまず 数字を把握すること
です。
話は変わりますが、今年の北海道はクマのトラブルが多いように感じましたね。
その度に頭数管理をしろ!とか声をあげる方をネットでよく見かけましたが、まず大切なのなのは現状を把握し全体の数字を把握することです。そこがスタートの一つなわけですね。
そして、細かくどのエリアにどんな分布をしているのか?など吟味していくのですが、釣りも同じなんじゃ?と思っています。
今回、開始早々2週間足らずで遊漁自粛の協力要請が入り、そして、いきなりあと3トン程度で大型の採捕ができなくなるってことに今なったのですが、私は、 この一年はガチで釣り人に釣らせるべき
だったと思います。
そうじゃないと、しっかりした数字が把握できません。それは採捕場所であったり、量、時期もです。
そうなると、遊漁の全体の採捕量もわからず、今後も20トンって頭ごなしに言われるだけなので、 遊漁にとって、適切な採捕量の設定も難しくなる
でしょう。(遊漁がどれだけ我慢してるかわからなくなる)
と、言うのもこれから海が荒れやすくなって出航率がガクっと落ちますよね。
漁師は別にキャスティングでマグロを獲るわけではないので、多少海が荒れてても漁はできるのですが、釣り人はそうはいきません。
加えて海が荒れると狙ってキャストもできなくなりますし、ナブラも見つけずらくなりますし、ファイトもラインディングも難しくなります。そもそも、釣りが成立しません。
5月~8月ぐらいまでは調子よく釣れてた物が徐々に釣れなくなるわけですから、この辺の推移もしっかり把握できるように今年ぐらいは数字を取って欲しかったのが本音です。
また、以前水産庁はこう言っていました。
遊漁は地域活性化策としても期待される一方で、資源管理の重要性が高まる中で、遊漁における資源管理の取組を図ることが必要となってきています。このため、水産庁では、遊漁と漁業の共存及び資源管理に関する検討を令和元(2019)年度より開始したところであり、今後もこれを進めていきます。
引用:水産庁ホームページ
遊漁は地域活性化策としても期待されるのです。
道具の購入も含めるとそれなりの産業になるのです。そう考えるとただマグロを釣ってるだけじゃないんだなとも思えます。
話は少しずれてしまいましたが、私はまずは一年遊漁者が釣りをすると日本全体でどれぐらいの量が採捕されるのか、リサーチする必要があったのではないか?と思いました。
●そもそも遊漁に規制は必要なのか?
はい。ラストです。
産卵期における巻き網の漁獲量はとてつもない量です。一日でその辺の港の一年分の量を獲るぐらいです。
それさえやめれば、 全ての釣り人がこんな思いをしなくてよい と思うのが私の感想なのです。
そして、 巻き網漁をしていない多くの漁師もこんな思いをしなくてもよい と思っています。
もしかすると、産卵期の巻き網を漁業者の中でも良く思っていない地域もあるかもしれません。
であれば、この件について遊漁者と漁業者の一部でタッグを組んで協議してもよいかもしれません。
先ほど、述べた委員会の中に遊漁者を入れるメリットとしてこんなメリットも後々出て来るかもしれませんね。
で、同じ釣り人でも賛否両論があると思いますが、資源が回復傾向にある今、私は 30キロ未満のマグロを採捕しなければ、遊漁者による規制は特にいらない と個人的に思っています。
と、言うのも、 信ぴょう性のない報告をしても意味がないという事と、急激に資源を回復させるのも危険 じゃないのかと思う部分もありまして。
マグロことだけ考えて言うのであれば、マグロ漁をしないのがベストかと思いますが、マグロが急激に増えるとイワシとかイカとかどうなるの?って思うところもあります。それで生活をしている方もいるわけです。小型のマグロと言ってもウン十キロですからね。それなりの海産物は食べますよね。
それでも規制は必要だと言うのであれば、例えばの話、自主的に大型魚のキープラインを50キロ以上などに上げる選択肢もあるかと。目測で50キロが判断できないのであれば、長さでもよいと思います。
そう考えると遊漁に採捕禁止と言う処置はって必要なの?って思う事がよくあります。
多少の意見の違いはあるにしても、私達の知らないところで、多くの遊漁者のために日々がんばっていただいている方も多数いると思うのですが、背中を押してあげられる機会が与えらるのであれば、是非協力したいですね。
※もし今回の記事で私の知識不足で全く違うこと書いてたらごめんなさい。正確な情報を知ってたらこっそりツイッターで教えて下さい(笑)
まとめ
っと言う私の感想でしたー。現状ではひたすらリリースすると言う選択肢しかありません・・・。
もうね、あと3トンで終了だよって時にいきなり言わないでよね!!遅いよっ!!!って感じなんですけど、長くなりましたがこんな感じです。
本当はまっっっっっっっっっっだまだ書きたいことあるんですけど、今回は読むのも大変だと思うのでやめておきます(笑)
最終的には色んな関係者の良い落としどころがあれば良いなと思っています。
とりあえず、採捕は禁止になったとしても釣り自体は続けれるなら続けたいですね。
-
【マグロ】あなたが単独ファイトできない… 2024.10.25
-
マグロに壊されたウッドプラグ補修。 2024.10.14
-
クロマグロ釣りが四日で終了なんだけどそ… 2024.08.03