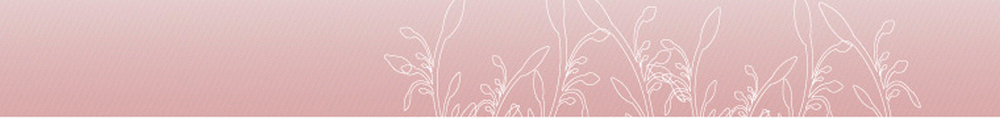全6201件 (6201件中 1-50件目)
-

大阪市内全ての福祉事業所を対象に調査 障害者の就労支援を行う事業所の給付金過大受給疑惑を受け。
大阪市内全ての福祉事業所を対象に調査 障害者の就労支援を行う事業所の給付金過大受給疑惑を受け 大阪市で障害者の就労支援を行う事業所が、給付金を過大に受け取っていた疑惑を受け、市は同様の支援を行う全ての事業所を対象に調査に乗り出しました。 福祉事業会社「絆ホールディングス」に関連する5つの事業所は、障害者の就労支援で国などから給付される加算金について、利用者を自らの事業所で雇用し、その後利用者の立場に戻して再び雇用するなどし、20億円以上を過大に受け取っていた疑いが持たれています。 市は監査を行っていますが、他の事業所でも過大受給がないか確認するため、17日から市内全ての福祉事業所を対象に調査に乗り出したということです。 大阪市・横山英幸 市長「調査をかけて、状況を把握した上で、通常では考えられないような状況があれば、重点的にチェックをしていくことになると思う」就労支援のための加算金が、ルールに基づいて申請されているかどうかなどを確認するということで、事業所に28日までに回答するよう求めています。【YTV NEWS NNN】(動画あり)氷山の一角とならないといいですね。昨日は前代未聞の一万アクセス越え、昨日(11/25)のアクセス数13510トータルのアクセス数6233770ということで623万アクセス達成しております。いつもご訪問にコメント感謝です。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.11.01
コメント(0)
-

障害書かされ自殺、遺族敗訴 社会福祉法人に賠償請求。
障害書かされ自殺、遺族敗訴 社会福祉法人に賠償請求 精神障害や知的障害のある大阪市の男性=当時(36)=が2019年、市営住宅の自治会役員から障害があることを書かされ自殺した問題を巡り、調整を担った社会福祉法人の対応に不備があったとして、男性の両親が約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は14日までに請求を棄却した。 争点は、男性と法人側との間で調整を巡る契約関係が認められるかどうかだった。斎藤毅裁判長は判決理由で「法人の担当者は男性から相談を受け、自治会役員らと調整し、話し合いに同席したが、相談への対応の延長だった」と指摘。両者の間に準委任契約が成立したとは認められないとした。 判決によると、男性は市営住宅で1人暮らしをしていた19年11月、自治会の班長決めで選出対象から外してもらおうと同法人に相談し、役員との調整を依頼。法人の担当者も同席した役員との話し合いの場で、他の住民に説明するためだとして「おかねのけいさんはできません」などと書かされ、その後自殺した。KYODO[YAHOOニュース]ご遺族にとっては辛い結果となりましたね。生きている内に、もう少し、寄り添った対応はできなかったのかと悔やまれますね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.31
コメント(8)
-

知的障害の男性が児童ケア。
知的障害の男性が児童ケア養護施設で支援職、異例 活躍も「周囲の目」不安 関東地方の児童養護施設で、軽度の知的障害がある男性(40)が子どもの世話全般を担う職員として働いている。知的障害者が福祉施設や保育所で働く例はあるが、清掃や補助的な業務が多く、子どもを直接支援するのは珍しい。ただ、男性は「周囲からどう見られるか」と不安も漏らす。「本当はそんなことを気にせずに済む社会になってほしい」と願っている。 「これ買ったんだよ!」。9月下旬、児童養護施設のリビング。4歳の男の子がおもちゃを見せながら、うれしそうに男性に抱きついた。男性は別の児童と将棋を指しながら、ざっくばらんに子どもたちと日々の出来事を話し合う。 男性は2021年からこの施設で働く。中学生の時に知的障害...(この先は会員限定です)【新潟日報】既に4年もこのお仕事に従事されていてすっかり馴染んでいられますね。回りの目が気になるのも健常な証拠ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.30
コメント(8)
-

障害者社員 制服からPCバッグ。
障害者社員 制服からPCバッグJR西など再利用 あすから限定販売JR西日本と特例子会社のJR西日本あいウィルは、鉄道事業で使い終えた制服を活用し、障害を持つ社員らが制作したPCバッグを、17日からJR西の公式オンラインショップで限定販売する。障害者雇用の拡大と廃棄資源の活用を目指す。 両社は障害を持つ社員を計約470人(今年6月時点)雇用しており、雇用率は2・69%。グループとして、2027年度に2・8%に引き上げる目標を掲げている。一方、鉄道事業では、駅員や乗務員、保守社員らが使い終えた制服が毎年回収されており、活用が課題となっていた。これまでも、あいウィルで働く障害者らが、汚れの程度などに応じて制服を仕分け・裁断して、コースターやパスケースに生まれ変わらせるアップサイクルに取り組んできたが、障害者が関わる工程や商品のラインアップを増やすため、ノートパソコンを収容できるPCバッグ(縦約25センチ、横約36センチ)の制作を始めた。汚れや傷みの少ない制服の上着を使い、胸ポケットや社名ロゴなどをいかしたデザインで、再利用した制服によって「駅・乗務員」「施設・電気保守社員」「車両保守社員」の3種類あり、先着順で各15個を限定販売。いずれも2万2000円(税込み)。【読売オンライン】乗務員らの制服から作ったPCバッグすてきなPCバッグですね。リサイクル品でも貴重なだけにかなりの高価品ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.29
コメント(11)
-

障害者就労で労基署から是正勧告 「人権重視」の区長に思わぬ失点。
障害者就労で労基署から是正勧告 「人権重視」の区長に思わぬ失点現場へ! いま、杉並で(5) 東京都杉並長の岸本聡子(51)は9月2日の記者会見で、杉並区障害者団体連合会が新宿労働基準監督署から労働基準法違反の是正勧告を受けた、と発表した。 同連合会は15の障害者団体からなり、区の障害者交流館の運営を受託している。連合会は知的障害者や精神障害者の就労訓練として、都の最低賃金の半分以下の時給520円で清掃作業に従事させていた。労基署はこの清掃員を労働者と判断し、最低賃金に満たない部分を支払うよう勧告した。 実は、この問題は2年前に区議会で表面化していた。区議の田中裕太郎(50)が質問で、「杉並区障害者団体連合会が清掃員を最低賃金以下で働かせている」と指摘した。・・(この記事は有料記事です)[朝日デジタル]熊狩猟の猟師の皆さんにも言えることだけど、賢明に任務に励む者への賃金の配慮が無さ過ぎますね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.28
コメント(7)
-

これってわがままですか? 障害者差別を考える UR、知的障害者入居拒否 なぜ、借りられないの 「同居親族要件は差別的」。
これってわがままですか? 障害者差別を考える UR、知的障害者入居拒否 なぜ、借りられないの 「同居親族要件は差別的」なぜ、借りられないのか――。独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が1人暮らしを始めようとした大阪府枚方市に住む知的障害のある女性(60)の入居申し込みを断っていた。国は障害者の暮らしの拠点を入所施設から地域へ移そうとしているが、障害者の住まいの確保にはなお高い壁が横たわる。女性は2024年12月、市内のUR枚方営業センターを訪れた。弟の結婚に伴い、姉弟2人で暮らしていた実家を出る必要があったからだ。1人暮らしの準備はその1年前から始めていた。女性が通う作業所を運営するNPO「パーソナルサポートひらかた」(枚方市)の支援を受け、NPOが借りるワンルームマンションで自立生活に向けて練習した。週に2~3泊し、定期的に訪れるヘルパーと共に家事もこなした。 NPOは女性の自立生活は可能と判断し、職員も説明するために営業センターに同行した。だが、センターの窓口のスタッフから「(療育手帳が)Aの場合、審査で引っかかる可能性がある」と告げられた。大阪府が発行する療育手帳ではアルファベットで障害の等級が決められ、重度の知的障害は「A」に区分される。女性は自閉症でAと判定されたものの受け答えは可能で、作業所で働く前には枚方市役所で非常勤職員として30年近く勤…(この記事は有料記事です)【毎日新聞】弟さんに他の住まいを探して貰うのが得策なのでしょうが、こういう事態は実際に起きている訳で、国は早急に対策を掲げないと、ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.27
コメント(10)
-

特別支援学校で段ボールの車制作。
特別支援学校で段ボールの車制作トヨタ自動車は13日、愛知県瀬戸市の瀬戸つばき特別支援学校で、知的障害のある生徒が段ボールの車を制作するイベントを開いた。社会貢献活動の一環として企画した。誰でもつくりやすい設計「ユニバーサルデザイン」を学び、将来の職業を考えるきっかけにもしてもらう狙いだ。高校1年の約50人が参加し、オープンカーとトレーラー、小型トラックをつくった。トヨタ社員の手助けを受け、段ボールや発泡スチロールの部品を組み立てたり、水性インクで車体を桃色に塗ったりした。段ボールの折り方は山折りに統一して作業を簡単に。一部の生徒はカッターを使って部品を切り出すなど障害の程度に応じ作業を分担した。【カナロコ】 知的障害のある生徒らが制作した段ボールの車=13日午前、愛知県瀬戸市インパクトのある、素敵な作品に仕上がりましたね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.26
コメント(10)
-

「♯国は安楽死を認めてください」の先に存在する恐怖の現実。
「♯国は安楽死を認めてください」の先に存在する恐怖の現実「生きるのに向いていないから、生きるのを辞めたい」「他人の自殺に巻き込まれたくないなら、安楽死を認めよう」「国は楽に確実に死ねる薬を解禁してくれるだけでいい」「#国は安楽死を認めてください」というタグとともに、こんな悲しい投稿が毎週土曜日にX(旧Twitter)にあふれていることを知っている人は、どのくらいいるのでしょうか。実はこれ「安楽死デモ」と呼ばれており、毎週土曜日の夜にはXのトレンドになっています。デモの方法はシンプルで、土曜日の夜7時以降に、Xに「♯国は安楽死を認めてください」というタグをつけて、自分の安楽死したいという願望を投稿するのです。しかしその参加者のプロフィールを見ると、うつ病などの精神疾患や発達障害で苦しんでいる人、知的障害や境界知能のため生きづらさを感じている人がちらほら見受けられるのが、とても気にかかっています。わたし自身双極性障害とADHDを抱えており、障害者がこの国で生きることがどれほどつらいか分かっているつもりです。しかし、その「国に安楽死させてほしい」という願望を持っている方々に、確認しておきたいことがあります。現在、すでに先行して安楽死を合法化した国がどうなっているか知っても、まだ「安楽死したい」と思いますか?「安楽死」とは何か「安楽死」とは、人または動物に苦痛を与えずに死に至らせることを指します。一般的には終末期患者に対する医療上の処遇を意味します。その安楽死にもいくつか種類があり、医師が患者に致死薬品を投与する積極的安楽死と、治療を行わないことで死に至らせる消極的安楽死があります。そこに加えて医師が致死薬を用意し、安楽死を希望する患者が自ら服用する「医師による自殺ほう助」という手法を容認する、国や地域が増えてきました。数年前にNHKで「彼女は安楽死を選んだ」という番組が放送され、その中で安楽死希望者の命が消えるまでを放送されたことが物議をかもしましたが、彼女が死に場所として選んだスイスは、実は「医師による自殺ほう助のみを、刑法の解釈にもとづき認めている」だけにすぎません。「デスツーリズム」(安楽死の旅)といえばスイスだと連想する人は多いのではないかと推測しますが、スイスは積極的安楽死を認めていないのです。また、スイスで自殺ほう助を受ける場合、厳しい条件と手続きをクリアしなければなりません。これは自殺ほう助の乱用を防止し、倫理的な基準を保ち続けるためには必要不可欠なのです。では「積極的安楽死」を認めている国や地域はどこなのでしょう。「積極的安楽死」と「医師による自殺ほう助」の両方が容認されている国は、オランダ、ルクセンブルク、ベルギー、カナダ、オーストラリアの一部、ニュージーランド、スペイン、コロンビアです。「医師による自殺ほう助」のみを認めている国はスイスのほか、オーストリア、アメリカのオレゴン、ワシントン、コロラド、カリフォルニアなどの各州。「そこまで多くの国や地域で安楽死が合法化されているなら、日本で認めても良いではないか」と思う人は多いでしょう。しかし、先行して安楽死が合法化した一部の国で起きている問題を、知ってもらいたいのです。障害由来の「生きづらさ」が安楽死の選択につながるオランダでは2012年から2021年にかけて積極的安楽死や医師による自殺ほう助の事例が約6万件ありました。そのうち約900件の症例報告がオンラインのデータベースに登録されており、必要があれば内容を確認できます。900件の症例報告のうち、LDもしくはASD、あるいはその両方が原因とされる事例が39件登録されていたのです。さらにその39件の事例のうち、8例が障害特性による「生きづらさ」、すなわち「世間や環境の急激な変化に順応できない」「友人を含む人間関係がうまく作れない」ことを苦にしたことで、安楽死や自殺ほう助を選択したことがわかりました。また、上記事例のうち3分の1のケースで、医師が安楽死もしくは自宅ほう助を希望する障害者に対し、これらの特性が治療不可能であることを明確にしたうえで、改善の見込みがなく、死ぬことが残された唯一の選択であると評価し、安楽死を許可しているというのです。「あれ?安楽死って、凄まじい苦痛があって、治る見込みがなくて、余命いくばくもない患者さんだけが受けられるものではないの?」と疑問に思った方もいるでしょう。実は安楽死や医師による自殺ほう助は、もはや「耐え難い苦痛があり、治る見込みもなく、余命の短い患者」だけの適用ではなくなりつつあります。安楽死を公的に実行している国の中には、「QOLの低下」が、安楽死を許可する基準にしているところがあるのです。また、精神、発達、知的障害者については教唆や誘導の影響を受けやすい特性を持つことが多く、周囲とのコミュニケーションに問題を抱えやすいことが、最近少しずつ知られてきました。そうした特性がある障害者の意思決定をどのように判断するか、または慎重に考慮するかといった検証や方法の議論が十分になされないまま、発達障害者の安楽死がすでに行われている現状があります。なお、オランダの場合は安楽死事案の審査はあくまでも事後的になされるものであり、その段階では安楽死を希望した障害者はすでに死亡しています。そのため、もし審査が適切になされていない場合、もう取り返しがつかないことは皆さんにもおわかりでしょう。オランダでの安楽死ではありませんが、ベルギーで行われた安楽死の審査に疑問が残るケースとして、精神障害と発達障害を持つティネ・ニースの安楽死があります。ティネが安楽死の申請をしたときは38歳でした。彼女はこれまでに何度も自殺未遂を繰り返しており、耐え難い精神的苦痛があるとして安楽死を要望しました。実は先進国の中で日本とフィンランドに次いで自殺者が多いベルギーは、精神障害者の最後の選択肢として安楽死を認めています。ベルギーだけでなく、近年ではオランダでも、認知症患者や精神、発達、知的障害者が精神的な苦痛のみを理由とした安楽死が増えているのです。ティネは家族に看取られながら亡くなったのですが、その後家族が「安楽死の承認プロセスに不信感を感じる」として、医師を相手取った訴訟を起こしています。家族が特に問題視していたのは、ティネの安楽死の面談を担当したのが、ある論文で「ベルギーの精神医療はもう収容の限界を迎えている。死を望む精神障害者は終末期だと考え、死なせてやるべきだ」と語っていた精神科医でした。この精神科医ギデリーヴ・ティエンポンは、ティネをASDと診断しながらも特にSSTやカウンセリングを提供することもなく、精神症状の治療さえしなかったのです。加えて、ベルギー国内の精神障害による苦痛を理由とした安楽死申請の約35%から50%を、ギデリーヴひとりが承認した可能性があることを家族は知り、訴訟を提起したのです。安楽死を願う障害者は、安楽死に関する審査を担当する医師が、善意から自分の苦しみに寄り添い、公平な審査を経て、安楽死を許可してくれるものと考えているでしょう。しかし、安楽死の審査を行う医師が、いわゆる「偏った思想を持つ医師」だとしたら、どうでしょう。そして教唆や誘導のされやすい特性を持つ障害者に、安楽死へ導く「誘導」をおこなう可能性も否定できません。安楽死の審査をおこなう現場に、危険な思想の持ち主など絶対に入り込ませない!という保障は、どの国もおそらくできないでしょう。だからこそ、安楽死を国が承認するのは非常に危険だと思うのです。「無益な治療論」がもたらす恐怖実は、安楽死を実施している諸外国の中に、無視できないある言論が生まれつつあります。その名も「無益な治療(futile treatment)」論。この「無益な治療」論、簡単に説明すると「完治が望めない患者を、効果が期待できない治療で生かして、無駄に苦しませるのはやめよう」という一見ありふれた議論。ところが、この「無益な治療」論は議論を重ねるごとに、どうもおかしな方向に話が進み始めました。あるときから「非常に重い障害のある人の延命治療について、医師サイドはたとえ求められても断固として一方的に拒否する必要がある」と、主張する人々があらわれはじめたのです。この「断固として一方的に拒否する」というのは、たとえ患者や患者の家族が強く望んでいたとしても、医師の判断により治療を控えたり完全に中止できるという、医療側に一方的な権限が起こりうるもの。一方的過ぎる医療側の権限について、到底許容できないと感じるのは、わたしだけでしょうか?なお、この「無益な治療」を肯定する法律はすでに存在しています。その中で特にラディカルなものは、テキサス事前指示法(通称「TADA」)。TADAではテキサスにある病院の倫理委員会が終末期や治療が不可逆など「無益な治療」と判断した患者に対し、病院は患者サイドにその旨を通知し、一定の猶予期間を与えて転院先などを探させるものです。しかし、もし転院先が見つからない場合は生命維持を含めて、一方的に治療を打ち切ることができてしまいます。このTADA,テキサス以外のアメリカの州やカナダにおいても、類似するプロトコルが拡がりつつあり、すでにこの法律に関連する係争事件が多発していることは、日本ではほとんど知られていません。こうした「無益な治療」論が起こる背景には、日本でもたびたび話題となる「社会保障コストの削減問題」があります。カナダでは安楽死が合法化された後すぐに、もし毎年1万人の国民が安楽死を選択した場合、試算ではありますが、1億3000万ドルの医療コスト削減が可能になるとの報道がありました。かつて「人工透析者は自業自得で高額な医療を受けているのだから、保険適応にするな」と暴言を吐いた議員がいましたので、そのうち日本でも「安楽死で社会保障コストを削減しよう」とのたまう政治家が、出てくるかも知れませんね。安楽死後臓器提供の恐怖ベルギーで安楽死を希望すると、安楽死の手続きに必要な書類の中に「臓器提供の意思表示」の紙面が必ず入っています。安楽死と臓器提供の両方をおこなうという意思表示をすると、臓器提供を円滑に行うために手術室のそばで安楽死をおこないます。心停止を待って臓器を摘出するという「安楽死後臓器提供」は、日本では知られていませんが、実はベルギーでは2005年から、オランダでは2012年からはじまっています。安楽死後臓器提供のドナーとなるのはALS(筋萎縮性側索硬化症)やMS(多発性硬化症)など疾患の患者が多いそうですが、そのドナーの中に精神障害者も含まれているというのです。ベルギーの移植医たちは「これは自己決定の範疇だ」といいます。それどころか「一人で何人もの命を救う、利他的な自己決定だから尊重しよう」「安楽死後臓器提供はよいことだからもっと啓発して、何れは臓器不足の解消につなげられないか」という医師までいるのです。2018年には米国の生命倫理学者ロバート・トゥルーグが、カナダの医師との共著論文で、安楽死後の臓器提供が出来るよう法改正を提案しています。彼らは論文で、このような主張までしています。「安楽死後の臓器提供ではドナーが亡くならないかぎり臓器摘出ができないという国際規範が存在しているが、そうなると臓器の劣化は避けられない」「しかし、臓器提供後の安楽死なら、生きた状態で臓器を取り出せる」「ドナーはもともと安楽死を望んでいる。臓器提供の意思があるのなら、安楽死の前に臓器摘出を行っても良いのでは」どうせ死ぬんだから、死ぬ前に臓器を取り出したほうが、フレッシュな臓器が得られるではないか……といわんばかりの論調で、これでは人間が「医療資源」とみなされているかのようですよね。そして何よりも恐ろしいのは、「自己決定が誘導や教唆によって左右されやすい」特性を持つ障害者が、こうした「どうせなら臓器をとってから死ぬほうが、もっと社会の役に立てるかも」という考えに影響され、餌食にされる可能性があることです。実際「これまで社会的軽視を経験してきた障害者に『障害者は臓器でも提供して、人様の役に立ってから死ね』という誘導につながるのでは」と懸念するアメリカの医師がいます。社会的強者にとって都合の良い「社会的弱者の自己決定権」わたしは以前「東京で問題視されている『立ちんぼ』の中には、軽度知的障害や発達障害者が多く含まれている。売春を罰するよりも福祉につなげる必要がある」と、ある掲示板に投稿したことがあります。すると「知的障害者の自己決定権を無視するのか、自由に仕事を選ぶこともできないのか」と、すぐに返信が来ました。知的障害者女性などの社会的弱者が、仕事が続かないことからやむを得ず売春することが、まだまだ世間には知られていないのだなと痛感しました。が、同時に「女体を安く買いたい男性からしたら、丸め込みやすい知的障害の女性に売春していて欲しいよね。都合の良い『障害者の自己決定権』ですこと」と、いじわるな返信をしてやろうかと思ったものです。社会的強者が社会的弱者の自己決定権を擁護するときは、それが「社会的強者にとって都合の良い『自己決定』だから」だとわたしは考えていますが、安楽死についても同じことがいえないでしょうか?「生きる権利があるのと同じように、死ぬ権利もある」と安楽死推進派は主張しますが、障害者については安楽死後の臓器提供のため、社会保障コストの節約のため、そうした「『強者にとって都合の良い』死を選ぶ権利」になってしまう可能性もあるのです。今回お話しした安楽死の事例ですが、いずれも安楽死の運用についてはかなりラディカル(急進的)な国のケースがほとんどです。しかしながら、もしも日本で安楽死が合法となった場合、絶対にラディカルな運用にならないという保障は有りません。さて、最後にもう一度確認します。あなたは、それでもまだ「安楽死の合法化」を望みますか?[障害者.com]日本ではまださほど論議にはならないけど、一歩踏み込むとやはり恐怖さえ感じるテーマですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.25
コメント(7)
-

【書評】『小児・成人・高齢者の発達障害における診断・鑑別・治療』児童精神科医から一般精神科医まで,すぐに役立つマニュアル。
【書評】『小児・成人・高齢者の発達障害における診断・鑑別・治療』児童精神科医から一般精神科医まで,すぐに役立つマニュアル精神科医療の現場では、発達障害患者の受診が増加の一途をたどっている。児童精神科医のみならず一般精神科医にとっても、発達障害患者の診療は今後ますます重要となるであろう。しかし、残念ながら一般精神科医には発達障害患者の診療を忌避する人が少なくない。その一因として,発達障害の教科書の大部分が,児童思春期の患者を対象としていることが挙げられる。一般精神科医が発達障害の成人患者の診療で困ったとき、すぐに役立つ教科書がほとんどないのである。本書は,評者の前の職場、熊本大学病院神経精神科において発達障害患者の診療に長年従事してきた、豊富な臨床経験を有する著者によって執筆された。現場感覚が反映された内容と、明快でわかりやすい記述、見やすいレイアウトが魅力的な好著である。特に第3〜5章では、児童思春期から高齢者まで、年代別に発達障害の特徴を解説している。ここが類書にはない,本書の最大の特徴である。また、発達障害患者の診察は長時間を要することが多く、一般精神科医を発達障害患者の診療から遠ざける一因となっている。しかし、著者は短時間での適切な診療を実現していた。なぜそのようなことが可能なのか評者は不思議に思っていたが、第2章を読むと著者の診療のコツの一端を理解することができた。本書は,児童思春期の患者をベースに記載してあるが、成人患者にも十分に応用可能な内容であり、一般精神科医にとっても、臨床現場で困ったときにすぐ役立つマニュアルとなるであろう。評者にとって非常に勉強になったのは、第6章「WISCの読み取り方」である。精神科医にとってこれほどわかりやすく、明快で,臨床現場ですぐに役立つ知能検査の解説はほかにはないと思われる。本書は著者の熱意が凝縮され、現場感覚が存分に反映された一冊である。ノウハウ型専門書として、精神科医のみならず発達障害に関係するすべての職種の方々にとって、臨床現場ですぐに役立つ内容となっている。【日本医事新報社】小児・成人・高齢者の発達障害における診断・鑑別・治療 [ 佐々木博之 ]1冊あると、何かと参考になる文献ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.24
コメント(9)
-

手帳未所持の精神、発達障害者は雇用率対象外 現行の仕組み維持の方針〈厚労省〉。
手帳未所持の精神、発達障害者は雇用率対象外 現行の仕組み維持の方針〈厚労省〉 厚生労働省は、障害者手帳を所持していない精神、発達障害者について、引き続き雇用率制度の対象外とする方針を固めた。精神障害者保健福祉手帳(有効期間2年)を更新できなかった場合は、現企業に今後も雇用される見込みであれば一定期間、従来通り雇用率に算定できるようにする。10月29日に開いた今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(座長=山川隆一明治大教授)で、委員から大筋で合意を得た。 障害者雇用促進法における障害者は、身体、知的、精神障害者に加え、そのほかの心身機能障害により職業生活が困難な人も含まれている。一方、事業者に求められる雇用義務の対象は原則、手帳所持者に限っているため、手帳を所持していない障害者の扱いについて整理するよう求められていた。 精神障害者保健福祉手帳は国際疾病分類における、すべての精神・行動障害(発達障害を含む)と、てんかんを対象とし、生活に制限があると認められると交付される。そのため厚労省は、手帳を所持していない人を別の基準を設けて雇用率の対象とする必要性は低いと判断した。 また、高齢・障害・求職者雇用支援機構が精神、発達障害者を支援したことのある就労支援機関を対象にした調査(2024~25年度)で、手帳を所持しない理由は必要性を感じないことが最多で、障害者雇用の拡大などを受けて、所持することに対する抵抗感が減少していることも判断理由に挙げた。福祉新聞【YAHOOニュース】手帳所持の有無でかなりその後の人生に影響しそうですね。幼少期から学童期のお子さんの保護者は責任大ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.23
コメント(11)
-

障害者の就労支援偽り1億円以上詐取疑い 。
障害者の就労支援偽り1億円以上詐取疑い北海道警は8日、障害者に就労支援サービスを提供したなどと偽って道内の3市から給付費計1億円以上をだまし取ったとして、詐欺の疑いで障害福祉サービス会社代表取締役の男ら3人を逮捕した。KYODO【YAHOOニュース】だまし取られる市側も、もう少しきちんと精査して頂きたいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.22
コメント(12)
-

【速報】障害者施設の入所者を殺害しようと包丁所持 容疑で逮捕の介護職員を不起訴に。
【速報】障害者施設の入所者を殺害しようと包丁所持 容疑で逮捕の介護職員を不起訴に大津地検彦根支部は10日、勤務先の障害者福祉施設(滋賀県東近江市)で入所者(44)を殺害しようと包丁を隠し持っていたとして、殺人予備と銃刀法違反の疑いで逮捕された滋賀県彦根市の介護職員男性(70)を不起訴処分とした。処分の理由は明らかにしていない。[京都新聞DIGITAL]処分の理由が分からないとあれこれと憶測が働きますね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.21
コメント(9)
-

「自閉症の兄がいたから、今の私がいる」。 ヘラルボニーの中塚美佑、 "きょうだい児"として歩んできた道を明かす。
「自閉症の兄がいたから、今の私がいる」。ヘラルボニーの中塚美佑、"きょうだい児"として歩んできた道を明かす自閉症のある兄とともに過ごした子ども時代から、傷つきながらも育まれた優しさと観察力——それらすべてが、いまの中塚美佑をかたちづくっている。ヘラルボニーのビジュアルディレクターとして働く彼女が、初めて語る“きょうだい児”としての日常と、自分自身の成り立ちの話。中塚美佑:1997年、神奈川県横浜市生まれ。大学で福祉を学んだ後、アパレルブランドでの販売・SNS運用を経て、2020年ヘラルボニーに入社。現在は同ブランドでビジュアルディレクターを務める。兄と過ごした幼少期──中塚さんのお兄さんは、どんな方ですか?とても真面目で穏やか。3歳のころに重度の自閉症と診断され、幼い頃は療育センターに通っていました。その後は小学校・中学校・高校と進み、中度の診断を経て、現在は広汎性発達障害と診断されています。いまはかんしゃくもなく、私よりも社会に適応しているような感じがします。何にでも好奇心があって、電車で一人で遠出もします。昔は偏食で白いご飯と牛乳しか口にしなかったのに、母の努力の末、今では好き嫌いゼロで、家事もほぼできてしまう。見た目もかわいらしくて、人に嫌われるようなことはしない人。診断された精神年齢は小学6年生なので弟のようですが、私にとっては尊敬する存在です。──お兄さんとの日常の中で、心に残っている幼少期の思い出はありますか?兄はひとつ年上で、保育園も小学校も一緒。"リョウリョウの妹"という肩書きで過ごしていました。ただ中学で初めて離れて、兄は隣の区にある個別学級に進みました。私は兄を隠したいとは一度も思ったことがなくて。たまに兄が交流級というかたちで私の学校に来ると、友達や先輩に紹介していました。兄は私の感情にすごく敏感で、私がイライラすると兄もイライラしはじめるし、私がうれしいと、兄もうれしそうにニコニコして「美佑ちゃん!」と指を差してきたりするんです。きょうだい児として紡ぐ未来──サポートと共生のバランスについて、どう感じていますか?兄のように言語での表現が難しい人に対しては、本人が何を伝えようとしているのか、表面的な言動の奥にある気持ちを知ろうとする努力を、周囲がどれだけ意識できるか。それができると、かなり状況は変わってくると思います。私自身、兄と接する中で「理解しようとしてもできないこと」がたくさんありますが、"きっとこうだと思う"と丁寧に言葉にすることで、人を知る幅も広がります。それを楽しむというのが大事なんだろうなと。──それは、優しい社会をつくる鍵でもありますね。興味を持って、思考を巡らせること、それに尽きると思います。目の前の人や状況に対して、すぐに判断せず、どうしてこの言動が出たのかを考えてみる。それは兄との関係にも通じるし、日々の暮らしや仕事でも活きています。その感覚を誰かと共有できたとき、「優しい社会」に一歩近づける気がしています。──これからしていきたいことはありますか。私がまだ学生のときに、弊社の代表が「きょうだい」についてハッピーに語り合う飲み会を企画してくれて、2回目の開催時にインスタでつながった一歳下の女性を誘って参加しました。彼女は後日、「この日をきっかけに重度の自閉症の兄のことを、初めてパートナーに打ち明けた」と話してくれて……それを聞いた瞬間、胸がいっぱいになって、涙が出てきたんです。そうした“語りの場”に「カタルボニー」という名前をつけてくださった方がいて。カジュアルな語りを通して、きょうだいや家族の見えづらい葛藤に光があたるような、そんな場を育てていきたいと思っています。BAZAAR[YAHOOニュース]過去があるから今がある。無駄な経験などないのでしょうね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.20
コメント(9)
-

大阪万博が教えてくれた大切なこと 〜発達障害のASDとADHDを併発しています!<vol.30>
大阪万博が教えてくれた大切なこと〜発達障害のASDとADHDを併発しています!<vol.30>私はパニック障害があるので人混みが苦手ですが、今回の万博会場には4回行けました。今までの体調などを考えると、とてもいろんなことを乗り越えられて嬉しいです。万博は、私にとって夢のような時間だったので、終わってしまって今はロスにもなっています。本当に楽しかったのです。もちろん、まだまだできなかったこともたくさんありますが、今回の万博ではどんなことに挑戦できたのか振り返っていこうと思います。まず、人混みを避けるため普段は大きな会場でのコンサートやイベントには参加できないし、はじめから行けないと諦めていました。悔しいですが、パニック障害になってからは体調を崩してまで行くもんじゃないと思っていたし、はじめのうちは今回の大阪万博も行くつもりはありませんでした。でも、障害者手帳で優待があると知り、行ってみたらすんなり入場することができました。これだけでもとても感謝しています。それから、私が特に苦手な地下鉄に何十年かぶりに乗ることができました。4回行ったうちの最後に行った日の万博入場チケットが東ゲートでタクシーが使えず、どうしても地下鉄で行かなければいけなくて怖かったのですが挑戦してみたい気持ちもあり、今しかないとも思いました。もうすでに入場者数は大幅に増えていてものすごい満員電車なのを知っていたため緊張しましたが、アナウンスやテーマソングが流れるなどワクワクする仕掛けがあり、とても楽しかったのです。今までの息苦しくて怖い地下鉄のイメージとは全く違いました。電車に乗る時は音楽を聴くなど工夫していたので、コブクロのテーマソングが流れたり、「次はいよいよ夢洲です。驚きと感動に満ちた夢洲へさあ行きましょう!」のアナウンスが本当に非日常だったので驚きました。こんな楽しい仕掛けなら、苦手な地下鉄でもワクワクできるのだなと発見でした。あと、人混みは苦手なのですが、開催前の万博やミャクミャクへの批判をみていて悲しかったので、人気が爆発してたくさんの人が万博を訪れることがとても嬉しかったのでした。たくさんの飲食店にも入ることができて楽しかったです。せめて飲食店は並んで入店を待ちました。海外の食事は珍しくて楽しくて美味しかったです。大屋根リングも高所恐怖症のため、はじめのうちは登ってもすぐに降りたり、なかなか距離も歩けませんでしたが、階段があることを教えていただいたり、だんだん滞在時間が長くなりました。ですが、噴水ショーを観るために海の上まで歩いていきましたが恐怖が勝ち、残念ながら降りてしまいました。花火の時も大屋根リングにはたくさんの人が登っていたので怖くて下から観ていました。本当は一周ぐるっと歩いたり、上から花火やショーが観たかったのですが、流石に怖くてできなかったのが心残りでした。それでも美しい大屋根リングや間近で観る花火や噴水ショーやドローンショーはものすごい迫力で綺麗で感動しました。スタンプラリーやお土産屋さんなども楽しめました。大屋根リングやミャクミャクが大好きになりました。ミャクミャクグッズも可愛くてお土産などもたくさん買いました。いろんなパビリオンのいろんな国から楽しそうな歌や演奏や音楽が聴こえてきて、お祭り騒ぎが楽しくてあっという間に時間が過ぎていきました。ライトアップも綺麗で、スタッフさんも皆さん元気で温かくて優しくて、たくさん周りたくて万博に行くといつも一万歩以上歩いていました。こんなに楽しい場所があったのか、つらいことや日々のストレスはたくさんあるけど生きててよかったと思いました。万博を体験する前と後では明らかに良い変化を感じます。お友達の描いた絵が使われているプロジェクションマッピングを観た時も本当に嬉しかったし、素敵な絵と想いに感動しました。感想を報告したところ、今度はお家に招待していただいたので楽しみです。大好きな万博会場の近くにいたくて、閉幕前の数日間はチケットがない日も何度も舞洲まで花火や会場を見に行きました。パニック障害でも満員の万博を楽しむことができて、一生の想い出になりました。いろんなご縁に感謝しています。本当はもっとたくさん行きたかったです。パビリオンの中も観て周りたかったです。ですが、出来る限りの体験の中で得たものをこれからの人生に前向きに活かしていきたいと思います。いのちかがやかすぞ。https://www.youtube.com/@yuichi_naomi_hattatsu[shougaisha.com]思い切って外に出て見ると、新たな発見があるものですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.19
コメント(9)
-

「専門学校を強制的に退学させられた」 30歳女性の主張 「事前に自分が発達障害を持っていることを申告したのに…」。
「専門学校を強制的に退学させられた」30歳女性の主張「事前に自分が発達障害を持っていることを申告したのに…」・・・この状況でも復学を希望するワケ――沼田さんは復学を希望しておられますが、普通に考えて、学校側から受け入れられていない状態で戻るのは居心地が悪くないですか。沼田:学校側はおそらく、そうした言説を吹聴して私を学校から排除しようとしているのだと私は考えています。時間が経てば進級や復学を諦めると見込んでいるのではないでしょうか。ただ、私にとっては無償で栄養士の勉強をできるチャンスであり、それが合理的配慮なく奪われたことは理不尽だと思っているので、抗議していこうと考えています。また、友だちが在籍している間に実習をクリアできたほうが良いとも思います。――いま、専門学校側に対して思うことはありますか。沼田:私を退学処分にしたあと、学校が運営するブログに大量調理の実習の風景を掲載していました。そのなかに、加害学生が全員写っています。また、オープンキャンパスでは、主犯となった加害学生のレシピを採用しました。これらは、私へのあてつけではないかと思います。 私は事前に自分が発達障害を持っていることを申告していました。おそらく学生はそうした事情を知らなかったと思いますが、もしも学校側が他の学生と一緒に学ぶことが難しいと判断したのであれば、退学ではなく、オンライン授業を実施するなどの代替手段もあったはずです。それらがなく排除されたことにやりきれなさを感じます。===== インタビューの途中、何度も沼田さんは悔しさをにじませた。一般に理解づらい苦しみを抱えて、なりたい自分になるためにこれからも奮闘する。SPA![YAHOOニュース]思いがあればとことん、ですね。視野を広げれば、他にも見えて来るもの、ありそうですね。621万アクセス達成しております。いつもご訪問にコメント感謝です。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.18
コメント(9)
-

松山ケンイチが発達障害抱える裁判官に NHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』放送決定。
松山ケンイチが発達障害抱える裁判官に NHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』放送決定松山ケンイチが主演を務めるNHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』が、2026年1月6日よりNHK総合で放送されることが決定した。原作は、新聞記者・直島翔による同名リーガルミステリー。裁判官、検事、弁護士、そして裁判所職員らが“真実”を追い求め、時にかみ合わない会話を交えながらぶつかり合う姿を描く。発達障害を抱える裁判官が、自らの特性と格闘しながら難解な事件に挑んでいく。 脚本を手がけるのは、『イチケイのカラス』(フジテレビ系)シリーズや『絶対零度』(フジテレビ系)シリーズなどmの浜田秀哉。チーフ演出はNHKドラマ『宙わたる教室』の吉川久岳が務める。制作統括には橋立聖史(ランプ)、神林伸太郎(NHKエンタープライズ)、渡辺悟(NHK)が名を連ねた。 松山が演じるのは、前橋地方裁判所第一支部に異動してきた特例判事補・安堂清春。幼少期にASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)の診断を受け、自らの特性と向き合いながら生きてきた人物だ。「法律だけは個人の特性に関わらず変わらないルールだから」と裁判官を志す安堂が、特性ゆえに社会とのズレに葛藤しながらも、真実を見つめていく。 松山は「普段何気ないことからも繊細に多くの情報を捉える一方で、コミュニケーションが難しい。そんな人間が周囲にどんな影響を与えていくのかを、温かく優しい目線で描いている作品」とコメント。さらに「安堂の感性と向き合いながら、人間について新たな発見や気付きがある作品にできれば」と意気込みを見せた。 原作者の直島は、「安堂は理解されがたい特性を多く持ち、それでも社会にまざって懸命に生きようとする人物」と説明し、「涙に濡れる異能の裁判官を松山さんが演じると聞いて、とても安心しました」と期待を寄せた。・・脚本の浜田秀哉さん、演出の吉川久岳さんをはじめとする制作陣が、この物語にどんな新しい命を吹き込んでくれるのか、今から楽しみでなりません。リアルサウンド編集部【YAHOOニュース】裁判官役の松山ケンイチ、楽しみですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.17
コメント(7)
-

町田粥「発達障害なわたしたち」新刊発売記念トークイベント、大童澄瞳も登壇。
町田粥「発達障害なわたしたち」新刊発売記念トークイベント、大童澄瞳も登壇町田粥「発達障害なわたしたち」2巻の発売を記念し、12月21日にオンライントークイベントを開催。イベントには町田のほか、担当編集者の神成明音氏、マンガ家の大童澄瞳、オモコロライターのダ・ヴィンチ・恐山が登壇する。「発達障害なわたしたち」は軽度のADHD(注意欠如・多動性障害)と診断されているマンガ家と担当編集者が、大人の発達障害当事者たちにインタビューをし、理解を深めていくエッセイマンガ。約2年ぶりの新刊として11月8日に発売される2巻には、大童と恐山のゲスト回が収録される。トークイベントのチケットは、MARUZEN JUNKUDO Online Serviceで本日11月2日より販売。開催に先立ち、登壇者たちへの質問を別途特設フォームで受付中だ。なおチケットは2026年1月25日まで購入可能で、イベント翌日の15時からアーカイブ配信が視聴できる。「『発達障害なわたしたち②』刊行記念 町田粥×ダ・ヴィンチ・恐山(品田遊)×大童澄瞳トークイベント」日時:2025年12月21日(日)14:00~15:30開催形式:オンライン(Zoom ウェビナー)【コミックナタリー】【送料無料】〔予約〕発達障害なわたしたち 2何よりご本人たちからの発信、有意義な時間になりそうですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.16
コメント(8)
-

阪神 ドラ3岡城が「岡城プログラム」構想 知的障害のある子供たちを招待。
阪神 ドラ3岡城が「岡城プログラム」構想 知的障害のある子供たちを招待阪神にドラフト3位指名された岡城快生外野手(22)=筑波大=が29日、同大学キャンパス内で畑山統括スカウトらから指名あいさつを受けた。 岡城はプロで活躍し、将来的に知的障害のある子供たちを試合に招待したい考えを示した。 卒業論文のテーマは「知的障害のある子どもたちが野球をするための環境と道具の工夫についての研究」だといい、昨夏に青島特別支援学校が西東京大会予選に単独出場したことに感銘を受け、福祉に興味を持ったという。「岡城プログラムっていうのができれば面白いかなと思います」と思いを明かした。デイリー【YAHOOニュース】幸先楽しみな選手ですね。野球界にも多様性の時代ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.15
コメント(6)
-

障害者就労支援の加算金、 再雇用を繰り返し20億円超を過大受給か …大阪市の事業所グループ内で。
障害者就労支援の加算金、再雇用を繰り返し20億円超を過大受給か…大阪市の事業所グループ内で大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス」(絆HD)の子会社などが運営する三つの「就労継続支援A型事業所」が、障害者就労支援の加算金を2024年度以降に20億円以上、過大に受け取った疑いがあるとして、市が障害者総合支援法に基づく監査に入った。複数の関係者への取材でわかった。絆HDは「法令を 遵守じゅんしゅ している」としているが、市は不適切な受給とみて返還請求を検討している。関係者によると、3事業所は絆HDの役員が理事を務めるNPO法人が運営する「リアン内本町」と子会社が運営する「レーヴ」、「リベラーラ」(いずれも大阪市)。A型事業所は、利用者と雇用契約を結んで軽作業などに従事してもらい、利用者数に応じた給付金を受け取る。企業へ就職する「一般就労」も支援しており、一般就労が半年以上続いた場合に「就労移行支援体制加算」と呼ばれる加算金が出る。加算金を含む給付金は基礎自治体がいったん負担した後、国と都道府県が4分の3を支払う。加算金は前年度に半年以上一般就労した人数の実績と、当年度の事業所の利用実績のかけ算で算出されるため、一般就労した人数が増えると金額は跳ね上がる仕組みになっている。 3事業所では自らの事業所を一般就労先とし、半年間スタッフとして雇った後、再び利用者としての雇用に戻すことを繰り返し、利用者1人につき複数回の加算金を受け取っていた。それぞれ21~23年頃からこうした手法で加算金を請求しており、給付が膨大なことから、市は制度を所管する厚生労働省に報告していた。 厚労省は24年4月、3年間は同じ利用者について加算を複数回申請できないようルールを改正した。 これに対し、3事業所は「3年」のルールは改正前の加算歴には遡って適用されないなどとして、24年度以降も同様の請求を継続。24、25年度に過大に受け取った加算金は20億円以上となる疑いがある。 厚労省の担当者は取材に「利用者が事業所で一般就労に移行するのは問題ないが、加算目当てに複数回、一般就労するのは制度の趣旨とは異なる」と説明。ルールは改正以前の加算歴にも適用されるとの見解を示す。 絆HDは読売新聞の取材に「法令を遵守の上、障害のある方々の自立支援・就労支援に 真摯しんし に取り組んでいる。現在、関係行政機関からの指導を踏まえて確認や調整を行っている事項があるため、個別の事案等について詳細に答えることは控える。今後伝えられる状況となった際には、改めて適切に説明する」とのコメントを出した。◆ 就労継続支援A型事業所 =障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つ。利用者は検品や 梱包こんぽう といった軽作業やウェブ制作などに従事しながら就労支援を受ける。厚生労働省によると、今年6月時点で全国に4363か所あり、利用者は延べ8万6611人。[読売新聞]余りにも法外な過大受給、もう少し早く気が付かない市も杜撰ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.14
コメント(8)
-

大阪府 障害者支援「就労継続支援B型事業所」約2050施設対象に調査 適切な訓練提供していない疑いある複数の事例 不適切な場合は指導。
大阪府 障害者支援「就労継続支援B型事業所」約2050施設対象に調査 適切な訓練提供していない疑いある複数の事例 不適切な場合は指導就労支援を在宅で利用する障害者に対して、事業者が適切な訓練を提供していない事例などが報告されているとして、大阪府が調査を進めていることが分かりました。大阪府の調査はものづくりなどを通して障害者の就労支援を行う府内の「就労継続支援B型事業所」およそ2050施設を対象に行われています。「B型事業所」は、行政が給付する資金で運営していますが、府によると在宅で就労支援を受ける障害者に対し、適切な訓練を提供していない疑いがある事業者が複数報告されているということです。中には「自宅で1日数回程度植物に水やりをする」といった事例もあり、府は支援内容などについて確認し、不適切な場合は指導を行う方針です。【カンテレNEWS】日常茶飯事に行われている事態、改善するも難儀でしょうね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.13
コメント(7)
-

相模原障害者施設19人殺害 死刑囚の再審認めず 最高裁。
相模原障害者施設19人殺害 死刑囚の再審認めず 最高裁神奈川県相模原市の障害者施設で入所者19人を殺害した罪などで死刑が確定した植松聖死刑囚(35)について、最高裁は裁判のやり直しを認めない決定をしました。 植松聖死刑囚は2016年7月、相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者19人を殺害し、26人にけがをさせた罪などに問われ、1審の横浜地裁は2020年3月に死刑判決を言い渡しました。弁護人が控訴しましたが、植松死刑囚自らが控訴を取り下げ死刑が確定していました。 その後、植松死刑囚は再審請求をしましたが、横浜地裁、東京高裁ともに再審を認めない決定をしていました。植松死刑囚側は不服として特別抗告していましたが、最高裁は今月27日付で退ける決定をしました。 これで再審を認めない判断が確定しました。【テレ朝ニュース】何を不服としているのか、こればかりは当然だと思いますね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.12
コメント(8)
-

旗の台に「障害者就労体験事業」施設 カフェや憩いの場を運営、製品販売も。
旗の台に「障害者就労体験事業」施設 カフェや憩いの場を運営、製品販売も。「品川区障害者就労体験事業」施設(品川区旗の台5、TEL 03-6433-2579)が9月25日、旗の台駅南口近くにオープンした。運営は社会福祉法人げんき(東大井5)。 リサイクルショップ「リボン 旗の台店」跡を改装して活用する同施設。店舗面積は167坪。 就労意欲のある障害者に、カフェでの接客や事務補助、清掃業務などの就労体験の場を提供する。障害、持病、引きこもりなどで長時間労働が難しい人が週20時間未満で働く「超短時間雇用」を支援する。外出が困難な人のため、遠隔操作で接客ができるロボット「OriHime」を区内の就労体験事業所では初めて導入した。 事業を始めた経緯について、品川区障害者支援課課長の松山香里さんは「近年、品川区の障害者就労支援センターの登録者が増加しており、障害がある方の就労意欲が高まっている。一方で、民間企業への就職後に雇用が定着しないケースも多い。就労体験の機会や社会との関わりをつくり、自身の適正を把握できる場を創出したい」と話す。 施設内には、カフェコーナー、ソファ、キッズスペースなどを用意し、区民の憩いの場として誰もが利用できる。 超短時間雇用の体験は、品川区在住で長時間働くことが難しい人が対象。見学や面談を経て実習に移る。就労体験は在住区や年齢に関わらず誰もが可能。予約不要で、事務作業や「OriHime」操作を体験できる。 カフェコーナーでは、カプセル式コーヒーメーカーの「リッチブレンド」や「カフェオレ」(以上130円)、「ミルクティ」(150円)などを販売。このほか、区内の就労継続支援A・B型事業所で作る焼き菓子や雑貨なども用意する。同区障害者支援課の長尾祟弘さんは「区内にある12事業所の製品を置いている。『しながわみやげ』や品川区と連携協定を結ぶ自治体の特産品も販売しているので、そちらも楽しんでもらえたら」と話す。 同事業では、企業などの発注元と就労継続支援A・B型事業所の受注元をつなぐ、共同受注窓口の役割も担う。1事業所では対応が難しい大口案件を受注し、複数の事業所に分散して発注するよう調整する。このほか、不要となった区内学校標準服などを回収し、必要な人に無償で譲渡するリユース事業も行う。 今後の展望について秋山さんは「区民が集えるスペースでは体操プログラムなどを行っていく予定。多くの人に利用してもらい、共生社会を具現化できる場にできたら」と話す。 営業時間は、火曜~金曜=11時~18時、土曜=10時~17時。月曜・日曜・祝日定休。品川経済新聞【YAHOOニュース】多様型の就労体験施設、区民ではないけどチャンスがあれば寄ってみたいです。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.11
コメント(11)
-

[社会福祉] 障害福祉現場の賃上げ率3.81% 関係8団体調査。
[社会福祉] 障害福祉現場の賃上げ率3.81% 関係8団体調査 日本知的障害者福祉協会など8団体は21日、加盟する1,547事業所の2025年度の賃上げ率は3.81%で、前年度を0.12ポイント下回ったとする調査結果を発表した(参照)。障害福祉の現場では、賃上げ努力により着実に職員の処遇改善を実施しているものの、全産業との賃金格差は拡大しているとして、8団体は処遇改善の抜本的な拡充を国に求めている(参照)。 調査は、物価高などで経営環境が厳しさを増している障...こちらは有料記事です【MCplus】賃上げ率の低下は、社会全体の歪みですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.10
コメント(8)
-

江原啓之「発達障害の息子」を持つ母に“愛の喝”! 「問題は親。過干渉、過保護」「親がレッテルを貼って」。
江原啓之「発達障害の息子」を持つ母に“愛の喝”!「問題は親。過干渉、過保護」「親がレッテルを貼って」スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。10月19日(日)の放送では、発達障害を持つ中学3年生の息子の進路と、その言動に悩む母親からの相談に、江原がアドバイスを送りました。<リスナーからの相談>中学3年生の息子は、高校受験を控えています。息子には発達障害があり、集中力が乏しく、きっと私が思っているよりも頭の中が疲れるのだと思いますが、「みんなと同じように高校に行きたい」と言うので塾に入り、なんとか夏期講習も行きました。いよいよ本格的に私立の個別相談など始まるこの時期に、私はとても不安です。たとえ、まぐれで高校に進学しても勉強でついて行けず、途中退学にでもなったら、本人が一番傷つくのではと不安になり、いっそのこと最初から通信の高校で、ある程度ゆっくりのペースで勉強ができる環境が良いのではと悩んでいます。ただ本人は、通信の高校に良いイメージをもっていません。そして息子は自己肯定感が低く、機嫌が悪いと「どうせ俺は頑張れない。生きていても意味がない、死ぬからロープ買ってきて」と時々口にします。発達障害のことを伝えたうえで進路を考えさせたら良いのか、どうしたら良いでしょうか。<江原からの回答>問題なのは、親(あなた)だと思う。過干渉、過保護。だから、その親が発達障害ということに物すごいレッテルを貼って。そんなの良いじゃない、どんな子でもみんな個性はあるんだし。本人が行きたいと言っているんだから、行かせればいいじゃない。何で、転ばぬ先の杖を、そこまで用意しなきゃいけないのかね。やはり、親子は葛藤しながらも、もし学校(の勉強)についていけなかったら「しょうがないよ!」って(言ってあげる)。それはそれでね、学びになりますもんね。子どもには、期待やら心配とか、いろいろしますよ。かわいい子どものことだからね。でもね、なるようにしかならないから。もうどうしようもない。何かあったとしても、それがお子さんの学びになる。子どもは、どんな子でもみんな良い子なんですよ。みんな健康で生きていてくれれば、それで良いのよ。たとえ、病気があったとしても、その病気と向き合って、それをサポートしてあげて、頑張って生きていければ良いんだから。今日1日を充実して過ごして。99の苦労に1のご褒美なの。その1のご褒美のために生きているようなものだからね。そうやって心配できることも勉強で、必要な学びとして与えられていることだから。相談者さんの気持ちは分かるけれど、息子さんとやり合ってください(笑)!この息子さんの心配がなかったら、きっと生きる張りもありませんよ。毎日をハラハラしていることが、後々、「あれが幸せだったんだな」って思いますよ、きっと。思い合って、愛と向き合って、何が正しいのか?とお互いに“育む”こと、それが教えを育むことなの。子どもは子どもで、「親に酷いこと言っちゃったな」とか思って、そういう思いを免罪符にする。そして、後々いろいろ気づいて「お母さん、ありがとう」なんて言ったりしてね。それで報われますもんね。お母さんはお母さんで、子どもに対してワーッて言ったとしても、「今日はあなたが好きな春巻きを作ってあげました」とか言ってね。それがね、“育む”ことなの。だから、どーんと「お前の好きなように生きてごらん」「できるだけサポートはしてやるから!」と言って。それで良いじゃない。●江原啓之 今夜の格言「教育とは、“教えを育む”ことなのです」----------------------------------------------------この日の放送をradikoタイムフリーで聴く※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時:TOKYO FM/FM 大阪 毎週日曜 22:00〜22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30〜12:55出演者:江原啓之、奥迫協子番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/oto/[dmenuニュース]江原さん、まだまだお元気ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.09
コメント(11)
-

就労継続A型利用者急増の自治体も 障害者部会が地域差是正を議論。
就労継続A型利用者急増の自治体も 障害者部会が地域差是正を議論生労働省は1日に開いた「社会保障審議会障害者部会」(座長=菊池馨実早稲田大理事)に、障害福祉サービスの地域差を見るため、市町村別の利用実態のデータを示した。就労継続支援A型では2024年度平均利用者数が前年度比で28倍に増えた市町村があれば、利用者がゼロになった市町村もあった。A型以外の5サービスでは、児童発達支援21倍▽放課後等デイサービス12倍▽グループホーム3・38倍▽就労継続支援B型2・47倍▽生活保護1・5倍に利用者が増えた市町村があった。一方、B型を除く4サービスで利用者がゼロになった市町村があった。部会は第8期(27~29年度)障害福祉計画の基本指針を年内に作成するため議論を進めている。同日は地域差の是正やサービス見込み量の在り方が議題となり、六つのサービスについて地域差に関するデータが提示された。市町村別の人口に占める利用者数割合では、6サービスとも全国平均と大きく乖離かいりしている市町村があった。また、24年度の単年度だけでは一時的な要因の影響を受けている可能性もあるため、21年度と23年度の利用者数を比較したデータも示された。障害福祉サービスは全国どこでも必要なときに受けられることが基本となっている。データにより利用実態に地域差があることは確認できたが、委員からデータだけでは地域差の原因が読み取れない、人材確保などサービスを提供する側の実態を踏まえないと判断できない、といった趣旨の発言があった。部会では次回以降、統計などに知見のある専門家に意見を聞き、議論を深めることにしている。【福祉新聞】利用者の必要なところに妥当な支援が整うといいのでしょうね。620万アクセス達成しております。いつもご訪問にコメント感謝です。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.08
コメント(6)
-

鎮痛剤の自閉症警告表示要請、米ケンビューがFDAに却下求める。
鎮痛剤の自閉症警告表示要請、米ケンビューがFDAに却下求める[20日 ロイター] - 米コンシューマーヘルス会社ケンビューは米食品医薬品局(FDA)に対し、同社の市販鎮痛剤「タイレノール」の妊娠中の利用に関して、自閉症との関連についての警告表示の要請を却下するよう求めた。市民団体は先月、FDAに対し、タイレノールやアセトアミノフェンを含むその他の製品について、自閉症と注意欠陥多動性障害(ADHD)などの症状との関連性に関する警告表示を義務付けるよう求めた。ケンビューは10月17日に提出した書類で、この請願書は「科学的証拠による裏付けがなく、法的にも手続き的にも不適切」と反論した。トランプ大統領は9月、医学界の助言に反して、女性にタイレノールと自閉症との関連で警告を発した。医学界は、タイレノールの有効成分、アセトアミノフェンは妊婦の健康に安全な役割を果たすことを示す数多くの研究データを引用している。 FDAは先月、このリスクについてタイレノールと類似製品の表示ラベルに警告文を追加する方針を示した。 しかし、FDAのマカリー長官は医師らに宛てた書簡で「アセトアミノフェンと自閉症との関連は多くの研究で報告されているが、因果関係は確立されておらず、科学文献には反対の結論を示す研究もある」と指摘した。ケンビューは「10年以上にわたり、そしてつい最近の8月にも、FDAは新たな科学的証拠を徹底的に評価し、妊娠中のアセトアミノフェンの使用と自閉症などの神経発達障害との因果関係を示すデータはないと繰り返し結論づけてきた」と強調した。アセトアミノフェンは妊婦にとって安全とされる唯一の鎮痛剤。医師は既に妊婦に妊娠中の痛みや発熱を抑えるために、できるだけ短期間、最小限の使用量で服用するよう呼びかけている。REUTERS[YAHOOニュース]一時の騒動もこれで一悶着ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.07
コメント(8)
-

自閉症で重度の知的障害のある奈良市の井…。
自閉症で重度の知的障害のある奈良市の井…自閉症で重度の知的障害のある奈良市の井上和晃さん(27)が、顔を水面から上げたまま足の力だけで泳ぐヘッドアップキックでギネス世界記録を樹立した。きつい姿勢のまま1時間で1750メートルを泳いだ泳力、精神力は素晴らしかった。 記録挑戦の場だった「三重交通G スポーツの杜 鈴鹿」(三重県鈴鹿市)の屋内水泳場の施設充実度にも驚いた。井上さんが泳いだ国際公認50メートルプールのほか25メートルのサブプール、飛び込み台・プールを備えていた。 競泳のほか数々の水の公式競技に対応できる内容。約2千の観客席、大型モニターも迫力がある。 施設関係者に聞けば、アーティスティックスイミングのクラブも活動。元五輪メダリストが指導しているという。 施設の満足度に近隣府県からも選手らが訪れるらしく、井上さんもその一人。器が優れたアスリートや指導者を呼び寄せ、良質なスポーツ文化が発展している好例だろう。 同施設の開場は約30年前。県でも新アリーナや国スポに向けた施設整備を協議中だ。予算は無視できぬが、将来を展望した他所の事例に学ぶものはある。[奈良新聞DIGITAL]ギネス世界記録を樹立、何より本人が喜びとして自覚できればほんとうに素晴らしいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.06
コメント(8)
-

特別支援学校の教室、全然足りない! 発達障害への理解進み希望する児童生徒が急増。
特別支援学校の教室、全然足りない! 発達障害への理解進み希望する児童生徒が急増特別支援学校に通う子どもの数が増え、教室が不足する問題が全国で起こっている。特別支援教育への理解が進み、入学を希望する保護者が増えたことなどが背景にあるが、急激な増加に行政の対応が追い付いていない。作業訓練の部屋などを教室に転用するなどしてしのいでいるケースがあり、子どもの学ぶ場として最適な環境の整備が喫緊の課題となっている。 岐阜県で最多の児童生徒が通う大垣市の大垣特別支援学校。本年度は小学部から高等部まで340人が在籍しており、2020年度比で約45%増えた。昨年度比でも8%の増加だ。 足りない教室を補うため、現在は利用されていない旧寄宿舎を活用。広い特別教室を仕切って複数の学級で使うなどしている。児童生徒の増加に伴って教員が増えた分、職員室のスペースも足りなくなり、県は来年度から普通科の大垣西高校(同市)に大垣特別支援学校の分教室を設置する案を検討。今年5月に両校の保護者らに説明した。 しかし「あまりに突然すぎる」「環境の変化に敏感な子どものことを考えられていない」など...(会員限定記事です)【中日新聞】少子化とは言え、実際に発達障害の診断を受ける児童が就学時で増えている昨今、早め早めの対策が臨まれますね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.05
コメント(9)
-

「障害ある兄弟姉妹が恥ずかしい」「健康に生まれて申しわけない」 …「きょうだい」ゆえの悩みや孤独。
「障害ある兄弟姉妹が恥ずかしい」「健康に生まれて申しわけない」…「きょうだい」ゆえの悩みや孤独[ケアラーの風景]きょうだい<1> 障害や病気がある兄弟姉妹を持つ人は「きょうだい」や「きょうだい児」と呼ばれる。子どもの頃から兄弟姉妹のケアを担ったり、親の関心が向けられずに孤独を感じたりしている。周囲の差別に苦しむケースもある。きょうだいの声に耳を傾け、必要な支援について考えたい。「自分見失いそうに」関東地方に住む福祉施設職員の女性(21)は、悟ったように話す。50代の両親と、重い知的障害と発達障害がある双子の弟と暮らす。弟は、食事や入浴、排せつなど日常生活全般に介助が必要。言葉は発するが会話はできない。福祉施設に通う平日の日中以外は、家族3人で世話をする。「お風呂だよ」。夕食後、父親が弟を連れて浴室に向かう。女性より20センチも背が高い弟の入浴介助は父親の役目だ。その間、女性と母親は、弟の着替えやおむつ、歯ブラシなどを用意し、居間のソファにバスタオルを敷く。風呂から出た弟はソファに寝転び、母親に歯を磨いてもらう。午後9時過ぎ、弟が寝る時間になると、電気もテレビも消して家の中を真っ暗にする。音や光に敏感な弟が眠りやすい環境を作るためだ。そして弟が眠るまで、3人で静かにじっと待つ――。「友達に話せない」弟には幼くして障害があることがわかった。女性は幼稚園も小学校も弟とは別のところに通った。「弟のことは友達に話せなかった。一人っ子だと思われていたのではないか」と振り返る。小学生時代、同級生たちが「障害者みたい」などと言って、ふざけあっているのを見ると、心がえぐられるようだった。「弟のことを知られたら、ばかにされるかも」。恐怖を覚え、自宅に友達を呼んで遊ぶことはあきらめた。 家の中でも不安だった。母親が買い物に行く時はたいてい留守番をして、弟の見守り役を務めた。小学4年生頃のある日、母親がいないことに気付いた弟が突然パニック状態に陥り、大声を出して歩き回り、ドアや階段に頭を打ち付けたり、手の指をかんだりして自傷行為を始めた。「お願い、やめて」。必死に弟をなだめたが、その後どうなったかは思い出せない。高校時代、夜に興奮して眠れなくなった弟が声を出して歩き回るのを、親と交代しながら朝まで見守ったこともあった。家族4人で外出したのは、小学校低学年の頃が最後だ。弟の体も声のボリュームもまだ小さく、親も対応しやすかった。「もっとみんなで旅行や外食をしたかったし、ディズニーランドにも行きたかった。でも、無理だと分かっていたから、親には言えなかった」一人暮らし断念 昨年秋、就職試験のため、東京都内のホテルに初めて一人で泊まった。家族の気配も、音もない一人だけの空間。静寂が心地良く、満ち足りた気持ちになった。「社会人になったら一人暮らしをしたい」。思い切って両親に切り出すと、「弟の世話を一緒にしてほしい」「私たちを支えてほしい」と懇願された。弟を世話する大変さは十分に分かる。親の反対を押し切ることはできなかった。この春、地元で就職した。時折、将来について考える。「結婚相手は障害のある弟を受け入れてくれるだろうか」「自分が産んだ子どもに障害があったら」――。学生時代に付き合っていた男性に、「(弟のことを)理解できない」と言われたことが、ずっと心に引っかかっている。 「弟も親も大切な家族」。その思いは確かにある。ただ、心は揺れる。「もう『他人軸』で生きることをやめたい。自分を見失いそうになる」 当事者らの団体「全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会(全国きょうだいの会)」が2019年に実施した調査によると、「きょうだい」の77%が、兄弟姉妹に「困った行動がある」と回答。61%は「兄弟姉妹の困った行動がつらい」と感じていた。複数回答でつらかったことを尋ねると、多い順に「他の家族と違う」「友達に話せない」「親の関わり」などが挙げられた。家族支援や理解必要障害や病気がある兄弟姉妹を持つ「きょうだい」は、特有の悩みや課題を抱えやすいという。全国きょうだいの会によると、きょうだいは、親の関心がケアが必要な兄弟姉妹に向きがちなため、子どもの頃から孤独感を抱いたり、自分の感情や欲求を抑えて「良い子」になろうとしたりする傾向がある。常に家族を気遣って、日常的に兄弟姉妹のケアを担うこともあり、自分の希望より家族を優先してものごとを判断することも少なくない。ストレスをため込み、精神疾患につながるケースもある。 大人になっても、兄弟姉妹を巡る不安や負担はなくならない。相手の理解を得られずに結婚できなかったり、親が亡くなった後の兄弟姉妹の世話が心配だったりするためだ。 同会事務局の増田京子さん(56)は「周囲からは、優しくて良い子に見えるため、気に留められないが、複雑な思いを抱えている。自分の意思や価値観を大切にして生きていけるような支援が必要」と語る。 現状、きょうだいを集めてプールやカラオケ、ゲームなどのレクリエーションを行ったり、オンラインで気軽に日頃の思いや悩みを話し合えたりするなどの支援活動が、民間団体を中心に行われている。しかし、地域差が大きく、活動は限定的。公的な支援も十分ではない。 明星大学教授(社会福祉学)の吉川かおりさんは「障害のある子を持つ親の負担が大きいため、きょうだいにしわ寄せが及んでいる」と指摘する。親の愛情を感じることができないなど、子どもの頃に不健全な家庭環境で育つと、大人になってからも生きづらさや精神的な問題を抱えやすい。「あらゆる子どもに健やかな成長の場が保障されるべきだ。公的な家族支援の充実と社会の理解が不可欠だ」と訴える。[yomiDr.]どんな境遇でも兄弟隔たりなくというのもなかなか難しいもの。家族で、話し合ってそれぞれの生き方、希望を含めて最適な方法が模索できるといいのでしょうね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.04
コメント(9)
-

入浴時に障害者がやけど負い死亡の施設、前年も熱傷事故 再発防げず。
入浴時に障害者がやけど負い死亡の施設、前年も熱傷事故 再発防げず宮城県石巻市の障害者支援施設で2022年、入浴支援を受けた利用者が全身にやけどを負って死亡する事故があり、宮城県警は、高温で入浴させて利用者を死亡させたとして、当時の施設関係者3人を業務上過失致死の疑いで15日にも書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。 捜査関係者によると、書類送検されるのは当時の現場責任者の男性と、入浴支援にあたった女性2人。3人は同県石巻市門脇の「ひたかみ園」で22年12月30日、利用者の阿部加奈さん(当時38歳)の入浴支援をする際、湯の温度に注意する義務があるのに高温で入浴させ、3日後に死亡させた疑いがある。 遺族によると、阿部さんは車いすを利用し、知的障害があるため言葉などによる明確な意思表示ができなかったという。施設の事故報告書によると、やけどは全身の60%に達しており、死因は全身熱傷による敗血症だった。温度は50度前後だった可能性があるという。別の利用者も入浴熱傷、改善策「徹底されなかった」 この事故の約1年前にも、別の利用者が入浴時にやけどしていたことが朝日新聞の取材でわかった。・・(この記事は有料記事です)【朝日デジタル】つい、先日もクリップしたこの事故、不慮の事故が繰り返していたとなると、介護施設としては失格ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.03
コメント(10)
-

遠藤牧場裁判 原告側が本人尋問へ向け障害者への質問など 配慮求める意見書を提出。
遠藤牧場裁判 原告側が本人尋問へ向け障害者への質問など配慮求める意見書を提出恵庭市の牧場で、知的障害を抱える3人が障害年金を横領されたなどとして牧場と市に損害賠償を求めている裁判。原告側が今後本人尋問を求めていくため、障害者に配慮するよう意見書を提出しました。恵庭市の遠藤牧場で働いていた知的障害を抱える3人は、プレハブ小屋に住み込みで給料もなく働かされ、支給された障害年金も横領され、市が隠蔽したなどとして、牧場と市に損害賠償を求めています。17日の裁判で恵庭市側は、書面で市に虐待の相談や通報はないとして「経済的虐待の可能性はないという認識に至った」と改めて主張。一方、原告側は今後本人尋問を求めていくことを明らかにしたうえで、知的障害を抱える原告らへの質問などに配慮するよう裁判所に意見書を提出しました。■原告弁護団・中島哲弁護士:「これが単発の被害じゃなくて何十年にもわたって続けられてきたこと、障害者相手であれば許されるのか、そういうことの根源的な過ちを(本人尋問で)明らかにしたい。」次回の裁判は、来年1月28日に行われます。【HTB 北海道ニュース】まだまだ先が遠い道のりですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.02
コメント(11)
-

「うるせえばばあ」「じじい」小学生同士の“暴力トラブル”裁判、保護者に50万円賠償命令も…「息子はやってない」えん罪主張。
「うるせえばばあ」「じじい」小学生同士の“暴力トラブル”裁判、保護者に50万円賠償命令も…「息子はやってない」えん罪主張2016年4月、神奈川県内の公立小学校に通う女子児童(当時5年生)が、男子児童(当時4年生)からひざを蹴られ後遺症を負ったなどとして、男子児童の保護者である両親と学校を運営する市を相手取って損害賠償を求めていた民事裁判で、10月3日、横浜地裁小田原支部は、男子児童の暴行と後遺障害との因果関係を認めなかった。しかし、男子児童が1度暴行をふるったことは認め、男子児童の両親に対し、約50万円の損害賠償を支払うよう命じた。判決後、男子児童の両親は記者会見を開き、「(暴行は)虚偽の事実であり、不当な判決」として、東京高裁へ控訴する方針を示した。「うるせえばばあ」「じじい」言い合いからトラブルに判決文などによると、原告の女子児童Aと、1学年下の男子児童Bは地域ごとに班に分けて集団登校させる「登校班」が同じだった。Bは、通常学級に在籍していたが、発達障害(自閉症スペクトラム障害)を有しており、学校および市は特性を理解し、学校内の教諭らはもちろん、市のスクールカウンセラーなどにも情報が共有され、定期的なケース会議を開くなど対応がとられていたという。2016年4月11日の下校時、小学校の敷地内でBがAから「早く帰るように」と注意されたことを機に、「うるせえばばあ」「じじい」などとお互い言い合いになった。AとBは別々に校門を出たが、その後BがAに追いつき、通学路上のコンビニ付近でAの右膝を蹴ったという。これにより、Aは右膝を打撲、後遺障害が残ったと主張した。Aはほかにも「膝を蹴られて、髪の毛を引っ張られた」「12日登校時にも足を蹴られた」「(学校内ですれ違った時に)殴るまねをされ、進路をふさがれた」などとも主張していたが、Bはいずれも否認していた。さらに、A側はBとの一連のトラブルで心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したなどとして、Bの両親と安全配慮措置を講じなかった市に対して約2400万円の損害賠償を求めていた。1度の暴行認めたが“後遺症”に因果関係は「なし」裁判所は、2人のやりとりを目撃していた児童への聞き取りやこれまでの両者の発言などから、コンビニ付近でBがAに対し1度暴行を加えたことを認め、Bの両親に対し、約50万円の損害賠償を支払うよう命じた。しかし、そのほかの行為は「Aの述べた内容を裏付ける事情、Bが述べた内容を排斥できる事情はない」として、Aの主張を認めなかった。また、Aが主張していた後遺症についても、裁判長はAが暴行よりも前の2014年から右膝痛を訴えて通院・受診していたことなどを挙げ、「打撲が後遺障害を残すような重篤なものであったとは認められない」と、暴行との因果関係を否定した。弁護士「非常に問題のある『冤罪事件』」批判判決後の会見で、被告(B)側の代理人である伊藤克之弁護士は、暴行と後遺障害との因果関係が認められなかったことは「評価すべき」と述べたが、「そもそもBは暴力をふるっておらず、非常に問題のある『冤罪事件』だ」として判決を批判した。「AはBから3回暴行を受けた結果、後遺症を負ったと主張していました。判決は、このうち2回の暴行については、証拠が不十分とのことで認定しませんでしたが、1回の暴行について、警察による触法調査の結果をもとに認定してしまいました」(伊藤弁護士)Aは警察に「ランドセルを引っ張る、首を絞めるなどの暴行を受け、逃げたにもかかわらず追いかけてきて胸とお腹のあたりを1回ずつ殴る、右膝を5、6回蹴る、髪を引っ張る等の暴行を受けてけがを負った」として被害届を出しており、それに基づきBは触法・ぐ犯調査(※)を受けている。※少年が事件や非行(ぐ犯事由)を起こした場合に、警察や児童相談所、家庭裁判所が行う調査調査の結果がまとめられた「申述書」は裁判の証拠としても提出された。これには、Bが調査の中で、「左足でAのスネ辺りを1発蹴りました」と述べたことが書かれており、「本当に1発だけかな」という問いに対しては、「はい」と回答したとされ、最後には署名捺印がされているという。これに対して、伊藤弁護士は「冤罪事件ではいわゆる『供述弱者』という言葉が使われていますが、Bは発達障害を抱えており、コミュニケーションが非常に苦手です。周りが騒ぐことで本人の記憶が混乱してしまい、実際に蹴ったのかわからないなどの曖昧な中で調書を取られてしまっています」と説明する。また、伊藤弁護士は事件を目撃した児童について、「原告のAと親しい間柄であり、他にさしたる証拠もないのに、証言を鵜呑みにしているのは問題」と指摘。さらに、Bは主治医から運動能力が劣る「発達性協調運動障害」とも診断されていることを挙げ、「Aは複数回に渡ってひざを蹴られたと主張していましたが、Bはサッカーボールを蹴ることも満足にできず、同じ箇所を何回も蹴ることはできないと主治医も証言しています。しかし、判決は、『少なくとも一回は蹴った』と認定しました。しかも、申述書ではBは『膝』ではなく、『スネを蹴った』と供述したことになっていますが、判決では『膝を蹴った』とされました」(伊藤弁護士)「息子はAから嫌がらせをうけ、嫌な思いをすることがあった」会見に出席したBの母親は「裁判でも発達障害の診断書などを出しましたが、判決は、Bの障害を考慮したものではありませんでした」と落胆する。「この事件があってから私たちも知ったのですが、息子はAから嫌がらせをうけ、嫌な思いをすることがあったそうです。息子は(特性から)なかなか(自分の悩みについて)言えないし、言葉にできない。原告に訴えられて以降、息子は壁に頭をぶつけたり、薬を大量に飲んだり、ハサミを持ち出そうとしたり、細かいものも含めれば、何回自傷行為に及んだのか数え切れません。病院に運ばれたことも3回あります。いつどんなきっかけで(自傷の)スイッチが入るのかわかりません」同じく会見に出席したBの父親は怒りをあらわにする。「警察の触法調査は、休憩なしで3時間続き、黙秘権の告知も全くありませんでした。息子は、発達障害でこだわりや正義感が強い。だからこそ、警察官になるのが夢で『僕みたいな子を助けたい』と言っていた。それなのに、警察官に冤罪をかけられた。今では(訴えられたことを)思い出すたびにフラッシュバックを起こし、息子は死にたくなるほど苦しんでいます」両親は1回の暴行が認められた判決を不服として、東京高裁へ控訴することを考えているという。■渋井哲也栃木県生まれ。長野日報の記者を経て、フリーに。主な取材分野は、子ども・若者の生きづらさ。依存症、少年事件。教育問題など。【弁護士JPニュース】今は小学校の現場でも、ちょっとしたことで裁判沙汰になるんですね。教員の成り手が減る一方ですね。自閉症でもある程度会話ができたり、関わりが持てると、なかなかその障害の本質を理解されるのが難儀です。通常学級に入学時にはある程度の覚悟と見守る心構えが必要になります。回りが成長してくると、助けてくれたり、守ってくれるようになっても、それが本人にとってベストかどうかも悩む昨今です。常に学校と連携を取って低姿勢で協力を惜しまないことが親に最小限に求められます。今、実際に似たような児童を抱えて支援員を務めている者としては現場での対応の難しさを感じています。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.10.01
コメント(9)
-

自閉症は人類の脳が「進化した結果」との研究結果 ...脳の発達の遅れが進化に貢献した可能性も。
自閉症は人類の脳が「進化した結果」との研究結果...脳の発達の遅れが進化に貢献した可能性も<ASDは発達障害の一種とされているが、単なる「障害」ではない可能性が浮上してきた>人間の脳の進化過程に、自閉症の起源があるかもしれないことが、科学者たちの研究によって明らかになった。「この研究結果は、人間の脳を特異なものにした遺伝的変化が、人間の神経多様性の増大にも関与していることを示唆している」と、研究の筆頭著者アレクサンダー・L・スターは述べた。米国疾病予防管理センター(CDC)によると、アメリカでは約3.2%の子どもが自閉症スペクトラム障害(ASD)と診断されている。世界保健機関(WHO)によると、ASDは、世界中でおよそ100人に1人の子どもに影響を与えている複雑な発達障害だ。ASDには、社会的なコミュニケーションにおける持続的な困難、限定された興味、反復的な行動といった特徴がある。動物にも見られる他の神経疾患とは異なり、自閉症や統合失調症は基本的に人間に特有のものと思われる。これは、発話の生成や理解など、他の霊長類には見られない人間特有の高度な能力が関与しているためと考えられている。人間の脳と遺伝的変化の関係は科学者たちは、単一細胞RNA配列解析の進歩により、脳内の細胞の種類に驚くほどの多様性があることを突き止めた。並行して、大規模な遺伝学的研究によって、人間の脳における他の哺乳類には見られない大きな変化も明らかになっている。こうしたゲノム要素は、他の哺乳類では長い進化のあいだほとんど変化しなかったのに、人類では急激に進化した。ホモ・サピエンスと他の異なる種の脳サンプルを分析したところ、大脳皮質の外層に最も多く存在する「L2/3 ITニューロン」と呼ばれる神経細胞のタイプが、ホモ・サピエンスは他の類人猿と比較して、急速に進化していたことがわかった。この急激な変化は自閉症と関連する遺伝子の大きな変化と一致していることから、自閉症も人類特有の自然選択圧によって形作られた可能性が高い。しかし、こうした変化が人類の祖先にもたらした進化的な利点は、いまだ明確になっていない。研究チームによれば、これら多くの遺伝子は発達の遅れと関係していることから、チンパンジーに比べて人間の脳の出生後の成長が遅いことと関係している可能性がある。また、発話と言語理解といった人間特有の能力も関係していると考えられる。実際、自閉症に関連する遺伝子の進化が、初期の脳の発達を遅らせたり、言語能力を拡張したりすることにより、幼少期に学習と複雑な思考ができるようになるための時間的な猶予を広げたという仮説も存在する。そして、自閉症に起因する発達の遅延が、より高度な推論能力を育むための時間を確保することこそが、進化における利点となった可能性もあるのだ。自閉症は「障害」ではなく、人類の進化から生まれた副産物なのかもしれない。【参考文献】Starr, A. L., & Fraser, H. B. (2025). A general principle of neuronal evolution reveals a human-accelerated neuron type potentially underlying the high prevalence of autism in humans. Molecular Biology and Evolution.[NEWSWEEK]ウェンデイ・チャン:自閉症ーわかっていること(と、分かっていないこと)つかみどころのない自閉症の特性に、似たようなことを考えたことがあります。人間特有と言うのも、納得できますね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.30
コメント(7)
-

遺族「本当のことが知りたい」 宮城・障害者施設熱傷事故で書類送検。
遺族「本当のことが知りたい」 宮城・障害者施設熱傷事故で書類送検 宮城県石巻市の障害者支援施設「ひたかみ園」で2022年、利用者の女性(当時38)が入浴時に全身にやけどを負って死亡する事故があり、宮城県警は15日、施設関係者3人を業務上過失致死の疑いで書類送検した。起訴を求める厳重処分の意見を付けた。 石巻署によると、3人は当時の職員で、現場責任者の30代男性、入浴介助にあたった40代女性と20代女性。22年12月30日、利用者の阿部加奈さん(当時38歳)の入浴を介助する際、湯の温度に注意する義務があるのに、50度前後の高温で阿部さんを入浴させて全身にやけどを負わせ、呼吸不全で23年1月2日に死亡させた疑いがある。 3人はいずれも容疑を認め、腕と手で湯をかき混ぜたが、確認が不十分だったと話しているという。署は阿部さんは約5分間、湯につかっていたとみている。 阿部さんの母親(76)は「娘に報告できることが一つ増えた。娘と同じような思いをする人を出さないために、園には職員の教育を徹底してほしい。そして、園にも捜査機関にも本当は何が起こったのか明らかにしてほしい」と話した。再発防止を訴える遺族の胸中は【朝日デジタル】50度の熱湯に5分も浸かったとは、まるで虐待そのものですね。それも二人で温度を確認していたとは信じがたいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.29
コメント(7)
-

「平和な街なのに」地域住民に衝撃 埼玉の老人ホーム殺人事件。
「平和な街なのに」地域住民に衝撃 埼玉の老人ホーム殺人事件埼玉県鶴ケ島市若葉2の老人ホームで15日、入所者2人が死亡する事件があり、うち1人に対する殺人容疑で元施設職員が逮捕された。「事件なんてない平和な街なのに」。周辺の住宅街には早朝から救急車のサイレンが響き渡り、地域住民に衝撃が広がっている。事件は午前4時55分ごろ明らかになった。「入所者の高齢女性2人が血を流している」。老人ホーム「若葉ナーシングホーム」の女性職員からの110番を受けて警察が駆けつけたところ、4階と5階の別々の部屋で、高齢女性がベッド上で頭から血を流して倒れていた。2人は搬送先の病院で死亡が確認された。 県警は、フードをかぶり、マスクを着けた姿で施設の防犯カメラに映っていた人物が事情を知っているとみて捜査。午前8時40分ごろ、施設近くにいた元職員の木村斗哉(とうや)容疑者(22)=熊谷市箱田4=を発見し、2人のうち小林登志子さん(89)を刃物で切りつけるなどして殺害したとして殺人容疑で緊急逮捕した。 現場は東武東上線若葉駅の南約200メートルで、「市役所通り」に面した5階建ての施設。周囲は低層の戸建て住宅が多い。 現場近くに住む50代女性は「午前5時半ごろ、救急車と消防車が施設前に止まって騒ぎに気付いた。上の階に明かりがつき、心肺蘇生をしている様子が見えた。ただごとではないと思った」と声を震わせた。 事件の一報を受け、午前中には多くの報道陣が現場付近に詰めかけた。取材に応じた60代女性は「施設の前は駅に行く時によく通る。このへんは治安が悪い印象はない。こんな大きなニュースは初めて」と言う。近くのマンションに住む80代女性は「事件が起きるなんて信じられない。このあたりは平和な街だったから」と驚いた様子だった。 県警は西入間署に53人態勢の特別捜査班を設置。詳しい経緯や動機の解明を進める。毎日新聞【YAHOOニュース】規制線が張られた事件現場周辺の道路。中央奥の5階建ての建物が「若葉ナーシングホーム」=埼玉県鶴ケ島市で2025年10月15日午前9時31分自分が以前に働いていた施設に戻っての殺人事件。以前にも似たような事件もあり、今回も暗証番号を憶えていて、簡単に鍵のロックを解除できたとか。折に触れて鍵を変えないと、ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.28
コメント(8)
-

重度知的障害者の地域生活推進で団体設立へ〈神奈川〉。
重度知的障害者の地域生活推進で団体設立へ〈神奈川〉重い知的障害のある人が入所施設ではなく、支援者に囲まれてアパート暮らしができる環境を整えようと、行政などに働き掛ける動きが始まった。発起人は神奈川県座間市の尾野剛志さん。2016年7月、県立津久井やまゆり園(相模原市)の殺傷事件で重傷を負った一矢さんの父親だ。9月28日、同市内でその推進団体の設立準備会を開いた尾野さんは「一矢が座間でアパート暮らしを始めて5年。施設にいる時とは180度違う暮らしを送り、落ち着いた。一矢のような暮らしを望む人はたくさんいるはずだ」と話し、賛同者を募っている。現在、尾野さん夫妻とは別のアパートで暮らす一矢さんを支えるのが重度訪問介護サービス。一矢さんはNPO法人自立生活企画(益留俊樹代表、東京)の介護職員による同サービスを使う。外出時を含め生活全般を支える同サービスの利用者は全国で約1万3000人。その多くは肢体不自由者だ。制度上は知的障害者も対象だが、実際に利用する人はわずかだ。益留代表によると、神奈川県内にも同サービスを提供する事業所はあるものの、一矢さんを受け入れるところはなかったという。「一矢さんは偶然利用できた、と言う人がいるが、一矢さんをレアケースにしてはいけない」と強調した。同日の準備会には県営時代の津久井やまゆり園職員だった西角純志さん(専修大講師)らが駆け付け、議論の末、団体名を「重度知的障害者の地域生活を進める会」とすることに決めた。今後の活動や一矢さんの暮らしぶりは公式サイト「よってけ一矢んち」で確認できる。【福祉新聞】団体の設立を呼び掛けた尾野さん(右奥公式サイトに感動です。諦めずに一歩一歩の取り組みが大切ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.27
コメント(9)
-

南の楽園で「発達障害児8年で44倍」の衝撃 対岸の火事か、日本の縮図か 各地で頻発する水の“異変”。
南の楽園で「発達障害児8年で44倍」の衝撃 対岸の火事か、日本の縮図か 各地で頻発する水の“異変”発達障害児が急増している宮古島で、その原因と疑われている農薬による地下水汚染。宮古島では大きな問題となっているが、全国ニュースではまったくと言っていいほど報じられていない。しかし、同様の地下水汚染や河川汚染、水道水汚染は、実は近年、日本各地で起きている。必ずしも「対岸の火事」と看過できない状況だ。元農相が講演宮古島に滞在中、島内のコンベンションセンターで「未来の子どもたちのために地下水を守るセミナー」と題した無料のイベントが開かれた。市民グループ「宮古島の地下水を守る会」が主催し、元農林水産大臣の山田正彦さんが講演した。山田さんは政治家を辞めてからも全国を回って農業の立て直しを訴えている。講演では、日本でも欧米のように有機農業が広がりつつあり、それに伴い各地の小中学校で有機給食を導入する動きが盛んになっている現状を紹介。宮古島でも有機給食を推進することが地下水の安全を守ることにつながると説いた。同じ日に偶然、別の場所で人気イベントが開かれたことから、人が集まるか主催者は気を揉んでいたが、蓋を開けてみると予想を上回る260人強の市民が参加。守る会の関係者の目撃では、少なくとも全市議会議員の3分の1にあたる8人の市議の姿があった。この関係者は「これまではセミナーを開いても、来てくれる市議はせいぜい1人か2人だった」と語り、地下水汚染問題に対する島民の関心の高まりを指摘した。島外からも視察に参加者の中には本州のとある自治体の議員もいた。この議員の住む地域では近年、沿岸の魚介類の漁獲高が激減しているという。それを裏付けるデータも見せてもらった。原因は不明ということだが、議員は、陸地から河川や地下水を経由して海に流れ込む農薬や有機フッ素化合物(PFAS)など化学物質の影響を可能性として疑っているようだった。それで宮古島の地下水汚染問題にも関心を抱き、調べに来たという。以前、松枯れ病対策としてネオニコチノイド系農薬を空中散布していることが問題となった長野県のある地域からも関係者が視察に来たという話も聞いた。宮古島で起きていることはけっして対岸の火事ではない。そう思う人は日本各地に大勢いるようだ。宮古島市内で開かれたセミナーで講演する山田正彦・元農相(筆者撮影)同様の問題が各地で次々と実際、全国ニュースにはほとんどならないが、宮古島と同じような化学物質による環境汚染は近年、多くの地域で起きている。東京大学大学院の山室真澄教授が2022年に秋田市内の水道水を調べたところ、最大で欧州連合(EU)の水質基準を8倍強上回る1リットルあたり868ナノグラムのジノテフランが検出された。ジノテフランはネオニコチノイド系の殺虫剤で、稲作によく使われるため、日本ではよく検出される農薬の一つだ。翌年に行われた同様の調査では、EU基準の約30倍の濃度にあたる1リットルあたり3063ナノグラムのジノテフランが検出された。島根県の宍道湖では1993年を境にウナギとワカサギの生息数が激減した。原因を調査した山室教授は、同時期に周辺の水田で使われ出したネオニコチノイド系農薬との関連を指摘した。公益財団法人日本釣振興会(日釣振)によると、釣り人に人気のウグイ、オイカワが20年ほど前から全国各地の河川でどんどん釣れなくなっているという。日釣振は独自調査の結果、ネオニコチノイド系農薬の影響を疑い、現在、専門家の協力を得て本格的な調査を進めている。佐渡島の取り組み一方、行政、農業協同組合(農協)、農家が協力して水の汚染を含む環境汚染の低減に取り組み、実績を上げている地域も増えている。宮古島と同じく周囲を海に囲まれた佐渡島(新潟県佐渡市)は2004年、台風で主要農産品の米が大凶作に見舞われた。それによって他の産地に奪われた市場シェアはなかなか回復せず、佐渡の経済は大ピンチに陥った。起死回生を狙って打ち出したのが、他の産地との差別化を念頭に、農薬や化学肥料をできるだけ使わない、生きものと環境に優しい米作りだった。折しも佐渡では、絶滅した国の特別天然記念物トキの復活・放鳥計画が進行。トキの放鳥を成功させるには、水田をドジョウやカエル、水生昆虫などトキの餌となる生物が泳ぎ回る昔の姿に戻すことが不可欠で、そのためには生物にとって有害な農薬を極力減らすことが必須条件だった。かくして行政、農協、農家が一体となって生きものと環境に優しい米作りがスタート。農薬や化学肥料の削減は、農家にとっては収量減のリスクが高まり、農協にとっては重要な収益源である農薬や化学肥料の売り上げ減を意味する。だが、目立った抵抗や反対の動きはなかった。差別化できなければ島全体が沈没するという運命共同体意識が共有されていたからだ。そして何よりトキの放鳥をいかに成功させるかが島民にとって最大の明るい話題だった。世界農業遺産に認定2008年、佐渡市は「朱鷺(トキ)と暮らす郷認証制度」を創設した。農薬と化学肥料の使用量を一定量以下に減らすなどして栽培した米を市が認証するもので、認証米にはトキをかたどった認証マークを付与した。一方、佐渡農業協同組合(JA佐渡)は2015年にネオニコチノイド系農薬の米作向け販売を中止、2018年にはJA佐渡が販売する米の全量をネオニコチノイド系農薬不使用の米に切り替えるなど、生きものと環境に優しい米作りを加速させた。取り組みがメディアに取り上げられるなどして、佐渡米の知名度は全国的に上昇。2011年、国連食糧農業機関(FAO)は、佐渡市を石川県の能登地域と共に日本初の「世界農業遺産」に認定した。FAOの公式サイトは佐渡市を「トキと共生する佐渡の里山」と紹介している。農家の生き残り策有機農業を推進する農協として脚光を浴びている茨城県・常陸農業協同組合(JA常陸)の秋山豊組合長は「有機農業に取り組む理由としては、環境問題を挙げる人もいれば健康問題を挙げる人もいるが、JA常陸が有機農業に取り組む最大の理由は、農家の生き残り」と、10月上旬に東京都内で開かれたイベントで語った。秋山組合長は、JA常陸のある茨城県北部は耕地の約3分の2が山間地で生産性が非常に低く、安価な輸入農産物に勝つには生産物に付加価値を付けることが不可欠と指摘。そこで出した答えが有機農産物への転換だった。茨城県の大井川和彦知事や地元・常陸大宮市の鈴木定幸市長の支援も得て、有機農業への本格参入は2022年と比較的最近ながら、他の地域から注目されるほどの成果を上げている。果たして宮古島は災い転じて福となすことができるか。すべては当事者である島民の意思に委ねられている。終わり。猪瀬聖ジャーナリスト(エクスパート)米コロンビア大学大学院(ジャーナリズムスクール)修士課程修了。日本経済新聞生活情報部記者、同ロサンゼルス支局長などを経て、独立。食の安全、環境問題、マイノリティー、米国の社会問題、働き方を中心に幅広く取材。著書に『アメリカ人はなぜ肥るのか』(日経プレミアシリーズ、韓国語版も出版)、『仕事ができる人はなぜワインにはまるのか』(幻冬舎新書)など。[YAHOOニュース]こういうニュースこそもっと全国視野で放送して欲しいものですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.26
コメント(6)
-

お金の管理が苦手な人へ…うまく付き合うコツ教えます! 発達障害あるFP岩切健一郎さん(長岡市)が本出版。
お金の管理が苦手な人へ…うまく付き合うコツ教えます!発達障害あるFP岩切健一郎さん(長岡市)が本出版発達障害の注意欠陥多動性障害(ADHD)当事者で、お金に苦労した経験があるファイナンシャルプランナー(FP)岩切健一郎さん(39)=長岡市=が9月、「発達障害かもだけど、お金のことちゃんとしたい人の本」(ダイヤモンド社)を出版した。発達障害の特性を踏まえ、お金と付き合うこつを指南する。岩切さんは「お金の管理が苦手だと思っている全ての人に届けたい」と話している。 岩切さんは宮崎県出身。新潟大を卒業後に保険会社勤務などを経て、現在は...(この記事は会員限定記事です)[新潟日報]発達障害かもだけど、お金のことちゃんとしたい人の本 [ 岩切健一郎 ]実体験からの指南は貴重ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.25
コメント(11)
-

厚労省、障害福祉の「望まないセルフプラン」解消へ 相談支援体制の強化を検討。
厚労省、障害福祉の「望まないセルフプラン」解消へ 相談支援体制の強化を検討厚生労働省は10月1日の社会保障審議会・障害者部会で、本人や家族が本意ではなくやむを得ずセルフプランを選んでいるケース(望まないセルフプラン)の解消に向けて、全国の自治体に取り組みを促していく意向を示した。次の第8期の障害福祉計画に、こうした課題の改善に向けた取り組みを記載していくべきとの認識も示した。各自治体に地域の状況を自ら分析し、相談支援体制の充実・強化を図るよう呼びかける考えだ。障害福祉サービスのセルフプランは、身近に相談支援事業所がない場合、本人・家族が希望する場合などで認められている。セルフプラン率は自治体間のばらつきが大きい。昨年3月末時点の全国平均は計画相談が15.8%、障害児相談が30.7%だが、これを大きく上回る自治体もあるのが実情だ。【JOINT 介護ニュース】《 社保審・障害者部会|10月1日 》望まないセルフプランなど、あったこと自体が問題ですね。619万アクセス達成しております。いつもご訪問にコメント感謝です。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.24
コメント(8)
-

16歳の悲劇教訓…行方不明共有アプリ、障害者も対象に 八王子。
16歳の悲劇教訓…行方不明共有アプリ、障害者も対象に 八王子行方が分からなくなった認知症患者らの情報を官民で情報共有し、早期発見を図る「SOSネットワーク」について、東京都八王子市は8月から障害者も対象に含めた。知的障害のある市内の男性が行方不明後、遺体で発見された悲劇を教訓とした対応で、全国的にも珍しいという。 同ネットワークは、自治体や警察、公共交通機関、企業などが連携。事前に認知症患者らの名前や写真などを登録しておくと、行方不明時に関係者に情報が伝わる仕組み。厚生労働省によると、昨年4月時点で全国区市町村の8割超が同様の体制を築き、東京都八王子市を含む115自治体でスマートフォンアプリを活用している。専用アプリを活用することで行方不明時にアプリをダウンロードしている人に対し、捜索依頼を出せるほか、行方不明者の写真や家族の連絡先などを配信できる。対象を広げるきっかけとなったのは昨年7月、特別支援学校に通う市内の知的障害のある男子生徒(16)が自宅から外出したまま行方不明となり、6日後に山梨県内で遺体で発見された事案だ。知的障害や発達障害がある人の中には、感覚過敏や特定のこだわりがあり、物音や周囲の状況に反応してその場を飛び出すなど突発的に行動することもあるとされる。こども家庭庁の調査では2022年度、全国の放課後等デイサービスなど障害児の支援施設などで計167件の行方不明・見失い事案が発生した。 男性の一周忌にあたる今年7月、市内の障害者の家族や支援者の団体が障害者の見守り体制構築などを求める要望書を国に提出。市は再発防止策として認知症患者らを想定した同ネットワークの対象を広げることを決めた。 初宿和夫市長は9月30日の記者会見で「亡くなった方のご冥福を祈る。命が救われるようにしたい」と述べた。【毎日新聞】こういう事態が起きないとなかなか実現しないものでも、これを機に、できたら全国展開して欲しい教訓ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.23
コメント(7)
-

鈴木一真、発達障害の息子の「ファンタジックな夢」にエール。
鈴木一真、発達障害の息子の「ファンタジックな夢」にエール米国を拠点に活動している俳優・鈴木一真(56)が3日、インスタグラムで、発達障害と診断された息子の近況について報告した。 息子が海でサーフィンを楽しむショート動画などをアップ。「今年の夏休みも、週末はサーフィンのクラスに参加しました。一昨年から続けて参加している発達障害や身体障害のある子ども専用のクラスです」と紹介し、「かつては波を怖がっていたセガレも、インストラクターのサポートを受けながら波に乗れるようになり自信をつけました」と伝えた。 さらに「今年はテレビ、ラジオやSNSなどから取材を受け、さまざまなインタビューに応じたセガレ。なんと『波の中でサーフィンをしたい』というファンタジックな夢まで語っていました。いつか実現するといいなと思います!」とつづった。 鈴木は2010年に一般女性と結婚し、14年4月に長男が誕生。15年には「文化庁新進芸術家海外研修制度」を利用し、米・ロサンゼルスに拠点を移した。今年4月に11歳になった息子が幼少期に発達障害と診断されていたことや、米生活を続ける背景について明かしていた。※写真は資料テレビ朝日【YAHOOニュース】西海岸にての貴重な体験は一生の宝ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.22
コメント(4)
-

発達障害の子どもに寄り添う美容師 児童書を寄贈。
発達障害の子どもに寄り添う美容師 児童書を寄贈発達障害の子どもが安心して髪を切れるよう工夫する「スマイルカット」を広めてきた美容師で、NPO法人「そらいろプロジェクト京都」代表の赤松隆滋さん(51)の活動が児童書になった。そらいろプロジェクト京都は9月、京都市内の市立小学校や総合支援学校計162校に、寄贈した。 児童書「スマイルカットでみんな笑顔に! 発達障がいの子どもによりそう美容師さん」は、赤松さんの15年以上の取り組みをもとに、安心感を与える声かけやカットの工夫を紹介。2月に出版された。子どもや保護者との体験談、イラストも盛り込まれている。作家の別司芳子さんが、赤松さんや子どもら関係者に取材をし、書き上げた。 赤松さんの活動のきっかけは2010年、児童館でのカット講座だった。保護者から「発達障害の子は美容院で髪を切るのが難しい」と相談を受け、赤松さんは「断らずにやってみよう」と応じたが、知識不足から失敗。その経験が学びの出発点となり、スマイルカットにつながった。 14年には活動を広げるため「そらいろプロジェクト京都」をNPO法人化。全国で講演や研修を行い、障害者への合理的配慮の重要性を伝えている。これまでに赤松さんが直接カットした子どもはのべ9千人を超え、スマイルカット実施店舗は全国で100以上に広がった。 しかし、「業界全体の理解は十分ではない」と赤松さんは言う。昨年4月に改正障害者差別解消法が施行され、事業者に合理的配慮が義務づけられた。しかし、美容師の国家資格の教科書には、合理的配慮の具体的な内容が盛り込まれていない。赤松さんは厚労省と、障害者が安心できるヘアカットのガイドラインを作成した。しかし、普及はなかなか進まない。 「この取り組みが当たり前になり、NPOが不要になる日をめざしたい」。赤松さんはそう語り、活動の輪を広げている。朝日新聞社【YAHOOニュース】スマイルカットでみんな笑顔に! 発達障がいの子どもによりそう美容師さん [ 別司芳子 ]丁寧な取り組み、全国的に展開して欲しいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.21
コメント(9)
-

「助けて」と言えなかった母親…赤ちゃん3人遺棄事件、 弁護人が語る"見えない生きづらさ"。
「助けて」と言えなかった母親…赤ちゃん3人遺棄事件、弁護人が語る"見えない生きづらさ"出産した赤ちゃん3人の遺体を自宅の押し入れに遺棄したなどとして死体遺棄と殺人の罪に問われた母親に、今年2月、懲役6年の判決が言い渡された。1人目は死産後の死体遺棄、2人目は困窮の末の殺人と死体遺棄、3人目は自然死後の死体遺棄という事件だった。裁判では、女性がホストに騙されて経済的に困窮していたことや、事件後にADHD(注意欠如・多動症)と診断されていたことが明らかになった。「孤立し、追い詰められた末に起きた事件だった」。法廷でそう訴えた女性の国選弁護人、田中拓弁護士に弁護活動の経緯を聞いた。(弁護士ドットコムニュース)●発達障害の特性に周囲は気づかず──今回、3人の子の遺体を遺棄した女性の弁護を担当されました。彼女には発達障害の特性がありましたが、家族にも周囲にも気づいてもらえず、兄弟と比べて幼い頃から「お金にだらしない」「片付けができない」と親から評価されず、自分だけが認められないと感じて育ってきたようでした。また、特性とそこに由来する自己肯定感の低さから、問題解決能力が極めて低く、次々と男性に騙され、唆(そそのか)されて風俗業を転々とし、引っ越しても住民票を移さず、コロナ禍においても国民一律に支給された給付金の存在も知らないなど、その場しのぎで生活しているような状況でした。交際相手を装うホストは、彼女を騙し、より過酷な環境で働かせ、彼女は交際相手を喜ばせるつもりだったところが、実際には搾取され続けていたのです。●女性視点の必要性を感じて女性弁護士に相談──どのように弁護活動に取り組まれたのでしょうか。接見時、彼女は明るくよく話し、十分コミュニケーションが取れたので、当初は発達障害を見抜けませんでした。しかし、女性の視点の必要性を感じ、女性弁護士に相談したところ、起こっている出来事の表をなぞるのではなく、生い立ちから事件まで女性としての歩みを丁寧に聞き取らねばならないと助言を受けました。妊娠・出産の大変さを経験した女性からすれば、彼女のとった行動は、あまりにもあり得ないものだったからです。そこで、改めてじっくりと話を聞き、違和感が積み重なっているところへ、協力医が現れ、精神科医師にも相談して聞き取りや検査を実施してもらった結果、ADHDと診断されました。同時に社会福祉士と連携し、更生支援計画を策定しました。これには、日弁連の「罪に問われた障がい者等の刑事弁護等の費用に関する制度」を活用し、福祉的支援の立案に必要な費用を補助してもらいました。この制度は、もともと弁護人が手弁当で足していた費用を、弁護士会の基金で援助するものです。本来は、このような費用は国選制度として支出されるべきだと思います。●責任能力に影響しない障害を軽視した裁判所──判決は懲役6年で確定しました。犯行に至った背景には「発達障害」「水商売の男性による風俗業界で働く女性に対する経済的・精神的・性的な搾取」「コロナ禍」という三つの要因が重なっています。コロナ禍が要因というのは、赤ちゃん3人の中で死産等ではなく、殺人と認定された子の事件は、コロナ禍で対人接客業が成り立たなくなった令和2年4月に発生しているからです。障害特性については裁判でも訴えましたが、裁判所は「責任能力に影響しないレベルの障害特性」をあまりに軽視し、残る二つの要因には目を向けませんでした。あくまで経緯にすぎず、動機そのものではないというのでしょう。こうした事情が量刑を判断するうえで重視されないのは妥当なのか、大きな疑問が残ります。ただ、彼女自身は、刑事手続きを通して自分の生きづらさやその原因に気づき、支援を受けての再出発を想像し、将来への希望を見出せたと感じています。彼女は必ず生き直せると信じています。●「助けて」を言えない人がいる現実──社会や周囲に求めたいことはありますか?刑事弁護をしていると、障害特性や環境の劣悪さ、虐待や搾取に遭った被害体験などの生きづらさが要因であると感じることが多いです。それが自己責任の名のもとに、悪質な事件の犯人として罰を受ける。「なぜ弱い人がさらに追い込まれるのか」と思うことがよくあります。今回の彼女のような風俗で働く人についても、「本人が好きでやっている」という認識の方もいるかもしれません。しかし、実際には発達障害や精神障害といった生きづらさを抱える人が、周囲の食い物にされているという側面があるかもしれないという目線が必要だと感じます。今回の女性は、困っていると気づきにくい、気づいてもSOSを出せない、相談できないという方でした。「助けて」と言えない人がいる。その現実を社会に知ってほしいと思います。この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。[弁護士ドットコムニュース]女性は裁判で懲役6年の実刑判決を言い渡され、その後確定した(弁護士ドットコムニュース撮影)なんとも大変な人生ですね。親や家族とすっかり疎遠となってしまったこと、果たして親の責任は?と残念に感じます。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.20
コメント(10)
-

涙の母親「発達障害の息子をおもちゃに」 暴行、土下座を動画撮影、被害生徒にトラウマ。
涙の母親「発達障害の息子をおもちゃに」 暴行、土下座を動画撮影、被害生徒にトラウマ大阪市の淀川河川敷で知人少年2人から暴行を受けるなどした高校1年の男子生徒(15)と母親が産経新聞の取材に応じた。発達障害で意思表示がうまくできない男子生徒に対し、少年らは「スパーリング」と称して暴行を繰り返したという。母親は「息子をおもちゃにしている。本当に許せない」と憤る。「遊ぼうや」。6月中旬の午後8時ごろ、電話で呼び出された男子生徒が河川敷に着くと、いきなり「けんかしようや」とからまれ、暴行が始まった。「やめてほしい」と伝えたが暴行は止まらず、土下座させられた上、川に入るよう命令された。「ぬれていたらばれるから」と下着姿になることも指示されたという。母親が一連の事態を知ったのは約1週間後。少年の一人が暴行の様子を撮影した動画を知人らに見せたことがきっかけだった。息子に時間をかけてゆっくりと詳細を尋ねると、重い口を開いた。繰り返し電話をかけられて呼び出されたこと、反撃を恐れ抵抗せずに暴行が終わるまで我慢していたこと…。涙ながらに「怖かった」と全てを打ち明けてくれた。被害を母親に伝えなかったのは、「シングルマザーのママに心配をかけたくなかったから」。その言葉に母親は「なぜ自分がもっと早く異変に気付いてあげられなかったのか」と涙を流した。事件後、男子生徒は少年らとの関係を断っているが、あの夜の出来事は「忘れたくても忘れられない」。深夜にふとフラッシュバックすることもあり、事件を思い出すと頭が痛くなるという。母親は「発達障害のある息子が遊び道具のようにされたことは許せない。『障害があるから守ろう』とする、そんな社会になってほしい」と訴えた。【産経新聞】男子生徒が少年らから暴行を受けた淀川の河川敷=1日午後、大阪市淀川区苛めはどの社会でもありますね。いかに日々の中で、子どもと向き合い、学校と連携を取っていくかでしょうね。この後の対応については、更に慎重に、高校生らしくのびのびと学生生活を送らせてあげたいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.19
コメント(10)
-

「嫌がらせしてやろうと思った」小学生2人が同級生の水筒に睡眠導入剤を混入 健康被害なし 運動会の練習中に教室に侵入し水筒持ち出し 教室の鍵紛失に気づくも校長に報告せず。
「嫌がらせしてやろうと思った」小学生2人が同級生の水筒に睡眠導入剤を混入 健康被害なし 運動会の練習中に教室に侵入し水筒持ち出し 教室の鍵紛失に気づくも校長に報告せず東京・足立区の小学校で、児童2人が同級生の水筒の飲み物に睡眠導入剤を混入していたことが分かりました。足立区教育委員会によりますと、先月26日、足立区内の小学校で、児童2人が同級生の水筒の飲み物に睡眠導入剤「メラトベル」を混入していたことが分かりました。児童2人は運動会の練習時間に教室から水筒を持ち出し、児童の1人が家から持ってきた睡眠導入剤3袋程度をトイレで混入したということです。 その様子を見た別の児童がすぐに学習支援員に報告し、水筒の中身は同級生が飲む前に処分されたため、健康被害はありませんでした。当時、教室には鍵がかけられていましたが、児童2人は鍵を持っていて、教室の中に入ることができたということです。 教員が7月に教室の鍵がなくなっていることに気づき副校長に報告していましたが、副校長は校長への報告を怠っていました。 児童2人は学校の聞き取りに対し、「(被害児童に)あまりいい感情をもってなかった。嫌がらせをしてやろうと思った」などと話しているということです。 足立区教育委員会は「児童や保護者に心配をおかけしてしまっている。1日でもはやく子どもたちの安心して通える環境を作っていく」としています。TBSテレビ【YAHOOニュース】教室に鍵を掛けてもその鍵を勝手に持ち出せてしまうとなるとあまり意味がないですね。きちんと子ども達の言動を普段から見守る態勢が必要なんでしょうね。大事に至らなくて良かったです。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.18
コメント(11)
-

韓国・障害者虐待の通報、2024年6000件超…4年連続増加、支援活動は減少。
韓国・障害者虐待の通報、2024年6000件超…4年連続増加、支援活動は減少【10月02日 KOREA WAVE】韓国で障害者虐待の通報件数が4年連続で増加し、2024年には初めて6000件を超えた。一方で、被害者への相談や支援活動は人員不足のため減少したことが分かった。 保健福祉省と中央障害者権益擁護機関が9月26日に発表した「2024年障害者虐待現況報告書」によると、2024年に全国の障害者権益擁護機関に寄せられた通報件数は6031件で、前年比9.7%(534件)増加した。2020年4208件から2021年4957件、2022年4958件、そして2024年には6031件と、この4年間増加傾向が続いている。 通報のうち虐待が疑われる事例は3033件(全体の約半数)で、前年より2.2%増加した。特に本人による通報は15.5%増、知的障害者の通報は21.1%増と、障害者自身の権利意識向上が反映された。通報者の73.7%は法的通報義務のない人で、義務者による通報の2.8倍に上った。疑い事例のうち47.8%(1449件)が「虐待」と認定された。被害者の71.1%が発達障害者で、年齢別では10代以下22.8%、20代22.6%、30代18.1%の順だった。虐待の種類は身体的虐待が33.6%で最多、次いで心理的虐待(26.5%)、経済的搾取(18.6%)が続いた。 また全体の13.0%(189件)は「再虐待」と判定され、5年前に比べて約3.9倍に増加した。18歳未満の障害児への虐待270件のうち、39.6%は親が加害者だった。 2024年、障害者権益擁護機関は虐待認定1449件に対して1万6513回の相談・支援を実施した。前年の1418件に対して1万7127回だったことと比べて減少しており、福祉省は人員不足が要因だと説明した。KOREA WAVE/AFPBB News【YAHOOニュース】2024年11月、障害者権利保障法の制定を求めて記者会見を開く光州の障害者団体深刻な問題ですね。いずれ誰でも高齢化とともに障害者になる可能性があるので、更に踏み込んで対応して欲しいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.17
コメント(10)
-

車椅子の子も、全盲の子も、知的障害の子も …障害のある子とない子とを“分けない教育”を貫く、 大阪・南桜塚小の実践とは。
車椅子の子も、全盲の子も、知的障害の子も…障害のある子とない子とを“分けない教育”を貫く、大阪・南桜塚小の実践とは障害のある子どもと、そうでない子どもを分離しない――。それを当たり前のこととしている学校があります。大阪府の豊中市立南桜塚小学校。ここでは、車椅子の子も、全盲の子も、知的障害のある子も、みんな一緒に教室で学んでいます。「分けない」教育の実践について、前校長の橋本直樹さんに聞きました。 ■支援学級の先生が、通常学級に「入り込み」──橋本さんが2024年度まで校長を務められていた豊中市立南桜塚小学校は、現在も「インクルーシブ教育の先進校」として注目されています。 全国各地から、教員や研究者の方が視察に来られていました。でも、私たちは何か特別なことをやってきたつもりはありません。「すべての子どもたちが安心して学び成長できる学校をつくろう」という、当たり前のことを続けてきただけ。それが結果的に「インクルーシブ教育」と言われるものだったのだと思います。私が南桜塚小を退職した今も、基本的なスタンスは変わっていません。 ──具体的に、どのような取り組みをされているのでしょうか。 南桜塚小には現在(2024年度当時)、さまざまな障害があって「支援学級」(特別支援学級)に在籍する子どもが48人います。けれど、支援学級の部屋はありますが、脳性まひで車椅子を使っている子も、全盲の子も、知的障害や情緒障害のある子もみんな、ほかの子どもたちと同じ通常学級の教室で机を並べ、一緒に授業に参加します。それが南桜塚小の「ともに学び、ともに育つ」教育なのです。 障害のある子は支援学級の教室で個別に学び、教科によっては通常学級に行くというふうにはしません。例え週に数時間でも「分ける」ことをしてしまうと、子どもたちは「場合によっては分けてもいいんだ」という意識を持つようになります。それが大人の社会における「排除」につながっていくのだと思うのです。 だから、南桜塚小では学校のどの部屋も、全校児童が使っていい部屋。私の机があった校長室も、教室では落ち着けない子どもが休憩しに来たり、水槽で飼っている生き物を見に来たりと、だれもが自由に出入りできる「みんなの部屋」になっていました。──通常学級の授業の進め方についても教えてください。 豊中では「入り込み」と言っていますが、通常学級の授業に支援学級の先生が入り込んで支援を行うんです。支援学級の先生は、障害のある子どもだけを見るのではありません。その子にサポートが必要な時はそばにいますが、それ以外は少し離れたところからクラス全体を見ています。 通常学級の子どもが学習に行き詰まっていたり、低学年の子どもが泣いていたりしたらわけを聞き、心が穏やかになるような対応をします。授業中子どもが教室から出ていった場合、通常学級の担任が話を聞き、授業の続きを支援学級の先生が引き継ぐ……なんていうことも。それくらい、臨機応変に対応するのです。 ■クラスメイトの「お手伝い係」はつくらない ──子どもたちから見ても「支援学級の先生」ではないんですね。 「この先生は○○さんの担当」というふうに「担当」を明確にしてしまうと、その先生と子ども、2人だけの世界になってしまって、ほかの子どもたちとの関係性が切れてしまいます。それでは、せっかく通常学級にいるのに、その中に支援学級を作ってしまうようなもの。だから、支援学級の先生であってもべったり一人につくことはせず、適度に距離を取って支援するのです。 それは、子どもたち同士の関係性も同じです。昔、障害のある子の「お手伝い係」を決めるようなことがよく行われていました。でも、それでは「係」になった子どもにとって、障害のある子との関わりは「仕事」になってしまう。同時に、周りの子どもたちは「自分は係じゃないから」と、関わることをやめてしまうのです。 自立とは、何でも自分でやることではなくて、できないことがあった時にお願いできる相手が周りにたくさんいるということ。先生でも子どもたちでも、「この人が担当」と決めてしまうのは、そのための人間関係を切ってしまうことになると思うのです。 ■安心して学び生活できる教室空間を創造 ──みんな同じ授業だと、理解が難しい子どももいるのではないでしょうか?学習の進度や進め方は、子どもによってさまざまです。教科書とは別に、授業の内容をわかりやすくまとめたプリントを使って勉強する子、一学年下の内容をおさらいしている子、授業とは違う教科のドリルに取り組む子もいます。子ども同士は長い時間を一緒に過ごす中で、互いのことをよく知っていますから、違うことをしているからといって、偏見の目で見るようなことはありません。 同じ授業を受けないのなら、同じ教室にいる意味がないのでは? と思う人もいるかもしれません。でも、別のことをしていても、そこに「その子がいる」こと、子どもたちの心がつながっていることが大事なのです。 それに、支援学級の子どもだけではなく、すべての子どもにとって教室が「安心して学べる場所」であるために、先生たちはひたすら知恵を絞っています。「教室にいると、周りの人の視線が気になって落ち着かない」という子のために、パーテーションで囲ってホッとできる空間をつくったり、「人の話し声や音が気になる」という子には、もう一つか二つ机と椅子を持ってきて、廊下側の窓を開けて授業内容が聞こえるようにし、廊下で授業を受けている姿を見ることもあります。 ■運動会は「勝ち負け」にもこだわりながら支援 ──運動会などの学校行事ではどうしているのですか。 子どもたちも一緒になってアイデアを出し合います。運動会には、障害があってみんなと同じように走れない子どもも参加しますが、「○○ちゃんがいるから、順位は関係なし」なんてことはしません。きちんと勝ち負けにもこだわりながら、参加できる形を考えていきます。 例えば、あまり歩けない子がリレーに出場する時、その子は「みんなより短い距離を、平均台につかまりながら膝で歩く」というルールがつくられたこともありました。その分、ほかの子が長い距離を走るわけです。保護者の方から「家で一生懸命練習をしていました」という話を聞きました。 ──「一緒に授業を受ける」からといって、「みんな同じことをする」のではないのですね。はい。同じ教室にいるから、みんな一斉に同じことをしなくてはいけないとか、先生の話をじっと聞いていなくてはならないとか、そういう発想そのものから抜け出したい。教室の中に、多様な学びの形を創造することで、「ともに学び、ともに育つ」を実現していきたいと考えています。〇橋本直樹(はしもと・なおき)豊中市立の中学校 3 校で 25 年間の勤務後、豊中市教育委員会人権教育企画課指導主事、小学校・夜間中学校教頭、小学校長をへて、2020 年度から 5 年間豊中市立南桜塚小学校長を務める。著書に『子どもを「分けない」学校:「ともに学び、ともに生きる」豊中のインクルーシブ教育』(教育開発研究所)。2025年学校法人あけぼの学園に入職し、2026年度開校予定の「六瀬ほしのさと小学校」(仮称)の設立準備に携わっている。AERA with Kids(Plus)[YAHOOニュース]これこそが本当のインクルーシブ教育ですね。ここまでしっかりと態勢が整うと障害の有無に関わらず、親も安心ですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.16
コメント(7)
-

米ワクチン被害補償、自閉症追加を政権が検討-制度の根幹揺らぐ恐れ。
米ワクチン被害補償、自閉症追加を政権が検討-制度の根幹揺らぐ恐れ(ブルームバーグ):トランプ米政権は、自閉症を抱える人が政府の「ワクチン健康被害補償プログラム(VICP)」で補償を受けられるようにすることを検討している。政権のアドバイザーが明らかにしたもので、実現すれば制度の根幹を揺るがしかねない。 この制度は1980年代にワクチンメーカーに対する訴訟が相次ぎ、メーカーが市場から製品を撤去して供給不足に陥ったことを受けて88年に創設された。 ワクチンメーカーを訴訟から守る一方、対象のワクチンで重い副反応を起こした人に補償金を支払う仕組みだ。創設以来、計約50億ドル(約7500億円)が支給されてきた。 ケネディ厚生長官は以前から、補償が過少で、制度を利用しにくいとVICPを批判してきた。同長官には補償対象範囲を見直す権限がある。 ワクチン健康被害訴訟が専門の弁護士でケネディ氏の顧問を務めるアンドリュー・ダウニング氏は25日、首都ワシントンで開かれたイベントで「われわれのチームがそれを検討している」とし、自閉症の「子どもたちをどう取り込むかを考えなければならない」と語った。 自閉症とワクチンの関連を主張し続けるケネディ氏は、訴訟を提起する反ワクチンの非営利団体「チルドレンズ・ヘルス・ディフェンス」の会長を務めたこともある。VICPの制度変更は、ワクチンと自閉症を結び付けようとする新たな試みとなる。 実際に変更されれば、VICPには申請が殺到して処理が滞る恐れがある。米国で自閉症の子どもの割合は31人に1人程度とされる。VICPでは通常、医療費や将来の逸失利益、慰謝料最大25万ドルが支給される。 原題:RFK Jr. Mulls Adding Autism Symptoms to Vaccine Injury List (2)(抜粋) (c)2025 Bloomberg L.P.TBS CROSS DIG with Bloomerg【YAHOOジャパン】長男もそういえば、幼児期に何かしらのワクチンを米国で受けています。こういう補償は、各方面に波紋を呼びそうですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.15
コメント(8)
-

門の鍵を自分で外し、二つ目の門は隙間をすり抜け …保育園から園児1人抜け出す。
門の鍵を自分で外し、二つ目の門は隙間をすり抜け…保育園から園児1人抜け出す東京都武蔵野市の保育園で昨年5月、園児1人が園外に抜け出す事案が発生していたことが分かった。門の施錠が不十分で、園児自身が鍵を開けたという。園児は数分後に通行人に保護され、けがはなかった。市によると、園児は昨年5月10日、他の園児と園庭で遊んでいた際、園外につながる二つの門を通って外に出た。園児は針金を使った一つ目の門の鍵を外した後、施錠されていた二つ目の門の隙間をすり抜けたという。 園児がいないことに気づいた保育士が園内を捜していたところ、通行人が園の近くで発見した。園は一つ目の門の鍵をワイヤ錠に変更した。市は市内の約50か所の保育士施設に事例を共有し、再発防止を図るという。読売新聞【YAHOOニュース】子どもは思い立ったら、如何なる隙間からでもすり抜けて仕舞いますね。今は小学校でも、塀を乗り越えて脱走しようとする児童がいます。現場を見守る目は幾つあっても足りませんね。だいぶ前のできごと、大事に至らなくて良かったです。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.14
コメント(8)
-

障害者の就労支援へ しいたけ栽培のハウス完成 山梨 中央。
障害者の就労支援へ しいたけ栽培のハウス完成 山梨 中央本格的な就労を目指す障害のある人に、農作業を通じて経験を積んでもらおうと、中央市にしいたけを栽培する農業用ハウスが完成し、関係者に披露されました。農業用ハウスは障害のある人が賃金をもらいながら訓練を積む「就労継続支援A型事業所」を運営する甲府市の企業が設置しました。・・・NHK NEWS WEB[山梨 NEWS WEB](動画あり)地道な地道を繰り返すしいたけ栽培は、何より自閉症者に適していると聞いたことがあります。良い方向に支援が進むといいですね。☄にほんブログ村にほんブログ村
2025.09.13
コメント(9)
全6201件 (6201件中 1-50件目)
-
-

- 共に成長する家族!子供と親の成長日…
- 我が家の「沈黙の戦隊」
- (2025-10-24 09:33:10)
-
-
-

- 子供服ってキリがない!
- エクオール20%オフ
- (2025-11-26 19:00:06)
-
-
-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…
- 大宮科学技術高校
- (2025-10-20 13:16:42)
-