PR
カレンダー
サイド自由欄
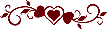

リュキア伝説・本館
☆完結しました☆
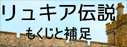

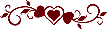

真魚子さまの絵

エメラルドeyesさんのブログ
『ねこマンサイ』
で紹介していただいた、
ふろぷしーもぷしーの過去日記
『迷い犬を保護してしまいました』2008.6.19~10.7

『いっしょに歩こう!』
2008.12~2009.1
キーワードサーチ
2024.11
2024.10
2024.08
 New!
千菊丸2151さん
New!
千菊丸2151さん小説「ゲノムと体験… マトリックスAさん
パンの日々 nako7447さん
道楽オヤジのお気楽… 車屋のオッサンさん
ゆっくりね ラブドルフィンさん
コメント新着
猫好きの美緒がたちまち身を乗り出した。
「へえ! 昇一さんが猫の子を? どんな猫? かわいかった?」
「もちろん、すっごく可愛かったさ! 全身が輝くように真っ黒で、目はきれいな青緑色。 俺、こんなきれいな生き物は見たことがないと思って、大喜びで家の中に連れて行ったら、」
ここで昇一さんは、ちょっと悔しそうに、あまりがまちに腰掛けたおじさんをちらっと睨んだ。
「いきなり親父に怒鳴りつけられちゃったんだ。 ばかやろう、ウチは食い物商売だ、そんな汚ねえもんを拾ってくるんじゃねえ、飼うのは許さねえ、って。 ・・・いやあ、悔しかったなあ」
美緒も、ぷーっと口を膨らませておじさんを睨んだ。
「そうだよ! 猫は汚くなんかないよ! きれいに洗って飼ってやればよかったのに」
おばさんが、新しいどんぶりをあたためながら口を挟んだ。
「そういうことじゃないんだよ、美緒ちゃん。 どんなにきれいにして飼っていようと、たとえここのお客さんたちの手や顔より清潔だったとしても、ようは、自分が食事しているそばに犬や猫がいるのはいやだ、って言うお客さんが少なくないってことなんだねえ。 美緒ちゃんは猫が好きだから、そういうお客さんの気持ちはわかりにくいかもしれないけど、たとえば、カエルとかクモとかだったら? もし自分の目につくところにそんなものがいたら、たとえ害がなくたって、気になって、落ち着いてご飯を食べていられないよね。 嫌いっていうのはそういうことでね、理屈じゃないんだよ。 ・・・だけどねえ、あのころはおとうちゃんも今よりもっと頑固だったし、あたしも忙しくて、昇一のそういう気持ち、よく考えてやれなかった。 納得できるようにきちんと説明してやる余裕もなくて、ただ頭ごなしに叱りつけてしまっただけ・・・昇一にはかわいそうなことしちゃったよねえ、おとうちゃん?」
相変わらず新聞に目を落としたまま、ふん、とか、へん、とか、生返事をするおじさんを、昇一さんは、今度は優しい表情で眺め、言った。
「それで、俺は二人に黙って、そこの駐車場の生垣の隅でこっそり、その黒い子猫を飼い始めたんだ。 俺の古い毛布で空き箱に寝床を作ってやって、毎日水やえさを運んでやって・・・、そのとき正樹や珠子ちゃんも手伝ってくれたから、あいつのこと覚えてたんだよな」
ラーメンを大鍋から上げ、シュッとお湯を切る昇一さんを、美緒がますます身を乗り出して見上げる。
「それで? その黒いきれいな猫ちゃんは今どこに?」











