PR
X
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(16)歴史
(47)経済
(47)政治
(45)社会
(44)哲学・思想・文学・科学
(44)サブカル・小説・映画
(43)音楽・文化
(20)スポーツ・ゲーム
(13) C58、C50 亀山機関…
 GKenさん
GKenさん
─ 灼熱 ─ HEAT1836さん
余多歩き くれどさん
tabaccosen breton005さん
ミョウの魅 stadanさん
ぶらぶらブラジル日記 Gaobrazilさん
沖縄でよんなよんな sinarsinarさん
りゅうちゃんミスト… りゅうちゃんミストラルさん
再出発日記 KUMA0504さん
 GKenさん
GKenさん─ 灼熱 ─ HEAT1836さん
余多歩き くれどさん
tabaccosen breton005さん
ミョウの魅 stadanさん
ぶらぶらブラジル日記 Gaobrazilさん
沖縄でよんなよんな sinarsinarさん
りゅうちゃんミスト… りゅうちゃんミストラルさん
再出発日記 KUMA0504さん
Comments
日本刀ファン@ Re:★ NHKはウソだ! 『その時歴史が動いた 鉄は国家なり ~技術立国 日本のあけぼの~』について (旧・建設予定地) 接触編(02/21)
とにかく歴史的古代日本で生み出された…
Nov , 2025
Oct , 2025
Sep , 2025
Aug , 2025
Jul , 2025
Oct , 2025
Sep , 2025
Aug , 2025
Jul , 2025
Jun , 2025
May , 2025
Apr , 2025
Mar , 2025
Feb , 2025
May , 2025
Apr , 2025
Mar , 2025
Feb , 2025
Freepage List
Keyword Search
▼キーワード検索
テーマ: 社会関係の書籍のレビュー(95)
カテゴリ: 政治
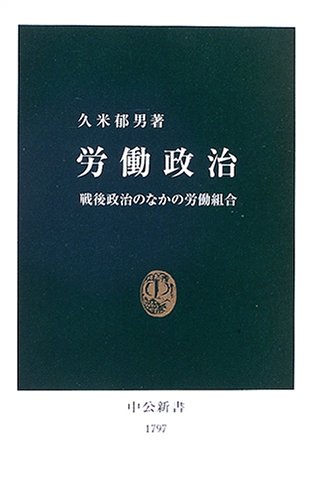
読売新聞傘下からくる、保守臭漂う「帯」に騙されてはいけない。
ほんと、こうした帯でずいぶんと損しているようにおもう。
労働組合の功罪は、政治的立場によって、左右されやすい。労働組合は、1970年代から出現した「新しい政治主義」=「大企業労使連合」から、中曽根行革を支持していた。それが、なぜ今では抵抗勢力視されているのか。それには、そもそも労働組合は、どのような形で利益を組織してきたのか、労働組合の分析の重要性がここでは宣言されています。
そのために使う道具立ても、説明が行き届いています。利益(圧力)団体は、政治学でどう位置づけられるのか。多元主義では、圧力団体の存在は、否定されない。「影響力」であろうと、「効率的政治市場」仮説をとろうと、多数の専制を防ぐことができる、柔軟なシステムだという。ただフリー・ライダーの存在ゆえに、「少数の優位」をもたらしがちな、【集合行為問題】が生じる。「特殊政治団体」という批判は、そこに集中しやすい。
「効率的な経済」と「大きな政府」は、スウェーデンなどでは両立していた。それは、労働組合が「包括的」な組織で、国民経済の生産性を高めるインセンティブがあったことが大きい。オルソンによれば、包括的集権的労働組合と社民党政権、分権的弱い労働組合と保守政権の組み合わせがよく、平等主義的な賃金体系も、民間労働組合の覇権が貫徹しているなら問題はないという。日本は、包括的な経団連の活動だけではなく、ミクロレベルで労組は「包括的」で、産業間移動とはことなった、企業内での調整がおこなわれた。労働政策も、利害調整型の経済合理的なものであった。
そうした、自民党一党政権下、拡大しつつも非政治化されていた、政策過程における労働組合の関与。それは、1990年代、政治化される。それは、グローバリズムによる経営攻勢ではなく、労働戦線統一と政界再編によるものだという。90年代、弱者保護と再分配に積極的な、官公労を中心とした労働組合の影響力がつよく、橋本行革では反対にまわったという。
そうした動きを生むことになった、「連合」成立前史も充実していてすばらしい。産業報国会を基礎に出発した、戦後労働組合。共産党・産別会議と総同盟の対立。総同盟のコーポラティズム路線の挫折。産別会議に対抗する組合民主化運動の末生まれた、総評の「左傾化」。総評からの全労会議の分離。同盟、新産別、総評、中立労連の四ナショナルセンターの成立の過程は、なかなか面白い。「春闘」の開始は、民間製造業セクター主導で、組織化されていない労働者の賃金標準化機能をになったという。1950年代、労使の「生産性連合」の確立とともに、長期低落傾向の1970年代の社会党が左翼路線を強める中ですすむ、1967年から始まる労働組合統一化の流れ。1975年、「スト権スト」の敗北は、総評左派の政治主義の衰退と、民間労組の経済主義の覇権が確立をもたらした。1989年、74単産800万人のナショナルセンター「連合」の誕生。そこでは、「統一」を急ぐあまり、労働組合主義、経済合理主義の路線の貫徹を、官民統一の際に確認できなかった。それが、「改革へ抵抗する労組」像にしているという。
いまひとつ面白くないのは、おそらく2つ理由があるとおもう。
そして、もうひとつは、鍵となっている「経済合理的」「効率的」の説明が、一言もないことであろう。
まず、立論のかなめにあたるはずの、アンケートの分析がおかしい。
本書第四章に登場した、新自由主義的諸改革に対する、労働組合を2つにわけるためにもちいられた、「政府への役割期待」の項。たしかにそこでは、官公労と民間労組は思想に違いがみられ、後者は「小さな政府」を指向していたことが、アンケート調査によって検出されている。
しかし、行政改革を支持した民間労組は、どうして中曽根行革と同じように、90年代、政府の提出する「住専処理法」「地方分権法」「産業再生法」に賛成しなければならないのだろう。これらの法案のどこに「行革」が存在しているのか?まるでわからない。 しかも、90年代における官公労と民間労組の、政府法案への態度(賛否)の差異は、アンケートからは検出されていない。都合が悪い結果がでたから、出したくなかったのだろうか。おまけに、クラスター分析では、労働組合の政府法案への賛成度があがっており、普通の利益団体化しているという。そもそも、この本の出発点となったアンケート調査の分析そのものに、評者は疑念をいだいてしまう。
さらにいえば、国民経済「全体」において、「経済合理的」「効率的」とは何なのか。そのことについての説明がまるでない。なるほど。たしかに経済を語るには、念頭においておかねばならぬ理念だ。しかし、なにが「経済合理的」「効率的」であるかを、どうやってそれぞれの「主体」が判断できるのか。そもそも、労組も、企業も、政府も、個人も、「経済合理的である施策とは何か?」をめぐって、常に争っているのではなかったか?(むろん、自己の利益をそうした美辞麗句で粉飾するわけだが)。「経済合理主義」組合運動ならば、なぜ小泉構造改革を支持しなければならないのか? これらの説明がどこにも書かれていない。
そこには、暗黙の前提に「政府は合理的」という考えがあるとしかおもえない。
それは、中曽根~小泉改革のバックボーンとなった、新自由主義的改革のスローガン=「市場は合理的」の対極にある思想ではないだろうか?
官公労以上に、筆者ご自身が「改革抵抗勢力」ではないのか?
靴(理論、結論)に合わせて足(現実、歴史)を切る。
そんな感じが、どうしてもぬぐえなかった。
1980年代と90年代の、労働組合の「改革」に対する反応の違い。それは、労組をとりまく「好不況」といった環境にこそあるようにおもえる。そういえば、2000年総選挙で「構造改革」を唱えたのは、組合を基盤とする民主党だった。しかし、ここでは何ひとつ言及がない。どうやら、「改革」という言葉さえ同じなら、中曽根とおなじ対応を橋本・小泉に与えないとダメで、民主は考慮に値しないようだ。というか、一歩間違えれば、アカデミズムを装った、ただのデッチアゲ、イカサマ、プロパガンダに堕してしまうのではないか?
評価は、その2つの分だけにしました。
いささか残念な感じがします。
評価 ★★☆
価格: ¥840 (税込)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[政治] カテゴリの最新記事
-
★ 民主党はなぜ戦わない?! 小沢代表秘… Mar 7, 2009 コメント(3)
-
★ 世界一の新聞社と主筆、読売新聞と渡辺… Nov 9, 2007 コメント(3)
-
★ 鉄道政治・社会学へのいざない 原武… Jun 13, 2007 コメント(1)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.









