PR
X
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(16)歴史
(47)経済
(47)政治
(45)社会
(44)哲学・思想・文学・科学
(44)サブカル・小説・映画
(43)音楽・文化
(20)スポーツ・ゲーム
(13) C58、C50 亀山機関…
 GKenさん
GKenさん
─ 灼熱 ─ HEAT1836さん
余多歩き くれどさん
tabaccosen breton005さん
ミョウの魅 stadanさん
ぶらぶらブラジル日記 Gaobrazilさん
沖縄でよんなよんな sinarsinarさん
りゅうちゃんミスト… りゅうちゃんミストラルさん
再出発日記 KUMA0504さん
 GKenさん
GKenさん─ 灼熱 ─ HEAT1836さん
余多歩き くれどさん
tabaccosen breton005さん
ミョウの魅 stadanさん
ぶらぶらブラジル日記 Gaobrazilさん
沖縄でよんなよんな sinarsinarさん
りゅうちゃんミスト… りゅうちゃんミストラルさん
再出発日記 KUMA0504さん
Comments
日本刀ファン@ Re:★ NHKはウソだ! 『その時歴史が動いた 鉄は国家なり ~技術立国 日本のあけぼの~』について (旧・建設予定地) 接触編(02/21)
とにかく歴史的古代日本で生み出された…
Nov , 2025
Oct , 2025
Sep , 2025
Aug , 2025
Jul , 2025
Oct , 2025
Sep , 2025
Aug , 2025
Jul , 2025
Jun , 2025
May , 2025
Apr , 2025
Mar , 2025
Feb , 2025
May , 2025
Apr , 2025
Mar , 2025
Feb , 2025
Freepage List
Keyword Search
▼キーワード検索
テーマ: 歴史分野の書籍のレビュー(111)
カテゴリ: 歴史
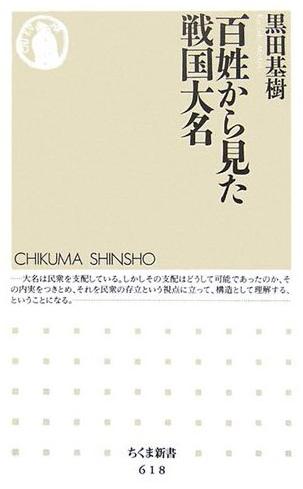
▼ こんな刺激的な書物が、新書という体裁をとって、700円強で手に入る時代になったとは、ホント、幸せな世の中になったもんだ、というしかない。 皆の衆。 ひとまず、本屋に走れ。
▼ 大河ドラマでは、今放映されている「巧妙が辻」を初めとして、一般に人気が高い、戦国時代。 そんな時代、民衆と戦国大名とは、どのような関係にあったのか。 この本は、赤裸々に解明して余すところがない。
▼ とかく、戦国大名は、社会、とりわけ「ムラ」に依存していた。 北条氏康の隠居、武田晴信(信玄)のクーデターは、飢饉時の「世直し」 とした行われたものらしい。 飢饉に深く彩られ、政治に陰を落としていた 戦国時代は、江戸時代後半の大飢饉の時代と同様、端境期に死亡率が急騰するのが恒常化していた時代 だった。 他国に侵攻しての 「刈田狼藉」による略奪は、生存のための、国内飢饉対策として必要 だったという。 その戦争には、大名と家臣団のみならず、食いつめた村人が、略奪目当てで、足軽として参加していた。
▼ そんな社会のベースになったものこそ、畿内では13世紀後半、全国的には15世紀までに形成された、「惣村」「惣庄」にほかならない。 メンバーシップ(構成員)を認定して、「政治団体」として「法人格」をもち、「警察権」「徴税権」「立法権」まで掌握し、独自の武力を保有しては公権力を振るう「ムラ」の創成。 それは、階級差・身分差を持ちながらも、飢饉を背景として生存のため、鎮守や村寺を結集の核として、用役確保のため結成された、構成員の「寄り合い」で運営される組織 であるという。 ムラ同士、用役をめぐって「合戦」「訴訟」を展開。それがムラの領主同士の戦争にまで発展していく。 否、 ムラこそ領主を作り出していく存在 なのだ、という指摘には驚くほかはない。
避難場所の整備ため、ムラの提供していた「城普請役」が、やがて土木工事、特に「治水工事」に転用 されていく。 大名・国衆は、ムラを維持するために年貢減免を行わなければならない。 また ムラは、領主による平和・安穏の対価として、年貢・公事を「ムラ請」 でにない、減免をエサに百姓を招聘して農業をおこなう。
▼ また、戦国大名・国衆の 家中(家臣団)は、個別領主層が自力救済を放棄して、裁定権を唯一の主家に委ねていくことによって誕生 してゆく。 そこでは、ムラ同士の対決が、領主同士の対決に発展していくことを断固禁止された。大名・国衆は、小代官の任免などを通して、年貢・公事徴収権にまで容喙、ムラとのルートを開く。 このとき、領主・小代官でもない、ムラの徴税担当者が、役人であると同時にムラ代表者という、「村役人」制度が形成されていく。 減税・「徳政」を通して、大名権力を確立していく。
▼ 「ムラ」同士の紛争も、北条氏統治下の「目安(訴状)制」の全面展開によって、「家人(中)」を飛び越した 直接訴訟権が認められ、「万人に開かれた裁判制度」の創出 されてゆく。 中世までの裁判とは、大名や御家人、公家や寺社といった、権力関係者間の利害調停にすぎず、ムラが訴訟しようとすれば、自分の領主を通じて、莫大な礼物を関係機関に渡さなければならない。 戦国大名下では、領主との伝統的な相論方法で、実力行使の一つであった「逃散」も、「自力救済」ということで禁止。 「首謀者一人を斬首」は、百姓一揆の処罰法にも転用 されていったという。 また宿場町においても、「実力行使」が禁止され、相論が起きた際にも、大名が裁判権を行使する、「楽市」―――大名自らが平和(楽)を保障―――の制度が始まるのだという。この頂点において、大名間の「実力行使」を禁止して裁判を待つよう求めるものこそ、羽柴秀吉の「惣無事令」のほかならない。
▼ 実は、信長・秀吉の領国の年貢収取体系は、まったく分かっていないという。 むしろ、北条家研究によって、 戦国大名こそ、近代国民国家の出発点 になっていることが、様々な方面から、明らかにされて面白い。 村高は、イコール耕地面積ではない。 領主とのギリギリの政治交渉によって決まるらしい。 また、永禄3年頃の大飢饉をきっかけに、税金は「銅銭」から「米」―――現物給付に一大転換をとげる。 その反面、ムラ同士の「実力行使」は近世でも続く。 なによりも驚かされるのは、北条統治下では、税金増額の論理として、「御国のため」が使われた―――「御国概念」の出現―――ことにあるかもしれない。 近代国民国家の時代、国民を戦争に動員するため、日本で使われた単語 「御国」は、北条統治下で出現した、家臣団・奉公人以外の村人に対して、貢献を呼びかけるもの だったのだ。
▼ ただ行論上、惜しまれるのは、「惣村」の成立は、15世紀までであって、戦国時代と重なっていないことの説明が、尽くされていないことであろうか。 「惣村」を基盤として、戦国大名が析出されたのは、あらかた理解できる。 しかしそうして成立した戦国大名は、「惣村」をどのように変容させていったのか。 当然の疑念であるだろうに、あまり触れられていない 。ただ、「惣村」が無批判に、現代の「ムラ社会」の原型として、超歴史的に説明するだけで終わってしまっていないか。 歴史でありながら、「惣村」と大名権力が―――他にもいろいろあるけれど―――ノッペラボウな同質なものとして扱われ、非歴史的な説明になっている嫌いが見え隠れする。
評価 ★★★★
価格: ¥ 735 (税込)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[歴史] カテゴリの最新記事
-
★ NHK特集「振武寮」、特攻隊の憂… Oct 21, 2007 コメント(3)
-
★ 靖国右翼は、自分が卑怯者の子孫であ… Aug 16, 2007 コメント(1)
-
★ 原田 敬一 『日清・日露戦争』 岩波… Apr 27, 2007 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.









