PR
X
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(16)歴史
(47)経済
(47)政治
(45)社会
(44)哲学・思想・文学・科学
(44)サブカル・小説・映画
(43)音楽・文化
(20)スポーツ・ゲーム
(13) C58、C50 亀山機関…
 GKenさん
GKenさん
─ 灼熱 ─ HEAT1836さん
余多歩き くれどさん
tabaccosen breton005さん
ミョウの魅 stadanさん
ぶらぶらブラジル日記 Gaobrazilさん
沖縄でよんなよんな sinarsinarさん
りゅうちゃんミスト… りゅうちゃんミストラルさん
再出発日記 KUMA0504さん
 GKenさん
GKenさん─ 灼熱 ─ HEAT1836さん
余多歩き くれどさん
tabaccosen breton005さん
ミョウの魅 stadanさん
ぶらぶらブラジル日記 Gaobrazilさん
沖縄でよんなよんな sinarsinarさん
りゅうちゃんミスト… りゅうちゃんミストラルさん
再出発日記 KUMA0504さん
Comments
日本刀ファン@ Re:★ NHKはウソだ! 『その時歴史が動いた 鉄は国家なり ~技術立国 日本のあけぼの~』について (旧・建設予定地) 接触編(02/21)
とにかく歴史的古代日本で生み出された…
Nov , 2025
Oct , 2025
Sep , 2025
Aug , 2025
Jul , 2025
Oct , 2025
Sep , 2025
Aug , 2025
Jul , 2025
Jun , 2025
May , 2025
Apr , 2025
Mar , 2025
Feb , 2025
May , 2025
Apr , 2025
Mar , 2025
Feb , 2025
Freepage List
Keyword Search
▼キーワード検索
テーマ: ヨーロッパ旅行(4301)
カテゴリ: 経済
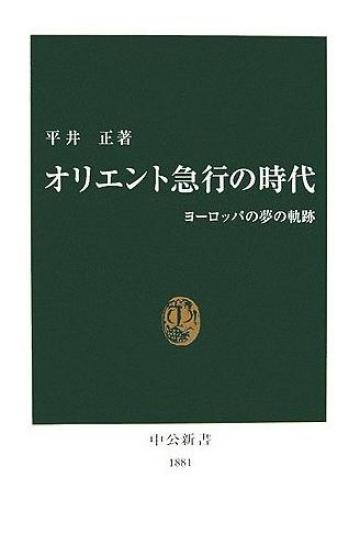
▼ ヨーロッパ鉄道旅行を通した素晴らしい歴史物語の書である。 ゴールデンウィークのご旅行の際、伴侶とされてはいかがだろうか。
▼ 1883年10月4日、開業したオリエント急行。 弱小国ベルギーの若者、ナゲルマケールスは、「国際寝台車会社」を創設して、細切れ状態にある鉄道会社と個別交渉の末、運行させたもの。 オリエント急行は、ヨーロッパで例のない、画期的な、豪華列車で国際列車だったらしい。 個人主義ヨーロッパにふさわしい、「コンパートメント(個室寝台)」というものを発明したのも、実はオリエント急行だという。 「へー」ではないか。
▼ なによりも、「19世紀ヨーロッパ」の薫りがただよっているのが喜ばしい。
▼ オーストリア・ハンガリー帝国
かの国の鉄道を作ったのは、当初、ロスチャイルド家だったという。 「エルサレム王」なる称号までもつ皇帝、フランツ・ヨーゼフ2世以外、時間をまもるものはいない都市、ウィーン。 オスマントルコが廃棄していったコーヒー豆の袋から始まる、コーヒーハウスの喧噪。 オスマン軍楽隊から始まるクラシック音楽。 ドイツ色の強い王城ブダと、マジャール色の強い商都ペスト。 ハンガリーは、ルーマニアに次いでロマ族が多く、ジプシー音楽がハンガリー情緒とされていた。 オーストリアから独立を企てたコシュート・ラヨシュの墓参にわざわざ出かけた、日本史研究者・黒板勝美の逸話も面白い。 ハンガリー平原は、大地主支配の水不足に苦しむ褐色の平原 だったようだ。
▼ ルーマニア王国
オリエント急行開通直前、1881年に王制に移行したばかりの国家だったという。 もともとオスマン時代は、自治が認められていたので、黒海沿岸のドブルジャを除けば、あまりトルコ人がいなかった。 むしろ、 ファナリオットと呼ばれたコンスタンチノープルのギリシャ人商人が経済を支配 していたらしい。 そんな中、1859年、モルダヴィアとワラキアは、クザ公をいだき、同君連合として出発。 1861年、ルーマニア公国が誕生する。 急進的改革は、貴族層の反発を買い、66年、大公追放。 プロイセン王家から王様を連れてきて、ルーマニア語を話せない王様が、君臨していたのだとか。
ブルガリア
1883年、オリエント急行開通時には、「公国」としてオスマン朝主権の下、独立したばかり(露土戦争 1878年)だったらしい。 ブルガリア大公の息子は、「鉄っちゃん」趣味が昂じて、領土通過中は、オリエント急行の機関士として、急制動をかけまくり、列車をオモチャにしていたという。 ブルガリアは、ルーマニア同様、オスマン時代、ギリシャ人が牛耳っていた。 そのため、ブルガリア正教会を樹立することで、知識人達は精神的独立を図ったとされる。 本来、 西欧近代の創作物にすぎない「古代ギリシャ・イデオロギー」に感染しローマの後裔から「ギリシャ人の末裔」と思いこみ始め独立運動をおこすギリシャ人の姿 は、喜劇といってよいだろう。 バルカン半島を悩ますナショナリズムは、ギリシャから始まったのだから。
▼ オスマン・トルコ
驚くなかれ。 開業時、イスタンブールまで列車は走っていなかった。 1888年までは、いったん、ブルガリアの港町ヴァルナに出て、そこから船でイスタンブールに行ったという。 イスタンブールは、オリエントの典型的都市ではない。 むしろ、ギリシャ人や西欧人のつどう、国際都市だった。 かつては、巨大な大帝国として、居住制限があるものの通商の自由が認められる、「キャピチュレーション勅令」で片務的特権を欧米人たちに与えたら、いつのまにやら主客逆転。 フランス人たちはイスタンブールのペラ大通りを闊歩。 フランスで印刷された、不正確なコーランが流布して問題になったこともあったという。 アブデュルハミトの専制政治ぶりがエリア・カザンの映画『アメリカ!アメリカ!』に描かれているとは、まったく知らなかった。 人種・民族ではなく、宗教を社会統合の道具としていたオスマン朝 の姿は、非常に面白い。
▼ 第1次大戦後になると、ヨーロッパは一変してしまう。 もはや王侯貴族はどこにもいない。 一般化したオリエント急行。 豪華サロンカーは過去のもの。 第1次大戦休戦協定調印の舞台は、オリエント急行を運行させていたワゴン・リー社の2419号客車であり、ヒトラーはこの屈辱を決して忘れなかった。 1940年、フランス征服の際、同じ車両で降伏文書署名をさせた挙句、連合国反攻の際、降伏文書調印車両として再々使用されることがないように、1944年、命令で破壊してしまったという。 第2次大戦後は、社会主義国の鉄のカーテンによって、検問の連続。 豪華な食事も提供できず、豪華列車としてのオリエント急行は1962年、定時列車としての「オリエント急行」は1977年に運休してしまう。 最晩年期は「難民列車」 だったというから、悲しさもひとしおである。
▼ 西欧にとっては、エキゾチックな異国情緒をかきたてるオリエント急行も、オリエント側にあたる東欧にとっては、文明を運んでくる列車だった。 オリエント急行開業前までの汽車旅というものは、食堂車がなく、駅に長時間停車して、レストランに入って食事を取っていた らしい。 また「最後の授業」で知られるエルザス・ロートリンゲンは、ドイツ唯一の「帝国国有鉄道」が走っていたものの、ドイツに同化されることなく、第一次世界大戦を迎えたというのも、初めて聞く話である(たいてい、元々ドイツ語圏としか説明されないことが多い)。 ドイツでは、王国固有の鉄道会社が走り、ビスマルクは帝国国有化に失敗。 プロイセンとバイエルンの機関車速度競争は、子供じみていてなかなか楽しかった。 ルーマニアでは、ロマ族は1851年まで奴隷扱いされていたらしい。 ウィーンから先になると、オリエント急行でも、なかなか定時運行ができなかった という。
▼ 逸話もふんだんに盛りこまれてたいへん興味深い。 オリエント急行開通時、その乗客は、ルーマニア王カロル1世の離宮に招待され、オスマン皇帝アブデュル・ハミトにまで謁見したという。 靴の先に接吻させるローマ法王と同様、オスマン皇帝は、接見時、ひれ伏させて衣服の裾に接吻させていたらしい。 森鴎外は、日本人として最初期の乗客の1人でありながら、劃期性をまるで理解していなかったらしい。 「列車の王者」たるオリエント急行を利用しないことには、王のステータスを保てないとばかりに、東欧の国王たちも利用すれば、あの伝説の女スパイ、マタ・ハリも利用していたという。 インドのマハラジャたちも利用して、異国趣味に花をそえる。 なお、開通当初は、手荷物車両を2両も連結していたという。 女性の荷物の多さは、日本に限ったことではない。
ナゲルマケールスは、オリエント急行をシベリアをこえて東京まで延伸させたかったらしいのだ 。 なんとも、残念な話ではないか。
▼ むろん、「オリエント急行」は、政治とも密接にかかわり、むしろ政治そのものになることもマレではない。 19世紀、鉄道は、支配を維持するため積極的に建設された………チベット・ラサへ向けた中国の鉄道建設を知る人たちにとってはおなじみの図式だろう。 「列車の王者」オリエント急行の運行をめぐって、対立しあう東中欧各国。 最初は、パリ~ウィーン~イスタンブールだったが、シンプロン・オリエント急行(ミラノ・ベオグラード経由)が登場。 第1次大戦後になると、オリエント急行が百花繚乱。 ロンドン~アテネなど様々なオリエント急行が毎週走っていたらしい。 ドイツは、フランスのオリエント支配を象徴するオリエント急行に我慢ならず、バグダット鉄道を建設し、「バルカン列車」なるものを第一次大戦中走らせた ものの、敗戦で水の泡。
▼ 1988年、日本全国をまわって、今では箱根に鎮座する、「オリエント急行」の客車。 日本だけではない。 今では、タイ~シンガポール、アメリカ、メキシコでは、「オリエント急行」の名を冠する列車が走っている という。 「命がけの通商」から、お気楽なツーリズムへの転換こそ、「オリエンタリズム」「異国趣味」を支えていた。 オリエント急行のみが喚起させる「異国情緒」「未知の世界への憧憬」こそ、『ラインゴルト』『ゴールデンアロー』など、他の単なる豪華列車とはちがい、オリエント急行を「ツーリズムのシンボル」「最高級豪華サービスを提供する不滅のブランド」にさせた原因
▼ ただ、難点をいえば、これは誰に向けて書かれたのか、いまいち分かりかねることだろうか。 「オリエント急行史」「東欧社会史」「ツーリズムの発生史」としてなら、浅いとしか言いようがない。 観光ガイドなら逆に濃くて使えない。 どっちにしろ、散漫な印象をいだいてしまう。 日本人のアジア認識につきまといがちな「知の支配の一形態」=オリエンタリズムを糾弾するならともかく、ヨーロッパ人のアジア認識(=オリエンタリズム)について、日本語で批判的記述をすることに、何か意味があるのだろうか。 旅行先で突っ慳貪な対応を受けた場合、東アジア・東南アジア旅行なら激怒する日本人も、ヨーロッパ~イスラム旅行ぐらいだと、「これが外国旅行というものね」と、借りてきた猫のように大人しい。 元から理解できないイスラムや、精神的に隷属している欧米には、ヘイコラする日本人。 他人のことより、自分のこと、だと思うんだけどね。 オリエンタリズムの解説は、まったくされていないので、「ヨーロッパ人悪い、日本人はやっぱり素晴らしいのだな」と誤解されちゃうんじゃないか?
▼ しかし、ヨーロッパ臭が好きな人にはたまらない一品でしょう。 だいたい、日本人の好きなヨーロッパって、大方、19世紀でしょうしね。
▼ という訳でお薦めしておきます。
評価: ★★★☆
価格: ¥ 903 (税込)
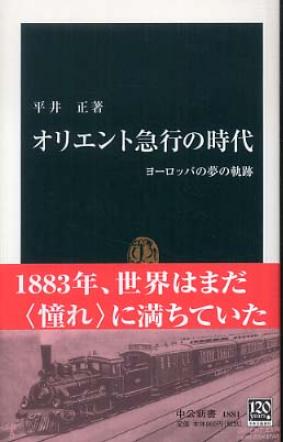
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[経済] カテゴリの最新記事
-
★ 祝! 武藤日銀総裁人事否決!!! Mar 12, 2008 コメント(1)
-
★ 大活躍する非営利組織 藤井良広 『… Sep 18, 2007 コメント(1)
-
★ 「一大敵国」大阪朝日新聞社はどうし… Aug 29, 2007
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.









