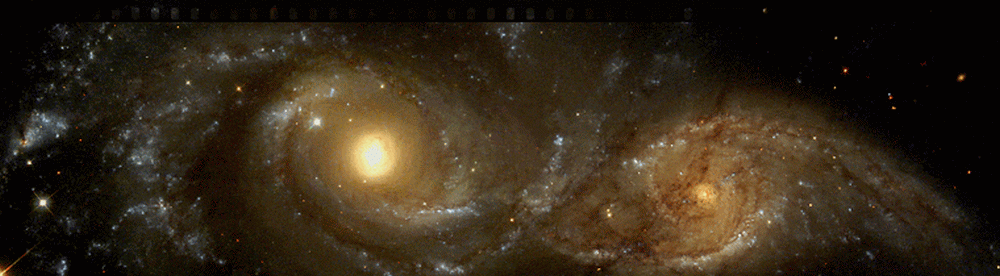PR
X
Free Space
《自己紹介》
佐藤直幹(さとうなおみき)と申します。令和二六年で満58歳になります。丙午です。現在、フランスのパリ近郊在住で、翻訳を中心に仕事をしています。
メールアドレス:nsato75@yahoo.fr
X(旧Twitter)のアカウント:https://x.com/NaomikiSato
インスタグラム:
https://www.instagram.com/satonaomiki/profilecard/?igsh=MXRycTEzMmYzYTJieA==
進化する自己記憶の存在論という、テーマに取り組んでいます。言語の本質を追い求めているうちに、人間とは何か、認知とは何か、生命とは何か、太陽系とは何か、時空間とは何か、物質とは何かという問いが生まれ、これらの根底に流れているが「自己記憶」という概念だと気がつきました。
ただ。ここでいう「自己記憶」の概念は、端的に言うと私の造語で、我々の知っている「記憶」をカバーしてますが、全く新しい概念で「すべての存在を生み出し、支え、進化させる」ものです。
進化する自己記憶の存在論は、今の科学の枠組みとは全く違うものになりますが、今の人類の知識を、新しい枠組みで捉え直すというプロセスと考えれば、矛盾は無いと思います。一言で言うと「科学のパラダイムシフト」を起こしたい訳です。
今は、ソシュールの記号学を「進化する自己記憶の存在論」という枠の中で再構築することを課題としています。ソシュールの「一般言語学講義」を再読しながら、記号学を新たなレベルに引き上げることを目標としています。
日本の大学では経済学を専攻しました。卒業後、金属素材メーカーに就職しましたが4年後の1995年に退職、直後にフランスに渡航し、言語学の勉強を始め今に至ります。一応フランスで修士と同等の免状(DEA)を取得していますが、博士論文は途中で断念しました。
高校三年のときにアメリカのイリノイ州に1年間のホームステイ留学、大学3年に上がる前に、韓国に一年間、語学留学していました。最近は大分忘れましたが、フランス手話もフランスで勉強し、私の言語理論の重要な支えになっています。
始めはフランス語で発信しようと思いましたが、フランス語の語彙の概念を借用しながら、日本語で書く事にしました。あまりネガティブなコメントにはおつきあい出来ないと思いますが、興味があれば読者の方々と色々とディスカッション出来ればと思います。
「日本人の為のフランス語自習室」というブログもあります。最近は更新していませんが、フランス語に興味の有る方は是非どうぞ。
http://francais75.exblog.jp/
趣味は折紙ですが,最近は半分プロとしてやっています。
折紙のバラが専門です。ここに作品を発表しています。ミクシーでは、もっと多くの作品を公開しています。ハンドルネームは「Mikki」
http://pliagedepapier.com/gallery/index.php?cat=11645
最近はインスタグラムの方を主に使っています:
https://www.instagram.com/satonaomiki/profilecard/?igsh=MXRycTEzMmYzYTJieA==
2015年8月に、「バラの折り紙 ROSE」という本が出版されました。
http://www.amazon.co.jp/バラの折り紙-1枚の紙から作る-佐藤直幹/dp/452905466
2018年1月27日に「美しいバラの折り紙」という本が出版されます。
https://www.amazon.co.jp/%E7%BE%8E%E3%81%97%E3%81%84%E3%83%90%E3%83%A9%E3%81%AE%E6%8A%98%E3%82%8A%E7%B4%99-%E4%BD%90%E8%97%A4%E7%9B%B4%E5%B9%B9/dp/4529057674/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1516427564&sr=1-1&keywords=%E4%BD%90%E8%97%A4%E7%9B%B4%E5%B9%B9
2019年9月24日にアメリカのTuttle社から「美しいバラの折り紙」の英語版「Naomiki Sato's Origami Roses, create lifelike roses and other blossoms」が出版されます。
https://www.tuttlepublishing.com/other/naomiki-satos-origami-roses
Copyright (C) 2009-2025 Naomiki Sato All Rights Reserved
佐藤直幹(さとうなおみき)と申します。令和二六年で満58歳になります。丙午です。現在、フランスのパリ近郊在住で、翻訳を中心に仕事をしています。
メールアドレス:nsato75@yahoo.fr
X(旧Twitter)のアカウント:https://x.com/NaomikiSato
インスタグラム:
https://www.instagram.com/satonaomiki/profilecard/?igsh=MXRycTEzMmYzYTJieA==
進化する自己記憶の存在論という、テーマに取り組んでいます。言語の本質を追い求めているうちに、人間とは何か、認知とは何か、生命とは何か、太陽系とは何か、時空間とは何か、物質とは何かという問いが生まれ、これらの根底に流れているが「自己記憶」という概念だと気がつきました。
ただ。ここでいう「自己記憶」の概念は、端的に言うと私の造語で、我々の知っている「記憶」をカバーしてますが、全く新しい概念で「すべての存在を生み出し、支え、進化させる」ものです。
進化する自己記憶の存在論は、今の科学の枠組みとは全く違うものになりますが、今の人類の知識を、新しい枠組みで捉え直すというプロセスと考えれば、矛盾は無いと思います。一言で言うと「科学のパラダイムシフト」を起こしたい訳です。
今は、ソシュールの記号学を「進化する自己記憶の存在論」という枠の中で再構築することを課題としています。ソシュールの「一般言語学講義」を再読しながら、記号学を新たなレベルに引き上げることを目標としています。
日本の大学では経済学を専攻しました。卒業後、金属素材メーカーに就職しましたが4年後の1995年に退職、直後にフランスに渡航し、言語学の勉強を始め今に至ります。一応フランスで修士と同等の免状(DEA)を取得していますが、博士論文は途中で断念しました。
高校三年のときにアメリカのイリノイ州に1年間のホームステイ留学、大学3年に上がる前に、韓国に一年間、語学留学していました。最近は大分忘れましたが、フランス手話もフランスで勉強し、私の言語理論の重要な支えになっています。
始めはフランス語で発信しようと思いましたが、フランス語の語彙の概念を借用しながら、日本語で書く事にしました。あまりネガティブなコメントにはおつきあい出来ないと思いますが、興味があれば読者の方々と色々とディスカッション出来ればと思います。
「日本人の為のフランス語自習室」というブログもあります。最近は更新していませんが、フランス語に興味の有る方は是非どうぞ。
http://francais75.exblog.jp/
趣味は折紙ですが,最近は半分プロとしてやっています。
折紙のバラが専門です。ここに作品を発表しています。ミクシーでは、もっと多くの作品を公開しています。ハンドルネームは「Mikki」
http://pliagedepapier.com/gallery/index.php?cat=11645
最近はインスタグラムの方を主に使っています:
https://www.instagram.com/satonaomiki/profilecard/?igsh=MXRycTEzMmYzYTJieA==
2015年8月に、「バラの折り紙 ROSE」という本が出版されました。
http://www.amazon.co.jp/バラの折り紙-1枚の紙から作る-佐藤直幹/dp/452905466
2018年1月27日に「美しいバラの折り紙」という本が出版されます。
https://www.amazon.co.jp/%E7%BE%8E%E3%81%97%E3%81%84%E3%83%90%E3%83%A9%E3%81%AE%E6%8A%98%E3%82%8A%E7%B4%99-%E4%BD%90%E8%97%A4%E7%9B%B4%E5%B9%B9/dp/4529057674/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1516427564&sr=1-1&keywords=%E4%BD%90%E8%97%A4%E7%9B%B4%E5%B9%B9
2019年9月24日にアメリカのTuttle社から「美しいバラの折り紙」の英語版「Naomiki Sato's Origami Roses, create lifelike roses and other blossoms」が出版されます。
https://www.tuttlepublishing.com/other/naomiki-satos-origami-roses
Copyright (C) 2009-2025 Naomiki Sato All Rights Reserved
Category
カテゴリ未分類
(542)「ともちゃん」さんのコメントへの返事
(155)新ソシュール記号学
(1753)イタリア語の研究
(184)Panpsychism(汎心論)
(2)記憶言語学について
(10)言語の起源
(14)個体性理論
(39)知性(インテリジェンス)
(13)手話
(40)言語学
(38)離散性 discret
(19)コミュニケーション
(2)差異
(7)二重分節 Double articulation
(2)線形性 linearite
(3)恣意性 arbitraire
(3)チョムスキーの評価
(10)記憶の進化
(143)シーニュ(記号論)
(13)音韻論
(4)夢と言語学
(4)二極性
(2)記憶言語学
(830)記憶宇宙論と記憶言語学に関するフェイクインタビュー
(10)価値、価値のシステム
(3)ピダハン
(2)離散化原理
(10)アイデンティティー
(41)記憶科学
(743)フラクタル
(1)個人の記憶、集団の記憶
(54)サイクル
(6)離散性理論
(45)西田幾多郎
(3)日本哲学vs西洋哲学
(2)離散化ループ
(18)離散差位
(14)日本のアイデンティティー
(60)自己同一性
(18)離散系
(4)意識
(19)未来の記憶
(2)宇宙離散化論
(3)二人称の言語学
(7)言霊
(2)離散融合更新循環
(24)相似相違体
(3)リアルタイム言語学
(4)Calendar
Keyword Search
▼キーワード検索
まだ登録されていません
Comments
Freepage List
カテゴリ: 記憶言語学
一つ前の投稿の ChatGPT による英訳:
Recently, I often hear discussions about the “technical limits of AI” or the “collapse of the AI investment bubble.”
However, in real society, the practical use of AI continues to advance rapidly and shows no sign of slowing down.
I believe that the language model currently used by AI differs fundamentally from the one we humans actually use, and for that reason, I think the current boom will eventually come to an end.
The limitation of today’s AI language models lies in the fact that they are based on machine learning, which merely simulates the memory recall and response mechanisms of human cognition.
No matter how much the speed and accuracy of machine learning improve, I do not believe a singularity will ever occur.
Humanity has not yet truly understood the essence of language.
Language was the first cognitive tool acquired by humankind.
Before that, however, as small individual beings born merely as cognitive entities—infants—humans undergo a process of discretization within the chaos of unconscious cognitive memory, transforming them into beings capable of building civilization.
The main reason for this inability lies in Western philosophy.
In Western thought, the subjective, first-person perspective is the default and unshakable standpoint.
If you watch any lecture or video on “consciousness,” you will always encounter the same schema:
Consciousness = subjective experience / reality.
The greatest failure of Western philosophy and Western-based linguistics is that they never developed a discussion about the origin of the three grammatical persons—a structure that is fundamentally nested in nature.
Even though grammatical person distinctions are a common phenomenon across Western languages, their deep significance was completely overlooked.
In contrast, Japanese lacks explicit grammatical distinctions of person, yet without an internally structured triadic framework—(1st / 2nd) nested within 3rd person—it becomes impossible to determine “who is doing what to whom.”
Without this, no shared context can exist.
And without shared context, language cannot function as a tool of communication at all.
However, Western linguistics, grounded in the philosophy of subjectivity, has adopted the premise that “language is a tool for communication” without ever questioning the origin of the three grammatical persons.
I see this as a fundamental problem.
Moreover, I contend that the triadic structure of grammatical persons—tangible and intangible, nested within one another—is itself the true universal grammar.
This nested structure of the three persons functions as a mechanism that transforms Saussure’s signified (concept) into a shared contextual meaning among speakers.
Saussure, in his theory of linguistic value, stopped his inquiry at the level of the signified, that is, the conceptual side of meaning, leaving the matter unresolved beyond that point.
Chomsky noticed this gap, but his attempt to resolve it through syntactic rules (syntax)—the order of words—was, in my view, a failure.
While I support Chomsky’s idea of universal grammar, I oppose his belief that universal grammatical knowledge is innate or genetically embedded within the human species.
Recently, I often hear discussions about the “technical limits of AI” or the “collapse of the AI investment bubble.”
However, in real society, the practical use of AI continues to advance rapidly and shows no sign of slowing down.
I believe that the language model currently used by AI differs fundamentally from the one we humans actually use, and for that reason, I think the current boom will eventually come to an end.
The limitation of today’s AI language models lies in the fact that they are based on machine learning, which merely simulates the memory recall and response mechanisms of human cognition.
No matter how much the speed and accuracy of machine learning improve, I do not believe a singularity will ever occur.
Humanity has not yet truly understood the essence of language.
Language was the first cognitive tool acquired by humankind.
Before that, however, as small individual beings born merely as cognitive entities—infants—humans undergo a process of discretization within the chaos of unconscious cognitive memory, transforming them into beings capable of building civilization.
The main reason for this inability lies in Western philosophy.
In Western thought, the subjective, first-person perspective is the default and unshakable standpoint.
If you watch any lecture or video on “consciousness,” you will always encounter the same schema:
Consciousness = subjective experience / reality.
The greatest failure of Western philosophy and Western-based linguistics is that they never developed a discussion about the origin of the three grammatical persons—a structure that is fundamentally nested in nature.
Even though grammatical person distinctions are a common phenomenon across Western languages, their deep significance was completely overlooked.
In contrast, Japanese lacks explicit grammatical distinctions of person, yet without an internally structured triadic framework—(1st / 2nd) nested within 3rd person—it becomes impossible to determine “who is doing what to whom.”
Without this, no shared context can exist.
And without shared context, language cannot function as a tool of communication at all.
However, Western linguistics, grounded in the philosophy of subjectivity, has adopted the premise that “language is a tool for communication” without ever questioning the origin of the three grammatical persons.
I see this as a fundamental problem.
Moreover, I contend that the triadic structure of grammatical persons—tangible and intangible, nested within one another—is itself the true universal grammar.
This nested structure of the three persons functions as a mechanism that transforms Saussure’s signified (concept) into a shared contextual meaning among speakers.
Saussure, in his theory of linguistic value, stopped his inquiry at the level of the signified, that is, the conceptual side of meaning, leaving the matter unresolved beyond that point.
Chomsky noticed this gap, but his attempt to resolve it through syntactic rules (syntax)—the order of words—was, in my view, a failure.
While I support Chomsky’s idea of universal grammar, I oppose his belief that universal grammatical knowledge is innate or genetically embedded within the human species.
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[記憶言語学] カテゴリの最新記事
-
Closer To Truth:Jonathan Schooler - Wh… 2025.11.24
-
私の新しいライフワーク:ソシュールの一… 2025.11.24
-
「言語には、正の項が無く、差異しか無い… 2025.11.23
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.