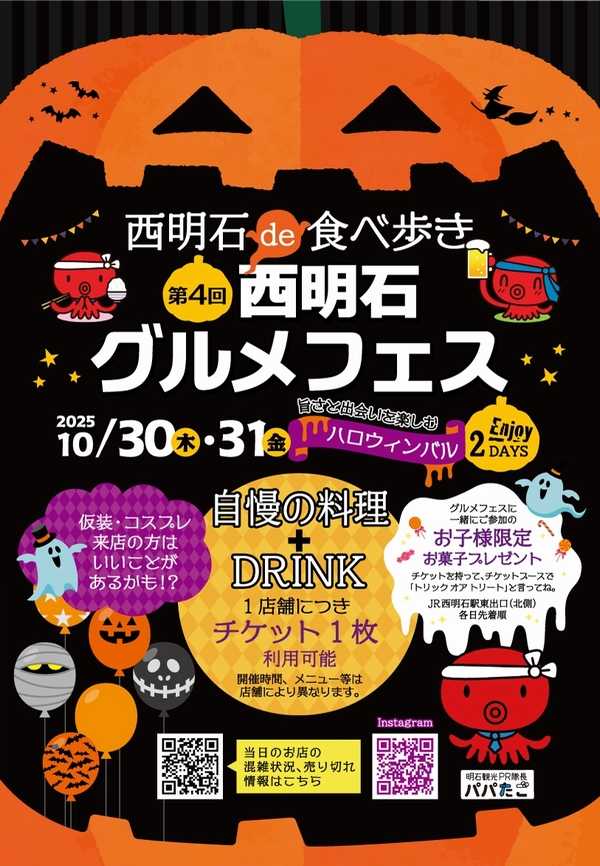○出汁の取り方
出汁の取り方
| 昆布だし >>取り方 |
|---|
| 肉など動物性の素材を使わない精進料理によく使われます。動物性の素材を使わない精進料理に昆布は使用を許されているという理由だけであり、動物性の素材と合わないということではありません。むしろ動物性の素材と相性がいいと言えます。しんじょを伸ばす時にも使われます。
|
| かつおだし >>取り方 |
|---|
| 昆布を使わないので安価にできるため、お味噌汁など、ご家庭での毎日の食事に重宝。おひたしにもいいです。
|
| 一番だし(淡麗) >>取り方 |
|---|
| 和食において絶対不可欠な出汁。これを覚えるだけで出汁の8割を習得したと言えるでしょう。この取り方による出汁はもっとも繊細かつ上品で、繊細な素材の椀ものには欠かせません。昆布、かつお節ともにぜいたくに使いますので、ぜひ二番だしも作りましょう。
|
| 一番だし(芳醇) >>取り方 |
|---|
| 淡麗より少しコクが出ます。淡麗では素材に負けてしまいそうな場合はこちらの取り方にしましょう。昆布、かつお節ともにぜいたくに使いますので、ぜひ二番だしも作りましょう。
|
| 一番だし(濃口) >>取り方 |
|---|
| 淡麗よりかなり濃いめで、芳醇よりコクがあります。味噌汁やおひたしにも使えます。昆布、かつお節ともにぜいたくに使いますので、ぜひ二番だしも作りましょう。 |
| 二番だし(追いがつお) >>取り方 |
|---|
| 一番だしはもっともぜいたくな出汁の取り方で、二番出汁まで取るのが一般的であり、食べ物が無駄になりませんのでおすすめです。味を濃いめにに仕上げたい時のためのものですから、お茶の二番煎じとはまったく意味合いがちがいます。
|
| 煮干し[じゃこ]だし >>取り方 |
|---|
| 従来、和食料理屋では限られた使い方をされてきました。そのためか昨今は、個性的な味、新しい味を出したい時に使われることがあります。家庭用での用途は最も多く、日本人の舌にもっとも慣れ親しんだ味といえるでしょう。
|
| 椎茸だし >>取り方 |
|---|
| だしが一番の目的とはなりにくく、食のため乾燥品を戻すときに出来上がった汁をだしに利用するという副産物的なだし。したがってだしの取り方というより、乾燥椎茸の戻し方というのが本来なのかも知れません。昆布と並んで精進料理に重宝されます。
|
| あらだし >>取り方 |
|---|
| ここでは鯛を使った方法をご紹介しますが、鯛に限らず、ブリ、さわらなどにも応用ください。
|
| 煮干し[干しえび]だし >>取り方 |
|---|
| 独特の香り、風味が楽しい出汁です。甘みを感じる出汁で、単独でも美味しいですが、他の出汁と組み合わせることで旨味のハーモニーが生まれます。
|
| 混合精進だし >>取り方 |
|---|
| 一般的な精進料理用の出汁です。
|
| 野菜だし >>取り方 |
|---|
| 水炊きやおでんに向いた出汁で、動物性の具を使った、具そのものから出る出汁の旨味を楽しむ時に使います。 |
| 鶏ガラだし(茶濁) >>取り方 |
|---|
| 茶濁の鶏ガラだしは煮炊き、炊き込みご飯に最適です。香りが強いのでこれのみでは鍋には向かず、鍋で用いるためにはほかのだしで薄めて使います。
|
| 鶏ガラだし(白濁) >>取り方 |
|---|
| 白濁の鶏ガラだしは茶濁のだしより香りは弱くなりますが、反面コクは強くなります。骨の中の旨味が効いて、とり鍋などにもっとも適しています。
|
| 鶏ガラだし(澄まし) >>取り方 |
|---|
| 茶濁、白濁にくらべ、澄んだ鶏ガラだしはかなりあっさりしています。茶濁のだしより香りは弱くなりますが、反面コクは強くなります。骨の中の旨味が効いて、とり鍋などにもっとも適しています。
|
© Rakuten Group, Inc.