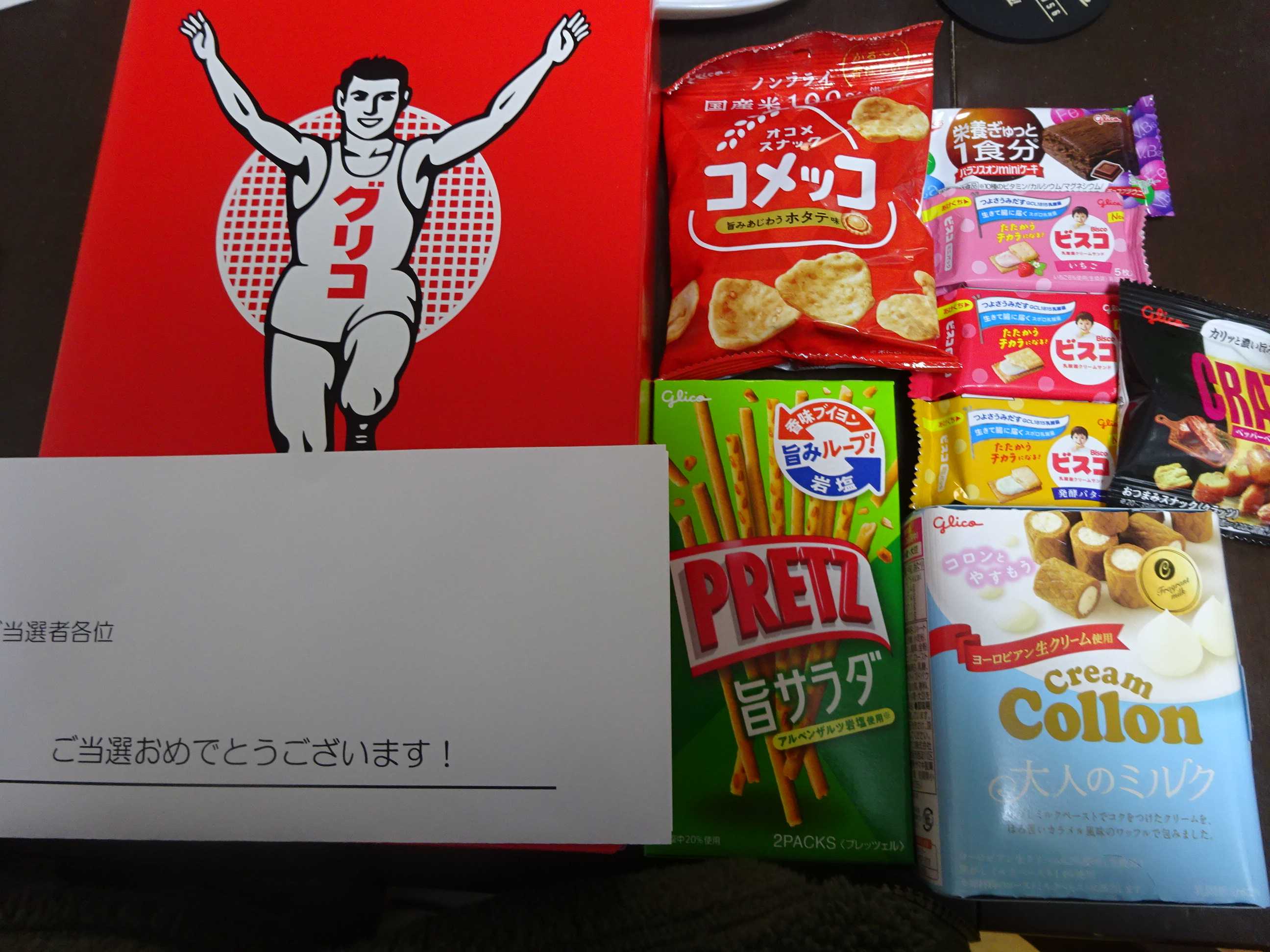2011年01月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
超読者層の広がり!!
アメブロで読者登録をしてくださった「福岡のライフオーガナイザー研究生きこさん」のブログを拝見すると、なんと、小さなお子さんが『まんがと図解でわかるドラッカー』を読んでいる!!!(正確には“見ている”だろう)多分、就学前だと思う。(女性の年齢はわからない)http://ameblo.jp/st-703/ ご参照。ここまで読者層が広がるとは思ってもみなかった!!!(笑次の著書は『絵本でまなぶドラッカー』かな???(爆何はともあれ、きこさん、ありがとうございました。
2011.01.17
コメント(0)
-
仕事が国境を超えた!
昨日、拙著『図解で学ぶドラッカー入門』(JMAM)が台湾でも出版されることが決まり、その関係の契約書類が郵送されてきた。本書は、『図解で学ぶドラッカー戦略』とともに、すでに中国でも出版が決まっており、「海外の方にも読んで頂ける」と喜んでいるところだ。『20代から身につけたいドラッカーの思考法』(中経出版)『20代から身につけたいドラッカーのマーケティング思考法』(中経出版)は電子書籍版が今月発行される予定だ。こちらは日本語だが、より広域の方々に読んで頂ける。また、『20代から身につけたいドラッカーの思考法』は韓国と台湾から出版のオファーが来ており、こちらも発行が待ち遠しい。本人より一足先に、著書が海外に出ていった。がんばって、本人も海外から声がかかるようにしていこう。その前に、国内でもっと多くの方々に支持して頂けるようにならなくては!!「知りたいドラッカー」「使えるドラッカー」の普及をめざしている。一人でも多くの方が、ドラッカーの教えで精神的にも・経済的にも豊かになって頂きたいと思う。私の仕事に国境はつくらない。ところで、『まんがと図解でわかるドラッカー』(監修、宝島社)は、ブックオフ社長の橋本真由美さんの寝室に『ストーリーとしての競争戦略』(楠木建著、東洋経済新報社)とともに、今、置いて頂いているとのこと。書籍販売のプロに、多くの中から選んで頂けたことを知って、たいへん嬉しかった。明日は、同書の製作スタッフが10数人集まり食事会を行なう。喜びを共有できると思う。さて、今日から2泊3日で、東京出張。実り多い出張になりそうだ。
2011.01.12
コメント(0)
-
『まんがと図解』が『もしドラ』を抜いた!
と言っても下記のサイトのランキング(3位と4位)だけの話。全体的には『もしドラ』(岩崎夏海著、ダイヤモンド社)が圧倒的に強いことに変わりない。3月14日から始まるNHKでのアニメ放送に向けて、今以上に売れるだろう。http://www.e-hon.ne.jp/bec/OS/SE/Genre?site=30474&memo=QkOxxGP&dcode=06&ccode=99とは言え、一時的にしろ限定的にしろ、これは奇跡に近い。でも、これからはこうした現象が、あちこちで見られるのではないかと思う。それがまんがの強みだ。このまんがの要素を取り入れた『まんがと図解でわかるドラッカー』(宝島社)を企画した編集者の感性はすごいと思う。ドラッカーと小説を合体させた『もしドラ』もイノベーションならば、ドラッカーをまんがで表現した『まんがと図解でわかるドラッカー』もイノベーションである。出版不況と言える中で、前者は200万部超の発行部数、後者は発売1週間程度で20万部の増刷を決めている。もちろん、『もしドラ』がブームを起こし、市場を開拓したから『まんがと図解』がヒットできたのである。しかし、そのチャンスを『まんがと図解でわかるドラッカー』はチャンスとしてとらえ、みごとに売上げに転換した。既存市場は成熟や飽和・衰退していても、新規市場は無限の可能性を秘めており、無競争の世界が広がっている。もっとも、開拓した市場には無数の追随者が入ってくる。それはマイナス要因だけではなく、市場を広めるため共存しなければならないパートナーでもある。広がった市場でまた新しい商品を投入すれば、その恩恵を受けることができる。私は、そうしたおかげでドラッカーの解説本を8冊、累計456,500部(昨年だけで40万部超)を発行することができた。今年は、また違った視点でドラッカーを書いていく。昨年初めとは違い、分かりやすくするだけでは「差別化」ができなくなっているからだ。ドラッカーの「売れないのは、不精な経営をやっているからだ」の教えを肝に銘じて、今年も、執筆のみならず、セミナー・講演、コンサルティングにおいても、お客様の視点に立った仕事をしていきたいと考えている。それも、売上げに結びつくまで。。。
2011.01.08
コメント(0)
-
嬉しいブログ発見!
『まんがと図解でわかるドラッカー』をネットで検索していると、下記のようなブログがあったので、その一部を転記させて頂いた。まさに、本書が意図した内容そのものだった。なお、全体の文は下記のアドレスをご参照下さい。ちょこさん、ありがとうございました。http://ameblo.jp/milkywhite68/entry-10759701078.htmlー前略ー女子高生が、恋や学校行事を成功させる為に、ドラッカー理論を用いて納得していく過程は、なるほどな~と感心しました。これなら、女子マネージャーが野球部に当てはめても成功するわね。というか、なんにでも当てはめることが出来るんじゃないかしら。ママのダイエットにも当てはめている所を見ると、これは「もし専業主婦がドラッカーの『マネジメント』を読んだら」でも、いいんじゃないの?家庭経営というところからも、参考になるものが沢山ありました。マーケティングの「既存の商品に顧客は満足しているか?」は、「お母さんの作るご飯に家族は満足しているか?」と置き換えると、ワンパターンなメニューに飽きている…とかね (ノ´▽`)ノ利益などは、「蓄えは充分か?」「現状の利益で企業は存続できるか?」「そのために必要な利益はどれだけか?」に当てはめると、我が家の貯蓄や使い方で、この先の教育資金&老後は大丈夫か?とかね。特に、5つの習慣という項目では1.時間を体系的に使う → 自分は何に時間を取られているのかを自覚する2.期待されていることを意識する → やりたいことではなく、周りがしてほしいことを察知して、仕事を組み立てる3.自分の強みから考える → 他者より秀でている長所を見つける4.常に最優先の仕事をする → まずやるべきこと、今やらなくてよいことを問う5.手順を明確にする → 仕事の進め方を決めてから進めるすぐに実践出来る事だし、主婦としてだけでなく、ライフオーガナイザーとしても身につけておきたいことですわ。ピーター・F ・ドラッカーさんの、幼少期から成功までの生涯をマンガでおさらいも出来たし、マネジメントとか、マーケティングとか、イノベーションといった、主婦にはあまり関係ない単語も、理解すれば生活に応用できる、というか、すでにしている事も沢山あることに気づきました。まずは、わかりやすいものから入るというのもありですな。ー後略ー
2011.01.06
コメント(0)
-
今年は、イノベーションを意識しよう
昨年末で既刊8冊(監修を含む)の発行部数が456,500部となった。いずれもドラッカーの解説本であるが、今も順調に売れている。ドラッカーブームだから売れているのは間違いない。ただし、すべてのドラッカー本が売れているわけではない。1.『まんがと図解でわかるドラッカー』(宝島社)が235,000部2.『20代から身につけたいドラッカーの思考法』(中経出版)が86,000部3.『図解で学ぶドラッカー入門』(JMAM)が66,000部4.『図解で学ぶドラッカー戦略』(JMAM)が21,000部5.『20代から身につけたいドラッカーのマーケティング思考法』(中経出版)が19,000部「1」がメガヒット、「2」「3」が大ヒット、「4」と「5」がまあまあのヒットと言ったところである。あとの3冊も発売即重版だったから「そこそこ」とは言える。売れるには訳がある。と言っても「買って頂ける」ことが大前提であることは間違いない。ビジネス書における「よい本」とは“むずかしいことをわかりやすく、わかりやすいことをおもしろく、おもしろいけれど使える”でなければならないと考えている。私が『図解で学ぶドラッカー入門』を出すまで、ドラッカー関連本で「入門書」はあった。「図解書」もあった。しかし、いずれも経営の専門用語を用い、ドラッカーの言葉で図解していた。表現も一般的な経営用語や漢語表現が多かった。つまり、ある程度勉強した人たちを対象にしたドラッカー本だった。しかし、『図解で学ぶドラッカー入門』は「図解」と「入門」を組み合わせるため、専門用語、英語・漢語表現を極力使わずに書いた。そこにはイノベーションがあった。『ドラッカー経営戦略実践ワークブック』(秀和システム)はドラッカー本では初めての本格的なワークブックだった。ワークをともなうため、発行部数は9,000部(第4版)である。しかし、このワークに真剣に取り組めば、ドラッカー理論が実践できるようになっている。私がV字回復を支援しているコンサルティングでの経営者への「質問&課題集」である。ワークブックは山ほどあるが、ドラッカーというニッチ分野では初めての形式でありイノベーションであった。読者の評価は高い。『20代から身につけたいドラッカーの思考法』が発行されるまで、ドラッカーは30代以上の管理職の読みものだった。それを本書は、読書対象を20代からとした。そのためには、経験の少ないビジネスパーソンでもわかるように、さらにやさしくする必要があった。この本で新たな読者層を開拓できた。『まんがと図解でわかるドラッカー』は、長年の課題であった「もっと分かりやすくするために、ドラッカーを漫画で表現したい」との私の思いと一致したものである。それまでドラッカーをまんがで解説したものはなかった。いずれも編集者から企画をご提案頂いたものだった。しかし、ブームに乗っただけで売れたわけではない。いずれもイノベーションがあったから売れたのである。それは、それまでなかった読者層の開拓であり、表現や構成面での技術開発だった。とは言え、「無」から「ヒット」が生じたわけでもない。ドラッカーのいう「企業家的柔道戦略」や「創造的模倣戦略」(これらの内容については著書参考)である。既存のあるものとあるものを組み合わせたにすぎない。ドラッカーはそれがイノベーションだという。現在、あなたや周りの人が感じている不満や不便を、既存の何かと何かを組み合わせて解消すればよい。そのためには、現場に出て、よく観、よく聴くことだ。既存の市場は飽和状態であり過当競争であるが、新しい市場は無限の可能性があり無競争である。今年はそこにチャレンジしてみてはどうだろうか。
2011.01.04
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1