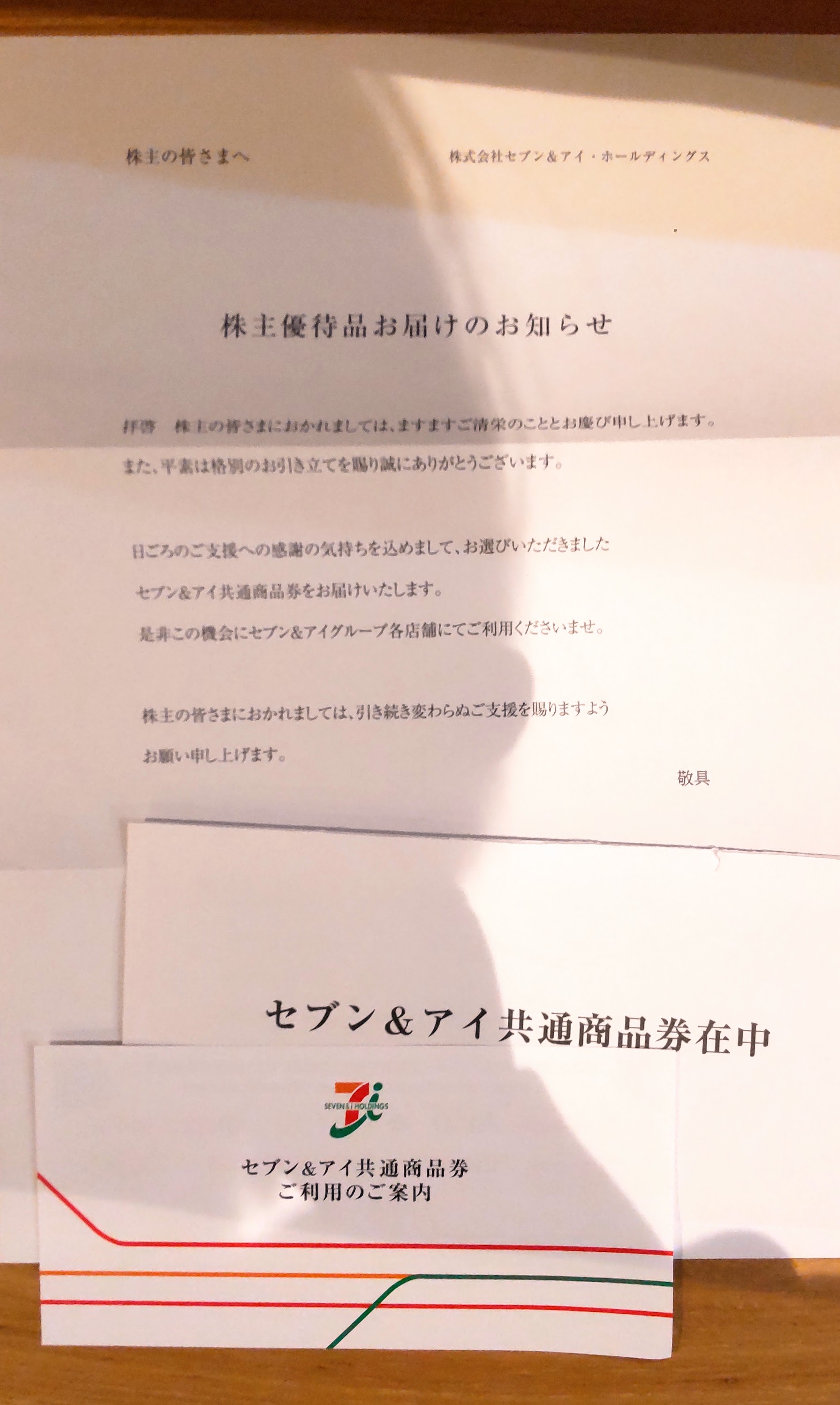-
1

労災保険の療養給付の請求手続き 様式5号と6号の説明
一般的な労災事故発生時に使用する用紙が様式5号です。様式5号は、労災発生当初から、労災保険指定病院にかかり、労災保険を使用することを前提に治療を受けた場合に使用する用紙です。労災請求手続きのうち、最も手がける頻度の高いものでしょう。記入内容は、さほど難しくありませんので、ここでは触れません。様式5号の例外的な手続きの必要な場合がありますので、その事に触れたいと思います。■薬を院外処方とした場合様式5号の提出が薬局にも必要となります。病院にも様式5号を提出しますから、2枚必要という事です。なお、記入内容はどちらも同じです。■病院を移った場合新しい病院(労災保険指定病院に限る)に提出する用紙は様式6号となります。事故後すぐにかかった病院は事業所近くの事がほとんどですが、回復してくると、自宅近くに転院することがあります。その際は、様式6号を提出します。なお、様式5号や6号などの書類を、病院に提出するのは誰でも構いません。ですから、被災者が重病ではなく通院できる場合には、被災者が病院にかかる時にでも持参してもらえば良いのです。その為、私たち社労士は書類作成の部分まで担当すれば良いわけです。電話やファックス、訪問などの手段で書類作成はできます。できあがった書類は、事業所の印を押印してもらい、そのまま置いてくれば済みます。ただし、できるならば、病院に一本電話を入れ、労災保険を利用する旨、社労士として書類作成を担当している旨、連絡しておくとなお良いでしょう。そして、もし重症で、被災者本人が提出することが不可能な場合には、私たち社労士もしくは会社側が提出することになります。この場合には、多くは、様式8号の休業補償給付の手続きも必要となるでしょう。岩倉市の社会保険労務士
2007年05月09日
閲覧総数 102621
-
2

標準報酬月額の改ざん
昨日に続いて、厚生年金の標準報酬月額改ざん問題に触れます。 被保険者による記録改ざんの是正について、考えてみました。 正しい記録を回復する為には、物証が必要になるかと思われます。その場合、物証として該当するものは、給与明細、賃金台帳、源泉徴収票、などになるでしょう。しかし、これらの書類は全て民間組織が作成した資料です。また、パソコンとプリンタで過去のものをいくらでも作成することが可能です。ですから、これらの資料の場合、その記載内容を証明するような第2の資料が必要なのでは無いでしょうか? そして、第2の資料とは、税務署・市役所などの公的機関の発行した収入証明書になると考えます。給与明細などの資料は、公的機関の資料とセットになり、やっとその効力を発揮することができる、という結論です。これならば、第三者機関も、認めてくれる可能性が高いでしょう。 ただ、これらの証明方法は、完璧ではありません。まず、公的機関において法的保存期間を過ぎてしまったような時期の収入証明などが取れない可能性のあることです。 そして、収入証明書などの記載内容からも、審査への影響を懸念せざるを得ない点があります。収入証明などは、年間分の数値しか記録されていません。 年間収入・控除・所得、扶養人数などです。これでは、月々の給与がいくらであったか判別できません。その為、申立人側において、収入証明などの金額を月々ベースに分解し、さらにその合理性を主張する事まで強いられます。そして、賞与の割合が多かったり、2箇所以上から収入があったりすると、もう収入証明などからでは、到底正確な数値が導き出せなくなります。 国民年金の未納問題において、不正申告を防ぐ為、第三者委員会では、パターン分類といった方法で審査体制を迅速化しています。当然厚生年金でも行なわれるでしょうが、そもそも正しい申告とされるパターンが描けるのか、そこが心配です。厚生年金の方が、金額が大きく、期間が長期にわたる可能性が十分考えられます。慎重性が求められますが、それに答えられる対応は見つかるのでしょうか? 本当に今回の件に関しては、罪深い行為そのものだという事が分かります。
2008年10月21日
閲覧総数 179