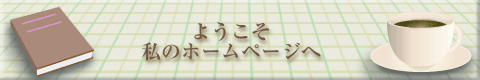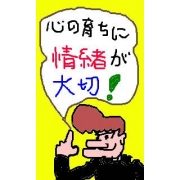フリーページ
情緒の表れ方には、人それぞれ生まれつきの傾向があります。いわゆる気質と言われるものです。これを、情緒の先天的傾向と呼びましょう。不機嫌になりやすいとか落ち着きがないといった生まれつき持っている性格は、周りとの関わりで維持される傾向にあります。例えば、不機嫌な子に対しては、子どもに影響されて周りの人も腹を立てやすくなります。そのために、家族の間でストレスがたまるために、子どもの不機嫌になりやすい性格は、子どもが成長しても継続しやすくなります。逆に子どもがおっとりした性格であれば、周りの人ものんびりすることになり、子どものおっとりとした性格はそのまま続くことになります。
子どもの性格によっては、子どもの性格を変えようというしつけがなされる場合があります。その時でさえ、先天的な情緒表現の傾向が続くようになりがちです。例えば、おっとりした子どもに対して、親はもっとテキパキと動いてほしいと思い、子どもを急がせるように声かけしがちとなります。この場合、子どもは、自信を失い、しかもテキパキしなければならない場面では頑張らなければいけないと思い、緊張が高まってぎこちない動きしかできなくなったりします。また、テキパキ動くことに対して、不快感を持ち回避したいと思うようになりますから、よけいもたもたした動作になってしまいます。
一方、落ち着きのない子に対しては、親は落ち着くようにとしつけることになります。子どもが動き回ると親はうるさく注意するでしょう。すると、子どもの方はストレスがたまり、ますます落ち着きがなくなるということになってしまいます。子どもの性格を変えるための働きかけが、逆に子どもの性格を固定する方向に働いてしまうわけです。子どもの性格に合わせても、子どもの性格に逆らっても、子どもの先天的な性格は続いてしまいますので、多くの人は生まれつきの性格は変わらないと考えてしまいます。
-
常識的判断も情緒が支えている 2025年11月26日
-
情緒起源の認知(2) 2025年11月19日
-
情緒起源の認知 2025年11月12日
PR
キーワードサーチ
コメント新着