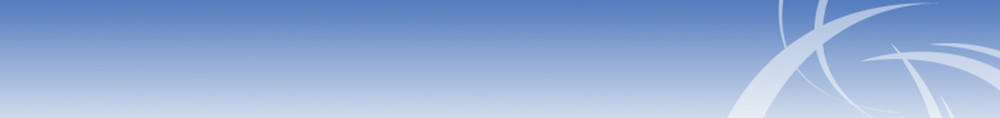そうした中で全体的にはどのような年だったのでしょうか?
まず国の動きとしては表面的に大きな動きは見られませんでしたが、各分野(換気、建材、生物、化学物質など)に関しての研究は当然のことながら今現在も継続はされています。こうした中でこれからのシックハウス問題の取り組みに関しては官から民へというように、官は民へ期待しているという声も聞こえてきました。
その中でシックハウス問題に関連する省庁で一番我々に身近に情報発信を行なってきたのが経済産業省だと思います。
しかしそれさえも中々一般的には認知されていなかったとは思いますが、わかりやすい情報発信を行なう点は評価ができると思います。
建築業界においてはどうだったのでしょうか?
建築材料の業界団体では自主規制として芳香族系の数種類の化学物質に建材への使用規制を行うという動きがありました。
又、建設レベルにおいてはシックハウス問題を引き起こさず、安心して生活できる建物を供給するという考えが浸透していきました。
しかしこうした業界内での動きには徐々に温度差が生じてきています。これについては「 建築業界におけるシックハウス問題に対する温度差
」をご覧ください。
一般の方に対してシックハウス問題はどう捉えられていたのでしょうか?
これも業界内で起きているように温度差が再び生じた年でした。これについては「 シックハウス問題に対する温度差
」をご覧ください。
このようにシックハウス問題の取り組みが官から民へと移行していく中で業界内にも一般的にも徐々に温度差が生じ始めた年だったといえます。
次に感じたことはシックハウス問題の捉え方が問題解決を図るために建築分野にポイントを絞って対応したことで、
「建築業界=シックハウス問題を引き起こしたすべての根源」
「建設業界=シックハウス問題の全責任」
「建設業界=シックハウス問題を引き起こした悪」
などといったような図式が成立し、偏った考え方が広がっていった年であったといえます。
これについては「 建設業界が置かれた立場 その1
」「 建設業界が置かれた立場 その2
」をご覧ください。
最後にシックハウス問題により積極的に取り組むことが関連企業の姿勢として及び社会的責任であると認知されはじめた年でもありました。
実際にはこのシックハウス問題の本質を理解し、取り組んでいくという面においてはようやくスタートラインに立てたのではと考えています。その理由として上記で述べた様々な問題点が露見し始め、さらなる問題提議が起きたことで徐々にシックハウス問題が我々に教える本質に近づきつつあるからです。
このように2007年を振り返って要約すると、
・ 官から民へ
・ 温度差
・ 偏見による弊害
・ 企業の社会的責任
・ 次の段階への問題提議
といったような言葉で表わせるのではと考えています。
2008年1月18日
-
語ってみたこと 2011.04.01
-
思わぬ落とし穴 2011.04.01
-
第三者機関の対応の難しさ 2011.03.31
PR
カレンダー
サイド自由欄