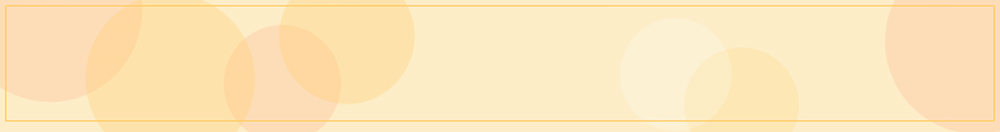-
1

♪Rasa Sayang(ラサ・サヤン)♪
マレーシア、インドネシアで古くから歌い継がれているフォークソングのひとつが「♪Rasa Sayang(ラサ・サヤン)♪」Feeling of Love(愛する気持ち) という意味のタイトル。この歌は、シンガポールの日本人学校でもマレーの代表的な歌のひとつとして子ども達に教えてくれます。ラサ・サヤンという名前のリゾートホテルやレストランもありますね。ラサ・サヤンの歌詞は「パントン(Pantun)」と呼ばれる形式になっていて即興でオリジナルの歌詞をつけて歌う楽しみもあるようです。パントンは、15世紀のマラッカ王国時代から脈々と歌い継がれきた4行詩でマレーの自然や風物、教訓や価値観、愛などが歌われています。前半2行で謎をかけ、後半2行で気持ちを表現する形で1行目と3行目、2行目と4行目はできるだけリズムも合わせ、最後の単語は韻を踏みます。とっても興味深い、すてきな文化です(*^-^*)こんな歌♪ → ♪Rasa Sayang♪(YouTube)◆ Rasa Sayang の、ポピュラーな歌詞 ◆Rasa sayang hey Rasa sayang sayang heyラサ サヤン ヘイ ラサ サヤン サヤン ヘイHey lihat nona jauh Rasa sayang sayang heyヘイ リハ ノナ ジャウ ラサ サヤン サヤン ヘイ (訳)愛する気持ち ずっとあの子を見つめてるBuah cempedak di luar pagarブア チャンパダ ディ ルア パガAmbil galah tolong jolokkanアンビルカン ガラ トロン ジョロッカンSaya budak baru belajar サヤ ブダッ バル ベラジャ Kalau salah, tolong tunjukkanカラウ サラ トロン トゥンジュッカン (訳)塀の外のチェンペダックの実 竿でつついて落としてちょうだい 私は子供で、学び始めたばかり 間違えたら教えてちょうだいSorong papan tarik papanソロン パパン タリッ パパンBuah keranji dalam perahuブア クランジ ダラム プラフSuruh makan saya makan スル マカン サヤ マカンSuruh mengaji engkau tak tahuスル ムンガジ エンカウ タッ タフ (訳)板を押したり引いたりして クランジの実をボートの中に 召し上がれ 私もいただく 知らないことは学べばいいRasa sayang hey Rasa sayang sayang heyHey lihat nona jauh Rasa sayang sayang heyPulau Pandan jauh ke tengahGunung Daik bercabang tigaHancur badan dikandung tanahBudi yang baik dikenang juga (訳)パンダン島ははるか沖 ダイク山には峰三つ 体は土に還っても いい行いは忘れられる事がないPisang emas dibawa belayarMasak sebiji di atas petiHutang emas boleh dibayarHutang budi dibawa mati (訳)金のバナナを船で運べば 船の上で熟してしまう 人のお金は返せば済むけど 人の恩は死ぬまでRasa sayang hey Rasa sayang sayang heyHey lihat nona jauh Rasa sayang sayang hey ・ ・ ・
August 24, 2007
閲覧総数 4904
-
2

南の国のとっぽい鳥 (ハシビロコウ)
シンガポールには、魅力的な野鳥たちがいっぱい。街の鳥、森の鳥、水辺の鳥、9月ごろからやってくるシギ・チドリの仲間たち。大好きな鳥達はたくさんいるけど・・それはちょっとおいといて・・写真も無いし(^^;)今回は、野鳥じゃないんだけど、私の大好きな鳥を。アフリカに生息する鳥で、シンガポールのジュロン・バードパークで会うことができます。今は、「African Wetlands Exhibit 」というアフリカの湿地の生態系を再現したエリアに飼われています。いや、ほんと、始めて会った時は、びっくりしたよー。鳥なのに、鳥みたいじゃない・・気取ってないのにとっぽい。この子に会いたくてバードパークに行く私(笑)写真をいっぱい載せるから、ごゆっくりお楽しみくださいませ(笑)バードパークのサインボードには「SHOEBILL」(シュービル)という名前。靴のくちばし? どれどれ・・・・説明書きには↓なことが。 くちばしが、オランダの木靴に似ている事から Shoebill と呼ばれる。 また、頭とくちばしが非常に大きくて太いことから 「Whale-headed Stork(くじら頭のコウノトリ)」とも呼ばれている。木靴?くじら?・・えー、どんな鳥なんじゃー?!で、さがす。動いてるものはいないかな・・なかなか見つからない。いたー!!・・・じーっとしてる。・・でかい! ものすごくでかい!なんか、頭を下げてお辞儀してくれる。それを見た人間さんたちは、そりゃもう大騒ぎ。「おおきいー!」「変な顔ー!」「かわいいーー!」「いやーん、もっとお辞儀してー!!」騒ぎの中、逃げるでもなくなんとなく不機嫌そうな顔になってく。ぶす~っまったく賑やかやねぇなんか言いたいことあるの?ま、関係ないけどねこの子は、日本語では「ハシビロコウ」と呼ばれるコウノトリの仲間。野生でも、彫刻のようにじっとしてることが多いんだって。水辺でじーっとして、えさになる魚が射程距離に来るのを待ってる。大きな体で動き回ると獲物は逃げてしまうから、とか(笑)動くものはいないかー、じゃ、見つからないわけだ。あっちを向いても、こんなにキュート↓。コウノトリは鳴き声を出さないかわりに(?)上下のくちばしをたたき合わせるようにしてカタカタ音を出す。この「カタカタ」は、クラッタリングと呼ばれてる、コミュニケーション手段らしい。でね、シュービルも・・たぶんクラッタリングだと思うんだけどこっちを向いてくちばしを鳴らすの。・・ただし、大きなくちばしは、「カタカタ」いわずに「ばくばく」いう。挨拶してくれてるのか、威嚇してるのかわからないけどとりあえず、挨拶を返しておいた。始終、仏頂面のシュービル君。急に顔を上げて、お目目がキラ~ん。そのわけは・・お魚が好物で、大きな肺魚も丸呑みしちゃうらしい。バードパークでもらえるごはんは・・・ちょっと小さい・・(笑)羽を広げたら2mにもなるというシュービル。本来の生息地で飛翔する姿を見ることができたら・・と、夢見ています。※日本国内でハシビロコウが見られる所は 東京・上野動物園、千葉市動物公園、伊豆シャボテン公園 ◆◆ ハシビロコウ ☆ 豆知識 ◆◆■学 名 : Balaeniceps rex■英 名 : Shoebill ■分 類 : コウノトリ目 ハシビロコウ科 ハシビロコウ亜科(1属1種) ■大きさ : 体長 1.2メートル 体重 5キロ■分 布 : ウガンダ共和国のビクトリア湖周辺■食 餌 : 魚、カエルやヘビ、まれに水鳥のヒナや小動物*ワシントン条約で国際取引が規制されている希少種*学名の「Balaeniceps rex」はラテン語で「クジラ頭の王様」の意味*コウノトリ目に分類されることが多いが、サギ類、ペリカン類に近いという説もある
April 13, 2008
閲覧総数 3346
-
3

「これ、な~んだ?」 : 回答編 (コガネキヌカラカサタケ)
レモン色のまぁるいもの、な~んだ?4名さまから、レス頂いていました。ありがとうございましたm(_ _)m正解も既に(*^-^*)実はこれ、家の中、リビングのプランターに突如出現。コルジリーネの鉢の根元のとこ・・・はい、ズーム!レモン色の、ほっこりとした形の大きいキノコ。小人の国のランプシェードのような・・。「うわ!なにこれ!」「きれいなー!!」って、リビング内騒然(笑)このコルジリーネは19年前に新婚旅行先のハワイから買って来た5cm程の細い茎から育ったもの。「熱帯のキノコみたいだねー。」「ハワイから連れてきたんじゃねぇ?」キノコの図鑑はまだ持ってないから、さっそくネット検索開始。で、「日本キノコ協会」のHPを見つけて、画像掲示板でお尋ねしたらすぐにお返事が(*^-^*)「コガネキヌカラカサタケ」という熱帯産のキノコだそうな。 (ほんとに熱帯のキノコだった/笑)日本でも、沖縄や奄美大島では自生してるそうだけど本州で見られるのは、園芸用の腐葉土なんかに混在してたものらしいです。(コルジリーネに付いてきて19年間眠っていたわけじゃないんだね/笑)観葉植物の鉢に突然現れる大きな黄色いキノコに仰天する人も多いそうな。真横から見ると・・こんなにかわい~真上から見ると・・・・ごめん(^^;)見つけてから12時間後、翌日のお昼にはカサがいっぱいに開いて、よりキノコらしく。裏側のひだもびゅーてぃふるその6時間後には、もうしぼみ始めて・・・でもまだ、小さい小さい幼菌がたくさん顔を覗かせてます。森の中では、落ち葉や倒木は、たくさんの生き物、微生物の力を借りて分解されて栄養たっぷりの土に還る。キノコもまた、そういった貴重な分解者のひとつ。コガネキヌカラカサタケは、コルジリーネにいい栄養をくれてるのかも。 ◆◆ コガネキヌカラカサタケ ☆ 豆知識 ◆◆■学 名 : Leucocoprinus birnbaumii■和 名 : コガネキヌカラカサタケ ■分 類 : ハラタケ科 キヌカラカサタケ属 ■原産地 : 熱帯 *食毒不明・・今のところ、これを食べて中毒を起こしたという報告はないようですが 食べてみた人もいないのかも・・・?
September 18, 2007
閲覧総数 4149
-
4

春を待つ形・・(ロゼット)
タンポポやオオバコのように根から出た葉が放射状に地面に張り付くように広がるような植物をロゼット植物と呼んだりします。ロゼットというのは、ラテン語の「rosa(バラ)」が語源でフランス語でロゼット(rosette)と言えば、小さなバラ。・・そこから派生してバラの花形の飾りを意味します。放射状に並ぶ葉を八重咲きのバラの花びらに見立てたすてきな呼び名です。冬になると、あちらこちらでロゼット状に葉を広げた植物に出会います。根から出た葉(根生葉、ロゼット葉)を少しづつずらして放射状に広げた形は1枚1枚の葉に日が当たる。茎を作るためのエネルギーを必要としないし、冷たい冬の風にあおられることもない。厳しい冬に耐え、春を待つ、理想的な形に思えます。ロゼットは、冬にはとても有利ですが春に背の高い草が伸び始めると、日が当たらなくなって不利。春には春の戦略をもっています。春になるとロゼットの中心から花茎を伸ばして花開きますがその方法は3タイプ。1.花茎には葉をつけない純粋なロゼット型植物(タンポポなど)2.花茎にも葉をつける偽ロゼット型植物(ハルジオンなど)3.花茎に葉をつけ、ロゼット状の根生葉は枯れてしまう一時ロゼット型植物(ヒメジョオンなど) ちょっと外に出てみれば、あそこにもここにも・・冬になったばかりだけれど、ロゼットの形で春の準備をしています(*^-^*)
December 2, 2007
閲覧総数 858